個人、法人問わず多くの業界やビジネスで導入されているSaaS(Software as a Service)は、従来のソフトウェアの概念を大きく変えました。SaaSはインターネットを経由してサービスを利用することで、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進や場所や時間にとらわれない働き方にも大きく貢献しています。
今やSaaSと全く無縁という企業はほぼ考えられませんが、SaaSの基本概念や特徴について誰もがしっかりと理解しているわけではないでしょう。この記事ではSaaSとクラウドサービスの違いやメリット・デメリット、さらには具体的なSaaSの製品についても紹介します。
組織のDX化について知りたい方はこちら
目次
SaaS(サース)とは
クラウドサービスとの違い
SaaSのメリット・デメリット
SaaSサービスの代表例
使えるねっとが提供するSaaS製品
ホワイトラベルで再販も!SaaS導入のポイントと選択肢
FAQ

SaaS(サース)とは、「Software as a Service」の略で、クラウドサービス事業者が提供しているソフトウェアを、ユーザがインターネットを経由して利用するサービスのことです。
従来、法人・個人関わりなくソフトウェアを利用するにはCD-ROMなどパッケージとしてライセンス販売されているものを購入し、端末にインストールして利用していました。通常は1台の端末にのみ限定され、アップデートの際には再インストールする必要があったのです。それに対してSaaSは複数のデバイスで利用でき、オンラインで随時アプリケーションを更新することが可能です。
また、従来の端末のソフトウェアはユーザがプロダクトを購入し、その際に対価を支払う点で「売り切り型」のビジネスでした。それに対して、SaaSは継続的に課金する、いわゆる「サブスクリプションモデル」です。つまり、従来のソフトウェアはプロダクト提供がゴールであったのに対し、SaaSにとってはサービス提供こそがスタートといってもよいでしょう。サービス提供事業者は常にユーザの声を聞き、分析し、価値を提供し続けないと事業として生き延びることができないからです。
そのため、SaaSの開発、運用の現場では、データ管理・分析が非常に重視されます。自社のSaaSの「どの機能がよく使われていて、どの機能があまり使われていないのか、使いにくい理由はなにか、どのように改善できるか」が常に分析され、PDCAが高速で回され、プロダクト改善が行われます。そのようにしてサービスの価値が高まり、ユーザのロイヤリティも高まっていくというわけです。
SaaSの世界的リーディングカンパニーであるSalesforce社は「Customer Success(顧客の成功)」という概念を打ち出しましたが、これこそがSaaSの本質を表しています。単に「Customer Support(顧客の支援)」をするだけにとどまらず、能動的に顧客の価値を追求して「サービスとしてのソフトウェア」を提供するビジネスモデルがSaaSです。
.png)
SaaSと同じようなクラウドサービスに「IaaS」や「PaaS」があります。ここでは、IaaSやPaaSがSaaSとどのように異なるかについて解説します。
IaaS(アイアース)とは、「Infrastructure as a Service」の略称であり、インターネット経由で仮想化されたコンピューティングリソースを適用するクラウドコンピューティングサービスを指します。サーバシステムや電源設備、ストレージなどを、物理的なハードウェアを持たずにインターネット経由で利用するため、リソースを柔軟に拡張・縮小でき、効率的な運用が可能になります。IaaSの代表的サービスとして、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureなどがあります。
SaaSがインターネット経由でソフトウェアを提供するのに対し、IaaSはシステム構築のためのインフラを提供する点で異なります。また、SaaSのユーザには個人も含まれますが、IaaSを利用する個人ユーザは通常おらず、企業のIT部門が主な利用者です。
それに対して、PaaS(パース)とは、「Platform as a Service」の略で、アプリケーション開発のためのプラットフォームを提供するサービスのことです。開発者はインターネット経由で開発のためのツールやライブラリを利用できます。そのため、開発環境構築の手間を省き、開発スピードを向上させることが可能です。
SaaSと異なるのは、事業者が提供するのがソフトウェアではなく、アプリケーション開発のためのプラットフォームである点です。また、PaaSのユーザはアプリケーション開発者に限定されます。
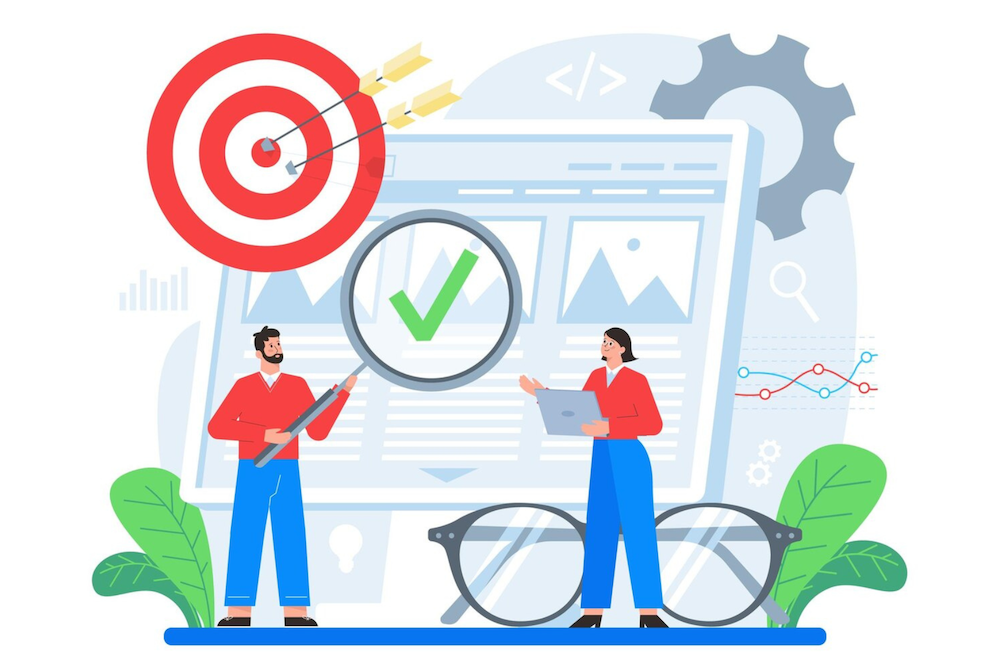
SaaSについてより高い解像度で理解するために、SaaSのメリットとデメリットをそれぞれ分析してみましょう。
メリット
SaaSの主なメリットは以下の3点です。
導入コストが安価
SaaSを利用しない場合、ユーザは高額なソフトウェアパッケージをその都度購入したり、大がかりなシステムを構築したりする必要がありました。しかし、SaaSであれば、自社の従業員数や事業規模に合わせて一定の月額、あるいは年額料金を支払えば足ります。スピーディーに導入でき、時間的、経済的コストを圧倒的におさえることが可能です。
保守管理の負担が少ない
ソフトウェアを自社開発した場合、保守管理や障害対応などは自社のIT部門が24時間体制で行わなければなりません。それに対して、SaaSはクラウドサービス提供事業者が保守管理を担ってくれます。そのため、社内リソースが限られている中でDXを推進したい中小企業にとってSaaSはありがたいサービスといえるでしょう。
柔軟性とスケーラビリティ
スケーラビリティ(Scalability)とは、システムや機器、ソフトウェアの拡張性のことです。スケーラビリティが高ければ、ソフトウェアやシステムは利用者数の増加や負荷に耐えることができ、事業をスムーズに成長させることができます。
また、従来の端末にインストールする形のソフトウェアだとアップデートする場合にはユーザ側にダウンロードが必要ですし、アップデートが必ずしもユーザのニーズに適合しているとも限りませんでした。それに対し、SaaSは事業者側でユーザに対する価値提供を目指し、データ分析とソフトウェアのアップデートが行われているため、常に最新の、高いクオリティのソフトウェアサービスを利用できます。
デメリット
SaaSの主なデメリットは以下の2点です。
データセキュリティ
SaaSの最大の特徴はインターネット経由で利用することです。常に開かれた環境であるネットワークゆえにセキュリティリスクと隣り合わせです。もちろん、SaaS提供事業者も万全のセキュリティ対策を講じていますが、ユーザ側でも任せっきりにしないことが大切でしょう。自社でも、ウイルスやランサムウェアなどの不正プログラム対策や安全なパスワードの設定や管理はもちろん、サービス提供事業者が講じているセキュリティ対策についても知っておくべきです。
カスタマイズが困難
SaaSはユーザのさまざまなニーズをデータに基づき絶えず分析していますが、そこに自社のニーズが必ずしも反映されるとは限りません。そのため、欲しい機能がいつ追加されるかは分かりませんし、それをサービス提供社側に要求することもできません。
それに対して、自社開発のアプリケーションやシステムであれば、随時カスタマイズが容易です。
.png)
いまやSaaSの利用はあらゆる領域に広がっています。主な分野にグループウェア、コミュニケーションツール、会計ソフト、CRMなどがあります。そのうちのいくつかを紹介しましょう。
企業や組織のコミュニケーションを円滑にし、業務効率化を図るためのグループウェアソフトには、Microsoft 365やGoogle Workspaceなどがあります。いずれもエンタープライズから中小企業に至るまで幅広く活用されており、いまや業界に関わらずリモートワークに最適なSaaSツールといえます。
コミュニケーションツールは無料で利用できるものも多く、その中にはChatworkやSlackなどがあります。チャットツールはオフィス内でだけでなく、出先やリモートワーク先でも活用できるようスマートフォンでも利用できます。
会計ソフトの代表的なものには、個人事業主から中小企業まで幅広く利用されているfreeeやMoney Forwardクラウドがあります。いずれも取引データを自動で取得し、AIによって自動で仕訳、入力を行います。
さらにCRM(顧客管理システム)では、顧客から得られる情報をクラウド上に記録、ユーザと企業の最初のタッチポイントからアクションに誘導するまでのデータを管理し、営業支援を行うためのSalesforceがよく知られています。

ここでは使えるねっとが提供する代表的な3つのSaaS製品を紹介します。
使えるファイル箱
使えるファイル箱は、ユーザ数無制限のクラウドストレージサービスです。ユーザが100人でも1,000人でも料金は一律のため、企業の成長や事業規模の拡大に合わせて社員が増えても、ユーザ課金や発行権限に悩む必要はありません。
また、SaaSのデメリットの1つにインターネットを経由することによるセキュリティリスクが挙げられますが、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズム「AES256ビット暗号化」を採用しています。また、各フォルダごとにアクセス権限の設定も可能であり、セキュアな環境を担保しながら、外部取引先との情報共有も自由自在です。
専用のインターフェイスを必要とせず、使い慣れたエクスプローラーやFinderのような使い勝手も魅力です。30日間の無料トライアルも実施していますので、異次元の使いやすさをじっくり、ゆっくりお試しいただけます。
使えるファイル箱は、デフォルトで大容量1TB、月単価21,230円(税込、1年契約)から導入可能です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら
使えるクラウドバックアップ
使えるクラウドバックアップは、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。多くのサービスはバックアップとウイルスチェックは別契約ですが、使えるクラウドバックアップはデータを守るだけでなく、万が一のときもすぐに復元して「使える」ことを重視したSaaSといえるでしょう。
その鍵となるのはAIベースのテクノロジー「アクティブプロテクション」で、ランサムウェアやウイルス等のマルウェアから大切なデータをしっかり守ります。また、イメージバックアップを採用し、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、さらにはオペレーティングシステムを含むシステム全体を一気にバックアップするため、データが消失したときにもすぐに業務再開が可能です。
使えるねっとは中小企業の大切な情報資産を守るべく、圧倒的高品質なサービスを低コストでご提供します。費用は月額2,200円~(税込、1年契約)、1日あたり73円~で最適なプランをご案内します。30日間無料トライアルを実施していますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。
「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら
使えるメールバスター
使えるメールバスターは、使えるねっとが提供する完全クラウド型メールセキュリティサービスです。使えるメールバスターを導入することで、迷惑メール、スパムメール、ウイルスメールなどを、メールサーバに届く前に遮断します。その確率は驚異的で、ウイルス撃退率100%、スパム撃退率99.98%という高精度を実現。ランサムウェア、標的型攻撃メール対策としても有効です。使えるメールバスターはクラウド型なので初期投資が不要、月額11,770円~(300ユーザまで、1年契約)という低コストで手軽に始められます。
「使えるメールバスター」の詳細はこちら

ホワイトラベルとは、他社メーカーで製造されたものを自社ブランドとして販売するビジネスモデルです。ホワイトラベルは私たちの生活の至るところに溢れていますが、使えるねっとが提供しているSaaS製品である使えるファイル箱、使えるクラウドバックアップ、使えるメールバスターはいずれも自社ブランド化して再販が可能です。使えるねっとの製品を取り扱っているパートナーは北海道から沖縄まで日本全国250社を超えています。
ホワイトラベルの魅力は、自社での開発や製造の必要がないため、コストを大幅に削減できることです。開発や製造のリソースを企画やマーケティングに振り向け、製品を使う人たちの顧客体験を向上させるように努めることができます。
ホワイトラベルについての詳細はこちら
SaaS製品をホワイトラベル化することにはさまざまなメリットがありますが、その中に「アップセル」や「クロスセル」があります。アップセルとはより高価格なものにサービスを乗り換えること、クロスセルとはメインの製品やサービスに関連した別の製品やサービスの購入を促すことです。例えば、コピー機などのオフィス製品のリースを扱っている代理店が自社サービスにSaaS製品を追加できれば、顧客を囲い込むことができ、顧客単価の向上を期待できます。
使えるねっとが提供するSaaS製品を自社ブランド化することは、サブスク型ビジネス、あるいはストックビジネスともいえます。つまり、契約したら継続的な収益につながるのです。将来が不確実で、社会も市場もより複雑化する中で、ストックビジネスを展開することで安定的な収入を確保でき、企業の着実な成長につなげることができます。
ストックビジネスに興味がある、もっと知りたい!という方はこちら>>
導入事例:株式会社No.1
株式会社No.1は、情報セキュリティ機器の企画開発、製造・販売及び保守事業に加え、情報通信機器・OA関連商品の販売と保守サービスの提供など、中小企業の経営上の課題に対してビジネスソリューション提供を行っている企業です。高い営業力と顧客基盤を活かした安定的な収益獲得を実現することで、使えるねっとOEMパートナーの中でも高い売上を誇ります。
株式会社No.1が取り扱っているSaaS製品は使えるクラウドバックアップですが、顧客のほとんどは従業員数10名未満の企業であり、リソースの関係で設定業務や管理業務もワンストップで任せたいという顧客ニーズがあります。使えるねっとのSaaS製品なら、その顧客の期待にしっかり応えられます。
ランサムウェアの脅威がかつてなく身近に感じられるようになった昨今、使えるクラウドバックアップの顧客数はさらに増え続け、さらなるストック収益の拡大を見据えて進み続けています。
国内クラウド市場の規模は今後も拡大することが予測されています。SaaS製品をホワイトラベル化することで、ビジネスチャンスの波に乗りませんか?導入費用を含めた詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
使えるねっとパートナープログラムの詳細はこちら>>
.jpg)
(1)SaaSとはわかりやすく言うと何ですか?
SaaS(サース)とは、インターネットを経由して利用するソフトウェアのことです。従来は各端末にソフトウェアをインストールしていましたが、SaaSではその必要はありませんし、複数の端末でソフトウェアを同時に使用できます。
(2)SaaS製品のホワイトラベルとは何ですか?
SaaS製品をホワイトラベル化することで自社製品として販売することができます。また、SaaSはストックビジネスの商材としても最適であるため、ホワイトラベル化して他のサービスと組み合わせることで安定的な収益を見込めます。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
クラウドサービスは、現代のビジネスにおいてますます重要な役割を果たしています。その理由は、クラウドというテクノロジーが全社的な情報共有をスムーズにし、時間や空間を超えた働き方を可能にするだけでなく、「ストックビジネス」「サブスクリプションビジネス」と呼ばれるビジネスモデルも優れているからです。
本記事では、初めにクラウドサービスのビジネス面での優位性について触れ、ストックビジネスとは何か、そしてサブスクリプションビジネスとの違いについて、さらにはOEMと組み合わせるビジネスモデルについて詳しく解説します。
目次
マーケットから見るクラウドサービスの成長性
ストックビジネスとは?サブスクリプションビジネスとの違いも
OEM(ホワイトラベル)のメリット
クラウドサービスがOEMとしてよい理由
使えるねっと製品ならOEM販売でストックビジネスを実現
まとめ
FAQ
.png)
最初に、クラウドサービスの成長性について考えてみましょう。
『情報通信白書(令和5年版)』によると、世界のパブリッククラウドサービス市場は2021年に45兆621億円(前年比28.6%)でした。今後も高い成長が見込まれており、2025年には7,804億ドル(約119兆447億円)、2026年には9,152億ドル(約140兆79億円)に達する見込みです。
一方、国内に目を向けると、2021年の国内パブリッククラウド市場規模は1兆5,879億円でした。2026年までは年間平均成長率が18.8%で、約2.4倍の3兆7,586億円になると予測されています。クラウドバックアップ市場においては、2020年から2025年の年間平均成長率24%であり、今後もますます拡大が期待されています。
こうしたクラウドサービスの成長の背景には、現代のビジネス環境のデジタル化があります。例えば、『情報通信白書(令和2年版)』によると、利用しているクラウドサービスで最も多かったのは「ファイル保管・データ共有(56%)」でした。従来は紙ベースで共有されていた情報が、クラウドを利用することで社内共有が一層スムーズになったことで、どの企業も業務効率化を実現できているのです。
また、クラウドサービスはデータのバックアップやセキュリティの確保などの点からも、ビジネスにおいて欠かせない要素となっています。この成長性を見据えると、クラウドサービスというビジネスモデルは注目されるべきでしょう。

ストックビジネスとは、製品やサービスの仕組みやインフラを最初につくり、継続的に収益を確保するビジネスモデルです。「ストックビジネス」と英単語の組み合わせが使われていますが、実は和製英語です。「ストックビジネス」に近い英語は「recurring revenue model」で、「継続課金モデル」「リカーリングビジネス」のことです。
ストックビジネスの例として、不動産や駐車場の賃貸、塾や家庭教師、フィットネスジム、商品やサービスの定期購入、電気・ガス・水道・インターネットなどのインフラ、オフィス機器のリース、アフィリエイトなどが挙げられます。
ストックビジネスの最大のメリットは、いったん仕組みを作ってしまえば継続的・安定的に収益が得られる点です。そのため、長期的な経営の見通しを立てやすいといえるでしょう。
他方、デメリットは売上が積み上がるまで一定の時間がかかるため、開始直後は収益が上がりにくい点でしょう。また、継続的な利益を生み出すためのサービスを設計することは容易ではなく、時間や資金の投資を覚悟しなければなりません。
ストックビジネスの特徴について理解するために、対極にあるビジネスモデル「フロービジネス」についても簡単に触れておきましょう。フロービジネスとは、売り切り型のビジネスモデルであり、飲食店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアのような小売店が代表的な例です。
ストックビジネスとは逆で、比較的短期間で収益を上げることができますが、継続的・安定的な収益を確保することが困難です。外的要因によって売上が落ち込む可能性もありますし、単発的な取引で終わらないようにリピートに繋がる営業力、企画力が必要といえます。
取次販売とOEMの違い
取次販売とは、製品をメーカーから仕入れ、小売業者を通じて販売する方法です。一般的に取次契約においては、代理店が案件創出から受注までを行うため、メーカー側としてはコスト削減になりますが、代理店側としては高い営業力がなければ負担が大きい契約形態です。また、製品に何かトラブルがあれば、例えメーカーにサポート窓口があっても、代理店側に連絡が来て対応に追われることも少なくないようです。
それにもかかわらず、販売価格の自由度は低く、取次代理店が得られる手数料率は平均して10~30%といわれており、払うコストに見合うだけの利益が得られない可能性も高いビジネスモデルです。結果として、現場は目標達成のため、取り次いだ製品に関しては積極的な販売をせずに収益がかえって悪化してしまうことになりかねません。
それに対して、OEMとは「Original Equipment Manufacturer」を略した言葉で、他社ブランドの製品を製造することです。「ホワイトラベル」という語で言い換えられることもあるように、メーカー側からすれば代理店のブランド資源と販売網を最大限に活用できます。つまり、メーカーは同じ製品やサービスを複数のOEMパートナーにそれぞれのブランドとして提供するのです。
OEMは代理店側にとっても大きなメリットがあります。自社で製品を開発し、工場を建設して製造することは多額の投資が必要ですが、メーカーが提供してくれる製品を活用して自社のブランドで売り出せるからです。代理店は在庫管理の必要もありません。
もちろん、OEMにデメリットがないわけではありません。製品開発や製造が他社依存になることや、製品の差別化が難しいなどの難点もあります。
サブスクリプションビジネスとOEMの違い
サブスクリプションビジネスは近年注目されているビジネスの一つです。「サブスク」と省略されることもありすっかり耳慣れた契約形態は、あらゆる業界やサービスで導入されています。
サブスクリプションビジネスでは、顧客は定期的な支払いを行い、特定の期間にわたって製品やサービスを利用します。では、サブスクリプションビジネスは前出のストックビジネスと同じなのでしょうか?
サブスクリプションビジネスは、継続的に収益を得るストックビジネスの一形態です。ただ厳密にいえば、サブスクリプションはストックビジネスを実現する課金方法の一つであり、ビジネスモデルではないという点で異なっているといえるでしょう。
ここでOEMとサブスクリプションビジネスの関係についても整理しておきましょう。前述したように、OEMは代理店契約の一形態です。OEMが扱うサービスや製品は幅広く、含まれるビジネスにはストックビジネスもフロービジネスもあります。
例えば、フロービジネスの一つとして、近年小売店が売り出しているプライベートブランドが挙げられます。他社ブランドが製造したものを自社ブランドで売り出す手法であり、典型的なOEMといえるでしょう。
プライベートブランドとして、セブン&アイグループの「セブンプレミアム」のアイテム数は約3,500、累計売上額は10兆円を超えました。イオンの「トップバリュ」の2020年の売上高は8,414億円、2021年は8,389億円、2022年は9,000億円でした。いずれも全国に店舗をもつセブンイレブンやイオンの販売網を商品メーカーが最大限に活用した「Win-Win」関係といえます。
他方、ストックビジネスのOEM販売の例として、クラウドサービスがあります。クラウドサービス事業者のストレージやバックアップのサービスを自社ブランドとして提供することで、継続・安定的な収益を見込めます。
.png)
ここでは、前出のOEM(ホワイトラベル)のメリットについて深掘りしてみましょう。
すでに述べたようにOEMは他社の製品を利用し、自社での開発や製造の必要がないため、コストや時間を大幅に節約できます。そのため、スピーディーに市場投入ができますし、短時間での自社ブランド確立が可能です。
自社で開発や製造に多くのコストを投下する必要がないため、より多くのリソースを「価値」の提供、つまりサービスや製品の企画やマーケティング戦略に振り向けることができます。「セブンプレミアム」にしても「トップバリュ」にしても、目指しているのは単なる「モノ」を売ることではなく、商品の購入を通じて得られる顧客体験(UX)の向上です。
どの製品やサービスにおいてもUX向上が重要なのは、製品やサービスの「質」や「特徴」だけでは競合との差別化が難しくなっているからです。また、インターネットやSNSを通じて膨大な製品やサービスの情報を手に入れることができます。
そんな中、ブランド名を見るだけで心が踊ったり、ワクワクしたり、便利だ、安心だと感じたりすると、顧客はリピーターとなり、継続的にそのブランドの製品を購入したいと願うようになるのです。
ホワイトラベルについて詳しく知りたい方はこちら

OEMとしてクラウドサービスを選択することにはどんなメリットがあるのでしょうか?
クラウドサービスで「アップセル」「クロスセル」が可能
顧客単価を高めることを目的としたマーケティング手法に「アップセル」「クロスセル」があります。アップセルとは、より高価格なものへの乗換をすること、クロスセルとは、メインの製品やサービスと関連した別の製品やサービスの購入を促すことです。
クラウドサービスをOEMとして利用することを検討している代理店の中には、コピー機などのオフィス製品のリースを扱っているケースもあります。クラウドサービスを導入する企業が急増している現状において、自社の製品やサービスにクラウドの機能を追加できれば、相乗効果が高まり、顧客を囲い込むことができ、顧客単価を向上できます。
クラウドサービスはスケーラビリティやセキュリティが優れている
OEMのメリットは、優れた価値を提供することで顧客体験の向上を狙える点です。しかし、逆にいえば、提供するサービスの質によっては自社のブランドを毀損することになりかねません。
この点、クラウドサービスはスケーラビリティやセキュリティが優れており、OEMとして利用することで、顧客は「自社のビジネスの拡大や発展」という価値を体感できます。
また、クラウドサービスが提供する「セキュリティ」という価値も非常に重要です。なぜなら、顧客のビジネスにとってクラウドサービスが扱うデータや情報の価値は高まり続けているからです。その一方、企業の情報という資産を盗取しようとするサイバー攻撃や、データを消失させてしまう自然災害は脅威といわざるを得ません。加えて、新規のハードウェアは1年で5~10%、5年で25~40%が故障するといわれています。クラウドサービスによって自社の情報資産が「安全」に保護されることは、どの企業にとっても大きな価値を生みます。
クラウドサービスなら代理店の負担も少ない
OEMをビジネスとして選択する場合、利益を最大化するためには、代理店側の負担をできるだけ少なくしたいところです。
この点、クラウドサービスなら、サービス提供事業者が定期的なアップデートやメンテナンスを行ってくれます。代理店側には多くの作業が必要ないため、より多くのリソースを営業やカスタマーサポートに割くことができ、さらなる売上向上を目指せます。
.png)
ここでは、数あるクラウドサービスの中でも、使えるねっと製品をOEMにおすすめする理由について解説します。
使えるねっとが提供する製品には、ユーザ数無制限のクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」、災害やマルウェアからデータを守る「使えるクラウドバックアップ」、検出率ほぼ100%のクラウドメールセキュリティサービス「使えるメールバスター」があります。
・顧客に高レベルで低価格なサービスを提供可能
例えば、「使えるファイル箱」は専用のインターフェースを必要とせず、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有フォルダを扱うため、普段の業務とシームレスに心地よく使ってもらえます。
また、モバイルアプリを活用することで現場や外出先からのデータもタイムレスに共有・同期することが可能です。もちろん、複合機との連結も可能であり、スキャンやFAXデータのアップデートも簡単です。
法人向けクラウドストレージのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
・コストを大幅に削減
使えるねっと製品の管理やメンテナンスに関しては使えるねっとの専門スタッフが対応するため、代理店側の人的、機械的コストを割いていただく必要はありません。
・サービス価格を自社で設定可能
サービス価格を自社で設定できるため、キャンペーン時に自社の他製品と組み合わせて割引すれば、クロスセルも可能です。その結果、売上の相乗効果や顧客の囲い込みが期待できます。
使えるクラウドバックアップの高度なソリューション
使えるクラウドバックアップは、世界150カ国、50万社以上の企業が利用するアクロニスのサイバープロテクションを採用しています。また、ファイルだけでなく、アプリケーション、オペレーティングシステム、ユーザアカウント、各種設定を含めてシステムイメージ全体を一気にバックアップするため、バックアップにかかる時間短縮が可能です。
さらにバックアップ機能以外にも、ランサムウェア攻撃からデータを守るためのAIベースのテクノロジーを搭載し、セキュリティ対策も万全です。
クラウドバックアップ製品の多彩な機能について詳しく知りたい方はこちら
クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
使えるねっとの製品を自社ブランド化することで、顧客を囲い込み、安定・継続的な収益を目指してみるのはいかがでしょうか?使えるねっとのサービスは顧客満足度も高く、解約率も低いため、営業の効率化を実現することも可能です。
20年以上の業界実績、パートナー契約は北海道から沖縄まで130社超、使えるねっとはサブスクビジネスの経験とノウハウを活かし、御社のビジネスモデル転換を手厚くサポートいたします。
導入費用を含めた詳細に関してはお気軽にお問合せください。
使えるねっとパートナープログラムの詳細はこちら>>

(1)ストックビジネスの強みは?
ストックビジネスの強みは、安定した継続的な収益が得られることです。将来の売上の見通しを立てやすいため、具体的な経営計画を策定することができます。
(2)ストックビジネスが向いている業種は?
ストックビジネスの典型例はインフラサービスです。水道や電気・ガス・インターネットなどはほとんどの人が毎日のように使うため、継続的な収益が見込めますが、その分、初期投資に莫大な費用がかかります。クラウドサービスもデータセンターの建設やセキュリティの構築など初期投資には費用がかかりますが、今後のビジネスにとっては欠かせないサービスであるため、ストックビジネスとの親和性が非常に高いといえます。
(3)ストックビジネスが初めてでも大丈夫?
ストックビジネスを始めるためにはそれなりに投資が必要ですが、OEMと組み合わせることで、初期コストを最小限に抑えることができます。「ストックビジネス×OEM」なら、使えるねっとの製品がおすすめです。使えるねっとは蓄積してきたノウハウに基づき、初めての方にも充実したサポートを提供できます。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
近年、「ホワイトラベル(white label / ホワイトレーベルとも)」という言葉を耳にする機会が増えました。「OEM(Original Equipment Manufacturing)」と言い換えても良いと思いますが、他社メーカーで製造されたものを自社ブランドとして販売するビジネス手法のことです。ちなみにプライベートラベル(プライベートブランド)とは、サービス業者や小売店がメーカーへOEM生産を委託することです。
お気づきの通り、ホワイトラベルやプライベートラベルは私たちの生活の至るところに溢れています。身近な例でいえば、セブンイレブンに並んでいる「セブンプレミアム」が思い浮かびます。スイーツからパン、お菓子や飲み物など様々な商品がありますが、どれも他社が製造した商品をセブンイレブンが自社ブランドとして売り出している「ホワイトラベル」です。ちなみに多くの方が使っているiPhoneもアップル社が生産している訳ではありませんので、ホワイトラベルと言って良いでしょう。
そして実は、弊社の「使えるファイル箱」をはじめ、「使えるクラウドバックアップ」や「使えるメールバスター」も、皆さまに自社ブランド化してお使いいただけるんです。
目次
ホワイトラベル/販売代理店ご検討中の企業様必見のクラウドサービスとは?
ホワイトラベルに「使えるファイル箱」が選ばれる理由
クラウドサービス需要の高まり
ホワイトラベルなら手軽で安全
FAQ

「使えるファイル箱」とは弊社が提供しているクラウドストレージサービス、つまりインターネットでつながれたサーバにデータを保存するサービスのことです。
インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでもファイル共有が可能なため、データ管理の利便性が高くなります。加えて、クラウド化により社内の基幹システムを統合している企業様とも親和性があるといえるでしょう。
また、「使えるクラウドバックアップ」とは、もしものときに備えてデータをバックアップ、確実かつ迅速なデータ復旧を可能にし、さらにはランサムウェア対策、ウイルス・マルウェア対策、脆弱性診断やパッチ管理など、対象端末を総合的に保護するための情報セキュリティサービスです。
さらに「使えるメールバスター」は、標的型攻撃メールをはじめ、迷惑メールがメールサーバに届く前にブロックするメールセキュリティサービスで、撃退率はなんと99.98%。
では、「使えるファイル箱」や「使えるクラウドバックアップ」、「使えるメールバスター」を自社ブランド化することにはどんなメリットがあるのでしょうか?
ホワイトラベル化のメリット
現在、使えるねっとは北海道から沖縄まで約150社のパートナー様と提携していますが、約90%は「使えるファイル箱」のOEM提供、つまり自社ブランドとして展開していただいています。
UX向上につながる
ホワイトラベル化のメリットの一つは、UX(ユーザ体験)向上です。
それぞれの企業様にはそれぞれの商品や商材、サービスがありますが、目指すところは共通しています。それは単に「モノ」「サービス」を売るのではなく、お客様に「モノ」「サービス」を通じて感動を与えることではないでしょうか?
先ほどの「セブンプレミアム」の例でいえば、その商品数はすでに多岐にわたり(2022年7月末時点で約3,500アイテム)、ユーザの生活の隅々に浸透しています。ユーザは「おいしい」「便利」というだけの理由で購入しているのではなく、そこから得られる快適さ、心地よさを感じており、いわばそのような体験に対して対価を払っているのです。どの商品からもシームレスに得られる満足感こそがセブンプレミアムが多くの人に支持されている理由でしょう。
同様に「使えるファイル箱」などのサービスを自社ブランド化していただくことで、お客様のメインサービスに「プラスアルファ」の体験をご提供いただけます。クラウドサービスはデータを扱うため、どのお客様にとっても毎日使うものであり、ありとあらゆる業務に直結します。具体的な特徴は後述しますが、「使えるファイル箱」などのサービスを自社ブランド化することで、御社のお客様に使うたびに「簡単」「分かりやすい」「安心」という体験を提供することができます。
今後も需要の高まりが見込める
IDC Japanの調査によると、2022年の国内クラウド市場は売上ベースで前年比37.8%増の5兆8,142億円でした。また、今後2027年までCAGR(年間平均成長率)17.9%で推移し、2027年の市場規模は2022年の約2.3倍の13兆2,571億円になると予測しています。
こうした日本でのクラウドサービス需要の動向に関するデータが示す通り、クラウド市場は今後も拡大が見込まれます。クラウドサービスOEM提供のビジネスチャンスを生かすことで営業拡大を狙えるのです。また、中小企業向けホワイトラベルクラウドサービスは、商品開発や品質管理にかかるコストが一切不要な点も大きなメリットといえるでしょう。
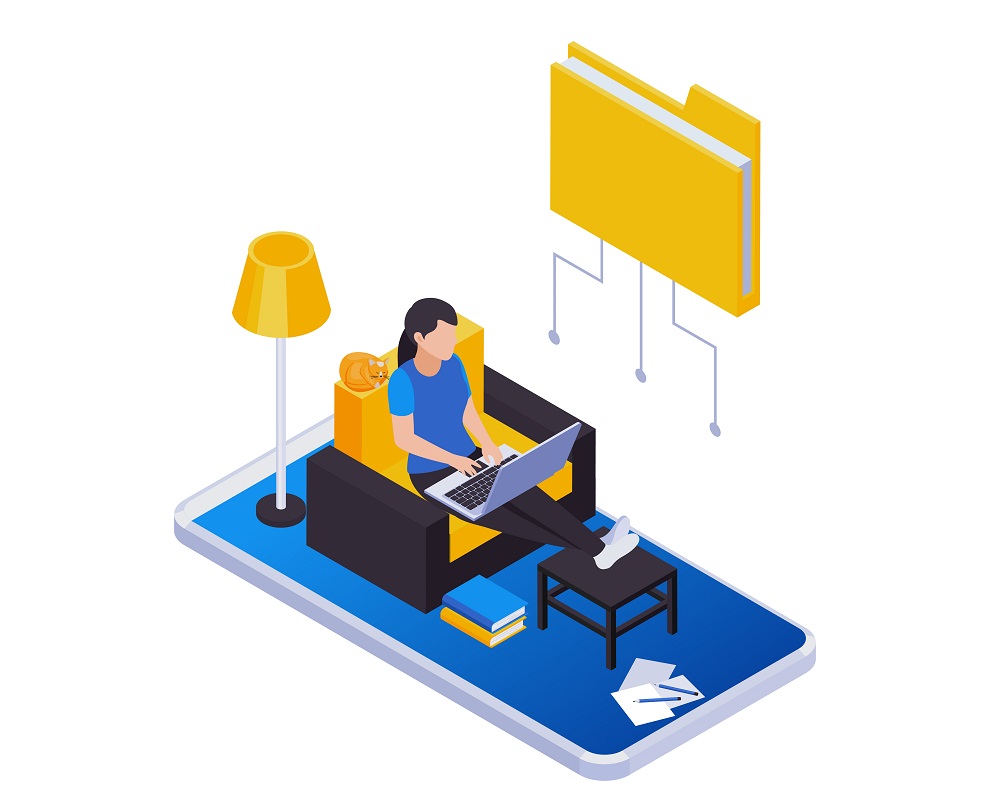
ホワイトラベルクラウドストレージのカスタマイズ方法
例えば、「使えるファイル箱」のOEM(販売代理店)化をお申込みいただきますと、約1ヵ月から1ヵ月半くらいで御社にお引渡しが可能です。御社のロゴやコーポレートカラーにカスタマイズさせていただきます。お引渡し後、自社ブランド化された「使えるファイル箱」をどのように販売するか、つまり価格設定や契約期間は御社の販売計画やブランド戦略に合わせて決めていただくことができます。「使えるファイル箱」は、カスタマイズ可能なクラウドストレージの選び方に迷っている方にとってもおすすめです。

使えるねっとが提供するクラウドサービスが「自社ブランド化」に耐えうるサービスなのか、不安を感じる方も少なくないでしょう。ここでは、「使えるファイル箱」を例として取り上げ、本当に御社ユーザ様に最高のUXを提供できるのか、検討してみましょう。
抜群の機能性×ユーザ数無制限で使いやすい
Webサイトやアプリの開発で重視されているのはどのページを開いても色やラベルが同じパターンであること、ボタンやアイコンのデザインが統一されていることです。これが、「情報が探しやすく、使いやすく、親切」というUXにつながります。
この点、「使えるファイル箱」も専用のインターフェースを必要とせず、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有フォルダを扱うため、普段の業務とシームレスに心地よく使っていただけます。
また、オフィス端末だけでなく、外部のモバイル端末での使いやすさも必須です。「使えるファイル箱」ならモバイルアプリを活用することで、現場とオフィスのデータもタイムレスに共有・同期可能です。加えて、複合機との連携も可能なので、スキャン・FAXデータを自動でファイル箱へアップロードもできます。
さらにユーザ数無制限のため、100人でも1,000人でも料金が一律です。無制限ユーザ対応クラウドサービスのメリットは、追加料金なしで会社の成長に合わせて自由にユーザを追加できる点です。権限はユーザごとに設定できるため、共有情報の管理も楽ですし、社員だけでなく、顧客や協力会社との情報共有にも使えます。

販売代理店パートナーもエンドユーザもはじめてでも安心
UXの中でも特に重要な要素は「安心感」です。食品であれば「産地表示があること」「無農薬であること」「エコであること」、電化製品であれば「壊れにくいこと」「誰でも使いやすいこと」「サポートがしっかりしていること」などがユーザに安心感を与えてくれます。
ではクラウドストレージサービスにおいてはいかがでしょうか?エンドユーザがまず重視するのは何と言っても「セキュリティ」です。
クラウドストレージのセキュリティ機能とは?
この点、「使えるファイル箱」は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビット暗号化を使用しており、2要素認証設定も可能です。また、近年甚大な被害を中小企業にもたらしているランサムウェア対策もばっちり、初心者でも安心のクラウドストレージサービスといえるでしょう。
ストックビジネスにも魅力的!データ保護を強化するクラウドストレージの活用法
使えるファイル箱の自社ブランド化はいわゆる「ストックビジネス」として魅力的です。ご承知のようにストックビジネスとは契約したら終了までその期間は継続して対価を得られるビジネスモデルです。売り切り型のビジネスモデルではなく、継続的な収益につながりますので、資産を蓄積(ストック)し、安定的な事業構築に寄与します。また、ストレージソリューションは解約率が低い製品のため、営業の効率化を実現することも可能です。(厳密に言えば全く同じではありませんが)最近流行りの「サブスクリプションビジネス」と言い換えても良いかもしれません。
今のビジネスシーンは「VUCA(ブーカ)」つまり、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」が特徴ですが、御社のビジネスモデルに「ストックビジネス」を取り入れることで収益の見通しが立ちやすくなり、「安心感」が得られます。
さらに「使えるファイル箱」に疑問や問題があったときには弊社のサポートセンターが電話、チャット、メールで丁寧にサポートさせていただきます。

総務省の情報通信白書(令和3年版)によると、2020年においてクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%であり、2019年よりも4.0ポイント上昇しました。また、クラウドサービスの効果について「効果があった」と回答した企業は87.1%(「非常に効果があった」32.5%、「ある程度効果があった」54.6%)に達しており、今後この傾向はさらに強まると考えられます。
デジタル化が進む中、クラウド移行はもはや必須に
多くの経営者がデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出するDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性を感じていますが、いまだにその取り組みは不十分と言わざるを得ません。経済産業省はDXを阻んでいる要因の一つとして、既存システムが事業部門ごとに構築されていて、全社横断的なデータ活用ができていない点を挙げています。そして、このまま課題が解決されなければ2025年以降、毎年最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています(「2025年の崖」)。そのためのソリューションは多岐に渡りますが、クラウドサービスの活用は必須だといえます。
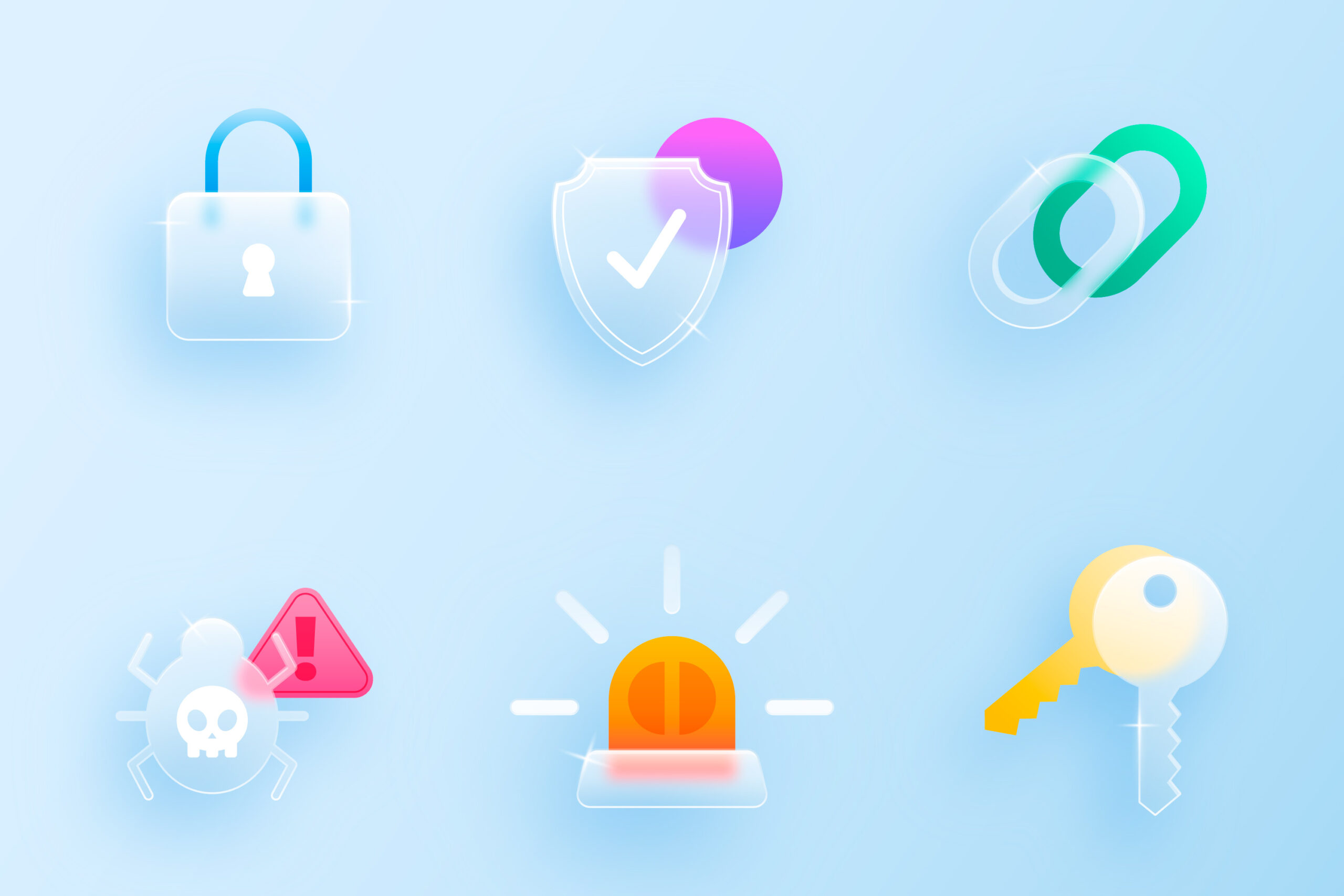
上述した総務省の情報通信白書(令和3年版)によるとクラウドサービスの利用内訳で一番多かったのが「ファイル保管・データ共有」(59.4%)でした。多くの企業はこの流れに乗り遅れないよう今後もクラウドサービスの導入を進めていくものと思われます。
この機会に使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」を自社ブランド化し、御社のお客様のUX向上を目指してみてはいかがでしょうか?20年以上の業界実績、サブスクビジネスの経験とノウハウを生かし、御社のビジネスモデル転換を手厚くサポートいたします。
また、価格設定や販売形態は自由に選べるため、御社の強みや状況に合わせて利益を出しやすい契約形態をお選びいただけます。単体での販売の他、既存製品とのクロスセルも効果的です。
導入費用を含めた詳細に関しては是非お気軽にお問い合わせください。
クラウドサービスの販売代理店パートナー募集中!
<ホワイトラベル化可能サービス>
・「使えるファイル箱」
・「使えるクラウドバックアップ」
・「使えるメールバスター」
*その他のサービスについてはお問合せ下さい。>>
.jpg)
(1)ホワイトラベルとは何ですか?
他社メーカーで製造されたものを自社ブランドとして販売するビジネス手法のことです。OEM(Original Equipment Manufacturing)とも言い換えられます。 たとえば、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」「使えるファイル箱」などのサービスを企業様でご購入いただき、自社製品・サービスとして別のブランド名の下で販売することができます。
(2)クラウドサービスをホワイトラベル化/OEM提供することのメリットとは?
商品開発や品質管理にかかるコストが一切不要で、迅速に市場で販売を開始できる点は大きなメリットです。独自のソリューションをゼロから企画・開発するには時間も資金も要してしまいますが、ホワイトラベルの仕組みを利用すれば最小限のリソースで質の高い自社ブランドを確立することができます。 自社の販売計画やブランド戦略に従って、今後も拡大が見込まれるクラウド市場において、お客様に対して向上したUX(ユーザ体験)を提供しながら営業拡大を狙えます。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)



.png)
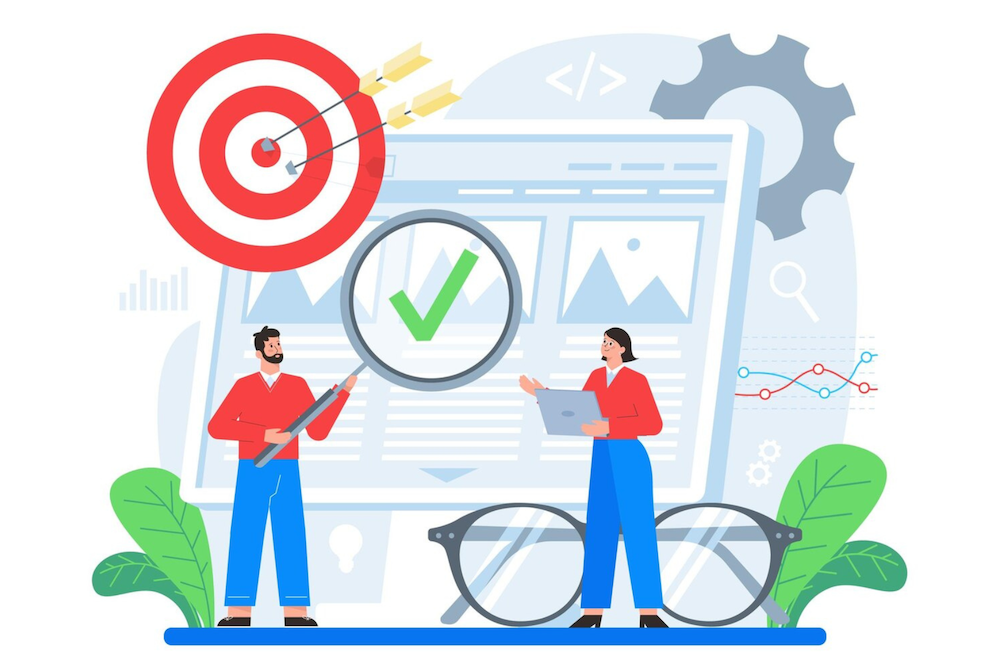
.png)


.jpg)
.jpg)
.png)

.png)

.png)

.jpg)




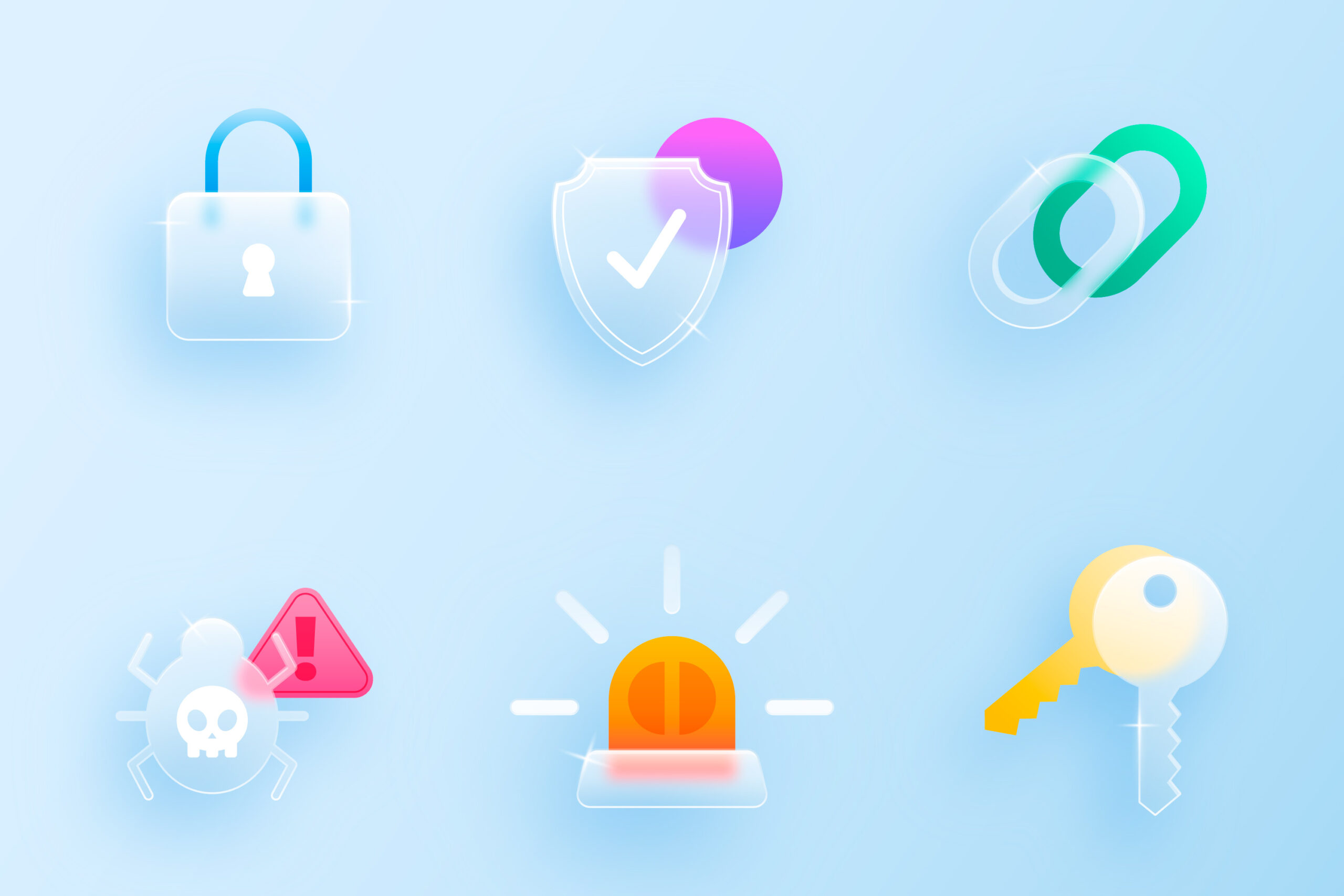
.jpg)
.jpg)
