日々、SNSや広告向けのコンテンツ制作に追われるマーケティング部署や制作チームの皆さん、動画保存や画像ファイルの共有に苦労していませんか?特に、大容量データのやり取りやストレージ容量の制限は、効率的な業務の大敵です。
多くのマーケティング部署や制作チームは、データの共有や編集・加工のためのツールとしてクラウドストレージを活用しています。今や、世の中にはたくさんのクラウドストレージサービスがあふれていますが、この記事では、中でもユーザ数無制限のクラウドストレージ「使えるファイル箱」にフォーカスして紹介します。
大容量動画やSNS素材をラクラク保存でき、チーム全体の生産性向上を実現したいご担当の方、必見です。
クラウドファイル共有について知りたい方はこちら
目次
データ容量の現実:マーケチームや制作チームの課題
必要なストレージ容量の目安と一般的なクラウドサービスの比較
大容量データを効率的にやり取りするポイント
「使えるファイル箱」の特徴とメリット
クラウドストレージでチームの働き方を変革しよう
FAQ
.jpg)
ツールのICT化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、どの企業、どの部署にとってもデータの重要性は高まる一方ですし、扱うデータ量は増加の一途をたどっています。
ここでは、マーケチームやコンテンツ制作チームが直面している課題について概観します。
マーケチームが直面する課題~データ量の増加
マーケチームや制作チームが直面している課題を一言で表すとすれば、データ量の増加です。その背景には以下の理由が挙げられます。
ユーザとデジタルとの接点が増加している
かつてユーザの購買行動は対面・店頭がメインでした。しかし、今では多くの人たちがECサイトや自社ホームページ、SNSなどを通じて、サービスや製品について認知し、購入するようになっています。こうしたデジタルとの接点の増加により、企業は膨大な情報を蓄積できるようになりました。
そのため、多くの企業が担当者の経験や直感にたよっていたマーケティングから、いわゆる「データマーケティング」「デジタルマーケティング」へとシフトしています。例えば、Webサイトの訪問者の行動データや購入履歴、ソーシャルメディア上の反応など、入手したデータをもとに顧客の趣向や行動傾向を把握し、マーケティング戦略に活用しているのです。
その結果、より顧客のニーズに合致したサービスや製品を提供することが可能になり、無駄なコストを削減し、効果的な販売戦略を展開できます。
SNS動画や広告動画の運用
デジタルマーケティングの中でも特に重要なのが「SNSマーケティング」です。SNSマーケティングとは、InstagramやXなどのSNSを企業の担当者が運用し、自社商品の認知や購買活動を促進し、ユーザの顧客体験を向上させ、ファン獲得を目指すマーケティング活動を指します。
多くのユーザが複数のSNSアカウントを保有しているため、SNSの効率的な運用により、企業はユーザとの継続的かつ効果的な顧客接点を持つことが可能になります。特に魅力的なSNS動画や広告動画を制作すれば、いわゆる「バズる」ことで、スピーディかつ爆発的に情報を拡散できます。
動画や画像ファイルの容量はどのくらい?
以上のように、マーケティングにおけるデータの重要性が大きくなるにつれ、マーケチームが保存する動画や画像ファイルの量も増大していきます。
マーケチームが日常的に制作する動画や画像ファイルの大きさはどのくらいなのでしょうか?例えば、1分のHD動画であれば約100MB、SNS用画像1枚であれば5MBを目安と考えていただければよいでしょう。動画1本、画像1枚であれば大した容量ではないように思いますが、動画であれば100本、画像であれば2,000枚で10GBに達します。
こうした動画保存や画像制作が続けば、あっという間に容量不足やデータ管理が課題になってしまいます。
.jpg)
データ量の増加に伴い、どのくらいのストレージ容量を必要とするかは各企業ごとに違いがあるでしょう。ただ、前述したように1分のHD動画100本で10GBに達することを考えると、年間で数十GB~数TB(1,000GB=1TB)に及ぶケースも十分考えられます。
1TB(テラバイト)とはどのくらい?パソコン(HDD)やデータストレージの容量も解説
データを保管する方法として考えられるのはサーバなどのオンプレミスか、インターネットを経由してデータセンターに保管するクラウドストレージです。それぞれメリットとデメリットがありますが、増加の一途をたどるデータ量に対応するためにはクラウドストレージがおすすめです。
オンプレミスVSクラウドストレージ
データ保管場所としてクラウドストレージをおすすめする理由は以下の通りです。
1. 拡張性
前述した通り、最大の理由はクラウドストレージの拡張性の高さです。オンプレミスの場合、初期設定の容量から増設するには、新たなファイルサーバを購入し、システム全体を再設定しなければなりません。
それに対してクラウドストレージは、サービス提供事業者にプランの変更やストレージの追加を依頼するだけで、容量を増やすことができます。
ファイルサーバのクラウド化と比較について知りたい方はこちら
2. コスト
オンプレミスの場合、導入する際に機器の購入やシステムの構築が必要なため、高額なイニシャルコストがかかります。また、専門スタッフによる保守・点検が常に必要なので、そのための人件費もかかります。
それに対して、クラウドストレージであれば、サービス提供事業者に依頼すればすぐに導入可能であり、ほとんどのサービスで初期費用は必要ありません。一般的に月ごと、年ごとの利用料を支払い続けます。当然、利用期間が長くなればなるほどコストは増えますが、社内に専門スタッフを常駐する必要がないため、別途の人件費は必要ありません。
一般的なクラウドサービスの比較
現在、個人や企業が利用できるクラウドサービスは山ほどあります。それらのサービスをストレージ容量に注目すると、容量無制限か否かで分けられます。
増え続ける社内データのことを考えると、容量無制限のサービスを選んだ方がよいのでは、と考える方は少なくありません。確かにマーケチームや制作チームの場合、扱うデータがテキストベースではなく、画像やデザイン、動画が多いため、必要なデータ容量も必然的に増えます。しかし、容量無制限であればその分コストがかかる可能性があります。必要性とコスト面でバランスのとれた選択をするように心がけましょう。
以下では法人向けのスタンダードなプランを比較してみましょう。
|
プラン
|
容量
|
利用可能なユーザ数
|
料金
|
|
Microsoft 365
Business Basic
|
ユーザ1人あたり
1TB
|
~300人
|
899円(月額、
ユーザ1人、税抜)
※年間サブスクリプ
ションの場合
|
|
Dropbox Business
(Busienss)
|
9TB~
(チーム全体)
|
3人~
|
1,500円(月額、
ユーザ1人)
※年間払いの場合
|
|
Box
(Business)
|
無制限
|
3人~
|
1,881円(月額、
ユーザ1人、税込)
※年間一括払いの場合
|
|
Google Workspace
(Business Standard)
|
2TB
|
~300人
|
1,360円(月額、
ユーザ1人)
※年間契約の場合
|
|
使えるファイル箱
(スタンダード)
|
1TB
|
無制限
|
21,230円(税込)
※1年契約の場合
|
.png)
セキュリティの確保
最初に注意したいポイントはセキュリティです。そもそもクラウドストレージをデータの保存先として選ぶということは、セキュリティ管理を自社ではなく、サービス提供事業者にお任せするということです。そのため、クラウドストレージサービスを選ぶにあたっては、セキュリティ面がどの程度充実しているかをチェックしておきましょう。
クラウドサービスへの不正アクセスによって情報漏えいが発生すれば、企業に対する信頼は失墜しますし、場合によっては金銭的な賠償も必要になりかねません。
また、企業によっては情報資産を守るためのセキュリティポリシーを定めている場合もあります。サービスの使いやすさだけでなく、自社のセキュリティポリシーに準拠しているかどうかにも注意しなければなりません。
さらに、マーケチームや制作チームの場合、社内だけでなく、クライアントなど社外ユーザとクラウド経由でデータのやり取りを行うことも考えられます。そのため、リンク共有や権限設定の管理を慎重にする必要があります。
アップロード上限
ストレージ全体の容量が無制限であっても、クラウドサービスの中には単一ファイルのアップロードに上限を設けている場合もあります。例えば、単一ファイルのアップロード上限が1GBであれば、ストレージ容量自体に余裕があっても、そのデータが1GBを超えれば保存することはできません。
マーケチーム、制作チームの場合、取り扱うデータが高画質な画像や動画ファイルの場合も少なくないため、事前に単一アップロードの上限を確認しておくことは欠かせません。
.png)
数あるクラウドストレージサービスの中で、特におすすめは使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」です。ここでは、使えるファイル箱の特徴とメリットを4つ紹介します。
無制限の容量で安心感:動画や画像を制限なく保存可能
使えるファイル箱は「スタンダード」と「アドバンス」の2種類のプランをご用意しています。
概要は以下の通りです。
|
プラン
|
容量
|
ユーザ数
|
料金
(月単位、税込、
1年契約の場合)
|
|
スタンダード
|
1TB
|
無制限
|
21,230円
|
|
アドバンス
|
3TB
|
無制限
|
60,500円
|
上図に示す通り、初期設定ではスタンダードプランの容量は1TB、アドバンスプランの容量は3TBですが、ご希望に応じて無制限に容量の追加が可能です。料金は1TBごとに月額8,580円(税込)です。
クラウドサービスによっては無制限がデフォルトのものもありますが、使えるファイル箱であれば必要に応じて追加できるため、より効率的にクラウドストレージを活用できます。
高速アップロードとダウンロード:業務の効率化をサポート
マーケチームや制作チームでは、日常的に頻繁にデータのやり取りを行います。それだけにスピードは欠かせない要素といえるでしょう。
使えるファイル箱なら、高速アップロード&ダウンロードで業務の効率化をサポートします。また、アップロードのファイルサイズ上限はないため、大容量のデータも気兼ねなく扱えます。
簡単な共有機能:社内外のコラボレーションをスムーズに
使えるファイル箱ならデータの共有も簡単。共有したいファイルを右クリックし、メニューから共有リンクを作成して送るだけです。
また、外部ユーザなどと連携する場合は、ユーザごとに権限を設定できるため、共有情報の管理が容易ですし、セキュリティ対策もばっちりです。
アドバンスプランの場合、グローバルIPアドレスを指定することで他のIPアドレスからクラウドストレージへのアクセスを制限できたり、新しいデバイスでの初回アクセスを管理者に通知することで、認証されたユーザのみにクラウドストレージにアクセスさせたりする機能も付帯しています。
コストパフォーマンスの良さ:競合サービスとのコスパ比較
使えるファイル箱のコストパフォーマンスを競合サービスと比較してみましょう。前述したように、多くのクラウドストレージサービスはユーザ1人あたりの料金を設定していますが、使えるファイル箱はユーザ数無制限で、スタンダードプランは月単価21,230円です。つまり、ユーザ50人で使えば1ユーザあたり約425円、100人だと1ユーザあたり約212円です。
容量が1TBでは心配なら、10TB追加してみましょう。1TBあたり8,580円ですから、10TB追加すれば85,800円が追加され、月単位の料金は107,030円です。これをユーザ100人で使っても1ユーザあたり約1,070円であり、コスパの高さがお分かりになるのではないでしょうか?
.jpg)
高機能かつコスパの高いクラウドストレージである使えるファイル箱を活用することで、大容量ファイルの共有や加工・編集も容易になり、忙しい現場のストレスを軽減できます。特に企業のマーケティング部署やSNSマーケチーム、広告代理店での運用において実力を発揮すること間違いなしです。
ここでは、使えるファイル箱の活用事例を2つ紹介します。
福助株式会社
福助株式会社は1882年(明治15年)に創業した老舗中の老舗で、足袋の製造、卸売、小売に加え、靴下・肌着・ストッキングの製造、卸売、小売を展開しています。2022年で創業140年を迎えた現在は、老舗の看板に甘んじることなく、オンラインストアの事業展開や有名ブランドとのライセンス契約など、デジタルも活用した戦略を推し進めている点が特徴です。
同社の課題は、中間卸に加えて直営店の運営も行っているため、約2,000社との取引があり、データのやり取りが急増していた点です。また、近年のハイブリッドな働き方の導入も増えており、社内外で安心してコストを抑えたクラウドストレージサービスを探していたといいます。
福助では使えるファイル箱の導入に向け、WEB事業部でトライアル期間を設け、1ヶ月ほどの試験運用を実施しました。トライアル期間中に社内への使えるファイル箱導入のアナウンスとマニュアルを準備していたこともあり、導入はスムーズだったそうです。
使えるファイル箱のスタンダードプランは容量が1TBと制限があるため、現在は一時的な共有用として使用しています。デザイン等で高画質な画像をよく使用するため、ファイルサイズが大きい場合の外部とのファイルのやり取りに活用しているとのことです。
株式会社NBG
株式会社NBGは全国規模のお酒の買取およびバー事業を展開している企業です。NBGの本社は京都ですが、他にも大阪、東京、福岡などにもオフィスを設置しているため、複数拠点でデータの共有を行う際にタイムラグが生じたり、データ送信の確認に手間取ったりなど、コミュニケーション面で課題が生じていました。
最終的に使えるファイル箱を選ぶ決め手となったのは、導入の手軽さ・使いやすさだったといいます。主に社内用のドキュメントを共有するために使えるファイル箱を活用しているそうですが、事業部や役職ごとにフォルダを分けるなど、細かい設定ができる点も便利だと感じています。
無料トライアルからお試しを
大容量動画や画像の保存も思いのままに行えるクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」。ユーザ数無制限で、ニーズに応じてストレージも無制限に拡張可能です。
まずは30日間の無料トライアルからお試しください。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
.jpg)
1. 動画ファイルの容量はどれくらいが一般的ですか?
動画の容量はフォーマット、解像度、フレームレート、動画の時間によって変わります。1分の動画であれば、容量は以下の通りです。
|
フォーマット
|
解像度
|
フレームレート
|
容量
|
|
MP4
|
1080p
|
30fps
|
約45MB
|
|
AVI
|
1080p
|
30fps
|
約80MB
|
|
MOV
|
1080p
|
30fps
|
約60MB
|
2. クラウドサービスで効率よく動画をアップロードするには?
クラウドサービスはインターネットを経由するので、通信状況の影響を大きく受けます。効率よく動画をアップロードするためには、高速回線の環境を選びましょう。また、バックアップ作業を同時に行っているとアップロードに時間がかかってしまいます。
3. チームでクラウドストレージを使う際の注意点は?
チームでクラウドストレージを使う場合、アカウントの管理が重要です。特にユーザ数無制限の場合、ユーザがいつの間にか増えてしまい、セキュリティ管理が手薄になってしまう可能性があります。社外ユーザもアクセスできる場合は、権限設定にルールを設けるなどの配慮が必要です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
総務省が2024年6月に発表した「令和5年通信利用動向調査」によると、クラウドサービスを「全社的に利用している」「一部の事業所又は部門で利用している」と回答した企業の割合は合わせて77.7%であり、2022年の72.2%、2021年の70.4%から上昇し続けています。
さらに、同調査によると、「非常に効果があった」と回答した企業は33.5%、「ある程度効果があった」と回答した企業は54.9%で、合計88.4%がクラウドサービス利用の効果を実感している点は注目に値するでしょう。
ここでは、ますます導入が拡大しているクラウドサービスの基本や、使えるねっとの安心・お得なクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」について解説します。これからクラウドストレージの導入を検討している方、現在使用しているクラウドストレージの使い勝手に不満を感じている方は是非お役立てください。
目次
クラウドストレージとは?
クラウドストレージの容量無制限とユーザ数無制限のメリット
「使えるファイル箱」には本当に使える機能がたくさん
「使えるファイル箱」ならではの特徴
FAQ

クラウドストレージとは、「インターネットを経由してアクセスできるデータセンターにデータを保存するサービス」のことです。
従来、多くの企業でファイルはローカル環境(パソコンや会社のサーバなど)に保存していました。それに対してクラウドストレージの場合、ファイルを「クラウド」、つまりインターネットを経由してデータセンターに保存するため、以下のようなメリットがあります。
・いつでもどこでも、好きな場所・端末からファイルにアクセスでき、テレワークにもぴったり
・社内・部署内や、社外のコラボレーターと簡単にファイルを共有できる
・パソコンが壊れたり、会社のローカル環境が被災したりしても、データはクラウド内にあるから無事
.jpg)
クラウドストレージサービスにはたくさんの種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまうはずです。それぞれのサービスに特徴があり、強みがあれば、弱みもあります。
大切なのは、自社の業務スタイルや従業員規模に合ったサービスを選ぶことですが、迷ってなかなか決めきれない方におすすめなのは「容量無制限」、あるいは「ユーザ数無制限」のクラウドストレージサービスです。それぞれのメリットは以下のとおりです。
容量無制限のメリット
容量無制限のメリットは、サイズの大きなファイルや大量のデータも制限を気にせずに保存できることです。
近年中小企業も含め、多くの企業がDXに注力しています。デジタル技術を活用して新たな価値を創出しようとすると、企業が扱うデータの量は必然的に膨大になります。
また、毎日の業務で頻繁に利用することはないものの、法令により一定期間保管が義務付けられているデータもあります。こうしたアクセス頻度は高くないものの、削除するわけにはいかないデータを「コールドデータ」と呼びますが、容量無制限のクラウドストレージであれば心配することなく法的要請にも応えることができます。
容量に制限があると、企業が扱うデータが増加して足りなくなった場合、さらにコストを支払ってストレージを追加しなければならなくなります。そうなると、データ管理のためのコストが膨らみ、企業の経営を圧迫することにもなりかねません。その点、容量無制限のクラウドストレージサービスであれば、導入の段階でかけるコストを予測でき、管理がしやすいといえるでしょう。
ユーザ数無制限のメリット
ユーザ数無制限のメリットは、従業員の増減に柔軟に対応できることです。
例えば、わずかな従業員で企業を立ち上げた場合、クラウドストレージを利用するユーザ数はそれほど多くないでしょう。しかし、企業の成長とともに従業員は増えていきます。また、取引先などの社外と情報共有したいケースも増えてくるかもしれません。ユーザ数無制限であれば、ユーザの増加に伴う追加コストは必要なく、安心です。
限られているユーザ数で「ユーザ数無制限」のクラウドストレージを使うのは「もったいない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、企業の状況は刻一刻と変化し、その中でデータをどのように共有し、活用するかは重要な課題です。コストを気にすることなく、毎月同額で無制限のユーザにデータを共有できることは大きな安心感につながりますし、予算を組みやすい点でも大きなメリットがあるはずです。
クラウドストレージのタイプ比較とおすすめツールはこちら
.png)
使えるねっとの「使えるファイル箱」には、本当に「使える」機能が満載。以下では、そのうちのいくつかについて解説しましょう。
ユーザ数無制限
使えるファイル箱はユーザ数無制限のため、社員が増えてもユーザ課金や権限発行に悩むことはありません。これから成長が見込まれる中小企業としては、将来の発展を見据えながらも、予算を立てやすいといえるでしょう。逆に不要になったアカウントは、該当ユーザを削除するだけです。
他方、ストレージの容量はスタンダードプランで1TB、アドバンスプランで3TBです。もちろん、データ容量も追加は可能です。
シンプルで使いやすい抜群の操作性
使えるファイル箱は普段のパソコンと同じくシンプルな操作のため、クラウドストレージの導入に合わせて研修を実施して操作法を学ぶ必要はありません。Windowsならエクスプローラー、MacならFinderでデータのダウンロード、アップロードが可能です。
セキュアにファイルやバージョンを自由自在に復元
重要なファイルを保存し、共有する上で不可欠なのは、セキュリティです。使えるファイル箱なら、外部のユーザにファイルを送りたいときはWebリンクを使用して手軽にシェアできますが、パスワードと有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心です。ユーザごとにフォルダのアクセス権限を設定することも可能です。
ファイル箱についてよくある質問はこちら
.png)
使えるファイル箱には、上記で挙げた「使える」機能以外にも、以下のような特徴があります。
抜群のセキュリティで安心
SSL通信に加え、シークレットキーによる2重暗号化を実施。また、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムであるAES256ビット暗号化を採用しています。これは、2の256乗のパターンの鍵を持つことを意味しており、総当たり攻撃でパスワードを解析して不正アクセスを試みる場合、コンピュータによる解析を行ったとしても解読には数百兆年かかるといわれています。
充実のカスタマーサポート
どれだけシンプルな操作性だったとしても、はじめての方であれば使い方に悩むことはありますし、サイバー攻撃など思いがけないトラブルが発生することも考えられます。そのため、使えるねっとでは、専属スタッフによる充実のカスタマーサポートを設けています。電話はもちろん、メールやチャットでのお問い合わせも受け付けていますので、困ったときも安心です。
また、「使えるシャトル便」で弊社が郵送したHDDにお客様のデータをコピーして宅配便でご返送いただければ、弊社側でお客様の「使えるファイル箱」にアップロードを行います。(1回/1TB 55,000円、追加1TB 11,000円)
圧倒的なコストパフォーマンス
使えるファイル箱にはいずれもユーザ無制限のスタンダードプランとアドバンスプランをご準備。上述したように2つのプランでは容量が異なりますが、それ以外にもアドバンスプランでは、IP制限やダウンロード回数制限など、セキュリティ対策がさらに充実しています。
年間契約の場合、スタンダードプランは21,230円(月単価、税込)、アドバンスプランは60,500円(月単価、税込)です。スタンダードプランを従業員100人で使用された場合、月額1人あたり約210円、300人では月額1人約70円で済みます。
30日間の無料トライアルも実施しているため、気になる方は、「使えるファイル箱」でクラウドストレージの便利さを体感してみませんか?
使えるファイル箱の詳細はこちら
.jpg)
法人向けのクラウドストレージの市場規模は?
2021年度のクラウドストレージの市場規模は約3.5兆円でした。今後、クラウドストレージの市場規模は2025年~2026年には現在の2倍以上にまで拡大すると予測されています。
クラウドストレージのユーザ数は?
ICT総研によると、2021年3月末に5,176万人だった国内の個人向けクラウドストレージサービスの利用者は2022年3月末には5,345万人になりました。また、2021年3月末時点の有料サービスの利用者数は1,535万人でした。
クラウドストレージの国内シェアは?
ICT総研によると、2022年4月時点で個人利用のクラウドストレージサービスの中で最も利用者が多かったのはGoogleドライブで、ついでAppleのiCloud Drive、3位はMicrosoftのOneDriveでした。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
企業が情報を管理したり、共有したりする方法はさまざまです。その中の一つにNASがあります。近年、従来のファイルサーバに替えて、NASを導入する企業が増加しているともいわれています。
ここでは、NASとファイルサーバの違いや、それぞれのメリット・デメリット、選び方について、さらには「第三の選択肢」としてのクラウド型ファイルサーバの特徴について解説します。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
NASとファイルサーバの違いについて
NASとファイルサーバができること
ファイルサーバの見直しが求められている背景
ファイルサーバのメリット5つ
ファイルサーバのデメリット2つ
NASのメリット3つ
NASのデメリット2つ
NASとファイルサーバ5つの比較ポイント
NASとファイルサーバはどちらを使うべき?
NAS及びファイルサーバを運用する際の注意点
クラウド型のファイルサーバとは?
クラウド型ファイルサーバのメリット
クラウド型ファイルサーバのデメリット
「使えるファイル箱」ならコストを抑えてデータ共有が可能
FAQ

最初にNASとファイルサーバとは何か、それぞれの使い方と違いについて説明します。両者の違いについてよく理解しないまま導入すると、かえって業務効率が低下したり、必要以上にコストがかかったりする可能性があります。
NASとは
NASとは「Network Attached Storage」の頭文字を組み合わせたもので、日本語に訳すと「ネットワーク接続型ストレージ」です。
名前が示す通り、NASとはストレージ(補助記憶装置)です。すぐに思い浮かぶストレージとしてはPCとUSBケーブルなどで接続する外付けハードディスクがありますが、NASはネットワークを経由して接続する点が異なります。
NASの使い方
NASの主な使い方はファイルのバックアップと共有です。
ネットワークで接続しているため、ネットワーク内の異なるユーザがアクセスし、パソコンやスマートフォンなどのデータをバックアップしたり、相互に共有したりすることが可能です。
ファイルサーバとは
ファイルサーバとは、ネットワークを経由してファイルを管理したり、共有したりするためのシステムのことです。
サーバとはそもそも、ネットワークでつながるコンピュータからのリクエストに応じてさまざまなデータや機能を提供する仕組みのことです。サーバには、Webサーバやメールサーバがありますが、ファイルサーバとは、その中でもファイルの管理や共有に特化した機能を提供する仕組みを指します。
ファイルサーバの使い方
ファイルサーバは基本的に自社で導入構築するため、業務や用途に合わせて柔軟に設定したり、機能を追加したりできます。
例えば、管理者はファイルやフォルダごとにアクセス権限を自由に変更できます。また、ファイルサーバ上でのアクセスや編集などの履歴を記録すること(アクセスログ)も可能です。
NASとファイルサーバの基本的な違い
NASはハードディスクと同じような「機器」であり、ファイルサーバは「システム」です。
そのため、NASは購入して、すでに構築されているネットワークに接続すれば使えるのに対して、ファイルサーバは端末、ソフトウェアなどを組み合わせて構築するため、より手間がかかります。また、導入後に管理や運用をする上でも、ファイルサーバはNASよりもコストがかかります。

ここでは、NASとファイルサーバを比較します。どちら「にも」できること、どちらかに「しか」できないことを明確にすることで、自社にとって最適なソリューションを見つけられるでしょう。
NASとファイルサーバが両方できること
NASとファイルサーバが両方できるのは、ファイルの保存と共有です。
ファイルの保存ができるので、ネットワーク内のユーザは自分のパソコンを使って作成したファイルの保存先としてNASやファイルサーバを選べます。その結果、自分のパソコンのハードディスクがいっぱいになってしまうことを防げますし、データをNASやファイルサーバにバックアップし、万が一のデータ消失リスクにも備えられます。
また、NASやファイルサーバにデータを共有することで、他のユーザとの共同作業も楽になります。もし、NASやファイルサーバを使わなれば、メールに添付したり、USBメモリを使ったやりとりになったりするため、情報漏洩のリスクが高まります。つまり、NASやファイルサーバは情報セキュリティのソリューションとしても有効なのです。
NASだけができること
ファイルサーバと比べてNASが優れているのは、導入や運用が簡単なことです。NASはファイルサーバと違って自分でネットワーク構築する必要がないため、導入時に細かな設定は必要ありません。
ファイルサーバだけができること
NASよりもファイルサーバが優れているのは、導入時に自社のニーズに合わせて柔軟に機能を設定したり、追加したりできる点です。NASはあくまでも「ストレージ」のため、データの保存がメインですが、ファイルサーバは「システム」としてのカスタマイズが可能なのです。

ファイルサーバの見直しが求められている背景には、企業を取り巻く環境が大きく変化している点が挙げられます。ここでは具体的な2つの点を説明します。
・ランサムウェア攻撃などへの対応の必要性
・新しい働き方の普及
以下で一つずつ解説していきます。
ランサムウェア攻撃などへの対応の必要性
ランサムウェアとは、パソコンやサーバなどの端末を感染させて中のデータを暗号化し、そのデータを復元するために対価(金銭や暗号資産)を要求する不正プログラムです。いうまでもなく、ファイルサーバの中に保管されているデータも被害ターゲットになります。警察庁が2024年3月に発表した資料によると、2023年中に警察庁に報告されたランサムウェアの被害件数は197件で、前年比14.3%減でしたが、引き続き高い水準で推移しています。
リモートワークなどの柔軟な働き方に対応し生産性を維持しながらも、新たな脅威に対処していくことがすべての企業に求められています。
新しい働き方の普及
従来、端末がすべてオフィスに存在し、社内で情報を共有するにはファイルサーバで何ら問題はありませんでした。しかし、テレワークの導入で従業員が社外からもアクセスする必要が増大しています。
ファイルサーバに社外からアクセスする場合、VPNを使用することが一般的です。しかし、VPNを使用すれば安全という訳ではありません。例えば、IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威2024」によると、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が組織の情報セキュリティ上の脅威で第9位にランクインしており、その主な理由の一つはVPNの脆弱性を狙った不正アクセスだと考えられます。
テレワーク導入の要となるクラウドストレージについて知りたい方はこちら

ファイルサーバの最大の特徴は、上述したように柔軟な設定と自社のニーズに合わせた機能の追加です。さらに具体化すると、以下の5つに集約できます。
1. アクセス権を詳細に設定できる
2. スムーズに容量を拡張できる
3. 機能をカスタマイズできる
4. 業務効率の向上
5. 情報セキュリティの向上
1つずつ解説します。
1. アクセス権を詳細に設定できる
一般的にWindows Serverなどのサーバ用OSでは、Active Directory(Microsoftのユーザ管理機能)などにより、権限管理が容易です。
アクセス権を詳細に設定することで、不正アクセスのリスクを軽減でき、社内の情報セキュリティが向上します。
2. スムーズに容量を拡張できる
通常、個人で使うパソコンでHDDやSSDを増設するのは2台が限界です。しかし、ファイルサーバであれば、数百から数千のHDD、SDDを搭載できます。近年、扱うデータや1つ1つのファイルの大きさが増大しているため、ファイルサーバの拡張性は大きな魅力といえるでしょう。
3. 機能をカスタマイズできる
ファイルサーバでは、自社の特性や業務に合わせて自由度高く機能を追加できます。また、データの重要性に基づいて、自社のセキュリティポリシーに合わせてシステムをカスタマイズできるのもファイルサーバのメリットといえます。
4. 業務効率の向上
企業にとって業務効率の向上は常に重要な課題です。そのための施策はいろいろと考えられますが、データの管理、共有方法は中でも鍵といえるでしょう。ファイルサーバなら、自社の規模や業務内容、直近の課題などに合わせて、比較的自由に設定を変更したり、機能を追加したりできます。
5. 情報セキュリティの向上
今や情報は企業にとっては「資産」のひとつです。データ消失が一旦発生してしまえば、顧客からの信頼を失いますし、経済的な損害もはかり知れません。ファイルサーバは、セキュリティ設定も自由度が高いため、日々変化する企業の情報資産を脅かすサイバー攻撃に合わせて対策を講じることができます。
サイバー攻撃とは何か知りたい方はこちら
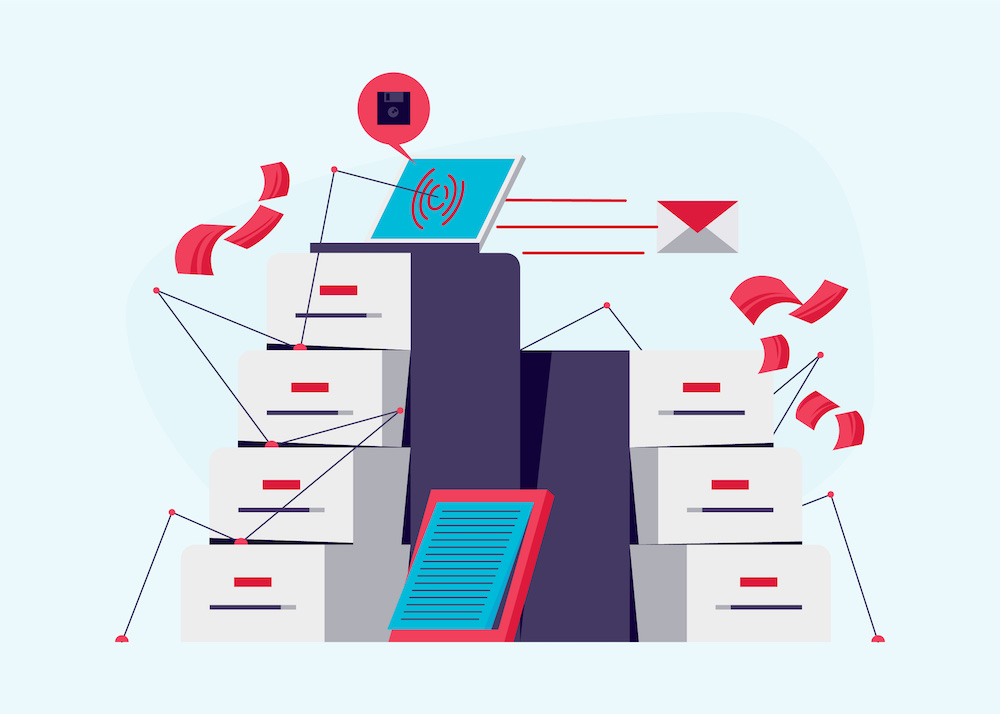
上述したようにファイルサーバには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。ファイルサーバは社内に設置するため、その保守管理を自社で行うことになります。具体的には、以下の2つのデメリットに集約されます。
1. 専門スタッフの常駐が必要
2. コストがかかる
1. 専門スタッフの常駐が必要
ファイルサーバは社内に設置し、社内に専門スタッフを常駐させることになります。その分、社内リソースをファイルサーバの保守管理に割くことになります。少子高齢化で労働力人口が減少している昨今、特に中小企業では人手不足が深刻です。そのため、専門スタッフを常駐することは現実的に困難な場合が少なくありません。
2. コストがかかる
ファイルサーバの設置には、高い導入コストがかかります。具体的には、サーバ機器の購入にかかる費用や社内環境の構築や初期設定にかかるコストも含まれます。
また、導入後のランニングコストにも注意が必要です。ライセンス費用やハードウェア、ソフトウェアのメンテナンス費用、サーバの稼働や空調のための光熱費などもかかります。さらにいずれ古くなったら、ファイルシステム全体を再構築することも不可避であり、それには膨大な費用がかかります。

上述したように、NASの最大の特徴は簡易な導入と運用です。そのことを前提にすると、具体的には以下の3点にまとめられます。
1. ファイルサーバに比べ手軽に導入できる
2. 自社の人的リソースの節約
3. 費用を抑えられる
1つずつ、各メリットの内容について説明します。
1. ファイルサーバに比べ手軽に導入できる
NASの最大のメリットは手軽に導入できる点でしょう。上述したようにファイルサーバの設定には膨大なイニシャルコストがかかります。それに対して、NASはほとんどの場合、ベンダーから製品を購入して、ケーブルをつないで簡単な設定をすればすぐに利用可能です。
2. 自社の人的リソースの節約
導入や運用が簡単なため、自社で専門スタッフを常駐させる必要がありません。そのため、社内の限られた人的リソースを他の業務に回すことができます。もし、使用上のトラブルが発生したら、社内スタッフがメーカーのサポートセンターに問い合わせることでほとんどの場合は解決が可能です。
3. 費用を抑えられる
「NASを導入する」と聞くと多額のコストがかかるイメージがありますが、簡単にいえばこれはストレージを購入することと同じです。そのため、従業員50人程度の中小企業向けなら10~30万円程度で購入でき、運用にも多くのコストはかかりません。

NASは導入、運用いずれの面でもコストを抑えられるため、中小企業には嬉しいのですが、デメリットもあります。具体的には主に2点にまとめられます。
1. 拡張性に限界がある
2. セキュリティレベルに限界がある
以下、それぞれのデメリットについて、その内容を説明します。
1. 拡張性に限界がある
NASは導入時に複雑な設定は必要ない半面、拡張性に欠けます。また、運用期間中に自由に設定を変更したり、機能を追加したりする点でも限界があります。
2. セキュリティレベルに限界がある
NASにもウイルス対策やアクセス権限の設定は可能ですが、状況に合わせた設定の自由度には限界があります。その点で、企業をとりまくサイバー攻撃の多様化を考えると、やや不安を感じる人もいるかもしれません。

NASとファイルサーバの比較ポイントは次の通りです。
1. カスタマイズ性
2. 利用範囲
3. セキュリティ対策
4. 導入、運用方法
5. 導入、運用のコスト
それぞれのポイントについてどちらが自社に最適なのか分析してみましょう。
1. カスタマイズ性
カスタマイズ性が高ければ高いほど、自社の業務や事業規模に最適化しやすくなります。この点、ファイルサーバはまさに自社にフィットするように機器を購入し、システムを構築します。そのため、非常にカスタマイズ性は高いといえるでしょう。一方、NASはファイルサーバほどのカスタマイズ性の高さはありません。カスタマイズ性についていえば、ファイルサーバに軍配が上がります。
2. 利用範囲
どんなシステムでも、漫然と導入すると失敗してしまいます。大切なのは、利用範囲や目的を確定しておくことです。例えば、自社は情報共有することでどのような課題を解決したいのか、そのためにはファイルサーバとNASとどちらが適切なのか、ということです。利用目的を明確にすれば、利用範囲も自ずから絞り込まれてきます。自社の従業員だけで利用するのか、それとも取引先など外部メンバーも含めて利用するのか、保管し共有したいデータはどのくらいのか、などです。
3. セキュリティ対策
結論からいうと、ファイルサーバの方がより安全性の高い情報セキュリティ対策を講じることができます。例えば、サイバー攻撃に対する対策についていえば、ファイルサーバはかなり細かいカスタマイズができるため、情報の重要度に合わせたセキュリティ対策が可能です。それに対して、NASはカスタマイズ性に限界があり、セキュリティ対策が手薄になりがちです。
また、物理的にもNASはコンパクトで持ち運べるメリットがある一方、その分、盗難などによるセキュリティリスクが高まります。ファイルサーバの場合、物理的な持ち出しはほぼあり得ません。
4. 導入、運用方法
上述したように導入の際にファイルサーバは大規模なシステム構築が必要です。それに対してNASは複雑な設定は不要であり、導入したらすぐに利用できます。
5. 導入、運用のコスト
NASはファイルサーバに比べて、導入や運用に手間がかからないため、その分コストも抑えることが必然的に可能です。
参考:NTTコミュニケーションズ 「ファイルサーバーとは? NASとの違いや選び方のポイントなどを解説」

NASかファイルサーバかどちらを選べば良いか迷いますが、重要なのは「何のために導入するのか」を明確にすることです。
「利用目的」に応じて選ぼう
NASとファイルサーバに限ったことではありませんが、機器やシステムを選ぶ際には利用目的をはっきりさせておくことが大切です。
例えば端末に関していえば、スマートフォンやタブレットはいつでもどこでもデータの閲覧をするのに最適なツールですが、動画編集など複雑な作業を行うには限界があります。対して、デスクトップはオフィスや自宅での使用に限られますが、作業範囲は広がります。
端末を使って何をしたいか明確にしておかなければ、費用をかけたものの十分に使いきれないという結果になりかねません。NASとファイルサーバにも同じことがいえます。
NASが適しているケース
NASが適しているのは、小規模の組織でできるだけコストを抑え、ファイルの保管や共有を行いたい場合です。小規模の組織であれば、ネットワーク内のユーザの業務も共通しているため、細かな設定変更がそれほど必要ないことも多いでしょう。
ファイルサーバが適しているケース
ファイルサーバが適しているのは、大規模な組織でファイルの保管や共有に加え、複数部署の多様な業務に対応するために柔軟な設定をしたり、機能を追加したりする場合です。
また、現在は小規模であっても、近い将来に従業員数や業務の増大が見込まれる場合もファイルサーバの導入を検討できます。そうすることで、イニシャルコストはかかるとしても、のちのち効率的にファイル共有を行うことで、生産性の向上が実現でき、長期的にはコスト削減につながるからです。
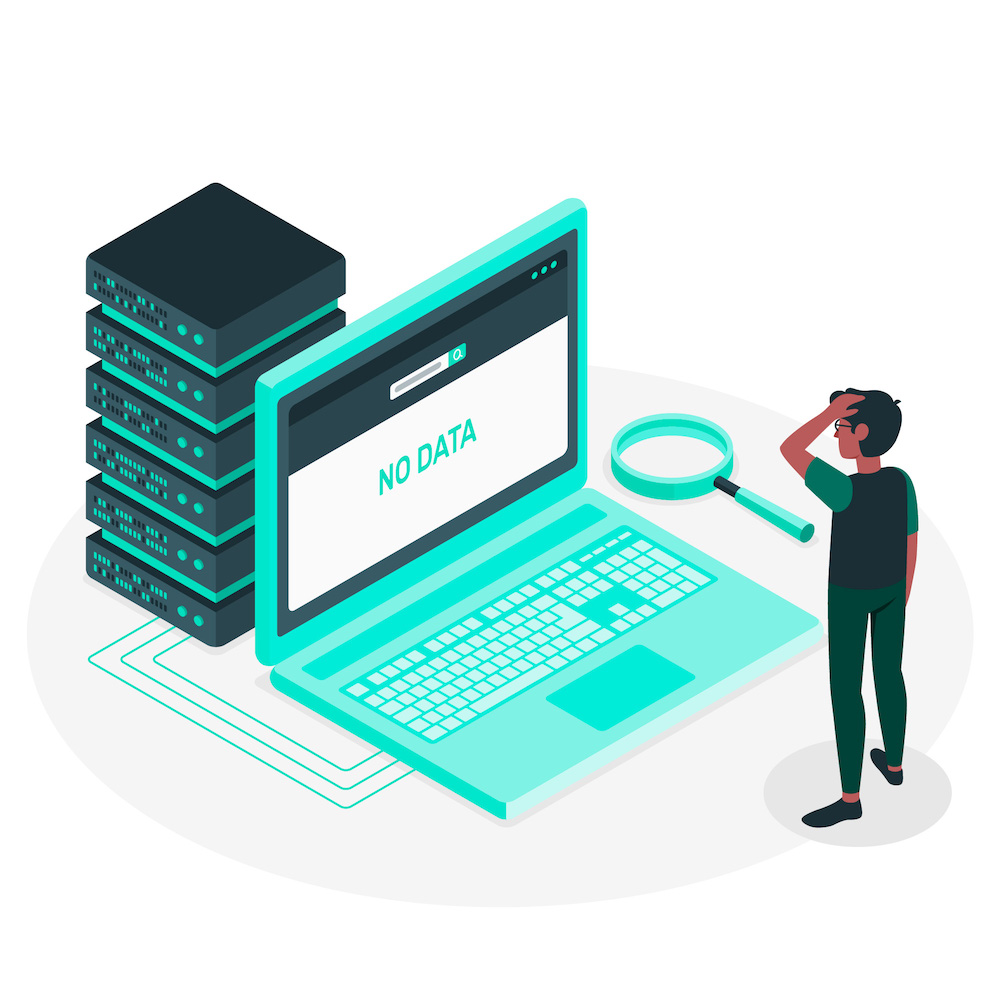
NASを運用する際には物理的影響によるデータ消失のリスクが高い点、ファイルサーバを運用する際には初期コストや人的コストがかかることに注意しましょう。
以下、それぞれについて説明します。
物理的影響によるデータ消失リスクが高い
NASはあくまでもハードディスクと同じように「機器」であるため、物理的な衝撃や経年劣化によるデータ消失リスクがファイルサーバよりも高いといえます。
NASを選択する場合はデータ消失のリスクに備えて、バックアップは必要不可欠でしょう。
導入・運用に対して初期コスト・人的コストがかかる
ファイルサーバは単に機器を購入すれば済むわけではなく、導入にはシステム設計や構築に専門家の手を借りなければなりません。また、導入後も運用や保守点検には専門知識が求められるため、初期コストや人的コストがどうしてもかかってしまいます。

ここまで、NASとファイルサーバを比較してきました。どちらにも一長一短があり、迷ってしまうかもしれません。もしそうであれば、「第三の選択肢」としてクラウド型のファイルサーバも検討してみることをおすすめします。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
法人向けクラウドストレージの比較を見たい方はこちら
クラウド型ファイルサーバは、インターネットを経由したファイルの管理、共有システムです。
インターネットという外部接続ネットワークを使用する点で、社内ネットワークを前提にしたNASやファイルサーバと異なります。
また、自社でファイル保管場所となる機器を設置する必要がない点も特筆すべき点といえるでしょう。
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら

クラウド型ファイルサーバのメリットは以下の4点です。
1. 専門スタッフを常駐させる必要がない
2. どこからでも接続できる
3. 柔軟な運用が可能
4. ランサムウェア対策が可能
以下で1つずつ解説します。
1. 専門スタッフを常駐させる必要がない
クラウド型ファイルサーバのストレージは、クラウドサービス提供業者のデータセンターです。そのため、ストレージの保守管理に自社でリソースを割く必要はありません。クラウドサービス提供業者の専門スタッフが24時間体制でモニターしているため安心です。
2. どこからでも接続できる
クラウド型ファイルストレージはファイルサーバと異なり、インターネットを経由してアクセスするため、どこからでも接続できます。中小企業を含め、多くの企業がテレワークを導入しており、働く場所も多様化しているため、オフィスの外からでも情報共有できるのは大きなメリットといえるでしょう。
3. 柔軟な運用が可能
ファイルサーバのカスタマイズ性の高さは大きな魅力ですが、クラウド型ファイルストレージもアクセス権限を制限したり、柔軟な運用が可能です。クラウド型ファイルストレージを提供している事業者はたくさんあるため、自社に合った機能やサービスをきっと見つけられるはずです。
4. ランサムウェア対策が可能
クラウド型ファイルストレージはランサムウェア対策でも大きな力を発揮します。
ランサムウェアとは、ターゲットが保有する情報を不正に暗号化し、データの復元と引き換えに多額の身代金を要求する悪質なマルウェアです。ランサムウェア攻撃に遭うと企業は多大なる損失を被ります。例えば、2024年6月に株式会社KADOKAWAグループはランサムウェア攻撃を受け、2025年3月期に36億円の特別損失を計上する見通しです。
大企業だけでなく、中小企業もランサムウェア攻撃の対象になります。警察庁が公表した「令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、業種を問わず中小企業が全体の約6割を占めています。
ランサムウェア攻撃を受けた場合、被害を最小限にとどめるためには早期に復旧作業を始めることがなによりも重要です。そのためには万が一に備えたバックアップが欠かせませんが、同じネットワークにつながっているファイルサーバやNASにバックアップデータを保存していると、端末がランサムウェアに感染することで、バックアップデータも暗号化されるリスクがあります。その点、クラウド型ファイルストレージにバックアップを取っておけば、安心なのです。
ウィルス・ランサムウェア対策からパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な用途について知りたい方はこちら
.png)
もちろん、クラウド型ファイルサーバにもデメリットはあります。クラウド型ファイルサーバのデメリットは以下の3点です。
1. 既存システムと統合するのが困難
2. セキュリティリスクが高まる
3. 利用料金が高額になる可能性がある
以下で一つずつ解説します。
1. 既存システムと統合するのが困難
多くの企業がクラウド化を進めたいと思いながらも躊躇している理由の一つとして、既存システムとの統合が難しい点が挙げられます。新しく導入するクラウド型のシステムと既存システムとの連携がうまくいかず、データ共有の際に手作業工程が発生するなど、業務効率がかえって下がってしまうことはよくあります。もっともこの点は社内一丸となって一気にDXを進めることで解決することが可能です。クラウド化をチャンスととらえて、業務フローやシステム全体を見直してみるのも一つの手です。
DXについて知りたい方はこちら
2. セキュリティリスクが高まる
何度も述べているようにクラウド型ファイルサーバはインターネットを経由するため、「閉じられた」社内ネットワークよりもセキュリティリスクはどうしても高まってしまいます。ただ、多くのクラウドストレージサービスがセキュリティ向上に注力しているため、比較して選ぶことでセキュリティ面での不安はかなり軽減できるはずです。
3. 利用料金が高額になる可能性がある
クラウド型ファイルサービスの特徴の1つは導入コストがファイルサーバに比べて低いことです。しかし、課金体系に注意しないと、運用コスト(利用料金)が高額になる可能性もあることを覚えておきましょう。
基本的なクラウドストレージサービス以外にも、オプションでさまざまなサービスを選択できるため、自社にとって本当に必要な機能を見極め、きちんと契約内容を確認しておけば料金について心配する必要はありません。
.png)
クラウド型ファイルサーバをお考えなら、「使えるファイル箱」がおすすめです。
「使えるファイル箱」なら、クラウドに保存したファイルを編集・整理し、Webリンクを使用してファイルやフォルダを無制限に他のユーザに共有できます。
心配なセキュリティに関しても2要素認証設定、暗号化、ログ記録、ISO認証データセンターなどで、自社の情報資産を情報漏洩からしっかり守ります。また、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムAES256ビット暗号化を採用し、ウェブサーバとブラウザ間のデータ通信を暗号化するウェブ管理画面のSSL化も行うため、ファイル型クラウドサービスの懸念点であるセキュリティの不安も払拭してくれます。
ファイルサーバとNASの、それぞれのメリットを併せ持った「使えるファイル箱」を是非ご検討ください。
容量1TB、ユーザ数無制限で月単価21,230円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価60,500円(税込、1年契約)で、WebDAV連携も可能です。料金体系がシンプルで分かりやすいのも使えるファイル箱の魅力です。
30日間の無料トライアルも実施していますので、まずは使い勝手の良さを体感してみてください。
.jpg)
(1)ファイルサーバの種類は何がある?
主なファイルサーバには以下のようなものがあります。
・データベースサーバ
データベースサーバは数値などのデータの管理に特化したサーバで、通常ビジネスで使用するファイルは扱わない。
・クラウドサーバ
社内の機器ではなく、インターネットを経由してつながっているデータセンターにデータを保管するシステム。
・Windowsファイルサーバ
Windowsの機能を利用したユーザ間でファイルを共有するサーバ。導入が簡単だが、セキュリティリスクが高い点に注意。
(2)NASを導入するリスクは?
物理的損傷に弱いNASの最大のリスクは、設置場所で災害が起きた場合にデータ消失してしまう可能性が高い点です。
(3)NASやファイルサーバの置き場所は?
クラウド型ファイルサーバが社外のデータセンターにデータを格納するのに対して、NASやファイルサーバは社内に機器を設置して、そこにデータを保管します。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
IoTやAIなどのテクノロジーが低コストで利用できるようになり、中小企業を含め、企業が保有するデータ量はますます増え続けています。そのため、膨大なデータ管理をどうしたら良いのか、頭を悩ませているご担当の方も少なくないでしょう。データが増えれば増えるほど、災害に備えた大容量データオンラインバックアップ方法も検討しなければなりません。また、ランサムウェアなどのサイバー攻撃にも耐えうる安全なオンラインファイルストレージサービスも必要です。
ここでは、企業がデータを保管するファイルストレージとは何か、そのメリットやデメリット、活用方法に関して説明します。また、数多くあるクラウドストレージサービスの中から自社に適したものを選ぶポイントについても解説します。
目次
ファイルストレージとは?
ファイルストレージを利用するメリット
ファイルストレージを利用するデメリット
ファイルストレージの比較検討のポイント
ファイルストレージの活用方法
高機能&セキュリティで安心:おすすめファイルストレージ「使えるファイル箱」
FAQ

ファイルストレージとは、デジタルデータやファイルを保存・管理するためのオンラインサービスです。厳密にいえば、これまで多くの企業で導入されてきた社内サーバもデータを格納するストレージであり、「ファイルストレージ」とみなして差支えありませんが、近年はクラウドサービスの急速な浸透に伴い「ファイルストレージ=オンラインストレージ」という理解が定着しつつあります。この記事でもその前提で「ファイルストレージ」という語を用います。
ファイルストレージはインターネットを通じてアクセスできるので、社内サーバと異なり、ネット環境さえあればいつでもどこもで繋がることができます。そのため、オフィス内だけでなく、出張先や取引先訪問時でもファイルにアクセスすることができる点が一番の利点でしょう。
多くの企業でコロナ禍のテレワークにより、ファイルストレージの導入が一気に進みました。そして、コロナ後も引き続き高いテレワーク率が維持されています。
例えば、国土交通省が令和5年5月に発表した「令和4年度テレワーク人口実態調査」によると、令和4年度の従業員数1,000人以上の企業のテレワーカーの割合は36.7%で、令和3年度よりも3.4ポイント減少したものの、コロナ前の令和元年時の19.9%のほぼ倍の割合でした。企業規模が小さくなればテレワーカーの割合は減るものの、全体的な傾向としてコロナ前よりも高い水準が保たれています。
.png)
出典:令和4年度テレワーク人口実態調査(令和5年3月)|国土交通省
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001598357.pdf)
また、ファイルストレージは、個人や企業が日常業務の中でファイル共有したり、災害時などに備えたバックアップをしたりするのに利用されます。DXによって企業にとっての情報資産の価値は高まっているため、ファイルストレージはただ大容量でたくさんのデータを保管できるだけでなく、安全性の高さも求められます。

ここでは、ファイルストレージを利用する3つのメリットについて解説します。
データのバックアップ
1つ目に、ファイルストレージを利用することでデータのバックアップを簡単に行うことができます。
現在、企業が保有するデータは多岐に渡ります。商品や顧客情報だけでなく、日常的なメールや社内SNSを使ったやり取り、社内の各種データへのアクセスログなどが含まれ、このすべてを従業員が個別のバックアップで対応するのは困難です。
また、データにとっての脅威として災害やサイバー攻撃だけでなく、ヒューマンエラーの存在も見逃すことはできません。どの企業においてもデータの重要性が高まる中、理由が何であれデータを消失してしまうなら、取引先や顧客からの信頼を一気に失ってしまいます。
この点、ファイルストレージによりデータのバックアップをしておけば、リスクを最小限に抑えることが可能です。
データの共有
2つ目に、ファイルストレージがあれば複数の人が同じデータにアクセスできるため、チームでの作業や共同プロジェクトの管理がスムーズに行えます。
ファイルストレージがなければ、データの共有はメールやチャット、オフィス内であればUSBメモリ経由で行うことになりますが、やりとりできるデータ量が限られてしまいます。また、受け取ったファイルを複数人が編集する場合、どのデータが最新版なのかが分からなくなることもあります。
この点、ファイルストレージなら大容量データを扱えますし、複数人がファイルストレージ上で編集できるため、データ保存の手間も省け、どのバージョンが最新版なのかも一目瞭然です。
ストレージ容量の拡張
3つ目に、ファイルストレージは必要に応じて容量を拡張することができるため、データ量が増えても安心です。
スタートアップのフェーズではそれほど多くの容量が必要なくても、従業員数や企業規模が拡大するにつれて保管するデータ量は増えていきます。ファイルストレージなら、事業の成長に合わせて大切な情報を保管できます。

多くのメリットがあるファイルストレージの利用ですが、デメリットがない訳ではありません。ここでは2つのデメリットについて説明します。
インターネット接続が必要
ファイルストレージを利用するためには、常にインターネットに接続している必要があります。オフライン環境では利用できません。
そのため、ファイルストレージに格納されているデータへのアクセスや、ファイルストレージ上での編集はインターネットの速度に依存してしまいます。オフィスなどネット環境が整った場所では快適にファイルを閲覧したり、仕事ができますが、出張先などで不安定なネット環境だと業務に支障が出る可能性があります。
セキュリティリスク
ファイルストレージの別のデメリットは、オンライン上にデータを保存するため、セキュリティリスクが存在する点です。適切なセキュリティ対策を行う必要があります。
これまでサイバー攻撃からデータを保護する点で、ファイルストレージはオンプレミスよりも安全だと考えられてきました。しかし、クラウド特有の脆弱性を悪用し、企業のクラウドデータを感染させて窃取する「ランサムクラウド」と呼ばれる攻撃がトレンドになってきている点を、多くの専門家が指摘しています。
従来型のオンプレミスでは、ファイアウォールによって内側と外側の境界を区切り、企業の情報資産は常に社内ネットワークの中に保管されていました。しかし、ファイルストレージはインターネットで繋がっているため、内側と外側の境界線が引きにくくなり、従来の社内サーバで採用していた方法では情報を守ることができません。
そこで、ファイルストレージが直面するセキュリティリスクに対応するために生まれたのが「ゼロトラスト」の考え方です。これは、名称が示す通り、社内外関わりなく「何も信頼しない」ことを前提にして、通信経路の暗号化やユーザ認証の強化、ログ監視などにより、情報資産を守ろうとするアプローチです。

現在オンプレミスを使用していて、これからファイルストレージを導入する場合、数多くある中から自社に最適なサービスを選ぶにはどうすれば良いのでしょうか?
比較するポイントはたくさんありますが、ここでは必ずチェックしておきたい5つのポイントである「ストレージ容量」「セキュリティ」「ユーザ数」「料金体系」「操作性」について解説します。
ストレージ容量
企業の規模や従業員数、業務形態や保管するデータの種類などによって、自社にどのくらいのストレージ容量が必要なのかを検討します。
自社の将来性も考慮すれば、安心なのは「容量無制限」です。しかし、使い切れない可能性もありますし、サービスによっては「容量無制限」を選択すると料金が高額になる場合もあるため、安易に選ぶのではなく、必要十分な容量を見極めるようにしましょう。
ちなみに比較する際には「1TB(テラバイト)」がどのくらいかを理解しておくと役立ちます。大体の目安ですが、1枚1MBのオフィスファイルなら約100万枚、1分ほどの短い動画(10MB)なら約10万本、フルHD動画ファイルなら約166時間に相当します。
セキュリティ
いくらたくさんのデータを保管できても、それらがサイバー攻撃を受け、貴重な情報が消失してしまうなら、企業は甚大な被害を被ります。そのため、ファイルストレージサービスを選ぶ際にはセキュリティを重視する必要があります。
具体的にはアクセス制限、通信経路、ファイルの保存や送受信においてどのようなセキュリティ体制が構築されているのかをチェックしましょう。
ユーザ数
多くのサービスではユーザ数に制限があります。サービスを利用するために最低限必要なユーザ数を定めていたり、ユーザ数が増えるとプランの変更手続きが必要になったり、料金が加算されたりします。
一方、同じ料金でユーザ数無制限のサービスもあります。その場合、企業が急成長を遂げ、従業員が増えてもプランを変更する必要はありませんし、必要に応じて取引先にユーザIDを発行し、データ・ファイル共有することも自由にできます。
料金体系
ファイルストレージサービスの料金体系は大きく「データ容量課金制」と「ユーザ課金制」に分けられます。
前者はデータ容量に応じて料金が決められているサービス、後者はユーザ数に応じて料金が決められているサービスです。自社のユーザ数や必要なデータ容量に応じて、コストパフォーマンスを考慮してサービスを選びましょう。
操作性
ファイルストレージサービスの操作性も重要なポイントです。操作を学ぶのに従業員の大がかりな研修が必要になるとすれば、導入に二の足を踏んでしまうでしょう。普段使っている自社のOSと親和性がありスムーズに操作できれば、導入コストも最低限に抑えられるはずです。

「ファイルストレージがあると便利そう」とは思っても、実際の業務や現場でどのように使われているのか、イメージが湧きにくい方もいるでしょう。ここでは、ファイルストレージの具体的な活用方法について紹介します。
取引先とのデータの受け渡し
ファイルストレージがあれば、ユーザIDとパスワードを新たに発行し、自社の従業員に加えて、外部の取引先や協力会社ともデータ・ファイル共有が簡単にできます。サービスによってはユーザ数が無制限のため、何十、何百ものユーザを簡単に追加できるのです。
ただ、社外のユーザが簡単に自社のファイルストレージにアクセスできることを懸念される方もいるかもしれません。もちろん、社内機密の情報に簡単にアクセスできないように、ファイルストレージでは権限の設定も自由自在です。例えば、「ダウンロードのみ」「アップロードのみ」のように設定し、ゲスト専用のフォルダにのみアクセスできるようにすれば、セキュリティ面でも安心です。
また、ユーザ数が増えれば増えるほど心配なのは共有するデータ量かもしれません。確かに社内サーバのようなストレージに保存する場合は物理的な限界がありますが、クラウドサービスならデータ量に応じて自由にストレージを増やすことができますし、最初から容量無制限のサービスを選ぶこともできます。
請求書のペーパーレス化
2022年1月に電子帳簿保存法(電帳法)が改正されてから2年の猶予期間がありましたが、2024年1月より電子保存が完全に義務化されました。これにより、電子データとして受領した請求書はすべてデータのままで保存しなければならなくなり、出力はできなくなりました(紙で受け取った請求書を電子化する義務はなし)。
この改正をきっかけに多くの企業が進めているのが請求書のペーパーレス化です。これまでは社内で作成、修正、承認、発行、送付という手続きをプリントアウトした書類で行っていた会社が、請求書をペーパーレス化し、ファイルストレージを使って社内他部署や取引先と共有するワークフローに徐々に移行しています。
これにより、紙やインク代などのコストだけでなく、請求書の発行や送付の作業が不要になり、人的コストも大幅に削減できます。取引先に共有する場合はアクセス権限の適切な管理・設定も自由自在です。
テレワーク環境の充実
コロナ禍以前になかなかテレワークが導入されなかった理由に、多くのファイルが社内サーバに保管されていたため、必要なデータに自宅などテレワーク環境からアクセスできないという問題がありました。
しかし、ファイルストレージを導入すれば、自宅であっても、出張先や取引先であっても、ネットワーク環境さえあればすぐに必要な情報に社内と同じようにアクセスできます。ファイル同期や編集もストレージ上で可能なため、共同作業も簡単に行え、いつでもどこでもオフィスにいるのと同じような作業環境を作り出すことができるのです。
BCP対策
BCP対策とは、企業が災害などの緊急事態においても被害を最小限に抑え、事業を継続できるようにするための対策・計画のことです。その一環としてファイルストレージを活用できます。ファイルストレージに企業にとって重要な情報を保管しておけば、万が一の事態に備えたバックアップになります。
.png)
「使えるファイル箱」は使えるねっとが提供するファイルストレージサービスです。ここでは、「使えるファイル箱」を企業向けファイル共有ソリューションとしておすすめする3つの理由について解説します。
ユーザ数無制限
「使えるファイル箱」はユーザ数無制限なので、企業の成長や従業員の増減に合わせて金額はそのままで柔軟に対応できます。ちなみに使えるファイル箱のスタンダードプランは1年契約の場合、月額21,230円(税込)で利用できるため、100人で利用すれば1人あたり月額210円程度、300人で利用すれば1人あたり月額70円程度で済みます。容量も必要十分な1TBです。
セキュアストレージで大切なデータを保護
「使えるファイル箱」は安心のセキュリティ対策で企業の大切なデータをしっかり守ります。
具体的には、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズム「AES256ビット暗号化」を採用し、Webサーバとブラウザ間のデータ通信も暗号化します。また、ユーザごとに権限を設定できるため、外部取引先や協力会社とのファイル共有も安心です。もちろん、「使えるファイル箱」はバックアップサービスとしても利用可能です。
普段のパソコンと同じくシンプルな操作
Windowsはエクスプローラー、MacはFinderでデータのアップロードやダウンロード、共有が行えるため、使い慣れた操作でファイル共有が可能です。「使えるファイル箱」は導入したらすぐに社内で使い始めていただけます。
「使えるファイル箱」は容量が1TBのスタンダードと、3TBのアドバンスの2つのプランがあります。アドバンスプランでは、IPアドレス制限やダウンロード回数制限など、セキュリティ面をさらに強化しています。
1年契約の場合、スタンダードプランは月額21,230円(税込)、アドバンスプランは月額60,500円(税込)です。1年契約には、初回契約期間中ならいつでも解約・返金申請ができる全額返金保証が付帯します。
まずは30日間の無料トライアルで使い心地や操作感を試してみてはいかがでしょうか?
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>

(1)ファイルストレージとは?
ファイルストレージとは、デジタルデータやファイルを保存・管理するためのオンラインサービスです。厳密にいえば、これまで多くの企業で導入されてきた社内サーバもデータを格納するストレージであり、「ファイルストレージ」とみなすことができます。近年はクラウドサービスの急速な浸透に伴い「ファイルストレージ=オンラインストレージ」という理解が定着しつつあります。
(2)ファイルストレージのメリットとは?
1. データのバックアップ
企業が保有する多岐にわたるデータのバックアップを簡単に行うことができます。
データにとっての脅威として災害やサイバー攻撃、ヒューマンエラーなどありますが、取引先や顧客からの信頼失墜になりかねない、データ消失のリスクを最小限に抑えることが可能です。
2. データの共有
ファイルストレージがあれば、複数の人が同じデータにアクセスできるため、チームでの作業や共同プロジェクトの管理がスムーズに行えます。
3. ストレージ容量の拡張
ファイルストレージは必要に応じて容量を拡張することができるため、事業の成長に合わせて、データ量が増えても大切な情報を保管できます。
(3)ファイルストレージのデメリットとは?
1. インターネット接続が必要
ファイルストレージを利用するためには、常にインターネットに接続している必要があります。オフライン環境では利用できません。
2. セキュリティリスク
ファイルストレージの別のデメリットは、オンライン上にデータを保存するため、セキュリティリスクが存在する点です。適切なセキュリティ対策を行う必要があります。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)



.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)



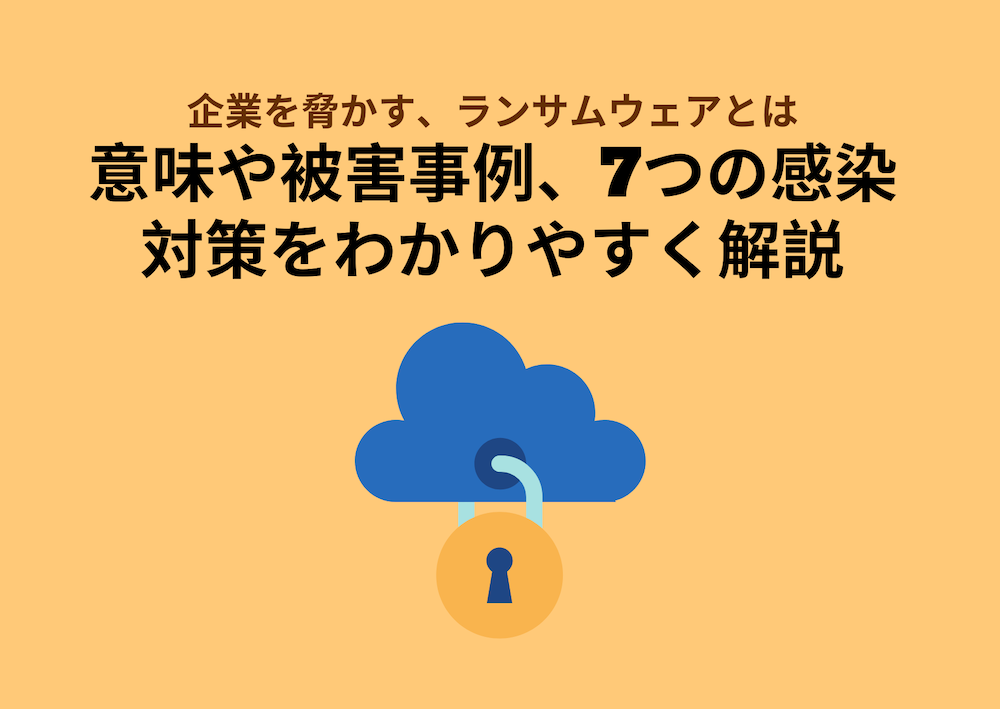

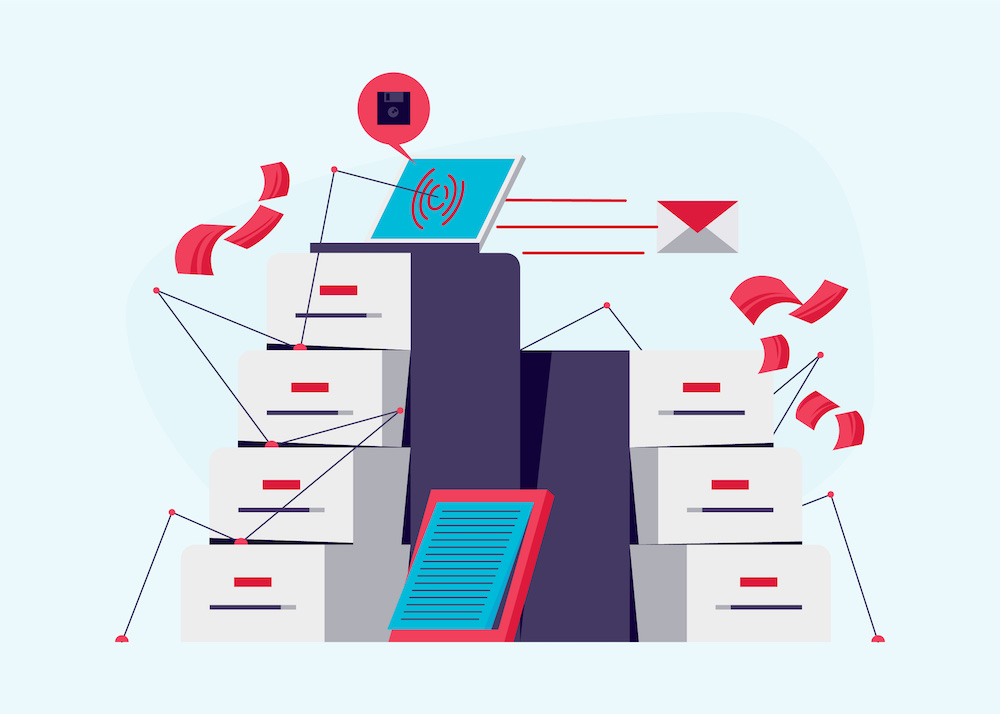




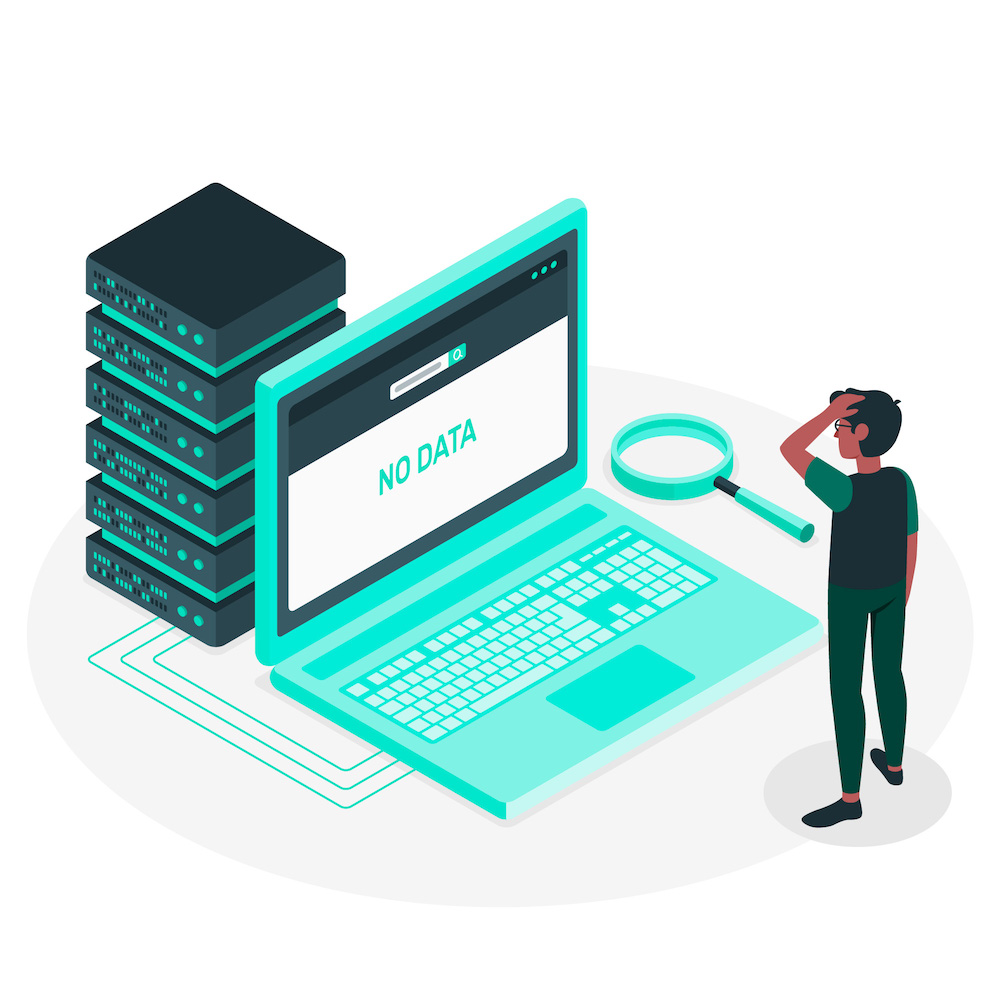

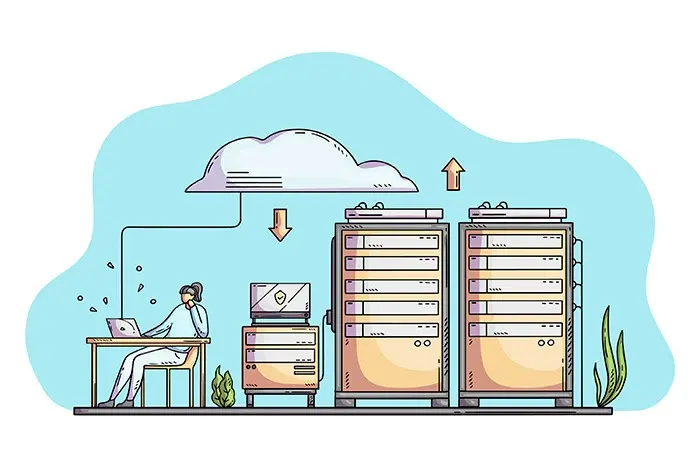

.png)
.png)
.jpg)
.jpg)


.png)




.png)

.jpg)
