令和5年の情報通信白書によると、世界のパブリッククラウドサービス市場は2021年に45兆621億円となり、前年比28.6%増加しました。日本のパブリッククラウドサービス市場も2022年に前年比29.8%増の2兆1,594億円に達しており、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるために今後どの企業もクラウドストレージをますます活用し、ICT基盤を強化していくことが予測されます。
今やビジネスに欠かせない存在となったクラウドストレージですが、自社にとって最適なサービスを選ぶのは至難の業です。ここでは、クラウドストレージの基本をおさらいし、クラウドストレージを比較するポイントをご紹介します。また、中小企業、個人事業主にぴったりのクラウドストレージサービスをおすすめします。
目次
クラウドストレージの特徴
法人・個人のクラウドストレージの上手な活用例
最適なクラウドストレージが見つかる6つの比較ポイント
無料ストレージと有料ストレージ、どちらを選ぶべき?
【法人・個人】「無料版の容量サイズが大きい」クラウドストレージ2選
【法人】「機能性重視」のおすすめクラウドストレージ9選
どのクラウドストレージを選ぼうか迷ったら
クラウドストレージの5つのメリット
クラウドストレージを活用・導入する際に注意すべきポイント
クラウドストレージを比較する際によくある質問
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

クラウドストレージとは?
クラウドストレージ(cloud storage)とは、インターネットを通じてアクセスする保管場所(データセンター)にデータを保存したり、転送・共有したりできるストレージサービスです。「オンラインストレージ」や「ファイルストレージ」と呼ばれることもあります。
クラウドストレージには以下のような特徴があります。
特徴1. いつでも、どこからでもアクセスできる
クラウドストレージはインターネットを通じてデータにアクセスするため、ネット環境さえあればどこからでもアクセスできます。スマートフォンやタブレットからでも利用できるため、出張先や営業先からでもストレージ上のデータをチェック可能です。そのため、コロナ禍での在宅ワークやテレワークの導入に伴い、その利用は増加しました。
日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とITRが国内企業1,022社を対象に2023年1月に実施した「企業IT利活用動向調査2023」によると、「大半はクラウドサービスを使っている」と回答した企業の合計は2022年1月の18.2%から23.8%に上昇しました。「一部クラウドサービスを使っている」と回答した企業を含めると、全体の約9割がなんらかの形でクラウドサービスを利用していることになります。
これらの調査結果からも、いつでもどこからでもアクセスできるクラウドストレージがテレワーク促進に貢献したことが分かります。

出典:日本情報経済社会推進協会「JIPDEC IT-Report2023 Spring」
特徴2. 必要に合わせて容量を調整可能
クラウドストレージは容量を増やしたり、減らしたりすることが可能です。一般的に容量の大きさと料金は比例するため、自社がクラウドにかけられるコストを必要に応じて調整できるのです。
例えば、従業員数の少ない中小企業がクラウドストレージを導入する場合、まず少な目の容量でコストを抑えておいて、業務規模の拡大や従業員数の増加に合わせて、徐々に増やしていくことができます。こうした柔軟な運用がクラウドストレージの特徴の1つです。
特徴3. 保守・点検が不要
クラウドストレージは自社で保守・点検を行う必要がありません。クラウドストレージの提供事業会社に在籍する専門家が保守・点検を行ってくれるため、自社のリソースを節約できます。もちろん、保守・点検が不十分であれば、重大なセキュリティインシデントにつながるため、サービスを選ぶ際には慎重に選択することが重要です。
クラウドストレージの主な機能
一般的にクラウドストレージは以下のような3つの機能を備えています。
機能1. 自動バックアップ
クラウドストレージは定期的に自動バックアップを行う機能を備えています。そのため、システム障害が発生したり、災害などで機器が破損したりしても、中にあるデータは保護されます。
バックアップを行わないとさまざまなリスクにつながります。例えば、トラブルが発生したときにシステムの復旧が行えず、業務取引や顧客との連絡が途絶えてしまう可能性があります。その結果、経済的損失が生じるばかりか、社会的信用を失うことにもなりかねません。さらに、コンプライアンス違反を指摘されたり、損害賠償を請求されたりすることも考えられます。
企業が保有するデータの量と重要性は日に日に高まっているため、クラウドストレージの自動バックアップは非常に心強い機能だといえるでしょう。
機能2. ファイル転送
クラウドストレージを使えば、サイズが大きいファイルを転送することも簡単です。
メールではサイズが大きすぎて送れないし、以前のようにフラッシュメモリを使って社内でやりとりするのはセキュリティ面で不安です。しかし、クラウドストレージなら、ファイルをオンラインストレージにアップロードし、相手にダウンロードURLをメールなどで連絡するだけで大きなデータのやりとりもスムーズに行えます。
ユーザとして登録しておけば、取引先など社外の人もデータのアップロード、ダウンロードを行うことができます。
機能3. ファイル共有
クラウドストレージにはファイル共有機能もあります。
ファイル共有機能を使うことで、オンラインストレージにアップロードされたファイルを複数人で閲覧したり、編集したりできます。チームメンバーすべてがオフィスに集まらなくても、クラウドストレージを使えば、在宅で業務をしている人も外出先でスマホでアクセスしている人も含めて、ストレスなく共同作業が可能です。
もちろん、管理者はファイルの閲覧や編集に関して制限を設けることができるため、部外者が社内や部署内の機密情報にアクセスすることはできません。
以上のような特徴や機能を前提にすると、クラウドストレージとオンプレミスには以下のような違いがあります。
クラウドストレージとオンプレミスの違い
違い1. データの保管場所
クラウドストレージは、インターネットを通じてアクセスする「クラウドサービス事業者のデータセンター」にデータを保管します。それに対して、オンプレミスは自社のサーバ内でデータを管理します。
違い2. 導入期間
クラウドストレージは、クラウドサービス事業者が提供するサービスであるため、データ保管のための環境はすでに構築されています。そのためすぐに導入できます。
それに対して、オンプレミスは自社の環境に最適化したシステムを一から構築しなければならないため、ハードウェアを購入・設定しなければなりません。導入を決定してから、実際にシステムを使えるようになるまで何か月もかかる場合も少なくありません。
違い3. コスト
クラウドストレージには、クラウドサービスを提供する事業者に対して利用する対価を支払います。初期費用はさほどかかりませんが、一般的に毎月、毎年ペースで利用料を払い続けるため、利用期間が長ければ長いほどコストが増大する可能性があります。
それに対して、オンプレミスの場合、前述したように導入する際に機器の購入やシステム設定が必要なため高額なイニシャルコストが発生します。ただ、いったん導入しさえすれば、あとは社内の担当部署の保守・点検のみで十分です。
違い4. 拡張性
クラウドストレージは、サービス提供事業者に対してプランの変更さえすれば、ストレージの容量を増やせます。
それに対して、オンプレミスの場合、新たなファイルサーバを購入し、再度設定しなければならず、拡張する上では手間がかかります。
参考:NTT東日本 「オンプレミスとは?意味やクラウドとの比較までわかりやすく解説」
オンプレミスについて知りたい方はこちら

法人・個人かかわりなく、クラウドストレージはサイズが大きいファイルの転送や共有をするために効果的なツールです。
法人に絞るとすれば、オンプレミスの負荷軽減のためにクラウドストレージを活用することもできます。全社が保有するデータやシステムをすべてオンプレミスだけに依存させると、アクセスが集中してシステムダウンが起きる可能性が高くなります。そうなると、システム復旧まで業務が停止してしまいます。
こうした事態を避けるために日常的にはクラウドストレージを使用し、もしもの場合に備えて重要なデータをオンプレミスに保管するのも1つの方法です。
クラウドストレージのメリットや上手な活用方法については後述します。
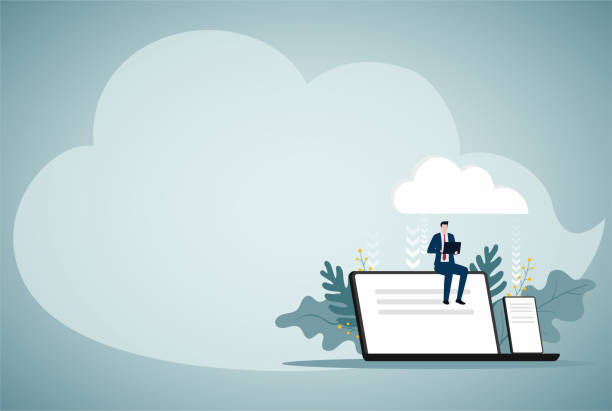
クラウドストレージのニーズが高まるにつれ、どんどん新しいサービスが登場しています。たくさんある中から最適なクラウドストレージを選ぶのは至難の業です。
ここでは、ぴったりのクラウドストレージを見つけるための6つの比較ポイントを紹介します。
1. 必要なデータ量を保存できるか
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
6. ストレスを感じない操作感か
1. 必要なデータ量を保存できるか
最適なクラウドストレージを選ぶ1つ目のポイントは、必要なデータ量を保存できるかという点です。
どのくらいの容量が必要かは個人と法人とでは大きく異なるでしょう。また、企業の中でも保存するデータがテキストベースの資料なのか、画像や動画が中心なのかによって変わってきます。例えば、デザインや図面を扱う企業であれば、必要なデータ容量も必然的に増えると考えられます。
法人向けのサービスには「容量無制限」のクラウドストレージがあります。確かに容量無制限であれば、将来データ量がどれだけ増えても安心と思うかもしれませんが、その分コストがかかります。必要性とコスト面でバランスのとれた選択をするよう心がけましょう。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ2つ目のポイントは、上述したデータ容量と料金プランのコストパフォーマンスです。
クラウドストレージサービスには、無料プランもあります。ただ、容量は5~20GB程度にとどまるため、法人で使用するにはやや足りない印象です。
有料プランを前提にすると、料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスは「1GBあたりいくらか」で測ることができます。
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ3つ目のポイントは、ファイル共有やオンライン共同作業に関してです。
上述したように、ファイル共有やオンライン共同作業はクラウドストレージの基本的な機能です。ただ、クラウドストレージサービスの中にはファイル共有機能のみに特化したものもあります。また、ファイル共有の際、リンクを共有することで閲覧するだけでなく、編集権限も付与できるか、パスワードや保存期間が設定できるかも異なります。自社の用途に合わせて、チェックしておきましょう。
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ4つ目のポイントは、必要な機能やサービスが備わっているかという点です。
各事業者とも差別化をはかるために、さまざまな付加的なサービスを提供しています。例えば、以下のようなものがあります。
・スマホでも利用可能か
・導入後のサポートはあるか
・利用するすべての端末で利用可能か
・期限付き共有リンクの生成ができるか
自社の使用形態に応じて、必要十分なサービスが備わっているかも選ぶポイントの1つだといえるでしょう。
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ5つ目のポイントは、万全なセキュリティ対策がされているかという点です。
セキュリティ対策を考えると、法人で無料プランは選ばない理由が分かります。当然ですが、利用料金が高くなればなるほど、事業者のセキュリティに対する責任は重くなるからです。
クラウドストレージでは、セキュリティ対策は自社担当者ではなく、事業者に大部分を委ねることになります。そのため、前もって事業者のセキュリティ対策について精通しておきましょう。
この点、総務省も2021年9月に「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」を改訂しました(第3版)。利用者の設定ミスや不十分な変更管理に加え、クラウドサービス自体の障害も多数報告されている点が指摘されています。そのため、セキュリティ対策をクラウドサービス事業者に丸投げするのではなく、クラウドサービス利用者も自らの責任範囲において、やるべきことをおこなうことが不可欠、というのが改訂理由だとしています。
参考:「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン (第3版)」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf) を加工して作成
セキュリティ対策について知りたい方はこちら
6. ストレスを感じない操作感か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ6つ目のポイントは、ストレスを感じない操作感かどうかです。
例えば、反応が遅かったり、操作性が普段使っているOSと大きく乖離するようなら、従業員はそのサービスを次第に活用しなくなってしまいます。また、操作を学ぶために特別な研修が必要になれば、普及するまで時間がかかることでしょう。

以上を前提とすると、法人がクラウドストレージを導入する際には有料ストレージを選ぶべきです。なぜなら、無料ストレージの場合、利用している側はセキュリティの脆弱性や容量に関して事業者に責任を問うことはできないからです。
事業規模の小さい企業の場合、ランニングコストを考えると、有料ストレージを導入することに二の足を踏んでしまうかもしれません。その場合、1つの方法は無料のトライアル期間を活用することです。無料期間中にコストパフォーマンスや必要性を検証することをおすすめします。

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
MEGA
|
10GBまで無料
|
・転送マネージャーで大容量のファイルをアップロード
|
・エンドツーエンド暗号
・2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護
・ランサムウェア対策
|
|
Googleドライブ
|
15GBまで無料
|
・オンラインでの共同編集
・ファイルの一括管理
|
・ゼロトラスト機能
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人向けのクラウドストレージは有料版を選ぶことになると思いますが、部署やチーム内で共同作業を行う際に、あるいは個人で無料版を検討することもあるでしょう。
ここでは、10GB以上であることを前提に、無料版で容量サイズの大きいクラウドストレージを2つ紹介します。
1.『MEGA』10GBまで無料
MEGAはニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウドストレージです。10GBまでは無料で利用できます。
セキュリティ面では「エンドツーエンド暗号」を採用しており、第三者が通信内容を傍受できない対策がなされています。また、2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護し、データを安全に守ります。そのセキュリティの高さはサービスを提供しているMEGAさえもアクセスできないほどです。MEGAではファイルはゼロ知識で暗号化され、鍵を保有しているのはユーザだけだからです。
さらに、ランサムウェア対策も万全です。仮にランサムウェア攻撃を受けた場合、ローカルストレージとMEGA間で自動同期が行われている場合でも、感染する前の時点にファイルを戻せます。
MEGAのユーザが扱うファイルは大容量になりがちですが、デスクトップアプリでは強力な転送マネージャーが利用できます。そのため、短時間に大容量ファイルをアップロードすることが可能です。
有料プランである「ビジネス」は、最小3人のユーザで3TBの基本ストレージを利用でき、毎月の利用プランは2,399円(2024年12月11日時点の日本円での見積価格、実際はユーロで請求)です。ユーザ数や容量は必要に応じて変更可能です。
公式HP:MEGA
2.『Googleドライブ』15GBまで無料
Googleドライブは、Googleが提供しているクラウドストレージです。Googleアカウントを作成することで15GBまで無料で利用できます。1日あたり750GBまでなら大容量のファイルもアップロードが可能です。
Googleドライブの特徴は、ドキュメントの編集機能など、オンラインでの共同作業がしやすい点です。また、さまざまなタイプのファイルを一括して管理し、必要なファイルをすぐに見つけることができます。GoogleのAI機能を利用して、ユーザにとって必要なファイルをリアルタイムに予測し、表示できるのです。
また、Googleドライブはセキュリティにおいて「ゼロトラスト機能」を採用。ゼロトラストとは、テレワークの増加やモバイル端末によるアクセスなどにより、企業の内部と外部を隔てる「境界」があいまいになる中、その概念をすべて捨て去り、情報資産にアクセスしようとするものはすべて信用せずに安全性を検証しようとする考え方のことです。
法人が利用を検討する場合には、有料プランの「Google Workspace」がおすすめです。有料プランは「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランが準備されており、料金や容量は以下の通りです。Googleドライブの無料版を個人で使っている方も多いと思いますが、Enterpriseを含めて、幅広い企業ニーズにも対応しています。
|
プラン
|
Business Starter
|
Business Standard
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜300人
|
無制限
|
|
容量
(ユーザ1人あたり)
|
30GB
|
2TB
|
5TB
|
5TB
(追加リクエスト
可能)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Googleドライブ

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
機能
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円~(税込、1年契約の場合)
|
・スマホアプリ
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元
|
・IDパスワード認証
・2要素認証
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
|
|
OneDrive for Business
|
Plan 1の場合 749円〜(税抜、1ユーザあたり)
|
・Microsoft 365と連携
・アクセス権のコントロール
・アクセス有効期限の設定
|
・データを暗号化
・各フォルダを保護し、バックアップ
|
|
Dropbox Business
|
Businessの場合 1,500円〜(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・Dropbox上でファイルを作成、編集
・デスクトップアプリ
・コンテンツアップデートの通知機能
|
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円〜(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
・Box Signで電子サイン
・仮想ホワイトボードツールBox Canvasにより、コラボレーションを支援
|
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・強力なユーザ認証
・7段階のユーザ権限設定
|
|
Fileforce
|
Small Businessの場合 990円〜(1ユーザあたり)
|
・Officeアプリ上で快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
|
・IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限
・キャッシュデータを自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 2,860円(1ユーザあたり)
|
・マルチデバイス対応
・優れたプレビュー機能
・管理者作業を一元管理・自動化
|
・様々な第三者認証を取得
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲などを柔軟に設定可能
|
|
GigaCC ASP
|
STANDARDプランで10IDの場合 12,000円〜
|
・リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・一斉振り分け送信機能
|
・2段階認証機能
・2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
|
|
NotePM
|
プラン8の場合 4,800円〜
|
・高機能エディタと画像編集機能
・全文検索
・チャット連携、API対応
|
・柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)+初期費用 15,000円(税別)
|
・サムネイル画像を自動生成、高速表示
・直感的な操作性
・最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モード
|
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全アクセス、操作等を記録
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここからはいよいよ法人向けの有料プランをご紹介します。
以下に示すように、上述した6つのポイントに加え、利用可能なユーザ数についてまとめてみました。
・容量
・料金
・ファイル共有やオンライン共同作業
・特徴的な機能
・具体的なセキュリティ対策
・操作感
・利用可能なユーザ数
3.『使えるファイル箱』
使えるファイル箱は、使えるねっとが提供する「空気みたい」に自然に使える便利で安心なクラウドストレージサービスです。
使えるファイル箱の特徴は、PCにインストールしてエクスプローラーやFinderから使用できるため、操作性が高く、特別な研修も必要なくスムーズに導入できる点です。また、他のアプリケーションからも直接保存できますし、ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集したり、複数人で同時編集したりもできます。アップロードできるファイルサイズは無制限なので、大容量ファイルの共有も安心です。
特徴的な機能:
・スマホアプリ(Android&iOS)
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元(最大999日/最大999バージョン)
・汎用的なWebDAVプロトコルに対応しているため、さまざまなアプリが利用可能(アドバンス)
セキュリティ:
・IDパスワード認証
・2要素認証設定
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
・国内データセンター(長野)
・GDPRコンプライアンス(EU一般データ保護規則)対応
・サーバ内シークレットキー対応
・履歴ログ管理
・リンクのパスワード保護
・共有リンクの有効期限
・ランサムウェア対策
・ログイン許可IP制限(アドバンス)
・ダウンロード回数制限(アドバンス)
・デバイスデータの遠隔削除(アドバンス)
・特定デバイスからのアクセスブロック可能(アドバンス)
使えるファイル箱は、スタンダードプランでも利用可能なユーザ数が無制限で、容量も1TBから追加可能。拡張性の高さにも注目です。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
利用可能なユーザ数
|
無制限
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
月額料金
(税込)
※1年契約の場合
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
4.『OneDrive for Business』
OneDriveはMicrosoftが提供しているクラウドストレージサービスです。家庭向け、一般法人向け、大企業向けのサービスがありますが、ここでは一般法人向けを紹介します。
OneDriveの最大の特徴は、Microsoft 365のビジネスソフトとシームレスに連携できる点です。そのため、複数ユーザによる共有や編集作業がスムーズです。
特徴的な機能:
・ファイル共有のアクセス権のコントロール
・共有されるファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可能
・共有ファイルのダウンロードを防止
・Android、iOS、Windows用のOneDriveモバイルアプリでどこからでもアクセス
・ファイルのダウンロードをせずにアクセスできるため、デバイスのストレージスペースを節約
・差分同期を選択できる
・Webでのプレビューで320種類以上のファイルを忠実に再現
・最も関連性の高いファイルを検出するためのインテリジェントな検索と検出のツール
・複数ページのスキャン可能
セキュリティ:
・転送中および保管中のデータを暗号化
・「既知のフォルダの移動」を使用することで「デスクトップ」「ピクチャ」「ドキュメント」の各フォルダを保護、バックアップ
|
プラン
|
OneDrive
for Business
(Plan 1)
|
Microsoft 365 Business Basic
|
Microsoft 365 Business Standard
|
|
利用可能なユーザ数
|
ー
|
〜300人
|
|
容量
|
ユーザ1人あたり1TB
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税抜)
※年間サブスクリプション
の場合
|
749円
|
899円
|
1,874円
|
公式HP:OneDrive
5.『Dropbox Business』
Dropbox Businessは、個人向けの無料サービスも展開しているDropboxの法人向けクラウドストレージサービスです。従来のファイルに加えて、クラウドコンテンツやウェブコンテンツのショートカットもすべて同じ場所に保存できるため、情報を整理して効率的にチームで作業を進めることができます。
特徴的な機能:
・Dropboxで直接クラウドコンテンツやMicrosoft Officeファイルなどを作成、編集可能
・スマートなコンテンツ提案機能を備えたデスクトップアプリ
・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたときの通知機能
・作業ファイルの横にある最近のアクティビティ情報で最新情報を把握
・Slack、Zoomなどの使い慣れているツールとリンクすれば、検索したりアプリを切り替えたりする必要なし
・Dropbox Paperでチームメンバー全員で締切とファイルを共有し、リアルタイムで更新しながら作業可能
セキュリティ:
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証設定
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
・管理者がチームの共有権限をきめ細かく管理
・デバイスのリンクを解除
・社員が退職した場合やデバイスを紛失した場合、パソコンとモバイルデバイスの両方からデータとローカルコピーを削除
|
プラン
|
Essentials
|
Business
|
Business Plus
|
|
利用可能なユーザ数
|
1人
|
3人〜
|
|
容量
|
3TB
|
9TB〜
(チーム全体)
|
15TB〜
(チーム全体)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)
※年間払いの場合
|
2,000円
|
1,500円
|
2,400円
|
公式HP:Dropbox
6.『Box』
Boxはカリフォルニアに本社を置く、2005年にアメリカで設立されたクラウドストレージで、日本でも代理店を経由してサービス展開しています。Boxの特徴は、どのプランも容量無制限であり、ユーザも3人以上であれば、事業規模の拡大に合わせて人数に関係なく利用できる自由度の高さでしょう(「Box Starter」を除く)。
特徴的な機能:
・仮想ホワイトボードツールであるBox Canvasにより、コラボレーションを支援
・Box Signが標準機能として提供され、電子サインにより迅速でコスト効率の高いDXを支援
・Box Relayにより、デジタルアセットの承認や予算管理などの反復業務をシンプルでフレキシブルなワークフローとして自動化
セキュリティ:
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・SSO(シングルサインオン)とMFA(多要素認証)をサポートする強力なユーザ認証
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・すべてのファイルが保管時また転送時にAES256ビット暗号化
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
3人〜上限なし
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
※年一括払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
6,600円
|
公式HP:Box
7.『Fileforce』
Fileforceは国内のさまざまな業界・業種の企業に導入されているクラウドストレージサービスです。端末に関係なく、Webブラウザからログインするだけで手軽に利用でき、スマートフォンやタブレット端末、自宅のPCなどさまざまな環境からアクセス可能です。Active Directoryなどに基づく権限管理に対応しているため、既存のファイルサーバの運用をそのまま引き継ぐことができます。
特徴的な機能:
・Officeアプリ上でもクラウドに保管されたデータを意識することなく快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
・Fileforceに保管されるすべてのファイルは自動で保護される
・社内外問わずファイルやフォルダを共有
・変更履歴はすべて保存
・ファイル更新時には自動的に履歴を保存するバージョン管理を適用、ファイル単位で任意の時点に戻せる
セキュリティ:
・社外ユーザはメールアドレスとパスワードによる認証を基本とし、IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限も可能
・キャッシュしたデータはユーザが意識することなく自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
Fileforceの料金プランはユーザ数やストレージ容量に合わせて細かく分かれており、事業規模や会社の成長に合わせて最適なサービスを選択できます。
|
プラン
|
Small Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
10ID
|
無制限
|
|
容量
|
ユーザ
あたり
10GB
|
1TB
|
3TB
|
10TB
|
30TB
|
|
月額料金
(税抜)
※年契約の場合
|
990円
/1ID
|
60,000円
|
108,000円
|
216,000円
|
360,000円
|
公式HP:Fileforce
8.『Box over VPN』
Box over VPNは、BoxをNTTコミュニケーションズが提供する閉域網サービス「Arcstar Universal One」経由で、セキュアなVPN環境下で利用できるサービスです。VPN回線を経由して利用できるため、Boxサービスよりもセキュリティレベルが強化されています。また、ネットワークからBoxまで、NTTコミュニケーションズが24時間365日の一元保守を担当してくれるため、手厚いサポートを受けられます。
特徴的な機能:
・マルチデバイス対応で、PCはもちろんのこと、スマートフォンやタブレットからもBoxを利用可能
・Boxの優れたプレビュー機能により、端末にインストールされていないアプリで作成されたデータも閲覧可能
・NTTコミュニケーションズが提供するBoxではユーザ登録など管理者作業を一元管理・自動化できるオプションを用意
・60日間無料トライアル実施中
セキュリティ:
・さまざまな第三者認証を取得、Boxは米司法省をはじめ、世界各国の政府機関や法人で採用されているため、機密性の高いファイルも安心して保管可能
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲、ダウンロードの可否、パスワードの有無、アクセス有効期限なども柔軟に設定可能
|
プラン
|
Business
|
Business Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
20ID〜
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
|
2,860円
|
4,180円
|
5,500円
|
公式HP:Box over VPN
9.『GigaCC ASP』
GigaCCは、日本ワムネットが提供する純国産の企業間ファイル共有・転送サービスです。テレワークをより便利に行える各種機能を備えており、ユーザにITリテラシーを求めない使いやすさも魅力といえるでしょう。
特徴的な機能:
・Microsoft Entra IDと連携し、リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・受信時にエラーが発生した場合は、スマートダウンロードのレジューム機能により、未受信部分からの再受信が可能
・一斉仕分け送信機能により、複数の宛先へ異なるファイルの自動送信・転送が可能
・「共有ノート」を活用し、アイディアや会議のメモなどを社内外で自由に共有できる
セキュリティ:
・メールによるワンタイムパスワードを利用した2段階認証機能
・スマートフォンの認証アプリを使用した2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
・アクセス元を制限し、なりすましを防ぐIPアドレス制限
・SSL/TLS暗号化通信
・万が一、権限のないユーザがファイルにアクセスしても中身を見ることができないようにするサーバ内暗号化
・誰がいつ、どこからアクセスし、どんなコンテンツを送信したかを記録する履歴ログ管理
導入には初期費用50,000円がかかります。STANDARD、ADVANCED、PREMIUMの3つのプランがあり、提供機能が異なります。基本月額費用は10IDが12,000円~、1000IDは280,000円~で、ADVANCEDプランはさらに25,000円、PREMIUMプランは42,000円が上乗せされます。
公式HP:GigaCC ASP
10.『NotePM』
NotePMは社内で情報共有をするための社内wikiツールです。いままでバラバラに管理されていたマニュアルやノウハウなどの社内ナレッジを一元管理します。例えば、ファイルサーバの検索が弱く、欲しい情報がすぐに見つからなかったり、マニュアルの作成が人によってバラバラで統一されていなかったり、ナレッジが属人化しているなどの悩みを解決します。
特徴的な機能:
・高機能エディタとテンプレートでバラバラなフォーマットを標準化、マニュアル作成に便利な画像編集機能も用意
・Word、Excel、PowerPoint、PDFなどのファイルの中身も全文検索するので、欲しい情報がすぐにみつかる
・チャット連携、API対応
・マルチデバイス対応
・お知らせ通知
・動画共有
・「人気ページのランキング」など、レポート機能
・変更箇所を自動でハイライト表示し、履歴を記録
・3,000以上のアプリとデータ連携が可能
・1,000以上の絵文字に対応
セキュリティ:
・プロジェクト単位、組織単位など、柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
・IPアドレス制限
・閲覧履歴管理
・ログイン連続失敗した場合に自動でアカウントロック
・ログインした端末情報を記録
|
プラン
|
プラン8
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜8人
|
〜15人
|
〜25人
|
〜50人
|
〜100人
|
|
容量
(チーム全体)
|
80GB
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
|
月額料金
(税込)
|
4,800円
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
公式HP:NotePM
11.『IMAGE WORKS』
IMAGE WORKSは富士フイルムイメージングシステムズが提供するクラウドストレージで、画像や動画コンテンツの一元管理・共有に特化したサービスです。検索機能が充実しており、AIを活用したラクラク検索機能も搭載しています。そのため、単にデータを詰め込むだけのオンラインストレージのみでなく、100項目を超えるファイル属性情報(メタ情報)から、業務や用途に合わせ、必要なファイルをすぐに探し出すことが可能です。
特徴的な機能:
・ファイル登録と同時に閲覧用のサムネイル画像を自動生成・高速表示
・直感的な操作性
・1ファイル最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モードも提供
・レジューム機能・整合性確認機能で送受信を支援
・IDを持たないゲストユーザとの送受信も可能
・ダウンロード申請・承認機能により、ファイルダウンロード前に利用者・利用目的等の申請を行う
セキュリティ:
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全てのユーザのアクセス・操作等の利用状況をログとして記録
・SSO(シングルサインオン)
・プロジェクトの利用期限が定められていれば、あらかじめ決めた期間で自動的にユーザやデータを削除
費用は、初期費用15,000円(税別)+月額費用15,000円(税別)のミニマムプランから、今すぐ始められます。
公式HP:IMAGE WORKS

主に法人向けのクラウドストレージサービスを紹介しました。「あまりに多すぎて選べない」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、そんな方のために「中小企業向け」「個人事業主向け」に分けておすすめなクラウドストレージをご紹介します。
中小企業に特におすすめのクラウドストレージ2選
中小企業に特におすすめなクラウドストレージは次の2つです。
■使えるファイル箱
■Fireforce
これらのクラウドストレージに共通していることは、拡張性の高さです。中小企業の場合、スタート時のユーザ数は少なく、保存すべきデータもあまり多くないですが、短期間のうちに業務拡大の可能性が高いといえます。それとともに、クラウドストレージを使用するユーザや必要な容量も増えていくはずです。
また、中小企業の一番の悩みはコストです。クラウドを導入したいと考える一方、少しでもコストを削減したいという中小企業の経営者は少なくありません。その点、上述したサービスはどれもイニシャルコストはかからず、企業の成長に合わせてプランを選べます。ユーザ数が無制限なため、従業員が増えることを心配する必要もありません。
セキュリティ対策も見落とせないポイントです。最近のサイバー攻撃は大企業だけでなく、サプライチェーンを含めて中小企業をターゲットに絞ったものも増えています。そのため、企業規模が小さくてもセキュリティ対策は万全にしておくべきです。セキュリティ面でも、上述のサービスは総合的に高い基準を満たしているといえるでしょう。
個人事業主に特におすすめのクラウドストレージ3選
個人事業主に特におすすめなクラウドストレージは次の3つです。
■Googleドライブ
■OneDrive
■Dropbox Business
この3つのクラウドストレージに共通しているのは、無料もしくは低コストで使えることです。企業であれば保有するデータが機密情報や顧客情報を含むため、無料のサービスを選ばないはずです。しかし、個人事業主の中には機密性の高い情報を保有する方は多くないため、無料であり、かつ汎用性のあるGoogleドライブは十分考えうる選択といえるでしょう。
また、個人事業主の場合、企業のように多くのメンバーと情報のやりとりをすることはないと思われます。主に取引先やクライアントとファイルを共有することになるでしょう。そのため、ファイル共有や転送の際のセキュリティよりも、機能が充実しており、操作性が高いものを選びたいところです。

ここでは、オンプレミスではなく、クラウドストレージを選ぶメリットについて改めてまとめておきます。クラウドストレージには以下のようなメリットがあります。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
以下、1つずつ説明します。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
クラウドストレージを使えば、ファイルやデータを一元管理できます。そのため、ファイルを探す手間を省き、データを転送・共有する工数を減らせて、業務効率が上がります。
オンプレミスでもデータの一元管理は可能ですが、クラウドストレージはインターネット経由でアクセスできるため、出張先やテレワーカーとも情報の共有が容易です。また、オフィスと工場など拠点が複数に分かれている場合でもクラウドストレージなら簡単にデータの一元管理ができます。
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
クラウドストレージを使えば、ファイル共有や共同編集も簡単です。どのサービスを選ぶかにもよりますが、容量の大きなデータも相手を選ばずに送ることができます。アップロードして、リンクを生成、送付するだけで完了です。
また、OneDriveやGoogleドライブだけでなく、多くのクラウドストレージサービスはさまざまなアプリケーションと連携しているため、オンラインで共同作業や編集が可能です。
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
クラウドストレージサービスを使うことで、オフィスだけでなくどこの場所からでもファイルにアクセスできます。また、アクセスする時間帯も選びません。
多くの企業でテレワークやワーケーションをはじめとした「時間や場所を選ばない働き方」が導入されていますが、そうした新しい働き方とも親和性があるのがクラウドストレージなのです。
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
クラウドストレージを使えば、社内にファイルサーバを設置する必要がないため、運用管理業務は不要です。
オンプレミスの場合、サーバにかかる負担を監視したり、災害・停電などで起きるトラブルに対処するために運用管理者が必要になります。外注の場合は、サーバ構築費の10~15%が保守運用費用として月額でかかるといわれています。
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
クラウドストレージの場合、データは社内のサーバではなく、災害のリスクが低いデータセンターに保存することになります。
災害大国である日本はどこであっても地震や台風、水害のリスクがあります。システムが破壊され、データが失われれば、企業は業務を停止せざるを得ず、膨大な損害を被ることになります。企業のBCP(事業継続計画)対策の一環としても、クラウドストレージ導入は有効です。
BCP対策について知りたい方はこちら

さまざまな要素を考慮し、最終的にどのクラウドストレージを選ぶにしても、活用・導入にあたって注意したい以下のポイントがあります。
1. インターネット環境の整備
2. セキュリティ対策
3. 運用体制の整備
4. 課金要素
1つずつ説明します。
インターネット環境の整備
サービス自体がどれほど優れていても、インターネット環境が整備されていないと、持っているポテンシャルを十分引き出すことはできません。
クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスのため、回線速度によってパフォーマンスが大きく左右されます。ネットワークの混雑によって、クラウドストレージの機能が低下しないように大容量の回線を準備しましょう。
セキュリティ対策
クラウドストレージを活用する際にはセキュリティ対策に注意を払うべきことは何度も強調しました。クラウドストレージを導入すれば、確かに自社での保守点検は基本的に不要になりますが、セキュリティ対策をクラウドストレージサービス提供事業者に丸投げしてしまって良いわけではありません。
いくらクラウドストレージ側にしっかりとしたセキュリティ対策が施されていても、利用者側でそれを使いこなせていなければ意味がありません。例えば、多くのクラウドストレージはユーザのアクセス権限を細かく設定できるようになっていますが、この設定のミスがセキュリティインシデントにつながるケースも増えています。
また、利用者側の端末のOSやアプリの脆弱性を放置すれば、サイバー攻撃者の格好のターゲットになります。情報漏えいなどを防ぐためには、常に最新のOSやアプリケーションにアップデートしておくことが必要です。さらに、クラウドストレージも万能でないことを認め、災害やサイバー攻撃によるデータ喪失に備えて、バックアップ先を複数用意するなどの対策も求められます。
脆弱性について知りたい方はこちら
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
運用体制の整備
クラウドストレージを導入する際にも運用体制を整備することを忘れないようにしましょう。言い換えると、クラウドの運用を「仕組み化」「システム化」するということです。
「誰が」「何を」「いつ」するのかを決めずに責任の所在をあいまいにし、何となく人的な対応でやりくりしていると、効率化、コスト削減の面でも無駄が生まれます。それだけでなく、やるべき工程に「抜け」が生じて、それがセキュリティインシデントにつながることがあります。経営者主導でクラウドストレージの運用体制を盤石にしましょう。
参考:株式会社アールワークス 「システム運用方針のまとめ方と、運用体制構築に必要なこと」
課金要素
クラウドストレージ導入にあたっては、課金体系をしっかりと把握しておく必要があります。
クラウドストレージサービスの中には、どの程度料金が発生するか分かりづらいものもあります。また、不要になったサービスを利用していないのに停止せずに放置したり、実装したアプリケーションに不備があり、無駄な処理が発生したりすることもあります。
毎月の請求内容にはきちんと目を通し、不明な点はサービス提供事業者に確認するなどして、「なんとなく」料金を支払い続けることがないようにしましょう。そうでないと、イニシャルコストを抑えられるクラウドストレージの強みが失われてしまいます。

ここでは、クラウドストレージを比較する際によくある質問を3つ取り上げます。
Q1:クラウドストレージは社外の人でも使えますか?
クラウドストレージが利用できるか否かは、そのサービスのIDを保有しているかどうかです。そのため、例え社外の人であっても、IDがあれば利用可能です。もっとも管理者によりどの程度までアクセスできるか、権限が制限されることはあります。
Q2:容量無制限のサービスを選べば安心ですか?
「容量無制限」という響きにはたしかに魅力があります。しかし、前述したように容量無制限のサービスを選ぶべきかは企業の業務規模や従業員数によります。現状で使う必要がないのに、やみくもに容量無制限を選ぶと逆にコスト面で損をする可能性もあります。
Q3:クラウドストレージにはデメリットはないのですか?
もちろんあります。
クラウドストレージがあらゆる面でオンプレミスに優れているわけではありません。例えば、クラウドストレージはサービスが定型化、パッケージ化されているため、オンプレミスのように自由なカスタイマイズはできません。
大切なのは、自社がクラウドストレージを導入する目的を見極めることです。
.png)
ここでは、中小企業におすすめする「使えるファイル箱」についてさらに詳しく説明します。
使えるファイル箱の3つの特長
使えるファイル箱にはさまざまな魅力がありますが、ここでは3つの特長を取り上げます。
1. ユーザ数無制限
100人でも、1,000人でも料金は一律です。フォルダのアクセス制限が設定できるため、ユーザIDの一部を外部に渡して、大容量データのやりとりもできます。ちなみに、100人で使えば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
2. 普段のパソコンと同じように操作できる
使えるファイル箱は特別なインターフェースを必要とせずに、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有ファイルを操作できます。そのため、特別な研修は必要なく、普段のパソコンと同じような感覚でファイル共有が可能です。
3. 高機能なのに低価格、無料トライアルもある
使えるファイル箱はクラウドストレージサービスを利用したくてもコスト面で限界がある中小企業に使っていただきたいと思っています。そのため、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。
また、スタンダードプラン、アドバンスプランいずれも30日間の無料トライアルがあるため、じっくり使い勝手を試してから決めることができます。
中小企業に最適な機能と料金形態
中小企業にとってコスパは重要な要素ですが、見逃すべきではないポイントはセキュリティです。使えるファイル箱なら、2要素認証やAES256ビット暗号化、ISO認証取得の長野県のデータセンターなど、貴重な情報資産を守るための対策もばっちりです。
さらに、使えるファイル箱は電子帳簿保存法上の区分のうち、電子取引にも対応しているため、書類の保管場所も節約でき、業務の効率化を図れます。
中小企業に最適な機能を備えた使えるファイル箱の料金体系は以下の通りです。
|
プラン
|
容量
|
1ヵ月契約
|
1年契約
|
|
スタンダード
|
1TB
|
25,080円(税込)/月
|
21,230(税込)/月
|
|
アドバンス
|
3TB
|
75,680円(税込)/月
|
60,500(税込)/月
|
おすすめは1年契約のプランで、容量1TBの場合は月単価21,230円(税込)。より高度な機能が搭載されたアドバンスプランではセキュリティを強化し、汎用性が増すWebDAV連携が可能です。容量3TBのアドバンスプランは60,500円(税込)!
最短で即日ご利用可能!
使えるファイル箱を試してみたいと思われたら、是非お気軽にご連絡ください。
即日または翌営業日に対応させていただき、お見積りいたします。ご希望に合わせてオンラインでのご案内や無料トライアル、勉強会を実施させていただき、本契約となります。最短で即日のご利用開始も可能です。
.jpg)
(1)無料クラウドストレージの容量は?
A:無料クラウドストレージの代表はGoogleドライブですが、ストレージ容量は15GBです。ほかのサービスは2~10GBのものが多いようです。
(2)ストレージ容量に余裕がなくなるとどうなるの?
A:ストレージはデータの保管庫のことで、クラウドに限らず、パソコンやスマホなどの端末でも容量不足の問題は付きものです。
クラウドストレージで容量が足りなくなると、バックアップがとれなくなったり、デバイス間のデータの同期ができなくなったりするなどの障害が生まれる可能性があります。個人で使用する場合であっても、無料のクラウドストレージでは容量不足の問題にぶつかると、有料版を購入することになります。
(3)自社サーバのデメリットは?
A:自社サーバを利用するデメリットには以下の点があります。
1. 運用管理の手間
2. 災害対策が容易でない
3. リモートワークに対応するためにはVPN環境を整えなければならない
4. 容量の拡張にコストがかかる
これらのデメリットもクラウドストレージなら解決可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
テレワークが多くの企業で導入された今、クラウドストレージを活用したデータ共有は常識になってきました。もっとも、中小企業の経営者や担当者の中には、クラウドストレージの導入を検討しつつも、さまざまな理由でなかなか踏み切れない方もいるかもしれません。
この記事では、クラウドストレージとはそもそも何かを理解し、メリットと注意点を詳しく説明します。また、数多くあるクラウドストレージサービスの中から自社に最適なサービスを選ぶポイントについても解説します。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
クラウドストレージとは?
クラウドストレージのメリット7つ
クラウドストレージを利用する際の注意点4つ
クラウドストレージの選定ポイント3つ
おすすめクラウドストレージサービス5選
使いやすく低コストの「使えるファイル箱」
FAQ

最初に、クラウドストレージの概要、ファイルサーバとの違いについて解説します。
クラウドストレージはネット上のファイルの保存場所
クラウドストレージとは、インターネット上に用意されているファイルやデータの保存場所(領域)です。一般的には、サービスの運営事業者が提供するストレージサービスを、有料または無料で利用します。
オンラインストレージとは何かを知りたい方はこちら
クラウドストレージとファイルサーバの違い
クラウドストレージとファイルサーバの大きな違いは、ファイルの格納・共有場所が社内かインターネット上かという点です。
従来、多くの企業や組織がファイルサーバを用いて、データを共有していました。社内ネットワークによってつながったユーザはファイルサーバにファイルを格納したり、そのデータを参照したり、編集することが可能です。
それに対して、クラウドストレージはインターネットを経由してファイルにアクセスし、閲覧、編集、共有するサービスです。企業はクラウドストレージを提供している事業者と契約すれば、アカウントIDとパスワードによって、サービスを利用することができます。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
ファイルサーバのクラウド比較を見たい方はこちら
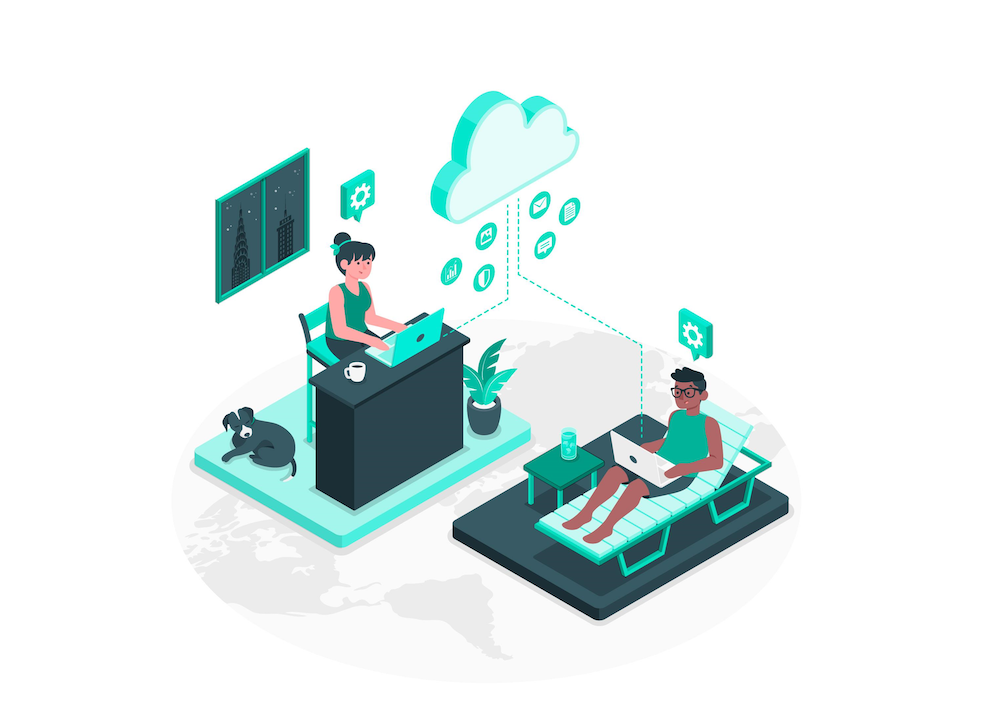
クラウドストレージのメリットを紹介します。以下の7つについて、1つずつ説明しましょう。
1. 場所を問わずどこからもアクセスできる
2. クラウド上でファイル共有、編集できる
3. 初期投資や運用コストが抑えられる
4. 常に最新の機能を利用できる
5. ファイルが自動的にバックアップされる
6. 災害時に備えられる
7. ストレージの容量問題を解消できる
1. 場所を問わずどこからでもアクセスできる
ファイルサーバは社内のネットワークで構築されているため、基本的に社外からアクセスすることを前提にしていません。テレワークの導入などにより、自宅など社外からアクセスする必要性も高まっており、VPNや仮想デスクトップが利用されています。ただ、いずれもセキュリティ面での不安を抱えていることは否定できません。
それに対して、クラウドストレージはインターネット経由でファイルを共有します。つまり、インターネット環境さえあれば、自宅であってもオフィスであっても、国内外関係なく、クラウドストレージに格納されているファイルにアクセスできます。
公益財団法人日本生産性本部によると、2024年1月時点のテレワーク実施率は14.8%で、2020年5月以降で最も低くなりました。それでも、育児や介護と両立でき、通勤などのストレスフルな行動をカットできるテレワークは、すでに一部の従業員にとっては新しい働き方として定着しています。こうした従業員のニーズを満たすために企業は情報共有のためのインフラを整える必要があります。
加えて、クラウドストレージなら、取引先を含め社外の人ともデータ共有が簡単にできます。クラウドストレージを使わなければ、ファイルをメールに添付して送付することになりますが、手間がかかります。また、添付できるファイルの大きさには制限があるでしょう。クラウドストレージを使うことで、少ない工数でファイルの共有ができるため、作業の効率化が図れます。
テレワーク導入の要となる「クラウド化」について知りたい方はこちら
2. クラウド上でファイル共有、編集できる
クラウドストレージを使えば、ファイルをクラウド上で共有できるだけでなく、編集も可能です。
現在、ビジネスパーソンが扱うデータの量、ファイルの数は膨大です。そのため、一括管理しなければ、どのファイルがどこにあるのか、分からなくなってしまいます。また、ファイルをやりとりしながら編集・更新しているうちにどれが最新なのか見分けが付かなくなることもよくあることです。例えば、ファイルをメールに添付して別のユーザに送り編集した場合、そのたびにファイル名を変えるなどの工夫が必要です。
この点、クラウドストレージであれば、クラウド上で編集・更新作業が可能です。さらにメールに添付するなどして共有する作業が不要になるため、工数を減らせます。それにより、生産性向上が図れますし、ミスも減らすことができるでしょう。
3. 初期投資や運用コストが抑えられる
クラウドストレージなら、ファイルサーバよりも初期投資を抑えることができます。
一般的にファイルサーバを構築するには、ハードウェアとソフトウェアの両方に対する投資が必要です。ハードウェアとしてサーバの購入、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどの端末に加え、ソフトウェアをインストールし、さらに各種設定、セキュリティ対策を行うことになります。
価格はスペックによって大きく異なりますが、サーバは法人使用を前提にすると、エントリーモデルで約10万円程度といわれています。ただ、ハイスペックなものを求めると20~30万円程度になりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えるものが必要になるでしょう。また、20~30人前後のオフィスの場合、周辺機器への投資も全部で10万~30万円程度になることが予想されます。
ハードを購入したら、OSやソフトウェア、Windowsの共有サービスなどをインストールしなければなりません。この作業は一般的にシステム開発会社に委託することになります。各会社の料金体系によって予算は大きく変わりますが、メールサーバ、Webサーバの構築の場合は5~10万円前後は見込んでおく必要があります。さらにサーバに端末を接続するためのネットワークの設計・構築にも費用がかかり、中小企業のオフィスであれば10~20万円前後かかります。
クラウドストレージであれば、ハードウェアの購入、ソフトウェアのインストール、ネットワークの構築の費用はかかりません。クラウドストレージサービスを提供している事業者に連絡し、契約すればすぐに使うことができます。初期投資が必要な事業者もありますが、その多くが無料です。
また、ファイルサーバの場合は多額の費用をかけてシステムを構築した後も、さらに定期的な運用保守が必要です。外部に委託する場合、月額の運用費はサーバの構築費用の10~15%が相場といわれています。例えば、サーバの構築に50万円かかったとしたら、月額5万~7万5,000円かかることになります。もちろん、自社で運用保守を行うことは可能ですが、24時間体制の監視ですし、システム障害やサイバー攻撃など突然のトラブルに迅速に対応するには相当の負荷がかかるでしょう。
この点、クラウドストレージであれば、保守運用を含めてサービス提供事業者が行ってくれます。一般的に月額の使用料に保守運用費用も含んでいるため、ランニングコストが過大に膨らむこともありません。
4. 常に最新の機能を利用できる
自社にファイルサーバを設置する場合、最新の機能を利用したければソフトウェアのアップデートが必要になります。もし、システムの構築、保守・運用を外部に委託している場合は、別途追加費用を支払う必要があるでしょう。
この点、クラウドストレージであれば、アップデートは自動的に行われます。常に最新の機能を利用できるのも魅力の1つです。
アップデートが重要なのは、最新の機能によって業務効率化が図れるだけではありません。ソフトウェアを常に最新の状態に保つのは、サイバー攻撃から企業の機密情報を守るためにも欠かせないポイントです。
一般的にソフトウェアは、リリースされた時点から時間の経過とともに新たな脆弱性が発見されます。そのため、システムの保守管理担当者は、常にソフトウェアの開発元やシステム機器メーカーから提供される更新プログラムをチェックしておかなければなりません。可能な限りスピーディーに更新プログラムを適用しなければ、システムの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の被害を受けかねません。
特にサーバは企業内の基幹業務と関連しているため、簡単に止められないなどの理由でソフトウェアの更新が先延ばしにされがちです。先延ばしが続けば続くほど、システムのセキュリティリスクが高まります。
サイバー攻撃はますます巧妙かつ複雑になっています。例えば、ソフトウェアの脆弱性が発見されてから、修正プログラムが配布されるまでの期間を狙って行われる「ゼロデイ攻撃」と呼ばれる手法があります。企業のシステム管理担当者がどれだけ更新情報に注目していても、対策を講じるまでには必ず一定の空白期間が生じ、無防備な状態になってしまいます。
その点、クラウドストレージであれば、サービス提供事業者でその対策をすべて講じてくれます。もちろん、サイバー攻撃を完全防備できる訳ではありませんが、ファイルサーバと比べて格段に安全な環境を作り出すことができるといえるでしょう。
参考:総務省『国民のためのサイバーセキュリティサイト』
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_01.html)を加工して作成
5. ファイルが自動的にバックアップされる
ファイルサーバに格納されているデータを保護するために欠かせないのがバックアップです。オフィスに設置されたサーバはいつどのようにしてサイバー攻撃を受けたり、物理的に壊れたりするか分からないからです。
また、ファイルサーバの場合、定期的にバックアップしていてもバックアップ先が同じネットワーク内であれば、ランサムウェアの感染時に一緒に暗号化されるリスクが高いです。
この点、クラウドストレージの場合、一般的に自動でバックアップされるシステムが構築されているため、その手間が省けます。また、バックアップデータを社内ネットワークとは物理的に異なるデータセンターに保存します。そのため、仮に社内データがランサムウェアの攻撃を受けても、バックアップデータまでが被害を受けるリスクを下げられるのです。
6. 災害時に備えられる
災害大国である日本においては、どの企業も保有する機密データを守り、万が一の場合に事業を継続できるよう備えておくことが大切です。いわゆる「BCP(事業継続計画)対策」を講じる上でも、クラウドストレージにはメリットが大きいといえるでしょう。
一般的にファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが災害の被害に遭えばデータも同時に失われます。しかし、クラウドストレージの場合、データセンターは地震や火災、停電にも強い堅牢な設計であり、自社のサーバでデータを保存するよりも安全です。
もっとも、クラウドストレージでバックアップをとっていれば万全な訳ではありません。バックアップに関してはいわゆる「3-2-1ルール」が提唱されます。クラウドストレージのデータセンターとは言え、大規模な停電などに見舞われればデータにアクセスできなくなる可能性があるため、クラウドストレージとは別に他の媒体でのバックアップも必要でしょう。
BCP対策について知りたい方はこちら
7. ストレージの容量問題を解消できる
年々企業の保有するデータは増大しています。どの業種でもDXが推進され、ビッグデータの活用が経営課題として強調されているからです。
そのため、ファイルサーバだけでは容量オーバーになってしまう可能性もあります。もし、ファイルサーバのストレージ容量を増やしたければ、新しいハードウェアの購入や設定が必要ですが、追加コストがかかってしまいます。
この点、クラウドストレージであれば、容量の追加はとても簡単です。サービスの提供事業者にプラン変更を申し入れれば、必要に合わせて無制限に容量を増やすことができます。特にスタートアップ企業などは最初から多くのストレージ容量を必要とするわけではないかもしれません。しかし、事業規模の拡大に応じて、必要十分な容量を常に確保できるのです。

ここでは、クラウドストレージを利用する際の注意点について解説します。以下の4つの点について1つずつ説明します。
1. オフライン時は利用できない
2. セキュリティ対策が求められる
3. カスタマイズに適さない
4. ユーザ数に応じた費用がかかる
1. オフライン時は利用できない
クラウドストレージは、インターネットを経由して格納されているデータにアクセスする仕組みです。そのため、使用はオンラインであることが大前提です。
オンラインであれば、一括管理されたクラウドストレージ上の作業はスムーズに行えますが、一旦オフラインになってしまうと、すべてのデータにアクセスできなくなり、業務に支障が出てしまいます。
また、完全にオフラインでなくても、場所によってはインターネット環境が良好でないことがあります。例えば、ワーケーションなどで郊外に出かけた場合、インターネット回線の弱い場所だと仕事のパフォーマンスに影響が出るでしょう。
せっかく制度としてワーケーションやテレワークを導入していても、情報共有のためのクラウドストレージがどの程度活用されるかは、インターネット回線にも依存していることを覚えておきましょう。
2. セキュリティ対策が求められる
サイバー攻撃に対処するための修正プログラムなども含めて、クラウドストレージなら自動的にアップデートされると上述しました。さまざまなセキュリティ対策をサービス提供事業者が行ってくれることは確かです。しかし、たとえそうであっても自社で最低限のセキュリティ対策は行っておかなければいけません。
まずセキュリティ対策において非常に重要なのは、信頼できるサービスを選ぶことです(選ぶためのポイントについては後述)。また、クラウドストレージ提供事業者がどれだけ高いセキュリティ対策を行っていても、社内での運用が徹底されていないとリスクは高まります。
例えば、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関してルールを策定し、それをきちんと遵守するための周知徹底が社内でも求められるでしょう。
クラウドストレージのセキュリティ対策について知りたい方はこちら
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
3. カスタマイズに適さない
上述したようにファイルサーバはハードウェアの購入から、ソフトウェアのインストール、システムの構築まですべて自社のニーズに合わせて好きなように行えます。その点で、カスタマイズ性が非常に高いといえるでしょう。
この点、クラウドストレージはそもそも自社に最適化された形でサービスが提供される訳ではありません。事業規模に合わせてストレージの容量や、セキュリティレベルは選択できるものの、細かな設定やカスタマイズを行える点ではファイルサーバに及びません。
4. ユーザ数に応じた費用がかかる
ファイルサーバはユーザがどれだけ増えても、それに伴って費用が増大することはありません。それに対して、クラウドストレージはユーザ数に応じて費用がかかります。つまり、事業規模に合わせてユーザが増えれば増えるほどコストが増大するということです。
もっとも、クラウドストレージサービスの中には、ユーザ数無制限のサービスもあります。ユーザ数が増えることが確実に見込まれる場合は検討してみるのも良いかもしれません。
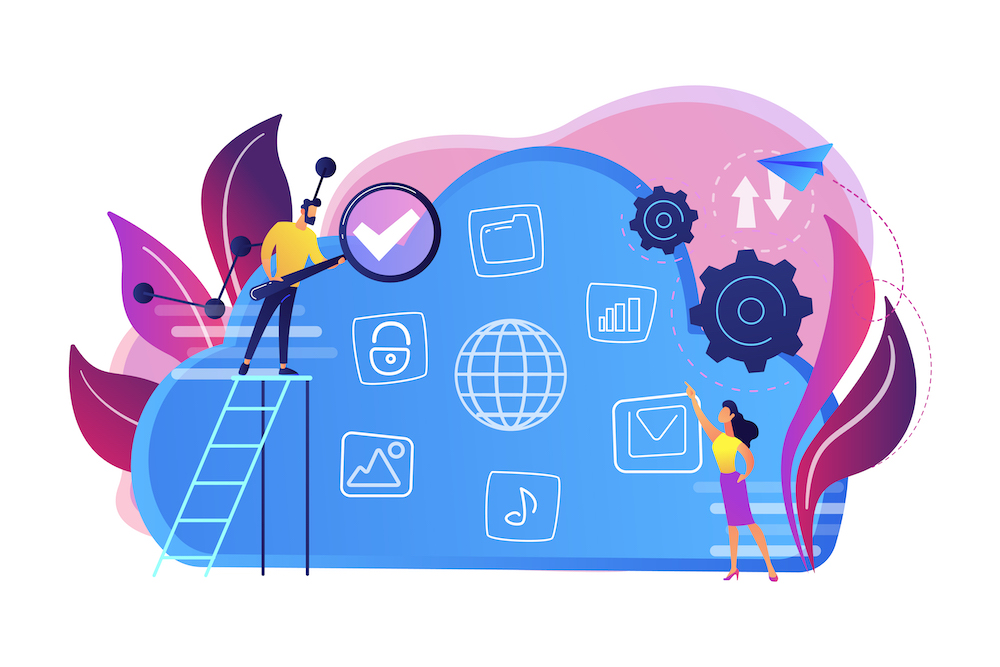
クラウドストレージのメリットと注意点を踏まえた上で、選定ポイントについて解説いたします。以下、3つについて説明します。
1. 必要な機能の充実度、費用を確認する
2. サポート体制の充実度を確認する
3. セキュリティ対策の内容を確認する
1. 必要な機能の充実度、費用を確認する
機能に関しては、対応している端末の種類に注目しましょう。いつでもどこでもアクセスして、情報を編集できる点がクラウドストレージのメリットの1つであるため、スマートフォンやタブレットにも対応しているかチェックしておきたいところです。
費用面に関しては容量とユーザ数を確認しておきましょう。容量無制限のプランも多いですが、自社の事業規模からどのくらいのストレージが必要なのか、費用と相談しながら検討すべきです。事業規模に合わせてより多くのストレージが必要となる可能性が高いようなら、容量を増やせるプランを選びましょう。
また、価格が低めに設定されている場合、必須機能がオプションになっており追加費用が求められることもあるため、料金体系は細かなところまでチェックする必要があります。
2. サポート体制の充実度を確認する
クラウドストレージは、運用や保守をすべてサービス提供事業者に委ねることになります。そのため、サポート体制の充実度は非常に重要なポイントです。エラーやトラブルが発生したときに、自分のことのように丁寧にスピーディーに対応してくれるかを見極めたいところです。
多くのクラウドストレージサービスには無料のトライアルがあるため、その期間にサポート体制について確認するのも1つの方法でしょう。
3. セキュリティ対策の内容を確認する
クラウドストレージのセキュリティ対策は多岐に渡ります。チェックしたいポイントとしては、総務省が挙げている以下の項目が参考になります。
・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策(災害対策や侵入対策など)
・データのバックアップ
・ハードウェア機器の障害対策
・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策
・不正アクセスの防止
・アクセスログの管理
・通信の暗号化の有無
出典:総務省 『国民のための情報セキュリティサイト』
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/admin/15.html)
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
機能
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円(税込、1年契約の場合)
※年契約の場合、初年度は全額返金保証
|
・優れたインターフェースと操作性
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
|
|
Dropbox Business
|
Standardの場合 1,500円(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・モバイル端末からアクセス可能
・Dropbox上でファイルを作成、編集
・更新時の通知機能
|
・パスワード保護、期限付きリンク、ダウンロード権限
・30日間データを復元可能
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年払いの場合)
|
・1,500以上のアプリ統合
・Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフロー自動化
|
・アクセス権限の管理
・ゼロトラストセキュリティ機能
・データ漏えい対策とサイバー脅威の検知
|
|
Google Workspace
|
Business Starterの場合 680円(1ユーザあたり、1年契約の場合)
|
・Googleアプリと連携
・クラウド上で直接編集
|
・2段階認証プロセス
・エンドポイント管理
・高度な保護機能プログラム
|
|
OneDrive for Business(Plan 1)
|
630円(税抜、1ユーザあたり、年間サブスクリプション)
|
・モバイル専用アプリあり
・差分同期
・20種類以上のファイルをウェブプレビュー
|
・受信者に対するアクセス制御指定
・共有リンクのカスタムパスワード
・アクセス有効期限の設定
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
以上のポイントに沿って、おすすめのクラウドストレージサービスを5つ紹介します。
1. 使えるファイル箱
使えるファイル箱の特徴はユーザ数が無制限で利用できる点です。そのため、最初はスモールスタートから始めて、事業拡大とともにユーザ数が増えていっても費用はまったく変わりません。
機能面は以下のように充実しています。
・優れたインターフェースで操作性に優れている
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
サポート体制は電話、サポートメール、チャットいずれも対応。サーバのトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間対応しています。
セキュリティも以下のように万全です。
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランを準備。どちらも1年契約であれば、初年度全額返金保証が付帯します(業界初)。また30日間の無料トライアルも実施中です。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
2. Dropbox Business
Dropbox(ドロップボックス)はクラウドストレージの先駆け的な存在です。個人向けサービスは無料で利用できますが、Dropbox Businessは法人向けの有料サービスです。Dropbox Businessも利用可能なユーザ数に制限がないため、事業規模の拡大に合わせて課金なしで情報共有を行えます。
機能面は以下のような特徴があります。
・パソコン、スマートフォン、タブレットいずれからもアクセス可能
・Dropbox上で直接コンテンツやファイルを作成、編集できる
・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたら通知を受け取れるため、最新情報を把握
・SlackやZoomなどとリンクすることが可能、アプリを切り替える必要なし
セキュリティ面は以下のような特徴があります。
・パスワード保護、期限付きリンク、ダウンロード権限などの機能を使用し、適切なユーザに適切なアクセス権を付与できる
・いざという時も30日間はデータを復元可能
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
・多要素認証設定
サポート体制も充実しており、24時間年中無休でヘルプセンター、コミュニティ、チャットボットが対応してくれます。
法人向けのプランは「Standard」「Advanced」「Enterprise」の3つのプランから選択できます。チーム全体の利用可能容量が異なり、Standardは5TB、Advancedは15TB、Enterpriseは必要なだけのスペースを一度に購入できます。
|
プラン
|
Standard
|
Advanced
|
Enterprise
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※年間払いの場合
|
1,500円
※ユーザは3人〜
|
2,400円
※ユーザは3人〜
|
応相談
|
|
チーム全体の容量
|
5TB
|
15TB〜
|
必要に応じて
|
公式HP:Dropbox Business
3. Box
Box(ボックス)は2005年の創業以来、人々がどこからでも簡単に情報にアクセスし、コラボレーションができる環境づくりを目指してきました。
10GBの無料オンラインストレージはすぐに利用できますが、法人向けの有料プランは「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」の4つがあります。法人向けプランの最小ユーザ数は3名、利用できるストレージはどれも容量無制限です。
各プランによってファイルのアップロード容量上限が異なります。Businessは5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GB、Enterprise Plusは150GBです。
以下のような機能面の特徴があります。
・Microsoft Office、Salesforce、Google Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合
・Box Sign:Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフロー自動化
・データ損失防止
セキュリティ面は以下の通りです。
・アクセス権限の管理
・ゼロトラストセキュリティ機能
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
応相談
|
|
アップロード
容量上限
|
5GB
|
15GB
|
50GB
|
150GB
|
公式HP:Box
4. Google Workspace
多くの個人ユーザに利用されているGoogle Drive(グーグルドライブ)の法人向けサービスが「Google Workspace」です。Google Workspaceの最大の特徴は、Googleの他のビジネスソフトやアプリケーションと連携できる点です。
また、クラウド上でPDFやMPEG4などの100種類以上のファイル形式を開けるため、直接編集・作業が可能、工数を減らし、作業効率をアップできます。さらにAI機能を利用して、検索の際、ユーザにとって必要なファイルを予測、表示してくれます。
セキュリティ面に関しては、厳格なプライバシー基準とセキュリティ基準に準拠するように設計されており、複数の独立した第三者機関による監査を受けています。その中には、ISO/IEC27001や、FedRAMPなどがあります。
Google Workspaceには、4つのプランが準備されています。プランごとに使用可能なストレージ容量が異なります。「Business Starter」がユーザあたり30GB、「Business Standard」はユーザあたり2TB、「Business Plus」はユーザあたり5TBまで、「Enterprise」はユーザあたり5TBに加えて、追加リクエストが可能です。
|
プラン
|
Business
Starter
|
Business
Standard
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
応相談
|
|
ストレージ容量
(1ユーザあたり)
|
30GB
|
2TB
|
5TB
|
必要に応じて
|
公式HP:Google Workspace
5. OneDrive for Business
OneDrive for Business(ワンドライブフォービジネス)は、法人向けに設計されたOneDriveクラウドストレージサービスです。最大の強みは、Microsoft 365やTeamsと連携してシームレスに共同作業が行える点です。
機能面では以下のような特徴があります。
・モバイル専用のOneDriveアプリが用意されているため、外出先でもファイルの作成、表示、編集、共有が可能
・ファイル全体ではなく、変更部分のみが同期される差分同期を採用
・Webでのプレビューで320種類以上のさまざまなファイルを忠実に再現
・クラウド上のファイルにアクセスする際にダウンロードは不要、デバイスのストレージを節約
・関連性の高いファイルを検索するためのインテリジェントなツール
セキュリティ面では以下のような特徴があります。
・受信者に対してファイルやフォルダへのアクセス制御を指定できる
・カスタムパスワードを設定して共有リンクを保護
・共有ファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可
一般法人向けのOneDrive for Businessには、ファイル共有とストレージの使用を目的とした「Plan 1」があります。さらにMicrosoft 365も含んだサービスには「Microsoft 365 Business Basic」「Mirosoft 365 Business Standard」などがあります。
|
プラン
|
OneDrive
for Business
(Plan 1)
|
Microsoft 365
Business Basic
|
Microsoft 365
Business Standard
|
|
月額料金
(1ユーザ、税抜)
※年間サブスクリプション
|
630円
|
750円
|
1,560円
|
|
合計ストレージ
|
ユーザ1人あたり1TB
|
公式HP:OneDrive for Business

「使えるファイル箱」は使いやすく、低コストのクラウドストレージサービスです。ユーザ数無制限なので、従業員数に関わりなく料金は一律です。また、専用のインターフェースを必要とせず、導入したその日から使える操作性の高さも魅力といえるでしょう。
中小企業が安心して使い続けられるように、容量課金制の低価格でサービスを提供。データ容量は企業規模に応じて、無制限に追加できます(オプション追加容量1TB 税込8,580円)。
価格だけでなく、セキュリティも充実しています。2要素認証設定、暗号化、ログ記録、ISO認証データセンターなどで大切なデータを情報漏えいからばっちり守ります。
容量1TB、ユーザ数無制限で月単価21,230円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価60,500円(税込、1年契約)です。例えば、スタンダードプランをお選びいただいた場合、従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
.jpg)
(1)クラウドストレージの無料と有料プランの違いは?
クラウドストレージの無料と有料プランの主な違いは容量の大きさ、セキュリティ面の充実度です。無料プランの場合、ストレージ容量は5GB~10GBが主流で、個人ユーザを対象にしています。また、ビジネスでの使用を前提としていない無料プランでは、データのやりとりやセキュアなコミュニケーションの点で不十分であると言わざるを得ません。
(2)クラウド上に保存とはどういうこと?
クラウド上に保存するとは、インターネットを経由して、クラウドストレージサービスを提供する事業者のデータセンターにデータが格納されている状態を指します。そのため、インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末を使って、データを閲覧、編集、共有することが可能なのです。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
やりとりするデータ量が増大し、機密性の確保が重要になっている昨今、中小企業にとってデータの管理方法は喫緊の課題です。
ここでは、多くの企業が導入しているクラウドストレージについて徹底解説します。クラウドストレージの基本や、中小企業にとってクラウドストレージが安全かつ効率的なデータ管理方法である理由を説明し、数多くのサービスの中から自社に最適なサービスを選ぶための視点をお届けします。クラウドストレージの導入について不安を抱えておられる経営者、担当者の方はぜひお役立てください。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
クラウドストレージとは
中小企業にとって最も安全かつ効率的なデータ管理方法とは
法人のクラウドストレージの選び方
法人向けクラウドストレージの比較一覧
「データ容量課金制」のおすすめクラウドストレージ4選
「ユーザ課金制」のおすすめクラウドストレージ5選
「ファイル転送機能」が充実しているクラウドストレージ4選
「無料版の容量サイズが大きい」クラウドストレージ2選
クラウドストレージの6つのメリット
法人向けクラウドストレージの上手な活用例
企業がクラウドストレージを導入する際に注意すべきポイント
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

クラウドストレージとは、インターネットを通じてアクセスする保管場所(データセンター)にデータを保存したり、転送・共有したりできるストレージサービスです。似たような言葉に「オンラインストレージ」がありますが、ほぼ同義と考えてよいでしょう。
従来、法人が保有するデータを保存・管理するためには「オンプレミス型」のファイルストレージが用いられてきました。「オンプレミス(on – premises)」とは「建物内、構内で」という意味で、自社施設内にサーバや通信回線などの必要な設備を設置し、システムを構築することを指します。
2010年前後から、インターネット回線の高速化、コンピュータの仮想化技術の向上により、企業は自社内にサーバを設置せずにシステム構築やデータ管理ができるクラウドサービスを導入、運用しはじめました。そして、その割合はますます高まっており、総務省の通信白書(令和5年版)によると2022年には72.2%に達しました。2017年は56.9%で6割弱だったにもかかわらず、約5年で全体の7割を超えたことが分かります。
.png)
出典:総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/datashu.html#f00250)
なぜこれほど多くの企業がオンプレミス型に替えて、あるいは並行してクラウドストレージを導入しているのでしょうか?理由は各企業によってさまざまですが、共通している2点にフォーカスしてみましょう。
それは「低コストで導入可能」であることと、「拡張性の高さ」です。以下、1つずつ詳しく説明しましょう。
クラウドバックアップについて知りたい方はこちら
クラウドストレージの特徴1. 低コストで導入可
オンプレミス型からクラウドストレージに多くの企業が移行している理由の1つは、低コストで導入可能だからです。
企業にとって利便性、機能性はもちろん重要ですが、高い導入コストは現実的ではありません。大企業に比べ、設備投資に掛けられるコストに限界がある中小企業はなおさらでしょう。
これまで発表されているデータからも、中小企業にとってクラウドサービスを導入するにあたっては、コストが大きな壁になっていることがうかがえます。
オンプレミス型の場合、サーバの設置、他の設備の購入資金、システム構築や運用には膨大な費用がかかります。しかし、クラウドストレージであれば自社で機器やシステムを準備しなくてよいため、初期費用がほとんどかかりません。また、保守・運用もクラウドストレージサービスの提供会社が行ってくれるため、自社で専門スタッフを常駐させる必要もありません。
さらに時間面からみても、クラウドストレージは低コストで導入可能です。オンプレミス型だと設備購入、システム構築のために数か月かかるのが一般的です。それに対して、クラウドストレージであればクラウドストレージサービスの提供会社に連絡し、契約が成立すれば即日使用を開始することも可能です。
クラウドストレージの特徴2. 拡張性の高さ
近年、多くの企業がクラウドストレージに移行しているもう1つの理由は拡張性の高さです。
クラウドストレージでは、企業規模や従業員数に合わせて最初は少な目のストレージ容量からスタートできます。その後、企業の成長に合わせてプランを変更し、容量を簡単に増やしていけばよいのです。
また、機能面の拡張性でいえば、元来クラウドでは他社のアプリケーションとの連携が難しいといわれていました。しかし、近年APIという技術により、各社アプリケーションとの連携が可能になり、高い拡張性を手に入れることができるようになりました。
APIとは、「アプリケーションプログラミングインターフェース(Application Programing Interface)」のことで、自社のアプリケーションと外部アプリケーションを連携させるために橋渡しの役割を果たします。これにより、クラウドストレージでデータを共有するとき、MicrosoftのビジネスソフトやSlackやChatworkなどのコミュニケーションアプリとの連携が可能になります。

企業がデータを管理する方法として、従来のオンプレミス型とクラウドストレージがあることを上述しました。ここでは、それに加えて、「法人向けサービスVS個人向けサービス」、「無料サービスVS有料サービス」という軸を加え、中小企業にとって安全かつ効率的なデータ管理方法について検証します。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」どちらを使うべきか
中小企業がデータ管理方法を選ぶ場合、クラウドストレージをおすすめします。
社内サーバ(オンプレミス)とクラウドストレージのどちらが優れているか、コストと拡張性の面からすでに比較しました。ここでは、中小企業にとって「安全かつ効率的な」データ管理方法はどちらかを検証します。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」、どちらが安全?
安全面に関していえば、社内サーバは自社でシステム構築が可能なため、お金と時間をかければ強固で堅牢なセキュリティ環境をつくりだせます。自社のセキュリティポリシー、セキュリティ要件を高めれば、いくらでも安全面で優れた環境は可能なのです。
また、社内サーバのネットワークは基本的にローカルネットワークシステムで運用されるため、外部ネットワークからは遮断されており、セキュリティインシデントの発生リスクを最小限に抑えられます。
一方、クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスであり、常時オンラインでないと利用できません。そのため、絶えず不正アクセスやサイバー攻撃の脅威にさらされていることは確かです。
ただ、以上の比較から、単純に社内サーバのほうがクラウドストレージよりも安全だと結論づけることはできません。
というのも、社内サーバの場合、システムの堅牢性をどの程度高めるかは経営者がセキュリティにどれほど高い意識を持っているかにかかっているからです。もし、経営層が厳格なセキュリティポリシーを設定し、高度かつ安全なシステムを作り上げるためにコストを厭わないというのであれば別ですが、中小企業の場合、上述したようにコスト面で限界があります。
逆にクラウドストレージサービスに関していえば、サービスの数も年々増え、多くの選択肢があります。その中でセキュリティ面で万全の対策を施し、なおかつ費用を抑えたサービスを選べば、コストパフォーマンスは社内サーバよりも高くなるのです。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」、どちらが効率的?
次に、社内サーバとクラウドストレージの効率性について検証してみましょう。
一口に効率的といってもさまざまな要素が関係していますが、効率的に業務を進めるためには「ムダ」を減らさなければなりません。
特に重要なのは情報共有での「ムダ」を減らすことです。例えば、共有するのがオフィス内でのテキストファイルがメインなら、社内サーバでもクラウドストレージでもかかる工数に大きな違いはないでしょう。しかし、昨今のようにテレワークが導入され、働く場所が多様化すると、社内サーバの場合は共有するのに手間がかかり、どうしても「ムダ」が生まれてしまいます。この点、クラウドストレージであれば、どこにいても、またファイルのサイズが大きくても共有可能です。また、出先などでスマートフォンやタブレットを使って共有できるのもクラウドストレージの魅力といえるでしょう。
「法人向けサービス」と「個人向けサービス」どちらを使うべきか
中小企業がクラウドストレージサービスを選択する場合、「法人向け」か「個人向け」かも重要です。
中小企業の場合、コストを抑えるために最初は個人向けサービスという選択もありえます。しかし、いずれは法人向けサービスに移行することをおすすめします。なぜなら、法人向けサービスには個人向けサービスにはかなわない特徴があるからです。
それはセキュリティ面でのさまざまな機能です。例えば、法人向けのサービスはアカウント管理機能と、グループ管理機能を細かく設定できるようになっています。また、ログ管理機能にも違いがあります。個人向けサービスでも履歴を見ることはできますが、法人向けサービスはセキュリティ違反があった場合にアクセスログを取得したり、アクセスをリアルタイムでモニタリングしたりする機能が備わっています。
「無料サービス」と「有料サービス」どちらを使うべきか
前項同様、有料サービスの方がセキュリティ面で優れているため、中小企業が最初は無料サービスを使うことがあっても、いずれ有料サービスに移行することをおすすめします。
セキュリティ面に加えて、有料サービスを選ぶべき別の理由は容量です。無料のクラウドストレージサービスの場合、容量に制限があり、平均的なサービスは5~15GBです。無料サービスで容量がもっとも大きいものはMEGAで20GBですが、有料サービスには到底及びません。有料のクラウドストレージサービスは法人を対象にしているため、容量の追加が可能であり、容量不足の心配はありません。
有料サービスの多くが無料トライアルを実施しているため、自社で導入するサービスを選ぶ場合には実際の使い勝手を試してみるとよいでしょう。

ここでは、中小企業がクラウドストレージを選ぶ場合、何を基準にすべきか、さらに具体的に9つのポイントを挙げます。
1. ユーザ課金制かデータ容量課金制か
最初のポイントはユーザ課金制か、データ容量課金制か、です。
ユーザ課金制とは、「1ユーザあたり」「10人まで」など、ユーザ数に応じて課金されるタイプの料金体系です。少人数で使用する場合、必要十分なサービスを利用できます。ただ、スタートアップベンチャーなど、成長スピードが早い企業の場合、従業員が増えるたびに課金が増え、コストがかさむリスクもあります。
データ容量課金制とは、ストレージのデータ容量によって料金が決まるタイプです。ユーザ数に関係なく利用できるため、短期間でユーザ数が増加することが見込まれる中小企業の場合、コストパフォーマンスが高くなります。逆にユーザ数が少ないにもかかわらず、データ容量だけ大きくても使いきれないため、コストがかかり、ムダになります。
2. 最初は低スペックからスタートできるか
2番目のポイントは、最初は低スペックからスタートできるかという点です。
一般的にクラウドストレージサービスは同じ提供会社でもいくつかのプランが準備されています。主な違いは容量とスペックです。使用料金が高額になればなるほど、容量が増え、スペックが上がるため、機能も充実します。
中小企業の場合、クラウドストレージサービスを利用したことがなく、使い方に慣れていない経営者や従業員もいます。そのため、上述した調査結果が示していたように「費用対効果がわからない」という声が上がるのです。
それを避けるためには、まず低スペック、低料金のプランからスタートして、徐々に容量を増やし、スペックを上げていくとよいでしょう。
3. ストレージ容量は十分か
3番目のポイントは自社が選ぶクラウドストレージの容量が十分かどうかです。
容量面で心配なら「容量無制限」を選べばよいと思うかもしれませんが、従業員数がそんなに多くない中小企業では使いきれませんし、そのために多額のコストを支払うのは割に合いません。
自社がどのくらいの容量を必要とするかは、業界によって、扱うデータの種類によって異なります。テキスト文書を多く扱う企業と、デザイン会社、建築事務所、動画制作会社などでは、やりとりするファイルサイズに違いがあります。
1つの基準になるのは1TB(テラバイト)がどのくらいの大きさか把握しておくことです。1TBとは、1000GB(ギガバイト)のことですが、以下のように換算すればイメージが湧きやすいでしょう。
・1枚1MBのオフィスファイルで約100万枚
・1枚4MBのJPEGファイルで約25万枚
・1曲5MBのMP3音楽ファイルで約20万曲
・1分ほどの動画(10MB)で約10万ファイル
・フルHD動画ファイル約166時間分
クラウドストレージの容量について知りたい方はこちら
4. 管理者機能が充実しているか
4番目のポイントは管理者機能が充実しているかどうかです。
上述したように、法人向け(有料サービス)と個人向け(無料サービス)のもっとも大きな違いはセキュリティ強化のための機能であり、管理者機能も含まれます。
その中には以下のような機能が含まれています。
・認証機能:外部からの不正アクセスを防ぐための機能です。例えば、外部からのアクセスを制限するための「IPアドレス制限」や、会社支給の端末のみでアクセスできるように設定する「デバイス認証」などが含まれます。
・アクセスコントロール機能:クラウドストレージのユーザにはさまざまな人が含まれます。部署や職位に応じて、また社員か外部からアクセスする取引先なのかによってもアクセスの仕方は異なります。管理者は「閲覧」のみなのか、「編集」も可能なのかを設定して、アクセスをコントロールし、情報流出や持ち出しを防止できます。
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
5番目のポイントはセキュリティ対策です。中小企業でも大企業でも、法人として顧客情報や取引先の機密情報を保有している以上、特に重要なポイントです。
上述したようにオンプレミス型のストレージであれば、自社でいくらでもセキュリティポリシーを厳格にできますが、クラウドストレージの場合は、サービス提供会社にある程度依存することは避けられません。そのため、クラウドストレージの選択にあたっては注意深い検討が必要です。
例えば、総務省「国民のための情報セキュリティサイト」では、クラウドサービス提供事業者が行っているべき確認項目として以下の7つを挙げています。
・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策(災害対策や侵入対策など)
・データのバックアップ
・ハードウェア機器の障害対策
・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策
・不正アクセスの防止
・アクセスログの管理
・通信の暗号化の有無
出典:「国民のための情報セキュリティサイト クラウドサービスを利用する際の情報セキュリティ対策」
(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/admin/15.html)
また、クラウドサービスのセキュリティ対策のレベルを確認する方法として、第三者認証も役立ちます。第三者認証とは、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)など、当事者と直接の利害関係がない第三者によって行われる認証であるため、信頼性が高いと考えられています。
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
6. ディザスタリカバリ対策がされているか
6番目のポイントは大規模災害に直面しても業務の継続性が担保されているか、つまりディザスタリカバリ(災害復旧)対策がなされているか、です。
そもそもクラウドストレージ自体がディザスタリカバリ対策の一環です。なぜなら、自社サーバよりも、災害にも強い堅牢な構造であるデータセンターにデータを保存しているほうが、消失の恐れは低いからです。
もっとも災害時に大規模な停電が発生したり、ネットワークが遮断されたりした場合はデータセンターのデータも利用できません。そのため、クラウドストレージの提供会社がデータセンターの拠点を複数持っており、データを分散保存しているかも確認しておくとよいでしょう。
7. バージョン管理機能は備わっているか
7番目のポイントはバージョン管理機能が備わっているかどうかです。
バージョン管理機能とは、間違って上書きをしてしまった場合に、遡って変更前のファイルに戻せる機能です。どのクラウドストレージサービスにも装備されていますが、何世代まで戻れるかをチェックしておきたいところです。
8. 必要な機能やサービスが備わっているか
8番目のポイントは自社が必要としている機能やサービスが備わっているかどうかです。
ここですべての機能を挙げることはできませんが、例えば以下のようなものがあります。
・アカウントのない社外の人間でもファイルはアップロード可能なのか
・スマートフォンやタブレットなどの端末にも対応しているか
・更新通知やファイル公開の期限、ユーザの有効期限などの自動化機能
また、サポート体制の有無と充実度も確認しておきましょう。特に外資系サービスでは日本国内でのサポート体制が不十分な場合もありますので、前もってチェックしておくことが大切です。
クラウドストレージサービスの使用開始前から、どんな機能やサービスが必要かをすべて把握することは不可能です。無料のトライアル期間を利用し、実際に操作してみて、その使い心地を試してみることをおすすめします。
9. ストレスを感じない操作感か
最後のポイントは、ユーザビリティです。つまり、そのクラウドストレージサービスが使いやすいかどうかということです。
もし、クラウドストレージサービスが普段使っているソフトやブラウザと操作感が全く異なると、導入にあたり従業員研修が必要になるでしょう。しかし、中小企業の場合、ただでさえ人手不足で時間がないため、クラウドストレージ習熟のために別途リソースを割くことは困難でしょう。結果的に社内に浸透せずに使われずに終わってしまうことになりかねません。
クラウドストレージを選ぶにあたっては、シンプルなインターフェースで感覚的に使えるサービスを選ぶようにしましょう。
以下では全部で15の法人向けのクラウドストレージを紹介します。
法人がクラウドストレージを選ぶときには自社の企業規模や導入の用途を重視すると思われます。そこで、ここでは15のサービスを「データ容量課金制」「ユーザ課金制」「ファイル転送機能充実」「無料版の容量サイズが大きいもの」の4つに分けて説明します。

以下でそれぞれのサービスが法人、特に中小企業にとってどんなメリットがあるのか、「機能」、「セキュリティ」、「価格」の3つの面から紹介します。
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円(税込、1年契約の場合)
※年契約の場合、初年度は全額返金保証
|
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)+初期費用 15,000円(税別)
|
・自動メール通知
・ユーザごとに権限設定
|
・IPアドレスによるアクセス制限
・アクセスログを1年分取得
|
|
Fileforce
|
Unlimited-1の場合 55,000円(税別、年契約の場合)
|
・全社共通のディレクトリ構成
・他アプリケーションから直接保存
|
・ユーザごとの権限設定
・全アクセスを追跡
・ランサムウェア対策
|
|
PrimeDrive
|
1GBの場合 12,000円+初期費用 30,000円
|
・ユーザごとに権限設定
・ユーザ情報を自動で取得、登録
|
・誤送信を無効可
・承認機能によるファイルの事前チェック
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人向けの「データ容量課金制」のおすすめクラウドストレージは次の4つです。
使えるねっとが提供する使えるファイル箱には、容量1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。わかりやすいインターフェースで、いつものパソコン操作とほぼ変わらない形で使用できるため、複雑なトレーニングを実施する必要もありません。暗号化、ログイン認証、ランサムウェア対策といったセキュリティ面の備えも万全で、法人での使用に適したクラウドストレージです。
100人でも、1,000人でも料金一律で使用できるため、社員が増えてもユーザ課金や権限発行に悩むことなく、費用もかさみません。また、中小企業のお客様に満足して利用いただけるよう、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。また、24か国語で利用できるため、グローバルにビジネスを展開する企業様や、海外拠点・他国のクライアントとお取引がある場合などにも適しています。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・WebDAV連携(アドバンス)
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)
・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)
・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)
価格
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。
公式HP:使えるファイル箱
IMAGE WORKS(イメージワークス)は、富士フイルムが提供する、画像・動画・制作コンテンツをいつでも、誰でもどこででも活用できるようにするための法人限定クラウドサービスです。広報・宣伝部門など、企業内のチームで専用のスペースを作ってファイル管理・共有を行いたい場合に便利です。
専用のスペースを作ることで、特定のファイルは誰が持っているのか、一体どこにあるのかといった問題も解消。在宅やテレワーク先など、インターネットさえあれば手軽に仕事で使うファイルを共有することができます。社内だけでなく取引先の人や海外支店などとも簡単・安全にファイルのやり取りが可能。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・自動メール通知で、確実に情報共有
・ユーザごとに権限設定
・画像・ドキュメントファイルや映像をダウンロードせず、ビューイングだけ許可
・豊富な検索機能
・属性情報のカスタマイズで独自のデータシステムを構築可能
セキュリティ
・ID・パスワード認証だけでなく、IPアドレスによるネットワーク認証などのアクセス制限
・詳細に記録されたアクセスログは1年分取得
・アップロード/ダウンロード通信の暗号化
・登録データのウイルスチェック
・保存データの暗号化保管
価格
|
プラン
|
ミニマムプラン
|
|
初期費用
(税別)
|
15,000円
|
|
月額費用
(税別)
|
15,000円
|
公式HP:IMAGE WORKS
Fileforce(ファイルフォース)は、「Small Business」から「Enterprise」まで、企業の成長フェーズに合わせて容量を設定し、最適なプランを選択できます。
ユーザ無制限で利用したい場合は「Unlimited」がおすすめ。
利用可能なユーザ数は「Small Business(容量:ユーザあたり10GB)」の場合10~50人、「Enterprise(必要な容量を購入可能)」は10人~、「Unlimited(容量:1TB、3TB、10TB、30TBから選択可能)」だと無制限になるため、自社のニーズに応じて適したプランを選べます。
使い慣れたエクスプローラで快適に作業できるので、パソコンが苦手な方でも安心。新しいツールの導入にあわせてトレーニングを行う必要もありません。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・全社共通のディレクトリ構成で社内のファイル共有が容易
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集&同時編集可
セキュリティ
・ユーザごとの権限設定
・ファイルの操作ログを記録し、すべてのアクセスを追跡
・ランサムウェア対策
・不正アクセス防止機能
価格
|
プラン
|
Small
Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
Enterprise
|
|
月額料金
(税別)
※年払い
|
900円/
ユーザ
|
55,000円
|
98,000円
|
198,000円
|
330,000円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Fileforce
PrimeDrive(プライムドライブ)は、ソフトバンクの法人向けクラウドストレージサービスです。契約容量に関わらず1万ユーザまで登録できるため、企業拡大に伴うユーザ増加にも柔軟に対応できます。
オンラインストレージでのデータ転送にあたって懸念となる情報漏えいを防止することを念頭に置き、セキュリティ対策に不可欠な機能を搭載。大容量のファイル転送や機密文書など重要なファイルの受け渡しに適しています。また、会議などでプレゼンテーションをする際などにも、クラウドストレージを使用することで紙の配布資料を準備する手間を省くことができます。
機能
・ユーザごとに権限設定
・Active Directory連携によりユーザ情報を自動で取得、登録
・iPad、iPhone、Androidにも対応
・10個のアクセス権限を任意の組み合わせでカスタム設定、柔軟なファイル共有が可能
セキュリティ
・ダウンロードリンクを発行後、誤送信が発生したらいつでも無効可
・承認機能により承認者が事前にファイル内容をチェック
・ユーザごと、登録ユーザ全員に対してIPアドレス制限が適用
・多段防御ネットワーク
・2048ビットSSL暗号通信
価格
| 契約容量 |
1GB |
10GB |
100GB |
200GB以上 |
初期費用
(一時金) |
30,000円 |
|
月額料金
|
12,000円
|
69,800円
|
180,000円
|
個別見積り
|
公式HP:PrimeDrive
|
サービス名
|
月額(ユーザ)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
・1,500以上のアプリ統合
・Webアプリでの電子サイン
|
・7段階のアクセス権制御
・ゼロトラストアーキテクチャ
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 1,980円~(税込、1ユーザあたり)
|
・120種類以上の拡張子に対応
・AD連携によるシングルサインオン
|
・ユーザごとのアクセス権限設定
・60種類以上のログ・セキュリティレポート
・AES256ビット暗号化
|
|
OneDrive for Business(Plan 1)
|
630円(税別、1ユーザあたり、年間サブスクリプション)
|
・アクセス権をいつでも取り消し可
|
・転送中、保管中のデータを暗号化
|
|
Dropbox Business
|
Standardの場合 1,500円(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・ドキュメントに直接アクセス
・共有ファイルにロゴ、企業名、背景画像を追加
|
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
|
|
NotePM
|
プラン8の場合 4,800円(税込)
|
・チャット連携 、API対応
・全文検索
|
・変更履歴を自動記録
・柔軟なアクセス制限
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、ユーザ課金制のクラウドストレージを5つ紹介します。容量課金制ではクラウド容量が大きすぎる場合、ユーザ数に合わせて課金される料金体系のほうがコストを抑えられる可能性が高いです。
Box(ボックス)は個人では10GBまで無料で利用できますが、法人向けのBoxビジネスプランは3人以上から導入可能です。Microsoft 365やGoogle Workspace等と連携できます。機能やセキュリティの充実度、またファイルアップロードの容量上限の違いにより「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」といったプランがあります。
ファイル共有やオンライン共同作業の機能の違い
・Business:ファイルアップロードの容量上限5GB
・Business Plus:ファイルアップロードの容量上限15GB、外部コラボレータ無制限
・Enterprise:ファイルアップロードの容量上限50GB、外部コラボレータ無制限
・EnterPrise Plus:ファイルアップロードの容量上限150GB、外部コラボレータ無制限
以下では、もっともスタンダードな「Business Plus」の機能、セキュリティについて説明します。
機能
・Microsoft OfficeやGoogle Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合
・Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフローの自動化
・データ損失防止
・高度な検索フィルター
セキュリティ
・ゼロトラストアーキテクチャのアプローチにより、安全なコラボレーションが可能
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・AES256ビット暗号化
・データの保持、廃棄の管理など情報ガバナンスを効率化
価格
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
カスタム
|
公式HP:Box
Box over VPNは、NTTコミュニケーションズが提供する閉域網サービス「Arcstar Universal One」を経由することで、BoxをセキュアなVPN環境下で利用できるサービスで、5人以上から導入可能です。
このサービスでは単なるファイル転送を行うだけでなく、ファイル共有を通じた社内外とのコラボレーションや、Salesforceなどの業務アプリケーションとのシームレスな連携などよりビジネスに特化した機能が揃っており、法人向けの「コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム」として提供されています。VPN環境下だけでなく、希望に応じてインターネット経由で接続して利用する形態も相談可能です。
機能
・120種類以上の拡張子に対応するプレビュー機能
・容量無制限のごみ箱
・AD連携によるシングルサインオン
・最大100世代のファイル世代管理
・検索キーワードで文書の中身まで検索可能
・20地域以上のグローバル言語に対応
セキュリティ
・ユーザごとにアクセス権限を設定
・60種類以上のログ・セキュリティレポート
・AES256ビット暗号化
価格
月額 1,980円(税込)~
公式HP:Box over VPN
OneDrive(ワンドライブ)for Businessは、Microsoftが提供しているクラウドストレージサービスです。個人向けの無料プランもありますが、「OneDrive for Business」は一般法人向けです。ファイル共有とストレージの使用を目的としたサービスは「Plan 1」のみであり、Microsoft 365アプリも使える「Microsoft 365 Business」もあります。
ここでは「OneDrive for Business(Plan 1)」の機能やセキュリティについて紹介します。
機能
・セキュリティを維持しながら組織内外の相手とファイルを共有
・アクセス権をいつでも取り消し可
・外部と共有されるファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定
・共有ファイルのダウンロードを防止
・320種類以上のファイルをWebでプレビュー
・Officeファイルの共同編集
・ファイルオンデマンドで、クラウド内のファイルへのアクセスは端末のストレージ不要
・インテリジェントな検索と検出のツールで探したいファイルが見つかる
・複数ページのスキャンを使用して、書類やレシート、名刺などの画像を素早く保存できる
セキュリティ
・転送中、保管中のデータを暗号化
価格
年間サブスクリプションで、「Plan 1」は630円(ユーザ/月、税別)です。
公式HP:OneDrive for Business
個人向けの無料サービスも提供しているDropbox(ドロップボックス)の法人向けサービスがDropbox Businessです。個人事業主から大企業まで、ビジネスの成長フェーズに合わせて「Professional」「Standard」「Advanced」の中から、最適なプランを選べます(以下の表では一部のみ抜粋)。
利用可能なユーザ数
Professional:ユーザ1人、ユーザ1人あたり3TB
Standard:ユーザ3人以上、チーム全体で5TB
Advanced:ユーザ3人以上、チーム全体で15TBから開始
ここでは、「Standard」の機能とセキュリティについて紹介します。
機能
・Googleドキュメントなどのファイルに直接アクセス可
・共有ファイルにロゴ、企業名、背景画像を追加
・Webでファイルをプレビュー可
・すべてのファイルのコンテンツを簡単に検索
・閲覧者の履歴
・1回の転送で最大2GBのファイルを送信
・ユーザごとに権限設定
・多要素認証
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
・ダウンロード許可、有効期限を設定して、共有ファイルの表示やアクセスを管理
・チーム外のユーザとリンクを共有する場合、必要があれば簡単にアクセス権を取り消し
価格
|
プラン
|
Professional
|
Standard
|
Advanced
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※年間払いの場合
|
2,000円
|
1,500円
|
2,400円
|
公式HP:Dropbox Business
NotePM(ノートピーエム)は社内で情報共有をするための社内wikiツールです。バラバラに管理されていたマニュアルやノウハウなどの社内ナレッジを一元管理します。情報共有に特化したサービスのため、容量は少な目に設定されています。
ファイル共有というよりは、社内の重要な情報を一箇所で効率的に管理するという目的で設計されており、チャットやメールで情報が流れてきたが埋もれてしまった、かなり前の情報を参照したいが探す手立てがない、マニュアルを作ってもメンテナンスが大変で誰も更新しない、といった場合に適したサービスです。
容量やユーザ数によってプランが細かく分かれているのが特徴で、利用可能なユーザ数に応じてプラン8~200まで用意されています。一番上のプラン200だとユーザ数200人まで、容量は2TBと十分な量のクラウドストレージを利用できます。
自社の利用人数と業務の種類に応じて必要な容量、予算といった観点から利用したいプランを絞り込むとよいでしょう。
機能
・社員がさまざまな情報を書き込み、蓄積することで、社内の知りたいことが見つかる
・ファイルの中身を全文検索
・チャット連携・API対応
・マルチデバイス対応
・レポート機能
セキュリティ
・変更履歴を自動記録
・柔軟なアクセス制限
価格
|
プラン
|
プラン8
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
プラン200
|
|
容量
(全体)
|
80GB
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
2TB
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
8人まで
|
15人まで
|
25人まで
|
50人まで
|
100人まで
|
200人まで
|
|
月額料金
(税込)
|
4,800円
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
120,000円
|
公式HP:NotePM

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
ギガファイル便
|
無料
|
・ファイル数、容量無制限の転送
・無料プランのみ
|
・ダウンロードパスワード
・アップロード直後に削除可
・ファイル暗号化
|
|
GigaCC ASP
|
10IDの場合 12,000円(税抜)+初期費用 50,000円(税抜)
|
・共有ノート機能
・履歴ログ管理
|
・グローバルIPアドレス制限
・SSL暗号化通信
・サーバ内暗号化
|
|
クリプト便
|
エントリープランの場合 1,000円(1ユーザあたり)
|
・交換相手・権限を制御
・利用手順が簡潔明快
|
・承認機能
・クレジットカード情報を守るPCI DSS準拠のサービス
|
|
Fleekdrive
|
Teamプランの場合 600円(税抜、1ユーザあたり)
|
・自動バージョン管理
・最低10ユーザから利用可能
|
・自動でウイルスチェック
・全ファイルを暗号化して保管
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、クラウドストレージの中でもファイル転送機能が充実しているサービスを4つ紹介します。企業によっては日常的に高画質の動画など、容量が大きなファイルのやりとりが必要です。その場合、共同編集の機能よりも重視すべきなのは、転送のスピードや扱えるデータの大きさです。
皆さんも一度は、メールでギガファイル便のリンクを開いたことがあるのではないでしょうか?
GigaFile(ギガファイル)便は、ユーザ登録不要で利用できるファイル転送サービスです。転送できるファイルの容量には制限がなく(1ファイル300GBまで)、アップロード後最大100日間保持されます。
ファイルを送る側は、まずギガファイル便を開いてファイルをアップロードします。このときに保持期限やダウンロードパスワードなどを設定することができます。ファイルのアップロードが完了するとリンクが生成されるのでこれをメールやチャットなどで送信すればファイルの共有は完了です。
受け取った人はURLを開いてファイルをダウンロードするだけなのでとてもシンプル。
公式アプリもあり、モバイルでファイルをやり取りしたい場合もスムーズに作業できます。
機能
・ファイル数、容量は無制限でファイルの転送ができる
・有料プランはなし
セキュリティ
・ダウンロードパスワード
・誤ったファイルをアップロードした場合はすぐに削除可
・ファイル暗号化
価格
無料
公式HP:ギガファイル便
GigaCC ASP(ギガシーシー)は、日本ワムネットが提供する、国産の企業間ファイル共有・転送サービスです。初期費用が50,000円かかるものの、企業間での機密ファイルをセキュアな環境で、安心してやりとりできます。「STANDARD」「ADVANCED」「PREMIUM」の3つのプランがあります。
純国産のオンラインストレージサービスで、企業だけでなく行政機関・研究機関などからも支持されています。高度なセキュリティ対策も搭載されておりビジネス利用に安心です。
業務で使用するファイルをとにかくシンプルに、安全に共有したいという法人や組織に適しています。
また、ファイル共有だけでなく請求書を一括送信したり、既存のシステムとシームレスに連携したりと、業務効率化をサポートしてくれる点も企業にとって嬉しいメリットです。
ここでは「ADVANCED」の機能、セキュリティについて紹介します。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・共通ノート機能
・履歴ログ管理
・ユーザごとの権限設定
・ディレクトリ権限設定
セキュリティ
・グローバルIPアドレス制限
・SSL暗号化通信
・サーバ内暗号化
・不正アクセス自動ロック
価格
・初期費用 50,000円
・10IDの場合は月額12,000円、1,000IDの場合は月額280,000円
・「ADVANCEDプラン」は+25,000円、「PREMIUMプラン」は+42,000円
公式HP:GigaCC ASP
クリプト便は、金融系企業を中心に20年以上に渡る実績を持つファイル転送サービスです。提供しているのは情報セキュリティ会社であり、高い堅牢性を誇ります。
プランは「エントリー(適したユーザ数:20人前後)」「ライト(50人前後)」「スタンダード(100人前後)」の3つで、さらに個別見積もりも可能です。
クリプト(crypto)とはもともと暗号という意味で、昨今話題になっている仮想通貨(cryptocurrency)や暗号技術(cryptography)といったところでも使用されている用語です。
その名の通り、重要な情報や文書を安全に保護するセキュリティ対策を売りにしたサービスで、金融・IT企業などデータの受け渡しが業務の中で重要な位置づけを占める法人に支持されています。
機能
・グループ機能により、ファイルの交換相手・権限をこまかく制御
・普段通りの操作で利用可能
・利用手順が簡潔明快
・オートパイロット機能
セキュリティ
・承認機能(事前承認、事後承認)
・クレジットカード情報を安全・効率的に受け渡すPCI DSS準拠のサービス
価格
・初期費用(初月のみ)+基本料金(月額)+超過料金(前月分)
|
プラン
|
エントリー
|
ライト
|
スタンダード
|
|
基本料金
(1ユーザ、月額)
|
1,000円
|
1,000円
|
900円
|
|
プランに含まれるもの
|
・20ユーザまでの
利用料
・5MB/通までの
アップロード
・100通/月までの
利用料
|
・50ユーザまでの
利用料
・10MB/通までの
アップロード
・400通/月までの
利用料
|
・100ユーザまでの
利用料
・20MB/通までの
アップロード
・1,000通/月までの
利用料
|
公式HP:クリプト便
Fleekdrive(フリークドライブ)は、障害耐性に優れたクラウドサーバ「AWS(Amazon Web Services)」を基盤にしています。クラウド上にファイルをアップロードした時点で国内3か所に分散してデータが保管されるため、そのうちのどこかが災害の被害に遭ってもデータ消失の心配がありません。
プランは、基本的なファイル共有ができる「Team(10GB×契約ユーザ数)」、高セキュリティでビジネスで本格的に使う「Business(200GB×契約ユーザ数)」、容量無制限で利用する「Enterprise(無制限)」の3つです。場所を問わずにオンラインでやり取りすることが一般的になった今、時間も情報資産も社内外を問わず有効活用するためには安心かつ便利なサービスです。
ここでは「Business」の機能とセキュリティについて紹介します。
機能
・自動バージョン管理
・オンライン共同編集50名
・モバイル閲覧
・ユーザごとの権限設定
・SSO(シングルサインオン)連携で、複数のアプリをシームレスに利用
セキュリティ
・アップロード時に自動でウイルスチェック
・全てのファイルを暗号化して保管
・IPアドレス制限
・24時間体制で不穏なアクションを自動通知
・過去5年分の証跡を蓄積
価格
|
プラン
|
Team
|
Business
|
|
ストレージ容量
|
10GB × 契約ユーザ数
|
200GB × 契約ユーザ数
|
|
料金
(1ユーザ、月額、税抜)
|
600円
|
1,800円
|
全プラン、30日間無料トライアルが可能です。
公式HP:Fleekdrive

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
MEGA
|
20GBまで無料
|
・転送マネージャーでファイルの管理
・携帯端末からファイル転送
|
・エンドツーエンド暗号を採用
・二要素認証
・ランサムウェア対策
|
|
Googleドライブ
|
15GBまで無料
|
・転送マネージャーでアップロードとダウンロードを管理
・Googleアプリと連携
|
・データの暗号化
・二段階認証
・ユーザごとの権限設定
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、無料版の容量サイズが大きいクラウドストレージを2つご紹介します。
ただ、中小企業であっても法人である以上、扱う情報には機密情報が多く含まれており、無料のサービスは慎重に利用する必要があります。無料版のクラウドストレージはあくまでも補助的に活用することをおすすめします。
MEGAはニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウドストレージです。20GBまでは無料で利用できます(一部機能に制限あり)。
ホームページも日本ユーザ向けにシンプルで分かりやすくローカライズされています。より多くの容量を使いたい場合は有料プランが使用できますが、月額約1,616円(2024年3月14日時点)のPro Iだと2TB、ProⅡだと8TB、ProⅢだと16TBまでと、かなりの量が利用できてお得です。
外資系のサービスだと日本語のホームページの翻訳がわかりづらかったり、明らかに日本向けじゃなかったりと法人で利用するならちょっと…と感じてしまうこともあると思います。その点、MEGAはサイトでの説明もわかりやすく、他のサービスと比較しても安価で機能性も高いためビジネス利用にも向いているといえそうです。
機能
・ファイルやフォルダのアップロード、ダウンロードを転送マネージャーで管理
・携帯端末でもファイルの転送が可能
・共有リンク発行
セキュリティ
・エンドツーエンド暗号を採用し、第三者が通信内容を傍受できない対策
・二要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護
・ランサムウェア対策
公式HP:MEGA
もはや説明不要の無料クラウドストレージ。15GB以上を使いたい場合は「Google One」へのアップデートが必須です。
今ではGmailの独自ドメインを取得し、Google Workspaceの契約で企業のアセットをオンラインで管理している企業も増えてきました。社内で共有したいファイルや画像、その他データなどはすべてGoogleドライブ上で管理できますし、「同じメールドメインを使用する社内ユーザのみに共有」といった権限の指定も可能です。
ファイルの転送だけでなく、リアルタイムでの共同作業が可能であるところも法人に選ばれるメリットのひとつだといえます。また、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライド、Googleドライブとそれぞれのアプリが公開されており、スマホでもパソコンと遜色ないパフォーマンスを発揮してくれます。
機能
・ファイルやフォルダのアップロード、ダウンロードを転送マネージャーで管理
・携帯端末でもファイルの転送が可能
・ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどと連携し、共同編集可能
セキュリティ
・データの暗号化
・二段階認証
・ユーザごとの権限設定
公式HP:Googleドライブ
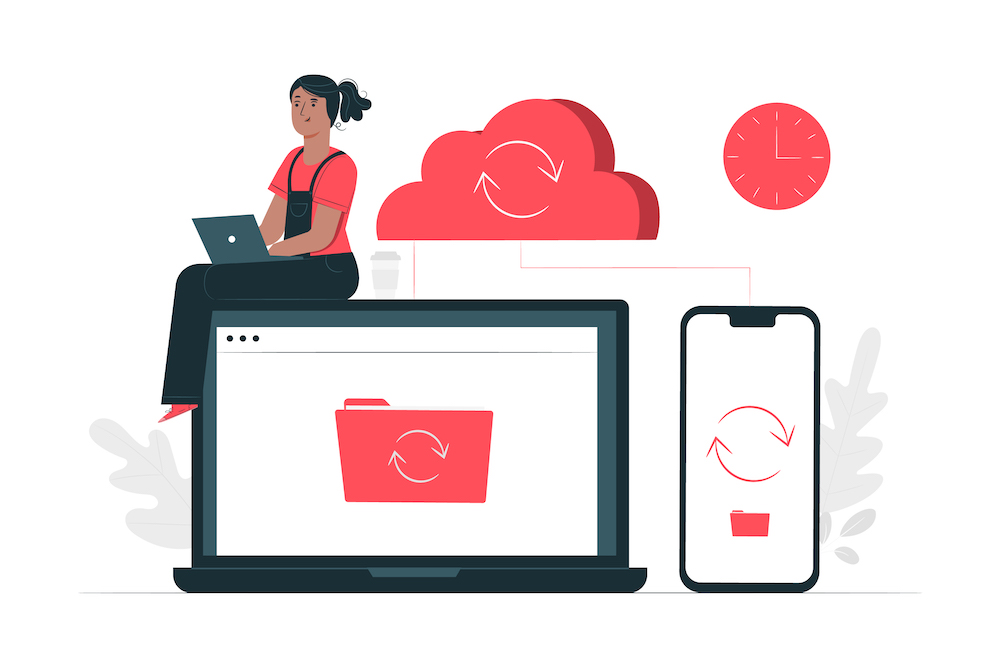
ここでは、クラウドストレージを導入する6つのメリットについてまとめておきます。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
1番目のメリットは、ファイルの一元管理による業務効率の向上です。
クラウドストレージを導入すれば、ユーザIDさえ持っていればいつでもどこでも必要な情報にアクセスできます。また、権限が与えられれば編集も可能です。作業工数を減らすことができるため、ムダを減らし、業務効率が上がります。
ファイルがさまざまな場所に分散すると、どのファイルが更新された最新のファイルかが分からなくなることがあります。しかし、クラウドストレージを活用して一元管理すると、すべてのユーザが常に最新のデータにアクセスできるようになります。
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
2番目のメリットは、ファイル共有や共同編集が簡単にできることです。
クラウドストレージがなければ、データをメールに添付して送り、受け取ったファイルを自分の端末で編集後、再度送付する作業が必要です。しかし、クラウドストレージがあれば、ファイル共有や共同編集を直接行えます。会社のパソコンだけでなく、出張先や現場などでスマートフォンさえあれば、ファイル共有が可能なのでとても便利です。
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
3番目のメリットは、いつでもどこからでもファイルにアクセスできる点です。
オンプレミスだと社内ネットワーク内でのやりとりに限定されますが、クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスのため、オフィスでも出先でも、自宅でも、コワーキングスペースでもアクセス可能です。
データやファイルにいつでもどこでもアクセスできるため、従業員の柔軟な働き方にもつながります。例えば、観光地やリゾート地で休暇をとりながらテレワークで仕事するワーケーションや、介護や育児などをしながら在宅で勤務する従業員にも必要なインフラを提供できます。
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
4番目のメリットは、ファイルサーバの運用や管理が不要になることです。
オンプレミスでは、システム構築や保守・運用に担当者を設置し、自社のリソースを割かなければなりません。それに対して、クラウドストレージでは、自社内のサーバ設置も、そのための運用管理のコストや人員も必要ありません。基本的にハード面での運用はクラウドストレージの提供会社が担ってくれます。
5. アクセス権限やログ監視機能によりセキュリティを強化できる
5番目のメリットは、アクセス権限やログ管理機能によるセキュリティの強化です。
上述したように、有料のクラウドストレージサービスはアクセス権限をこまかく設定できますし、ログ監視機能も充実しています。それにより、不正アクセスを防ぎ、万が一セキュリティインシデントが発生した場合も原因究明がしやすいといえます。
6. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
6番目のメリットは、災害が起きてもクラウドストレージならデータを消失するリスクが低いという点です。
日本が災害大国であることは誰も疑う余地がない事実です。実際、2008年から2018年の10年間で全世界で発生したマグニチュード6以上の地震の約13.1%は日本で発生しています。また、災害の被害額も1984年から2013年までの合計で全世界の17.5%を日本での災害が占めています。
クラウドストレージの場合、データは堅牢な構造のデータセンターに保存されているため、自社内のサーバに保存しているよりも、消失のリスクは低いといえます。企業のBCP(事業継続)計画の一環としても、クラウドストレージの導入は有効です。
参考:「情報通信白書(令和2年版)世界のマグニチュード6以上の震源分布とプレート境界(2010年~2019年)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd121140.html)を加工して作成
BCP対策について知りたい方はこちら

ここでは、各業界で法人向けクラウドストレージがどのように活用されているか、具体例を3つ取り上げます。
建設業|現場でタイムリーに情報を確認。仕事効率が大幅アップ!
建設業の特徴はオフィスだけでなく、取引先や現場での業務が多いことです。そのため、クラウドストレージがあれば情報の一元管理が可能になり、必要な情報はいつでもどこからでもアクセス可能です。
例えば、本社でアップした資料を現場で確認したり、逆に現場で撮った写真を取引先のフォルダにアップすることでデータ共有が完了します。データをタイムリーに共有できるため、業務効率がアップし、勤務時間の短縮にもつながるなど従業員のワークライフバランスに寄与します。
製造業|自社サーバを無くして管理コストや災害リスクを大幅削減
製造業に限ったことではありませんが、自社サーバを管理するには設置費用、電気代、保守運用のための人件費など、膨大なコストがかかります。クラウドストレージに切り替えることでそれらの費用を大幅に削減することが可能になります。
また、自社サーバの運用ではいくら建物の耐震性を強化しても災害リスクの削減には限界があります。この点、クラウドストレージなら、堅牢なデータセンターにデータが保管されていますし、被災リスクの低い場所が選ばれているため、災害リスクも大幅に低減します。
教育機関|ユーザ数無制限のクラウドストレージで費用削減
教育機関でクラウドストレージを活用したい場合はユーザ数無制限のプランがおすすめ。学生を含め利用者が多数に上ることが想定される場合でも、ユーザ追加コストの心配がありません。また、学生は閲覧のみ、教員には編集権限を与えるといった、ユーザごとのアクセス権限変更も可能であり、機密情報の管理も安心です。さらに、フォルダごとにアクセス可能なユーザを設定できるため、クラスや研究室ごとに使い分けることも可能です。
クラウドストレージについて知りたい方はこちら
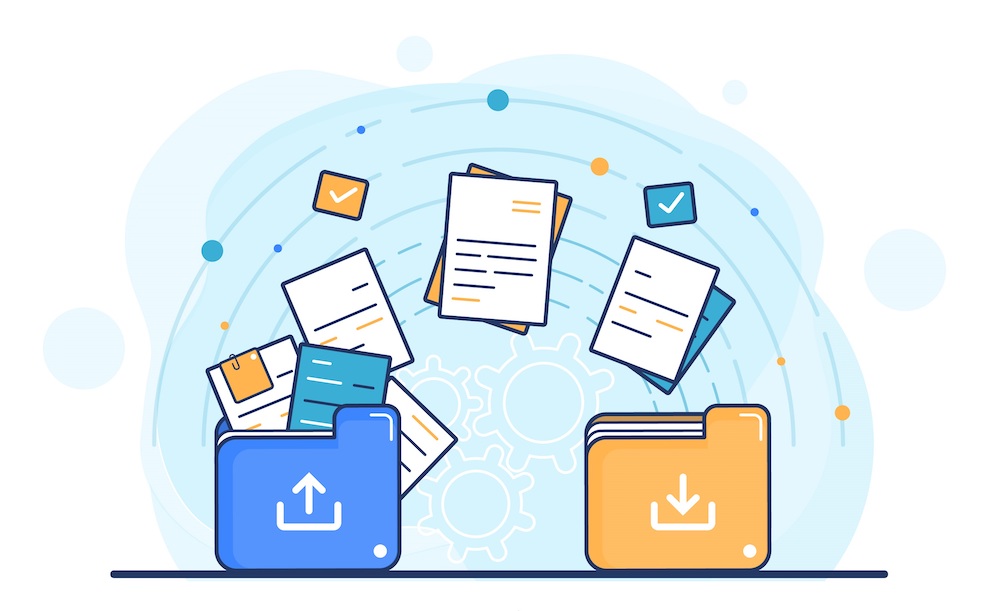
導入に多くのメリットがあるクラウドストレージですが、企業側が気を付けたいポイントもあります。ここでは、5つの注意すべきポイントを取り上げます。
インターネット環境の整備
1つ目のポイントは、インターネット環境の整備です。クラウドストレージはインターネットを経由して使うサービスのため、インターネット環境に大きく依存します。特に企業規模が大きく、多くの従業員が同時にクラウドストレージにアクセスする場合、高スペックの通信速度が必要です。
また、災害時だけでなく、システム障害などでネットワークが切断される可能性もあります。クラウドストレージにデータを保管している場合、オフィス内のネットワークが突然切断される可能性も考慮に入れておかなければなりません。さらに突発的なアクセス集中による負荷増大も考えて、予備設備を準備しておくこと(冗長化)も忘れないようにしましょう。
セキュリティ対策
2つ目のポイントは、セキュリティ対策です。クラウドストレージサービスを選ぶ際に提供会社がどの程度のセキュリティ対策を行っているのか見極める重要性については上述しました。ただ、セキュリティに関しては利用者である企業側にも責任があります。
例えば、提供会社がどれだけ強固なセキュリティ対策をとっていても、利用者側のパスワードやIDの管理体制が不十分であれば、情報漏えいや不正アクセスにつながります。そのため、パスワードを連続して入力できる回数を制限したり、定期的にパスワードを更新したり、人目につくところにメモで貼ったりすることがないよう、従業員全体に注意を喚起する必要があります。
IDに関して忘れがちなのが、退職者のID管理です。退職した社員のIDをそのままにしておけば、そのIDやパスワードがどのような形で誰に渡るか分かりません。そのため、退職と同時にすぐにIDを無効化する手続きをとりましょう。
脆弱性について知りたい方はこちら
運用体制の整備
3つ目のポイントは、クラウド導入時に運用体制を整備することです。運用体制とは、役割や責任の区分を明確にしておくということです。
中小企業でありがちなのは、経営者のITリテラシーがあまり高くないため、情報管理の担当者に導入から運用まですべて任せきりにしてしまうケースです。クラウドストレージの導入は企業にとって貴重な資産である情報を扱いますし、顧客情報の管理にも関係するため、経営課題として経営層が積極的に関わることが不可欠です。
運用体制を確立した上で、以下の点も導入時には行っておきましょう。
・運用ルールの作成
・マニュアルの整備
・トラブル時の連絡体制、問い合わせ先の明確化
・研修や周知徹底の手段
拡張機能による課金
4つ目のポイントは拡張機能による課金に注意するということです。
クラウドストレージの料金体系については上述しましたが、多くのサービスではさまざまなオプションをつけて機能を拡充することが可能です。その中には遠隔地へのバックアップを行ってくれる「ディザスタリカバリ機能」や、共有したファイルをアーカイブとして保管する「アーカイブ機能」などがあります。
利用を開始してから、次々とオプション機能を追加してしまうと毎月のコストがかさんでしまいます。自社にとって必要なオプション機能は何か、また毎月の利用コストの予算を超過しないかなど申し込み前によくチェックしておきましょう。
データ移行
5つ目のポイントはクラウドストレージ導入時のデータ移行です。これまで自社のサーバに保存されていたデータを移行する作業が必要です。この移行作業は無償(初期費用に含まれるため)で行ってくれる提供会社が一般的ですが、別途有償のサービスを利用しなければならない場合もあります。
.png)
ここでは、中小企業のリモートワーク導入にも対応している「使えるファイル箱」について解説します。
使えるファイル箱の3つの特長
使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」はデータ容量課金制で安心して使えるクラウドストレージサービスです。ここでは3つの具体的な特長を説明します。
1. ユーザ数無制限
使えるファイル箱の最大の特徴は、ユーザ数無制限で使用できることです。成長スピードの早い中小企業でも、最初は少人数からスタートし、追加料金を払うことなく事業規模に合わせてユーザ数を自由に設定できます。また、細やかな管理権限の設定が可能なので、ユーザIDの一部を取引先に渡して、大容量データのやりとりもできます。
2. 普段のパソコンと同じように操作できる
使えるファイル箱は特別なインターフェースを必要としません。例えば、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有ファイルを操作できます。中小企業でクラウドストレージを導入したものの、結局は従業員に使われることなく浸透しなかった、という事態を避けられます。
3. 高機能なのに低価格、全額返金保証もある
上述した通り、多くの中小企業がクラウドストレージ導入に二の足を踏む理由はコスト面での悩みです。そこで、使えるファイル箱はそんな悩みを少しでも軽減すべく、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。
また、2022年10月からは、1年契約の場合、初回契約期間中ならいつでも解約・返金申請できる全額返金保証を開始しました。中小企業のお役に立てる絶対の自信があるからこそできる、使えるファイル箱ならではの保証制度です。
中小企業に最適な機能と料金形態
具体的な料金体系を説明しましょう。
スタンダードプランのストレージ容量は1TBで、料金は1カ月契約の場合は25,080円(月額、税込)、1年契約の場合は21,230円(月単価、税込)です。セキュリティ機能が充実したアドバンスプランのストレージ容量は3TBで、1カ月契約の場合は75,680円(月額、税込)、1年契約の場合は60,500円(月単価、税込)です。例えば、スタンダードプランをお選びいただいた場合、従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
最短で即日ご利用可能!
使えるファイル箱を試してみたいと思われたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
即日または翌営業日に対応させていただき、お見積りいたします。ご希望に合わせてオンラインでのご案内やトライアル、勉強会を実施させていただき、本契約となります。最短で即日のご利用開始も可能です。
.jpg)
(1)クラウドのデータはどこにあるの?
クラウドのデータはデータセンターに格納されています。データセンターの所在地は、クラウドストレージの提供会社によって異なりますが、多くの場合被災リスクの低い場所が選ばれます。また、国外にデータセンターを設置する場合もありますが、セキュリティや治安の面、また電力供給において不安定な場所もあります。
(2)法人向けクラウドストレージの市場規模は?
2022年に国内企業を対象に行われた調査によると、2021年度のクラウドサービス市場規模は約3.5兆円でした。今後、2025年~2026年には現在の2倍以上の規模まで市場が拡大するものとみられています。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
今やクラウドを利用したサービスは企業にとって欠かせない存在です。その中の一つにオンラインストレージがあります。
今回はこのオンラインストレージをテーマに取り上げます。分かっているようで分かっていない「オンラインストレージとクラウドの違い」から、オンラインストレージを活用するメリット、また多くのサービスから自社に合った選択をするコツを徹底解説します。
クラウドストレージの比較を知りたい方はこちら
目次
オンラインストレージとは?
オンラインストレージの主な使い方
オンラインストレージを利用するメリット
オンラインストレージを利用する際の注意点・デメリット
無料版と有料版のオンラインストレージの違いは?
オンラインストレージの法人向けセキュリティ機能
【無料版】おすすめオンラインストレージ4選
【有料版】おすすめオンラインストレージ12選
オンラインストレージを導入する際の比較ポイント
使えるファイル箱なら低価格でファイルの保管・共有が可能
FAQ

オンラインストレージとは、ネット上の保管場所です。以下では、そもそもオンラインストレージとは何か、また混同されやすい「クラウド」との違いについて説明します。中小企業では従来からの社内サーバを利用して、機密データやファイルを保管している会社も多いかもしれません。オンラインストレージの特徴を理解することで、今後の導入のメリットについて明らかになるはずです。
オンラインストレージの意味は「ネット上の保管場所」
オンラインストレージを英語で表記すると「online storage」です。つまり、「online(インターネット上の)」「storage(保管場所)」を意味します。従来、情報を保管するためには、社内にサーバやハードディスクを設置する「local storage」が主流でした。しかし、「local(局所的な)」という英語が示すように、オフィス内など限られた範囲でしかアクセスできないという難点がありました。それに対して、オンラインストレージはネット環境さえあればいつでもどこでも情報を編集したり、共有したりできます。
オンラインストレージは「クラウドストレージ」とも呼ばれています。
クラウドストレージとは何かを知りたい方はこちら
クラウドストレージのおすすめを知りたい方はこちら
データの自動保存、自動同期が可能
オンラインストレージの特徴として、データの自動保存、自動同期が可能な点が挙げられます。社内サーバなど、ローカルストレージの場合、同じファイルが複数のユーザによって編集され、更新され、どれが最新版なのか分からなくなることがあります。
それに対して、オンラインストレージ上で共有、編集されたデータは自動保存、自動同期されるため、常に最新のデータが存在することになります。
オンラインストレージとクラウドの違い
クラウド(クラウド・コンピューティング)とは、インターネット経由でユーザに提供するサービス形態のことです。そして、オンラインストレージはデータを保管するストレージサービスに特化したクラウドの一種です。つまり、従来は手元のコンピュータに外付けHDDやファイルサーバを接続して保管していたデータを、ネットワーク経由でクラウド上に保管するのです。

オンラインストレージの主な使い方は、ストレージである以上、ファイルサーバや外付けHDDと同じです。データを保存するだけでなく、他のユーザにも共有できます。ローカルストレージと異なり、インターネット経由で保存、共有できるため、どこからでも操作可能です。そのため、テレワークとも親和性が高いといえます。もちろん、もしものときに備えてバックアップとして利用することも可能です。
データの保存
個人でも企業でもオンラインストレージを使えば、データを保存・管理するのが容易になります。
企業にとってデータの価値は高まる一方です。経営戦略でもマーケティングでも勘や経験、度胸ではなく、データ分析の結果をもとに施策や戦略策定を行う「データドリブン」が加速しているからです。また、企業が保有する顧客の個人情報も膨大です。さらにコロナ禍をきっかけに多くの企業で紙ベースだった資料を電子化しようとする動きも強まっています。これらのデータをオフラインのファイルサーバや外付けHDDだけに保存するには容量が足りません。
実際、NECが調査した200団体の統計値によると、データ容量は毎年1.55倍、5年で9倍ものペースで増加しているそうです。
この点、オンラインストレージであれば、必要に応じて簡単にストレージの容量を増やすことも可能です。
データの共有
オンラインストレージの醍醐味はデータ保存だけではありません。
保存したデータはオンライン上にあるため、インターネットを経由して複数の端末からいつでもどこからでもアクセスできます。コロナ禍をきっかけとしてテレワークの導入が一気に進みましたが、それを可能にした一つの要素はオンラインストレージによるデータ共有だったといっても過言ではないでしょう。自宅やコワーキングスペースからはもちろん、出張先やワーケーション先でもインターネット環境と端末さえあれば、互いにデータを共有できるのです。また、オンラインストレージではオフィスのPC、タブレット、スマホなどあらゆる端末からデータを共有できますし、WindowsやMacといったOSの違いも問題になりません。
テレワーク導入の要となる「クラウド化」について知りたい方はこちら
データのバックアップ
企業が保有するデータのバックアップの重要性は年々高まっており、強調してもし過ぎることはありません。
コロナ禍で世界的にビジネスがデジタル化したことでサイバー攻撃が急増しており、ミュンヘン再保険のレポートによると、2021年のサイバー攻撃による世界経済の損失額は約6兆ドル(約790兆円)で、2025年には10.5兆ドル(約140兆円)になると予測されています。
加えて災害大国である日本ではどこにいても洪水や台風、地震、火山噴火などの自然災害の影響を受けるかわかりません。オフィスで運用しているサーバが被災してデータが消失する事態に備えて、オンラインストレージを活用しデータバックアップをとることはBCP(事業継続計画)として今や必須だといえるでしょう。

オンラインストレージの特徴は、いつでもどこでも、必要とする情報にアクセスできることでしょう。そのため、コロナ禍をきっかけにして多くの企業で導入されたテレワークにも対応しやすいといえます。ここでは、企業がオンラインストレージを活用することで得られる具体的なメリットについて、7つのポイントを取り上げます。
業務効率化に役立つ
チームのメンバーでプロジェクトを進める場合、ファイルやデータのスムーズなやりとりは非常に重要です。
例えば、オフラインで外付けHDDやUSBメモリを使ってデータをやりとりしながら同じファイルを複数の人が編集する工程では、往々にしてトラブルが生じます。自分が持っているファイルが最新版と思っていたら別のメンバーがまだ編集していたり、そもそもファイルの居場所がわからなくなったりするからです。
しかし、オンラインストレージではその心配はありません。オンラインストレージはあたかも「ベースキャンプ」のような存在で、誰もがそこにアクセスすれば最新のファイルを見つけることができます。
また、多くのオンラインストレージサービスではアカウントごとにアクセス権限(閲覧・編集など)を管理者によって設定できます。アカウント保有者がログインした場合、オンラインストレージ上に表示されるのは自分に関係のあるフォルダやファイルのみのため、必要なデータにもアクセスしやすく、業務効率化に役立ちます。
働き方の多様化に対応できる
企業が優秀な人材を確保するためには、従業員の多様な働き方に対応したシステムを構築しなければなりません。例えば、子育てや介護をしながら地方で働く人や、副業をしながら二拠点生活を選択するメンバーがチームにいても、オンラインストレージがあればいつでもどこでもデータのやりとりを行うことができます。オンラインストレージなら、場所や時間にとらわれない、働き方の多様化に対応できるのです。
アナログで管理していた手間を省ける
アナログでのデータ管理ではヒューマンエラーを回避できません。データのやり取りや管理の過程で保存のし忘れ、誤削除、紛失などが必ず発生します。また、ファイルの更新も自動で行ってくれるとは限らないため、最新の情報を探すのにも手間がかかることがあります。
この点、オンラインストレージを使えば、データを格納すれば自動的に保存してくれますし、仮に誤削除しても作業を取り消したり、復元したりできます。
データを集約できる
オフラインでデータをやり取り・管理しようとすると、往々にしてどこに何のデータがあるのか分からなくなりがちです。仕事に必要なデータやファイルに限らず、紙ベースの資料や作業道具などもきちんとファイリングし、整理されていれば探す手間が省け、すぐにアクセスできます。結果としてより重要なことに時間を振り分けられるのです。
オンラインストレージがあれば、企業活動に必要なあらゆるデータを一元管理できるため、ムダを省くことができ、生産性が向上します。
災害時のリスクを回避できる
オンラインストレージを活用することで、災害時のリスクを軽減できます。災害大国である日本において、企業はどこに拠点を置いていても災害リスクへの対策が不可欠です。その中には、地震、水害、感染症、火災などがあります。
こうした災害が企業にもたらす被害は建物の倒壊や従業員の負傷、サプライチェーンの分断、ライフラインの断絶など物理的なものだけでなく、企業にとって計り知れない価値を持つ情報の消失にもつながります。
データが消失すれば、企業が事業を継続することは不可能です。そのため、BCP(事業継続計画)の一環として、オンラインストレージの活用は有効です。災害リスクの低い場所にデータセンターを設置しているため、仮にオフィスが物理的な被害を受けても、データを災害から守ることができます。
参考:みんなのBCP 「災害リスクから企業を守る!災害がもたらす影響と対策を解説」
BCP対策とは何かを知りたい方はこちら
サーバ運用、管理の手間を省ける
社内サーバなど、ローカルストレージを利用する場合には、運用や管理を自分たちで行わなければなりません。導入だけでなく、運用管理まですべて社内で行うためには多大なコストがかかります。
それに対して、オンラインストレージを活用すれば、運用管理の手間を省くことができます。なぜなら、オンラインストレージの運用管理はサービス提供事業者が負担してくれるからです。中小企業やスタートアップ企業は、サーバ運用、管理にまで専門人員を割けないことも少なくありません。オンラインストレージを導入することで、本業により一層専念できます。
大容量データも即座にアップできる
多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める中、保有するデータはますます増えています。また、業種によっては写真や動画を扱うこともあり、必然的に扱うファイル一つひとつは大容量になります。
大容量ファイルや、大量のデータをローカルストレージに一気にアップロードしようとすると、負荷が大きくなってアップロードに時間がかかったり、失敗したりすることもあります。この点、オンラインストレージであれば、大容量データも即座にアップできるため、効率的に安心して作業することができます。

いいことづくめに思えるオンラインストレージですが、デメリットがないわけではありません。ただ、前もってデメリットを把握しておけば、それを踏まえた上で活用の仕方を工夫することができます。大切なことは、メリットとデメリットを比較し、自社に最適なのがオンラインストレージか、ローカルストレージかを検証することです。ここでは、オンラインストレージを利用する際の5つの注意点・デメリットについて詳しく説明します。
リテラシーがない人は操作が難しい
従来のファイルサーバ経由で情報共有をしていた企業はまだしも、紙ベースで、あるいはUSBメモリやEメールに添付する形でデータをやり取りしていたシニア世代にとって、オンラインストレージの概念はなかなか理解しづらいかもしれません。オンラインストレージを全社的に導入するためにはあらゆる世代が最低限のITリテラシーを身に付けておく必要があります。導入の際に社内研修を行ったり、個別にサポートしたりすることでこのギャップは乗り越えられるはずです。
情報漏えい対策の徹底が必要
オンラインストレージの最大の懸念点がセキュリティという方も多いようです。その理由は「オンライン」である以上、サイバー攻撃の対象になりやすいのではという漠然とした不安からかもしれません。
しかし、実際はオンラインストレージを利用することで、ファイルサーバよりもセキュリティ不安が増大するということはほとんどありません。もっとも、どの程度のセキュリティ対策を採用しているかはオンラインストレージを提供している事業者により違いがあるため、事前に入念な調査を行う必要があります。
加えて、オンラインストレージを使用する場合は社内でもセキュリティ意識の向上は欠かせません。IDとパスワードがあれば誰でもログインできるため、第三者に知られないように定期的なパスワード変更をしたり、退職者のID・パスワードはその都度無効化したりすることも忘れないようにしましょう。
オンラインストレージを利用することに不安を感じるという方は、リスク回避のためのセキュリティ対策をまとめたこちらの記事もご覧ください。
クラウドストレージのセキュリティについて知りたい方はこちら
カスタマイズ性に乏しい
社内で独自にファイルサーバを運用している場合はニーズに合わせて自由なカスタマイズが可能です。他方、オンラインストレージの場合は事業者が汎用的なサービスとして提供しているため、自社に合わせてカスタマイズするのは難しいといえます。
もっともカスタマイズするためには自社に専門の人材を抱えなければなりませんが、オンラインストレージを使う場合は自社で運用、点検、維持のコストはかかりません。
障害時の自社対応が難しい
オンラインストレージの別のデメリットは障害時の自社対応が難しいという点です。前述したように、オンラインストレージの運用管理は、サービス提供会社が行っています。つまり、オンラインストレージに障害が発生した場合には、サービス提供会社に連絡をとり、対応を待つしかありません。
トラブル時に現場が混乱しているにも関わらず、ただ「待つのみ」というのは歯がゆいでしょう。そのため、障害時の混乱をできるだけ軽減するために、あらかじめサービス提供会社の運営管理体制を確認するだけでなく、社内でもデータを保存しておくなどの対応が求められます。
運用には一定の費用がかかる
ローカルストレージであろうと、オンラインストレージであろうと、一定の費用がかかるのは当然です。しかし、両者は費用がかかるタイミングが異なります。
社内サーバなどのローカルストレージの場合は、イニシャルコスト、つまり導入時に多くの費用がかかります。例えば、サーバなどの機器を購入したり、システムを構築したりする費用です。それに対して、オンライストレージの場合、初期費用よりも運用により多くの費用がかかります。導入時はサービス提供会社に連絡してすぐに始められますが、毎月必ずサービスに対する費用を支払うことになります。その期間が長くなればなるほど、費用が増えていきます。
もちろん、オンラインストレージには無料版もありますが、法人で使用する場合、セキュリティと容量の観点からは有料版のほうがメリットが大きいといえます。無料版と有料版の違いについては次項で説明します。
.jpg)
オンラインストレージには、無料版と有料版があります。個人のユーザにとって無料版のサービスは導入しやすく、機能的にも問題がないように思えます。しかし、法人のユーザが導入する場合は、有料版のオンラインストレージがおすすめです。その主な理由は上述したように、セキュリティと容量です。以下でそれぞれのポイントについて説明します。
セキュリティの制限
無料版と有料版ではセキュリティレベルで違いがあります。もっとも無料版だからといって、利用するのに不安を感じるほどセキュリティが低いわけではなく、個人が使う分には支障はありません。しかし、企業の機密情報や顧客情報を保管するにはやはり有料版の機能が不可欠だといえるでしょう。ただ、法人利用する場合に必要なセキュリティレベルはどのくらいなのだろう、と思われるかもしれません。この点については後の章で紹介します。
容量の制限
個人が5GB~10GB程度の容量を使用したいのであれば、通常は無料版のオンラインストレージで十分です。企業が利用する場合は保有するデータ量が比べものにならないほど増えるため、1TBを越える大容量ファイルの保管も可能な有料版を選択するとよいでしょう。ただ、当然ですが、容量が増えれば、その分費用もかかります。そのため、中小企業やスタートアップ企業がやみくもに容量が大きなプランや「容量無制限」を選択する必要はありません。必要に応じて容量を増やしていけば良いからです。

前述したように、オンラインストレージを利用する場合、個人では無料版でも十分かもしれませんが、法人利用ではそういう訳にはいきません。それは、企業が保有する情報は資産であり、機密情報や顧客情報は厳格な管理が求められるからです。そのため、必要十分なセキュリティ機能を備えた、有料版のオンラインストレージを導入しましょう。ここでは、法人向けのセキュリティ機能にはどのようなものが含まれるかを解説します。
アクセスコントロール機能
アクセスコントロールとは、オンラインストレージにアクセスできるユーザを制御する機能です。アクセスそのものをコントロールすることに加え、アクセスできるユーザが必要な操作のみを行えるように事前に設定しておくことも含みます。
アクセスコントロール機能が企業にとって必要なのは、悪意のあるユーザからの情報の窃取を防ぐためです。例えば、オンラインストレージ内の情報に企業外の取引先がアクセス、閲覧できるようにしておくならスムーズなコミュニケーションを図ることができます。しかし、閲覧だけでなく、編集や削除権限を与える必要はありませんし、アクセスできる情報の範囲も限定的でしょう。内部の従業員と同じだけの権限を与えるなら、セキュリティリスクは高まります。
アクセスコントロールには、「認証」「認可」「監査」の3つの機能があります。認証とは、次項で詳しく説明する通り、そもそもログインできるユーザを制限する機能です。認可とは、認証したユーザが可能な操作を制限することです。そして、監査とは、不正アクセスやサイバー攻撃などが発生した場合に、アクセス履歴などに基づき、被害を調査するために必要です。
サイバー攻撃とは何かを知りたい方はこちら
認証機能
認証機能はアクセスコントロール機能の一つです。ローカルストレージ内の情報にアクセスできるユーザを認証するためには、様々な方法が用いられます。もっとも一般的なのが、IDとパスワードを組み合わせる認証方法です。最近では、認証のセキュリティを高めるために、指紋や顔認証などを組み合わせた多要素認証が用いられます。
多要素認証とは、認証に複数の「要素」を組み合わせる方法ですが、その中には「知識要素」、「所有要素」、「生体要素」があります。知識要素とは、ユーザ本人が知っている情報であり、その中にはパスワードや「秘密の質問」などがあります。所有要素とは、ユーザが所有しているスマートフォンを用いたSMS認証やICカード、トークンなどが含まれます、そして、生体認証とはユーザの身体的特徴である、顔や指紋、声紋、静脈などによる認証を組み合わせる方法です。
バージョン管理機能
バージョン管理機能とは、ファイルの変更履歴を記録することをいいます。オンラインストレージでは、様々なユーザが同一ファイルにアクセスし編集、ファイルの内容に変更を加えます。そのため、いつ、誰が、どのような変更を加えたのかを記録しておくことで、バグが発生したときなどに過去の履歴を参照してファイルを復元したり、作業の問題点を検証したりすることが可能になります。また、間違って上書きをしたときに、変更前の状態に戻すこともでき、大変便利な機能です。
参考:NTT東日本 「【詳解】バージョン管理とは?|基礎知識をビギナーに分かりやすく解説」
カントリーリスク対策機能
そもそもカントリーリスクとは、投資などの対象国の政情や経済・社会情勢などの変化に起因するリスクをいいます。オンラインストレージにおいても、事業者が外資系の場合は、サーバ所在地が海外であるため、データの扱いは現地の法律やルールが適用されます。例えば、アメリカでは同時多発テロ事件以降、米国愛国者法が制定され、政府機関が裁判所の許可なくアメリカ国内にあるサーバ内の情報を調査することが可能になりました。
国による法律の違いは、企業が保有する顧客情報や機密情報をリスクにさらすことになります。そのため、オンラインストレージに顧客情報などの個人情報をメインに保管するのであれば、国産のオンラインストレージを選ぶほうが良いでしょう。
ディザスタリカバリ機能
ディザスタリカバリ(Disaster Recovery)機能とは、直訳すると「災害復旧」です。オンラインストレージに関していえば、災害時に遠隔地に設置したバックアップセンターを拠点にして、被害を受けたメインセンターの業務を移管する機能を指します。
災害時であっても、企業のシステムがダウンし、業務の停止に追い込まれれば、企業の信頼は失墜しますし、十分な措置を前もって取っていなかったと評価されるなら、社会的責任を追求される可能性もあります。
ディザスタリカバリ機能により、企業はダウンタイムを最小限に抑え、迅速にサービスを復旧できます。その指標になるのが、「どこまで遡って復旧するか」を表すRPO(目標復旧地点)と、「いつまでに復旧するか」を表すRTO(目標復旧時間)です。
参考:NTTコミュニケーションズ 「用語集」
ディザスタリカバリとは何かを知りたい方はこちら
ログ管理機能
オンラインストレージに誰が、いつログインし、どんな作業をしたのか、履歴を記録する機能です。ログ管理機能によって、不正な使い方を防止し、問題が発生したときに原因の特定に役立ちます。
ログは膨大な記録であるため、ただ記録すれば良いという訳ではありません。集めたデータを分析しやすいように管理し、レポート表示します。また、ログを管理するモニタリング機能を含むサービスもあります。

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
Google Drive
|
・15GBまで無料
・有料プランは30GB〜5TB
|
・Googleアプリと連携
・複数ユーザ間共有、共同編集
・オンライン対応の設定
|
・ファイルのスキャン
・アカウントごとに権限を設定
・2段階認証
|
|
Dropbox
|
・2GBまで無料
・有料プランは2TB〜
|
・モバイル端末から利用可
・自動同期
・30日間はバージョンを復元可能
|
・AES暗号化とSSL/TLS暗号化を採用
・サードパーティ製アプリの監視
|
|
firestorage
|
・2GBまで無料
|
・最大アップロードサイズ 2GB
・アップロード数無制限
・「photostorage」で写真を保管
|
・ダウンロードの期限設定
・ダウンロードパスワードの設定、変更
|
|
OneDrive
|
・5GBまで無料
|
・Officeアプリとの連携
・最大30日間のファイル復元
|
・2要素認証
・ゼロスタンディングアクセスポリシー
・データの暗号化
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
上述したようにセキュリティと容量制限の観点から、法人利用なら有料のオンラインストレージがおすすめです。しかし、個人利用に関していえば、無料版のオンラインストレージでも十分な機能とセキュリティを備えているといえるでしょう。ここでは、無料で使えるおすすめオンラインストレージ4選を紹介します。
Google Drive
Google Drive(グーグルドライブ)は、Googleが提供するオンラインストレージです。個人向けの無料プランと、企業向けの有料プランがあります。無料プランの容量は15GBまで利用できます。ちなみに有料プラン(「Google Workspace」)は「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」があり、ユーザ1人あたりのストレージは30GB、2TB、5TBです。さらに高度なセキュリティとストレージの追加が可能な「Enterprise」もあります。
Google Driveの強みは「ドキュメント」「スプレッドシート」「カレンダー」「スライド」などのビジネスソフトとシームレスに連携できるため、オンラインストレージ内のファイルの共同編集に便利な点でしょう。
Google Driveのセキュリティをチェックしてみましょう。オンラインストレージ内のファイルはスキャンされ、マルウェアやスパム、ランサムウェア、フィッシングが検出された場合は削除されます。また、ドライブのファイルへのアクセスは暗号化されます。さらに、Google Driveでは、アカウントごとに「編集権限」や「閲覧権限」を設定できます。また、2段階認証の設定も可能なため、悪意のあるユーザのアクセスを防ぐことができます。
ただ、編集権限や閲覧権限はあくまでも管理者が設定するため、人為的なミスが発生するリスクを完全に取り除くことは不可能です。そのため、情報流出のリスクを防ぐための対策を各自とることが必要です。
公式HP:Google Drive
Dropbox
Dropbox(ドロップボックス)に登録すると、2GBのオンラインストレージを無料で利用できるようになります。WindowsでもMacでも利用できますし、スマートフォンやタブレットからのアクセスも簡単、いつでもどこでも情報共有が可能です。
オンラインストレージ内にファイルを保存すれば、自動的に同期してくれます。また、誤ってファイルを削除してしまった場合でも、30日以内なら任意のバージョンに復元できます。
Dropboxは不正ログインを防止するため、様々なセキュリティ対策をしていますが、その一つにデータの暗号化があります。オンラインストレージ内にデータを保存するときにはAES暗号化を採用し、データ転送時にもSSL/TLSを使用、データ漏えいを未然に防ぎます。加えて、アカウントセキュリティページでは、アカウントにリンクしたデバイスや、アクセスを許可しているサードパーティ製アプリなどの監視も可能です。
もっとも、セキュリティに関しては無料版では限界があるのも事実です。ビジネス用プランであるDropbox Businessでは、「ISO 27001」など国際的に認められているセキュリティ規格や規制に準拠していますので、ワンランク上の安心が保証されます。
公式HP:Dropbox
firestorage
firestorage(ファイヤーストレージ)にも個人向け、法人向けのプランがあります。firestorageの料金プランには、「未登録会員」「無料会員」「ライト会員」「正会員」の4つがありますが、このうち、「未登録会員」「無料会員」が無料で利用できます。
firestorageでは、高画質な写真や動画など大容量ファイルをアップロードし、発行されたURLを相手に送ることで、データを共有できます。無料のプランでは、1ファイルの最大アップロードサイズは2GBであり、無制限にアップロードが可能です。ただ、未登録会員はストレージ保存はできません。会員登録することで2GBのストレージ容量が与えられ、そこに大切なファイルを保存することもできます。
また、「photostorage」を利用すれば、写真をオンライン上に保存し、思い出・資料ごとにロールを作って管理できます。サムネイルが表示されるため、一つひとつの写真を開かなくても一覧で確認できて便利です。また、photostorageに保存した写真はスマホやタブレットでも簡単に閲覧できます。
ファイルのダウンロードには期限を設定できますし、そのたびごとにパスワードを設定、変更できるため、セキュリティ面も安心です。
公式HP:firestorage
OneDrive
OneDrive(ワンドライブ)はMicrosoftが提供するオンラインストレージです。個人向けの無料プランの容量は5GBで、Microsoft 365のビジネスソフトであるWordやExcelなどのOfficeアプリとシームレスに連携させて、編集作業を行えます。
OneDriveは、データを保護するためにいくつかの方法を推奨しています。強力なパスワードを使用すること、Microsoftアカウントにセキュリティ情報を追加すること、2要素認証を使用すること、モバイルデバイスで暗号化を有効にすることなどです。
また、OneDriveは、「ゼロスタンディングアクセス」ポリシーを維持しています。これは、アクセスの昇格が必要な特定のインシデントに対応して明示的に許可されない限り、エンジニアもサービスにアクセスできないというものです。
また、OneDriveがランサムウェアまたは悪意ある攻撃を検出すると、アラートが送信される仕組みです。攻撃から30日以内であれば、影響を受ける前のバージョンにファイルを回復できます。データが転送されるときはTLS暗号化を使用して保護、保管中はAES256キーで暗号化され、ストレージ内の情報は高いセキュリティレベルで保護されています。
公式HP:OneDrive
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
容量
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円~(税込、1年契約の場合)
※年契約の場合、初年度は全額返金保証
|
1 / 3 TB
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー
・ウェブ管理画面のSSL化
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 2,860円〜(1ユーザあたり)
|
無制限
|
・AES256ビットでファイルを暗号化
・7種類のアクセス権限設定
・ファイル単位で共有の設定可能
|
|
Cmosy
|
・ライトの場合 550円〜(税込)
・基本料金 2,000円〜
|
100〜500GB
|
・パスワード、ダウンロード回数制限の設定
・社外メンバーの権限付与
・アクセス権限の可視化
|
|
FleekDrive
|
Teamの場合 600円〜
|
10GB〜無制限
|
・自動ウイルスチェック
・全ファイルを暗号化して保管
・IPアドレス制限
|
|
PrimeDrive
|
1GBの場合 12,000円〜
※初期費用(一時金)30,000円
|
1GB〜
|
・ダウンロードリンクの無効化
・承認機能による情報漏えい防止
・IPアドレス制限を適用可
|
|
GigaCC ASP
|
10IDの場合 12,000円〜
※初期費用 50,000円
|
要問い合わせ
|
・ワンタイムパスワードによる2段階認証機能
・認証アプリを利用した2要素認証機能
・ウイルスチェック機能
|
|
NotePM
|
プラン15の場合 9,000円
|
80GB〜30TB
|
・アクセスログ
・監視ログ
・SSO/SAML認証
|
|
Amazon S3
|
S3 標準の場合最初の50TB/月まで1GBあたり 0.023USD〜
|
容量制限なし
|
・「Amazon Macie」でデータを検出、保護可能
・Amazon S3とオンプレミスの間でのプライベート接続
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)
※初期費用 15,000円(税別)
|
要問い合わせ
|
・暗号化による通信、保管
・アクセスログを1年分取得
・登録データのウイルスチェック
|
|
Fileforce
|
Small Businessの場合 1ID900円〜
|
10GB〜30TB
|
・独自の仮想ファイルシステム
・ランサムウェアを検知するアルゴリズム
・高機能なファイル変更管理システム
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円〜(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
全プラン容量無制限
|
・SSOとMFAをサポートする強力なユーザ認証
・7段階のユーザ権限設定
・全ファイルのAES256ビット暗号化
|
|
iCloud Drive
|
50GBの場合 130円(税込)
|
50GB〜2TB
|
・2要素認証
・「標準のデータ保護」と「高度なデータ保護」でデータを暗号化
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人がオンラインストレージの導入を検討しているなら、セキュリティ面と容量のサイズを考えると、有料版のオンラインストレージがおすすめです。ただ、中小企業がオンラインストレージを導入する場合、イニシャルコストや月々の利用料金も気になるところです。
以下では、中小企業におすすめのオンラインストレージ12選をご紹介します。
使えるファイル箱
使えるねっとオンラインストレージである「使えるファイル箱」は、低コストでハイパフォーマンスを目指す中小企業におすすめです。注目すべき点の1つは、ユーザ数無制限なので事業規模に合わせて社員が増えても、課金が必要ないこと。また、エクスプローラーやFinderなど慣れた画面で使用できる分かりやすいインターフェースのため、操作性にも優れています。
また、使えるファイル箱は24か国語で利用できるため、生産拠点やクライアントが海外にいる場合でもビジネスのスピードが落ちることはありません。
容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。さらに30日間の無料トライアルも実施しているため、実際の使い勝手を試してみることもできます。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
・WebDAV連携(アドバンス)
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)
・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)
・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
Box over VPN
Box over VPN(ボックスオーバーVPN)は、NTTコミュニケーションズが提供する、VPN経由でセキュアにBoxを利用できるサービスです。Boxは「ISO 27001」「ISO 27018」、「HIAPP」など世界中の各種セキュリティ規格に準拠しており、企業だけでなく、政府機関でも利用されているオンラインストレージです。ストレージ容量は無制限です。
機能
・1ファイル標準5GBを上限にアップロード
・Adobe Photoshopなど、120種類以上の拡張子に対応するプレビュー対応
・スマートフォンやタブレットにも対応
・NTTコミュニケーションズが24時間365日一元保守のサポート
・60日間無料トライアル実施中
セキュリティ
・データの保管時にAES256ビットでファイルを暗号化
・プレビューのみから編集まで、7種類のアクセス権限を細かく設定可能
・公開期限やダウンロードの可否など、ファイル単位で共有の設定ができる
・60種類のログ・セキュリティレポート
接続方法はインターネット型、VPN型から選択可能で、最低利用IDはインターネット型が従業員数500名以下の場合は5ID、従業員数501名以上の場合は20IDです。それに対してVPN型の最低利用ID数は20IDです。
|
プラン
|
Business
|
Business Plus
|
Enterprise
|
|
インターネット型
【Web限定・1年契約】
(月額・1ID・税込)
|
1,958円
|
3,245円
|
4,510円
|
|
VPN型
(月額・1ID・税込)
|
2,860円
|
4,180円
|
5,500円
|
公式HP:Box over VPN
Cmosy
Cmosy(クモシィ)はGoogle Driveを十分使いこなせていない企業にセキュリティと管理機能をプラスする拡張サービスです。例えば、アカウントがない顧客にGoogle Driveから直接ファイルを送りたい場合にパスワード設定やダウンロード制限をかけたり、外部共有を制限していて開放できない場合にドライブから送付したりできる機能が追加されます。そうすることで、Google Driveにすべてのデータを集めて、社内メンバー同士が円滑なコラボレーションを図ることができ、社外メンバーに対してはより安全な管理を実現します。
多くの企業がGoogle Driveを使いながら、さらに別のクラウドストレージや送受信サービスを併用しています。そのため、管理の手間とコストがかかるだけでなく、生産性も低下してしまっています。Cmosyを使うことで、ドライブを一元化し、複雑な管理をすっきり分かりやすくすることが可能です。
機能
・送付するドライブリンクにパスワードを付与
・受け取りダウンロードに回数や期限を設定
・機密ファイルを顧客から安全にドライブへ直接回収
・いつダウンロードされたか履歴を残す
・送受信のログは永年保管でき、監査利用に最適
料金プランは「ライト」「スタンダード」「ビジネス」「プロフェッショナル」の4つです。以下の月額料金に加え、基本料金がかかります。基本料金は100ユーザ未満(100GB/月)の場合、月額2,000円、100ユーザ以上(500GB/月)の場合、月額10,000円です。
|
プラン
|
ライト
|
スタンダード
|
ビジネス
|
プロフェッショナル
|
|
利用アカウント数
|
10人~
|
50人~
|
5人~
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
|
550円
|
1,650円~
|
2,200円~
|
要問い合わせ
|
|
基本料金
(月額)
|
100ユーザ未満(100GB/月) 2,000円
100ユーザ以上(500GB/月)10,000円
|
公式HP:Cmosy
Fleekdrive
Fleekdrive(フリークドライブ)は、誰もが使いやすいインターフェース、豊富な管理機能、徹底したセキュリティ環境が特徴のオンラインストレージサービスです。建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、不動産業など様々な業種に対応しており、各業態に合わせたソリューションを提供します。
機能
・アプリ・ダウンロードなしでブラウザ上で閲覧
・メール添付せずに安全にファイルを共有
・公開スペースを使って、アカウントを持たないユーザとの共有も可能
・クラウド上のファイルをOfficeを使ってシームレスに編集
・英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語にも対応し、海外拠点ともスムーズに共有
・社内サーバのファイルを自動的にアップロードしクラウド化できる
・ファイルごとのチャットで気軽に意見交換し、スムーズに共同作業
・使われていないファイルを自動でアーカイブ
・バージョンの自動更新や古いファイルの自動削除
・ファイルの中身もすぐに見つかる検索機能
・ファイルにタグを付け用途に合わせてカテゴライズ
セキュリティ
・アップロード時に自動でウイルスチェック
・すべてのファイルを暗号化して保管
・IPアドレス制限
・PDFのコピー・印刷制限で情報漏えいを防止
・社内常駐パートナーのクラウド利用を制限
・ID・パスワードの一元管理でセキュリティ強化
・SSO認証(シングルサインオン)で複数のアプリにシームレスにログイン
|
プラン
|
Team
|
Business
|
|
月額料金
(1ユーザ、税抜)
※年間払い
|
600円
※最低10ユーザ〜
|
1,800円
※最低10ユーザ〜
|
|
ストレージ容量
|
10GB×契約ユーザ数
|
200GB×契約ユーザ数
|
公式HP:Fleekdrive
PrimeDrive
PrimeDrive(プライムドライブ)は、SoftBankが提供するオンラインストレージサービスです。アップロードするデータはSoftBankが運用する国内データセンターに保存されるため、カントリーリスク対策もばっちりです。また、地震や津波などの自然災害によるシステム障害対策として、メインサイトだけでなく、国内遠隔地にある「ディザスタリカバリサイト」も提供し、30分ごとにデータをバックアップします。
機能
・Microsoft Office Online連携機能で、WordやExcelなどのファイルを直接編集、閲覧可
・ファイルの保存期間を設定し、期間を過ぎると自動的に削除できる
・PKIクライアント認証
・PrimeDrive上に保存されたファイルをPDF化してダウンロード
・アドレス帳機能で送付頻度の高い相手を登録
・グループ作成機能
・ファイルは50世代まで保存
・一度開いたファイルはキャッシュ保存
・英語対応
セキュリティ
・誤送信が発生した場合はダウンロードリンクを無効にできる
・承認機能により、宛名ミスによる情報漏えいを未然に防止
・ユーザごと、登録ユーザ全員に対してIPアドレス制限を適用可
・ISO27001、ISO27017、ISMAP認証済
|
契約容量
|
1GB
|
10GB
|
100GB
|
200GB以上
|
|
初期費用(一時金)
|
30,000円
|
|
月額料金
|
12,000円
|
69,800円
|
180,000円
|
個別見積り
|
公式HP:PrimeDrive
GigaCC ASP
GigaCC ASPは、日本ワムネット株式会社が提供するオンラインストレージサービスです。ITリテラシーが高くなくても利用できる使いやすさが特徴です。また、多種多様な企業の業務内容やニーズに合わせたプランや導入方法を提供しており、幅広い業種・業界での実績があります。
機能
・承認ワークフローや宛先制限などでセキュアなファイル共有を実現
・直感的で使いやすいユーザインターフェース
・相手方の受取回数や受取可能期間の設定
・受取時のパスワード必須化機能
・送信先アドレス制限機能
・間違ったファイルを送信、転送してしまった場合に1クリックで受取用URLを無効化
・ブラウザ画面を利用せず、コマンドラインからファイル共有機能を操作できる「コマンドラインツール機能」
・大幅な業務効率化とコスト削減が図れるRPAと連携
・ナレッジ共有やメンバー間のコミュニケーションに使える「共有ノート機能」
セキュリティ
・メールによるワンタイムパスワードを利用した2段階認証機能
・スマートフォンの認証アプリを利用した2要素認証機能
・ウイルスチェック機能
・グローバルIPアドレス制限
・SSL/TLS暗号化通信
・サーバ内暗号化
・履歴ログ管理
|
プラン
|
STANDARDプラン
|
ADVANCEDプラン
|
PREMIUMプラン
|
|
初期費用
|
50,000円
|
|
月額費用
|
10ID 12,000円~ 1,000ID 280,000円~
|
|
追加費用
|
要件に応じて見積り可
|
+25,000円
|
+42,000円
|
公式HP:GigaCC ASP
NotePM
NotePMは、他のオンラインストレージとやや異なります。ストレージ容量は他社サービスに比べて小さめですが、情報を一元化して、社内のナレッジを共有するのに便利なツールです。
例えば、社内マニュアルをWordやExcelで作るのは大変ですし、一度作ってもファイルを更新すると最新版がどれなのか分からなくなることもあります。また、人によって作り方や完成度もバラバラという悩みもあります。そんな悩みをNotePMは解決してくれます。パソコンに詳しくない人でも簡単にマニュアル作成可能な高機能エディタとテンプレート機能で、バラバラなフォーマットを標準化し、オンラインストレージ上で簡単に共有できるのです。
機能
・高機能エディタとテンプレートで、バラバラなフォーマットを標準化。マニュアル作成に便利な画像編集機能も準備
・Word、Excel、PDFなど、ファイルの中身も全文検索可能
・スマホで撮影した動画マニュアルなどを簡単に動画共有
・変更履歴を自動で記録。変更履歴はハイライト表示されるため、誰が何を更新したか一目瞭然
・英語UIもあり
セキュリティ
・柔軟なアクセス制限により、社外メンバーとの共有も簡単
・アクセスログ
・監視ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
・IPアドレス制限
・ログイン連続失敗した場合に自動でアカウントロック
・ログインした端末情報を記録
|
プラン
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
|
月額料金
(税込)
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
|
ユーザ数
|
15人まで
|
25人まで
|
50人まで
|
100人まで
|
|
ストレージ量
(チーム全体)
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
|
無料枠
|
ユーザ数の3倍まで、見るだけのユーザは無料
|
公式HP:NotePM
Amazon S3
Amazon Web Services(AWS)には、さまざまなサービスがありますが、オンラインストレージサービスであるS3もその一つです。Amazon S3は、データの整理や管理を対象にした様々な機能を備えています。また、高いセキュリティレベルが特徴で、コンプライアンス要件を満たすことができます。AWS無料利用枠の一環として、サインアップするとS3 Standardストレージクラスで5GBを利用可能。
機能
・保存するオブジェクトの数に関わりなく、S3バッチオペレーションを使用し、ストレージ内のデータをあらゆる規模で簡単に管理
・データのバージョン管理を維持し、偶発的な削除を防ぐ
・ストレージのモニタリング
・「S3 Storage Lens」により、オブジェクトストレージの使用状況とアクティビティの傾向を組織全体で可視化
・「S3 ストレージクラス分析」でアクセスパターンを分析し、適切なデータを適切なストレージクラスにいつ移行するかの決定をサポート
・「AWS DataSync」により、数百TBに及ぶ数百万のファイルをAmazon S3に簡単かつ効率的に転送可
セキュリティ
・「Amazon Macie」を使用して、保存されている機密データを検出、保護することができる
・「AWS PrivateLink for S3」で、Amazon S3とオンプレミスの間でプライベート接続を行える
公式HP:Amazon S3
IMAGE WORKS
IMAGE WORKS(イメージワークス)は、富士フイルムが提供する画像・動画コンテンツ保存をメインにしたオンラインストレージサービスです。他のオンラインストレージと異なるのは、コンテンツ管理システムをベースとした共有サービスという点です。ただストレージにデータをため込むだけでなく、いつでもすぐに欲しいコンテンツを探せるように検索機能が充実しています。また、初めて使う人でも分かりやすい閲覧・操作性が特徴です。
料金はユーザの利用目的・用途に合わせて要相談ですが、ミニマムプランは初期費用15,000円(税別)、月額費用15,000円(税別)ですぐに始められます。
機能
・サムネイル機能による高速一覧表示
・ファイル登録、ダウンロードなどの操作時に自動でメール通知を送付できる
・フォルダ単位で、きめ細やかにアクセス範囲や操作権限のコントロールが可能
・画像や映像をダウンロードさせずにビューイングだけを許可することで拡散防止
・レジューム機能・整合性確認機能で送受信を支援
・IDを持たないゲストユーザとの送受信も可能
・ファイル名や登録日時に加え、メタ情報を利用したキーワード検索や絞り込み検索が可能
セキュリティ
・暗号化による通信、保管
・詳細に記録されたアクセスログも1年分取得
・登録データのウイルスチェック
・各サーバの冗長化
・遠隔地バックアップ
・ISO27001などの第三者機関による各種認証を取得
|
プラン
|
ミニマムプラン
|
|
初期費用
(税別)
|
15,000円
|
|
月額費用
(税別)
|
15,000円
|
公式HP:IMAGE WORKS
Fileforce
Fileforceは、企業が必要とする多彩な機能をオールインワンで提供するオンラインストレージサービスです。エクスプローラーから操作できるシンプルな使いやすさ、ユーザ数無制限のため導入しやすい、などの特徴があります。オンラインで30秒で申し込むことができ、30日間の無料トライアルも実施しています。
機能
・PC内にファイルが保存されているかのようなファイルの高速表示を実現
・全社共通のディレクトリ構成で社内のファイル共有がしやすい
・ファイルの共有範囲もフォルダツリーで見える化
・他のアプリケーションからの直接保存ができる
・オンライン編集もスムーズ
・バージョンファイル管理
・電子帳簿保存法の要件も満たす属性情報の検索に対応
・マルチデバイス対応
セキュリティ
・独自の仮想ファイルシステムによってランサムウェアが拠り所とするOSの機能を制御
・ヒューリスティックなアルゴリズムでランサムウェアの可能性があるプロセスを検知
・高機能なファイル変更管理システムで、ランサムウェアが書き換え・暗号化したファイルをピンポイントで特定
・被害を受けた可能性のあるファイルはワンクリックで自動的にリスト化
・被害にあったファイルのみをワンクリックで暗号化前の状態に復旧
|
プラン
|
Small
Business
|
Unlimited
-1
|
Unlimited
-3
|
Unlimited
-10
|
|
ユーザ数
|
10~50ID
|
無制限
|
|
ストレージ容量
|
ユーザあたり10GB
|
1TB
|
3TB
|
10TB
|
|
利用料
(月額、税別、年契約)
|
900円/1ID
|
55,000円
|
98,000円
|
198,000円
|
公式HP:Fileforce
Box
Boxは2005年の創業以来、人々が簡単にどこからでも必要な情報にアクセスし、コラボレーションできる環境を提供してきました。オンラインストレージサービスのみならず、プロジェクト計画やスケジュールの作成、電子サインなどの豊富な機能も魅力の一つです。
また、Box Relayを活用することで、予算管理などの反復業務を自動化し、業務の効率化を図ります。さまざまなアプリともシームレスに連携可能です。
機能
・Zoom、Slack、Microsoft 365など1,500以上の主要ツールとシームレスに統合
・ユーザフレンドリーな使い勝手
・ファイルのプレビューやダウンロード、コンテンツがいつどのように利用されているかを把握し、利用状況のトレンドを可視化
・数量無制限の電子サインを無料で提供
セキュリティ
・SSOとMFAをサポートする強力なユーザ認証
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・すべてのファイルが保管時また転送時にAES256ビット暗号化
・Box KeySafeにより、ユーザによる暗号キーの独自制御が可能
・ネイティブなデータ漏えい対策とサイバー脅威検知のための高度な学習ツール
・グローバルなコンプライアンス要件に対応
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
応相談
|
|
アップロード
容量上限
|
5GB
|
15GB
|
50GB
|
150GB
|
公式HP:Box
iCloud Drive
iCloud Driveは、Appleが提供するオンラインストレージサービスです。iCloudの一部であり、Apple製品のデバイスを複数使用している場合、各デバイスをシームレスに連携させ、データ共有を可能にします。容量は5GBまで無料で利用できますが、最大12TBまで増やせます。
iOS8では「iCloud Drive」というアプリが必要でしたが、iOS11以降はiCloudの機能の一つとして統合され、アプリは不要になりました。
機能
・共有中のファイルではスレッド形式で参加者と打合せや相談が可能
・編集結果がリアルタイムで反映され、色付けされる
・Pages、Numbers、Keynoteを共同作業可
セキュリティ
・2要素認証
・iCloudに保存するデータを暗号化するために「標準のデータ保護」と「高度なデータ保護」を提供。「標準のデータ保護」では、ユーザのデータは暗号化され、暗号鍵はAppleのデータセンターで保護されるため、Appleはデータとアカウントの復旧を支援できる
・「高度なデータ保護」では、大部分のiCloudのデータの暗号鍵にアクセスできるのはユーザ本人の信頼できるデバイスのみで、エンドツーエンドの暗号化によってデータが保護される
|
プラン
|
iCloud+ 50GB
|
iCloud+ 200GB
|
iCloud+ 2TB
|
iCloud+ 6TB
|
iCloud+ 12TB
|
|
月額料金
(税込)
|
130円
|
400円
|
1,300円
|
3,900円
|
7,900円
|
公式HP:iCloud Drive

以上、企業が導入の対象として検討できる有料のオンラインストレージをご紹介しました。あまりにもたくさんのサービスがあるため、何を基準にして選択したら良いか迷われる方も多いと思います。セキュリティが最重要ポイントであることは間違いありませんが、他にも比較ポイントがあります。一つずつ解説します。
料金プラン
以上の比較からもお分かりのように料金プランは基本的に「ユーザ」か「容量」に基づいて決定されます。「容量無制限」をうたっていても、「ユーザ」ごとの課金であれば企業規模によっては毎月の費用がかさんでしまいます。また、「ユーザ数無制限」をうたっていても、使用できる容量が不十分であれば、導入後も容量不足に悩まされることになるでしょう。
操作性
オンラインストレージを導入するにあたって操作が複雑だとITリテラシーの低い従業員に使ってもらえない可能性があります。また、操作方法を学ぶための研修を実施するなどして業務に支障をきたしかねません。
理想は専用のインターフェースなど必要とせず、普段使っているWindowsやMacのソフトと同じような感覚でデータのダウンロード、アップロード、共有ができるサービスです。
データ容量
「容量無制限」は魅力的ですが、「本当に必要か」どうか見極めなければなりません。例えば1TBであれば、1枚4MBの画像ファイルなら25万枚分、2時間のイベントをフルHDで撮影した動画83本分を保管できるほどの大きさです。それを超える「データ容量無制限」にコストをかける価値があるのか、慎重に考慮したいところです。自社が扱うデータ量、従業員数、事業拡大の可能性などを考えて必要十分なデータ容量を選ぶことをおすすめします。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
セキュリティ
前述したようにオンラインストレージが「インターネット上にあるからファイルサーバよりセキュリティリスクが高い」わけではありません。提供事業者のセキュリティ対策をチェックして、安心して自社のデータを預けられるか、「情報セキュリティポリシー」を策定しているならそれに則っているかも確認しておきましょう。
セキュリティに関してはデータセンターが国内なのか、国外なのか、国外ならどこなのかも重要です。なぜなら、各国によって保管するデータの扱い方について法律が異なります。国によってはテロなどの緊急事態が発生したら、裁判所の命令なしに強制的にデータを差押え、調査することが可能になります。
カスタマーサポート
いざというときのカスタマーサポートは心強い存在です。特にオンラインストレージを導入した企業はシステム障害が発生したときなどは自力での対処ができません。そのため、カスタマーサポートの充実度もチェックしたいポイントの一つといえるでしょう。カスタマーサポートの対応時間が24時間、365日だと安心です。また、カスタマーサポートの対応方法が電話、メール、チャットいずれかなのかも確認しておきましょう。
対応デバイス
いまやデータの共有はオフィス内だけでなく、在宅や出張先など様々です。特に取引先との商談にのぞむ前などにタブレットやスマートフォンで資料を閲覧できると便利です。また、スマートフォンやタブレットにオンラインストレージ内のファイルを操作するためのアプリをダウンロードする場合、その使い勝手も同時にチェックしておきましょう。
利用可能人数
オンラインストレージの中には、利用可能なユーザ数に上限があったり、利用人数を増やすと費用の増額が必要になる従量課金制を採用したりするサービスもあります。ユーザ数無制限が必ずしも良いわけではありません。大切なのは、自社の業種や従業員数に合わせて、身の丈にあったオンラインストレージを選ぶことといえるでしょう。
導入事例の有無
各サービスのホームページやパンフレットなどを見ると、導入事例が載せられています。一般的に、導入事例が多ければ多いほど信頼できる可能性が高いといえます。また、導入事例を見ることで、どんな業界や業種に選ばれているのか具体的なイメージを持てます。導入事例をチェックするときには、できるだけ自社と同じ業界であり、想定利用人数も近い企業を選ぶと良いでしょう。
.png)
「使えるファイル箱」は月額税込21,230円(スタンダードプラン、1年契約)で、ユーザ数無制限、容量も必要十分な1TB。例えば、100人で使えば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
セキュリティ機能を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランでも月額税込60,500円(1年契約)です。2要素認証やAES256ビット暗号化、ISO認証取得のデータセンター(長野県)など、気になるセキュリティ対策も万全です。
また、使えるファイル箱は電子帳簿保存法上の区分のうち、電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)に対応しています。電子データで保存することで書類の保管場所が最小限で済み、書類も整理しやすくなります。
低価格でファイルの保管、共有が可能なため、多くの中小企業にご利用いただいています。30日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひお気軽にお試しください。
使えるファイル箱の詳細はこちら>>
.jpg)
オンラインストレージの主な特徴は?
オンラインストレージの主な特徴は、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできる点です。そのため、近年多くの企業が導入しているテレワークにも適しています。また、自社でサーバなどの設備を準備する必要がないため、イニシャルコストを抑えられるのもオンラインストレージの特徴です。さらに、運用管理はオンラインストレージサービス提供会社が行ってくれるため、専門人材も必須ではありません。
オンラインストレージの容量を増やす方法とは?
オンラインストレージの容量を増やすためには、プランを変更しましょう。オンラインストレージを提供している事業者は、従業員数や企業規模に合わせたプランを複数準備しています。また、オンラインストレージを使っていると、ついついファイルの整理を怠ってしまうものです。ときにはストレージ内のファイルを見直し、余分なファイルを削除すれば、容量を増やせます。
オンラインストレージの基本的な使い方とは?
オンラインストレージの基本的な使い方は、情報の共有です。オンラインストレージにファイルを保管しておけば、社内外のユーザはさまざまな端末を使用してデータにアクセスできます。また、情報の閲覧のみならず、ストレージ内のファイルを複数のユーザで編集できるため、場所や時間にとらわれず同時に作業を進めることができ、生産性が向上します。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
いまや働き方の「ニューノーマル」としてすっかり定着したテレワーク。Web会議ツールやチャットツール、プロジェクト管理ツールなど、テレワーク導入前に準備すべきツールはたくさんあります。ただ中小企業の場合は、まず最初に「クラウドストレージ」を導入することをおすすめします。
今回の記事では、その理由と、クラウドストレージ導入のメリット・デメリット、自社に最適なクラウドストレージの選び方について解説します。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
法人向けクラウドストレージの比較を見たい方はこちら
目次
テレワークやサテライトオフィスを導入する際の課題
まず最初に導入すべきは「クラウドストレージ」
テレワークに欠かせないクラウドストレージとは
テレワークでクラウドストレージを導入するメリット
テレワークでクラウドストレージを導入するデメリット
テレワークに活用するクラウドストレージの選び方
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

テレワークやサテライトオフィスは、物理的なオフィスに人が集まって仕事をするのではなく、インターネットを経由したオンラインでのやりとりがメインになります。そのため、以下の2つの課題に直面します。
1. コミュニケーションにおける課題
2. セキュリティ面の課題
以下、それぞれについて説明します。
1. コミュニケーションにおける課題
オンラインで行うテレワークでは、以下のような課題があるといわれます。
・言葉にできない雰囲気や「空気」などいわゆる「暗黙知」を伝えにくい
・オフィスではできる雑談や、偶然出会った人との立ち話の機会がなくなり、アイディアやひらめきが生まれる機会が減る
・コミュニケーション効率が下がり、生産性も低下する
2. セキュリティ面の課題
オンラインを前提にしたテレワークの課題として頻繁に指摘されるのがセキュリティ面の課題です。
総務省が約8,200社を対象に、2021年12月~2022年1月に行った「テレワークセキュリティに関する調査」では、全体の51.6%がテレワークの導入にあたり「セキュリティの確保」が課題になったと回答しました。具体的に最も多かった取り組みは「マルウェア対策」(65%)であり、ほかにも「脆弱性管理」(53.4%)、「資産管理」(58.1%)などの回答がありました。
出典:「テレワークセキュリティに関する実態調査(R3年度)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000811683.pdf)

「クラウドストレージ」を最初に導入すべき理由は、上に挙げたテレワークの2つの課題に対応するためのソリューションとしてクラウドが効果的だからです。
以下、クラウドストレージとは何か、およびそれがどのようにコミュニケーションとセキュリティの問題を解決できるのかをご説明します。
クラウドストレージとは、インターネット上にデータを保存しておく記憶装置のことです。自社内に情報システムを構築し、サーバを運用する「オンプレミス」とは異なり、インターネットを経由する点が特徴です。
クラウドストレージの仕組み
クラウドストレージは記憶装置であるため、文書や動画、画像などさまざまなデータやファイルを保存できます。アクセス権限を持ったユーザなら、社内の従業員であれ、外部の取引先であれ、クラウドストレージの情報を閲覧したり、アップロード・ダウンロードしたりすることが可能です。
テレワークでのクラウドストレージの活用シーン
テレワークでクラウドストレージを活用すれば、複数のメンバーでプロジェクトを進めるときなどにも共同作業がしやすくなります。ユーザごとに権限を設定できるため、プロジェクトのメンバーには編集権限を与え、取引先からのアクセスは閲覧のみにすることなども可能です。
また、メールに添付するには容量が大きい動画ファイルなども、クラウドストレージがあれば簡単に他のユーザと共有できます。
【事例】株式会社トラステック:ファイル箱のメリットは「共同作業」がしやすいこと
オンラインストレージについて知りたい方はこちら
ファイルサーバのクラウド比較を見たい方はこちら
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら

テレワークでクラウドストレージを導入するメリットとして以下の5つについて説明します。
1. どこからでもファイルにアクセスできる
2. データのバックアップの役割もかねている
3. 社員同士や外部と連携が取りやすくなり業務効率が上がる
4. テレワークにむけた環境構築・整備の手間が省ける
5. データや機器の保守管理の負担が軽減される
以下、ひとつずつ説明します。
1. どこからでもファイルにアクセスできる
クラウドストレージはインターネット環境さえあれば、どこからでもファイルにアクセスできます。そのため、テレワークの実現はもちろん、温泉地や大自然の中のリゾート地で休暇中に時間の一部を仕事にあてる「ワーケーション」とも親和性があります。
2. データのバックアップの役割もかねている
クラウドストレージには業務に必要なあらゆるファイルやデータが集約されており、絶えず更新されています。ユーザが使用している端末からデータが失われても、クラウドストレージには残っているため、バックアップの役割もかねているといえるでしょう。
もっとも、クラウドストレージのデータそのものもサイバー攻撃や災害などで失われるリスクはゼロではないため、クラウドストレージを利用していてもバックアップサービスの利用は別途必要です。
3. 社員同士や外部と連携が取りやすくなり業務効率が上がる
クラウドストレージを導入すれば、社員同士だけでなく、社外の取引先とも連携が取りやすくなり、業務効率が上がります。
例えば、ファイルのやりとりをするにしても、メールに添付したり、USBメモリを使って渡したりするにはどうしても工数が増えてしまいます。その点、クラウドストレージでは指定のフォルダにマウスで「ドラッグ&ドロップ」すれば一瞬のうちに共有が完了します。
4. テレワークにむけた環境構築・整備の手間が省ける
クラウドストレージを使ったテレワーク環境構築・整備はオンプレミスよりも圧倒的にコスト削減になります。
なぜなら、テレワークを前提にオンプレミス環境を整備しようとすると、あらかじめ利用者数や通信量などを予測して容量を選択しなければならず、予測より実際の需要が大きければさらにシステムの追加などが必要になるからです。
クラウドストレージでは、予想外の需要が生じても容量やユーザの上限を自由に拡張できます。
5. データや機器の保守管理の負担が軽減される
クラウドストレージを導入して、テレワーク環境を整備すればデータや機器の保守管理の負担が軽減されます。なぜなら、クラウドストレージサービスの提供業者がそれらの作業を行ってくれるからです。
それに対して、テレワーク環境をオンプレミスを前提に構築しようとすると、保守管理のために自社で人的リソースを割かなければなりません。もし、トラブルが起きたら、解決するまで担当者はつきっきりで対応せざるを得ません。
参考:「テレワークセキュリティガイドライン第5版」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf)

他方、テレワークでクラウドストレージを導入するデメリットや注意点としては以下の2点があります。
1. 提供業者のセキュリティ対策レベル
2. サービスの利用料金
1. 提供業者のセキュリティ対策レベルに注意が必要
クラウドストレージを利用する際には提供業者のセキュリティ対策レベルが十分に高いことを確認しておく必要があります。
例えば、あるベンチャー系中小企業A社はクラウドストレージ提供業者のレンタルサーバにのみデータを保存していたところ、提供業者B社にシステム障害が発生しました。しばらくすると、「レンタルサーバに保管していた重要なデータが消えてしまっており、復旧できない」とB社から連絡がありました。
サービス規約では、データのバックアップや復旧は利用者の責任であることが明記されていたためなす術はなく、データ消失によりA社は多大の損害を被ってしまいました。
データ消失のリスクを完全になくすことはできないとしても、できるだけそれを減らすためにクラウドストレージの提供業者に関する情報収集を行い、比較検討することが不可欠です。
出典:「安心してインターネットを使うために 国民のためのサイバーセキュリティサイト」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_case_13.html)を加工して作成
2. 大手のクラウドストレージはサービスの利用料金が高いことも
提供業者によってサービスの仕組みや価格帯が異なるため、大手のクラウドストレージは利用料金が高いことも十分ありえます。「導入するなら大手が安心」と短絡的に考えるのではなく、「自社がテレワーク環境を導入するにあたってクラウドストレージに何を求めるのか」という観点から考えれば、必要以上にコストを払い続けることが避けられるでしょう。

ここでは、テレワークに活用するクラウドストレージの選び方を解説します。以下の4つのポイントを覚えておきましょう。
1. 容量と料金プランが自社に見合っているか
2. 必要な機能を満たしているか
3. ストレスを感じない操作感か
4. 万全なセキュリティ対策がされているか
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 容量と料金プランが自社に見合っているか
自社の業務に必要十分な容量を選ぶ
クラウドストレージの容量はさまざまです。「将来性のことを考えると容量無制限」を選びたくなるかもしれませんが、本当にそんなに必要でしょうか?
どのくらいの容量を選ぶかは、主に企業規模と業務内容によります。大企業で数千人のユーザがアクセスする場合と、10人程度の中小企業が使用するクラウドストレージには容量の違いがあってしかるべきです。
また、テキストファイルのやりとりが多い企業と、デザインや映像を扱う企業とでは、クラウドストレージに保存するデータ容量も異なります。
クラウドストレージはオンプレミスに比べて拡張性が高いため、導入時の容量で足りなくなった場合は自由に追加できることも覚えておきましょう。
自社の業務に見合った料金プランを選ぶ
クラウドストレージサービスの料金プランは、大きく分けてユーザ数に基づいて課金されるタイプと、容量に基づいて課金される従量課金タイプがあります。
中小企業では、そもそも従業員数が少ないため、ユーザ課金のほうがコストを抑えやすいでしょう。しかし、一定の容量を確保しつつも、将来の業務規模拡大に備えたい場合はユーザ数無制限で従量課金タイプがよいかもしれません。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
2. 必要な機能を満たしているか
テレワークを前提にクラウドストレージを導入する場合、必要な機能が備わっているかどうかも確認しましょう。例えば、以下のような機能をチェックしておくとよいでしょう。
・ユーザに合わせて権限設定を変えられるか
・共有ファイルのサイズ上限は無制限か
・スマホからも簡単にアクセスできるか
・ブラウザ上でOfficeファイルを編集できるか
クラウドストレージを導入したものの、必要な機能が備わっておらず、結局使われなければ本末転倒です。
3. ストレスを感じない操作感か
ストレスを感じない操作感かどうかもポイントです。いくら万全のセキュリティ対策がされており、テレワークに必要な機能が備わっていても、操作性が普段使っているOSと大きく乖離するようなら、やはり社内で普及は難しいでしょう。
4. 万全なセキュリティ対策がされているか
クラウドストレージを導入する場合、提供業者に企業の重要情報を委託することになります。そのため、提供業者側に万全のセキュリティ対策がされているかは十分な調査が不可欠です。
もっとも、近年は総務省「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」において提唱されている「ゼロトラストモデル」が情報セキュリティにおいては主流になっています。「ゼロトラスト」とは、企業の情報に関与するものは内外問わずすべて「信頼しない」という考え方です。
つまり、「完璧な情報セキュリティ」も、「100%信頼できるクラウドストレージ提供業者」も存在しないという前提で、企業側が主体的かつ積極的にセキュリティ対策を行うべき点は忘れないようにしましょう。
参考:「テレワークセキュリティガイドライン第5版」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf)

成長期の中小企業がテレワークを導入する際におすすめなのが「使えるファイル箱」です。ポイントは以下の3つ。順を追って説明します。
1. ユーザ数無制限
2. 使いやすい操作性
3. 安心のセキュリティ対策
1. ユーザ数無制限!成長期の会社でも追加費用がかさまない
使えるファイル箱は、ユーザ数が100人でも、1,000人でも料金は一律です。成長期の中小企業では、従業員数が急激に増加する可能性もありますが、その場合でもユーザ課金や権限発行に悩むことはなく、追加費用はかさみません。
2. 普段のパソコンと同じような操作で使えるので講習の必要なし
使えるファイル箱は、専用のインターフェイスを必要としません。WindowsならExploler、MacならFinderで共有フォルダを扱うため、テレワーカーも含めて普段の使い慣れた方法で操作できます。いつもと同じようにデータのアップロード、ダウンロード、共有が可能です。
3. 安心のセキュリティ対策で大事な情報を守る
使えるファイル箱なら、セキュリティ対策も万全です。その中には以下のようなものがあります。安心のセキュリティ対策の一部をご紹介します。
.png)
使えるファイル箱の利用料金は、容量1TB、ユーザ数無制限で月単価18,480円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策をさらに強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価52,624円(税込、1年契約)です。
使えるねっとは、年間契約新規ご契約者の方を対象に最初1年間、プランの契約をいつでも解除可能とし、その場合の全額返金を保証いたします。これにより、使えるファイル箱が本当に満足できるサービスかどうかを、実際に1年間使ってみて、じっくり見定めていただけます。
使えるファイル箱の詳細はこちら>>
(1).jpg)
(1)無料のクラウドサービスにはリスクはある?
A:有料のクラウドサービスと比べると、セキュリティ面での心配があることは否めません。 サイバー攻撃やデータ消失のリスクを減らすために、企業での利用なら無料トライアル後の有料プランに切り替えるのがベストでしょう。
(2)ツールのセキュリティ対策だけでは不安…他の対策方法は?
A:大きく分けて「ルールの整備」と「技術的なセキュリティ対策」があります。「ルールの整備」には、テレワーカーを含めたセキュリティガイドラインの作成が、「技術的なセキュリティ対策」には、データ暗号化や、安全な回線の使用、ウイルス対策ソフトの導入などが含まれます。
(3)テレワークにおすすめの他のクラウドサービスは?
A:例えば以下のようなツールがあります。
1. Web会議システム:テレワークの定番ツール
2. ビジネスチャット:コミュニケーション課題を解決
3. グループウェア:業務で必要なアプリを集約
4. プロジェクト管理ツール:時間管理を効率よく
5. クラウド勤怠管理システム:労務管理を確実に
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
6月に入り、国内では県境を越える移動自粛が解除され、ヨーロッパでは国境を徐々に開放する動きも出てきました。一時期に比べれば、世の中は少しずつ正常化に向かっているようにも見えます。
しかしこの未曾有の危機を経た今、これからパンデミックが収束しても「すっかり元通り」にはなりそうもないものがひとつあります。それは私たちの”働き方”です。
アフターコロナの働き方を決定づける3つのキーワード
新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業が初めてのテレワークを経験しました。今後は通常勤務に切り替えるところが増えそうですが、それでも多くの経営者は「これからの時代、コロナ前に全部元通りというわけにはいかない」と考えています。
生産性やワークライフバランスがより重視されるアフターコロナの時代の働き方で、鍵となるのが「コラボレーション」「フレキシビリティ」「セキュリティ」という3つのキーワードです。
■コラボレーション
他企業との協業やフリーランサーの活用によってイノベーションを加速させることが、今後はもっと一般的になるでしょう。企業という枠を越えたコラボレーションは、新たな価値と利益を最短で生み出す効率的な方法です。
■フレキシビリティ
今回のコロナ禍で、「テレワークでも意外と仕事はできる」ことに気づいた人は多いはず。これからは大企業のみならず中小企業でも、従業員の事情やライフスタイルに合わせたフレキシブルな働き方をある程度認めることが主流になるでしょう。
■セキュリティ
上記のコラボレーションとフレキシビリティを推進する上で不可欠なのが情報セキュリティ強化です。「最低限の対策はしておく」という消極的な姿勢ではなく、「より高度で最新のセキュリティ対策を常に追求していく」という積極的なマインドが求められます。
アフターコロナ時代はクラウドストレージ導入が当たり前に?
社外とのコラボレーションを強化したり、フレキシブルな働き方を推進したりするには、ファイルのやり取りをスムーズかつセキュアに行える環境作りが大切です。しかしメール添付がメインとなる従来のやり方では、プロジェクトマネジメントやファイルバージョン管理が煩雑になってしまいます。
そこで今急速に利用が広がっているのが、クラウドストレージです。クラウドストレージなら必要な人が必要なときに簡単にファイルをダウンロード・アップロードできますし、クラウド上のファイルは常に最新版に更新されるため面倒なバージョン管理も不要。自社でファイルサーバを運用する手間やコストもかかりません。
「使えるファイル箱」を選択する理由
使えるねっとが提供するクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」は、全国で多くの企業・団体・教育機関様にご利用いただいています。使えるファイル箱が支持を集める理由をまとめてみました。
■「コラボレーション」をもっと簡単・スムーズに
社内外のチーム作業に最適な共有フォルダ作成、手軽にファイルを送受信できるWebリンク共有など、コラボレーションをスムーズにする機能が満載。誰でもすぐに使えるシンプルなインターフェイスも魅力です。
■働き方の「フレキシビリティ」と多様性を迅速に実現
使えるファイル箱は、テレワークでのファイルやり取りにぴったりです。いつでもどこでも、デバイスさえあればすぐにそこがテレワークオフィスに。公式アプリで、iPhone・iPad・Androidデバイスからもアクセスできます。
■最高水準の「セキュリティ」と充実サポートで安心
SSL通信に加え、シークレットキーによる2重暗号化を実現。ファイル・フォルダごとのアクセス権限設定や、アクセスデバイス・ログイン履歴の確認も簡単にできます。経験豊富な自社専属スタッフによるカスタマーサポートも好評です。
アフターコロナの時代に備える攻めの投資として、ぜひ「使えるファイル箱」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。14日間の無料お試しも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
使えるファイル箱のサービス詳細
お問い合わせフォーム







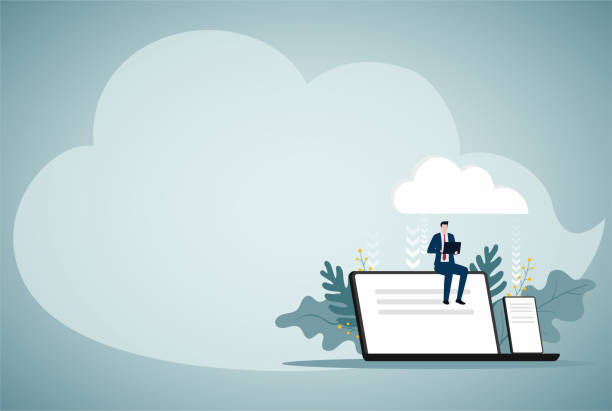





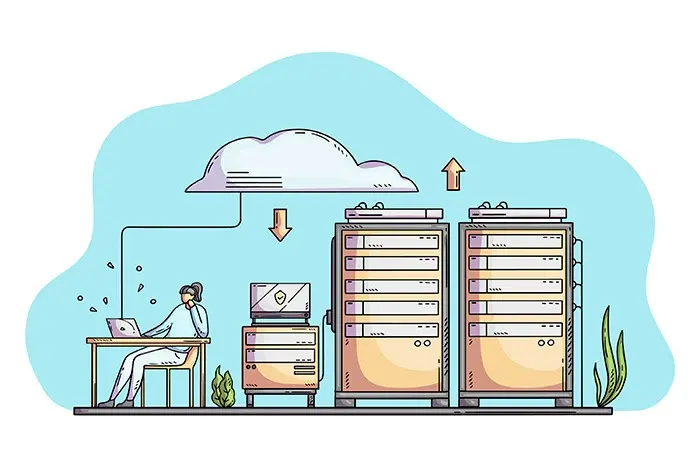


.png)
.jpg)
.jpg)

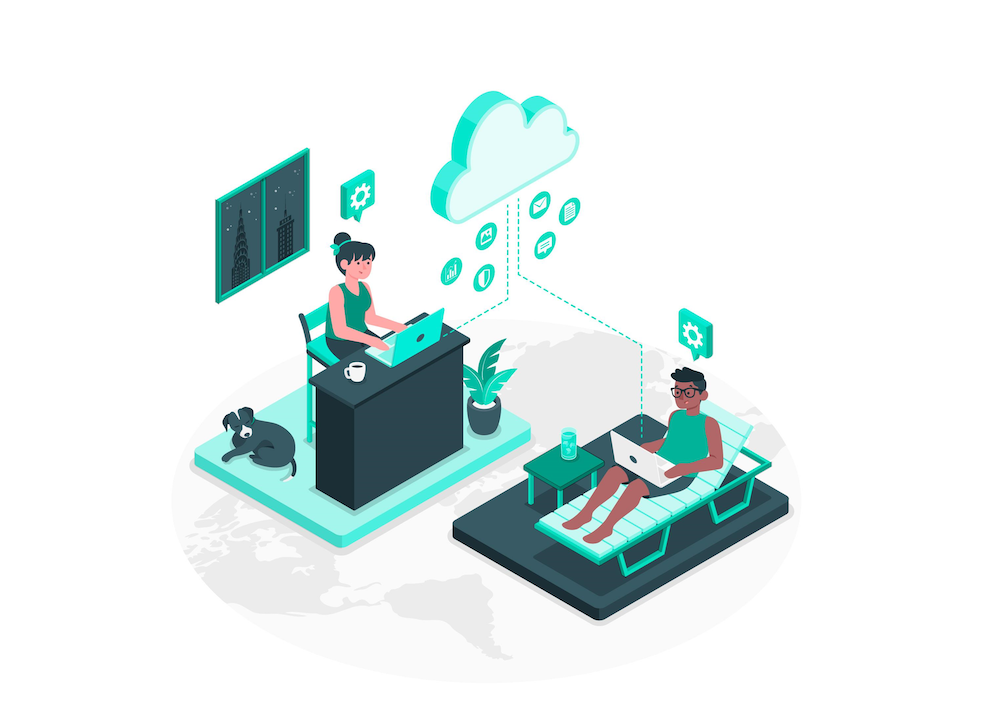


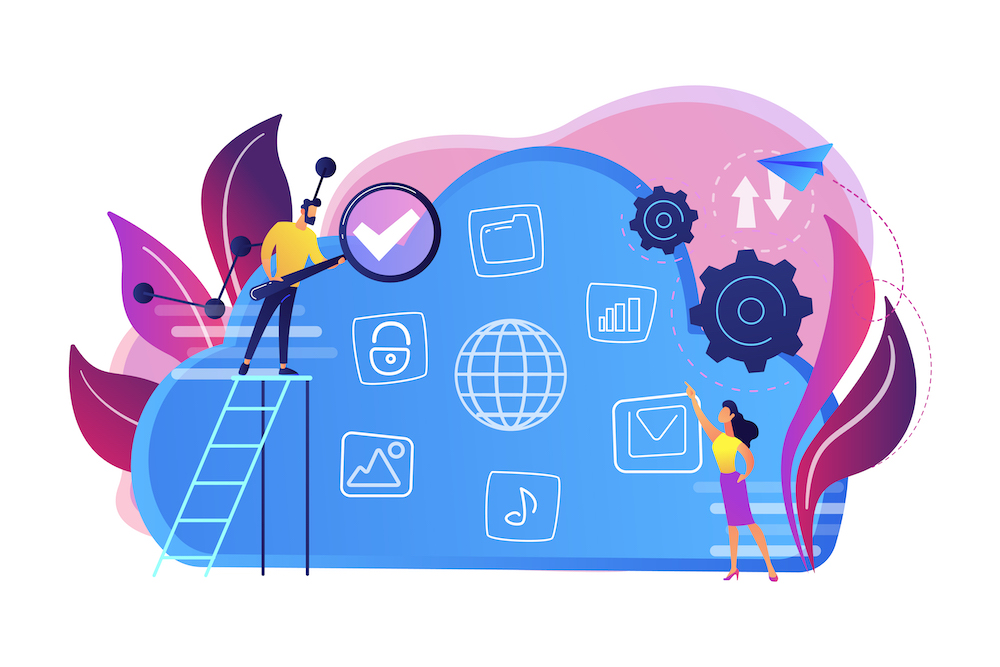

.jpg)
.jpg)


.png)





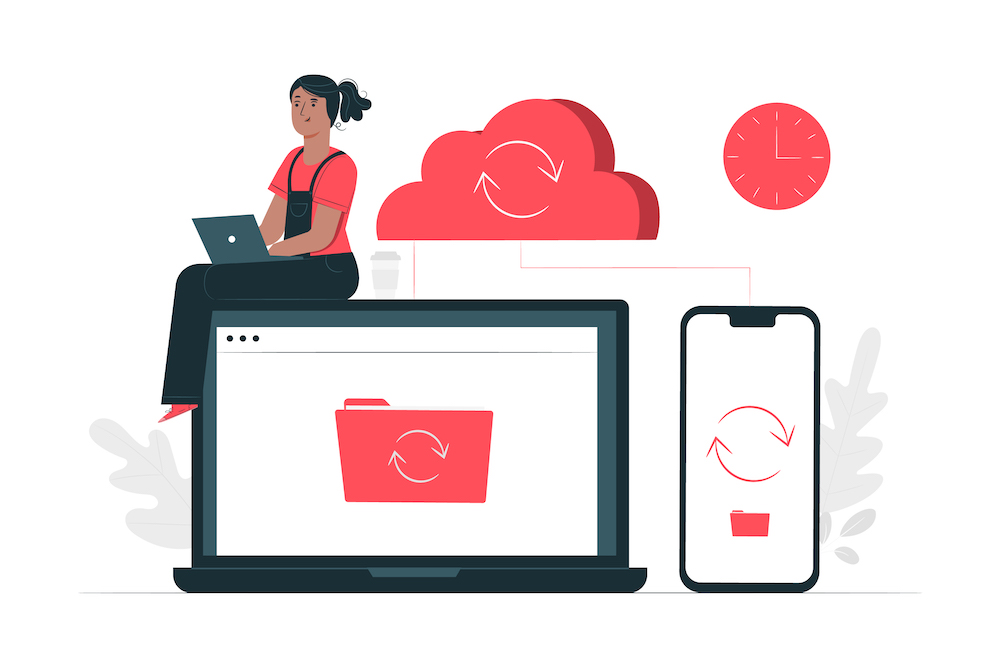

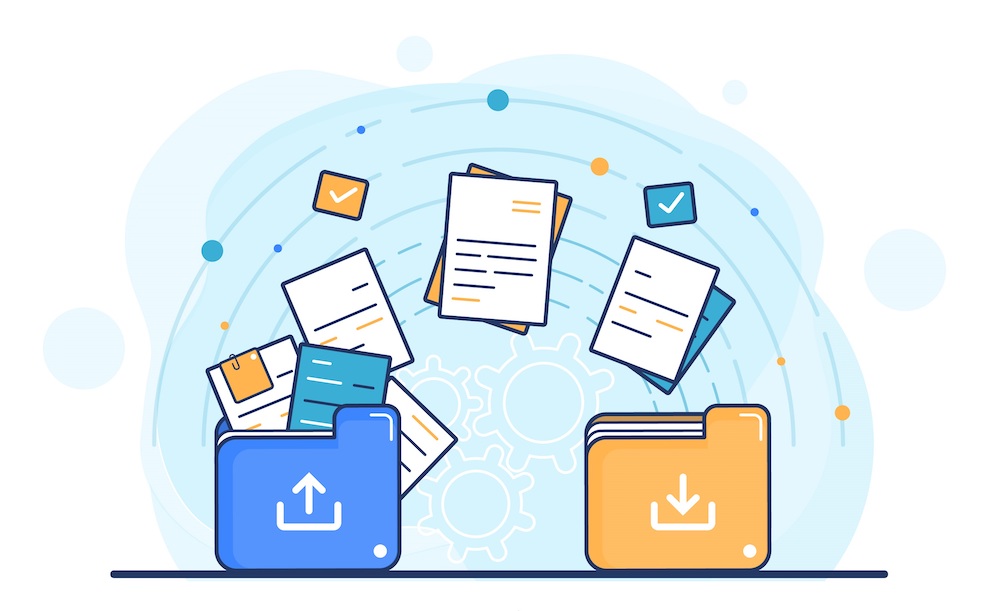
.png)
.jpg)
.jpg)




.jpg)



.png)
.jpg)
.jpg)





.png)
(1).jpg)
.jpg)
