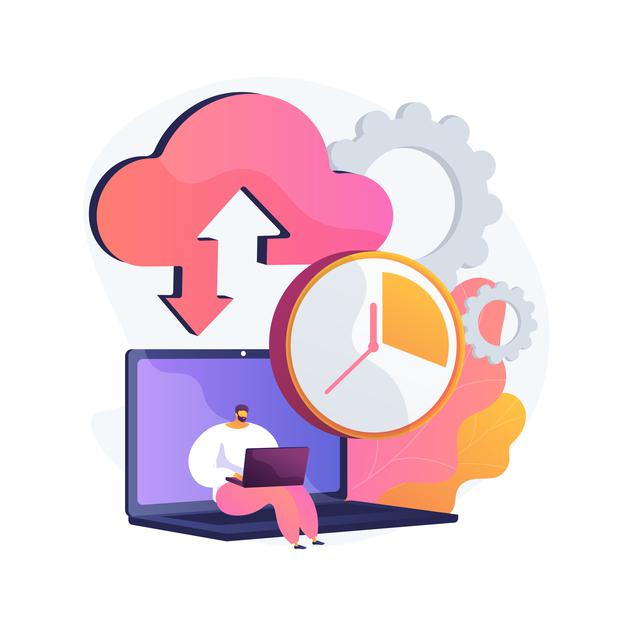ウェブサイトの運用などに欠かせないのがレンタルサーバです。サーバ選びは、ウェブサイトの安定稼働のためにとても大切。しかしレンタルサーバの選択肢は多く、どれにすればいいのか迷ってしまいがちです。
そこでこの記事では、レンタルサーバを選ぶときに確認したい項目や、レンタルサーバの上手な選び方のコツなどについてご紹介します。
レンタルサーバとは
ウェブサイトを作ってインターネットで公開するには、「サーバ」と呼ばれるスペースが必要です。サーバはいわば、ウェブサイトに必要な要素やファイル(テキスト、画像、動画など)を置いておくための場所になります。
サーバは会社や個人で物理的な機器をセッティングして用意することもできますが、この場合サーバの構築やメンテナス、トラブル発生時の対応などをすべて自前で行わなければなりません。そこで多くの企業で利用されているのが、「レンタルサーバ」です。レンタルサーバのサービスを契約すると、サービス提供会社が管理するサーバをレンタルできるようになり、自社で物理サーバを用意する必要がなくなります。
レンタルサーバを選ぶ前にチェックしておきたいこと
法人向けレンタルサーバのサービスはたくさんあり、その中から自社にあったものを選ぶのは大変な作業です。そこでレンタルサーバを選ぶ際は、事前に自分のニーズや重視するポイントを明確にしておくことが大切になります。
予想されるアクセス量
運営するウェブサイトのアクセス量がどれくらいになるのか、大体の予想を立てておきましょう。それによって、スペックをどれだけ重視すべきなのかが変わってきます。予想されるアクセス量に対してサーバのスペックや対応転送量が足りないと、エラーが発生してしまいます。
重視する項目と予算
レンタルサーバを選ぶにあたって、自分のニーズに照らし合わせて、何を重視するのか明確にしておきましょう。そうすることで、似たような選択肢で迷ったときに、事前に決めておいたプライオリティに基づいて適切なサーバを選べます。また、あらかじめ使える予算をはっきりさせておくことも大事です。
_2.jpg)
法人向けレンタルサーバの選び方
それではここからは、法人向けレンタルサーバの選び方のポイントをご紹介します。レンタルサーバの新規契約を考えている方や、レンタルサーバの乗り換えをご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
種類|メリットが異なる 3 タイプ
レンタルサーバには、主に「共有サーバ」「VPS」「専用サーバ」という 3 つの種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットをはじめに押さえておきましょう。
共有サーバは、ひとつの物理サーバを複数ユーザが共同使用するサービス。価格が一番安く、 シンプルな利用(サイト運用やメールアカウント管理など)を希望する方にとても人気です。 一方でカスタマイズなど独自設定の自由度はやや低く、他のユーザの影響を受ける場合もあります。
住宅に例えるならば、共有サーバは「シェアハウス」。個々に部屋はありますが、キッチン、お風呂などは共有するシェアハウスのイメージです。大家さん(使えるねっと)が共用部分を管理、借主は自分の部屋の中を管理します。共用部分は決められているスペックで運用をし、その分管理には手間をかけたくない方におすすめです。
おすすめ:個人サイト、小規模ウェブサイトなど
【メリット】
・ コストが低く安価
・ 専門知識不要で、気軽に始められる
・ サービス事業者がメンテナンスなどをしてくれる
【デメリット】
・ 他のユーザの使用状況による影響を受けやすい
・ 詳細なカスタマイズができない
・ 性能はやや低めのことが多い
VPS は、一台の物理サーバをユーザごとに「仮想化技術」で実質的に分割して提供されているサービスです。仮想化技術を取り入れたことによって、一台の物理サーバの中に複数の「仮想サーバ」を作ることが可能になり、その上にそれぞれ独立した環境(個別のメモリ、ディスク、ソフトウェアなど)を乗せることが実現しました。各仮想サーバは独立しているの
で、互いの影響を受けることはほとんどありません。
VPS は、例えるなら「マンション」。スペックが高く自由度もあるのに価格はお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。
共有サーバとの違いは「管理者権限が借主にある」ということです。マンション内のリフォーム(OS 変更、アプリケーションの構築など)のカスタマイズが可能です。ただし運用に関する知識は必要になります。共有サーバと専用サーバのいいとこどりをしているので、法人の方におすすめです。
【メリット】
・ 管理者権限を持てるので、細かいカスタマイズが可能
・ OS や CPU などのスペックを選べる
・ 他のユーザからの影響を受けずに済む
【デメリット】
・ サーバに関するある程度の知識が必要
・ 専用サーバほどの拡張性はないことも
ひとつの物理サーバを専用契約して、そのサーバを自由に自分だけで使えるサービスです。自由度も安定性も一番高いですが、その分コストはややかさみます。
専用サーバは、物理サーバを丸ごと管理することができるので、まさに「一戸建て」のイメージです。高性能で安定性、拡張度も高く、自分の好きなようにカスタマイズすることが可能です。もちろん他ユーザの影響もありません。ただしコストはやや高く、運用には専門的な知識も必要になってくるため、上級者向けになります。
【メリット】
・ 高性能なサーバを自分専用のものとして所有できる
・ 自分好みに自由にカスタマイズできる
・ 他のユーザからの影響を受けることがない
【デメリット】
・ 値段はやや高め
・ 専門知識が必要
スペック|CPU やメモリの数値に注目
サーバのスペックによって、サイトにアクセスしたときの速度やレスポンスに違いがあります。特に「CPU」と「メモリ」の数値に注目してみると良いでしょう。いずれも数値が大きいほうが性能が優れていることになります。また、当然ですがディスク容量にも気をつけましょう。ディスク容量はある程度余裕を持って見積もることをおすすめします。
ネットワーク回線|速度と転送量は要チェック
レンタルサーバによってネットワーク回線の強さも異なります。サイトへの予想アクセス量が多めの場合は、このネットワーク回線の速度にも注目してサーバを選びましょう。さらに、一部のレンタルサーバでは転送量の制限(「1 ヶ月○○GB まで」など)があるので、注意が必要です。
自動バックアップサービス|ビジネス用途ならほぼ必須
万が一のために、自動バックアップサービスが用意されていると安心です。自動バックアップサービスがついていれば、間違ってサイトに必要なファイルを消してしまっても、すぐに復元することができます。ビジネス用途でレンタルサーバを使うなら、ほぼ必須の機能だと言えるかもしれません。
サポート体制|レンタルサーバ選びの盲点
レンタルサーバ選びで意外と見逃しがちなのが、サポート体制の充実度です。トラブルが発生したときや、分からないことが出てきたときなど、サポート体制が充実していると安心してサーバを利用できます。電話、メール、チャットなど、連絡チャネルが多く用意されているところだと便利ですね。
法人向けレンタルサーバのおすすめは?
レンタルサーバ選びで迷ったら、全国で多くの企業や団体に採用されている「使えるねっと」のサーバがおすすめ。特に使えるねっとのクラウド VPS は、お手頃な価格と使い勝手の良さ、それに充実のサポート体制が評判の人気サービスです。個人から法人まで多様な用途に対応する豊富なプランも人気の理由のひとつとなっています。
「使えるクラウド VPS」でストレスフリーなサイト運営
現在「使えるクラウド VPS」では、利用料金が最大 50%OFF になる超お得なキャンペーンを実施中。さらに 1 年契約以上でご契約いただくと、なんと初期費用が無料になります。キャンペーンは 2021 年 4 月 28 日までの期間限定ですので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
「使えるクラウド VPS」の詳細はこちら
.jpg)
無料通話:0120-961-166
(営業時間:10:00-17:00)
最近よく聞く「クラウドストレージ」という言葉。「便利そうなのはわかるけど、具体的に何の役に立つのかいまいちイメージできない」という方は結構多いのではないでしょうか?
そこで今日は、「クラウドストレージ」の基礎や使い道などについて、初歩から解説していきたいと思います。じつはクラウドストレージは、ファイル共有や共同作業から経理データ管理まで、多様な使い方ができるとっても便利なツールなんですよ!
クラウドストレージとは?
クラウドストレージとは、「クラウドにデータを保存できるファイル置き場」のこと。
仕事で使う業務ファイルやフォルダを会社のパソコンに保存する場合、ファイルの保管先は「パソコンのハードディスク」です。
一方クラウドストレージの場合、このファイルの保管先が「クラウド」になります。(同じデータをパソコンのローカルディスクに保存することも可能)。クラウドというのは、インターネット経由で接続する保管場所のことです。
クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら
法人がクラウドストレージを使うメリットとデメリット
「なんでわざわざクラウドに保管する必要があるの?」と思われるかもしれませんが、ファイルやフォルダを「クラウド」に保存することには、以下のようなメリットがあります。
- 保管先のクラウドにはインターネット経由でアクセスできるから、パソコンだけではなくスマートフォンからでも書類をチェックできる
- 年月とともにデータがどんどん増えていっても、クラウドの容量をプラン変更で増やせば、いくらでも保管できる! パソコンの買い換えやハードディスクの増設などは一切不要なので低コストで運用ができる
- クラウドストレージ上のファイルは、保存した変更がリアルタイムで反映されるから、同僚や取引先との共同作業が効率的に
つまりクラウドストレージを使うと、「社内外との共同作業やコラボレーションがスムーズになる!」「いつでもどこでも書類をチェックしたり修正したりできる!」といった便利さや快適さなどが手に入るというわけです。
また、クラウドストレージは、「社外からでもファイルにアクセスできる」から、昨今普及した「テレワーク」との相性も抜群。働き方改革推進のためのソリューションとしても最適です。
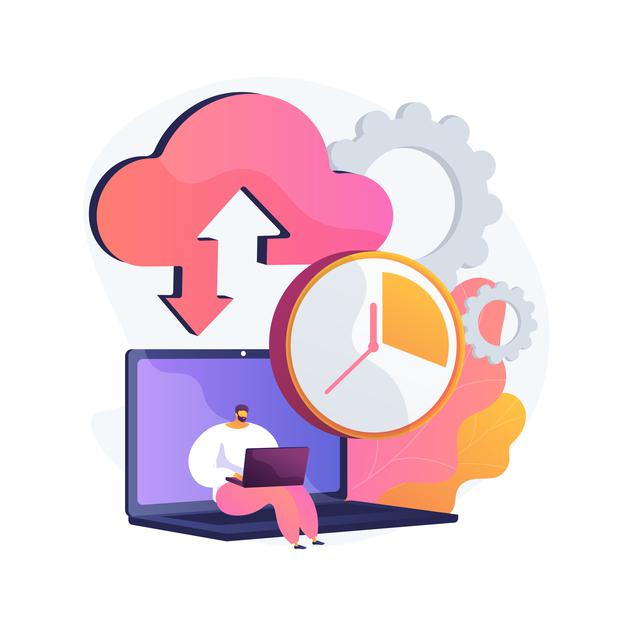
一方クラウドストレージのデメリットとしては、以下のような点がよく指摘されます。
1. オフラインだとファイルの同期ができない(→安定的なインターネット回線が必要)
2. 新しいサービスを導入することにより、社員へ使い方やマニュアル利用の指導に手がかかる
3. 社外からのファイルアクセスなどの利便性がある反面、セキュリティ対応も慎重に見当する必要がある
クラウドストレージの導入を検討する際は、こうしたメリットとデメリットを両方踏まえた上で、一度トライアル期間を設けて実際にサービスの使い心地を試してみることをおすすめします。
使えるねっとが提供するオンラインストレージサービス「使えるファイル箱」では、上記のデメリットを防ぐために下記の機能が備わっています。
1. オフラインでもファイルが閲覧できるように、ファイルごとに「常時同期」の設定が可能
2. windowsならエクスプローラー、MacOSならFinderからファイルのアップロード、ダウンロードリンク、共有リンクの作成ができるので、必要手順は保存フォルダをCドライブからUドライブに変更するだけ
3. 2要素認証、AES256ビット暗号化、監査レポート、ログ監視、遠隔データ削除を始めとしたセキュリティ機能が備わっているので安心して利用できる
経理データの管理にクラウド活用
ところで、ビジネスをしている人や個人事業主などの人にとって、特に頭を悩まされるのが税金や経理関連の手続き・管理ですよね。仕組みも複雑ですし、必要な書類も多いので、普段はついつい後回しにしてしまいがちな部分でもあります。
しかしもちろん、複雑だからと言ってこうした作業から逃れることはできません。さらに、帳簿などの書類は一定期間の保存が義務付けられているため、作業後もきちんと管理することが必要になります。後で何かあったときにすぐに的確な書類を取り出せるよう、分かりやすく整理しておくのも大切です。
とは言え、経理書類の管理は、労力もかかりますし、なかなか簡単なことではありませんよね。そこでおすすめなのが、紙の書類と並行して、クラウドでも経理データを管理する方法です。

経理データを効率的に管理するクラウド活用術
ここでは、経理関連の情報を効率的に管理するためのクラウド活用術について、具体的に紹介します! 経理データの管理・保管にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1. 社内共有で経理データを効率的に作成
最近では、オンラインで会計管理をできるソフトウェアの普及が進んでいるので、普段そういったツールを使用している人もいるのではないかと思います。しかし一方で、PDFファイルやExcelファイルなどといった、どんなソフトでも開けるような一般的なファイル形式でデータを作成・管理しなければならない場面もまだまだ多いはず。
そうしたときにおすすめなのが、経理データのファイルを、クラウドストレージに置いておくという運用方法です。クラウドストレージに経理データを保管しておくことで、複数の経理担当者によるファイルの作成や更新、変更などが常に一箇所にまとめられ、自動で同期されます。チーム全員が常に最新のデータをリアルタイムで共有できるため、連携不足による行き違いや、煩雑なバージョン管理などといった問題が発生しません。
2. テレワークでも経理事務をスムーズに
昨今のコロナ禍によって、テレワークを導入しているという企業様も多いことでしょう。ただ、テレワークには「業務データをどうやって持ち出し、管理するのか」「チームによる円滑な共同作業をどうやって実現するのか」などといった様々な課題もあります。
クラウドストレージは、こうしたテレワークの課題を解決するのに最適なツール。業務・経理事務に必要なファイルやフォルダをすべてクラウドストレージで管理するようにすれば、社員の自宅などから、複雑な手続きを経ることなくデータにアクセスできるように。チームでファイルを共同編集したりする際も、特別な設定をする必要なく簡単にリアルタイムの共同作業が実現します。
3. 会計事務所や税理士との書類共有も楽々
経理のお仕事では、社内外の税理士や、会計事務所などと書類をやり取りする機会もあると思います。多くの法人向けクラウドストレージサービスには、ファイルを安全に共有できる機能が付属しているので、これを活用すればそうした書類共有が楽々。作成した共有リンクを送るだけで簡単にファイルをシェアできるため、毎回ファイルを暗号化してメール添付したりする手間が不要になります。
関連記事:PPAPを今すぐ廃止するべき5つの理由|「パスワード付きzipをメール添付」はなぜ危険?
「使えるファイル箱」なら低コストで使いやすい
初心者でも使いやすく、また低コストで導入しやすいクラウドストレージとして今人気なのが、使えるねっとの「使えるファイル箱」です。ユーザー数無制限で1TBの大容量を自由に使うことができます。無料トライアル制度もご用意しているので、お金をかけずに使い勝手を体験することも可能です。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>



_2.jpg)
.jpg)