令和5年の情報通信白書によると、世界のパブリッククラウドサービス市場は2021年に45兆621億円となり、前年比28.6%増加しました。日本のパブリッククラウドサービス市場も2022年に前年比29.8%増の2兆1,594億円に達しており、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるために今後どの企業もクラウドストレージをますます活用し、ICT基盤を強化していくことが予測されます。
今やビジネスに欠かせない存在となったクラウドストレージですが、自社にとって最適なサービスを選ぶのは至難の業です。ここでは、クラウドストレージの基本をおさらいし、クラウドストレージを比較するポイントをご紹介します。また、中小企業、個人事業主にぴったりのクラウドストレージサービスをおすすめします。
目次
クラウドストレージの特徴
法人・個人のクラウドストレージの上手な活用例
最適なクラウドストレージが見つかる6つの比較ポイント
無料ストレージと有料ストレージ、どちらを選ぶべき?
【法人・個人】「無料版の容量サイズが大きい」クラウドストレージ2選
【法人】「機能性重視」のおすすめクラウドストレージ9選
どのクラウドストレージを選ぼうか迷ったら
クラウドストレージの5つのメリット
クラウドストレージを活用・導入する際に注意すべきポイント
クラウドストレージを比較する際によくある質問
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

クラウドストレージとは?
クラウドストレージ(cloud storage)とは、インターネットを通じてアクセスする保管場所(データセンター)にデータを保存したり、転送・共有したりできるストレージサービスです。「オンラインストレージ」や「ファイルストレージ」と呼ばれることもあります。
クラウドストレージには以下のような特徴があります。
特徴1. いつでも、どこからでもアクセスできる
クラウドストレージはインターネットを通じてデータにアクセスするため、ネット環境さえあればどこからでもアクセスできます。スマートフォンやタブレットからでも利用できるため、出張先や営業先からでもストレージ上のデータをチェック可能です。そのため、コロナ禍での在宅ワークやテレワークの導入に伴い、その利用は増加しました。
日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とITRが国内企業1,022社を対象に2023年1月に実施した「企業IT利活用動向調査2023」によると、「大半はクラウドサービスを使っている」と回答した企業の合計は2022年1月の18.2%から23.8%に上昇しました。「一部クラウドサービスを使っている」と回答した企業を含めると、全体の約9割がなんらかの形でクラウドサービスを利用していることになります。
これらの調査結果からも、いつでもどこからでもアクセスできるクラウドストレージがテレワーク促進に貢献したことが分かります。

出典:日本情報経済社会推進協会「JIPDEC IT-Report2023 Spring」
特徴2. 必要に合わせて容量を調整可能
クラウドストレージは容量を増やしたり、減らしたりすることが可能です。一般的に容量の大きさと料金は比例するため、自社がクラウドにかけられるコストを必要に応じて調整できるのです。
例えば、従業員数の少ない中小企業がクラウドストレージを導入する場合、まず少な目の容量でコストを抑えておいて、業務規模の拡大や従業員数の増加に合わせて、徐々に増やしていくことができます。こうした柔軟な運用がクラウドストレージの特徴の1つです。
特徴3. 保守・点検が不要
クラウドストレージは自社で保守・点検を行う必要がありません。クラウドストレージの提供事業会社に在籍する専門家が保守・点検を行ってくれるため、自社のリソースを節約できます。もちろん、保守・点検が不十分であれば、重大なセキュリティインシデントにつながるため、サービスを選ぶ際には慎重に選択することが重要です。
クラウドストレージの主な機能
一般的にクラウドストレージは以下のような3つの機能を備えています。
機能1. 自動バックアップ
クラウドストレージは定期的に自動バックアップを行う機能を備えています。そのため、システム障害が発生したり、災害などで機器が破損したりしても、中にあるデータは保護されます。
バックアップを行わないとさまざまなリスクにつながります。例えば、トラブルが発生したときにシステムの復旧が行えず、業務取引や顧客との連絡が途絶えてしまう可能性があります。その結果、経済的損失が生じるばかりか、社会的信用を失うことにもなりかねません。さらに、コンプライアンス違反を指摘されたり、損害賠償を請求されたりすることも考えられます。
企業が保有するデータの量と重要性は日に日に高まっているため、クラウドストレージの自動バックアップは非常に心強い機能だといえるでしょう。
機能2. ファイル転送
クラウドストレージを使えば、サイズが大きいファイルを転送することも簡単です。
メールではサイズが大きすぎて送れないし、以前のようにフラッシュメモリを使って社内でやりとりするのはセキュリティ面で不安です。しかし、クラウドストレージなら、ファイルをオンラインストレージにアップロードし、相手にダウンロードURLをメールなどで連絡するだけで大きなデータのやりとりもスムーズに行えます。
ユーザとして登録しておけば、取引先など社外の人もデータのアップロード、ダウンロードを行うことができます。
機能3. ファイル共有
クラウドストレージにはファイル共有機能もあります。
ファイル共有機能を使うことで、オンラインストレージにアップロードされたファイルを複数人で閲覧したり、編集したりできます。チームメンバーすべてがオフィスに集まらなくても、クラウドストレージを使えば、在宅で業務をしている人も外出先でスマホでアクセスしている人も含めて、ストレスなく共同作業が可能です。
もちろん、管理者はファイルの閲覧や編集に関して制限を設けることができるため、部外者が社内や部署内の機密情報にアクセスすることはできません。
以上のような特徴や機能を前提にすると、クラウドストレージとオンプレミスには以下のような違いがあります。
クラウドストレージとオンプレミスの違い
違い1. データの保管場所
クラウドストレージは、インターネットを通じてアクセスする「クラウドサービス事業者のデータセンター」にデータを保管します。それに対して、オンプレミスは自社のサーバ内でデータを管理します。
違い2. 導入期間
クラウドストレージは、クラウドサービス事業者が提供するサービスであるため、データ保管のための環境はすでに構築されています。そのためすぐに導入できます。
それに対して、オンプレミスは自社の環境に最適化したシステムを一から構築しなければならないため、ハードウェアを購入・設定しなければなりません。導入を決定してから、実際にシステムを使えるようになるまで何か月もかかる場合も少なくありません。
違い3. コスト
クラウドストレージには、クラウドサービスを提供する事業者に対して利用する対価を支払います。初期費用はさほどかかりませんが、一般的に毎月、毎年ペースで利用料を払い続けるため、利用期間が長ければ長いほどコストが増大する可能性があります。
それに対して、オンプレミスの場合、前述したように導入する際に機器の購入やシステム設定が必要なため高額なイニシャルコストが発生します。ただ、いったん導入しさえすれば、あとは社内の担当部署の保守・点検のみで十分です。
違い4. 拡張性
クラウドストレージは、サービス提供事業者に対してプランの変更さえすれば、ストレージの容量を増やせます。
それに対して、オンプレミスの場合、新たなファイルサーバを購入し、再度設定しなければならず、拡張する上では手間がかかります。
参考:NTT東日本 「オンプレミスとは?意味やクラウドとの比較までわかりやすく解説」
オンプレミスについて知りたい方はこちら

法人・個人かかわりなく、クラウドストレージはサイズが大きいファイルの転送や共有をするために効果的なツールです。
法人に絞るとすれば、オンプレミスの負荷軽減のためにクラウドストレージを活用することもできます。全社が保有するデータやシステムをすべてオンプレミスだけに依存させると、アクセスが集中してシステムダウンが起きる可能性が高くなります。そうなると、システム復旧まで業務が停止してしまいます。
こうした事態を避けるために日常的にはクラウドストレージを使用し、もしもの場合に備えて重要なデータをオンプレミスに保管するのも1つの方法です。
クラウドストレージのメリットや上手な活用方法については後述します。
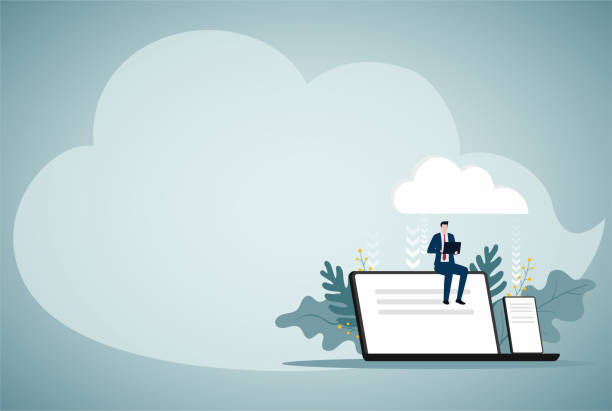
クラウドストレージのニーズが高まるにつれ、どんどん新しいサービスが登場しています。たくさんある中から最適なクラウドストレージを選ぶのは至難の業です。
ここでは、ぴったりのクラウドストレージを見つけるための6つの比較ポイントを紹介します。
1. 必要なデータ量を保存できるか
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
6. ストレスを感じない操作感か
1. 必要なデータ量を保存できるか
最適なクラウドストレージを選ぶ1つ目のポイントは、必要なデータ量を保存できるかという点です。
どのくらいの容量が必要かは個人と法人とでは大きく異なるでしょう。また、企業の中でも保存するデータがテキストベースの資料なのか、画像や動画が中心なのかによって変わってきます。例えば、デザインや図面を扱う企業であれば、必要なデータ容量も必然的に増えると考えられます。
法人向けのサービスには「容量無制限」のクラウドストレージがあります。確かに容量無制限であれば、将来データ量がどれだけ増えても安心と思うかもしれませんが、その分コストがかかります。必要性とコスト面でバランスのとれた選択をするよう心がけましょう。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ2つ目のポイントは、上述したデータ容量と料金プランのコストパフォーマンスです。
クラウドストレージサービスには、無料プランもあります。ただ、容量は5~20GB程度にとどまるため、法人で使用するにはやや足りない印象です。
有料プランを前提にすると、料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスは「1GBあたりいくらか」で測ることができます。
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ3つ目のポイントは、ファイル共有やオンライン共同作業に関してです。
上述したように、ファイル共有やオンライン共同作業はクラウドストレージの基本的な機能です。ただ、クラウドストレージサービスの中にはファイル共有機能のみに特化したものもあります。また、ファイル共有の際、リンクを共有することで閲覧するだけでなく、編集権限も付与できるか、パスワードや保存期間が設定できるかも異なります。自社の用途に合わせて、チェックしておきましょう。
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ4つ目のポイントは、必要な機能やサービスが備わっているかという点です。
各事業者とも差別化をはかるために、さまざまな付加的なサービスを提供しています。例えば、以下のようなものがあります。
・スマホでも利用可能か
・導入後のサポートはあるか
・利用するすべての端末で利用可能か
・期限付き共有リンクの生成ができるか
自社の使用形態に応じて、必要十分なサービスが備わっているかも選ぶポイントの1つだといえるでしょう。
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ5つ目のポイントは、万全なセキュリティ対策がされているかという点です。
セキュリティ対策を考えると、法人で無料プランは選ばない理由が分かります。当然ですが、利用料金が高くなればなるほど、事業者のセキュリティに対する責任は重くなるからです。
クラウドストレージでは、セキュリティ対策は自社担当者ではなく、事業者に大部分を委ねることになります。そのため、前もって事業者のセキュリティ対策について精通しておきましょう。
この点、総務省も2021年9月に「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」を改訂しました(第3版)。利用者の設定ミスや不十分な変更管理に加え、クラウドサービス自体の障害も多数報告されている点が指摘されています。そのため、セキュリティ対策をクラウドサービス事業者に丸投げするのではなく、クラウドサービス利用者も自らの責任範囲において、やるべきことをおこなうことが不可欠、というのが改訂理由だとしています。
参考:「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン (第3版)」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf) を加工して作成
セキュリティ対策について知りたい方はこちら
6. ストレスを感じない操作感か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ6つ目のポイントは、ストレスを感じない操作感かどうかです。
例えば、反応が遅かったり、操作性が普段使っているOSと大きく乖離するようなら、従業員はそのサービスを次第に活用しなくなってしまいます。また、操作を学ぶために特別な研修が必要になれば、普及するまで時間がかかることでしょう。

以上を前提とすると、法人がクラウドストレージを導入する際には有料ストレージを選ぶべきです。なぜなら、無料ストレージの場合、利用している側はセキュリティの脆弱性や容量に関して事業者に責任を問うことはできないからです。
事業規模の小さい企業の場合、ランニングコストを考えると、有料ストレージを導入することに二の足を踏んでしまうかもしれません。その場合、1つの方法は無料のトライアル期間を活用することです。無料期間中にコストパフォーマンスや必要性を検証することをおすすめします。

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
MEGA
|
10GBまで無料
|
・転送マネージャーで大容量のファイルをアップロード
|
・エンドツーエンド暗号
・2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護
・ランサムウェア対策
|
|
Googleドライブ
|
15GBまで無料
|
・オンラインでの共同編集
・ファイルの一括管理
|
・ゼロトラスト機能
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人向けのクラウドストレージは有料版を選ぶことになると思いますが、部署やチーム内で共同作業を行う際に、あるいは個人で無料版を検討することもあるでしょう。
ここでは、10GB以上であることを前提に、無料版で容量サイズの大きいクラウドストレージを2つ紹介します。
1.『MEGA』10GBまで無料
MEGAはニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウドストレージです。10GBまでは無料で利用できます。
セキュリティ面では「エンドツーエンド暗号」を採用しており、第三者が通信内容を傍受できない対策がなされています。また、2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護し、データを安全に守ります。そのセキュリティの高さはサービスを提供しているMEGAさえもアクセスできないほどです。MEGAではファイルはゼロ知識で暗号化され、鍵を保有しているのはユーザだけだからです。
さらに、ランサムウェア対策も万全です。仮にランサムウェア攻撃を受けた場合、ローカルストレージとMEGA間で自動同期が行われている場合でも、感染する前の時点にファイルを戻せます。
MEGAのユーザが扱うファイルは大容量になりがちですが、デスクトップアプリでは強力な転送マネージャーが利用できます。そのため、短時間に大容量ファイルをアップロードすることが可能です。
有料プランである「ビジネス」は、最小3人のユーザで3TBの基本ストレージを利用でき、毎月の利用プランは2,399円(2024年12月11日時点の日本円での見積価格、実際はユーロで請求)です。ユーザ数や容量は必要に応じて変更可能です。
公式HP:MEGA
2.『Googleドライブ』15GBまで無料
Googleドライブは、Googleが提供しているクラウドストレージです。Googleアカウントを作成することで15GBまで無料で利用できます。1日あたり750GBまでなら大容量のファイルもアップロードが可能です。
Googleドライブの特徴は、ドキュメントの編集機能など、オンラインでの共同作業がしやすい点です。また、さまざまなタイプのファイルを一括して管理し、必要なファイルをすぐに見つけることができます。GoogleのAI機能を利用して、ユーザにとって必要なファイルをリアルタイムに予測し、表示できるのです。
また、Googleドライブはセキュリティにおいて「ゼロトラスト機能」を採用。ゼロトラストとは、テレワークの増加やモバイル端末によるアクセスなどにより、企業の内部と外部を隔てる「境界」があいまいになる中、その概念をすべて捨て去り、情報資産にアクセスしようとするものはすべて信用せずに安全性を検証しようとする考え方のことです。
法人が利用を検討する場合には、有料プランの「Google Workspace」がおすすめです。有料プランは「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランが準備されており、料金や容量は以下の通りです。Googleドライブの無料版を個人で使っている方も多いと思いますが、Enterpriseを含めて、幅広い企業ニーズにも対応しています。
|
プラン
|
Business Starter
|
Business Standard
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜300人
|
無制限
|
|
容量
(ユーザ1人あたり)
|
30GB
|
2TB
|
5TB
|
5TB
(追加リクエスト
可能)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Googleドライブ

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
機能
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円~(税込、1年契約の場合)
|
・スマホアプリ
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元
|
・IDパスワード認証
・2要素認証
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
|
|
OneDrive for Business
|
Plan 1の場合 749円〜(税抜、1ユーザあたり)
|
・Microsoft 365と連携
・アクセス権のコントロール
・アクセス有効期限の設定
|
・データを暗号化
・各フォルダを保護し、バックアップ
|
|
Dropbox Business
|
Businessの場合 1,500円〜(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・Dropbox上でファイルを作成、編集
・デスクトップアプリ
・コンテンツアップデートの通知機能
|
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円〜(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
・Box Signで電子サイン
・仮想ホワイトボードツールBox Canvasにより、コラボレーションを支援
|
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・強力なユーザ認証
・7段階のユーザ権限設定
|
|
Fileforce
|
Small Businessの場合 990円〜(1ユーザあたり)
|
・Officeアプリ上で快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
|
・IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限
・キャッシュデータを自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 2,860円(1ユーザあたり)
|
・マルチデバイス対応
・優れたプレビュー機能
・管理者作業を一元管理・自動化
|
・様々な第三者認証を取得
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲などを柔軟に設定可能
|
|
GigaCC ASP
|
STANDARDプランで10IDの場合 12,000円〜
|
・リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・一斉振り分け送信機能
|
・2段階認証機能
・2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
|
|
NotePM
|
プラン8の場合 4,800円〜
|
・高機能エディタと画像編集機能
・全文検索
・チャット連携、API対応
|
・柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)+初期費用 15,000円(税別)
|
・サムネイル画像を自動生成、高速表示
・直感的な操作性
・最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モード
|
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全アクセス、操作等を記録
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここからはいよいよ法人向けの有料プランをご紹介します。
以下に示すように、上述した6つのポイントに加え、利用可能なユーザ数についてまとめてみました。
・容量
・料金
・ファイル共有やオンライン共同作業
・特徴的な機能
・具体的なセキュリティ対策
・操作感
・利用可能なユーザ数
3.『使えるファイル箱』
使えるファイル箱は、使えるねっとが提供する「空気みたい」に自然に使える便利で安心なクラウドストレージサービスです。
使えるファイル箱の特徴は、PCにインストールしてエクスプローラーやFinderから使用できるため、操作性が高く、特別な研修も必要なくスムーズに導入できる点です。また、他のアプリケーションからも直接保存できますし、ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集したり、複数人で同時編集したりもできます。アップロードできるファイルサイズは無制限なので、大容量ファイルの共有も安心です。
特徴的な機能:
・スマホアプリ(Android&iOS)
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元(最大999日/最大999バージョン)
・汎用的なWebDAVプロトコルに対応しているため、さまざまなアプリが利用可能(アドバンス)
セキュリティ:
・IDパスワード認証
・2要素認証設定
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
・国内データセンター(長野)
・GDPRコンプライアンス(EU一般データ保護規則)対応
・サーバ内シークレットキー対応
・履歴ログ管理
・リンクのパスワード保護
・共有リンクの有効期限
・ランサムウェア対策
・ログイン許可IP制限(アドバンス)
・ダウンロード回数制限(アドバンス)
・デバイスデータの遠隔削除(アドバンス)
・特定デバイスからのアクセスブロック可能(アドバンス)
使えるファイル箱は、スタンダードプランでも利用可能なユーザ数が無制限で、容量も1TBから追加可能。拡張性の高さにも注目です。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
利用可能なユーザ数
|
無制限
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
月額料金
(税込)
※1年契約の場合
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
4.『OneDrive for Business』
OneDriveはMicrosoftが提供しているクラウドストレージサービスです。家庭向け、一般法人向け、大企業向けのサービスがありますが、ここでは一般法人向けを紹介します。
OneDriveの最大の特徴は、Microsoft 365のビジネスソフトとシームレスに連携できる点です。そのため、複数ユーザによる共有や編集作業がスムーズです。
特徴的な機能:
・ファイル共有のアクセス権のコントロール
・共有されるファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可能
・共有ファイルのダウンロードを防止
・Android、iOS、Windows用のOneDriveモバイルアプリでどこからでもアクセス
・ファイルのダウンロードをせずにアクセスできるため、デバイスのストレージスペースを節約
・差分同期を選択できる
・Webでのプレビューで320種類以上のファイルを忠実に再現
・最も関連性の高いファイルを検出するためのインテリジェントな検索と検出のツール
・複数ページのスキャン可能
セキュリティ:
・転送中および保管中のデータを暗号化
・「既知のフォルダの移動」を使用することで「デスクトップ」「ピクチャ」「ドキュメント」の各フォルダを保護、バックアップ
|
プラン
|
OneDrive
for Business
(Plan 1)
|
Microsoft 365 Business Basic
|
Microsoft 365 Business Standard
|
|
利用可能なユーザ数
|
ー
|
〜300人
|
|
容量
|
ユーザ1人あたり1TB
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税抜)
※年間サブスクリプション
の場合
|
749円
|
899円
|
1,874円
|
公式HP:OneDrive
5.『Dropbox Business』
Dropbox Businessは、個人向けの無料サービスも展開しているDropboxの法人向けクラウドストレージサービスです。従来のファイルに加えて、クラウドコンテンツやウェブコンテンツのショートカットもすべて同じ場所に保存できるため、情報を整理して効率的にチームで作業を進めることができます。
特徴的な機能:
・Dropboxで直接クラウドコンテンツやMicrosoft Officeファイルなどを作成、編集可能
・スマートなコンテンツ提案機能を備えたデスクトップアプリ
・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたときの通知機能
・作業ファイルの横にある最近のアクティビティ情報で最新情報を把握
・Slack、Zoomなどの使い慣れているツールとリンクすれば、検索したりアプリを切り替えたりする必要なし
・Dropbox Paperでチームメンバー全員で締切とファイルを共有し、リアルタイムで更新しながら作業可能
セキュリティ:
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証設定
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
・管理者がチームの共有権限をきめ細かく管理
・デバイスのリンクを解除
・社員が退職した場合やデバイスを紛失した場合、パソコンとモバイルデバイスの両方からデータとローカルコピーを削除
|
プラン
|
Essentials
|
Business
|
Business Plus
|
|
利用可能なユーザ数
|
1人
|
3人〜
|
|
容量
|
3TB
|
9TB〜
(チーム全体)
|
15TB〜
(チーム全体)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)
※年間払いの場合
|
2,000円
|
1,500円
|
2,400円
|
公式HP:Dropbox
6.『Box』
Boxはカリフォルニアに本社を置く、2005年にアメリカで設立されたクラウドストレージで、日本でも代理店を経由してサービス展開しています。Boxの特徴は、どのプランも容量無制限であり、ユーザも3人以上であれば、事業規模の拡大に合わせて人数に関係なく利用できる自由度の高さでしょう(「Box Starter」を除く)。
特徴的な機能:
・仮想ホワイトボードツールであるBox Canvasにより、コラボレーションを支援
・Box Signが標準機能として提供され、電子サインにより迅速でコスト効率の高いDXを支援
・Box Relayにより、デジタルアセットの承認や予算管理などの反復業務をシンプルでフレキシブルなワークフローとして自動化
セキュリティ:
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・SSO(シングルサインオン)とMFA(多要素認証)をサポートする強力なユーザ認証
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・すべてのファイルが保管時また転送時にAES256ビット暗号化
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
3人〜上限なし
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
※年一括払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
6,600円
|
公式HP:Box
7.『Fileforce』
Fileforceは国内のさまざまな業界・業種の企業に導入されているクラウドストレージサービスです。端末に関係なく、Webブラウザからログインするだけで手軽に利用でき、スマートフォンやタブレット端末、自宅のPCなどさまざまな環境からアクセス可能です。Active Directoryなどに基づく権限管理に対応しているため、既存のファイルサーバの運用をそのまま引き継ぐことができます。
特徴的な機能:
・Officeアプリ上でもクラウドに保管されたデータを意識することなく快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
・Fileforceに保管されるすべてのファイルは自動で保護される
・社内外問わずファイルやフォルダを共有
・変更履歴はすべて保存
・ファイル更新時には自動的に履歴を保存するバージョン管理を適用、ファイル単位で任意の時点に戻せる
セキュリティ:
・社外ユーザはメールアドレスとパスワードによる認証を基本とし、IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限も可能
・キャッシュしたデータはユーザが意識することなく自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
Fileforceの料金プランはユーザ数やストレージ容量に合わせて細かく分かれており、事業規模や会社の成長に合わせて最適なサービスを選択できます。
|
プラン
|
Small Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
10ID
|
無制限
|
|
容量
|
ユーザ
あたり
10GB
|
1TB
|
3TB
|
10TB
|
30TB
|
|
月額料金
(税抜)
※年契約の場合
|
990円
/1ID
|
60,000円
|
108,000円
|
216,000円
|
360,000円
|
公式HP:Fileforce
8.『Box over VPN』
Box over VPNは、BoxをNTTコミュニケーションズが提供する閉域網サービス「Arcstar Universal One」経由で、セキュアなVPN環境下で利用できるサービスです。VPN回線を経由して利用できるため、Boxサービスよりもセキュリティレベルが強化されています。また、ネットワークからBoxまで、NTTコミュニケーションズが24時間365日の一元保守を担当してくれるため、手厚いサポートを受けられます。
特徴的な機能:
・マルチデバイス対応で、PCはもちろんのこと、スマートフォンやタブレットからもBoxを利用可能
・Boxの優れたプレビュー機能により、端末にインストールされていないアプリで作成されたデータも閲覧可能
・NTTコミュニケーションズが提供するBoxではユーザ登録など管理者作業を一元管理・自動化できるオプションを用意
・60日間無料トライアル実施中
セキュリティ:
・さまざまな第三者認証を取得、Boxは米司法省をはじめ、世界各国の政府機関や法人で採用されているため、機密性の高いファイルも安心して保管可能
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲、ダウンロードの可否、パスワードの有無、アクセス有効期限なども柔軟に設定可能
|
プラン
|
Business
|
Business Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
20ID〜
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
|
2,860円
|
4,180円
|
5,500円
|
公式HP:Box over VPN
9.『GigaCC ASP』
GigaCCは、日本ワムネットが提供する純国産の企業間ファイル共有・転送サービスです。テレワークをより便利に行える各種機能を備えており、ユーザにITリテラシーを求めない使いやすさも魅力といえるでしょう。
特徴的な機能:
・Microsoft Entra IDと連携し、リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・受信時にエラーが発生した場合は、スマートダウンロードのレジューム機能により、未受信部分からの再受信が可能
・一斉仕分け送信機能により、複数の宛先へ異なるファイルの自動送信・転送が可能
・「共有ノート」を活用し、アイディアや会議のメモなどを社内外で自由に共有できる
セキュリティ:
・メールによるワンタイムパスワードを利用した2段階認証機能
・スマートフォンの認証アプリを使用した2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
・アクセス元を制限し、なりすましを防ぐIPアドレス制限
・SSL/TLS暗号化通信
・万が一、権限のないユーザがファイルにアクセスしても中身を見ることができないようにするサーバ内暗号化
・誰がいつ、どこからアクセスし、どんなコンテンツを送信したかを記録する履歴ログ管理
導入には初期費用50,000円がかかります。STANDARD、ADVANCED、PREMIUMの3つのプランがあり、提供機能が異なります。基本月額費用は10IDが12,000円~、1000IDは280,000円~で、ADVANCEDプランはさらに25,000円、PREMIUMプランは42,000円が上乗せされます。
公式HP:GigaCC ASP
10.『NotePM』
NotePMは社内で情報共有をするための社内wikiツールです。いままでバラバラに管理されていたマニュアルやノウハウなどの社内ナレッジを一元管理します。例えば、ファイルサーバの検索が弱く、欲しい情報がすぐに見つからなかったり、マニュアルの作成が人によってバラバラで統一されていなかったり、ナレッジが属人化しているなどの悩みを解決します。
特徴的な機能:
・高機能エディタとテンプレートでバラバラなフォーマットを標準化、マニュアル作成に便利な画像編集機能も用意
・Word、Excel、PowerPoint、PDFなどのファイルの中身も全文検索するので、欲しい情報がすぐにみつかる
・チャット連携、API対応
・マルチデバイス対応
・お知らせ通知
・動画共有
・「人気ページのランキング」など、レポート機能
・変更箇所を自動でハイライト表示し、履歴を記録
・3,000以上のアプリとデータ連携が可能
・1,000以上の絵文字に対応
セキュリティ:
・プロジェクト単位、組織単位など、柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
・IPアドレス制限
・閲覧履歴管理
・ログイン連続失敗した場合に自動でアカウントロック
・ログインした端末情報を記録
|
プラン
|
プラン8
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜8人
|
〜15人
|
〜25人
|
〜50人
|
〜100人
|
|
容量
(チーム全体)
|
80GB
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
|
月額料金
(税込)
|
4,800円
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
公式HP:NotePM
11.『IMAGE WORKS』
IMAGE WORKSは富士フイルムイメージングシステムズが提供するクラウドストレージで、画像や動画コンテンツの一元管理・共有に特化したサービスです。検索機能が充実しており、AIを活用したラクラク検索機能も搭載しています。そのため、単にデータを詰め込むだけのオンラインストレージのみでなく、100項目を超えるファイル属性情報(メタ情報)から、業務や用途に合わせ、必要なファイルをすぐに探し出すことが可能です。
特徴的な機能:
・ファイル登録と同時に閲覧用のサムネイル画像を自動生成・高速表示
・直感的な操作性
・1ファイル最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モードも提供
・レジューム機能・整合性確認機能で送受信を支援
・IDを持たないゲストユーザとの送受信も可能
・ダウンロード申請・承認機能により、ファイルダウンロード前に利用者・利用目的等の申請を行う
セキュリティ:
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全てのユーザのアクセス・操作等の利用状況をログとして記録
・SSO(シングルサインオン)
・プロジェクトの利用期限が定められていれば、あらかじめ決めた期間で自動的にユーザやデータを削除
費用は、初期費用15,000円(税別)+月額費用15,000円(税別)のミニマムプランから、今すぐ始められます。
公式HP:IMAGE WORKS

主に法人向けのクラウドストレージサービスを紹介しました。「あまりに多すぎて選べない」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、そんな方のために「中小企業向け」「個人事業主向け」に分けておすすめなクラウドストレージをご紹介します。
中小企業に特におすすめのクラウドストレージ2選
中小企業に特におすすめなクラウドストレージは次の2つです。
■使えるファイル箱
■Fireforce
これらのクラウドストレージに共通していることは、拡張性の高さです。中小企業の場合、スタート時のユーザ数は少なく、保存すべきデータもあまり多くないですが、短期間のうちに業務拡大の可能性が高いといえます。それとともに、クラウドストレージを使用するユーザや必要な容量も増えていくはずです。
また、中小企業の一番の悩みはコストです。クラウドを導入したいと考える一方、少しでもコストを削減したいという中小企業の経営者は少なくありません。その点、上述したサービスはどれもイニシャルコストはかからず、企業の成長に合わせてプランを選べます。ユーザ数が無制限なため、従業員が増えることを心配する必要もありません。
セキュリティ対策も見落とせないポイントです。最近のサイバー攻撃は大企業だけでなく、サプライチェーンを含めて中小企業をターゲットに絞ったものも増えています。そのため、企業規模が小さくてもセキュリティ対策は万全にしておくべきです。セキュリティ面でも、上述のサービスは総合的に高い基準を満たしているといえるでしょう。
個人事業主に特におすすめのクラウドストレージ3選
個人事業主に特におすすめなクラウドストレージは次の3つです。
■Googleドライブ
■OneDrive
■Dropbox Business
この3つのクラウドストレージに共通しているのは、無料もしくは低コストで使えることです。企業であれば保有するデータが機密情報や顧客情報を含むため、無料のサービスを選ばないはずです。しかし、個人事業主の中には機密性の高い情報を保有する方は多くないため、無料であり、かつ汎用性のあるGoogleドライブは十分考えうる選択といえるでしょう。
また、個人事業主の場合、企業のように多くのメンバーと情報のやりとりをすることはないと思われます。主に取引先やクライアントとファイルを共有することになるでしょう。そのため、ファイル共有や転送の際のセキュリティよりも、機能が充実しており、操作性が高いものを選びたいところです。

ここでは、オンプレミスではなく、クラウドストレージを選ぶメリットについて改めてまとめておきます。クラウドストレージには以下のようなメリットがあります。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
以下、1つずつ説明します。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
クラウドストレージを使えば、ファイルやデータを一元管理できます。そのため、ファイルを探す手間を省き、データを転送・共有する工数を減らせて、業務効率が上がります。
オンプレミスでもデータの一元管理は可能ですが、クラウドストレージはインターネット経由でアクセスできるため、出張先やテレワーカーとも情報の共有が容易です。また、オフィスと工場など拠点が複数に分かれている場合でもクラウドストレージなら簡単にデータの一元管理ができます。
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
クラウドストレージを使えば、ファイル共有や共同編集も簡単です。どのサービスを選ぶかにもよりますが、容量の大きなデータも相手を選ばずに送ることができます。アップロードして、リンクを生成、送付するだけで完了です。
また、OneDriveやGoogleドライブだけでなく、多くのクラウドストレージサービスはさまざまなアプリケーションと連携しているため、オンラインで共同作業や編集が可能です。
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
クラウドストレージサービスを使うことで、オフィスだけでなくどこの場所からでもファイルにアクセスできます。また、アクセスする時間帯も選びません。
多くの企業でテレワークやワーケーションをはじめとした「時間や場所を選ばない働き方」が導入されていますが、そうした新しい働き方とも親和性があるのがクラウドストレージなのです。
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
クラウドストレージを使えば、社内にファイルサーバを設置する必要がないため、運用管理業務は不要です。
オンプレミスの場合、サーバにかかる負担を監視したり、災害・停電などで起きるトラブルに対処するために運用管理者が必要になります。外注の場合は、サーバ構築費の10~15%が保守運用費用として月額でかかるといわれています。
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
クラウドストレージの場合、データは社内のサーバではなく、災害のリスクが低いデータセンターに保存することになります。
災害大国である日本はどこであっても地震や台風、水害のリスクがあります。システムが破壊され、データが失われれば、企業は業務を停止せざるを得ず、膨大な損害を被ることになります。企業のBCP(事業継続計画)対策の一環としても、クラウドストレージ導入は有効です。
BCP対策について知りたい方はこちら

さまざまな要素を考慮し、最終的にどのクラウドストレージを選ぶにしても、活用・導入にあたって注意したい以下のポイントがあります。
1. インターネット環境の整備
2. セキュリティ対策
3. 運用体制の整備
4. 課金要素
1つずつ説明します。
インターネット環境の整備
サービス自体がどれほど優れていても、インターネット環境が整備されていないと、持っているポテンシャルを十分引き出すことはできません。
クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスのため、回線速度によってパフォーマンスが大きく左右されます。ネットワークの混雑によって、クラウドストレージの機能が低下しないように大容量の回線を準備しましょう。
セキュリティ対策
クラウドストレージを活用する際にはセキュリティ対策に注意を払うべきことは何度も強調しました。クラウドストレージを導入すれば、確かに自社での保守点検は基本的に不要になりますが、セキュリティ対策をクラウドストレージサービス提供事業者に丸投げしてしまって良いわけではありません。
いくらクラウドストレージ側にしっかりとしたセキュリティ対策が施されていても、利用者側でそれを使いこなせていなければ意味がありません。例えば、多くのクラウドストレージはユーザのアクセス権限を細かく設定できるようになっていますが、この設定のミスがセキュリティインシデントにつながるケースも増えています。
また、利用者側の端末のOSやアプリの脆弱性を放置すれば、サイバー攻撃者の格好のターゲットになります。情報漏えいなどを防ぐためには、常に最新のOSやアプリケーションにアップデートしておくことが必要です。さらに、クラウドストレージも万能でないことを認め、災害やサイバー攻撃によるデータ喪失に備えて、バックアップ先を複数用意するなどの対策も求められます。
脆弱性について知りたい方はこちら
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
運用体制の整備
クラウドストレージを導入する際にも運用体制を整備することを忘れないようにしましょう。言い換えると、クラウドの運用を「仕組み化」「システム化」するということです。
「誰が」「何を」「いつ」するのかを決めずに責任の所在をあいまいにし、何となく人的な対応でやりくりしていると、効率化、コスト削減の面でも無駄が生まれます。それだけでなく、やるべき工程に「抜け」が生じて、それがセキュリティインシデントにつながることがあります。経営者主導でクラウドストレージの運用体制を盤石にしましょう。
参考:株式会社アールワークス 「システム運用方針のまとめ方と、運用体制構築に必要なこと」
課金要素
クラウドストレージ導入にあたっては、課金体系をしっかりと把握しておく必要があります。
クラウドストレージサービスの中には、どの程度料金が発生するか分かりづらいものもあります。また、不要になったサービスを利用していないのに停止せずに放置したり、実装したアプリケーションに不備があり、無駄な処理が発生したりすることもあります。
毎月の請求内容にはきちんと目を通し、不明な点はサービス提供事業者に確認するなどして、「なんとなく」料金を支払い続けることがないようにしましょう。そうでないと、イニシャルコストを抑えられるクラウドストレージの強みが失われてしまいます。

ここでは、クラウドストレージを比較する際によくある質問を3つ取り上げます。
Q1:クラウドストレージは社外の人でも使えますか?
クラウドストレージが利用できるか否かは、そのサービスのIDを保有しているかどうかです。そのため、例え社外の人であっても、IDがあれば利用可能です。もっとも管理者によりどの程度までアクセスできるか、権限が制限されることはあります。
Q2:容量無制限のサービスを選べば安心ですか?
「容量無制限」という響きにはたしかに魅力があります。しかし、前述したように容量無制限のサービスを選ぶべきかは企業の業務規模や従業員数によります。現状で使う必要がないのに、やみくもに容量無制限を選ぶと逆にコスト面で損をする可能性もあります。
Q3:クラウドストレージにはデメリットはないのですか?
もちろんあります。
クラウドストレージがあらゆる面でオンプレミスに優れているわけではありません。例えば、クラウドストレージはサービスが定型化、パッケージ化されているため、オンプレミスのように自由なカスタイマイズはできません。
大切なのは、自社がクラウドストレージを導入する目的を見極めることです。
.png)
ここでは、中小企業におすすめする「使えるファイル箱」についてさらに詳しく説明します。
使えるファイル箱の3つの特長
使えるファイル箱にはさまざまな魅力がありますが、ここでは3つの特長を取り上げます。
1. ユーザ数無制限
100人でも、1,000人でも料金は一律です。フォルダのアクセス制限が設定できるため、ユーザIDの一部を外部に渡して、大容量データのやりとりもできます。ちなみに、100人で使えば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
2. 普段のパソコンと同じように操作できる
使えるファイル箱は特別なインターフェースを必要とせずに、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有ファイルを操作できます。そのため、特別な研修は必要なく、普段のパソコンと同じような感覚でファイル共有が可能です。
3. 高機能なのに低価格、無料トライアルもある
使えるファイル箱はクラウドストレージサービスを利用したくてもコスト面で限界がある中小企業に使っていただきたいと思っています。そのため、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。
また、スタンダードプラン、アドバンスプランいずれも30日間の無料トライアルがあるため、じっくり使い勝手を試してから決めることができます。
中小企業に最適な機能と料金形態
中小企業にとってコスパは重要な要素ですが、見逃すべきではないポイントはセキュリティです。使えるファイル箱なら、2要素認証やAES256ビット暗号化、ISO認証取得の長野県のデータセンターなど、貴重な情報資産を守るための対策もばっちりです。
さらに、使えるファイル箱は電子帳簿保存法上の区分のうち、電子取引にも対応しているため、書類の保管場所も節約でき、業務の効率化を図れます。
中小企業に最適な機能を備えた使えるファイル箱の料金体系は以下の通りです。
|
プラン
|
容量
|
1ヵ月契約
|
1年契約
|
|
スタンダード
|
1TB
|
25,080円(税込)/月
|
21,230(税込)/月
|
|
アドバンス
|
3TB
|
75,680円(税込)/月
|
60,500(税込)/月
|
おすすめは1年契約のプランで、容量1TBの場合は月単価21,230円(税込)。より高度な機能が搭載されたアドバンスプランではセキュリティを強化し、汎用性が増すWebDAV連携が可能です。容量3TBのアドバンスプランは60,500円(税込)!
最短で即日ご利用可能!
使えるファイル箱を試してみたいと思われたら、是非お気軽にご連絡ください。
即日または翌営業日に対応させていただき、お見積りいたします。ご希望に合わせてオンラインでのご案内や無料トライアル、勉強会を実施させていただき、本契約となります。最短で即日のご利用開始も可能です。
.jpg)
(1)無料クラウドストレージの容量は?
A:無料クラウドストレージの代表はGoogleドライブですが、ストレージ容量は15GBです。ほかのサービスは2~10GBのものが多いようです。
(2)ストレージ容量に余裕がなくなるとどうなるの?
A:ストレージはデータの保管庫のことで、クラウドに限らず、パソコンやスマホなどの端末でも容量不足の問題は付きものです。
クラウドストレージで容量が足りなくなると、バックアップがとれなくなったり、デバイス間のデータの同期ができなくなったりするなどの障害が生まれる可能性があります。個人で使用する場合であっても、無料のクラウドストレージでは容量不足の問題にぶつかると、有料版を購入することになります。
(3)自社サーバのデメリットは?
A:自社サーバを利用するデメリットには以下の点があります。
1. 運用管理の手間
2. 災害対策が容易でない
3. リモートワークに対応するためにはVPN環境を整えなければならない
4. 容量の拡張にコストがかかる
これらのデメリットもクラウドストレージなら解決可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
個人であれ、法人であれ、予期せぬ事態に備えた「データのバックアップ」は不可欠です。ただ、一口にバックアップといっても、データを別の端末に保管する「ローカルバックアップ」と、クラウドストレージを使用する「クラウドバックアップ」があります。
ここでは、クラウドバックアップにフォーカスして、その必要性や種類、選び方、さらにはおすすめのクラウドバックアップ8選を紹介します。
目次
クラウドバックアップとは
クラウドバックアップの必要性
【法人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由
【個人向け】クラウドバックアップがおすすめの理由
法人・個人おすすめのクラウドバックアップ比較8選
クラウドバックアップの種類
クラウドバックアップの選び方
クラウドバックアップを利用する上での注意点
安心・安全でおすすめのクラウドバックアップは「使えるクラウドバックアップ」
FAQ

「クラウドバックアップ」とは、オンライン上のストレージ(クラウドストレージ)に復元用のデータを保管することです。
従来は、別のハードディスクなどの端末やサーバにデータを複製しておくローカルバックアップが一般的でした。しかし、データを保管したハードディスクをうっかり落とすなど衝撃を与えると、中のデータが消失してしまう可能性があります。また、同じオフィス内にデータを保管した端末を置いておくと、災害リスクに常にさらされてしまいます。つまり、ローカルバックアップは物理的な障害に弱いのです。
この点、クラウドバックアップは、ローカルバックアップに比べ、物理的な障害に強く、しかも低コストで導入できるというメリットがあります。オンプレミスでバックアップ環境を構築するには高額な初期投資や運用コストが必要ですが、クラウドサービスなら月額料金で利用できるため、中小企業でも導入しやすいのが魅力です。特に、ナレッジとして蓄積した貴重なデータは一度失ってしまうと事業全体に影響を与えかねません。日ごろから自社の業務にデータがどれだけ深く関わっているのかを認識し、その扱いと保管・保護にはしっかりとした対策を取っておくことが重要となります。
クラウドバックアップとは?詳しくはこちら

クラウドバックアップは個人であれ、また企業の規模に関係なく必須です。クラウドバックアップが必要な3つの理由について説明します。
災害・障害対策
クラウドバックアップが必要な1つ目の理由は、災害・障害に備える必要があるからです。
日本は災害大国であり、災害に備える意識は他国と比べても高いといわれています。しかし、近い将来、ほぼ確実に起きることが予測されている南海トラフ巨大地震や、首都直下地震に向けて具体的な備えをしているか、自社の状況を改めて考えてみる必要があります。
例えば、気象庁が2024年11月に発表した情報によると、今後30年以内に南海トラフ巨大地震の発生する確率は70~80%です。その規模は東日本大震災の10倍と想定されており、震度7の揺れが静岡県から宮崎県まで広範囲にわたって襲います。さらに、南海トラフ巨大地震の津波もこれまでの地震をはるかに上回るもので、高知市を襲うとされている津波は34m、高知県の沿岸部はほぼ壊滅してしまうとさえいわれています。東日本大震災での津波は16.7mでしたが、静岡県を襲う津波は33mとほぼ倍の高さ、和歌山県でも20mに及びます。
多くの大企業が集中する首都圏を襲う首都直下地震の発生確率は、政府によると30年以内に70%(2020年1月24日時点)です。東京だけでなく、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県を含む関東地域のどこを震源にして起こるか分からないため、幅広いエリアの企業が備えをしておかなければなりません。
さらに激甚な被害をもたらすとされているのが、富士山の噴火です。噴火によって溶岩流や泥流が静岡県の一部に流れ出し、高速道路が寸断されたり、電力供給が寸断されたりする可能性も指摘されています。噴火によって火山灰が降るといわれていますが、私たちが普段イメージするような小さな灰とは異なり、ガラス片のようなものが降り注ぐと考えるべきです。そうした火山灰は私たちの体内に影響を与えるばかりか、企業のインフラや情報資産にも深刻な被害をもたらすでしょう。
災害が企業にもたらす被害は甚大ですが、他にも喫緊で発生確率がより高いものにシステム障害が考えられます。例えば、2019年に53の自治体のデータがシステム障害によって消失した例を取り上げましょう。
日本電子計算が提供している自治体向けIaaS(「Infrastructure as a Service」)にシステム障害が発生した結果、全体の15%のデータはバックアップが見つからず、復旧が不可能になりました。IaaSとは、サーバやストレージ、ネットワークなどのハードウェアからインフラまでを提供するサービスのことです。自治体が保管するデータが消失したことで住民サービスに大きな影響が出ましたが、企業が保有する情報にも多くの顧客データ、機密情報が含まれることから、クラウドバックアップによって対策するなど、データの保管には細心の注意が必要です。
ランサムウェア対策
クラウドバックアップが必要な2つ目の理由は、毎年増加しているランサムウェア攻撃です。
ランサムウェアとは、マルウェアの一種であり、感染すると端末がロックされたり、ファイルを暗号化したりします。ロックや暗号化を解除するためには被害者は「身代金」を支払わなければならないため、「ランサム(身代金)ウェア」と呼ばれています。
警察庁が2024年9月に発表した報告によると、令和6年度上半期の企業・団体等によるランサムウェア被害件数は114件であり、令和5年度下半期より20件増加しました。
近年、ランサムウェア攻撃の中で特徴的なのは「二重恐喝(ダブルエクストーション)」と呼ばれる手法です。これは、データを暗号化するのみならず、「対価を支払わなければデータを公開する」と二重に恐喝する悪質なもので、令和6年上半期では被害全体の82%を占めていました。また、警察庁に報告された被害件数114件のうち、大企業は30件、中小企業は73件であり、企業規模に関わりなくランサムウェア対策が必要であることが分かります。さらに被害企業・団体等のバックアップの取得・活用状況については、有効回答69件のうち11%にあたる8件で「バックアップを取得していなかった」と回答していることにも注目すべきでしょう。
ランサムウェアによるデータ消失の事例も多く発生しています。例えば、2022年7月には、千葉県南房総市の教育委員会の校務ネットワークがランサムウェア攻撃を受け、サーバのデータが暗号化されました。結果として、市内12の小中学校の個人情報が消失してしまいました。
「自社はセキュリティ対策をしっかりしているから大丈夫」と思うかもしれません。しかし、ランサムウェアの被害を受けた企業の多くはセキュリティ対策に着手していたのです。にもかかわらず、運用面に問題があったり、セキュリティソフトの更新が漏れていたりすることで、ランサムウェアに感染するケースが後を絶ちません。万が一のことを考えて、データのバックアップは必須なのです。
参考:「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R6kami/R06_kami_cyber_jousei.pdf)を加工して作成
人的なミスへの対策
クラウドバックアップが必要な3つ目の理由は、人的なミスに備える必要があるからです。
データ消失の要因といえば、サイバー攻撃やシステム障害をイメージする人も多いかもしれませんが、人的ミスもかなり高い割合を占めています。多くの企業で不注意によって重要なファイルを消去してしまったり、操作を間違えてデータを上書きしたりする事例も見られます。人間が操作する以上、人的なミスは必ずいつか生まれます。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、前もってバックアップしておけば、人的なミスに対処することも可能です。
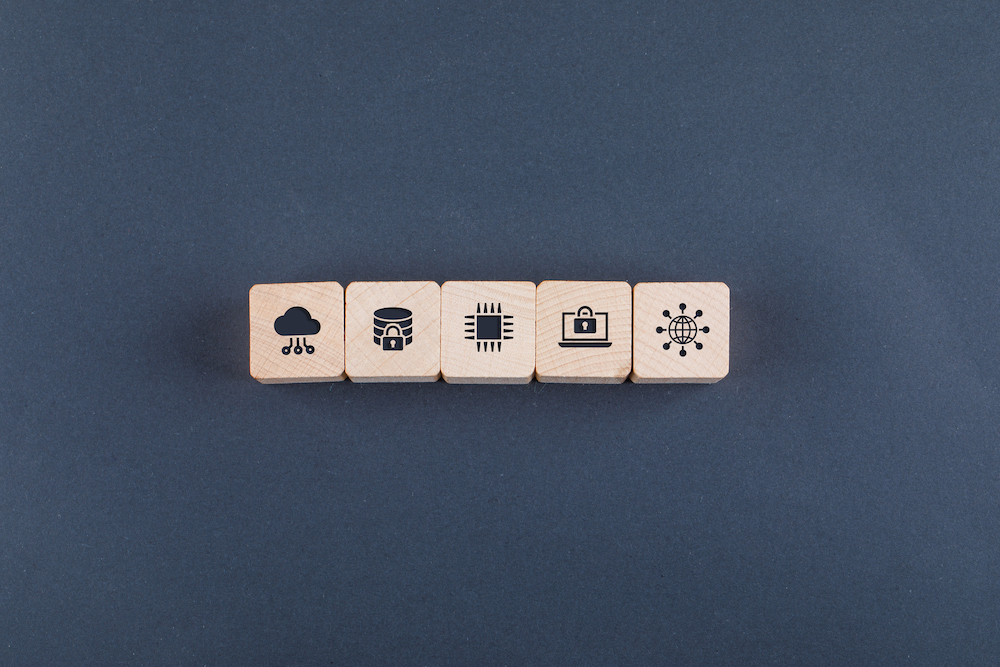
法人向けのバックアップには大きく分けて2つあります。1つは社内のサーバやハードディスクなど他の端末にデータを保管するローカルバックアップ、もう一つがクラウドバックアップです。
総務省の通信利用動向調査(令和5年版)によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は77.7%で、データバックアップとして利用しているのはそのうち42.0%でした。クラウドサービスの利用目的として最も多かったのが「ファイル保管・データ共有」(68.8%)だったことを考えると、企業のクラウドバックアップが広く浸透するのにはもう少し時間がかかるかもしれません。
まだ導入していない企業にもクラウドバックアップがおすすめな理由を4つご紹介します。
運用コストを抑えられる
クラウドバックアップがおすすめな1つ目の理由は、運用コストを抑えられることです。企業がローカルバックアップを選択する場合、運用するためにはサーバの費用だけでなく、管理するために専門スタッフの常駐が必要であり、そのための人件費がかかります。
それに対して、クラウドバックアップなら、サービスを提供する事業者のデータセンターにデータを保管するため、社内にサーバを設置する必要がありません。運用するスタッフも自社では基本的に必要ないため、人材コストも抑えられます。
また、事業の拡張とともにストレージが足りなくなった場合も、必要なリソースの分だけ増やせば足りるため、無駄な運用コストがかかりません。
操作が簡単で導入しやすい
クラウドバックアップがおすすめな2つ目の理由は、操作が簡単で導入しやすいことです。ローカルでバックアップを実施する場合、専門スタッフが付きっきりで対応することも少なくありません。
それに対して、クラウドバックアップなら、自動バックアップが可能で、手間がかかりません。範囲や時間を前もって設定しておけば、バックアップが実行されるため、専門的な知識がなくても大丈夫です。
データの復旧がしやすくBCP対策ができる
クラウドバックアップがおすすめな3つ目の理由は、データの復旧がしやすくBCP対策ができるからです。
BCP(事業継続計画:「Business Continuity Plan」)対策とは、企業が災害や感染症の流行、戦争やテロなどのリスクに直面した場合、事業を継続するために何を行うべきかを示した計画です。
上述したように、企業がデータを消失するリスクには地震や火山噴火、サイバー攻撃などさまざまな要因が考えられます。にもかかわらず、BCPを策定している企業は決して多くありません。
帝国データバンクが全国1万1,410社を対象に2024年5月に行った調査によると、BCPを策定している企業は19.8%にとどまりました。企業規模でみると、「大企業」は37.1%でしたが、「中小企業」は16.5%でした。中小企業の経営者もBCPの重要性は理解しているものの、策定するための人員や時間の不足が要因として挙げられました。
中小企業がこうした事態を改善するためには、少しでもBCP対策のハードルを下げることが重要です。BCPには、緊急時の指揮命令系統の構築や、調達先・仕入れ先の分散、従業員の安否確認手段の整備など多岐にわたる施策が含まれます。しかし、最初からあれもこれもやろうとするのではなく、できることから始めましょう。
そのための第一歩としてクラウドバックアップはおすすめです。前出の調査でも、BCPの実施内容として「情報システムのバックアップ」を挙げた企業は全体の57.9%だったことからも、BCPの中でも優先されるべき項目であることが分かります。
参考:帝国データバンク「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)」
BCP対策について知りたい方はこちら
ランサムウェア対策ができる
クラウドバックアップがおすすめな4つ目の理由は、ランサムウェア対策ができることです。
ランサムウェア対策をするにあたってはNIST(米国国立標準技術研究所)が策定した「サイバーセキュリティフレームワーク」が参考になります。2024年2月に約10年ぶりに大幅改訂された「サイバーセキュリティフレームワーク 2.0」は「統治」「特定」「防御」「検知」「対応」「復旧」の6つの機能から構成されています。ランサムウェアに対しても、この6つの機能に沿って対策を講じることができます。
・統治:組織のミッションや目標・利害関係者・役割・期待を踏まえた上で「どの対策を優先に取り組むべきか」という意思決定を導く
・特定:ランサムウェアのリスクについて理解を深める
・防御:適切なセキュリティパッチを適用し、ウイルス対策ソフトを定期的に更新して機器やシステムの脆弱性を防ぐ
・検知:サーバ、ネットワーク機器などのログ監視を徹底し、不正アクセスを迅速に検知する体制を整える
・対応:ランサムウェア攻撃を受けた場合の対応手順、連絡体制を策定しておく
・復旧:暗号化されたデータを復旧する
バックアップはその中でも「対応」「復旧」に関係しているといえるでしょう。ただ、ローカルバックアップだけだと、データを保管したサーバが社内の同一ネットワークとつながっており、ランサムウェアの攻撃対象になりかねません。せっかくサーバにデータを保管していても一緒に暗号化されてしまうなら本末転倒です。
この点、クラウドバックアップなら、社内ネットワークとは物理的に異なるロケーションにデータを保管します。クラウドバックアップのサービスによっては、ランサムウェア・ウイルスなどのマルウェアに対するセキュリティチェック機能も提供しているものもあり、万が一、ランサムウェア攻撃を受けても一緒に被害に遭うリスクを減らすことができ、ランサムウェア対策として効果的です。

クラウドバックアップは法人にだけでなく、個人にもおすすめです。ここでは、クラウドバックアップを個人におすすめする3つの理由を説明します。
クラウドストレージをバックアップとして使える
個人にクラウドバックアップをおすすめする1つ目の理由は、クラウドストレージがそのままバックアップとして使える点です。
クラウドストレージとは、クラウド上にデータを保存するストレージのことです。クラウドストレージによって、いつでもどこでもデータにアクセスできますし、複数の利用者で共有したり、編集したりできます。多くの人が利用しているGoogle DriveやiCloudもクラウドストレージです。
大企業、中小企業など規模を問わず、法人でクラウドストレージを利用する場合は複数のメンバーが絶えずアクセスするため、ファイルが書き換えられてしまう懸念があります。しかし、個人でクラウドストレージを利用する場合はその心配がなく、そのままバックアップとしても使用できるのです。
簡単な操作でバックアップができる
個人にクラウドバックアップをおすすめする2つ目の理由は、簡単な操作でバックアップができる点です。
ハードディスクを使ってバックアップをしたことのある方ならお分かりになると思いますが、定期的にバックアップを取り続けることは至難の業です。ついついバックアップを忘れてしまい、気が付くと前回のバックアップから何カ月も経過していたという方も少なくないでしょう。
この点、クラウドバックアップならインターネットとつながってさえいれば、自動的にバックアップを取り続けてくれます。手間がかからず、簡単な操作でバックアップができるのです。
バックアップを無料で使用できる
個人にクラウドバックアップをおすすめする3つ目の理由は、バックアップを無料で使用できる点です。
個人向けクラウドストレージサービスには無料で使えるものがたくさんあります。例えば、以下のようなサービスがあります。
・Google Drive:15GBまで
・Amazon Drive:Amazon会員なら5GBまで
・OneDrive Basic:5GBまで
・Dropbox Basic:2GBまで
・MEGA:20GBまで
・Box:10GBまで
・Yahoo!ボックス:Yahoo!一般会員なら5GBまで
・セキュアSAMBA:5GBまで
個人であれば保有するデータ量も企業ほど膨大にならないため、無料のクラウドストレージサービスでも十分足りるという人も少なくないはずです。
参考:NTT東日本「クラウドバックアップは利用すべき!おすすめする理由とサービス10選」

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
容量
|
特徴とセキュリティ
|
|
使えるクラウドバックアップ
|
200GBの場合 2,200円(税込、月単価、1年契約の場合)
|
200GB〜10TB
|
・ファイル転送をAES-256で保護
・イメージバックアップ採用
・ディザスタリカバリオプション搭載
・ランサムウェア対策
|
|
AOSBOX Business Pro
|
100GBの場合 40,000円(税別、年額)
|
・100GB〜1TB(通常ストレージ)
・1TB〜10TB(コールドストレージ)
|
・AES-256によりデータを暗号化
・間違ってデータを消去した場合も復元可能
|
|
USEN クラウドバックアップ
|
10GBコースの場合 2,900円(税別)+初期費用 2,900円(税別)
|
10GB〜8TB
|
・SSLとAES-256により暗号化
・変更されたデータブロックのみバックアップ
・一括バックアップ、部分バックアップを選択可能
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年一括払いの場合)
|
全プラン容量無制限
|
・AES-256による暗号化
・FIPS140-2認定を取得
・ゼロトラストのセキュリティ制御
|
|
Dropbox
|
Dropbox Plusの場合 1,200円(年間払いの場合)
|
・2GBまで無料
|
・ファイル共有、共同編集
・モバイル端末からアクセス
・3台までのデバイスをリンク可能
|
|
Google Drive(Google One)
|
プレミアム 2TBの場合 13,000円(年額)
|
・15GBまで無料
・有料プランは2TB〜30TB
|
・自動バックアップ機能
・複数ユーザ間共有、共同編集
・オンライン対応の設定
|
|
iCloud(iCloud+)
|
50GBの場合 150円(税込)
|
・5GBまで無料
・有料プランは50GB〜12TB
|
・Apple製品とのシームレスな連携
・自動バックアップ
・Android OSでは使用不可
|
|
OneDrive
|
Microsoft 365 Basicの場合 2,440円(年額)
|
・5GBまで無料
・有料プランは100GB〜6TB
|
・自動バックアップ
・最大30日間のファイル復元
・重要情報は「個人用 Vault」で保護
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
以下では、おすすめのクラウドバックアップサービスを法人向け、個人向けに分けて合計8選ご紹介します。どのサービスが「良い」「悪い」というよりも、それぞれのサービスの特徴に注目し、自社(自分)のニーズに合っているかどうか検証してみましょう。
【法人】おすすめのクラウドバックアップ
法人向けのおすすめのクラウドバックアップは4つです。
1. 使えるクラウドバックアップ
使えるクラウドバックアップは、使えるねっと株式会社が提供するサービスです。使えるねっと株式会社は、1999年からレンタルサーバ事業を開始し、2002年に設立されたクラウドサービスの老舗です。
使えるクラウドバックアップは、世界150か国、50万以上の企業が利用するアクロニス社のサイバープロテクションを採用しています。米軍も採用する最高レベルの暗号化をファイルがアップロードされる前に実施し、すべてのファイル転送もAES-256で保護しています。
具体的には後述しますが、使えるクラウドバックアップが採用しているのは「イメージバックアップ」という方法です。これは、すべてのアプリ、ファイル、ユーザアカウント、各種設定、オペレーションシステムを含むシステムイメージ全体を一気にバックアップするもの。これにより、万が一データが消失してもすぐに通常業務を再開できます。
またディザスタリカバリオプションの利用で、災害発生時には、バックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替えることができるため、事業を継続しながら、より確実にデータを保護します。BCP対策にも最適なソリューションといえるでしょう。
さらに、ランサムウェア攻撃からデータを守るための人工知能(AI)ベースの「アクティブプロテクション」を搭載しています。ファイル、バックアップデータ、バックアップソフトへの疑わしい改変があればすぐに検知、遮断、データを復旧します。既知のランサムウェアだけでなく、最新のランサムウェアやウイルスなどのマルウェアにも対応しているため、サイバー攻撃からデータを守る上でも安心です。
価格は月単価2,200円(税込)~で、自社の用途に合わせて容量を自由に増やせますし、契約期間も1カ月と1年のいずれかから選べます。さらにさまざまなライセンス追加も可能です。
|
容量
|
200GB
|
2TB
|
10TB
|
|
料金
(月単価、税込)
※年一括払いの場合
|
2,200円
|
7,920円
|
17,160円
|
公式HP:使えるクラウドバックアップ
2. AOSBOX Business Pro
AOSBOX Business Proは、スモールオフィスから大企業まで対応した法人向けクラウドバックアップサービスです。BCP対策としても手軽に導入できます。
AOSBOX Business Proの特徴は、復元速度が速い「通常ストレージ」と大量データを長期保存するのに適した「コールドストレージ」を選べるデータバックアップソリューションであるということです。
また、AES-256を採用し、データを暗号化します。しかも、マシン内、データ転送時、サーバ上の3箇所でそれぞれ暗号化するために強固にバックアップデータを保護しています。
さらにより高速にバックアップするために、AOSBOX Business Proは重複データを除外し、増分アップロード、小さなファイルのグルーピング機能を搭載しています。
価格は「通常ストレージプラン」と、大容量ストレージを希望される企業向けの「コールドストレージプラン」に分かれています。それぞれのプランの価格は容量ごとに以下のように設定されています。
|
通常ストレージプラン
|
|
容量
|
100GB
|
500GB
|
1TB
|
|
ユーザ数
|
無制限
|
|
料金
(年額、税別)
|
40,000円
|
160,000円
|
240,000円
|
|
コールドストレージプラン
|
|
容量
|
1TB
|
5TB
|
10TB
|
|
ユーザ数
|
無制限
|
|
料金
(年額、税別)
|
120,000円
|
480,000円
|
720,000円
|
公式HP:AOSBOX Business Pro
3. USEN クラウドバックアップ
USEN クラウドバックアップは、物理サーバ、仮想マシン、PC、アプリケーション、モバイル等あらゆるシステム環境に合わせてカスタマイズできるバックアップサービスです。
転送経路はSSLによって、データはAES-256によって暗号化され、データセキュリティを確保しています。
バックアップは変更されたデータブロックのみに適用、複数世代保存してもクラウド容量を圧迫しません。復元は遠隔からも可能ですし、WindowsでバックアップしたデータをMacに復元することもできます。
また、バックアップの形式として、一括バックアップか、必要な部分だけをバックアップすることも可能です。自社のニーズや業務形態にあわせて、最適化されたバックアップを実現できます。
価格は容量によって異なり、10GBコースから8TBコースまで11コースに分かれています。そのうちのいくつかのコースについて紹介します。
|
コース
|
10GBコース
|
100GBコース
|
1TBコース
|
|
初期費用(税別)
|
2,900円
|
12,000円
|
59,800円
|
|
月額料金(税別)
|
2,900円
|
12,000円
|
59,800円
|
すべてのコースで初期費用と月額料金は同額に設定されており、容量最大の8TBコースでは初期費用、月額料金ともに200,000円です。注意点として、クラウド側の最大容量に達するとバックアップは行われなくなることを覚えておきましょう。
公式HP:USEN クラウドバックアップ
4. Box
Boxは世界的にも多くの企業で導入されているクラウドバックアップサービスです。
AES-256による暗号化、FIPS140-2認定を取得し、ゼロトラストのセキュリティ制御を実現しています。データを保護するための「Box Shield」は深層学習を活用したマルウェア検知機能を備え、マルウェアの拡散を事前に発見・阻止することでデータ漏えいを防ぎます。
セキュリティレベルが高いことに加え、法人向けのすべてのプランでデータ容量は無制限で利用できる点も大きな特徴です。ファイルのアップロードの上限は5GBのため、動画など大容量のファイルでも問題なくアップロードできます。
バックアップシステムを備えた複数のデータセンターによって冗長性を確保することで、SLA(提供するサービスにおいて合意した保証レベル)は99.9%に達します。
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
料金
(1ユーザ、月額、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
6,600円
|
|
アップロード容量上限
|
5GB
|
15GB
|
50GB
|
150GB
|
どのプランも最小ユーザ数は3名で、表示価格は1ユーザ・年一括払いで月当たりの金額(税込)です。どのプランも容量無制限ですが、ファイルのアップロード容量の上限が異なり、Businessは5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GBです。
公式HP:Box
【個人】おすすめのクラウドバックアップ
以下では、個人向けのおすすめクラウドバックアップをご紹介します。ただ、以下の4つのサービスは本来はクラウドストレージであり、バックアップに特化したものではないことにご注意ください。
5. Dropbox
Dropboxは2GBまでは無料で利用できます。無料で利用できる容量は他のサービスと比べてやや小さめといえるでしょう。ただ、無料プランでも過去30日間に削除したものを復元でき、最大3台までのデバイスをリンク可能です。
Dropboxの特徴の一つとして、通常はファイルを共有したり、共同で編集したりするのにも便利な点が挙げられます。例えば、共有フォルダを作成した場合、そこにファイルをアップロードすれば他のメンバーも自由に閲覧、編集できます。相手がスマートフォンなどの携帯端末でもアクセス可能なため、いつでもどこでもスピーディな情報共有が可能です。
Dropboxを使用する際はWeb上でログインする必要はなく、デスクトップ上で専用フォルダにファイルをドラッグすれば、自動的にクラウド上でもデータをアップロードしてくれます。そのため、バックアップとして利用することも十分可能です。
ちなみに有料版へアップグレードすれば、Dropbox Plusで2TBまで、Dropbox Essentialsで3TBまで追加できます。
公式HP:Dropbox
6. Google Drive(Google One)
Google DriveはGoogleアカウントをもっていれば、15GBまで無料で利用できます。15GBは個人向けの無料サービスとしては余裕があるように思えますが、Google Photo、Gmailともストレージを共有する点に注意が必要です。自動バックアップ機能があるため、1人で使用する場合はバックアップとして用いることもできます。
Google Driveの別の特徴として複数のユーザで共有したり、編集したりすることもできます。
Google Driveでは、オフライン対応の設定も可能です。場所によってはネット接続が難しい環境があります。そんな場合でも、この機能を使えばデータの編集・変更が可能です。ネットが接続されると、自動的に同期されてデータは更新されるので、常に最新の状態に保たれて、安心です。
個人用アカウントで保存容量が足りなくなった場合は、Google Oneで追加購入できます。プレミアムは2TBで年額13,000円、5TBで年額32,500円、さらに大容量が必要な場合は20TB、30TBも選べます。
公式HP:Google Drive
公式HP:Google One
7. iCloud
iCloudはApple社が提供しているクラウドストレージサービスです。iPhoneなどApple社の製品ユーザ向けのサービスといえるでしょう。5GBまで無料で利用できます。
Apple社ユーザに特化しているため、パソコン、iPhone、iPadなどすべての端末でApple社の製品を使っている人にとって、データをいつでもどこでもシームレスに取り出すことができ、非常に使い勝手の良いサービスです。Apple Storeで購入したり、ダウンロードしたりしたアプリも他のデバイスで同じように使用できるのも大きなメリットといえるでしょう。それに対して、Android OSのスマホなどでは利用できないデメリットがあります。
自動バックアップは設定アイコンから行います。「iCloud」画面が表示されるので、「iCloud Drive」「写真」「メール」「カレンダー」などの一覧の中から自動バックアップしたいものをオン設定にします。この設定により、Apple社製品の端末をWi-Fi環境に接続すれば自動でバックアップできるようになります。
ちなみにiCloudにも有料プランがあり、以下の通りです。
|
プラン
|
iCloud+ 50GB
|
iCloud+ 200GB
|
iCloud+ 2TB
|
iCloud+ 6TB
|
iCloud+ 12TB
|
|
料金
(月額、税込)
|
150円
|
450円
|
1,500円
|
4,500円
|
9,000円
|
公式HP:iCloud+
8. OneDrive
OneDriveはMicrosoft社が提供しているMicrosoft 365に含まれるサービスです。Microsoft 365 Personalのユーザであれば1TBまで利用でき、作成したWordやExcel、PowerPointなどのファイルを自動でバックアップしてくれます。6ユーザまで使用できるMicrosoft 365 Familyであれば、6TBまで利用できます。どちらも年間サブスクリプションで、Microsoft 365 Personalで年額14,900円、Microsoft 365 Familyは年額21,000円です。
サイバー攻撃などの被害にあったり、データを誤って削除したりした場合も、最大30日間は元に戻すことができます。また、パスポートや免許証など個人情報が載せられた重要情報は「個人用 Vault」に保管して保護します。データはMicrosoftが管理するデータセンターに保管されますが、入退室が厳格に管理され、災害などに備えて幾重にもデータを保護する仕組みが採用されているため安心です。
公式HP:OneDrive
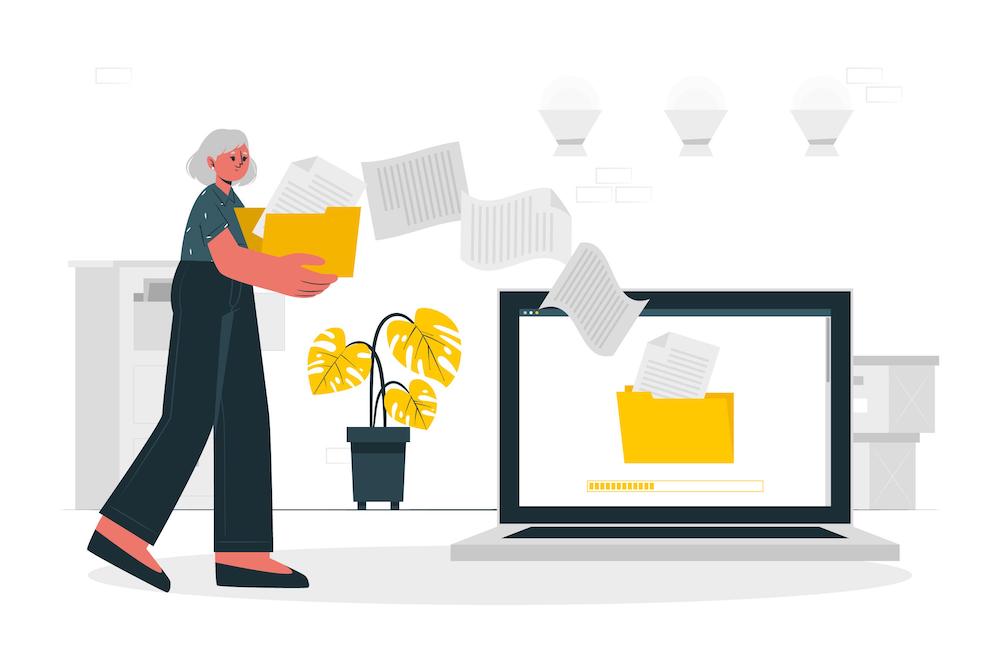
上でご紹介した8選の中にも登場した「イメージバックアップ」は、クラウドバックアップの一種です。
ここでは、クラウドバックアップの3つの種類である「イメージバックアップ対応型」「ファイルバックアップ対応型」「ファイルストレージの併用型」について説明します。
イメージバックアップ対応型
イメージバックアップとは、ファイルだけでなく、アプリケーションやOS、さらにはユーザアカウントや設定なども含めてシステム全体を丸ごとバックアップすることです。
イメージバックアップ対応型のメリットは、OSのインストールやアカウント設定などが必要ないため、復旧をスピーディに行えることです。復旧のコストも抑えられます。
イメージバックアップ対応型のデメリットは、バックアップの作業に時間がかかることです。また、万が一バックアップファイルが壊れたら、すべてのデータが失われるリスクもゼロではありません。
ファイルバックアップ対応型
ファイルバックアップとは、その名の通り、ファイル単位でバックアップを実行することです。
ファイルバックアップ対応型のメリットは、保管が必要なファイルやデータを選択できるため、バックアップの時間や容量を節約できる点です。
ファイルバックアップ対応型のデメリットは、イメージバックアップのようにアプリケーションアカウント設定をバックアップしないため、復旧に時間がかかることです。復旧する場合はOS、アプリケーションのインストールから始めて、それぞれの設定をしなければならないからです。企業によっては、復旧作業に膨大な時間がかかるため、経済的損失につながる恐れもあります。
ファイルストレージの併用型
ファイルストレージの併用型とは、Google Driveなどクラウドストレージサービスをバックアップとしても併用するパターンです。
ファイルストレージの併用型のメリットは、コストを抑えられることでしょう。クラウドストレージサービスの中には無料で利用できるものも多くあります。また、ストレージ内のファイルに変更が加えられたら、自動的にバックアップされる点も便利です。
ファイルストレージの併用型のデメリットは、企業がバックアップとして使用するには、無料版だとストレージ容量が足りない恐れがあることです。その場合、有料版に切り替えることも検討してみましょう。

上述の通り、クラウドバックアップサービスを提供している事業者はたくさんあります。その中から自社に最適なサービスを選択するのは簡単ではありません。ここでは、クラウドバックアップを選ぶ3つのポイントについて説明します。
バックアップの種類
クラウドバックアップを選ぶ1つ目のポイントは、バックアップの種類です。バックアップにはイメージバックアップと、ファイルバックアップがあります。そのどちらを選ぶかは自社が導入しているシステムに大きく依存しています。
もし自社が汎用的なシステムを導入している場合は、システム全体を含めてイメージバックアップする必要はないかもしれません。場合によっては、ファイルの一部のみで足りるようならファイルバックアップを選択しましょう。
加えて、NAS(Network Attached Storage)などを利用してバックアップを取っており、クラウドバックアップは補完的に使用したいという方もファイルバックアップがおすすめです。
それに対して、自社システムを高度にカスタマイズしている場合はイメージバックアップが向いています。復旧の際、アプリケーションやユーザの設定を一から行っていると膨大な時間がかかってしまうからです。
セキュリティの高さ
クラウドバックアップを選ぶ2つ目のポイントは、セキュリティの高さです。ローカルの端末ではなく、クラウド上にバックアップするということは、クラウドサービス提供事業者に運用やデータ管理を委ねるということです。相手が専門業者であることは確かですが、セキュリティ面に関してはクラウドバックアップを選ぶ際にしっかりと見極めておきましょう。
総務省はクラウドサービスを利用する際には、以下のような情報セキュリティ対策を行っているかを確認することを勧めています。
・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策
・データのバックアップ
・ハードウェア機器の障害対策
・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策
・不正アクセスの防止
・アクセスログの管理
・通信暗号化の有無
参考:総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/)
また、クラウドバックアップを社内のデータ保護対策として取り入れることで、取引先や顧客に対する安心感の提供にもつながります。「セキュリティ対策をしっかり導入している信頼できる企業」としての印象は、特に情報管理の厳しい業界では極めて重要な要素となります。特に、成長を遂げている最中の中小企業の場合、社員数の増加に伴い社内におけるデータインフラの構築を急ぐ必要が生じます。クラウドバックアップサービスは、このようなときに情報の安全を守り、業務効率を向上させるために効果的なソリューションです。
法人利用の場合は自社業務との相性も確認
クラウドバックアップを選ぶ3つ目のポイントは、自社業務との相性です。
相性を確認するためには、実際に一度バックアップを試験的に実行してみるのが一番です。その際、パソコンやサーバ、他の通信機器に影響がないか、動作が遅くなるなど負荷がかからないかをチェックしておきましょう。
.png)
さまざまな要素を検証してクラウドバックアップを導入したとしても、その後も引き続き注意することがあります。ここでは、導入後にクラウドバックアップを利用する上で注意したい3つのポイントを説明します。
クラウドバックアップのデメリット(リスク)についてはこちら
ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにする
クラウドバックアップを利用する上での1つ目の注意点は、ハードウェアに負荷がかかり過ぎないようにすることです。
クラウドバックアップを導入すると、オフィスの他のハードウェアに負荷がかかり、動作が遅くなる可能性があります。ハードウェアへの過大な負荷が常態化すると、業務効率が下がったり、従業員のモチベーションに影響が出たりする可能性があります。
上述したように、導入前にパソコンや他の通信機器への影響については検証しているはずですが、導入した後で気になるようなら、バックアップの範囲や頻度などを見直すなどの施策が必要かもしれません。
データ重複などによるコスト増に気をつける
クラウドバックアップを利用する上での2つ目の注意点は、データ重複などによるコスト増に気を付けることです。
クラウドバックアップサービスやクラウドストレージサービスの多くが、容量の大きさに基づいて使用料金を設定しています。バックアップに念を入れることは大切ですが、重複したデータが保管され、ストレージを占有していくと、料金がどんどんかさんでしまいます。
クラウドバックアップの設定には、重複するデータを排除する機能がありますので、活用しましょう。また、定期的に自社のバックアップの範囲や保管しているデータを見直してみることも重要です。
帯域圧迫で業務効率が低下する恐れがあるので注意する
クラウドバックアップを利用する上での3つ目の注意点は、帯域圧迫で業務効率が低下しないようにすることです。
帯域とは、時間単位で送信できるデータ転送量のことです。クラウドバックアップの場合、オフィスとは隔離された別の場所にあるデータセンターに大量のバックアップファイルを転送することになります。そのため、帯域を圧迫して、通信環境に影響を与え、オフィス内での他の業務効率を低下させるリスクがあるのです。
こうした事態を避けるためには、不要なデータを削除してバックアップするデータ量を減らすか、夜間などに時間帯を絞り、少しずつバックアップするなどの対策が可能です。また、そもそもバックアップする際にはネットワークの帯域を圧迫しないように転送量の上限を設定しておくとよいでしょう。
(2).png)
使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は、バックアップ機能だけでなく、データを守り、使うための機能を1つにまとめたサービスです。日々の業務に加え、もしもの時にも事業を止めることなく活用できるため、BCP対策にも最適です。
使えるクラウドバックアップが採用しているのはイメージバックアップ。ファイルだけでなく、ユーザアカウント、各種設定なども含めて丸ごとバックアップするため、ファイル復元がスピーディです。増分・差分バックアップも併用し、バックアップ自体の負荷軽減や容量節約も可能です。
また、大切なバックアップデータはAES-256で暗号化し、長野県のデータセンターで大切に保管します。設定により、お客様のHDDやNASに保存することもできます。もちろん、マルウェア対策にも優れており、セキュリティソフト(ウイルス対策ソフト)の機能を担う「アクティブプロテクション」によって、Petya、WannaCry、Osirisなど最新のランサムウェアからもシステムとデータをしっかり保護します。
ランサムウェアに感染!アクティブプロテクションを使用した場合/使用しなかった場合の、検証ビデオはこちら
使えるクラウドバックアップの別の特徴として、管理者のアカウントから社内の別デバイスを一元管理できる機能があります。デバイスの環境整備や異常が発生した際の対応が手元で行えるため、時間とコストの節約になるばかりか、業務効率化と迅速な対応が可能です。
加えて、近年の悪質なサイバー攻撃に対処するためのエンドポイントセキュリティ「EDR」や「XDR」の導入も可能です。「アドバンストセキュリティ+XDR」はわずか330円/月(税込)です。
ウイルスチェックやパッチ管理など、バックアップの多彩な機能について知りたい方はこちら
クラウドバックアップの導入をご検討中の方は、是非ご相談ください。多層のセキュリティ対策、最新の技術を備えているため、自社で整備するよりもコストパフォーマンスが高く、安心してご利用いただけます。
オンラインでのご案内、自社の状況に合ったプランのご提案、お見積りも可能です。お客様のご予定で30日間無料トライアルを実施していますので、使い勝手や自社の業務との相性をお確かめください。トライアル後そのまま本契約に移行可能です。
大企業、中小企業を問わず、競争力を高めるための投資として使えるクラウドバックアップをご活用ください。
.jpg)
(1)クラウドバックアップのメリットは?
クラウドバックアップのメリットには以下の点があります。
・コストを抑えられる
・BCP対策として有効
・アクセス管理が容易
・容量を柔軟に増やせる
1. コストを抑えられる
ローカルバックアップ(HDDなどのローカルデバイスを使用したバックアップ)を行うためにはさまざまな費用が必要です。その点、クラウドバックアップならサーバの設置などの導入コストだけでなく、専門スタッフの常駐など運用にかかるコストも抑えられます。
2. BCP対策として有効
企業にとって情報は今や貴重な資産です。また、顧客情報や機密情報の厳格な管理は法的要請でもあります。災害やサイバー攻撃に直面しても、情報の流出や消失を防ぐためにクラウドバックアップは有効です。
3. アクセス管理が容易
クラウドバックアップはファイルやフォルダごとに管理を設定でき、情報の不適切な共有や拡散を防止できます。また、ファイルへのアクセスのログデータを残せるため、万が一セキュリティインシデントが発生した場合も、誰がどの時点でどこからアクセスしたのかを特定できます。
4. 容量を柔軟に増やせる
バックアップデータが増大した場合、クラウドバックアップであれば、簡単に容量を増やせます。ローカルバックアップだとサーバの増設が必要であるのに対し、クラウドサービスの提供事業者に対してプランの変更を申し入れれば完了です。
(2)クラウドバックアップのデメリットは?
クラウドバックアップのデメリットには以下の点があります。
・適切に運用しないとコストがかさむ
・セキュリティに懸念がある
・オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある
1. 適切に運用しないとコストがかさむ
クラウドバックアップは適切に利用するとコストを抑えられるのですが、運用を事業者任せにして、何も関与しないとコストがかさむリスクもあります。
クラウドバックアップサービスのコストは、利用している容量に依存しています。そのため、使用期間が長くなり、データ量が増えれば増えるほど、利用料金もかさんでいくのです。「知らない間に請求額が増えている」という事態に陥らないように、データが重複してバックアップされていないかをチェックしたり、不要なデータを定期的に削除したりする施策が必要でしょう。
2. セキュリティに懸念がある
クラウドバックアップのセキュリティはサービスの提供事業者に委ねることになります。そのため、自社で管理できない領域でのセキュリティインシデントの発生を懸念する人がいるかもしれません。不安を解消するためには、クラウドバックアップの提供事業者のセキュリティ対策についてしっかり理解しておくことが大切です。
3. オフィスでの他の業務に影響を与える可能性がある
クラウドバックアップを実行することで、通信の帯域圧迫や他の通信機器に負荷をかける可能性があります。結果として、機器の動作や通信速度が遅くなり、業務効率が低下する懸念もあります。この事態を避けるためには、導入前にテストしておくことが不可欠でしょう。
(3)バックアップしないと起こるリスクは?
バックアップしなければ、企業の情報資産が流出したり、消失したりする恐れがあります。さらに具体的にいえば、バックアップせずにデータが失われてしまった場合、企業は4つのリスクにさらされることになります。
・法的責任を問われるリスク
・企業の競争力低下
・社会的信頼の失墜
・営業活動が停止する
1. 法的責任を問われるリスク
企業が保有するデータの管理に関しては法的責任を問われる場合があります。例えば、業務に関わる電子データはe-文書法や日本版SOX法などにより、保護を確実にすることが求められています。
また、個人情報の安全管理措置は法令によって義務化されています。もし、バックアップをせずに個人データが復旧できないとなると、適切な管理がなされていなかったとみなされ、法的責任を問われる可能性があります。
2. 企業の競争力低下
企業のマーケティングや戦略策定においてデータの存在感はますます大きくなっています。データの量と価値は増大し続けているため、データを損失することは企業の競争力低下に直結します。
3. 社会的信頼の失墜
データは自社が保有しているだけでなく、他社とやりとりするものです。そのため、データが失われてしまうと、取引先との業務や子会社とのやりとりも停止することになります。ランサムウェアや災害など、自社にとっては予測できなかった事態だとしても、バックアップさえしていればデータを復旧できます。しかるべき措置をしていなければ、自社の管理体制や経営姿勢に対する疑義を生み、信用は低下し、社会的信頼も失墜する可能性があります。
4. 営業活動が停止する
近年の企業活動はITシステムに大きく依存しています。在庫管理や営業支援、コミュニケーションツール、ECサイトなど、ありとあらゆる業務がシステムを通じて行わているのです。こうしたシステムはデータによって機能しているため、データが失われれば、広範囲にわたり業務が停止状態に追い込まれてしまうでしょう。企業活動が停止すれば、その間の逸失利益は膨大になります。
これらのデータがローカルサーバだけにしかなければ、災害などで物理的に破壊された場合、ビジネスは大きなインパクトを受けます。この点、クラウドバックアップでは遠隔地にデータを保管できるため、オフィスが仮に被害を受けてもデータを保護することが可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
その便利さや手軽さから、企業の間でもクラウドサービスを導入する事例が増えています。データを安全かつ手軽にやり取りするために欠かせないファイル共有サービスに関しても、近年ではクラウドソリューションを選択するケースが多くなってきました。
ビジネスに様々な恩恵をもたらしてくれるクラウドコンピューティングサービスですが、やはり気になってしまうのがセキュリティ。クラウドを利用するメリットは理解しつつも、「セキュリティや使い勝手が心配で導入に踏み切れない」という方もいるのではないでしょうか。
クラウド導入にあたっては、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。今回は、クラウドサービスのメリットとデメリットについて解説した上で、クラウドベースのストレージサービスを選ぶときに必ずチェックしておきたい、セキュリティ上の3つのポイントをまとめてみました。
法人向けクラウドストレージのおすすめを知りたい方はこちら
目次
クラウドサービスのメリットとは?
クラウドサービスのデメリットとは?
データセンターの安全性
サーバの管理体制
データ転送の暗号化
使えるファイル箱で簡単・安全にクラウドを導入
FAQ

クラウドソリューションには多くのメリットがありますが、ここでは代表的な3つのメリットについて取り上げます。
いつでも、どこからでもアクセスできる
従来のオンプレミス型のファイルサーバは社内LANによって構築されており、社外からのアクセスは想定されていません。それに対してクラウドサービスであれば、インターネット経由でデータを共有します。そのため、リモートワークで自宅で勤務していても情報共有や共同作業が簡単に行えます。
また、社外からのアクセスが可能なため、社員以外の取引先とも大容量のファイルの共有が可能です。多くのクラウドサービスではファイルごと、フォルダごとに権限設定ができるため、情報セキュリティの観点からも安心です。
コストを抑えられる
一般的にファイルサーバ構築のためにはハードウェアとしてのサーバ購入に加えて、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどハードウェア環境、さらにはソフトウェアのインストールや設定が必要です。サーバの購入費用だけでも最低でも20~30万円かかりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えます。それに加えて、他のハードウェアを購入し、ソフトウェアの設定をしなければなりませんから、初期コストだけでも中小企業にはかなりの負担になります。
それに対して、クラウドサービスであればハードウェアを購入する必要はなく、従業員数に合わせてプランを選択し、月額の利用料金を支払えば低コストで使い始めることができます。
BCP対策になる
BCP対策とは、「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもので、「事業継続計画」と訳されます。つまり、企業が災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面したときに被害を最小限に押さえ、事業を継続できるようにするために行う対策や計画のことです。
企業にとって情報の価値はますます高まり、中には顧客情報などの機密情報も含まれています。そのため、情報漏えいや消失を防ぐために企業がいかなる対策をとるかは、投資家などのステークホルダーにとっても大きな関心事の1つといえるでしょう。
ファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが被害を受ければデータも失われてしまいます。それに対して、クラウドストレージのデータセンターは災害や火災、停電にも耐えうる堅牢な設計であり、安全にデータを保管できます。その点でクラウドストレージはBCP対策の一環としても優れているといえるでしょう。
BCP対策について詳しく知りたい方はこちら
クラウド導入でDX化推進を検討している方はこちら

導入に多くのメリットがあるクラウドサービスですが、以下のようなデメリット、注意点もあります。ここでは2つ取り上げます。
カスタマイズに限界がある
クラウドサービスのデメリットの1つは、オンプレミス型のファイルサーバに比べてカスタマイズに限界がある点です。
上述したようにローカルファイルサーバの場合、ハードウェアの購入からソフトウェアのインストール、システムの構築まで自社のニーズに合わせて自由に行えます。それに対して、クラウドサービスはストレージ容量やユーザ数、セキュリティレベルに基づいてプランを選択できるものの、細かな設定には限界があり、ファイルサーバには及びません。
セキュリティ対策が必要
クラウドサービスの提供事業者はサイバー攻撃に対処するための自動アップデートなど、24時間体制でセキュリティ対策を行っています。といっても、セキュリティ対策はすべて任せて、自社では何もしなくて良いというわけではありません。
特に人為的なミスによってセキュリティリスクが発生しないように、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関しては社内で明確なルールをつくり、周知徹底することが必要です。
また、クラウドサービスを選ぶ際には以下の3つのポイントに注意して導入することをおすすめします。
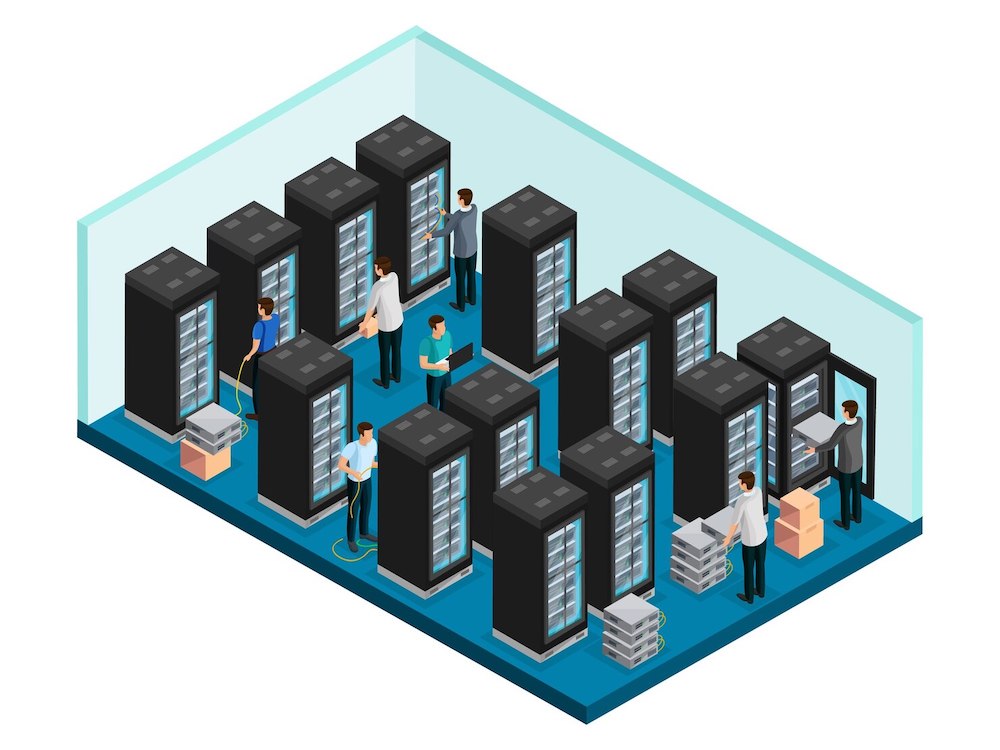
クラウドサービスを利用すると、データはサービス提供事業者のデータセンターに保存されることになります。セキュリティのことを考えると、データセンターの安全性、セキュリティ対策を確認することがとても大事なポイントになってきます。
具体的には、日本データセンター協会が制定した「データセンター ファシリティスタンダード」を参照するのも1つの手です。これは、グローバルな実情に合わせて作成された基準を、地震が多いなど日本の実情に合わせて改良したものです。
ティア1~4ごとに基準が設けられているので、データセンターのサービスレベルを測る1つの基準になります。
データセンターの立地については国内と国外のどちらが良いのか迷われると思いますが、二者択一というより、それぞれに一長一短あります。使えるねっとの国内データセンターは長野県にあり、その位置や地勢などから自然災害の影響を受けにくいエリアだといわれています。また前述のデータセンター ファシリティスタンダードでもティア3レベルの基準があります。
ティア3
・ 地震や火災など災害に対して、一般建物より高いレベルでの安全性が確保されている。
・ 機器のメンテナンスなど一部設備の一時停止時においても、コンピューティングサービスを継続して提供できる冗長構成の設備がある。
・ 建物およびサーバ室へのアクセス管理が実施されている。
・ 想定するエンドユーザの稼働信頼性:99.98%以上
ロケーションによりデータ転送速度も相違
また、データセンターのロケーションはデータの転送速度にも影響を与えます。クラウドであれば、自社のデータを世界中どこにいても同じように取り出し、処理できると思われるかもしれません。各サービスの特性により仕様は多少異なりますが、データは実際の物理的なロケーションに保存されているため、「データのロケーション」が国内か国外か、あるいはどのくらい離れているのかが重要なポイントとなる場合もあります。

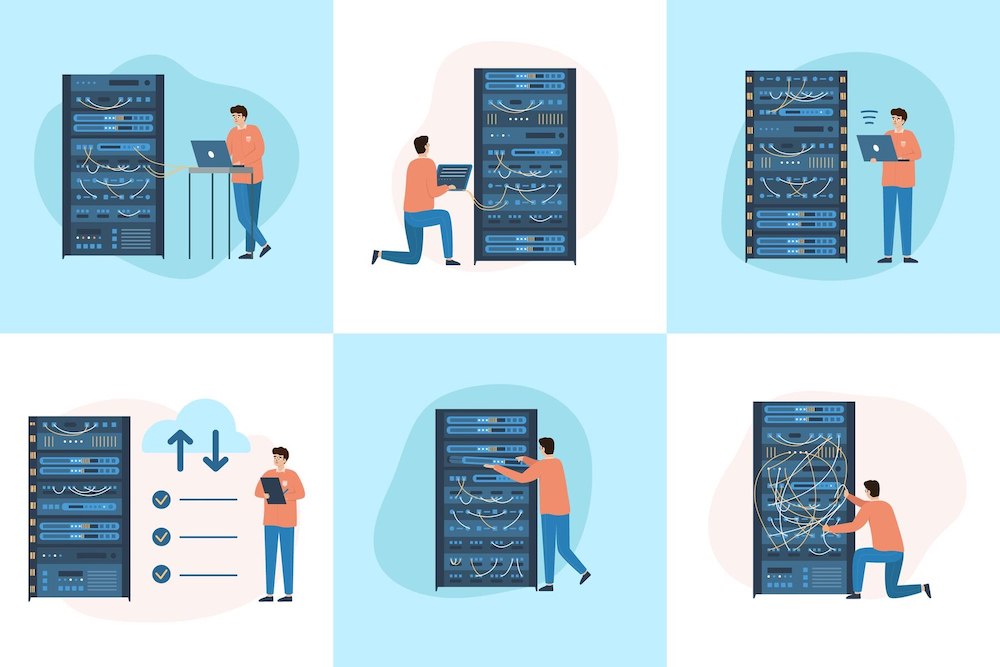
ファイルを保管するためのサーバをどのように管理しているのかは、事業者によってそれぞれ異なります。
外部への情報漏えいリスクを避けるためには、情報セキュリティ対策が万全で、ネットワークの冗長化ができているサービスを選ぶことが最善だと言えます。
使えるねっとは24時間体制のサポート&セキュリティ対策が万全
使えるねっとでは10時から17時まで、オペレーターへの電話やチャットサポートにてサービスに関する疑問や質問を受け付けています。もちろん、メールでのお問い合わせもいつでも可能。加えて、サーバトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間受け付けています。
また、使えるねっとはISO27001(ISMS)認定の万全なセキュリティ対策に加え、ネットワーク冗長、自家発電設備など20年以上のホスティングサービス提供の経験を生かし、最高基準のセキュリティポリシーで安定運用を実現しています。

クラウドサービスのセキュリティにおいて必須ともいえるのが「暗号化」です。データをそのままの生の状態で転送するのではなく、暗号化と呼ばれる技術によって保護することにより、情報の機密性を保つことができるのです。
データを保管・転送するときにはそれぞれ暗号化技術が必要になりますので、利用するサービスがきちんと対応しているかどうか忘れずに確認しておきましょう!
AES-256ビット暗号化(高度な暗号化)とは?
一口に「暗号化」といってもさまざまな方法があります。その1つがAESです。AESとは「Advanced Encryption Standard(先進的暗号化標準)」の略で、米国国立標準技術研究所が公募の結果、2001年に承認した技術で、現在に至るまで通信データの暗号化アルゴリズムとして標準的に使用されています。
これは「共通鍵暗号方式」と呼ばれ、同じ暗号鍵を使用して暗号化と復号(暗号化されたものを元に戻す)を行う方式を採用しています。この場合、暗号化と復号に使う暗号鍵のデータが長ければ長いほど安全性が高くなります。この暗号鍵の長さを「鍵長」といい、一般的に「bit(ビット)」で表されます。
AES登場前はDESと呼ばれる暗号化方式が標準でしたが、その鍵長は56bitと短く総当たり攻撃に弱いのが弱点でした。それに対してAESは128、192、256bitの中から鍵長を選べます。つまりAES自体、2024年時点でもっとも安全性の高い暗号化技術ですが、その中でも鍵長が一番長いAES-256ビット暗号化は現時点で最強の暗号方式ということなのです。AES-256ビットの解読には、最高の計算速度を誇るコンピュータでも数百兆年かかるといわれるほどです。
使えるファイル箱ならセキュリティも万全で安心
使えるねっとが提供している法人向けファイル共有サービス「使えるファイル箱」はAES-256ビット暗号化を暗号化アルゴリズムとして採用しています。それだけでなく、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も行っており、万全のセキュリティ対策で安心です。

.png)
クラウドの導入では、安心・信頼できるサービスを選択することが一番大切なことかもしれません。データ管理体制がしっかりしているサービスを利用すれば、セキュリティを心配することなくクラウドの利便性を最大限活用できます。
「使えるファイル箱」は、セキュリティを第一に考えた厳重な体制でデータを管理しています。サーバは自社国内データセンターで熟練の専属スタッフが運用し、お客様のデータを保管から転送まで最新の暗号化技術できっちり保護。セキュリティ面にとことんこだわったサービスですが、ユーザ数無制限、大容量1TBで月単価21,230円(税込、1年契約)から導入していただけます。コストパフォーマンスの高さも大きな魅力といえるでしょう。
30日間の無料トライアルも実施しておりますので、クラウドストレージサービスの導入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
クラウドストレージについて知りたい方はこちら
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
使えるファイル箱についてさらに知りたい方はこちら
(1)クラウドが普及しない理由は何ですか?
クラウド導入が進む一方、さまざまな理由でクラウドサービスの利用を躊躇する企業も少なくありません。その理由として考えられるのは、業務で電子的にデータを管理したり、共有したりする必要性を感じないという点に加え、セキュリティリスクの懸念を挙げる企業もあります。
(2)クラウド導入とは何ですか?
クラウド導入とは、企業の基盤システムやデータ管理をクラウド上で行うように整備することです。従来のオンプレミス型のファイルサーバからクラウド導入をするのは敷居が高いと感じる場合、クラウドへの完全移行ではなく、オンプレミスとの併用を選択する企業もあります。
(3)クラウド導入にかかる期間はどのくらいですか?
ローカルでサーバシステムを構築する場合、自社環境に合わせてカスタマイズすることは可能であるものの、導入には長い時間がかかります。それに対して、クラウド導入にかかる時間は圧倒的に短くて済みます。例えば、使えるファイル箱であれば、最短で即日からのご利用も可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
2011年6月にリリースされ、Word、Excel、PowerPoint、Exchange Onlineといったツールをクラウドベースで便利に使えるサブスクリプション型オフィススイート「Office 365」。現在ではOffice 365をさらにパワーアップさせた「Microsoft 365」を使っている企業も多いのではないでしょうか?生産性向上や働き方改革にもつながる、いまやあらゆる業務に不可欠なツールですが、気になるのが作業データのバックアップについてです。
この記事では、Microsoft 365のバックアップが必要な理由やメリット、さらには復元方法までご紹介します。
クラウドバックアップについて知りたい方はこちら
目次
Office 365(現:Microsoft 365)とは?
なぜOffice 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップを利用するのか?
Office 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップの必要性とは?
データバックアップの範囲
Office 365(現:Microsoft 365)のバックアップツールの選定のポイント
Office 365(現:Microsoft 365)向け!おすすめデータ保護対策のアプローチ3つ
Office 365(現:Microsoft 365)のメリットを享受しつつ、データを自社でコントロールする方法
使えるクラウドバックアップ「Microsoft 365プロテクション」
使えるクラウドバックアップ「Microsoft 365プロテクション機能」の紹介
FAQ
Microsoft 365とOffice 365は「名称が変わっただけで全く同じ製品」と勘違いしている方もおられるようですが、実はそうではありません。
Microsoft 365は2020年4月にMicrosoftからリリースされたクラウドサービスであり、Office 365の機能に加え、Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive for Business、Microsoft Teamsなど、オンラインでのプロジェクト管理を活性化するツールが含まれています。加えて、Microsoft OSやライセンス、業務アプリ一式をまとめて管理できるため、より高度な一元管理が可能です。
多くの企業がテレワークを導入しているため、時間や場所を越えてコミュニケーションし、情報を共有する上でMicrosoft 365は単なるビジネスアプリケーションを超えて、今や欠かせないビジネスプラットフォームになっています。
クラウドストレージ比較おすすめ12選!無料の容量が大きいものから機能重視型まで について知りたい方はこちら

Microsoft 365のバックアップと聞くと、「クラウドにデータが保存されているんだから、バックアップなんていらないのでは?」「サービス側できちんとバックアップしてくれているんじゃない?」と思うかもしれません。ここではMicrosoft 365のバックアップが必要な理由を説明します。
働き方が変化してOffice 365(現:Microsoft 365)やコラボレーションツールの利用が増加
上述したようにMicrosoft 365は2020年4月に登場しましたが、その背景の1つに新型コロナウイルス感染対策として導入が進んだリモートワークがあります。オフィスだけでなく、遠隔での共同作業が増える中で、Microsoft Teamsの利用数は一気に増加し、2019年11月時点では2,000万人だったのが、2022年1月には月間アクティブユーザーは2億7,000万人まで増加しました。それに伴ってオンラインでやりとりされるデータ量の増加も留まるところを知りません。
Microsoft 365のデータを定期的にバックアップしておかなければ、失われるデータ量もはかり知れず、ビジネスに与えるインパクトも甚大なものになるでしょう。
サービス側で利用者のデータは保証されていない
データバックアップが必要な最大の理由は、Microsoft 365は利用者のデータ保護を保証していないことです。「クラウドサービス=自動的にバックアップ」ではないのです。
実際、Microsoftのサービス規約には、「損失に一切の責任を負いません」「データの取得ができなくなることがあります」などと明記されており、第三者のサービスを利用しデータを保存することを推奨しています。
さらに、Microsoft 365の利用者データの保持期間にも制限があります(詳細は後述)。アカウント削除後、30日後にはデータまで削除されることになっており、長期間におよぶ監査作業や証拠保持が必要なコンプライアンス対策には向いていません。
ちなみにゴミ箱データの保持期間は以下の通りです。最大でも3カ月で、思ったより短いことが分かります。
|
データの保管場所
|
保持期間
|
|
Exchange Online(削除済みアイテムフォルダ)
|
30日
|
|
Exchange Online(削除済みアイテムフォルダから
削除されたアイテム)
|
14日
|
|
SharePoint Online
|
93日
|
|
OneDrive
|
93日
|

確かにクラウドサービスであるMicrosoft 365によってビジネスの生産性は向上しました。しかし、バックアップの必要性についていえば、これまでのオンプレミス環境と大きく変わったわけではないということです。どんな形でデータを保管しているかに関わりなく、ビジネスは日々データを失うリスクと常に隣り合わせであることを認識しましょう。
代表的なリスクには以下のようなものがあります。
利用者のヒューマンエラー(人為的なミス)対策
端末を操作するのは人間であり、必ずミスをするため、利用者のヒューマンエラーによるデータ消失リスクをゼロにするのはほぼ不可能です。ゼロどころか、アドバンスデザインの調査によると、サーバにおけるデータ消失トラブルの原因の30%は人為的ミスだといわれています。
外部のサイバー攻撃や感染リスク対策(ランサムウェアなど)
帝国データバンクが2022年3月に1,547社を対象に行ったアンケートによると、直近1ヶ月以内にサイバー攻撃を受けた企業は28.4%に及び、1年以内に受けた企業は36.1%にも上りました。
例えば、2024年6月にKADOKAWAが大規模なサイバー攻撃を受け、グループ会社の多くのサービスが使えなくなりました。特にニコニコ動画などの数百ものシステムが連携するサービスをほぼ一から作り直す必要に迫られ、復旧するまでに約2カ月を要しました。加えて、合計25万人の個人情報も漏えいしたとのことです。
これほど大規模なサイバー攻撃ではなくても、企業は巧みなメールや添付ファイルの脅威に絶えずさらされています。定期的なバックアップを取っておけば、仮に感染してもデータの復元が可能であり安心です。
ランサムウェアとは何かを知りたい方はこちら
退職者の嫌がらせなどのリスク対策
Microsoft 365を使用していた従業員が退職する場合、退職者のアカウントは削除することでしょう。しかし、Microsoft 365の場合、アカウントが削除されると、そのユーザーと紐づいたデータも一定期間を経て削除されてしまいます。
多くはないかもしれませんが、退職者が企業や在職従業員に対して嫌がらせをしていたことが明らかになったとき、退職者のメールなど証拠はすでに自動的に消去されてしまっています。こうした事態を回避するためのリスクマネジメントにもバックアップは有効です。
有事の監査などコンプライアンス対策
バックアップデータは企業コンプライアンスの観点からも重要といえます。例えば、税務当局の突然の監査にもバックアップデータにより財務データが残っていれば、求められる資料をすぐに提出できます。
また、ライバル企業から訴訟を提起されることもあり得るでしょう。過去の企業活動について適法性を証明する詳細な資料にすぐにアクセスできれば、企業の利益を保護できます。
障害発生時の重要データ損失リスク対策
企業の重要データを格納しているデータベースシステムもいつ障害が発生するか分かりません。災害などの物理的破損に加え、サーバ障害によるメモリ上のデータ消失や、ネットワーク障害によるトランザクションの異常終了などが考えられます。
クラウドのBCP対策について知りたい方はこちら
Office 365(現:Microsoft 365)のデータバックアップの範囲とは
上述したように、Microsoft 365はデータの保護を保証していません。しかし、同製品にバックアップ機能が搭載されていないかというと、そういう訳ではありません。ただ、標準搭載されているバックアップ機能には限界があるため、利用の際には注意が必要です。主な注意点は次の通りです。
Office 365(現:Microsoft 365)標準のバックアップ機能では「できないこと」
Microsoft 365でデータを削除しても、実際に完全に削除されるわけではありません。「削除済みアイテム」または「ゴミ箱」にファイルが残っており、復元できるからです。それらのフォルダが完全に空になれば、データも完全に削除されます。
Office 365(現:Microsoft 365)データバックアップの設定方法
①Windows通知領域に表示されるクラウドアイコンを選択して「OneDriveのヘルプと設定」→「設定」へと進みます。
②「同期とバックアップ」タブに移動します。画面でバックアップするフォルダを選択します。
.png)
③「バックアップの管理」を選択します。
④フォルダのバックアップを開始するには、「バックアップされていない」と表示されている任意のフォルダを切り替えて、「変更の保存」を選択します。

※参考:Microsoftサポートページ
Exchange Onlineのバックアップとは
Exchange Onlineはクラウド型のメールサービスです。
Exchange Onlineのデフォルトバックアップ範囲
Exchange Onlineのゴミ箱機能は2層になっており、画面から操作し、メールや予定を削除すると、一旦「削除済みアイテム」フォルダに移ります。「削除済みアイテム」のデータはいつでも復元可能です。
Exchange Onlineのバックアップ機能では「できないこと」
しかし、「削除済みアイテム」からも削除した場合、14日間の保持期間を経て、データは完全に消去されます。ただし、管理者は保持期間を最大30日まで延長することが可能です。
SharePoint Onlineのバックアップとは
SharePoint Onlineはファイル・情報共有サービスで、社内でポータルサイトを作成できます。どの端末からでも簡単にファイルにアクセス、編集可能です。
SharePoint Onlineのデフォルトバックアップ範囲
SharePoint Onlineでサイトを削除した場合、サイト上のすべてのデータはゴミ箱内に93日間保持されます。
SharePoint Onlineのバックアップ機能では「できないこと」
サイトを削除した場合、サイト上の特定のデータだけを復元することは原則としてできません。つまり、1つのデータを復元するためにはサイト全体の復元が必要なのです。

Microsoft 365にバックアップ機能は標準搭載されているものの、リスクマネジメントの観点からは別にバックアップツールを選定し、導入しておくことがベストでしょう。選定のポイントを挙げます。
Office 365(現:Microsoft 365)のデータ保護に対するビジネス要件を確認する
重要なのは導入コストが安いかどうかだけでなく、データ保護に対するビジネス要件を満たすかどうかです。
その中にはいくつかのポイントがありますが、RPO/RTO(目標復旧時点/目標復旧時間)が実現できるかに注目しましょう。簡単にいえば、RPOとは「過去のどの時点までのデータを復旧させるか」の目標値であり、RTOとは「障害が発生した際、いつまでに復旧させるか」の目標値を指します。RPO/RTOが短ければ短いほど、更新の頻度は高いですが、コストが高くなりますし、業務トラフィックにも影響を与えてしまいます。
ほかにもクラウドサービスで大規模な障害が発生した場合、オンプレミス環境からハイブリッドに切り替えられるか、また今後長期にわたってサービスを使用し続けられるかどうか、運営会社の信頼性も考慮しておく必要があります。
まとめて組織全体のデータ保護運用
Microsoft 365には、Exchange Onlineのメール・連絡先、添付ファイルや、OneDriveのファイル・フォルダ、SharePoint Onlineのポータルサイト、Teamsのチーム内で共有されるメールデータ、カレンダーデータなど、組織全体のデータが含まれています。これらを包括的に、かつ保持期間の拘束なしに設定し、保護運用できるのが理想です。
Cloud to Cloud:クラウド上でのバックアップ
オンプレミスではなく、クラウド上でバックアップすることには多くのメリットがあります。自社でサーバを設置したり、専門的な保守、運用をしたりする必要がなく、コストを抑えることができます。また、拡張などのカスタマイズも自由に行えます。
オンプレミスとは何かを知りたい方はこちら
クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
アーカイブ:メールの長期保管
メールの長期保管により、有事の際の監査など、企業のコンプライアンス対策としても有効です。

Microsoftのクラウドサーバだけに依存することは、自社データの完全なコントロールを会社が握れないことを意味します。昨今重要性が高まっている個人情報保護、コンプライアンス・監査対応などの観点から考えると、これはエンタープライズだけでなく、中小企業にとっても好ましくない状態だと言わざるを得ません。
そこでデータ損失リスクに対応しつつ、自社での完全なデータ管理を実現するために、Microsoft 365のデータもMicrosoftのクラウドサーバとは別のサーバにバックアップしておく必要があるのです。
使えるねっとが提供する「Microsoft 365プロテクション」はMicrosoft 365のメール、ファイル、フォルダなど全てのデータを完全に保護します。簡単なセットアップが完了すれば、全てのメール、すべてのファイルはクラウドに直接バックアップされ、貴重なデータはファイルロスの危険から守られることになります。情報セキュリティの観点から「Microsoft 365プロテクション」は非常に心強いサービスといえるでしょう。

「Microsoft 365プロテクション」は上述した3つのアプローチを満たす理想的なソリューションで、以下のような機能を備えています。
・Exchange、OneDrive、SharePointの全ファイルは長野にある使えるねっとの自社データセンターに直接バックアップ。エージェントを介さない「エージェントレスバックアップ」のため、ユーザーの機器上で他のプログラムは必要とされず、迅速かつシームレスな利用が可能。
・アクロニス社開発の直感的なインターフェイスでバックアップ・復元の進行状況を一目で確認できるだけでなく、ステータスに関する通知メールを送信することも可能です。
・様々な条件を設定し柔軟な復元が可能。またバックアップしたメールやファイルは日付、ファイル名、受信者、送信者など様々な項目による高度な検索が可能。ワード検索や部分一致による検索もできます。
完全にクラウドベースのため、開始時のセットアップ費用や高額な機器購入は不要です。具体的なサービスや費用については、お気軽にお問い合わせください。
Microsoft 365プロテクションの詳細はこちら>>
.jpg)
(1)Microsoft Teamsの特徴とは?
Teamsは多くの企業でビデオ会議やチャット機能などコミュニケーションツールとして活用されています。しかし、それだけでなく、Microsoft 365ツールと連携し、一元管理できる点も魅力です。例えば、Outlookと連携することで予定を効率化したり、ExcelやPowerPointの共同作業や管理をしたりすることも可能です。
(2)使えるクラウドバックアップを使うメリットは?
使えるクラウドバックアップは、初期費用不要で簡単に導入できる完全クラウド型バックアップソリューションです。多くのサービスではバックアップとウイルスチェックは別契約ですが、使えるクラウドバックアップはデータを守る・使うための機能を一つにまとめた一体型のソリューションです。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
クラウドサービスを選ぶ際に気になる点はいろいろとあります。導入コストやセキュリティも重要ですが、決め手になるポイントの一つは容量ではないでしょうか?DX(デジタル技術によって経営やビジネスプロセスを再構築すること)が進む中、企業間で転送・保管するデータは増加する一方です。
大容量と聞くと何となく「TB(テラバイト)」は大きそうだな…と連想されますが、実際どのくらいの量のファイルを保存できるのかイメージがわきづらいのではないでしょうか。そこで、今回の記事ではTB、GBなどストレージの容量にスポットライトを当てて、保存できるデータの量と人気のストレージサービスの容量設定について解説します。
クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
クラウドバックアップについて知りたい方はこちら
目次
1TB(テラバイト)とは?GB、TB、実際の容量別に解説
クラウドストレージサービスで一般的な容量設定
大容量データが必要な場合とは
業務で大容量データを使用する場合の例
クラウドバックアップサービスで一般的な容量設定
使えるファイル箱を導入した事例を紹介
使えるクラウドバックアップを導入した事例を紹介
使えるファイル箱で容量ニーズと高度なセキュリティ要件を両立
FAQ
1TB(テラバイト)とは1,000GB(厳密には1,024GB)のことです。具体的には1TB(テラバイト)の録画時間はフルHD動画で約166時間に相当します。しかし、容量が大きければ大きいほど良いわけでもありません。なぜなら、大きくても使い切れないこともあるからです。大切なのは、自社のユーザ数や業務形態に合わせて選ぶことです。
企業規模や業種に関わりなく、業務データの大容量化が進んでいるため、クラウドストレージサービスの導入が必須といえるでしょう。この点、使えるファイル箱なら1TB(追加も可能)、ユーザ数無制限で安心です。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
ノートパソコンのハードディスク(HDD)1TB搭載容量とは
デスクトップパソコンに比べ、ノートパソコンには大型のHDDを搭載することは難しく、128GB(ギガバイト)、256GB、516GB、1TBなどが主流といえるでしょう。ただ、近年個人が扱うデータも大容量化しているため、hddで1tbか2tbのどちらか迷ったり、ノートパソコンでも1tbは必要と考えたりする人も増えています。そうしたニーズゆえに1テラのハードディスクの価格も以前では考えられないくらいリーズナブルになりました。
データの基本単位は1バイトで、厳密にはその1,024倍で次の単位に移行しますが、1テラは何ギガかといえば、1,000ギガと覚えておいて問題ありません。
・1,000B(バイト)=1KB(キロバイト)
・1,000KB=1MB(メガバイト)
・1,000MB=1GB(ギガバイト)
・1,000GB=1TB(テラバイト)
最近ではHDDより読み書きの速度が速く、衝撃に強いSSD(ソリッドステートドライブ)も普及しています。ただ、HDDよりも価格が高く、容量も少な目のものが多く、ノートパソコンに内蔵しているSSDは240〜500GBが大半のようです。
各メディアに換算した場合の容量比較
1TBが大容量ということは分かっても、数字だけではイメージがわきにくいと思います。以下では身近なメディアに換算してその大きさを具体化してみましょう。
.jpg)
デジカメ写真の1TBとは?
→1枚4MBのJPEG画像ファイル約25万枚
スマホの1TBとは?
→1台100GBのスマホ約10台
動画録画時間の1TBとは?
→フルHD動画ファイル約166時間、4k映像の録画時間は1tb=約65時間
音楽の1TBとは?
→1曲5MBのMP3音楽ファイル約20万曲
文庫本の1TBとは?
→1冊100MBの文庫本約10,000冊
いかがでしょうか?1TBの大きさがどのくらいか何となく分かっていただけたかと思います。
それでは、使えるねっとが提供しているようなクラウドストレージサービスでは一般的にどのような容量設定なのかを見てみましょう。各企業ともさまざまなプランを用意していますが、以下では法人向けのスタンダードなプランを例に比較してみます。
| |
容量
|
料金
|
備考
|
|
A社
|
2TB/ユーザ
|
1ユーザ/月1,360円
|
4ユーザ以下の
場合は1TB/ユーザ
|
|
B社
|
5TB
|
1ユーザ/月1,250円
|
3ユーザ以上
|
|
C社
|
無制限
|
1ユーザ/月3,000円
|
アップロード上限
5GB
|
|
D社
|
100GB
|
66,000円
|
10ユーザ分
|
|
E社
|
500GB
|
50,200円/月
|
2ユーザの場合
|
|
使えるファイル箱
|
1TB
|
21,230円(税込)/月
(1年契約の場合)
|
ユーザ数無制限で料金は固定
|
上表から「使えるファイル箱」が他社に比べて必要十分な容量を備えており、料金体系がシンプルであることが分かります。また、圧倒的な魅力はユーザ数無制限です。
容量は大きければ大きいほどよいのか?
上記表では容量と料金だけを比較していますが、お気づきのように業界大手の容量設定は無制限のサービスも含めて増加傾向にあります。ただ、料金は1ユーザごとの設定がほとんどであることに注意が必要です。
ポイント1:ユーザごとの容量が多くても「使われない」ケースが大半
大手クラウドサービスのプランには1ユーザあたり2TBなど大容量のものもありますが、ある企業内の1ユーザが2TBもの容量を効率的に利用することは非常にまれでしょう(エクセルやワードを200万ファイルも保存するでしょうか…)。
一見「大きい方がお得!」に見えがちですが、実際に運用を始めるとそこまで使わない…ということが多く、費用削減のためにアカウントを共有し、ユーザ数を減らすことで対応しようとするケースが多く見られます。しかし、複数ユーザでアカウントを使いまわそうとするとやはりセキュリティ面が懸念されます(例えば、誰がデータを削除したのか分からなくなるなど)。
また、オンラインストレージの最大の魅力である「フォルダ毎、ユーザ毎に誰が何を閲覧、編集できるかを一元管理できる」メリットが失われてしまいます。「重要なデータは結局部長の個人PCの中」、なんていうことが起こってしまいかねません。せっかく大容量のプランを契約しても宝の持ち腐れになってしまうだけでなく、結果として自らセキュリティの脆弱性を招いてしまうため、費用削減のためのアカウント共有はおすすめできません。
ポイント2:「ユーザ数無制限」だと容量もセキュリティ効果も両立
逆に使えるファイル箱のようにユーザ数無制限であれば、追加料金なしで全社員や取引先でフォルダを分けて、無駄なく容量を共有できます。基本プランでは1TBご利用いただけるため、中小企業のユーザ様には十分な容量です。ユーザごとにアカウントを作成し、退職や契約終了などで不要になったら削除するだけで済むため管理・セキュリティ面でも安心です。
このようにクラウドストレージサービスは容量が大きければよいというわけではなく、自社の業務内容や使用する人数、扱うデータ量や種類に合わせて選ぶことが大切です。
使えるファイル箱の初期容量が1TBに設定されているのをはじめとして、クラウドストレージサービスが大容量化しているのには理由があります。それはコロナ禍やDX推進に伴い、企業が生み出し、やり取りするデータ量が増加しているからです。
総務省の調査によると、2022年11月の国内固定系ブロードバンドインターネットサービス契約者の総ダウンロードトラフィックは約29.2Tbps*(推定)で、前年同月比23.7%増でした。
*Tbps(テラビット毎秒):1秒間に何兆ビット(1テラビット = 1,000GB)のデータを転送できるかを表す単位。
業務データの大規模化が進み、データ保管・共有ニーズが拡大
これまでは企業間のデータのやり取りはメールやFTP(ファイル転送プロトコル)が主流でしたが、転送できるデータ容量に制限があり、送信する際に圧縮や加工、分割などが必要でした。メールに添付できるデータ容量は10~100MBであるため、高画質の画像ファイルや映像を送りたい場合はほぼ不可能です。
こうしたやり取りがスムーズに行えなければ時間のロスが発生し、工期に大幅な遅れが出てしまうことになります。テレワーク導入で業務拠点がさらに増加しているため、データをどのように保存、共有していくか、この課題を首尾よく解決できなければ、企業は結果的に競争優位性を失ってしまうでしょう。
以下に具体例を挙げてみましょう。
・製造業などで設計・書類データをやり取りする場合
・海外にエンジニアやクリエイター、マーケターを抱えており、言語やOSの違いを超えて情報共有する場合
・建築・建設業において、施工者とCADデータ・図面・現場写真のやり取りをする場合
・研究所が解析した巨大な研究データを送付する場合
・デザインデータを印刷・広告会社に送信する場合
・国内メーカーが海外工場に作業手順に関する説明動画を送付する場合
いずれもクラウドストレージサービスなら共有がスピーディー、安全かつ簡単です。
.jpg)
バックアップをクラウドサービスを使って行う場合、どのくらいの容量が必要になるのでしょうか?基本的にはバックアップは端末に保存しているデータが使用できなくなった場合のためのものですから、それと同容量と見積もっておくとよいでしょう。もし、複数台の端末にデータを格納している場合、その合計の容量が必要になります。
数あるクラウドストレージサービスの中で、容量1TB、ユーザ数無制限の「使えるファイル箱」の使い勝手はどうなのでしょうか?それを知るには実際に導入した中小企業様の事例を見てみるのが一番です。以下、2つご紹介いたします。
ビジネスアプリケーション開発やネットワーク構築を行っているIT企業
トラステックは主軸である金融に加えて、交通・医療の分野にも事業展開しているIT企業です。
クラウドストレージサービスの導入にあたって、使えるファイル箱を選んだ決め手は1TBの十分な容量と固定料金制の2点だったようです。
導入後、エンジニアが客先からでもファイルを閲覧できたり、オフィスに戻らずとも資料のやり取りを行ったりできるため、交通費や移動時間の節約に繋がっていると実感しておられます。
また、ユーザ数無制限で社員だけでなく、取引先にもIDを割り当てて使えるため、システム開発など共同作業をする際にとても使いやすいとのことです。さらにファイルをすべてクラウド上で管理してもらえていることで、災害時も安心して構えていられるともおっしゃっています。
使えるファイル箱で業務効率化を達成した導入事例の全文はこちらからご覧ください。
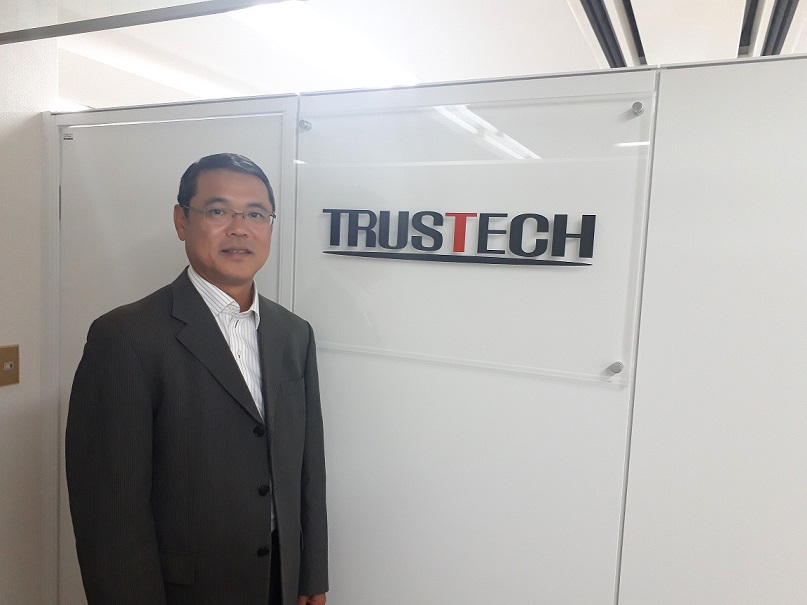
電子部品の製造や精密板金・塗装などを手掛ける老舗企業
松代工業株式会社は1958年の創業以来、電子部品および精密板金を軸にものづくりを通じて人々の豊かな暮らしや社会発展に貢献してきました。昭和・平成・令和という3つの時代を駆け抜けてきた同社は、変化に迅速に対応する先進的でチャレンジ精神旺盛な企業でもあります。
松代工業ではこれまで自社でファイルサーバを運用していましたが、日常的な運用コストだけでなく、定期的な物理サーバの入れ替えやアップデートが担当部門のリソースを圧迫していました。そうした中、ファイルサーバのクラウド化を模索し始め、最終的に「使えるファイル箱」を選択しました。
決め手になったのは、その「空気みたいに使える」使いやすさとシンプルさだったと言います。現在、同社では総務や経理に加えて、工場で発生したさまざまな品質保証データのやり取りに使えるファイル箱を活用しているとのこと。いずれは図面などの共有にも使いたいとおっしゃっていますが、余裕ある1TBの容量のため、将来性も抜群です。
1TBの導入実績に関する事例記事の全文はこちらからご覧ください。

データ容量が気になるのはクラウドストレージだけではありません。万が一に備えて利用するバックアップサービスの容量も、必要十分な大きさを選択する必要があります。
バックアップ先としてはオンプレミス(自社で保有、管理しているシステム)か、クラウドストレージが一般的です。総務省の情報通信白書(令和6年版)によると、クラウドサービスを利用している企業は77.7%(「全社的に利用している」50.6%、「一部の事務所又は部門で利用している」27.1%)で、そのうち42%が「データバックアップ」に利用していると回答しました。2019年には31.4%だったのが、5年で10%以上増加しており、データバックアップにクラウドサービスを利用する企業は今後ますます増えると思われます。
この点、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は初期費用不要で簡単に導入でき、効率的かつ安全な完全クラウド型バックアップソリューションとしておすすめです。容量は企業の事業規模や従業員数に合わせて、200GB~10,000GB(=10TB)まで選べます。
ここでは、使えるクラウドバックアップを導入した中小企業様の事例をご紹介しましょう。
全国約400社の中でトップシェアを誇るクラフトビールメーカー
株式会社ヤッホーブルーイングの基幹系システムは、サーバ1台、クライアントPC25台ほどからなるクライアント/サーバシステムで、従来NASへバックアップを取っていたそうです。しかし、バックアップの失敗が頻発するようになり、BCP対策の観点に加え、専門的な知識がなくても簡易にシステムを復元できるようにするため、2018年からクラウドバックアップを検討するようになったと言います。その際、重視したのがコストとバックアップ機能のバランスでした。
比較検討した結果、コスト面で最も優れていた「使えるクラウドバックアップ」をトライアルで使ったみたところ、操作のしやすさ、ランサムウェア対策機能が決め手になり、2019年1月から使えるクラウドバックアップの正式利用をスタートしました。
最初のフルバックアップは2時間ほどでスムーズに完了し、その後の毎日の増分バックアップも数分以内で終了すると言います。毎日のバックアップ完了をメーリングリストに通知するように設定したところ、メンバーのバックアップに関する意識も大きく向上したそうです。
使えるクラウドバックアップの導入実績に関する事例記事の全文はこちらからご覧ください。
使えるクラウドバックアップは月単価2,200円(税込)〜、用途や容量に合わせて多彩なプランから選べます。
テラバイトのクラウドストレージサービスである使えるファイル箱はユーザ数無制限で、スタンダードプランなら1年契約をしていただくと月単価21,230円(税込)でお得にご利用いただけます。
容量に関しては、WordやExcelのやり取りや保存であれば特に気にする必要はありませんが、前述したように建築会社やデザイン・動画の制作会社は専用のツールを用いて作業するため、そもそも処理するデータが大きくなりがちです。1TBの大容量であれば、個々の社員が処理するデータ量が比較的大きい場合でも安心です。
さらに大容量のデータを扱う場合にはアドバンスプランもご検討ください。容量は何と3TB、さらに以下4つの機能が追加されます。
|
IPアドレス
ホワイトリスト
|
指定のグローバルIPアドレスを登録することにより、登録外のIPアドレスからのアクセスを制限
|
|
デバイス管理
|
新しいデバイスからの初回アクセス時、管理者に通知が届き、管理者から認証された場合にのみアクセスが可能
|
|
WebDAV連携
|
WebDAVに対応したサードパーティ製のソフトウェアや、LinuxOS上で直接、ファイル箱の共有ドライブをマウント可能に
|
|
高度な共有リンク設定
|
ダウンロード回数の制限、リンク先にアクセスできる宛先を指定、閲覧のみ・ダウンロードのみ・閲覧とダウンロード両方と、設定を使い分けられる
|
アドバンスプランは1年契約の場合、月単価60,500円(税込)でご利用いただけます。
ユーザ数無制限+容量課金制でどんなユースケースでも安心
スタンダード、アドバンスいずれのプランでもユーザ数は無制限のため100人でも1,000人でも費用は固定です。データ容量は企業の成長や扱うデータ量に合わせて無制限に追加可能で(追加容量1TB/税込8,580円)、どんなユースケースでも安心。ウェブ管理画面での操作も可能ですし、普段の使い慣れたWindows、Macを使うように操作もできるため、メンバーの教育コストも不要です。まずは30日間無料のトライアルを試してみてはいかがでしょうか?
.jpg)
(1)BCP対策に「使えるクラウドバックアップ」が有利なのはなぜ?
BCP(Business Continuity Plan)とは「事業継続計画」のことで、自然災害やテロ、サイバー攻撃などの緊急事態に直面しても損害を最小限にとどめ、事業継続、早期復旧を可能にする事前計画のことを指します。使えるクラウドバックアップなら、データはデータセンターで安全に守られますし、BCP対策に有効なディザスタリカバリオプションを利用すると、万が一のときにバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替え、ビジネスを止めません。
(2)データ保管に「使えるファイル箱」が有利なのはなぜ?
オンプレミスだとハードウェアの導入やシステムの構築のために莫大な初期費用がかかりますが、クラウドストレージサービスである使えるファイル箱なら、最小限の初期費用で簡単に導入できます。また、クラウドストレージでの大容量データ管理ができるだけでなく、必要に応じてリソースの調整がしやすいこと、保守や運用の負担が軽減できる点も使えるファイル箱の利点です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
2010年以降、企業のITインフラをクラウド化する流れが一気に加速しました。しかし、ここにきて「オンプレミス」に回帰する動きが出始めています。
2023年12月にエイチシーエル・ジャパンが国内企業のマネジメント層150人を対象に実施した調査によると、全体の52.7%が「今後3年以内に勤務先のIT環境の一部を従来のオンプレミスへと移行を予定または検討中」と回答しました。
今回はクラウドと比較される「オンプレミス」とはそもそも何か、そのメリット・デメリット、および導入する際に注意すべき点についてご説明します。
目次
オンプレミスとは?
オンプレミスとクラウドの違い
オンプレミスを利用するメリット
オンプレミスを利用するデメリット
事例紹介:松代工業株式会社、オンプレミスのデメリット対策でクラウド化
オンプレミスとクラウドを導入する際のポイント
オンプレミスをクラウドに移行する際の注意点
使えるファイル箱なら、コストを抑えてデータの共有が可能
FAQ

オンプレミス(on-premises)とは、サーバやデータベース、ソフトウェアなどの情報システムを自社の施設内に導入・設置し、運用することです。現在、多くの企業が導入しているクラウドベースのシステム構築の対極にあるといえます。
現在のようにSaaS(Software as a Service)が多くの企業で利用される前は、オンプレミスが社内システムを構築するための方法でした。多くの場合、ハードウェアベンダーにサーバなどの機器を設置してもらい、SIer(エスアイヤー)と呼ばれるシステム開発会社に自社のニーズに合わせて業務システムや基幹システムの設計開発、サーバやデータベースの構築などをしてもらいます。また、導入後のシステム保守管理もそのまま外部事業者に委託したり、自社の専門部署で行ったりしていたのです。
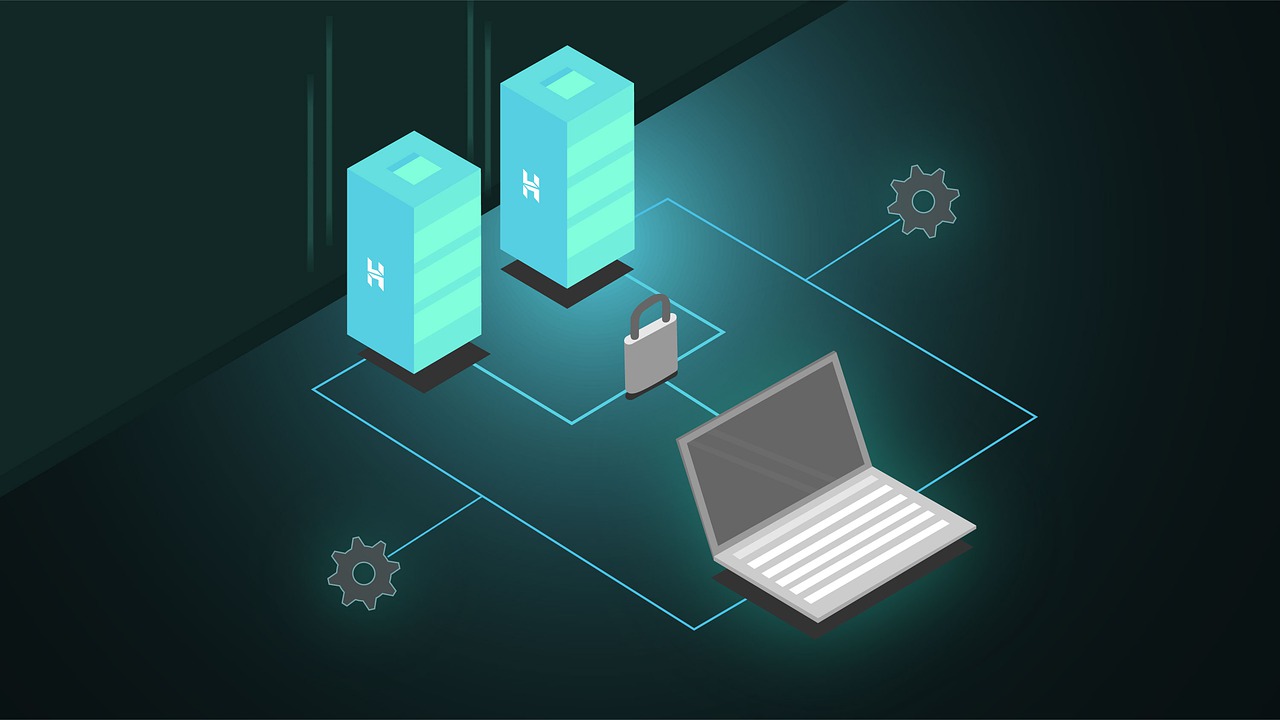
オンプレミスに対してクラウドでは、業務で利用するサービスやソフトウェア、データベースなどは自社内に格納せずに、インターネットを経由して利用します。
オンプレミスとクラウドの違いは具体的に以下のような点に表れます。
導入費用
システムの構築をオンプレミス、クラウドで行う場合、それぞれ以下のような初期コストがかかります。
|
オンプレミス
|
開発コスト、導入費、ライセンス価格
|
|
クラウド
|
ライセンス価格(サービス利用料)
|
オンプレミスでシステムを構築する場合、まずはハードウェアを準備し、基本的なソフトウェアなどを導入します。企業の業務形態によってはさらにカスタマイズをしたり、拡張機能を追加したりする必要があり、別途開発費がかかります。また、操作方法に精通するための教育費用も追加することになるでしょう。さらにライセンス価格も事業所ごと、ユーザごとに必要になります。具体的にどのくらいの費用になるかは企業規模や従業員数にもよりますが、オンプレミスの場合、初期費用が1,000万円を超えるのは珍しいことではありません。
それに対して、クラウドの場合は自社にサーバなどのハードウェアを設置する必要はありませんし、すでに製品化されたソフトウェアを使用するため基本的には開発コストもかかりません(最近ではカスタマイズできるクラウドサービスも増えています)。ライセンス価格(サービス使用料)が主なコストであり、導入後もランニングコストとして継続的に支払う必要があります。
導入までの時間
オンプレミスの場合、導入の際にサーバなどのハードウェアを選定することから始めなければなりません。そのため、ハードウェアの調達に少なくても1カ月かかりますし、ソフトウェアの開発やカスタマイズにはさらに数カ月という長い時間が必要です。導入の際の設定やテストにも手間とコストがかかります。
それに対して、クラウドの場合、申込からサーバの立ち上げまで基本的にはすべてインターネット経由で行うため、大きなトラブルがなければ数分から数時間で完了します。
操作性
「オンプレミスだから操作が複雑」、「クラウドだから簡単」と一律にはいえません。操作性は主に製品によって大きく異なります。そのため、オンプレミス、クラウド関わりなく、導入の際にはある程度の研修が必要になるでしょう。
ただ、オンプレミスは自社に合わせてカスタマイズできることから操作しやすいと考えがちですが、その逆になることもあります。つまり、細かなカスタマイズを行うことでかえって操作が複雑になる可能性があることも覚えておきましょう。
他システムとの連動性
オンプレミスは自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのが強みです。そのため、すでに自社に導入している既存のシステムと連動させやすいでしょう。
クラウドの場合、さまざまな企業のニーズに基づいて設計されているため、すでに導入している自社システムとの連動が難しい場合も考えられます。そのため、システムを統合するには「IaaS(Ingrastructure as a Service)」や「PaaS(Platform as a Service)」の導入も検討しなければなりません。
IaaSとはサーバやストレージ、ネットワークなどハードウェア環境やインフラまでを提供するためのサービスであり、PaaSとはプラットフォームや開発環境まで提供するサービスです。
セキュリティ
オンプレミスは自社独自のセキュリティ対策を講じやすく、サーバの設置場所やセキュリティ対策ソフトの導入、不正アクセスの監視など、かなり自由にカスタマイズできます。
それに対して、クラウドはオンライン上のサービスのため、オンプレミスに比べてセキュリティリスクが高いといわれることがあります。ただ、クラウドを利用する場合でも事業者によってセキュリティレベルは大きく異なるため、一律に「クラウド=セキュリティが弱い」、「オンプレミス=セキュリティに強い」とはいえません。クラウドでシステムを構築する場合は、自社のセキュリティポリシーにかなうサービスを選ぶことが大切です。
また、導入後のセキュリティ管理を誰が行うかもオンプレミスとクラウドでは異なります。オンプレミスは基本的に自社のセキュリティ部門が担当するか、外部事業者に委託するかのどちらかです。
クラウドの場合はクラウドサービスの提供事業者に委ねるため、自社で専門人材を準備する必要はなく、コスト削減につながります。それだけに、繰り返しになりますが、どの事業者を選ぶかは非常に重要な選択です。
オンプレミスとクラウドの比較まとめ
以上のオンプレミスとクラウドの比較を表にまとめてみましょう。
| |
導入費用
|
導入までの時間
|
操作性
|
他のシステムとの
連動性
|
セキュリティ
|
|
オンプレミス
|
高額
|
数カ月
|
複雑になることも
|
連動しやすい
|
ローカル環境で
安心
|
|
クラウド
|
低額
|
数時間
|
製品による
|
連動しにくいことも
|
インターネット
経由で不安も
|
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
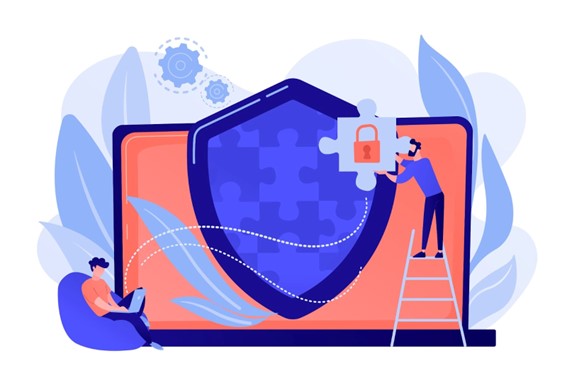
以上の比較からオンプレミスにもクラウドにも一長一短があることが分かります。ただ、冒頭で取り上げたように近年多くの企業で「オンプレミス回帰」の動きがあるのは、オンプレミスを利用するメリットが大きいからにほかなりません。
以下では、そのうちの3つを取り上げます。
カスタマイズ性に優れている
オンプレミスの最大の特徴は、自社でハードウェアもシステムもカスタマイズできる自由度の高さです。
クラウドの中にも柔軟な開発やカスタマイズが可能になるサービスが増えてきているとはいえ、拡張性の高さを考えるとオンプレミスに軍配が上がります。給与計算や労務管理、顧客管理、ストレージサービスといったどの企業にも共通するサービスでは細かなカスタマイズは必要ありませんが、中には業務の独自性が高く、パッケージ化されたサービスでは対応できない企業もあります。その場合は必然的にコストがかかるとしてもオンプレミスを選択することになります。
安全なセキュリティ構築ができる
オンプレミスは社内に設置しているローカル環境でシステム構築をしていることから、外部からのサイバー攻撃に対して比較的安全なセキュリティが構築できます。
ただ、上述したように「オンプレミス=セキュリティに強い」、「クラウド=セキュリティが弱い」という単純な図式では説明できない部分もあります。
例えば、2021年1月29日に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は「Salesforceの製品の設定不備による意図しない情報が外部から参照される可能性について」という異例の注意喚起を出しました。「Salesforce」はクラウド型のCRM(顧客管理)ツールですが、このサービスを利用する楽天やPayPay社をはじめ、多くの企業で「設定不備」によって個人情報流出が起きたのです。この事故はSaleforceがクラウドサービスゆえの脆弱性を攻撃されたというより、担当者の「設定不備」というヒューマンエラーに起因するものでした。
また、調査会社のガートナーは2019年、「2025年にかけて、クラウド上のセキュリティ事故の99%は利用者自身の設定ミスによるものとなる」と警告していましたが、まさにその通りのことが起きています。
このことはオンプレミスであっても、クラウドであっても注意深い運用があってはじめて安全なセキュリティが構築できることを示しています。
他のシステムと連動しやすい
オンプレミスはカスタマイズ性に優れていることから、自由度が高く、他のシステムとも連動させやすいといえます。ただ、その分のコストはかかることに注意が必要です。
.jpg)
初期費用が高い
上述したように、クラウドに比べ、オンプレミスに初期費用がかかることは間違いありません。ただコストは初期費用だけをみるのではなく、長期的な視野に立って考えることが大切です。
クラウドサービスの場合、初期費用はあまりかからないものの、月々のライセンス料(サービス利用料)がかかります。どのようなサービスを利用するかにもよりますが、毎月の支払いによって数年後にはオンプレミスの初期費用に追いついてしまうことも考えられます。
さらに、クラウドには多種多様な追加サービスがあります。例えば、ローカルで保管していたデータをクラウドストレージサービスに移行する場合、データが増えれば増えるほどストレージ容量を追加しなくてはならず、それに伴って費用がかかることになります。業務遂行に必要なサービスを追加していたら、いつの間にか費用がかさみ請求書を見てびっくりする、ということもあるようです。
導入までに時間がかかる
ハードウェアもソフトウェアの開発も必要としないクラウドに比べ、導入までに時間がかかるのはオンプレミスの大きなデメリットです。ビジネスにおいては、スピードが欠かせません。オンプレミスにしろ、クラウドにしろ、システムそのものが大事なのではなく、システムを使って生産性を高め、業績向上につなげることが企業の最優先課題です。
運用に専門の知識やリテラシーが必要になる
オンプレミスの運用は自社で行わなければなりませんが、専門知識を有する担当者を確保しなければなりません。
その点、クラウドであれば、運用は専門知識を持つ提供事業者に任せ、より多くの人材を本業に振り向けられます。もっとも、上述したように最低限の設定の仕方やセキュリティに関するリテラシーは自社のすべての従業員が押さえておくべきでしょう。
松代工業株式会社(本社・長野市)は、電子部品の製造や精密板金・塗装などを手がける老舗企業です。同社は、これまでオンプレミスでデータ管理を行ってきました。しかし定期的なメンテナンスや、日常的に発生する煩雑な管理が負担になり、担当部門のリソースを圧迫していました。
そんな中、本業により集中できる安心・安全なファイルマネジメント環境を構築すべく、松代工業はファイルサーバのクラウド化を模索し始めます。最終的にオンプレミスから使えるファイル箱にした決め手について、中小企業にとって「空気みたいに意識しないで使える」点だったといいます。
【松代工業株式会社様】事例の全文はこちら>>

セキュリティ重視ならオンプレミス
クラウドの場合、慎重に事業者ごとのセキュリティレベルを検証し、最終的には自分たちの側が相手のセキュリティポリシーに合わせるしかありません。この点、オンプレミスなら、自社の独自のセキュリティポリシーに基づき、コストをかけさえすれば、いくらでも厳格なセキュリティシステムを構築可能です。
オンプレミスは外部ネットワークから遮断されているため、機密度の高い個人情報を保管すれば、情報流出のリスクは最小限に抑えられます。それに対して、クラウドはインターネットをつないだ状態でしか利用できないため、常時不正アクセスやサイバー攻撃のリスクにさらされています。
とりわけ高いセキュリティを保つことが求められる金融機関や医療機関などはオンプレミスが適しているといえるでしょう。
コスト重視ならクラウド
上述したようにオンプレミスは初期費用がかかるのに対し、クラウド利用の場合も長期的にみればそれ相応のランニングコストがかかるため、どちらが「安い」とは言い切れません。
ただ、「コスト」には「人材」や「時間」も含まれます。オンプレミスの導入はもちろんのこと、運用やセキュリティ対策にも専門的な知識をもつ人材を継続的に確保しなければならず、それが難しい中小企業の場合は外部に委託することになります。
その点、クラウドは運用を完全に事業者に任せられるため、自社で選任のスタッフを持つ必要はありません。特に中小企業の場合は人材も限られているため、多方面でコストを削減できるクラウドの活用はメリットが大きいのです。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら
.jpg)
オンプレミスとクラウドのどちらが最適なのかは各企業の状況によります。完全にクラウドに移行せずに、機能によってオンプレミスとクラウドを使い分ける「ハイブリッド型」を選ぶ企業も増えています。
客観的に自社の現状を分析し、オンプレミスからクラウドに移行することを検討しているなら、以下の3つの注意点を覚えておきましょう。
データのバックアップをとっておく
オンプレミスのシステムが比較的シンプルなものであっても、移行する際には事前の準備やテストが欠かせません。しかし、予想外のトラブルが発生し、データの移行がスムーズにいかない場合もあります。データ消失のリスクを回避するために、データのバックアップは必ずとっておきましょう。
自社システムと連携できない可能性がある
既存システムとクラウドの連携がうまくいかないケースも考えられます。そうした事態を避けるためには現在の自社システムの要件洗い出しを行い、段階的に移行を行う必要があります。
カスタマイズ性に優れていないサービスがある
クラウドサービスもカスタマイズできるものが増えていますが、上述したようにオンプレミスの自由度にはかないません。そのため、クラウドに移行する際はオンプレミスと同じレベルの機能や操作性を求めるのではなく、自社にとって必要なものは何か取捨選択が必要でしょう。

オンプレミスからクラウド、あるいはハイブリッドへの移行をご検討中なら、使えるねっとのクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」もおすすめです。
使えるファイル箱はクラウドストレージサービスのメリットを最大化し、デメリットを最小化しています。3つのポイントをご紹介します。
万全のセキュリティ対策
オンプレミスに比べてやや心配になるのがクラウドのセキュリティかもしれません。この点、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムAES256ビットを採用しています。NIST(米国国立標準技術研究所)が採用している暗号技術で、AESの中でも最も安全といわれています。
また、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も採用し、ログインやウェブサーバとブラウザ間のデータ通信の安全対策も万全です。
さらにフォルダにはアクセス制限の設定も可能なため、取引先など外部ユーザとのやり取りも安心して利用していただけます。
企業の成長に合わせてユーザ数やデータ容量の調整が可能
オンプレミスはカスタマイズのしやすさがメリットですが、使えるファイル箱も負けていません。ユーザ数無制限のため、企業の成長に合わせて社員が増えても課金や権限発行に悩むことなく、自由自在に対応可能。また、データ容量も追加可能です(1TB追加で税込8,580円/月)。
高いコストパフォーマンス
クラウドストレージサービスのメリットの一つに低コストで導入できる点があります。この点、使えるファイル箱は、長く使っていただきたいので、毎月の料金も低めに設定、容量1TBのスタンダードプランなら月額21,230円(1年契約・税込)です。、容量3TBのアドバンスプランなら月額60,500円(1年契約・税込)で、IPアドレス制限などさらなるセキュリティ強化とWebDAV連携が可能になり、容量だけでなく機能面も拡張されます。
30日間の無料トライアルも実施しています。お気軽にお問い合わせください。
使えるファイル箱についてさらに知りたい方は、よくある質問をまとめたこちらの記事もご覧ください。
.jpg)
オンプレミスとクラウドの違いは何ですか?
オンプレミスは導入コストが高額になりがちですが、個々のニーズに合わせてローカル環境で構築できるため、他のシステムとの連携がしやすく、セキュリティ面で安心です。それに対して、クラウドは低額でスピーディに導入でき、拡張性が高い点がメリットです。
クラウドサービスはオンプレミスよりもセキュリティ面で不安?
一般的にクラウドサービスはインターネット経由で利用するため、オンプレミスよりセキュリティ面で不安があると指摘されることがあります。しかし、各クラウドサービス提供事業者によってセキュリティレベルが異なるため、一概にクラウドサービスがセキュリティ面で劣るとはいえません。例えば、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビットを使用し、ウェブ管理画面のSSL化など、万全のセキュリティ対策を行っています。
「ハイブリッドクラウド」とは何ですか?
ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなど、複数の環境を連携させて運用することを指します。マルチクラウドが複数のクラウドサービスを組み合わせるのに対し、ハイブリッドクラウドは異なる種類のクラウドやオンプレミスを組み合わせることで、それぞれのデメリットを最小化し、メリットを最大化することができます。
使えるファイル箱の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
ここ数年、企業のあり方・方向性がテーマになると必ずといってよいほど登場するのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というキーワード。「企業のデジタル化が大事なんでしょ?」くらいのイメージはあっても「IT化」との違いはいまいち分からない、という方も多いのではないでしょうか?
今回の記事ではこのDX化について理解を深め、自社の成長戦略にどのように活用できるか、また企業のデジタル変革とクラウドストレージの関係について、具体例を取り上げながらご説明します。
ファイルサーバのククラウド比較を見たい方はこちら
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
DXに対する認識の相違
スポーツ界にもデータ活用の波
使えるファイル箱
FAQ
Chatworkが2023年11月に中小企業の経営者・バックオフィス担当者2,125人を対象に行った調査によると、49.7%がDXを「聞いたことがない」と回答しました。「聞いたことはあるが、意味は知らない」と答えたのは19.5%で、「意味は知っているが、説明はできない」と答えたのは16.6%、「意味を理解しており、説明できる」人は14.3%にとどまりました。
政府や自治体が声を大にしてDXの重要性を叫び、補助金などの施策を講じても中小企業にはなかなか浸透しておらず、デジタルによる経営のアップデートを実現できていない状況がうかがえます。
DXの定義
では、そもそもDXとは何なのでしょうか?
2018年12月に経済産業省が公表した「DX推進ガイドラインVer.1.0」によると、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。
この定義から、企業がITを活用して組織を根底から変革することが「DX」だとお分かりいただけると思います。単にこれまで紙で送っていた請求書をPDFにするなど「ペーパレス化」を進めればDXが実現できるわけではないのです。
DXに取り組むべき理由〜「2025年の崖」とは?
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が2023年10月に行った調査によると、「DXに取り組むにあたっての課題」について「ITに関わる人材が足りない」が28.1%で最も多く、次に「DX推進に関わる人材が足りない」が27.2%、「予算の確保が難しい(24.9%)」、「具体的な効果や成果が見えない(21.0%)」、「何から始めてよいか分からない(19.9%)」と続いています。
とはいえ、経済産業省の報告によると、このままDX化を進めなければ2025年にはIT人材の不足が約43万人に拡大すると予想されています。さらに、古い基幹システムが全体の6割を占め、2025~2030年の間に年間最大12兆円の経済損失が出るという試算もあり、この問題は「2025年の崖」と呼ばれています。逆にDX化をいま推進すれば、2030年には約130兆円の実質GDPの押し上げが期待できるようになります。

前出の中小企業基盤整備機構が行った調査によると、「DXに期待する成果・効果」については「業務の効率化」が64%、「コストの削減」が50.5%と上位を占めました。また、「DXに向けての取組みの進捗状況について」で最も多かったのは「アナログで行っていた作業やデータのデジタル化を進めている」で29.1%、「個別の業務や製造等のプロセスのデジタル化を進めている」が13.4%でした。
前述したようにDX化の目的は、デジタルイノベーションによりビジネス変革を実現し、「競争上の優位性を獲得する」ことであるにもかかわらず、多くの中小企業がDXを業務効率化を目的とする「IT化」「企業の業務デジタル化」とほぼ同じようなイメージで捉えていることがうかがえます。
「ITを導入すればDX」になるの?
DXの狙いはデータとテクノロジーによる「デジタル変革」ですから、ITインフラを導入してもそれが業務効率化だけのためであれば、DXとはいえません。いわばDXは目的であり、IT活用はそのための手段に過ぎないのです。
上述した経済産業省の「DX推進ガイドライン」でも「DXを実現していく上では、デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業内の仕組みや体制の構築等が不可欠である」と述べており、データとデジタル技術を活用して「何をどのように変革したいのか」というビジョンこそが最重要であるといえます。
DX導入事例1)松代工業株式会社様、老舗企業の業務プロセスを改善
1958年創業の松代工業株式会社様(本社・長野市)は電子部品の製造や精密板金・塗装を手掛ける老舗企業で、長野県におけるものづくりを長年リードしてきました。本社・工場とのファイルマネジメントのためにローカルサーバを自社運用してきましたが、やりとりや管理が大変だったといいます。
同社はこうした業務プロセスを根本的に改善するために使えるねっとの「使えるファイル箱」を導入しました。それによりファイルのやり取りが楽に行えるようになり、クラウドストレージを「空気みたい」に使っているとのことです。技術やノウハウの積み重ねや承継を大切にしつつも、必要なときには大胆に新しい価値観を取り入れ、テクノロジー活用によりDX化を進めた事例といえるでしょう。
.jpg)
【松代工業株式会社様】事例の全文はこちら>>
DX導入事例2)株式会社レイメイ藤井様、災害の経験からクラウド化の必要性を痛感
明治23年(1890年)に熊本で創業し、現在は九州全域をカバーする拠点網を構築している株式会社レイメイ藤井様は、「知的生産をサポートする複合企業」を掲げ、商社や文具メーカーとして幅広い事業を展開しています。
同社は、2016年に発生した熊本地震がターニングポイントとなり、クラウド化の必要性を痛感したといいます。その際、数日出社できない社員が多数発生し、社外でも仕事ができる仕組みづくりが急務になったのです。ところが、当初導入したクラウドサーバはOSアップデートの度にシステムがダウンするなど、安定面から不安とストレスを感じていたとのこと。その後、「使えるファイル箱」に移行し、安定性の高さだけでなく、低コストや使いやすさに「目から鱗が落ちた」そうです。創業130年を経て今も進化し続ける原動力の1つがクラウドストレージだといえるでしょう。
(1).jpg)
【レイメイ藤井様】事例の全文はこちら>>
DX化が著しい業界にスポーツ界があります。とりわけ米大リーグ(MLB)ではその傾向が著しく、投手の投球速度や回転数、バッターの打ち出し角度や推定飛距離、球場での選手の動きを追跡してデータ化するシステムが導入されており、実際にデータ分析・活用の結果、ホームラン数が増えているとのことです。
.jpg)
スポーツ×テクノロジーで実現できるもの
かつてチームの強さは選手一人ひとりの力量や監督の経験によって大きく左右されましたが、ITによって膨大な情報をリアルタイムに得られるようになり、それをいかに分析し、活用するかで試合の結果を変えられるようになってきました。それとともにデータを高い精度で分析し、チーム内に分析結果を共有するシステムを構築できる専門家が求められています。
例えば、2019年のラグビーワールドカップで日本代表チームが大躍進できた背景にも、試合が優勢になるためにどのようにスクラムを組むべきなのか、試合の映像、選手一人ひとりのスピードやパワーを数値化して分析したアナリストたちの存在がありました。
使えるねっとのサービスでDXをサポート〜信州ブレイブウォリアーズ様
使えるねっとのサービスは、長野県長野市および千曲市を本拠地とするプロバスケットボールチーム、信州ブレイブウォリアーズ様にご利用いただいています。2021年10月からスタートしたシーズンにおいて、高品質で安定したクラウドサービスをチームに提供するのみならず、クラウド技術を活用したデータ管理を行ってチームのDX化をサポートしていきます。
(1).jpg)
使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」は使いやすくて低価格のため、多くの中小企業様に選ばれ、DX化のお手伝いをさせていただいています。
手軽なのにユーザ数無制限+高度なセキュリティ機能も搭載でDX化に最適
使えるファイル箱が使いやすい理由は専用のインターフェースを必要とせず、Windowsならエクスプローラーのように普段の使いなれた方法でデータのアップロード、ダウンロードが可能な点にあります。また、ユーザ数は無制限で100人でも、1,000人でも料金は一律のため、社員が増えてもユーザ課金や発行権限に悩むこともありません。
DX推進のために欠かせないのがデータ保存・データ管理のセキュリティ対策です。扱うデジタルデータの量は爆発的に増加し、機密性は高まる一方です。また、ランサムウェアなどサイバー攻撃の脅威も懸念されます。
ランサムウェアの意味や感染対策を知りたい方はこちら
この点、使えるファイル箱が採用しているのは暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズム「AES256ビット暗号化」。また、ウェブ管理画面のSSL化でウェブサーバとブラウザ間のデータ通信の暗号化も徹底しています。さらに、各フォルダごとにアクセス権限の設定が可能なので、セキュリティ面を心配せずに取引先など外部とのやりとりも自由自在です。
嬉しいことに、従来14日間だった無料トライアルの期間が2024年5月28日より30日間に延長。クラウドストレージサービス導入をお考えの方はじっくり、ゆっくりお試しいただけます。
使えるファイル箱は、デフォルトで大容量1TB、月単価21,230円(税込、1年契約)から導入可能。デジタル化によるビジネス変革を実現したい経営者の方、クラウドストレージサービスの導入方法についてお悩みの担当者の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
.jpg)
(1)DXとIT化はどう違う?
IT化は特定の業務に焦点を当て、デジタルを活用して効率化を目指すことです。それに対して、DXとは企業がデータやデジタル技術を活用し、自社のビジネスモデルや業務プロセス、企業文化などを変革し、競争上の優位性を確立することをいいます。つまり、DXは単なる効率化にとどまらず、組織全体の変革を指します。
(2)中小企業がDXを推進すべき理由とは?
中小企業はコストや人手不足ゆえにDXを後回しにしがちです。しかし、リソースが限られている中小企業こそ、DXを推進し「2025年の崖」を乗り切る必要があります。中小企業が遅らせずにDXに着手することで業務効率化のみならず、生産性や競争力の向上を実現できます。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
テレワークが多くの企業で導入された今、クラウドストレージを活用したデータ共有は常識になってきました。もっとも、中小企業の経営者や担当者の中には、クラウドストレージの導入を検討しつつも、さまざまな理由でなかなか踏み切れない方もいるかもしれません。
この記事では、クラウドストレージとはそもそも何かを理解し、メリットと注意点を詳しく説明します。また、数多くあるクラウドストレージサービスの中から自社に最適なサービスを選ぶポイントについても解説します。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
クラウドストレージとは?
クラウドストレージのメリット7つ
クラウドストレージを利用する際の注意点4つ
クラウドストレージの選定ポイント3つ
おすすめクラウドストレージサービス5選
使いやすく低コストの「使えるファイル箱」
FAQ

最初に、クラウドストレージの概要、ファイルサーバとの違いについて解説します。
クラウドストレージはネット上のファイルの保存場所
クラウドストレージとは、インターネット上に用意されているファイルやデータの保存場所(領域)です。一般的には、サービスの運営事業者が提供するストレージサービスを、有料または無料で利用します。
オンラインストレージとは何かを知りたい方はこちら
クラウドストレージとファイルサーバの違い
クラウドストレージとファイルサーバの大きな違いは、ファイルの格納・共有場所が社内かインターネット上かという点です。
従来、多くの企業や組織がファイルサーバを用いて、データを共有していました。社内ネットワークによってつながったユーザはファイルサーバにファイルを格納したり、そのデータを参照したり、編集することが可能です。
それに対して、クラウドストレージはインターネットを経由してファイルにアクセスし、閲覧、編集、共有するサービスです。企業はクラウドストレージを提供している事業者と契約すれば、アカウントIDとパスワードによって、サービスを利用することができます。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
ファイルサーバのクラウド比較を見たい方はこちら
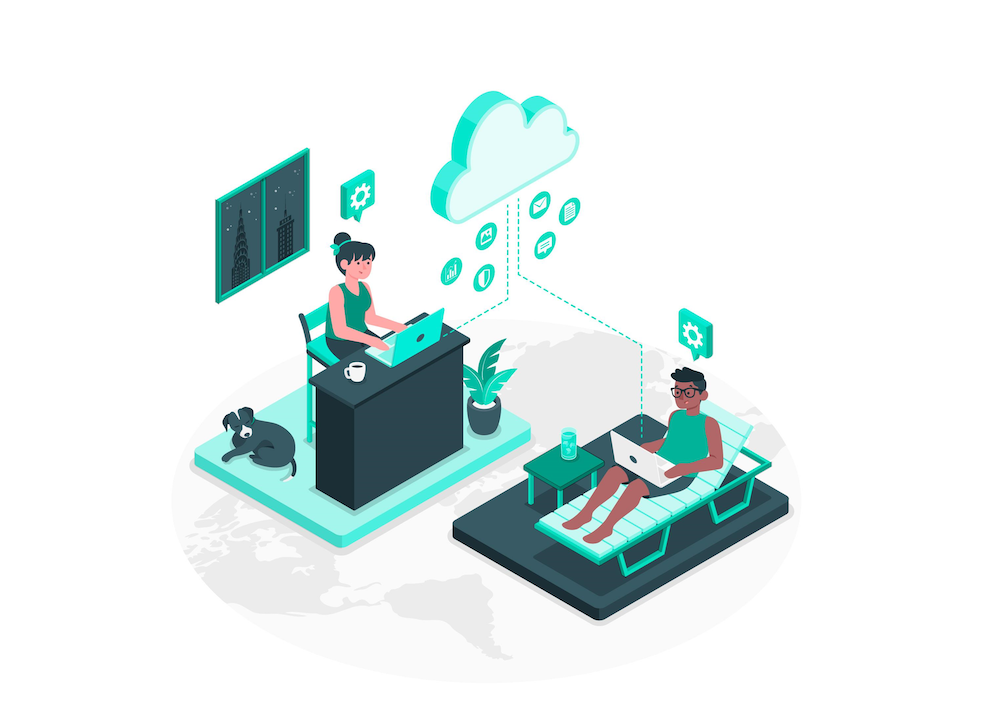
クラウドストレージのメリットを紹介します。以下の7つについて、1つずつ説明しましょう。
1. 場所を問わずどこからもアクセスできる
2. クラウド上でファイル共有、編集できる
3. 初期投資や運用コストが抑えられる
4. 常に最新の機能を利用できる
5. ファイルが自動的にバックアップされる
6. 災害時に備えられる
7. ストレージの容量問題を解消できる
1. 場所を問わずどこからでもアクセスできる
ファイルサーバは社内のネットワークで構築されているため、基本的に社外からアクセスすることを前提にしていません。テレワークの導入などにより、自宅など社外からアクセスする必要性も高まっており、VPNや仮想デスクトップが利用されています。ただ、いずれもセキュリティ面での不安を抱えていることは否定できません。
それに対して、クラウドストレージはインターネット経由でファイルを共有します。つまり、インターネット環境さえあれば、自宅であってもオフィスであっても、国内外関係なく、クラウドストレージに格納されているファイルにアクセスできます。
公益財団法人日本生産性本部によると、2024年1月時点のテレワーク実施率は14.8%で、2020年5月以降で最も低くなりました。それでも、育児や介護と両立でき、通勤などのストレスフルな行動をカットできるテレワークは、すでに一部の従業員にとっては新しい働き方として定着しています。こうした従業員のニーズを満たすために企業は情報共有のためのインフラを整える必要があります。
加えて、クラウドストレージなら、取引先を含め社外の人ともデータ共有が簡単にできます。クラウドストレージを使わなければ、ファイルをメールに添付して送付することになりますが、手間がかかります。また、添付できるファイルの大きさには制限があるでしょう。クラウドストレージを使うことで、少ない工数でファイルの共有ができるため、作業の効率化が図れます。
テレワーク導入の要となる「クラウド化」について知りたい方はこちら
2. クラウド上でファイル共有、編集できる
クラウドストレージを使えば、ファイルをクラウド上で共有できるだけでなく、編集も可能です。
現在、ビジネスパーソンが扱うデータの量、ファイルの数は膨大です。そのため、一括管理しなければ、どのファイルがどこにあるのか、分からなくなってしまいます。また、ファイルをやりとりしながら編集・更新しているうちにどれが最新なのか見分けが付かなくなることもよくあることです。例えば、ファイルをメールに添付して別のユーザに送り編集した場合、そのたびにファイル名を変えるなどの工夫が必要です。
この点、クラウドストレージであれば、クラウド上で編集・更新作業が可能です。さらにメールに添付するなどして共有する作業が不要になるため、工数を減らせます。それにより、生産性向上が図れますし、ミスも減らすことができるでしょう。
3. 初期投資や運用コストが抑えられる
クラウドストレージなら、ファイルサーバよりも初期投資を抑えることができます。
一般的にファイルサーバを構築するには、ハードウェアとソフトウェアの両方に対する投資が必要です。ハードウェアとしてサーバの購入、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどの端末に加え、ソフトウェアをインストールし、さらに各種設定、セキュリティ対策を行うことになります。
価格はスペックによって大きく異なりますが、サーバは法人使用を前提にすると、エントリーモデルで約10万円程度といわれています。ただ、ハイスペックなものを求めると20~30万円程度になりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えるものが必要になるでしょう。また、20~30人前後のオフィスの場合、周辺機器への投資も全部で10万~30万円程度になることが予想されます。
ハードを購入したら、OSやソフトウェア、Windowsの共有サービスなどをインストールしなければなりません。この作業は一般的にシステム開発会社に委託することになります。各会社の料金体系によって予算は大きく変わりますが、メールサーバ、Webサーバの構築の場合は5~10万円前後は見込んでおく必要があります。さらにサーバに端末を接続するためのネットワークの設計・構築にも費用がかかり、中小企業のオフィスであれば10~20万円前後かかります。
クラウドストレージであれば、ハードウェアの購入、ソフトウェアのインストール、ネットワークの構築の費用はかかりません。クラウドストレージサービスを提供している事業者に連絡し、契約すればすぐに使うことができます。初期投資が必要な事業者もありますが、その多くが無料です。
また、ファイルサーバの場合は多額の費用をかけてシステムを構築した後も、さらに定期的な運用保守が必要です。外部に委託する場合、月額の運用費はサーバの構築費用の10~15%が相場といわれています。例えば、サーバの構築に50万円かかったとしたら、月額5万~7万5,000円かかることになります。もちろん、自社で運用保守を行うことは可能ですが、24時間体制の監視ですし、システム障害やサイバー攻撃など突然のトラブルに迅速に対応するには相当の負荷がかかるでしょう。
この点、クラウドストレージであれば、保守運用を含めてサービス提供事業者が行ってくれます。一般的に月額の使用料に保守運用費用も含んでいるため、ランニングコストが過大に膨らむこともありません。
4. 常に最新の機能を利用できる
自社にファイルサーバを設置する場合、最新の機能を利用したければソフトウェアのアップデートが必要になります。もし、システムの構築、保守・運用を外部に委託している場合は、別途追加費用を支払う必要があるでしょう。
この点、クラウドストレージであれば、アップデートは自動的に行われます。常に最新の機能を利用できるのも魅力の1つです。
アップデートが重要なのは、最新の機能によって業務効率化が図れるだけではありません。ソフトウェアを常に最新の状態に保つのは、サイバー攻撃から企業の機密情報を守るためにも欠かせないポイントです。
一般的にソフトウェアは、リリースされた時点から時間の経過とともに新たな脆弱性が発見されます。そのため、システムの保守管理担当者は、常にソフトウェアの開発元やシステム機器メーカーから提供される更新プログラムをチェックしておかなければなりません。可能な限りスピーディーに更新プログラムを適用しなければ、システムの脆弱性を狙ったサイバー攻撃の被害を受けかねません。
特にサーバは企業内の基幹業務と関連しているため、簡単に止められないなどの理由でソフトウェアの更新が先延ばしにされがちです。先延ばしが続けば続くほど、システムのセキュリティリスクが高まります。
サイバー攻撃はますます巧妙かつ複雑になっています。例えば、ソフトウェアの脆弱性が発見されてから、修正プログラムが配布されるまでの期間を狙って行われる「ゼロデイ攻撃」と呼ばれる手法があります。企業のシステム管理担当者がどれだけ更新情報に注目していても、対策を講じるまでには必ず一定の空白期間が生じ、無防備な状態になってしまいます。
その点、クラウドストレージであれば、サービス提供事業者でその対策をすべて講じてくれます。もちろん、サイバー攻撃を完全防備できる訳ではありませんが、ファイルサーバと比べて格段に安全な環境を作り出すことができるといえるでしょう。
参考:総務省『国民のためのサイバーセキュリティサイト』
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_01.html)を加工して作成
5. ファイルが自動的にバックアップされる
ファイルサーバに格納されているデータを保護するために欠かせないのがバックアップです。オフィスに設置されたサーバはいつどのようにしてサイバー攻撃を受けたり、物理的に壊れたりするか分からないからです。
また、ファイルサーバの場合、定期的にバックアップしていてもバックアップ先が同じネットワーク内であれば、ランサムウェアの感染時に一緒に暗号化されるリスクが高いです。
この点、クラウドストレージの場合、一般的に自動でバックアップされるシステムが構築されているため、その手間が省けます。また、バックアップデータを社内ネットワークとは物理的に異なるデータセンターに保存します。そのため、仮に社内データがランサムウェアの攻撃を受けても、バックアップデータまでが被害を受けるリスクを下げられるのです。
6. 災害時に備えられる
災害大国である日本においては、どの企業も保有する機密データを守り、万が一の場合に事業を継続できるよう備えておくことが大切です。いわゆる「BCP(事業継続計画)対策」を講じる上でも、クラウドストレージにはメリットが大きいといえるでしょう。
一般的にファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが災害の被害に遭えばデータも同時に失われます。しかし、クラウドストレージの場合、データセンターは地震や火災、停電にも強い堅牢な設計であり、自社のサーバでデータを保存するよりも安全です。
もっとも、クラウドストレージでバックアップをとっていれば万全な訳ではありません。バックアップに関してはいわゆる「3-2-1ルール」が提唱されます。クラウドストレージのデータセンターとは言え、大規模な停電などに見舞われればデータにアクセスできなくなる可能性があるため、クラウドストレージとは別に他の媒体でのバックアップも必要でしょう。
BCP対策について知りたい方はこちら
7. ストレージの容量問題を解消できる
年々企業の保有するデータは増大しています。どの業種でもDXが推進され、ビッグデータの活用が経営課題として強調されているからです。
そのため、ファイルサーバだけでは容量オーバーになってしまう可能性もあります。もし、ファイルサーバのストレージ容量を増やしたければ、新しいハードウェアの購入や設定が必要ですが、追加コストがかかってしまいます。
この点、クラウドストレージであれば、容量の追加はとても簡単です。サービスの提供事業者にプラン変更を申し入れれば、必要に合わせて無制限に容量を増やすことができます。特にスタートアップ企業などは最初から多くのストレージ容量を必要とするわけではないかもしれません。しかし、事業規模の拡大に応じて、必要十分な容量を常に確保できるのです。

ここでは、クラウドストレージを利用する際の注意点について解説します。以下の4つの点について1つずつ説明します。
1. オフライン時は利用できない
2. セキュリティ対策が求められる
3. カスタマイズに適さない
4. ユーザ数に応じた費用がかかる
1. オフライン時は利用できない
クラウドストレージは、インターネットを経由して格納されているデータにアクセスする仕組みです。そのため、使用はオンラインであることが大前提です。
オンラインであれば、一括管理されたクラウドストレージ上の作業はスムーズに行えますが、一旦オフラインになってしまうと、すべてのデータにアクセスできなくなり、業務に支障が出てしまいます。
また、完全にオフラインでなくても、場所によってはインターネット環境が良好でないことがあります。例えば、ワーケーションなどで郊外に出かけた場合、インターネット回線の弱い場所だと仕事のパフォーマンスに影響が出るでしょう。
せっかく制度としてワーケーションやテレワークを導入していても、情報共有のためのクラウドストレージがどの程度活用されるかは、インターネット回線にも依存していることを覚えておきましょう。
2. セキュリティ対策が求められる
サイバー攻撃に対処するための修正プログラムなども含めて、クラウドストレージなら自動的にアップデートされると上述しました。さまざまなセキュリティ対策をサービス提供事業者が行ってくれることは確かです。しかし、たとえそうであっても自社で最低限のセキュリティ対策は行っておかなければいけません。
まずセキュリティ対策において非常に重要なのは、信頼できるサービスを選ぶことです(選ぶためのポイントについては後述)。また、クラウドストレージ提供事業者がどれだけ高いセキュリティ対策を行っていても、社内での運用が徹底されていないとリスクは高まります。
例えば、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関してルールを策定し、それをきちんと遵守するための周知徹底が社内でも求められるでしょう。
クラウドストレージのセキュリティ対策について知りたい方はこちら
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
3. カスタマイズに適さない
上述したようにファイルサーバはハードウェアの購入から、ソフトウェアのインストール、システムの構築まですべて自社のニーズに合わせて好きなように行えます。その点で、カスタマイズ性が非常に高いといえるでしょう。
この点、クラウドストレージはそもそも自社に最適化された形でサービスが提供される訳ではありません。事業規模に合わせてストレージの容量や、セキュリティレベルは選択できるものの、細かな設定やカスタマイズを行える点ではファイルサーバに及びません。
4. ユーザ数に応じた費用がかかる
ファイルサーバはユーザがどれだけ増えても、それに伴って費用が増大することはありません。それに対して、クラウドストレージはユーザ数に応じて費用がかかります。つまり、事業規模に合わせてユーザが増えれば増えるほどコストが増大するということです。
もっとも、クラウドストレージサービスの中には、ユーザ数無制限のサービスもあります。ユーザ数が増えることが確実に見込まれる場合は検討してみるのも良いかもしれません。
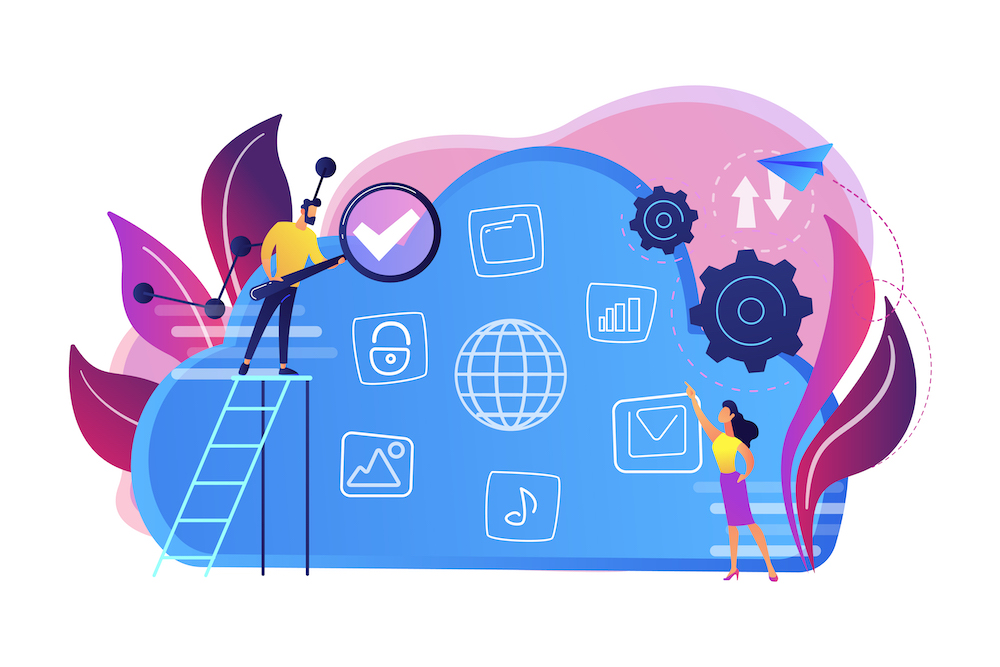
クラウドストレージのメリットと注意点を踏まえた上で、選定ポイントについて解説いたします。以下、3つについて説明します。
1. 必要な機能の充実度、費用を確認する
2. サポート体制の充実度を確認する
3. セキュリティ対策の内容を確認する
1. 必要な機能の充実度、費用を確認する
機能に関しては、対応している端末の種類に注目しましょう。いつでもどこでもアクセスして、情報を編集できる点がクラウドストレージのメリットの1つであるため、スマートフォンやタブレットにも対応しているかチェックしておきたいところです。
費用面に関しては容量とユーザ数を確認しておきましょう。容量無制限のプランも多いですが、自社の事業規模からどのくらいのストレージが必要なのか、費用と相談しながら検討すべきです。事業規模に合わせてより多くのストレージが必要となる可能性が高いようなら、容量を増やせるプランを選びましょう。
また、価格が低めに設定されている場合、必須機能がオプションになっており追加費用が求められることもあるため、料金体系は細かなところまでチェックする必要があります。
2. サポート体制の充実度を確認する
クラウドストレージは、運用や保守をすべてサービス提供事業者に委ねることになります。そのため、サポート体制の充実度は非常に重要なポイントです。エラーやトラブルが発生したときに、自分のことのように丁寧にスピーディーに対応してくれるかを見極めたいところです。
多くのクラウドストレージサービスには無料のトライアルがあるため、その期間にサポート体制について確認するのも1つの方法でしょう。
3. セキュリティ対策の内容を確認する
クラウドストレージのセキュリティ対策は多岐に渡ります。チェックしたいポイントとしては、総務省が挙げている以下の項目が参考になります。
・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策(災害対策や侵入対策など)
・データのバックアップ
・ハードウェア機器の障害対策
・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策
・不正アクセスの防止
・アクセスログの管理
・通信の暗号化の有無
出典:総務省 『国民のための情報セキュリティサイト』
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/admin/15.html)
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
機能
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円(税込、1年契約の場合)
※年契約の場合、初年度は全額返金保証
|
・優れたインターフェースと操作性
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
|
|
Dropbox Business
|
Standardの場合 1,500円(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・モバイル端末からアクセス可能
・Dropbox上でファイルを作成、編集
・更新時の通知機能
|
・パスワード保護、期限付きリンク、ダウンロード権限
・30日間データを復元可能
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年払いの場合)
|
・1,500以上のアプリ統合
・Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフロー自動化
|
・アクセス権限の管理
・ゼロトラストセキュリティ機能
・データ漏えい対策とサイバー脅威の検知
|
|
Google Workspace
|
Business Starterの場合 680円(1ユーザあたり、1年契約の場合)
|
・Googleアプリと連携
・クラウド上で直接編集
|
・2段階認証プロセス
・エンドポイント管理
・高度な保護機能プログラム
|
|
OneDrive for Business(Plan 1)
|
630円(税抜、1ユーザあたり、年間サブスクリプション)
|
・モバイル専用アプリあり
・差分同期
・20種類以上のファイルをウェブプレビュー
|
・受信者に対するアクセス制御指定
・共有リンクのカスタムパスワード
・アクセス有効期限の設定
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
以上のポイントに沿って、おすすめのクラウドストレージサービスを5つ紹介します。
1. 使えるファイル箱
使えるファイル箱の特徴はユーザ数が無制限で利用できる点です。そのため、最初はスモールスタートから始めて、事業拡大とともにユーザ数が増えていっても費用はまったく変わりません。
機能面は以下のように充実しています。
・優れたインターフェースで操作性に優れている
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
サポート体制は電話、サポートメール、チャットいずれも対応。サーバのトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間対応しています。
セキュリティも以下のように万全です。
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランを準備。どちらも1年契約であれば、初年度全額返金保証が付帯します(業界初)。また30日間の無料トライアルも実施中です。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
2. Dropbox Business
Dropbox(ドロップボックス)はクラウドストレージの先駆け的な存在です。個人向けサービスは無料で利用できますが、Dropbox Businessは法人向けの有料サービスです。Dropbox Businessも利用可能なユーザ数に制限がないため、事業規模の拡大に合わせて課金なしで情報共有を行えます。
機能面は以下のような特徴があります。
・パソコン、スマートフォン、タブレットいずれからもアクセス可能
・Dropbox上で直接コンテンツやファイルを作成、編集できる
・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたら通知を受け取れるため、最新情報を把握
・SlackやZoomなどとリンクすることが可能、アプリを切り替える必要なし
セキュリティ面は以下のような特徴があります。
・パスワード保護、期限付きリンク、ダウンロード権限などの機能を使用し、適切なユーザに適切なアクセス権を付与できる
・いざという時も30日間はデータを復元可能
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
・多要素認証設定
サポート体制も充実しており、24時間年中無休でヘルプセンター、コミュニティ、チャットボットが対応してくれます。
法人向けのプランは「Standard」「Advanced」「Enterprise」の3つのプランから選択できます。チーム全体の利用可能容量が異なり、Standardは5TB、Advancedは15TB、Enterpriseは必要なだけのスペースを一度に購入できます。
|
プラン
|
Standard
|
Advanced
|
Enterprise
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※年間払いの場合
|
1,500円
※ユーザは3人〜
|
2,400円
※ユーザは3人〜
|
応相談
|
|
チーム全体の容量
|
5TB
|
15TB〜
|
必要に応じて
|
公式HP:Dropbox Business
3. Box
Box(ボックス)は2005年の創業以来、人々がどこからでも簡単に情報にアクセスし、コラボレーションができる環境づくりを目指してきました。
10GBの無料オンラインストレージはすぐに利用できますが、法人向けの有料プランは「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」の4つがあります。法人向けプランの最小ユーザ数は3名、利用できるストレージはどれも容量無制限です。
各プランによってファイルのアップロード容量上限が異なります。Businessは5GB、Business Plusは15GB、Enterpriseは50GB、Enterprise Plusは150GBです。
以下のような機能面の特徴があります。
・Microsoft Office、Salesforce、Google Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合
・Box Sign:Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフロー自動化
・データ損失防止
セキュリティ面は以下の通りです。
・アクセス権限の管理
・ゼロトラストセキュリティ機能
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
応相談
|
|
アップロード
容量上限
|
5GB
|
15GB
|
50GB
|
150GB
|
公式HP:Box
4. Google Workspace
多くの個人ユーザに利用されているGoogle Drive(グーグルドライブ)の法人向けサービスが「Google Workspace」です。Google Workspaceの最大の特徴は、Googleの他のビジネスソフトやアプリケーションと連携できる点です。
また、クラウド上でPDFやMPEG4などの100種類以上のファイル形式を開けるため、直接編集・作業が可能、工数を減らし、作業効率をアップできます。さらにAI機能を利用して、検索の際、ユーザにとって必要なファイルを予測、表示してくれます。
セキュリティ面に関しては、厳格なプライバシー基準とセキュリティ基準に準拠するように設計されており、複数の独立した第三者機関による監査を受けています。その中には、ISO/IEC27001や、FedRAMPなどがあります。
Google Workspaceには、4つのプランが準備されています。プランごとに使用可能なストレージ容量が異なります。「Business Starter」がユーザあたり30GB、「Business Standard」はユーザあたり2TB、「Business Plus」はユーザあたり5TBまで、「Enterprise」はユーザあたり5TBに加えて、追加リクエストが可能です。
|
プラン
|
Business
Starter
|
Business
Standard
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
応相談
|
|
ストレージ容量
(1ユーザあたり)
|
30GB
|
2TB
|
5TB
|
必要に応じて
|
公式HP:Google Workspace
5. OneDrive for Business
OneDrive for Business(ワンドライブフォービジネス)は、法人向けに設計されたOneDriveクラウドストレージサービスです。最大の強みは、Microsoft 365やTeamsと連携してシームレスに共同作業が行える点です。
機能面では以下のような特徴があります。
・モバイル専用のOneDriveアプリが用意されているため、外出先でもファイルの作成、表示、編集、共有が可能
・ファイル全体ではなく、変更部分のみが同期される差分同期を採用
・Webでのプレビューで320種類以上のさまざまなファイルを忠実に再現
・クラウド上のファイルにアクセスする際にダウンロードは不要、デバイスのストレージを節約
・関連性の高いファイルを検索するためのインテリジェントなツール
セキュリティ面では以下のような特徴があります。
・受信者に対してファイルやフォルダへのアクセス制御を指定できる
・カスタムパスワードを設定して共有リンクを保護
・共有ファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可
一般法人向けのOneDrive for Businessには、ファイル共有とストレージの使用を目的とした「Plan 1」があります。さらにMicrosoft 365も含んだサービスには「Microsoft 365 Business Basic」「Mirosoft 365 Business Standard」などがあります。
|
プラン
|
OneDrive
for Business
(Plan 1)
|
Microsoft 365
Business Basic
|
Microsoft 365
Business Standard
|
|
月額料金
(1ユーザ、税抜)
※年間サブスクリプション
|
630円
|
750円
|
1,560円
|
|
合計ストレージ
|
ユーザ1人あたり1TB
|
公式HP:OneDrive for Business

「使えるファイル箱」は使いやすく、低コストのクラウドストレージサービスです。ユーザ数無制限なので、従業員数に関わりなく料金は一律です。また、専用のインターフェースを必要とせず、導入したその日から使える操作性の高さも魅力といえるでしょう。
中小企業が安心して使い続けられるように、容量課金制の低価格でサービスを提供。データ容量は企業規模に応じて、無制限に追加できます(オプション追加容量1TB 税込8,580円)。
価格だけでなく、セキュリティも充実しています。2要素認証設定、暗号化、ログ記録、ISO認証データセンターなどで大切なデータを情報漏えいからばっちり守ります。
容量1TB、ユーザ数無制限で月単価21,230円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価60,500円(税込、1年契約)です。例えば、スタンダードプランをお選びいただいた場合、従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
.jpg)
(1)クラウドストレージの無料と有料プランの違いは?
クラウドストレージの無料と有料プランの主な違いは容量の大きさ、セキュリティ面の充実度です。無料プランの場合、ストレージ容量は5GB~10GBが主流で、個人ユーザを対象にしています。また、ビジネスでの使用を前提としていない無料プランでは、データのやりとりやセキュアなコミュニケーションの点で不十分であると言わざるを得ません。
(2)クラウド上に保存とはどういうこと?
クラウド上に保存するとは、インターネットを経由して、クラウドストレージサービスを提供する事業者のデータセンターにデータが格納されている状態を指します。そのため、インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末を使って、データを閲覧、編集、共有することが可能なのです。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
やりとりするデータ量が増大し、機密性の確保が重要になっている昨今、中小企業にとってデータの管理方法は喫緊の課題です。
ここでは、多くの企業が導入しているクラウドストレージについて徹底解説します。クラウドストレージの基本や、中小企業にとってクラウドストレージが安全かつ効率的なデータ管理方法である理由を説明し、数多くのサービスの中から自社に最適なサービスを選ぶための視点をお届けします。クラウドストレージの導入について不安を抱えておられる経営者、担当者の方はぜひお役立てください。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
クラウドストレージとは
中小企業にとって最も安全かつ効率的なデータ管理方法とは
法人のクラウドストレージの選び方
法人向けクラウドストレージの比較一覧
「データ容量課金制」のおすすめクラウドストレージ4選
「ユーザ課金制」のおすすめクラウドストレージ5選
「ファイル転送機能」が充実しているクラウドストレージ4選
「無料版の容量サイズが大きい」クラウドストレージ2選
クラウドストレージの6つのメリット
法人向けクラウドストレージの上手な活用例
企業がクラウドストレージを導入する際に注意すべきポイント
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

クラウドストレージとは、インターネットを通じてアクセスする保管場所(データセンター)にデータを保存したり、転送・共有したりできるストレージサービスです。似たような言葉に「オンラインストレージ」がありますが、ほぼ同義と考えてよいでしょう。
従来、法人が保有するデータを保存・管理するためには「オンプレミス型」のファイルストレージが用いられてきました。「オンプレミス(on – premises)」とは「建物内、構内で」という意味で、自社施設内にサーバや通信回線などの必要な設備を設置し、システムを構築することを指します。
2010年前後から、インターネット回線の高速化、コンピュータの仮想化技術の向上により、企業は自社内にサーバを設置せずにシステム構築やデータ管理ができるクラウドサービスを導入、運用しはじめました。そして、その割合はますます高まっており、総務省の通信白書(令和5年版)によると2022年には72.2%に達しました。2017年は56.9%で6割弱だったにもかかわらず、約5年で全体の7割を超えたことが分かります。
.png)
出典:総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/datashu.html#f00250)
なぜこれほど多くの企業がオンプレミス型に替えて、あるいは並行してクラウドストレージを導入しているのでしょうか?理由は各企業によってさまざまですが、共通している2点にフォーカスしてみましょう。
それは「低コストで導入可能」であることと、「拡張性の高さ」です。以下、1つずつ詳しく説明しましょう。
クラウドバックアップについて知りたい方はこちら
クラウドストレージの特徴1. 低コストで導入可
オンプレミス型からクラウドストレージに多くの企業が移行している理由の1つは、低コストで導入可能だからです。
企業にとって利便性、機能性はもちろん重要ですが、高い導入コストは現実的ではありません。大企業に比べ、設備投資に掛けられるコストに限界がある中小企業はなおさらでしょう。
これまで発表されているデータからも、中小企業にとってクラウドサービスを導入するにあたっては、コストが大きな壁になっていることがうかがえます。
オンプレミス型の場合、サーバの設置、他の設備の購入資金、システム構築や運用には膨大な費用がかかります。しかし、クラウドストレージであれば自社で機器やシステムを準備しなくてよいため、初期費用がほとんどかかりません。また、保守・運用もクラウドストレージサービスの提供会社が行ってくれるため、自社で専門スタッフを常駐させる必要もありません。
さらに時間面からみても、クラウドストレージは低コストで導入可能です。オンプレミス型だと設備購入、システム構築のために数か月かかるのが一般的です。それに対して、クラウドストレージであればクラウドストレージサービスの提供会社に連絡し、契約が成立すれば即日使用を開始することも可能です。
クラウドストレージの特徴2. 拡張性の高さ
近年、多くの企業がクラウドストレージに移行しているもう1つの理由は拡張性の高さです。
クラウドストレージでは、企業規模や従業員数に合わせて最初は少な目のストレージ容量からスタートできます。その後、企業の成長に合わせてプランを変更し、容量を簡単に増やしていけばよいのです。
また、機能面の拡張性でいえば、元来クラウドでは他社のアプリケーションとの連携が難しいといわれていました。しかし、近年APIという技術により、各社アプリケーションとの連携が可能になり、高い拡張性を手に入れることができるようになりました。
APIとは、「アプリケーションプログラミングインターフェース(Application Programing Interface)」のことで、自社のアプリケーションと外部アプリケーションを連携させるために橋渡しの役割を果たします。これにより、クラウドストレージでデータを共有するとき、MicrosoftのビジネスソフトやSlackやChatworkなどのコミュニケーションアプリとの連携が可能になります。

企業がデータを管理する方法として、従来のオンプレミス型とクラウドストレージがあることを上述しました。ここでは、それに加えて、「法人向けサービスVS個人向けサービス」、「無料サービスVS有料サービス」という軸を加え、中小企業にとって安全かつ効率的なデータ管理方法について検証します。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」どちらを使うべきか
中小企業がデータ管理方法を選ぶ場合、クラウドストレージをおすすめします。
社内サーバ(オンプレミス)とクラウドストレージのどちらが優れているか、コストと拡張性の面からすでに比較しました。ここでは、中小企業にとって「安全かつ効率的な」データ管理方法はどちらかを検証します。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」、どちらが安全?
安全面に関していえば、社内サーバは自社でシステム構築が可能なため、お金と時間をかければ強固で堅牢なセキュリティ環境をつくりだせます。自社のセキュリティポリシー、セキュリティ要件を高めれば、いくらでも安全面で優れた環境は可能なのです。
また、社内サーバのネットワークは基本的にローカルネットワークシステムで運用されるため、外部ネットワークからは遮断されており、セキュリティインシデントの発生リスクを最小限に抑えられます。
一方、クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスであり、常時オンラインでないと利用できません。そのため、絶えず不正アクセスやサイバー攻撃の脅威にさらされていることは確かです。
ただ、以上の比較から、単純に社内サーバのほうがクラウドストレージよりも安全だと結論づけることはできません。
というのも、社内サーバの場合、システムの堅牢性をどの程度高めるかは経営者がセキュリティにどれほど高い意識を持っているかにかかっているからです。もし、経営層が厳格なセキュリティポリシーを設定し、高度かつ安全なシステムを作り上げるためにコストを厭わないというのであれば別ですが、中小企業の場合、上述したようにコスト面で限界があります。
逆にクラウドストレージサービスに関していえば、サービスの数も年々増え、多くの選択肢があります。その中でセキュリティ面で万全の対策を施し、なおかつ費用を抑えたサービスを選べば、コストパフォーマンスは社内サーバよりも高くなるのです。
「社内サーバ」と「クラウドストレージ」、どちらが効率的?
次に、社内サーバとクラウドストレージの効率性について検証してみましょう。
一口に効率的といってもさまざまな要素が関係していますが、効率的に業務を進めるためには「ムダ」を減らさなければなりません。
特に重要なのは情報共有での「ムダ」を減らすことです。例えば、共有するのがオフィス内でのテキストファイルがメインなら、社内サーバでもクラウドストレージでもかかる工数に大きな違いはないでしょう。しかし、昨今のようにテレワークが導入され、働く場所が多様化すると、社内サーバの場合は共有するのに手間がかかり、どうしても「ムダ」が生まれてしまいます。この点、クラウドストレージであれば、どこにいても、またファイルのサイズが大きくても共有可能です。また、出先などでスマートフォンやタブレットを使って共有できるのもクラウドストレージの魅力といえるでしょう。
「法人向けサービス」と「個人向けサービス」どちらを使うべきか
中小企業がクラウドストレージサービスを選択する場合、「法人向け」か「個人向け」かも重要です。
中小企業の場合、コストを抑えるために最初は個人向けサービスという選択もありえます。しかし、いずれは法人向けサービスに移行することをおすすめします。なぜなら、法人向けサービスには個人向けサービスにはかなわない特徴があるからです。
それはセキュリティ面でのさまざまな機能です。例えば、法人向けのサービスはアカウント管理機能と、グループ管理機能を細かく設定できるようになっています。また、ログ管理機能にも違いがあります。個人向けサービスでも履歴を見ることはできますが、法人向けサービスはセキュリティ違反があった場合にアクセスログを取得したり、アクセスをリアルタイムでモニタリングしたりする機能が備わっています。
「無料サービス」と「有料サービス」どちらを使うべきか
前項同様、有料サービスの方がセキュリティ面で優れているため、中小企業が最初は無料サービスを使うことがあっても、いずれ有料サービスに移行することをおすすめします。
セキュリティ面に加えて、有料サービスを選ぶべき別の理由は容量です。無料のクラウドストレージサービスの場合、容量に制限があり、平均的なサービスは5~15GBです。無料サービスで容量がもっとも大きいものはMEGAで20GBですが、有料サービスには到底及びません。有料のクラウドストレージサービスは法人を対象にしているため、容量の追加が可能であり、容量不足の心配はありません。
有料サービスの多くが無料トライアルを実施しているため、自社で導入するサービスを選ぶ場合には実際の使い勝手を試してみるとよいでしょう。

ここでは、中小企業がクラウドストレージを選ぶ場合、何を基準にすべきか、さらに具体的に9つのポイントを挙げます。
1. ユーザ課金制かデータ容量課金制か
最初のポイントはユーザ課金制か、データ容量課金制か、です。
ユーザ課金制とは、「1ユーザあたり」「10人まで」など、ユーザ数に応じて課金されるタイプの料金体系です。少人数で使用する場合、必要十分なサービスを利用できます。ただ、スタートアップベンチャーなど、成長スピードが早い企業の場合、従業員が増えるたびに課金が増え、コストがかさむリスクもあります。
データ容量課金制とは、ストレージのデータ容量によって料金が決まるタイプです。ユーザ数に関係なく利用できるため、短期間でユーザ数が増加することが見込まれる中小企業の場合、コストパフォーマンスが高くなります。逆にユーザ数が少ないにもかかわらず、データ容量だけ大きくても使いきれないため、コストがかかり、ムダになります。
2. 最初は低スペックからスタートできるか
2番目のポイントは、最初は低スペックからスタートできるかという点です。
一般的にクラウドストレージサービスは同じ提供会社でもいくつかのプランが準備されています。主な違いは容量とスペックです。使用料金が高額になればなるほど、容量が増え、スペックが上がるため、機能も充実します。
中小企業の場合、クラウドストレージサービスを利用したことがなく、使い方に慣れていない経営者や従業員もいます。そのため、上述した調査結果が示していたように「費用対効果がわからない」という声が上がるのです。
それを避けるためには、まず低スペック、低料金のプランからスタートして、徐々に容量を増やし、スペックを上げていくとよいでしょう。
3. ストレージ容量は十分か
3番目のポイントは自社が選ぶクラウドストレージの容量が十分かどうかです。
容量面で心配なら「容量無制限」を選べばよいと思うかもしれませんが、従業員数がそんなに多くない中小企業では使いきれませんし、そのために多額のコストを支払うのは割に合いません。
自社がどのくらいの容量を必要とするかは、業界によって、扱うデータの種類によって異なります。テキスト文書を多く扱う企業と、デザイン会社、建築事務所、動画制作会社などでは、やりとりするファイルサイズに違いがあります。
1つの基準になるのは1TB(テラバイト)がどのくらいの大きさか把握しておくことです。1TBとは、1000GB(ギガバイト)のことですが、以下のように換算すればイメージが湧きやすいでしょう。
・1枚1MBのオフィスファイルで約100万枚
・1枚4MBのJPEGファイルで約25万枚
・1曲5MBのMP3音楽ファイルで約20万曲
・1分ほどの動画(10MB)で約10万ファイル
・フルHD動画ファイル約166時間分
クラウドストレージの容量について知りたい方はこちら
4. 管理者機能が充実しているか
4番目のポイントは管理者機能が充実しているかどうかです。
上述したように、法人向け(有料サービス)と個人向け(無料サービス)のもっとも大きな違いはセキュリティ強化のための機能であり、管理者機能も含まれます。
その中には以下のような機能が含まれています。
・認証機能:外部からの不正アクセスを防ぐための機能です。例えば、外部からのアクセスを制限するための「IPアドレス制限」や、会社支給の端末のみでアクセスできるように設定する「デバイス認証」などが含まれます。
・アクセスコントロール機能:クラウドストレージのユーザにはさまざまな人が含まれます。部署や職位に応じて、また社員か外部からアクセスする取引先なのかによってもアクセスの仕方は異なります。管理者は「閲覧」のみなのか、「編集」も可能なのかを設定して、アクセスをコントロールし、情報流出や持ち出しを防止できます。
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
5番目のポイントはセキュリティ対策です。中小企業でも大企業でも、法人として顧客情報や取引先の機密情報を保有している以上、特に重要なポイントです。
上述したようにオンプレミス型のストレージであれば、自社でいくらでもセキュリティポリシーを厳格にできますが、クラウドストレージの場合は、サービス提供会社にある程度依存することは避けられません。そのため、クラウドストレージの選択にあたっては注意深い検討が必要です。
例えば、総務省「国民のための情報セキュリティサイト」では、クラウドサービス提供事業者が行っているべき確認項目として以下の7つを挙げています。
・データセンターの物理的な情報セキュリティ対策(災害対策や侵入対策など)
・データのバックアップ
・ハードウェア機器の障害対策
・仮想サーバなどのホスト側のOS、ソフトウェア、アプリケーションにおける脆弱性の判定と対策
・不正アクセスの防止
・アクセスログの管理
・通信の暗号化の有無
出典:「国民のための情報セキュリティサイト クラウドサービスを利用する際の情報セキュリティ対策」
(総務省)(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/admin/15.html)
また、クラウドサービスのセキュリティ対策のレベルを確認する方法として、第三者認証も役立ちます。第三者認証とは、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)など、当事者と直接の利害関係がない第三者によって行われる認証であるため、信頼性が高いと考えられています。
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
6. ディザスタリカバリ対策がされているか
6番目のポイントは大規模災害に直面しても業務の継続性が担保されているか、つまりディザスタリカバリ(災害復旧)対策がなされているか、です。
そもそもクラウドストレージ自体がディザスタリカバリ対策の一環です。なぜなら、自社サーバよりも、災害にも強い堅牢な構造であるデータセンターにデータを保存しているほうが、消失の恐れは低いからです。
もっとも災害時に大規模な停電が発生したり、ネットワークが遮断されたりした場合はデータセンターのデータも利用できません。そのため、クラウドストレージの提供会社がデータセンターの拠点を複数持っており、データを分散保存しているかも確認しておくとよいでしょう。
7. バージョン管理機能は備わっているか
7番目のポイントはバージョン管理機能が備わっているかどうかです。
バージョン管理機能とは、間違って上書きをしてしまった場合に、遡って変更前のファイルに戻せる機能です。どのクラウドストレージサービスにも装備されていますが、何世代まで戻れるかをチェックしておきたいところです。
8. 必要な機能やサービスが備わっているか
8番目のポイントは自社が必要としている機能やサービスが備わっているかどうかです。
ここですべての機能を挙げることはできませんが、例えば以下のようなものがあります。
・アカウントのない社外の人間でもファイルはアップロード可能なのか
・スマートフォンやタブレットなどの端末にも対応しているか
・更新通知やファイル公開の期限、ユーザの有効期限などの自動化機能
また、サポート体制の有無と充実度も確認しておきましょう。特に外資系サービスでは日本国内でのサポート体制が不十分な場合もありますので、前もってチェックしておくことが大切です。
クラウドストレージサービスの使用開始前から、どんな機能やサービスが必要かをすべて把握することは不可能です。無料のトライアル期間を利用し、実際に操作してみて、その使い心地を試してみることをおすすめします。
9. ストレスを感じない操作感か
最後のポイントは、ユーザビリティです。つまり、そのクラウドストレージサービスが使いやすいかどうかということです。
もし、クラウドストレージサービスが普段使っているソフトやブラウザと操作感が全く異なると、導入にあたり従業員研修が必要になるでしょう。しかし、中小企業の場合、ただでさえ人手不足で時間がないため、クラウドストレージ習熟のために別途リソースを割くことは困難でしょう。結果的に社内に浸透せずに使われずに終わってしまうことになりかねません。
クラウドストレージを選ぶにあたっては、シンプルなインターフェースで感覚的に使えるサービスを選ぶようにしましょう。
以下では全部で15の法人向けのクラウドストレージを紹介します。
法人がクラウドストレージを選ぶときには自社の企業規模や導入の用途を重視すると思われます。そこで、ここでは15のサービスを「データ容量課金制」「ユーザ課金制」「ファイル転送機能充実」「無料版の容量サイズが大きいもの」の4つに分けて説明します。

以下でそれぞれのサービスが法人、特に中小企業にとってどんなメリットがあるのか、「機能」、「セキュリティ」、「価格」の3つの面から紹介します。
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円(税込、1年契約の場合)
※年契約の場合、初年度は全額返金保証
|
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)+初期費用 15,000円(税別)
|
・自動メール通知
・ユーザごとに権限設定
|
・IPアドレスによるアクセス制限
・アクセスログを1年分取得
|
|
Fileforce
|
Unlimited-1の場合 55,000円(税別、年契約の場合)
|
・全社共通のディレクトリ構成
・他アプリケーションから直接保存
|
・ユーザごとの権限設定
・全アクセスを追跡
・ランサムウェア対策
|
|
PrimeDrive
|
1GBの場合 12,000円+初期費用 30,000円
|
・ユーザごとに権限設定
・ユーザ情報を自動で取得、登録
|
・誤送信を無効可
・承認機能によるファイルの事前チェック
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人向けの「データ容量課金制」のおすすめクラウドストレージは次の4つです。
使えるねっとが提供する使えるファイル箱には、容量1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。わかりやすいインターフェースで、いつものパソコン操作とほぼ変わらない形で使用できるため、複雑なトレーニングを実施する必要もありません。暗号化、ログイン認証、ランサムウェア対策といったセキュリティ面の備えも万全で、法人での使用に適したクラウドストレージです。
100人でも、1,000人でも料金一律で使用できるため、社員が増えてもユーザ課金や権限発行に悩むことなく、費用もかさみません。また、中小企業のお客様に満足して利用いただけるよう、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。また、24か国語で利用できるため、グローバルにビジネスを展開する企業様や、海外拠点・他国のクライアントとお取引がある場合などにも適しています。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・WebDAV連携(アドバンス)
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)
・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)
・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)
価格
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。
公式HP:使えるファイル箱
IMAGE WORKS(イメージワークス)は、富士フイルムが提供する、画像・動画・制作コンテンツをいつでも、誰でもどこででも活用できるようにするための法人限定クラウドサービスです。広報・宣伝部門など、企業内のチームで専用のスペースを作ってファイル管理・共有を行いたい場合に便利です。
専用のスペースを作ることで、特定のファイルは誰が持っているのか、一体どこにあるのかといった問題も解消。在宅やテレワーク先など、インターネットさえあれば手軽に仕事で使うファイルを共有することができます。社内だけでなく取引先の人や海外支店などとも簡単・安全にファイルのやり取りが可能。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・自動メール通知で、確実に情報共有
・ユーザごとに権限設定
・画像・ドキュメントファイルや映像をダウンロードせず、ビューイングだけ許可
・豊富な検索機能
・属性情報のカスタマイズで独自のデータシステムを構築可能
セキュリティ
・ID・パスワード認証だけでなく、IPアドレスによるネットワーク認証などのアクセス制限
・詳細に記録されたアクセスログは1年分取得
・アップロード/ダウンロード通信の暗号化
・登録データのウイルスチェック
・保存データの暗号化保管
価格
|
プラン
|
ミニマムプラン
|
|
初期費用
(税別)
|
15,000円
|
|
月額費用
(税別)
|
15,000円
|
公式HP:IMAGE WORKS
Fileforce(ファイルフォース)は、「Small Business」から「Enterprise」まで、企業の成長フェーズに合わせて容量を設定し、最適なプランを選択できます。
ユーザ無制限で利用したい場合は「Unlimited」がおすすめ。
利用可能なユーザ数は「Small Business(容量:ユーザあたり10GB)」の場合10~50人、「Enterprise(必要な容量を購入可能)」は10人~、「Unlimited(容量:1TB、3TB、10TB、30TBから選択可能)」だと無制限になるため、自社のニーズに応じて適したプランを選べます。
使い慣れたエクスプローラで快適に作業できるので、パソコンが苦手な方でも安心。新しいツールの導入にあわせてトレーニングを行う必要もありません。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・全社共通のディレクトリ構成で社内のファイル共有が容易
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集&同時編集可
セキュリティ
・ユーザごとの権限設定
・ファイルの操作ログを記録し、すべてのアクセスを追跡
・ランサムウェア対策
・不正アクセス防止機能
価格
|
プラン
|
Small
Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
Enterprise
|
|
月額料金
(税別)
※年払い
|
900円/
ユーザ
|
55,000円
|
98,000円
|
198,000円
|
330,000円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Fileforce
PrimeDrive(プライムドライブ)は、ソフトバンクの法人向けクラウドストレージサービスです。契約容量に関わらず1万ユーザまで登録できるため、企業拡大に伴うユーザ増加にも柔軟に対応できます。
オンラインストレージでのデータ転送にあたって懸念となる情報漏えいを防止することを念頭に置き、セキュリティ対策に不可欠な機能を搭載。大容量のファイル転送や機密文書など重要なファイルの受け渡しに適しています。また、会議などでプレゼンテーションをする際などにも、クラウドストレージを使用することで紙の配布資料を準備する手間を省くことができます。
機能
・ユーザごとに権限設定
・Active Directory連携によりユーザ情報を自動で取得、登録
・iPad、iPhone、Androidにも対応
・10個のアクセス権限を任意の組み合わせでカスタム設定、柔軟なファイル共有が可能
セキュリティ
・ダウンロードリンクを発行後、誤送信が発生したらいつでも無効可
・承認機能により承認者が事前にファイル内容をチェック
・ユーザごと、登録ユーザ全員に対してIPアドレス制限が適用
・多段防御ネットワーク
・2048ビットSSL暗号通信
価格
| 契約容量 |
1GB |
10GB |
100GB |
200GB以上 |
初期費用
(一時金) |
30,000円 |
|
月額料金
|
12,000円
|
69,800円
|
180,000円
|
個別見積り
|
公式HP:PrimeDrive
|
サービス名
|
月額(ユーザ)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
・1,500以上のアプリ統合
・Webアプリでの電子サイン
|
・7段階のアクセス権制御
・ゼロトラストアーキテクチャ
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 1,980円~(税込、1ユーザあたり)
|
・120種類以上の拡張子に対応
・AD連携によるシングルサインオン
|
・ユーザごとのアクセス権限設定
・60種類以上のログ・セキュリティレポート
・AES256ビット暗号化
|
|
OneDrive for Business(Plan 1)
|
630円(税別、1ユーザあたり、年間サブスクリプション)
|
・アクセス権をいつでも取り消し可
|
・転送中、保管中のデータを暗号化
|
|
Dropbox Business
|
Standardの場合 1,500円(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・ドキュメントに直接アクセス
・共有ファイルにロゴ、企業名、背景画像を追加
|
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
|
|
NotePM
|
プラン8の場合 4,800円(税込)
|
・チャット連携 、API対応
・全文検索
|
・変更履歴を自動記録
・柔軟なアクセス制限
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、ユーザ課金制のクラウドストレージを5つ紹介します。容量課金制ではクラウド容量が大きすぎる場合、ユーザ数に合わせて課金される料金体系のほうがコストを抑えられる可能性が高いです。
Box(ボックス)は個人では10GBまで無料で利用できますが、法人向けのBoxビジネスプランは3人以上から導入可能です。Microsoft 365やGoogle Workspace等と連携できます。機能やセキュリティの充実度、またファイルアップロードの容量上限の違いにより「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」といったプランがあります。
ファイル共有やオンライン共同作業の機能の違い
・Business:ファイルアップロードの容量上限5GB
・Business Plus:ファイルアップロードの容量上限15GB、外部コラボレータ無制限
・Enterprise:ファイルアップロードの容量上限50GB、外部コラボレータ無制限
・EnterPrise Plus:ファイルアップロードの容量上限150GB、外部コラボレータ無制限
以下では、もっともスタンダードな「Business Plus」の機能、セキュリティについて説明します。
機能
・Microsoft OfficeやGoogle Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合
・Webアプリでの電子サイン
・標準ワークフローの自動化
・データ損失防止
・高度な検索フィルター
セキュリティ
・ゼロトラストアーキテクチャのアプローチにより、安全なコラボレーションが可能
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・AES256ビット暗号化
・データの保持、廃棄の管理など情報ガバナンスを効率化
価格
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
月額料金
(1ユーザ、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
カスタム
|
公式HP:Box
Box over VPNは、NTTコミュニケーションズが提供する閉域網サービス「Arcstar Universal One」を経由することで、BoxをセキュアなVPN環境下で利用できるサービスで、5人以上から導入可能です。
このサービスでは単なるファイル転送を行うだけでなく、ファイル共有を通じた社内外とのコラボレーションや、Salesforceなどの業務アプリケーションとのシームレスな連携などよりビジネスに特化した機能が揃っており、法人向けの「コンテンツ・マネジメント・プラットフォーム」として提供されています。VPN環境下だけでなく、希望に応じてインターネット経由で接続して利用する形態も相談可能です。
機能
・120種類以上の拡張子に対応するプレビュー機能
・容量無制限のごみ箱
・AD連携によるシングルサインオン
・最大100世代のファイル世代管理
・検索キーワードで文書の中身まで検索可能
・20地域以上のグローバル言語に対応
セキュリティ
・ユーザごとにアクセス権限を設定
・60種類以上のログ・セキュリティレポート
・AES256ビット暗号化
価格
月額 1,980円(税込)~
公式HP:Box over VPN
OneDrive(ワンドライブ)for Businessは、Microsoftが提供しているクラウドストレージサービスです。個人向けの無料プランもありますが、「OneDrive for Business」は一般法人向けです。ファイル共有とストレージの使用を目的としたサービスは「Plan 1」のみであり、Microsoft 365アプリも使える「Microsoft 365 Business」もあります。
ここでは「OneDrive for Business(Plan 1)」の機能やセキュリティについて紹介します。
機能
・セキュリティを維持しながら組織内外の相手とファイルを共有
・アクセス権をいつでも取り消し可
・外部と共有されるファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定
・共有ファイルのダウンロードを防止
・320種類以上のファイルをWebでプレビュー
・Officeファイルの共同編集
・ファイルオンデマンドで、クラウド内のファイルへのアクセスは端末のストレージ不要
・インテリジェントな検索と検出のツールで探したいファイルが見つかる
・複数ページのスキャンを使用して、書類やレシート、名刺などの画像を素早く保存できる
セキュリティ
・転送中、保管中のデータを暗号化
価格
年間サブスクリプションで、「Plan 1」は630円(ユーザ/月、税別)です。
公式HP:OneDrive for Business
個人向けの無料サービスも提供しているDropbox(ドロップボックス)の法人向けサービスがDropbox Businessです。個人事業主から大企業まで、ビジネスの成長フェーズに合わせて「Professional」「Standard」「Advanced」の中から、最適なプランを選べます(以下の表では一部のみ抜粋)。
利用可能なユーザ数
Professional:ユーザ1人、ユーザ1人あたり3TB
Standard:ユーザ3人以上、チーム全体で5TB
Advanced:ユーザ3人以上、チーム全体で15TBから開始
ここでは、「Standard」の機能とセキュリティについて紹介します。
機能
・Googleドキュメントなどのファイルに直接アクセス可
・共有ファイルにロゴ、企業名、背景画像を追加
・Webでファイルをプレビュー可
・すべてのファイルのコンテンツを簡単に検索
・閲覧者の履歴
・1回の転送で最大2GBのファイルを送信
・ユーザごとに権限設定
・多要素認証
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・SSL/TLS暗号化
・ダウンロード許可、有効期限を設定して、共有ファイルの表示やアクセスを管理
・チーム外のユーザとリンクを共有する場合、必要があれば簡単にアクセス権を取り消し
価格
|
プラン
|
Professional
|
Standard
|
Advanced
|
|
月額料金
(1ユーザ)
※年間払いの場合
|
2,000円
|
1,500円
|
2,400円
|
公式HP:Dropbox Business
NotePM(ノートピーエム)は社内で情報共有をするための社内wikiツールです。バラバラに管理されていたマニュアルやノウハウなどの社内ナレッジを一元管理します。情報共有に特化したサービスのため、容量は少な目に設定されています。
ファイル共有というよりは、社内の重要な情報を一箇所で効率的に管理するという目的で設計されており、チャットやメールで情報が流れてきたが埋もれてしまった、かなり前の情報を参照したいが探す手立てがない、マニュアルを作ってもメンテナンスが大変で誰も更新しない、といった場合に適したサービスです。
容量やユーザ数によってプランが細かく分かれているのが特徴で、利用可能なユーザ数に応じてプラン8~200まで用意されています。一番上のプラン200だとユーザ数200人まで、容量は2TBと十分な量のクラウドストレージを利用できます。
自社の利用人数と業務の種類に応じて必要な容量、予算といった観点から利用したいプランを絞り込むとよいでしょう。
機能
・社員がさまざまな情報を書き込み、蓄積することで、社内の知りたいことが見つかる
・ファイルの中身を全文検索
・チャット連携・API対応
・マルチデバイス対応
・レポート機能
セキュリティ
・変更履歴を自動記録
・柔軟なアクセス制限
価格
|
プラン
|
プラン8
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
プラン200
|
|
容量
(全体)
|
80GB
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
2TB
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
8人まで
|
15人まで
|
25人まで
|
50人まで
|
100人まで
|
200人まで
|
|
月額料金
(税込)
|
4,800円
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
120,000円
|
公式HP:NotePM

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
ギガファイル便
|
無料
|
・ファイル数、容量無制限の転送
・無料プランのみ
|
・ダウンロードパスワード
・アップロード直後に削除可
・ファイル暗号化
|
|
GigaCC ASP
|
10IDの場合 12,000円(税抜)+初期費用 50,000円(税抜)
|
・共有ノート機能
・履歴ログ管理
|
・グローバルIPアドレス制限
・SSL暗号化通信
・サーバ内暗号化
|
|
クリプト便
|
エントリープランの場合 1,000円(1ユーザあたり)
|
・交換相手・権限を制御
・利用手順が簡潔明快
|
・承認機能
・クレジットカード情報を守るPCI DSS準拠のサービス
|
|
Fleekdrive
|
Teamプランの場合 600円(税抜、1ユーザあたり)
|
・自動バージョン管理
・最低10ユーザから利用可能
|
・自動でウイルスチェック
・全ファイルを暗号化して保管
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、クラウドストレージの中でもファイル転送機能が充実しているサービスを4つ紹介します。企業によっては日常的に高画質の動画など、容量が大きなファイルのやりとりが必要です。その場合、共同編集の機能よりも重視すべきなのは、転送のスピードや扱えるデータの大きさです。
皆さんも一度は、メールでギガファイル便のリンクを開いたことがあるのではないでしょうか?
GigaFile(ギガファイル)便は、ユーザ登録不要で利用できるファイル転送サービスです。転送できるファイルの容量には制限がなく(1ファイル300GBまで)、アップロード後最大100日間保持されます。
ファイルを送る側は、まずギガファイル便を開いてファイルをアップロードします。このときに保持期限やダウンロードパスワードなどを設定することができます。ファイルのアップロードが完了するとリンクが生成されるのでこれをメールやチャットなどで送信すればファイルの共有は完了です。
受け取った人はURLを開いてファイルをダウンロードするだけなのでとてもシンプル。
公式アプリもあり、モバイルでファイルをやり取りしたい場合もスムーズに作業できます。
機能
・ファイル数、容量は無制限でファイルの転送ができる
・有料プランはなし
セキュリティ
・ダウンロードパスワード
・誤ったファイルをアップロードした場合はすぐに削除可
・ファイル暗号化
価格
無料
公式HP:ギガファイル便
GigaCC ASP(ギガシーシー)は、日本ワムネットが提供する、国産の企業間ファイル共有・転送サービスです。初期費用が50,000円かかるものの、企業間での機密ファイルをセキュアな環境で、安心してやりとりできます。「STANDARD」「ADVANCED」「PREMIUM」の3つのプランがあります。
純国産のオンラインストレージサービスで、企業だけでなく行政機関・研究機関などからも支持されています。高度なセキュリティ対策も搭載されておりビジネス利用に安心です。
業務で使用するファイルをとにかくシンプルに、安全に共有したいという法人や組織に適しています。
また、ファイル共有だけでなく請求書を一括送信したり、既存のシステムとシームレスに連携したりと、業務効率化をサポートしてくれる点も企業にとって嬉しいメリットです。
ここでは「ADVANCED」の機能、セキュリティについて紹介します。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・共通ノート機能
・履歴ログ管理
・ユーザごとの権限設定
・ディレクトリ権限設定
セキュリティ
・グローバルIPアドレス制限
・SSL暗号化通信
・サーバ内暗号化
・不正アクセス自動ロック
価格
・初期費用 50,000円
・10IDの場合は月額12,000円、1,000IDの場合は月額280,000円
・「ADVANCEDプラン」は+25,000円、「PREMIUMプラン」は+42,000円
公式HP:GigaCC ASP
クリプト便は、金融系企業を中心に20年以上に渡る実績を持つファイル転送サービスです。提供しているのは情報セキュリティ会社であり、高い堅牢性を誇ります。
プランは「エントリー(適したユーザ数:20人前後)」「ライト(50人前後)」「スタンダード(100人前後)」の3つで、さらに個別見積もりも可能です。
クリプト(crypto)とはもともと暗号という意味で、昨今話題になっている仮想通貨(cryptocurrency)や暗号技術(cryptography)といったところでも使用されている用語です。
その名の通り、重要な情報や文書を安全に保護するセキュリティ対策を売りにしたサービスで、金融・IT企業などデータの受け渡しが業務の中で重要な位置づけを占める法人に支持されています。
機能
・グループ機能により、ファイルの交換相手・権限をこまかく制御
・普段通りの操作で利用可能
・利用手順が簡潔明快
・オートパイロット機能
セキュリティ
・承認機能(事前承認、事後承認)
・クレジットカード情報を安全・効率的に受け渡すPCI DSS準拠のサービス
価格
・初期費用(初月のみ)+基本料金(月額)+超過料金(前月分)
|
プラン
|
エントリー
|
ライト
|
スタンダード
|
|
基本料金
(1ユーザ、月額)
|
1,000円
|
1,000円
|
900円
|
|
プランに含まれるもの
|
・20ユーザまでの
利用料
・5MB/通までの
アップロード
・100通/月までの
利用料
|
・50ユーザまでの
利用料
・10MB/通までの
アップロード
・400通/月までの
利用料
|
・100ユーザまでの
利用料
・20MB/通までの
アップロード
・1,000通/月までの
利用料
|
公式HP:クリプト便
Fleekdrive(フリークドライブ)は、障害耐性に優れたクラウドサーバ「AWS(Amazon Web Services)」を基盤にしています。クラウド上にファイルをアップロードした時点で国内3か所に分散してデータが保管されるため、そのうちのどこかが災害の被害に遭ってもデータ消失の心配がありません。
プランは、基本的なファイル共有ができる「Team(10GB×契約ユーザ数)」、高セキュリティでビジネスで本格的に使う「Business(200GB×契約ユーザ数)」、容量無制限で利用する「Enterprise(無制限)」の3つです。場所を問わずにオンラインでやり取りすることが一般的になった今、時間も情報資産も社内外を問わず有効活用するためには安心かつ便利なサービスです。
ここでは「Business」の機能とセキュリティについて紹介します。
機能
・自動バージョン管理
・オンライン共同編集50名
・モバイル閲覧
・ユーザごとの権限設定
・SSO(シングルサインオン)連携で、複数のアプリをシームレスに利用
セキュリティ
・アップロード時に自動でウイルスチェック
・全てのファイルを暗号化して保管
・IPアドレス制限
・24時間体制で不穏なアクションを自動通知
・過去5年分の証跡を蓄積
価格
|
プラン
|
Team
|
Business
|
|
ストレージ容量
|
10GB × 契約ユーザ数
|
200GB × 契約ユーザ数
|
|
料金
(1ユーザ、月額、税抜)
|
600円
|
1,800円
|
全プラン、30日間無料トライアルが可能です。
公式HP:Fleekdrive

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
MEGA
|
20GBまで無料
|
・転送マネージャーでファイルの管理
・携帯端末からファイル転送
|
・エンドツーエンド暗号を採用
・二要素認証
・ランサムウェア対策
|
|
Googleドライブ
|
15GBまで無料
|
・転送マネージャーでアップロードとダウンロードを管理
・Googleアプリと連携
|
・データの暗号化
・二段階認証
・ユーザごとの権限設定
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、無料版の容量サイズが大きいクラウドストレージを2つご紹介します。
ただ、中小企業であっても法人である以上、扱う情報には機密情報が多く含まれており、無料のサービスは慎重に利用する必要があります。無料版のクラウドストレージはあくまでも補助的に活用することをおすすめします。
MEGAはニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウドストレージです。20GBまでは無料で利用できます(一部機能に制限あり)。
ホームページも日本ユーザ向けにシンプルで分かりやすくローカライズされています。より多くの容量を使いたい場合は有料プランが使用できますが、月額約1,616円(2024年3月14日時点)のPro Iだと2TB、ProⅡだと8TB、ProⅢだと16TBまでと、かなりの量が利用できてお得です。
外資系のサービスだと日本語のホームページの翻訳がわかりづらかったり、明らかに日本向けじゃなかったりと法人で利用するならちょっと…と感じてしまうこともあると思います。その点、MEGAはサイトでの説明もわかりやすく、他のサービスと比較しても安価で機能性も高いためビジネス利用にも向いているといえそうです。
機能
・ファイルやフォルダのアップロード、ダウンロードを転送マネージャーで管理
・携帯端末でもファイルの転送が可能
・共有リンク発行
セキュリティ
・エンドツーエンド暗号を採用し、第三者が通信内容を傍受できない対策
・二要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護
・ランサムウェア対策
公式HP:MEGA
もはや説明不要の無料クラウドストレージ。15GB以上を使いたい場合は「Google One」へのアップデートが必須です。
今ではGmailの独自ドメインを取得し、Google Workspaceの契約で企業のアセットをオンラインで管理している企業も増えてきました。社内で共有したいファイルや画像、その他データなどはすべてGoogleドライブ上で管理できますし、「同じメールドメインを使用する社内ユーザのみに共有」といった権限の指定も可能です。
ファイルの転送だけでなく、リアルタイムでの共同作業が可能であるところも法人に選ばれるメリットのひとつだといえます。また、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライド、Googleドライブとそれぞれのアプリが公開されており、スマホでもパソコンと遜色ないパフォーマンスを発揮してくれます。
機能
・ファイルやフォルダのアップロード、ダウンロードを転送マネージャーで管理
・携帯端末でもファイルの転送が可能
・ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどと連携し、共同編集可能
セキュリティ
・データの暗号化
・二段階認証
・ユーザごとの権限設定
公式HP:Googleドライブ
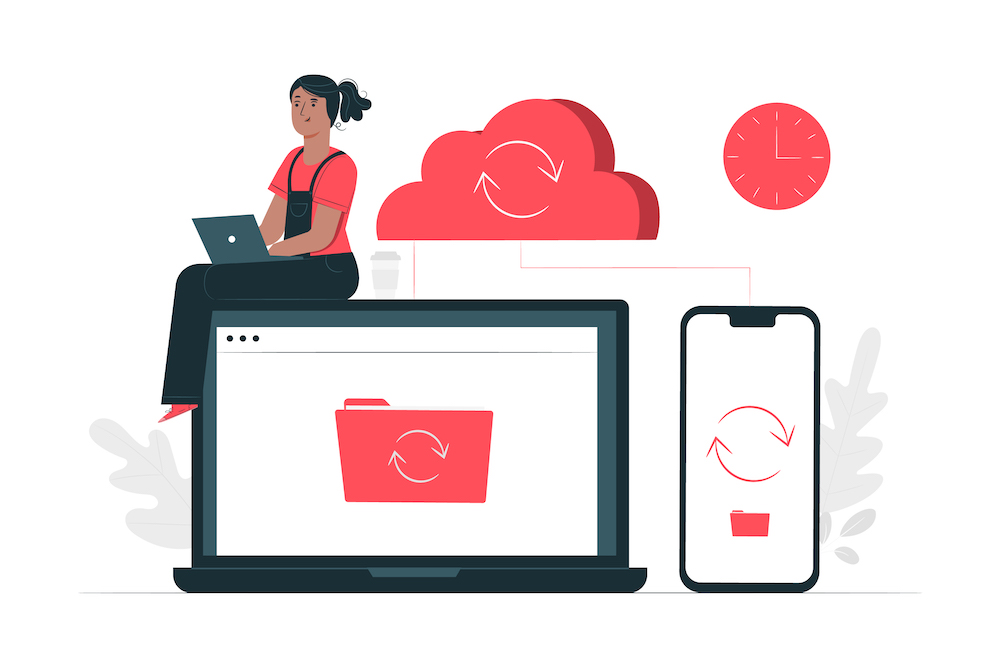
ここでは、クラウドストレージを導入する6つのメリットについてまとめておきます。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
1番目のメリットは、ファイルの一元管理による業務効率の向上です。
クラウドストレージを導入すれば、ユーザIDさえ持っていればいつでもどこでも必要な情報にアクセスできます。また、権限が与えられれば編集も可能です。作業工数を減らすことができるため、ムダを減らし、業務効率が上がります。
ファイルがさまざまな場所に分散すると、どのファイルが更新された最新のファイルかが分からなくなることがあります。しかし、クラウドストレージを活用して一元管理すると、すべてのユーザが常に最新のデータにアクセスできるようになります。
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
2番目のメリットは、ファイル共有や共同編集が簡単にできることです。
クラウドストレージがなければ、データをメールに添付して送り、受け取ったファイルを自分の端末で編集後、再度送付する作業が必要です。しかし、クラウドストレージがあれば、ファイル共有や共同編集を直接行えます。会社のパソコンだけでなく、出張先や現場などでスマートフォンさえあれば、ファイル共有が可能なのでとても便利です。
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
3番目のメリットは、いつでもどこからでもファイルにアクセスできる点です。
オンプレミスだと社内ネットワーク内でのやりとりに限定されますが、クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスのため、オフィスでも出先でも、自宅でも、コワーキングスペースでもアクセス可能です。
データやファイルにいつでもどこでもアクセスできるため、従業員の柔軟な働き方にもつながります。例えば、観光地やリゾート地で休暇をとりながらテレワークで仕事するワーケーションや、介護や育児などをしながら在宅で勤務する従業員にも必要なインフラを提供できます。
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
4番目のメリットは、ファイルサーバの運用や管理が不要になることです。
オンプレミスでは、システム構築や保守・運用に担当者を設置し、自社のリソースを割かなければなりません。それに対して、クラウドストレージでは、自社内のサーバ設置も、そのための運用管理のコストや人員も必要ありません。基本的にハード面での運用はクラウドストレージの提供会社が担ってくれます。
5. アクセス権限やログ監視機能によりセキュリティを強化できる
5番目のメリットは、アクセス権限やログ管理機能によるセキュリティの強化です。
上述したように、有料のクラウドストレージサービスはアクセス権限をこまかく設定できますし、ログ監視機能も充実しています。それにより、不正アクセスを防ぎ、万が一セキュリティインシデントが発生した場合も原因究明がしやすいといえます。
6. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
6番目のメリットは、災害が起きてもクラウドストレージならデータを消失するリスクが低いという点です。
日本が災害大国であることは誰も疑う余地がない事実です。実際、2008年から2018年の10年間で全世界で発生したマグニチュード6以上の地震の約13.1%は日本で発生しています。また、災害の被害額も1984年から2013年までの合計で全世界の17.5%を日本での災害が占めています。
クラウドストレージの場合、データは堅牢な構造のデータセンターに保存されているため、自社内のサーバに保存しているよりも、消失のリスクは低いといえます。企業のBCP(事業継続)計画の一環としても、クラウドストレージの導入は有効です。
参考:「情報通信白書(令和2年版)世界のマグニチュード6以上の震源分布とプレート境界(2010年~2019年)」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd121140.html)を加工して作成
BCP対策について知りたい方はこちら

ここでは、各業界で法人向けクラウドストレージがどのように活用されているか、具体例を3つ取り上げます。
建設業|現場でタイムリーに情報を確認。仕事効率が大幅アップ!
建設業の特徴はオフィスだけでなく、取引先や現場での業務が多いことです。そのため、クラウドストレージがあれば情報の一元管理が可能になり、必要な情報はいつでもどこからでもアクセス可能です。
例えば、本社でアップした資料を現場で確認したり、逆に現場で撮った写真を取引先のフォルダにアップすることでデータ共有が完了します。データをタイムリーに共有できるため、業務効率がアップし、勤務時間の短縮にもつながるなど従業員のワークライフバランスに寄与します。
製造業|自社サーバを無くして管理コストや災害リスクを大幅削減
製造業に限ったことではありませんが、自社サーバを管理するには設置費用、電気代、保守運用のための人件費など、膨大なコストがかかります。クラウドストレージに切り替えることでそれらの費用を大幅に削減することが可能になります。
また、自社サーバの運用ではいくら建物の耐震性を強化しても災害リスクの削減には限界があります。この点、クラウドストレージなら、堅牢なデータセンターにデータが保管されていますし、被災リスクの低い場所が選ばれているため、災害リスクも大幅に低減します。
教育機関|ユーザ数無制限のクラウドストレージで費用削減
教育機関でクラウドストレージを活用したい場合はユーザ数無制限のプランがおすすめ。学生を含め利用者が多数に上ることが想定される場合でも、ユーザ追加コストの心配がありません。また、学生は閲覧のみ、教員には編集権限を与えるといった、ユーザごとのアクセス権限変更も可能であり、機密情報の管理も安心です。さらに、フォルダごとにアクセス可能なユーザを設定できるため、クラスや研究室ごとに使い分けることも可能です。
クラウドストレージについて知りたい方はこちら
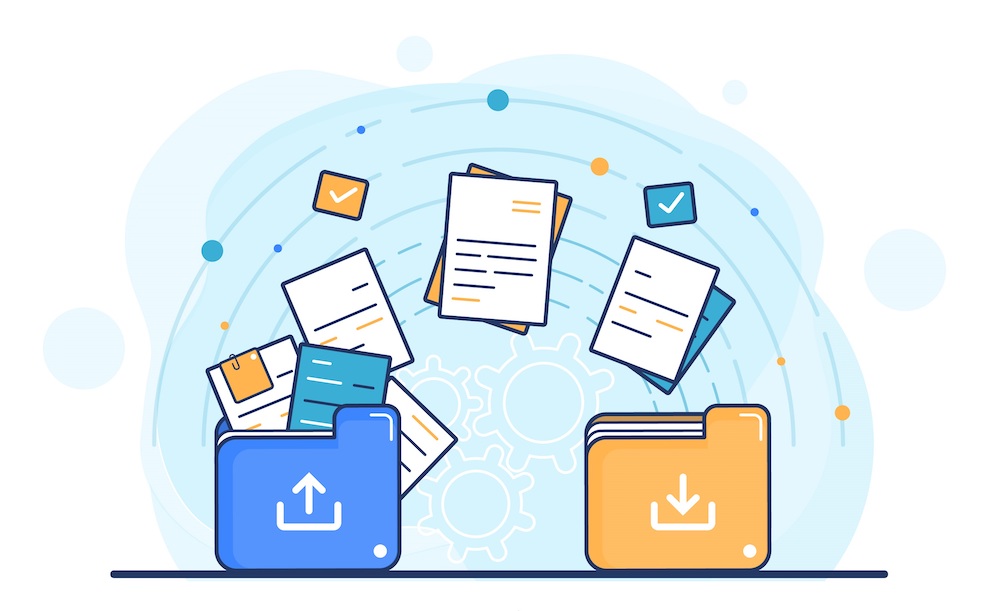
導入に多くのメリットがあるクラウドストレージですが、企業側が気を付けたいポイントもあります。ここでは、5つの注意すべきポイントを取り上げます。
インターネット環境の整備
1つ目のポイントは、インターネット環境の整備です。クラウドストレージはインターネットを経由して使うサービスのため、インターネット環境に大きく依存します。特に企業規模が大きく、多くの従業員が同時にクラウドストレージにアクセスする場合、高スペックの通信速度が必要です。
また、災害時だけでなく、システム障害などでネットワークが切断される可能性もあります。クラウドストレージにデータを保管している場合、オフィス内のネットワークが突然切断される可能性も考慮に入れておかなければなりません。さらに突発的なアクセス集中による負荷増大も考えて、予備設備を準備しておくこと(冗長化)も忘れないようにしましょう。
セキュリティ対策
2つ目のポイントは、セキュリティ対策です。クラウドストレージサービスを選ぶ際に提供会社がどの程度のセキュリティ対策を行っているのか見極める重要性については上述しました。ただ、セキュリティに関しては利用者である企業側にも責任があります。
例えば、提供会社がどれだけ強固なセキュリティ対策をとっていても、利用者側のパスワードやIDの管理体制が不十分であれば、情報漏えいや不正アクセスにつながります。そのため、パスワードを連続して入力できる回数を制限したり、定期的にパスワードを更新したり、人目につくところにメモで貼ったりすることがないよう、従業員全体に注意を喚起する必要があります。
IDに関して忘れがちなのが、退職者のID管理です。退職した社員のIDをそのままにしておけば、そのIDやパスワードがどのような形で誰に渡るか分かりません。そのため、退職と同時にすぐにIDを無効化する手続きをとりましょう。
脆弱性について知りたい方はこちら
運用体制の整備
3つ目のポイントは、クラウド導入時に運用体制を整備することです。運用体制とは、役割や責任の区分を明確にしておくということです。
中小企業でありがちなのは、経営者のITリテラシーがあまり高くないため、情報管理の担当者に導入から運用まですべて任せきりにしてしまうケースです。クラウドストレージの導入は企業にとって貴重な資産である情報を扱いますし、顧客情報の管理にも関係するため、経営課題として経営層が積極的に関わることが不可欠です。
運用体制を確立した上で、以下の点も導入時には行っておきましょう。
・運用ルールの作成
・マニュアルの整備
・トラブル時の連絡体制、問い合わせ先の明確化
・研修や周知徹底の手段
拡張機能による課金
4つ目のポイントは拡張機能による課金に注意するということです。
クラウドストレージの料金体系については上述しましたが、多くのサービスではさまざまなオプションをつけて機能を拡充することが可能です。その中には遠隔地へのバックアップを行ってくれる「ディザスタリカバリ機能」や、共有したファイルをアーカイブとして保管する「アーカイブ機能」などがあります。
利用を開始してから、次々とオプション機能を追加してしまうと毎月のコストがかさんでしまいます。自社にとって必要なオプション機能は何か、また毎月の利用コストの予算を超過しないかなど申し込み前によくチェックしておきましょう。
データ移行
5つ目のポイントはクラウドストレージ導入時のデータ移行です。これまで自社のサーバに保存されていたデータを移行する作業が必要です。この移行作業は無償(初期費用に含まれるため)で行ってくれる提供会社が一般的ですが、別途有償のサービスを利用しなければならない場合もあります。
.png)
ここでは、中小企業のリモートワーク導入にも対応している「使えるファイル箱」について解説します。
使えるファイル箱の3つの特長
使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」はデータ容量課金制で安心して使えるクラウドストレージサービスです。ここでは3つの具体的な特長を説明します。
1. ユーザ数無制限
使えるファイル箱の最大の特徴は、ユーザ数無制限で使用できることです。成長スピードの早い中小企業でも、最初は少人数からスタートし、追加料金を払うことなく事業規模に合わせてユーザ数を自由に設定できます。また、細やかな管理権限の設定が可能なので、ユーザIDの一部を取引先に渡して、大容量データのやりとりもできます。
2. 普段のパソコンと同じように操作できる
使えるファイル箱は特別なインターフェースを必要としません。例えば、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有ファイルを操作できます。中小企業でクラウドストレージを導入したものの、結局は従業員に使われることなく浸透しなかった、という事態を避けられます。
3. 高機能なのに低価格、全額返金保証もある
上述した通り、多くの中小企業がクラウドストレージ導入に二の足を踏む理由はコスト面での悩みです。そこで、使えるファイル箱はそんな悩みを少しでも軽減すべく、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。
また、2022年10月からは、1年契約の場合、初回契約期間中ならいつでも解約・返金申請できる全額返金保証を開始しました。中小企業のお役に立てる絶対の自信があるからこそできる、使えるファイル箱ならではの保証制度です。
中小企業に最適な機能と料金形態
具体的な料金体系を説明しましょう。
スタンダードプランのストレージ容量は1TBで、料金は1カ月契約の場合は25,080円(月額、税込)、1年契約の場合は21,230円(月単価、税込)です。セキュリティ機能が充実したアドバンスプランのストレージ容量は3TBで、1カ月契約の場合は75,680円(月額、税込)、1年契約の場合は60,500円(月単価、税込)です。例えば、スタンダードプランをお選びいただいた場合、従業員数100人の中小企業であれば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
最短で即日ご利用可能!
使えるファイル箱を試してみたいと思われたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
即日または翌営業日に対応させていただき、お見積りいたします。ご希望に合わせてオンラインでのご案内やトライアル、勉強会を実施させていただき、本契約となります。最短で即日のご利用開始も可能です。
.jpg)
(1)クラウドのデータはどこにあるの?
クラウドのデータはデータセンターに格納されています。データセンターの所在地は、クラウドストレージの提供会社によって異なりますが、多くの場合被災リスクの低い場所が選ばれます。また、国外にデータセンターを設置する場合もありますが、セキュリティや治安の面、また電力供給において不安定な場所もあります。
(2)法人向けクラウドストレージの市場規模は?
2022年に国内企業を対象に行われた調査によると、2021年度のクラウドサービス市場規模は約3.5兆円でした。今後、2025年~2026年には現在の2倍以上の規模まで市場が拡大するものとみられています。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
ファイル共有のセキュリティ対策として日本の多くの企業で採用されてきた「PPAP」。パスワード付きZipファイルとそのパスワードを2通のメールに分けて送受信する方法ですが、セキュリティリスクが高く、今では多くの行政機関や企業で禁止になっています。
それに取って替わってきているのがクラウドストレージを使った共有方法です。ここでは、クラウドストレージとはそもそも何なのか、そのメリットや数あるクラウドストレージの中で自社に最適なサービスを選ぶポイントについて徹底検証します。
目次
クラウドストレージとは?
クラウドストレージを導入するメリット
クラウドストレージを容量無制限にするメリット
容量無制限は必要?データ容量の目安
容量無制限のクラウドストレージ4つの比較ポイント
容量無制限のクラウドストレージを利用する際の注意点
容量無制限クラウドストレージ4選
ユーザ数無制限で利用できるクラウドストレージ3選
ユーザ数無制限「使えるファイル箱」3つのポイント
使えるねっとが選ばれる2つの理由
FAQ

クラウドストレージとは、インターネットでつながった場所(領域)にデータを保存する装置のことです。また、保存したファイルを共有することも可能です。
冒頭で言及したPPAPや社内サーバ経由で行われていたファイル共有にクラウドストレージを用いることで作業工数が減り、生産性が向上しました。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
クラウドファイル共有サービスを詳しく知りたい方はこちら

PPAPや社内サーバを使ったデータ共有方法と比較して、クラウドストレージを導入することにはどんなメリットがあるのでしょうか?以下、5つご紹介します。
ファイルサーバのクラウド化について知りたい方はこちら
データを一元管理できる
PPAPやUSBを使ってファイルをそのたびに渡す方法はセキュリティリスクが高いだけでなく、共有する際に手間がかかります。この点クラウドストレージはデータを一括管理できるため、共有の工数を劇的に減らせます。
データの共有による業務効率化を実現できる
上述したようなデータの共有が実現すれば、事業所や工場など拠点が複数ある場合にクラウドストレージを利用することで業務効率が向上します。また、多くの企業がテレワークを導入することで従業員の働き場所も多種多様になっています。相手がオフィスであっても出先や出張先であっても、インターネットがつながり、端末(もちろんスマホなどの携帯端末でも大丈夫)さえあれば、データ共有が可能であり、業務効率が格段に向上します。
テレワーク導入の要となる「クラウド化」について知りたい方はこちら
サーバの管理に時間を割かずに済む
クラウドストレージを利用しない場合、社内サーバを使ってデータ共有することになりますが、専門知識を有するスタッフが運用・管理しなければなりません。そうするためには当然時間と費用がかかります。
それに対して、クラウドストレージを利用すれば運用は基本的に業者に任せられるので、コスト削減が可能です。
どこからでもアクセスできる
上述したようにクラウドストレージなら社内サーバと異なり、どこからでもアクセスできます。例えば、営業担当が顧客先で急遽資料が必要になった場合、クラウドストレージならファイルの大きさに関係なく、ワンクリックで共有できます。
バックアップが自動で生成される
多くのクラウドストレージサービスは保管したデータを自動的にバックアップしてくれます。そのため、うっかり上書きしてしまったファイルの復元も可能です。
ただ、注意したいのは、クラウドストレージはバックアップ目的のサービスではなく、あくまでもファイル共有のためだということ。例えば、自分にとってバックアップが必要な重要ファイルをクラウドストレージに保管しているつもりでも、誰か別の人が削除すればバックアップ対象から外れてしまいます。
バックアップは「保管場所」として別途確保することをおすすめいたします。
クラウドバックアップとは何かを知りたい方はこちら
クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
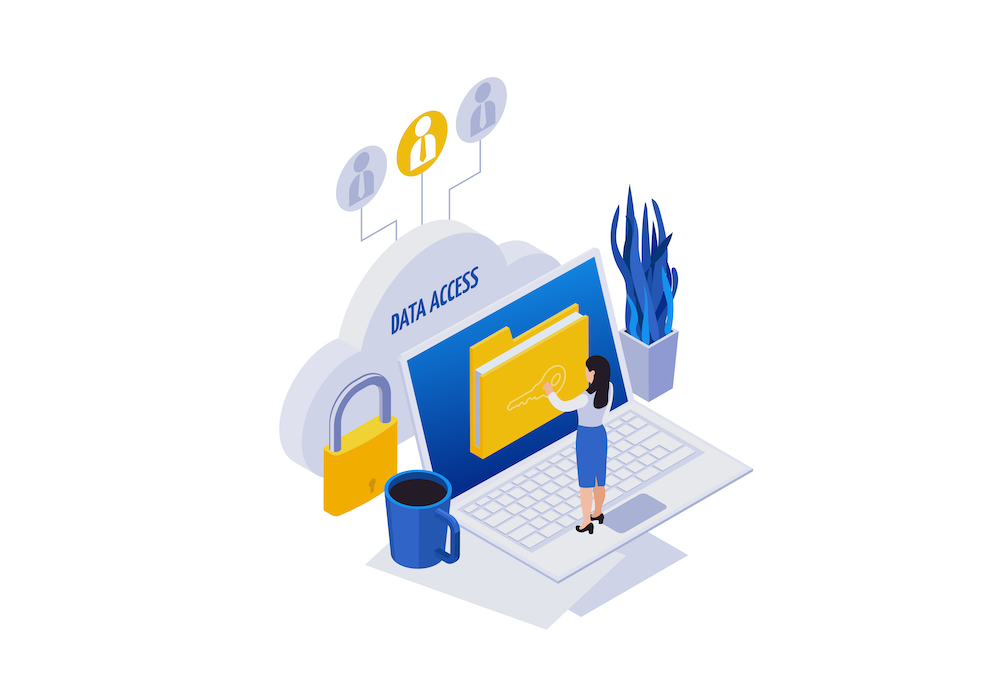
クラウドストレージを容量無制限するメリットは、サイズの大きなファイルやデータを大量に保存、バックアップできる点です。
どの企業もDXを進める中、ビッグデータの利活用が重要になっています。それに伴い、企業が保有するデータ量も年々増加しています。例えば、製造業や物流業では、IoTとAIを活用する事例が増えており、人が収集、保存するデータにとどまらず、IoT端末から得られるデータを加えるとその量は膨大になります。IDCによると、全世界で発生するデータ量は2025年には2016年のおよそ10倍になるともいわれているのです。
つまり、DXによって新たな価値を生み、競争優位性を保持しようとする企業にとって、大量のデータの保管は不可欠であり、そのためには容量無制限のクラウドストレージが効果的といえるでしょう。
参考:DIGITAL X 「2025年に全世界で発生するデータ量は163ゼッタバイトに、IDC調査」
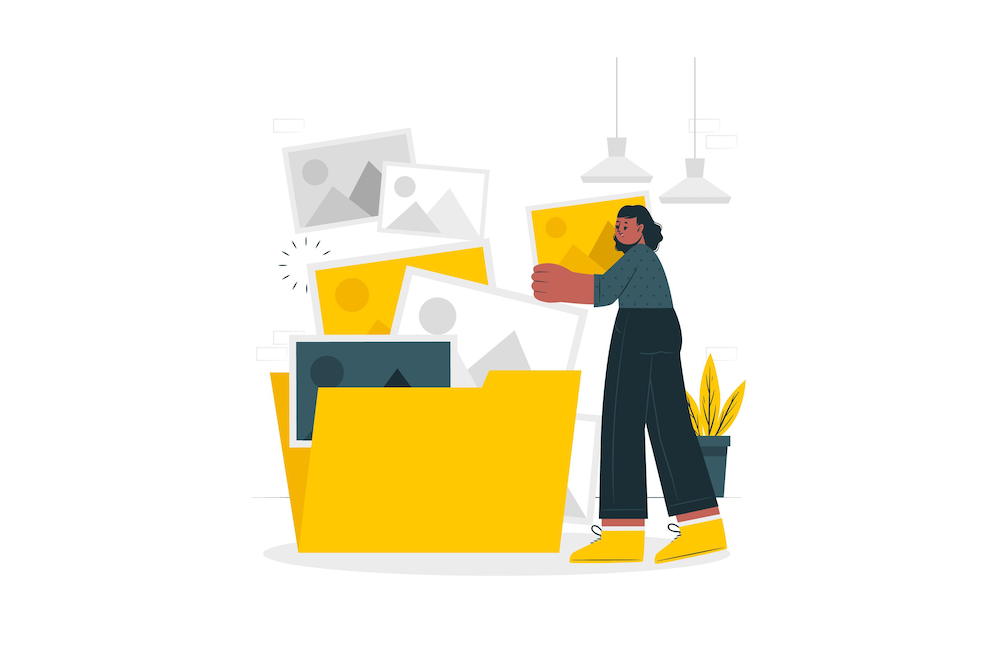
容量無制限のクラウドストレージは本当に必要なのでしょうか?
中小企業の中には、「容量無制限だとコストがかかるのでは?」「容量無制限のストレージが本当に必要なのか?」などと懸念している経営者、担当者の方も少なくないようです。ここでは、データ容量の目安について説明します。
写真のデータサイズの目安
写真のデータサイズの目安は以下の通りです。
・800万~2,000万画素のスマホカメラの場合:1枚3.6MB~24MB
・1,200万~1,800万画素のコンパクトデジカメの場合:1枚4.5MB~8MB
・1,200万~2,400万画素のデジカメの場合:1枚4.5MB~10MB
もし、画像データを1日100枚アップロードすると、1年で約3万6,000枚になります。1枚のデータが4.5MBであれば、年間162GBが画像データだけで必要になる計算です。
動画のデータサイズの目安
動画の容量はさらに大きく、10分のHD動画は1.8GBです。ちなみにフルHDであれば同じ1.8GBで時間は5分に、4K動画なら3分になります。
もし、3分の4K動画を1日1本アップロードすれば、年間657GBになります。動画制作会社や、メディアを扱う企業の場合、大容量のストレージが必要なことは明らかでしょう。
.png)
容量無制限のクラウドストレージを選ぶ際に注目したい4つの比較ポイントは以下の通りです。
・1度にアップできるデータ容量
・料金プラン
・セキュリティ対策の内容
・無料トライアル期間の有無
1つずつ説明します。
1. 1度にアップできるデータ容量
1つ目の比較ポイントは、1度にアップできるデータ容量です。
上述したように動画や画像ファイルを扱う場合、1つのファイル容量が大きいため、1度にアップできる容量が小さければ工数が増えてしまい、業務効率が低下してしまいます。できれば、1度にアップロードできる容量やファイル数に上限がないものを選びましょう。
2. 料金プラン
2つ目の比較ポイントは料金プランです。
クラウドストレージには主に「ユーザ課金型」と「プラン課金型(容量課金型)」の2つの料金体系があります。ユーザ課金型とは、各ユーザ1人ずつに課金される料金プランであり、プラン課金型とは、ストレージ容量に応じて課金される料金プランです。プラン課金型の中にも、ユーザ数に一定の制限があるものと、無制限のものがあります。
ユーザ課金型は、ユーザ1人あたりの料金がプラン課金型よりも抑えられている場合が多いため、利用ユーザが少なく、今後しばらくは従業員が大幅に増加する可能性が少ない場合はお得なプランといえるでしょう。
ただ、ユーザ課金型でスタートしたものの、業務規模の拡大とともにユーザを増やす必要が生じた場合、そのたびに追加IDやパスワードの管理の手間がかかります。また、大幅に増加した場合、1人あたりの金額にユーザ数を乗じることになるため、コストが急激に膨らむことも考えられます。他方、その分増えたストレージ容量を使い切れない可能性もあります。
それに対して、プラン課金型はコストをかけずに自由にユーザを追加できるため、従業員の増加に対応しやすく、取引先など外部にもアカウントを発行する敷居が低いといえます。また、社員入れ替え時などもアカウントを削除すれば事足りるため、管理者の業務簡素化にも役立ちます。結果的に多くのユーザで利用するようになれば、1人あたりのコストが低くなり、お得といえるでしょう。
もっとも容量課金型にもデメリットがあります。ユーザが少ない場合は1人あたりのコストはユーザ課金型に比べて割高になる可能性があります。
3. セキュリティ対策の内容
3つ目の比較ポイントはセキュリティ対策の内容です。
企業が管理するデータ容量が増大し、その重要性がますます高まっています。そのため、クラウドストレージサービスのセキュリティ対策の充実度は、比較ポイントの中で最重要といっても過言ではありません。
情報資産の重要度が増しているのに伴って、ランサムウェアなどのサイバー攻撃の頻度や悪質性も高まっています。もし、企業のセキュリティ対策が不十分で顧客リストや機密情報が流失してしまえば、取引先からの信頼を失いかねません。
セキュリティ対策は多岐に渡りますが、まずチェックしておきたいのが通信の暗号化です。例えば、WebブラウザとWebサーバ間の通信を暗号化するのに使われているのがSSL/TLSという通信手段です。また、悪意を持ったユーザがアクセスできないように、ユーザの真正性を確認するための多要素認証・2要素認証もチェックしておきたいところです。2要素認証とは、最初にパスワードなどで認証を行い、それを通過した場合に別の要素により認証を行うことを指します。
加えて、アカウントごとの動向をモニタリングできるように、管理者がログ監視できる機能も必要です。削除履歴やアップロード履歴、ログイン履歴などを確認できれば、何らかのセキュリティインシデントが発生した場合も、原因を見つけやすいでしょう。
4. 無料トライアル期間の有無
4つ目の比較ポイントは、無料トライアル期間の有無です。
現在、多くのサービスがUIをエクスプローラーに近づけており、直感的に使えるようにデザインされています。ただ、実際の操作性は使ってみないと分からないものです。無料トライアル期間があれば、オフィスで、外出先で、またテレワークをしているメンバーとの間でデータを共有する際の使いやすさを試してみて、フィードバックを集め、最終的に導入するかじっくり決められます。
参考:NTTコミュニケーションズ 「オンラインストレージの暗号化や多要素認証などセキュリティ向上のための機能」
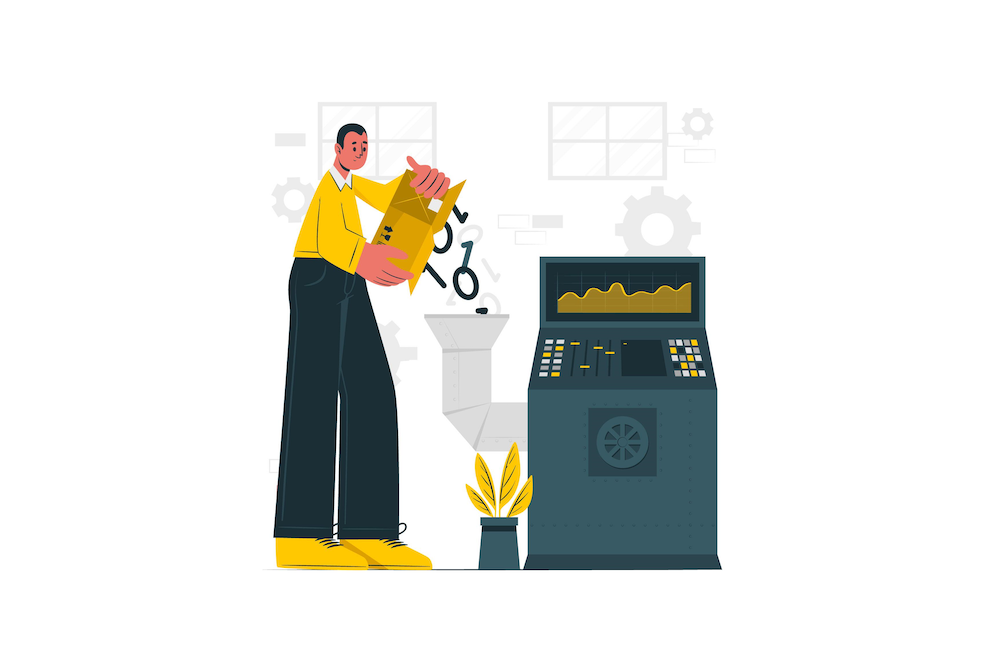
容量無制限のクラウドストレージを利用する際には以下の2点に注意しましょう。
・料金だけで判断しない
・容量無制限になる条件を確認しておく
料金だけで判断しない
容量無制限のクラウドストレージを利用する際の1つ目の注意点は、料金だけで判断しないことです。
どうしても料金が安ければお得だと考えてしまう傾向がありますが、機能面、セキュリティ面も含めて総合的に考慮しましょう。例えば、いくら料金が安くても、セキュリティ面で脆弱であれば、サイバー攻撃を受けやすくなり、情報流出につながるリスクが高くなります。結果的に損害賠償請求されることにでもなれば、長期的にみれば莫大な損失を被ってしまいます。そうなれば、まさに本末転倒でしょう。
容量無制限になる条件を確認しておく
容量無制限のクラウドストレージを利用する際の2つ目の注意点は、容量無制限になる条件を確認しておくことです。
具体的には、利用するユーザ数に条件があることが多いです。ほかにもサービスによって満たさなければならない条件があるため、契約前に確認しておきましょう。
|
サービス名
|
月額(1ユーザ)
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
Box Business
|
Businessの場合 1,881円~
|
・1,500以上のアプリ統合
|
・7段階のアクセス権制御
|
|
Dropbox Business
|
Standardの場合 1,500円~
|
・複数人での共同編集
・全文検索
|
・データ送受信時にSSL/TLS暗号化通信を採用
|
|
Google Workspace
|
Business Starterの場合 680円~
|
・他のGoogleサービスと連動可能
・ユーザ1人あたり30GBのストレージプール
|
・2段階認証
・エンドポイント
・高度な保護機能プログラム
|
|
Fleekdrive
|
Teamの場合 600円~
|
・クラウド上のOfficeファイルを直接編集
|
・自動ウィルスチェック
・24時間体制のモニタリング
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここでは、容量無制限のクラウドストレージのほか、ユーザ数無制限のクラウドストレージを紹介します。
1. Box Business
Box(ボックス)はアメリカのBox社が提供するクラウドストレージサービスです。日本でもさまざまな代理店を経由してサービスを展開しています。Boxには、法人向けに「Business」「Business Plus」「Enterprise」「Enterprise Plus」があり、Box Businessはもっともベーシックなプランといえるでしょう。
Microsoft Office、Microsoft Temas、Salesforce、Google Workspace、Slackなど1,500以上のアプリケーションと統合可能であり、ビジネスツールとして高い機能性を有しています。
セキュリティ面では、7段階のアクセス権制御で高度なセキュリティを実現。ユーザ一人ひとりに対して、閲覧、編集、ダウンロードの可否などを細かく設定できるため、トラブル回避にも有効です。
注意したいのはストレージは容量無制限ですが、Businessの場合、単一ファイルのアップロード容量上限が5GBであることです。また、最大ユーザ数は上限なしですが、最小ユーザ数が3人であることも覚えておきましょう。料金は年一括払いで、1ユーザ・月当たり1,881円(税込)です。
|
プラン
|
Business
|
Business Plus
|
Enterprise
|
|
料金
(1ユーザ、月額、税込)
※年払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
公式HP:Box
2. Dropbox Business
Dropbox Business(ドロップボックスビジネス)は、無料のクラウドストレージサービスDropboxの法人向けサービスです。
事業規模に合わせて「Plus」「Professional」「Standard」「Advanced」の4つのプランの中から選べます。最低利用ユーザ数や、ユーザ1人あたりの利用容量が異なります。以下の通りです。
・Plus:ユーザ1人、ユーザ1人あたり2TB
・Professional:ユーザ1人、ユーザ1人あたり3TB
・Standard:ユーザ3人以上、チーム全体で5TB
・Advanced:ユーザ3人以上、チーム全体で15TBから開始
他のビジネスソフトとの親和性も高く、Microsoft ExcelやPowerPointはブラウザから直接編集したり、数人で共同編集したりすることも可能です。また、ファイル検索機能がとても強力で、Plusを除くすべてのプランで全文検索機能を標準装備しています。他の人が作成したファイルも検索して見つけることが容易です。
セキュリティ面に関しては、データ送信時、受信時にSSL/TLS暗号化通信を採用しているため、盗聴による情報漏えいの心配を最小限にできます。また、データは暗号化されたブロックで保管されるため、万が一不正アクセスがあったとしても被害を最小限に抑えられます。
|
プラン
|
Plus
|
Professional
|
Standard
|
Advanced
|
|
料金
(1ユーザ、月単価)
※1年契約の場合
|
1,200円
※ユーザは1人
|
2,000円
※ユーザは1人
|
1,500円
※ユーザは3人~
|
2,4000円
※ユーザは3人~
|
公式HP:Dropbox Business
3. Google Workspace
Google Drive(グーグルドライブ)は、多くの個人ユーザに利用されています。Googleアカウントがあれば、15GBまで無料です。
法人向けのサービスは「Google Workspace」と呼ばれており、「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランがあります。「Business Starter」がユーザあたり30GB、「Business Standard」はユーザあたり2TB、「Business Plus」と「Enterprise」はユーザあたり5TBまで利用でき、「Enterprise」は追加リクエストが可能です。
Google Workspaceの強みは他のGoogleのサービスと連動できる点です。ドキュメントやスプレッドシート、スライドなどのビジネスソフトに加え、ビデオ会議システムであるMeetとも連携が容易です。そのため、テレワークを導入している企業など従業員の拠点がバラバラだとしても、チームでのスムーズな作業を可能にします。
セキュリティに関しては、2段階認証プロセス、エンドポイント管理、高度な保護機能プログラムを有しており、企業にとって重要な情報資産をしっかり保護します。
|
プラン
|
Business Starter
|
Business Standard
|
Business Plus
|
|
料金
(1ユーザ、月額)
※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
Enterpriseの料金はGoogleの下記サイトからお問い合わせ下さい。
公式HP:Google Workspace
4. Fleekdrive
Fleekdriveは、最低10ユーザから利用できる法人向けのクラウドストレージサービスです。プランは大きく「Team」「Business」「Enterprise」の3つに分かれています。主にストレージ容量が異なっており、容量無制限で利用できるのはEnterpriseです。Teamのストレージ容量は10GB×契約ユーザ数、Businessでは200GB×契約ユーザ数に設定されています。
クラウド上のOfficeファイルをシームレスに直接編集できるため、ローカルPCにファイルを保存する必要がありません。また、Officeファイルをはじめ、Adobeファイルもアプリを立ち上げなくても、ブラウザさえあれば手軽に閲覧可能。外出先などでスマホを使った資料チェックに便利です。
セキュリティに関しても万全の対策がなされています。ファイルをアップロードする際には自動でウイルスチェックを実行しますし、全てのファイルを暗号化します。また、あらかじめ決められたIPアドレスのみからのアクセスを許容する設定も可能。
さらに24時間体制で不穏なアクションをモニタリングし、何かあったら検出、自動で通知してくれます。加えて、ログインからログアウトまでの操作記録は5年間保管されるため、セキュリティインシデントが起きた場合は、原因追求も容易です。
|
プラン
|
Team
|
Business
|
|
料金
(1ユーザ、月額、税抜)
|
600円
|
1,800円
|
公式HP:Fleekdrive
|
サービス名
|
月額(プラン)
|
容量
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円~
|
1TB / 3TB
※年契約の場合、
初年度は全額返金保証
|
・AES256ビット暗号化
・2要素認証
・サーバ内シークレットキー
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
|
|
Xserverドライブ
|
スモールビジネスプランの場合 2,970円~
|
1~4TB
|
・監視ログでファイルの利用履歴やユーザーの動きを常に把握
|
|
Fileforce
|
Unlimited-1の場合 55,000円~
|
1~30TB
|
・アクセス権限管理
・管理者、ユーザの操作ログ確認
・上書き保存から60日間ファイルを保管
|
※記載の金額はサービスにより条件が異なります
1. 使えるファイル箱
使えるねっとのクラウドストレージ「使えるファイル箱」の特徴はユーザ数無制限、従業員が増えても課金の必要は一切ありません。また、分かりやすいインターフェースのため、操作性に優れていると評判です。
また、グローバルに展開している企業にとっては言語の障壁も気になる点です。この点、使えるファイル箱は24か国語で利用できるため、生産拠点やクライアントが海外にいる場合でもビジネスのスピードを落とすことはありません。
容量は1TBのスタンダードプランと、3TBのアドバンスプランがあります。どちらのプランも1年契約では、業界初の初年度全額返金保証が付帯します。もちろん、ご希望に応じて無制限に容量の追加も可能です。
機能
・普段通りの操作で利用可能
・IDやパスワード管理の一元化
・共有リンクの作成
・モバイル端末との連携
・ユーザごとに権限設定
・999世代まで復元可能な世代管理
・スキャンしたデータを自動でアップロード
・他のアプリケーションからも直接保存可
・ブラウザ上でOfficeファイルを直接編集&同時編集可
・共有フォルダへのアクセス権限の取り消し可
・発行したパブリックリンクの無効化が可能
セキュリティ
・AES256ビット暗号化
・2要素認証設定
・サーバ内シークレットキー対応
・ウェブ管理画面のSSL化
・ランサムウェア対策
・管理者権限で遠隔データを削除可能
・ISO認証データセンター(長野)
・指定のグローバルIPアドレス以外からのアクセスを制限(アドバンス)
・新しいデバイスでの初回アクセス時は認証された場合のみアクセス可(アドバンス)
・ダウンロード回数制限など、高度な共有リンク設定(アドバンス)
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
料金
(月単価、税込)
※1年契約の場合
|
21,230円
|
60,500円
|
※2024年3月27日までキャンペーン実施中。
1年契約の新規申込で、初年度価格が10%オフ+契約期間1カ月延長。
公式HP:使えるファイル箱
2. Xserverドライブ
Xserverドライブは、ユーザ数無制限の法人向け高速クラウドストレージサービスです。ストレージ容量上限によって、プランは大きく「スモールビジネス」「ビジネス」「ビジネスプラス」「エンタープライズ」に分かれています。
ストレージはHDDとSDDを選択できますが、HDDであれば、スモールビジネスは1TB、ビジネスで2TB、ビジネスプラスなら4TBです。さらに契約期間を3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月の中から選ぶことができ、契約期間が長ければ長いほど月額料金がお得になる料金体系です。
アップロードできる1ファイルあたりの上限はどのプランも同様に5GBで、スマホなどの携帯端末からもアクセスできるため、いつでもどこでもファイル共有が簡単です。また、部署やスタッフごとなど、柔軟に領域を変更して閲覧や共有、編集を制限できます。取引先へは面倒なユーザ登録をしてもらわなくても、URLを連絡するのみで情報共有可能です。
セキュリティ面も、ファイルの利用履歴やユーザの動きを常に把握する監視ログを備えているので、不審な動向や情報漏えいも許しません。
上記でご紹介しているプランの中からお好きなプランを選んで、10日間無料でお試しできるので、使い心地や操作性を確認してからの導入も可能です。
|
契約期間
|
スモールビジネス
|
ビジネス
|
ビジネスプラス
|
エンタープライズ(専用)
|
|
3ヶ月
|
3,960円
|
7,920円
|
15,840円
|
92,400円
|
|
6ヶ月
|
3,630円
|
7,260円
|
14,520円
|
84,700円
|
|
12ヶ月
|
3,300円
|
6,600円
|
13,200円
|
77,000円
|
|
24ヶ月
|
3,135円
|
6,270円
|
12,540円
|
73,150円
|
|
36ヶ月
|
2,970円
|
5,940円
|
11,880円
|
69,300円
|
※上記費用に加えて、初期費用がかかります。
※2024年1月9日~4月8日までキャンペーン価格で提供中。
公式HP:Xserverドライブ
3. Fileforce
Fileforce(ファイルフォース)は、初期費用0円で始められる法人向けのクラウドストレージサービスです。プランは大きく「Small Business」「Unlimited」「Enterprise」の3つに分かれています。大きな違いはユーザ数です。Unlimitedのみがユーザ数無制限で使えるプランであり、Small Businessは10~50IDを想定、Enterpiseは10ID以上に対応しています。
Unlimetedはさらに「Unlimted-1」「Unlimted-3」「Unlimted-10」「Unlimted-30」の4つに分かれており、基本ストレージ容量がそれぞれ1TB、3TB、10TB、30TBに設定されています。
機能も充実しており、エクスプローラーからアクセスし、ファイルサーバのようにファイル保存・編集、閲覧が可能です。また、ファイルをダウンロードしなくても、Officeファイルは高速、高精度のプレビューによって確認できます。アップロードは1ファイル10GBまで可能で、オプションで20GBまで増やせます。
セキュリティ対策も充実しており、アクセス権限管理や管理者、ユーザの操作ログの確認ができます。また、ランサムウェア対策として、ファイルのバージョンは上書き保存されてから60日間は保管されているため、ファイルが暗号化されてしまっても、利用可能です。
|
プラン
|
Small
Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
Enterprise
|
|
料金
(月額)
|
900円/
ユーザ
|
55,000円
|
98,000円
|
198,000円
|
330,000円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Fileforce
.png)
使えるねっとの「使えるファイル箱」は、いつでもどこでも、誰とでもつながるワークスタイルを実現する新しいクラウドストレージサービス。ユーザ数無制限で、ファイルの共有・編集・同期をどんなデバイスでも行えるのが特徴です。
1. ユーザ数無制限
他社サービスの大半は1ユーザ1ライセンス制を取っていますが、お得なビジネスプランはユーザ数にかかわらずひと月たったの21,230円(税込、1年契約の場合)から利用できます。加えて、容量もお得な1TBです。
たとえば100人で使えば月額1人210円程、300人では月額1人70円程度で済みます。法人向けプランはすべてユーザ数の制限がないので、急な増員などにも金額はそのままで柔軟に対応可能です。
2. 使い慣れたファイル構造でファイルを追加・編集・共有
使えるファイル箱は、ファイルサーバ型のクラウドストレージです。見慣れたフォルダ構造、使い慣れた操作方法のまま、クラウドのメリットを享受できます。ファイルの追加も編集も同期も、パソコンのエクスプローラーを操作するのとほとんど一緒。ファイルサイズの制限もないので、クラウドストレージにありがちな「容量が大きすぎてアップロードできない……!」といった事態も発生しません。
3. セキュアかつ簡単にファイルやバージョンを自由自在に復元
大容量・低価格のクラウドストレージは多々ありますが、大切なファイルを保存するにはそもそものセキュリティが非常に重要です。使えるファイル箱なら、外部のユーザやチームメンバーにファイルを送りたいときも、Webリンクを使用してたったの数クリックで簡単にシェアできます。共有用のWebリンクにはパスワードと有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心。共同作業用に共有フォルダを作成して、ユーザごとにフォルダのアクセス許可を制御することも可能です。
(1).png)
使えるねっとのクラウドサービスは、20年以上にわたって日本中のお客様からご利用いただいています。
1. クラウドストレージに最適なデータセンターのロケーション
使えるねっとのデータセンターがあるのは長野県。日本国内なので、海外にデータセンターがあるサービスよりも格段に速いスピードでデータにアクセスできるのが特徴です。さらに長野県は首都圏から離れ、比較的災害にも強いといわれているエリアなので、BCP対策としても非常に有効。まさにクラウドストレージにはベストな立地だといえるんです。
2. 充実のカスタマーサポート
使えるねっとのカスタマーセンターのスタッフは、全員自社専属のオペレーターです。専属スタッフならではの豊富な知識とノウハウで、お客様の課題解決を全力でお手伝いします。電話はもちろん、メールやチャットでのお問い合わせも受け付けているので、困ったときも安心です。
さらに大容量データのアップロードに便利なオプション「使えるファイル箱シャトル便」では、弊社が郵送したHDDにお客様のデータをコピーして宅急便でご返送いただけば、弊社側でお客様のファイル箱へアップロードを行います(1回/1TB 55,000円 追加1TB 11,000円)。
使えるファイル箱にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。無料トライアルのご希望もお待ちしております!
.jpg)
(1)無料で使えるクラウドストレージの容量は大体どれくらい?
無料で使えるクラウドストレージの容量は大体10GB前後です。
例えば、Google Driveは15GBまで無料で使用できます。中には、100GBまで無料で利用できるクラウドストレージサービスもあるようです。ただ、法人が利用する場合は容量の問題以外にもセキュリティ面も心配なため、有料プランを選びましょう。
(2)容量無制限のクラウドストレージの仕組みは?
容量無制限のクラウドストレージサービスの多くは、「〇人以上」「〇ユーザ以上」というように、使用人数に制限が設けられています。そのため、容量無制限のクラウドストレージは個人向けではなく、法人向けであることが分かります。ただ、容量無制限でも使い切れなければ意味がないため、セキュリティ面も考慮して、自社に最適のサービスを選ぶことが大切です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)







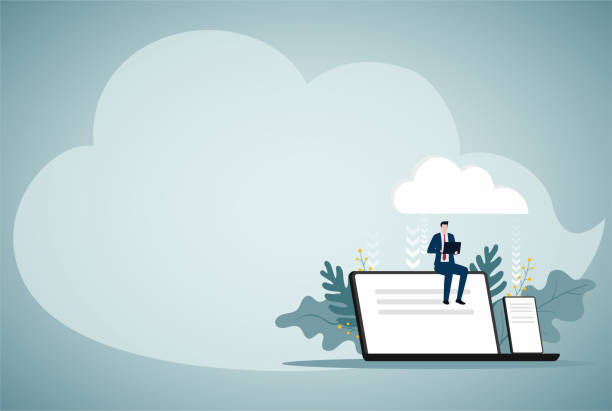





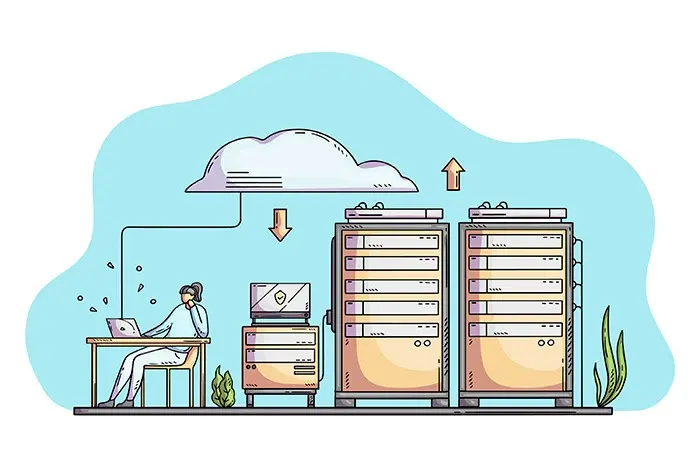


.png)
.jpg)
.jpg)


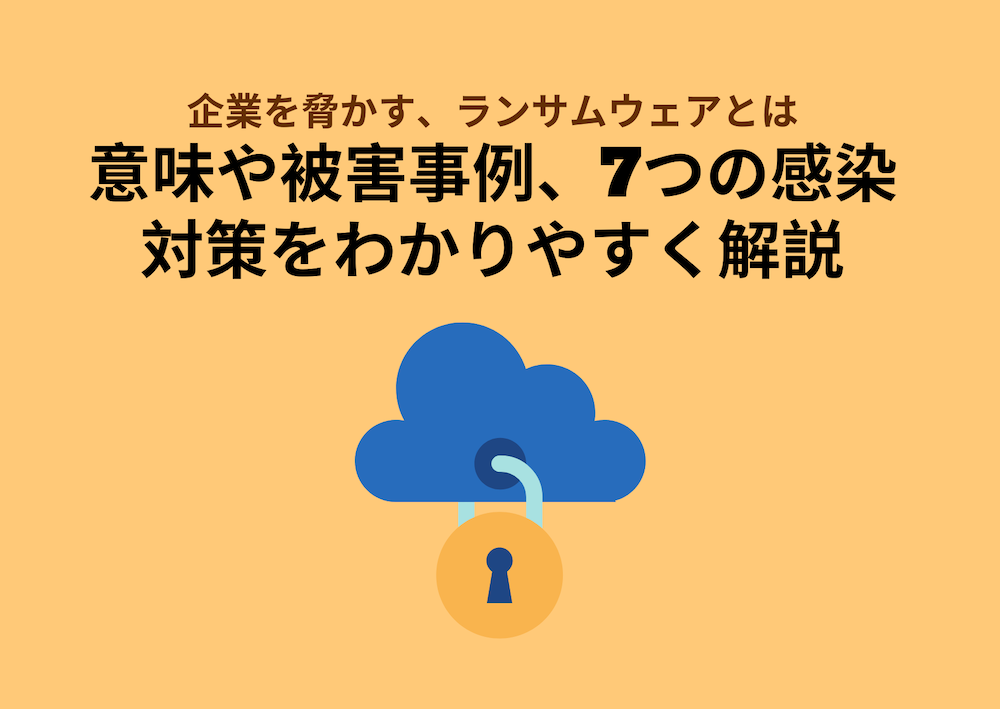


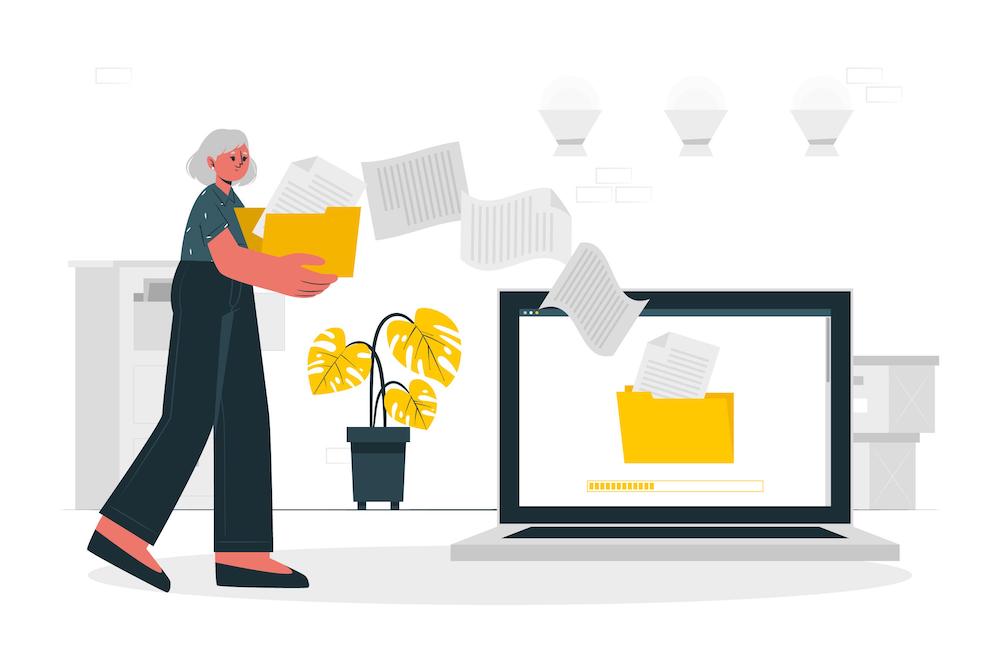
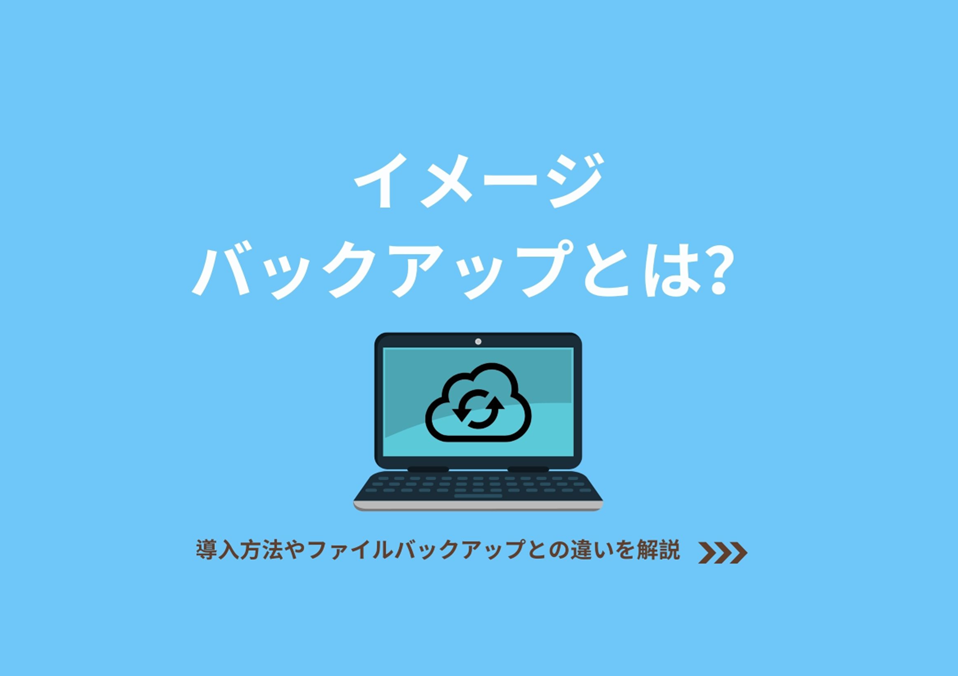

.png)
(2).png)
.jpg)
.jpg)


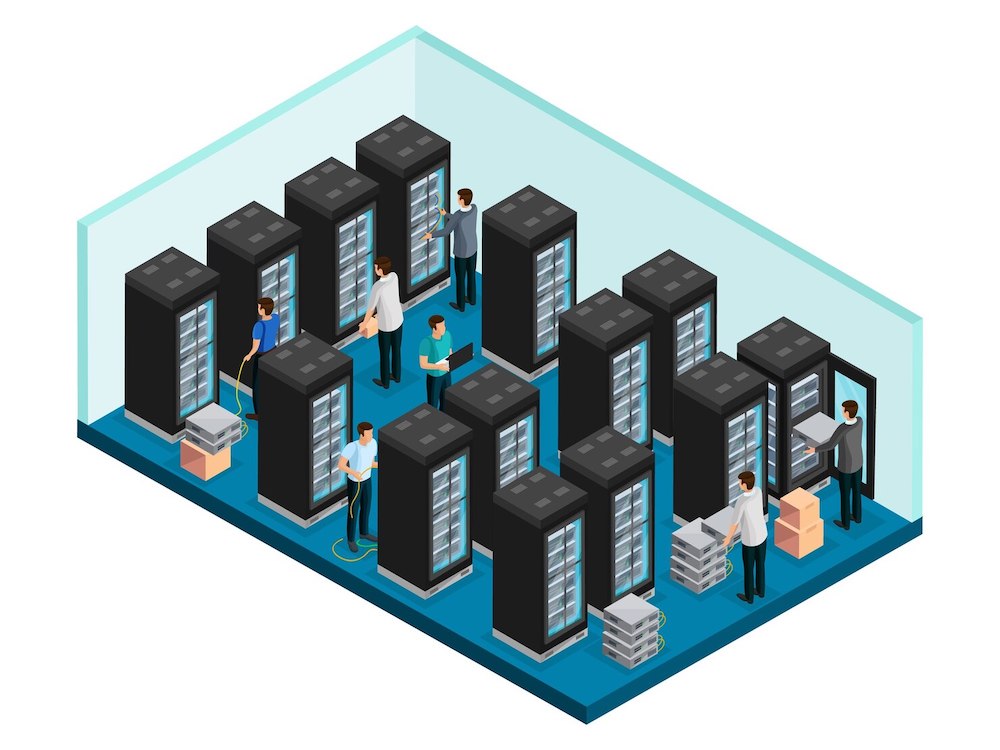

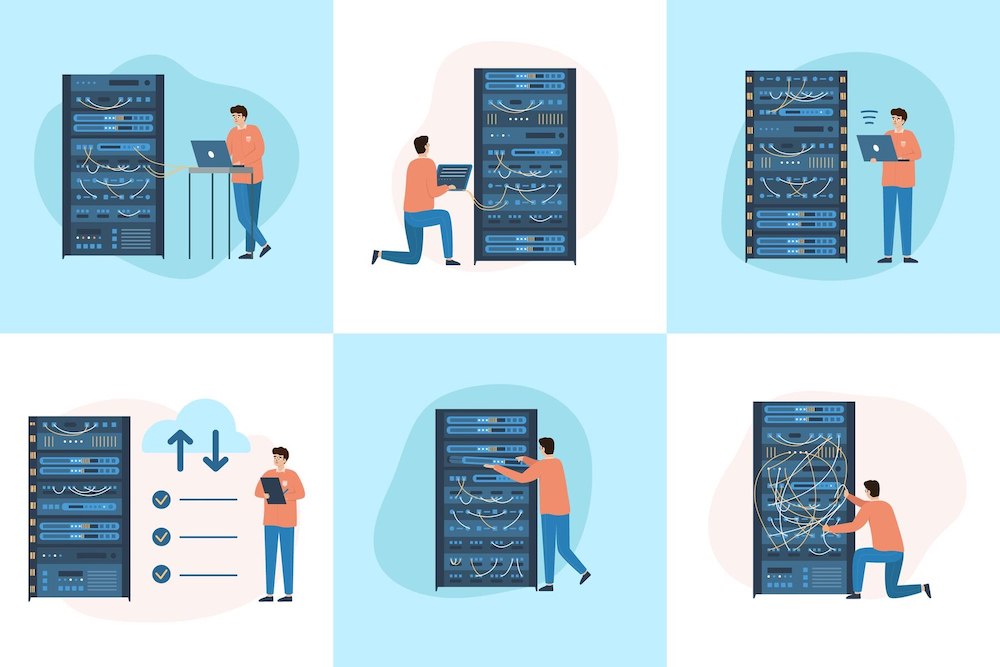

.png)
.jpg)



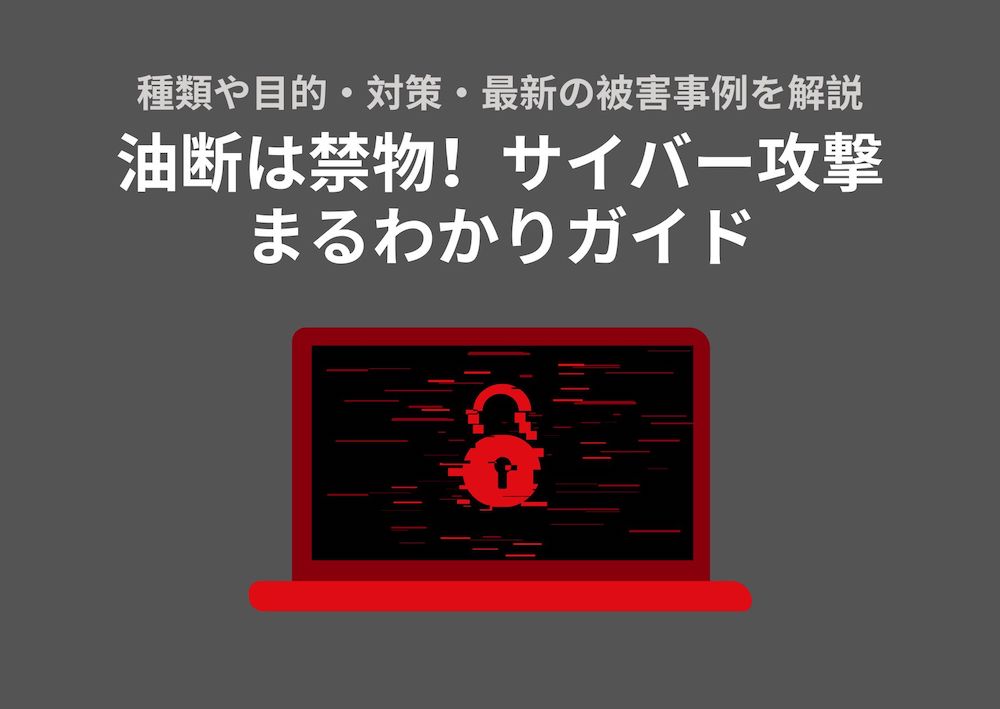
.png)


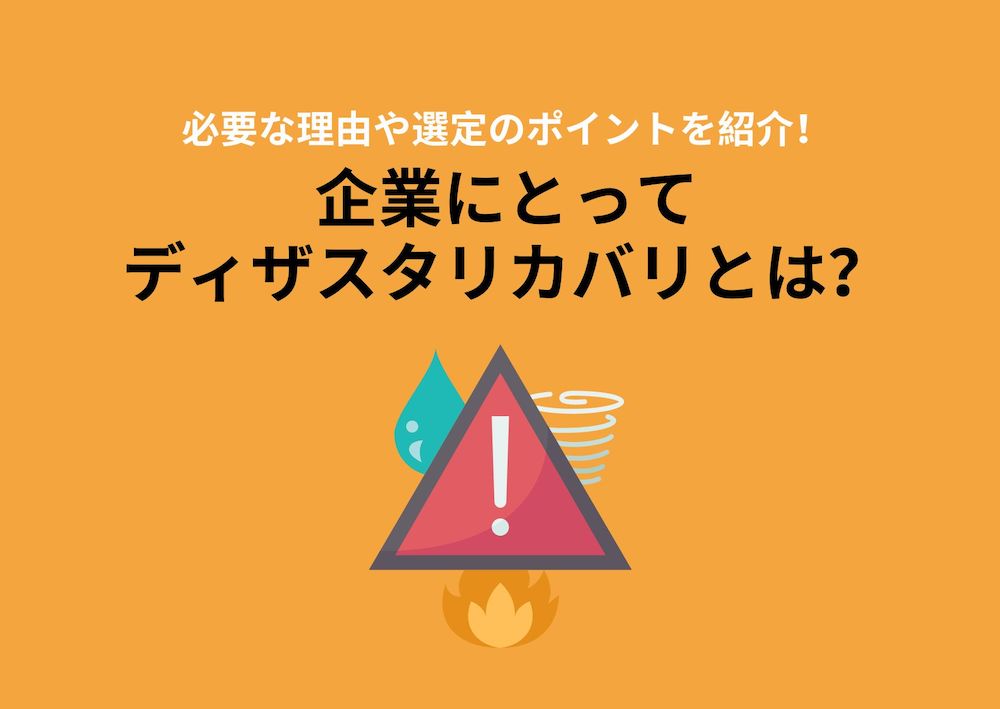


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
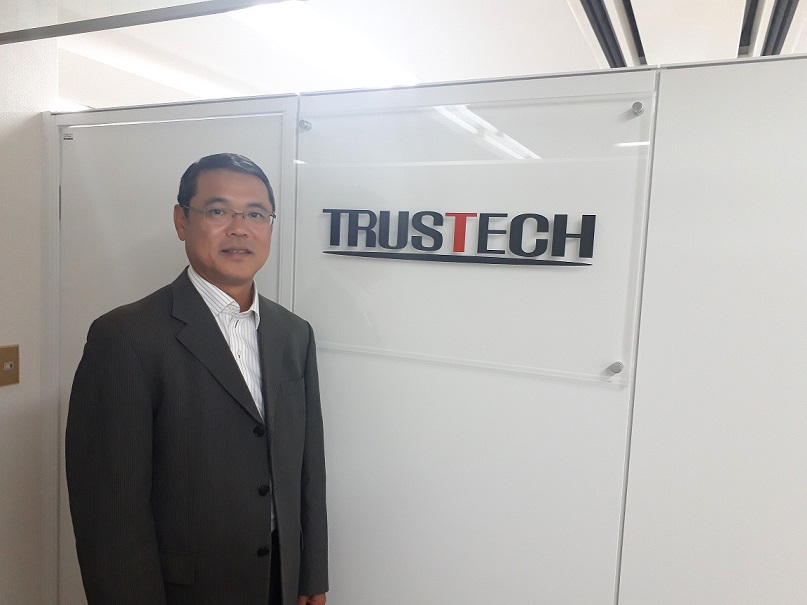

.jpg)
.jpg)

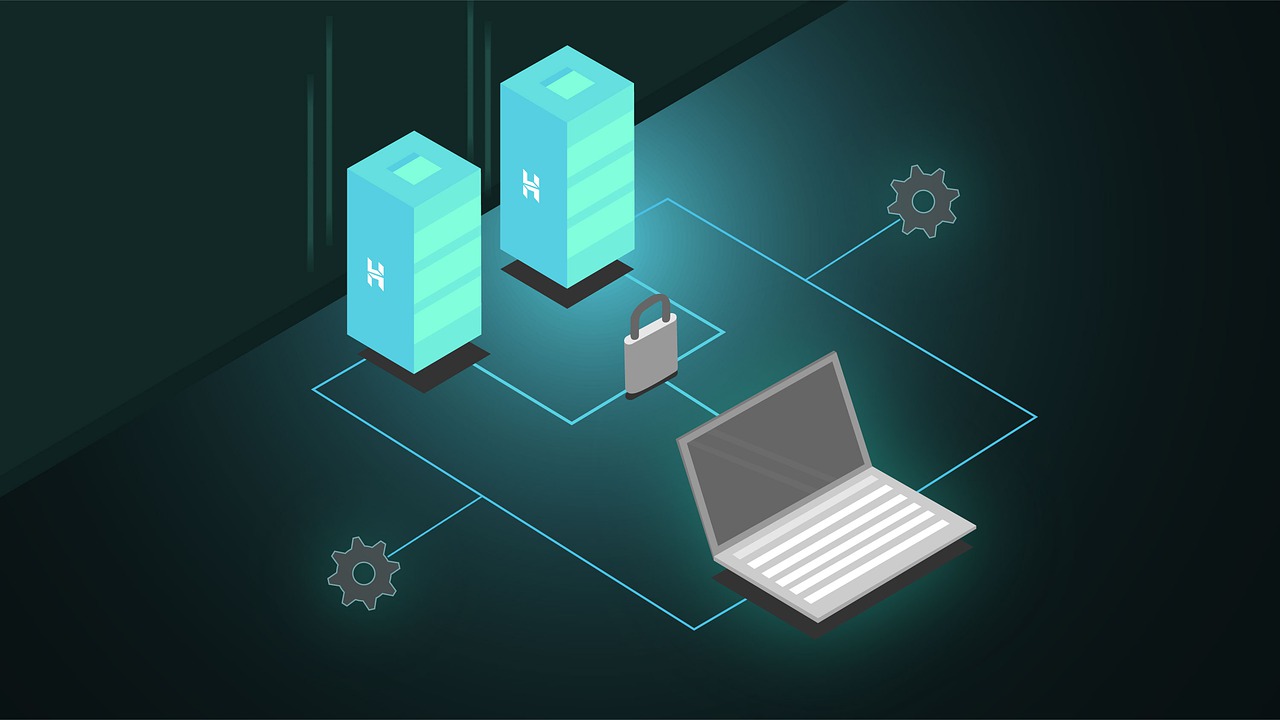
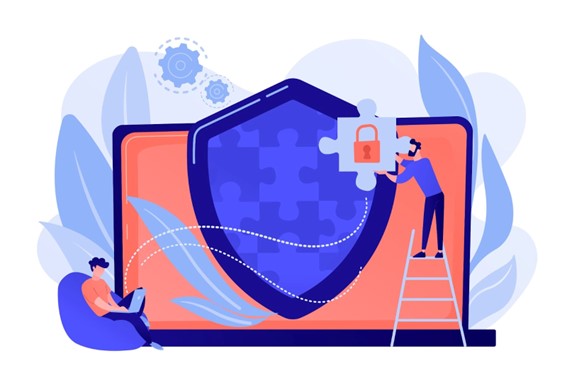
.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)

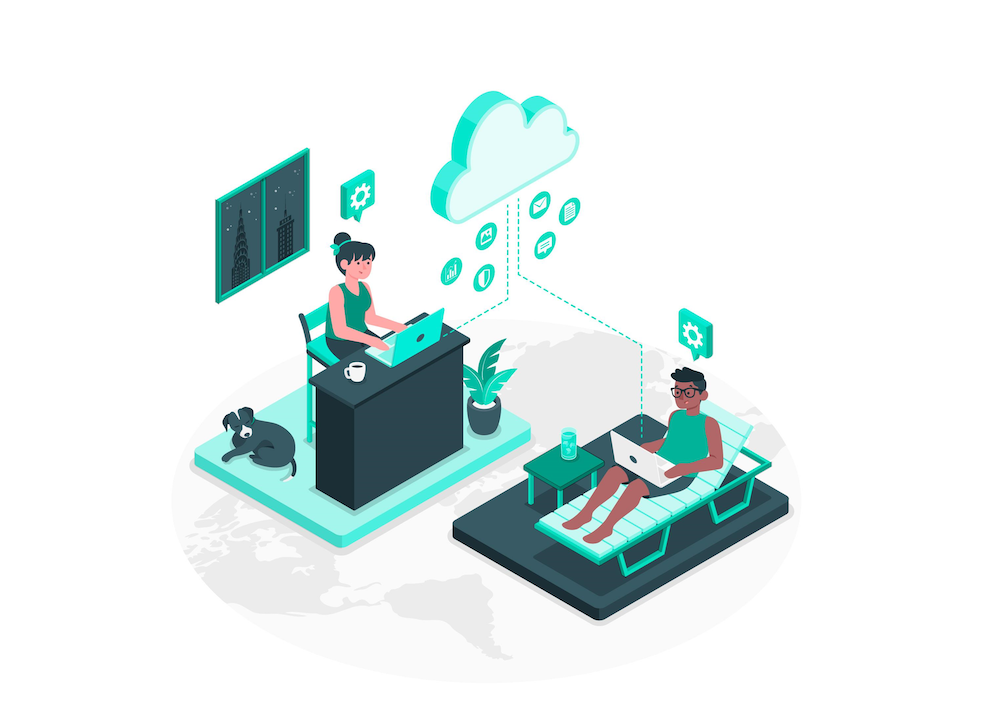


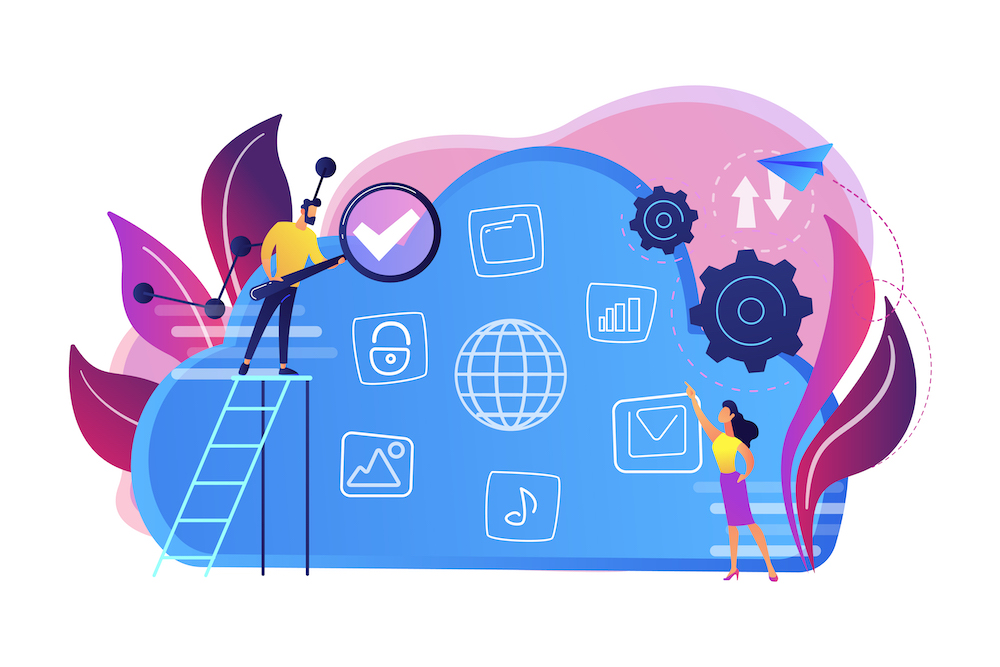

.jpg)
.jpg)


.png)





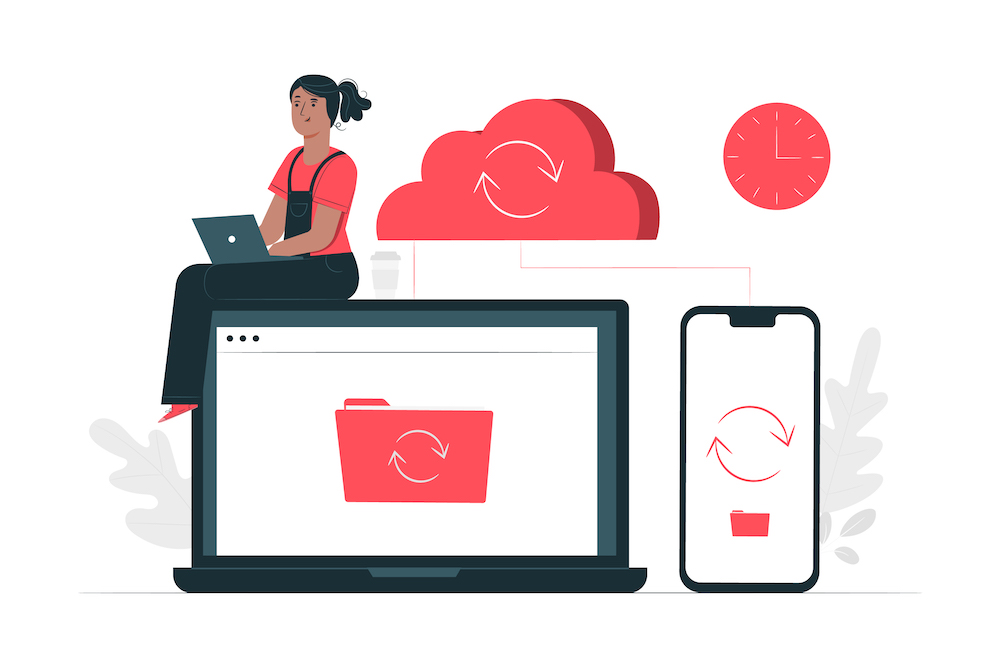

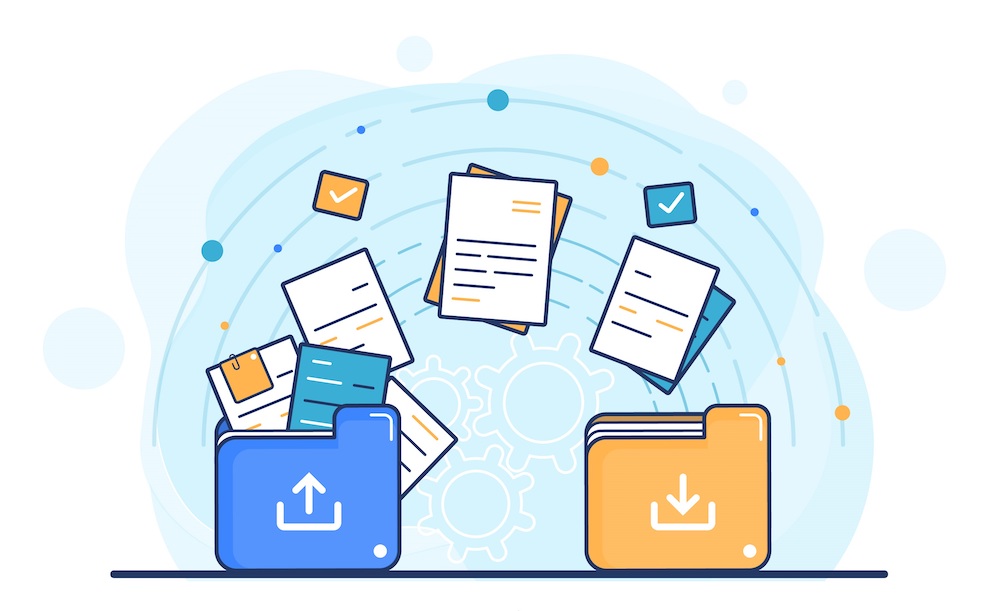
.png)
.jpg)
.jpg)


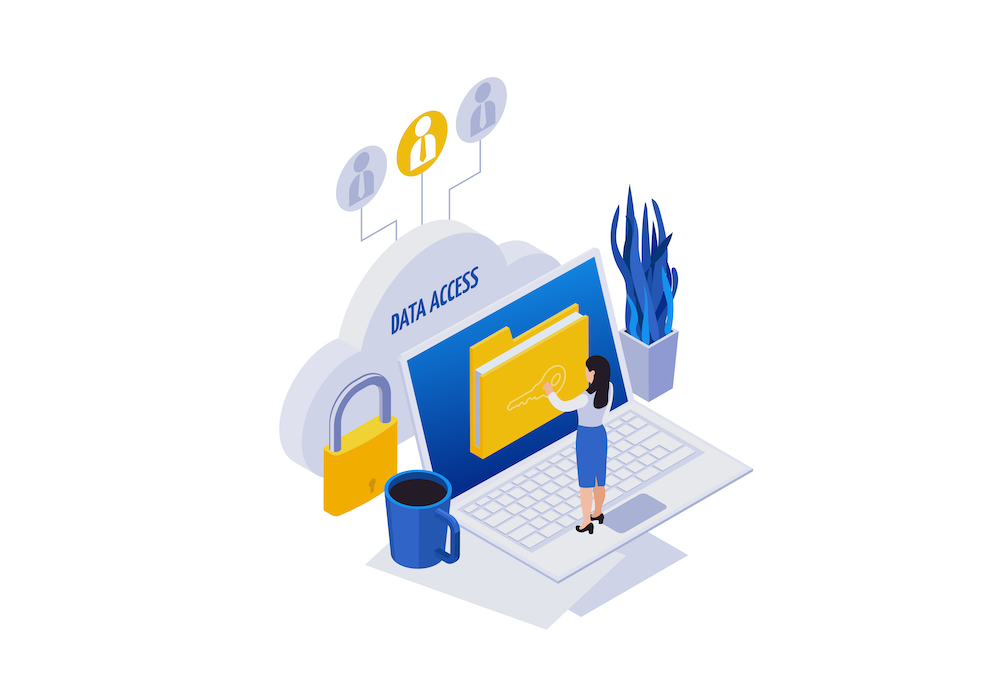
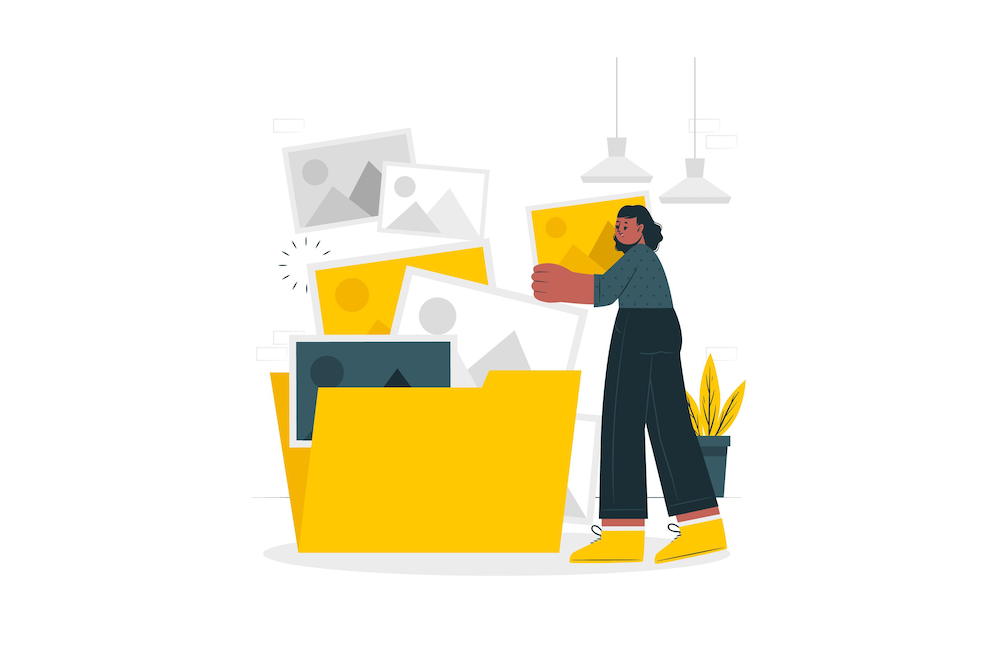
.png)

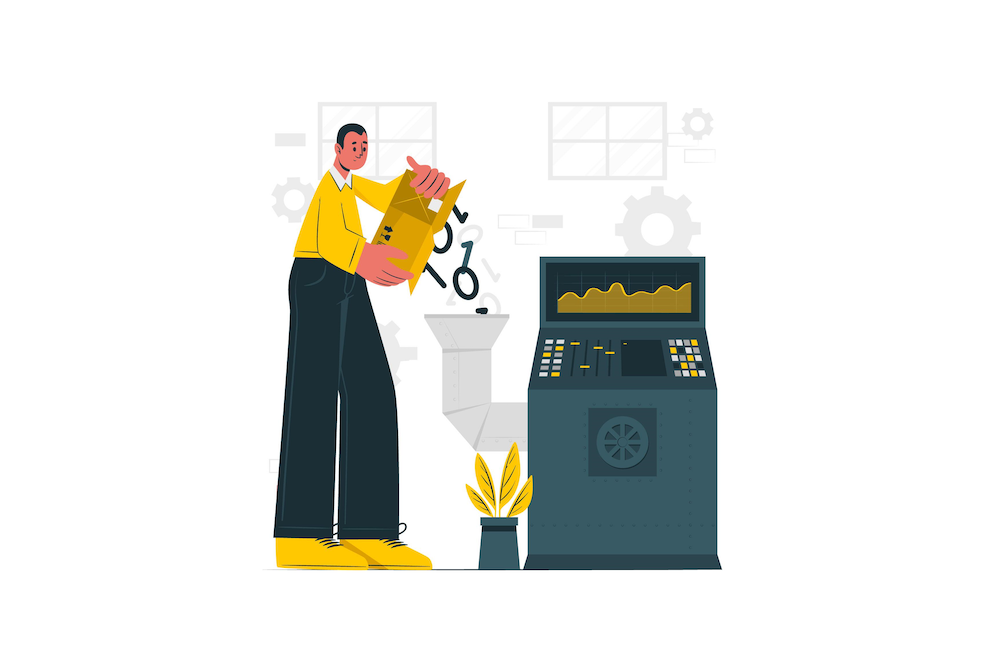
.png)
(1).png)
.jpg)
.jpg)
