日々、SNSや広告向けのコンテンツ制作に追われるマーケティング部署や制作チームの皆さん、動画保存や画像ファイルの共有に苦労していませんか?特に、大容量データのやり取りやストレージ容量の制限は、効率的な業務の大敵です。
多くのマーケティング部署や制作チームは、データの共有や編集・加工のためのツールとしてクラウドストレージを活用しています。今や、世の中にはたくさんのクラウドストレージサービスがあふれていますが、この記事では、中でもユーザ数無制限のクラウドストレージ「使えるファイル箱」にフォーカスして紹介します。
大容量動画やSNS素材をラクラク保存でき、チーム全体の生産性向上を実現したいご担当の方、必見です。
クラウドファイル共有について知りたい方はこちら
目次
データ容量の現実:マーケチームや制作チームの課題
必要なストレージ容量の目安と一般的なクラウドサービスの比較
大容量データを効率的にやり取りするポイント
「使えるファイル箱」の特徴とメリット
クラウドストレージでチームの働き方を変革しよう
FAQ
.jpg)
ツールのICT化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、どの企業、どの部署にとってもデータの重要性は高まる一方ですし、扱うデータ量は増加の一途をたどっています。
ここでは、マーケチームやコンテンツ制作チームが直面している課題について概観します。
マーケチームが直面する課題~データ量の増加
マーケチームや制作チームが直面している課題を一言で表すとすれば、データ量の増加です。その背景には以下の理由が挙げられます。
ユーザとデジタルとの接点が増加している
かつてユーザの購買行動は対面・店頭がメインでした。しかし、今では多くの人たちがECサイトや自社ホームページ、SNSなどを通じて、サービスや製品について認知し、購入するようになっています。こうしたデジタルとの接点の増加により、企業は膨大な情報を蓄積できるようになりました。
そのため、多くの企業が担当者の経験や直感にたよっていたマーケティングから、いわゆる「データマーケティング」「デジタルマーケティング」へとシフトしています。例えば、Webサイトの訪問者の行動データや購入履歴、ソーシャルメディア上の反応など、入手したデータをもとに顧客の趣向や行動傾向を把握し、マーケティング戦略に活用しているのです。
その結果、より顧客のニーズに合致したサービスや製品を提供することが可能になり、無駄なコストを削減し、効果的な販売戦略を展開できます。
SNS動画や広告動画の運用
デジタルマーケティングの中でも特に重要なのが「SNSマーケティング」です。SNSマーケティングとは、InstagramやXなどのSNSを企業の担当者が運用し、自社商品の認知や購買活動を促進し、ユーザの顧客体験を向上させ、ファン獲得を目指すマーケティング活動を指します。
多くのユーザが複数のSNSアカウントを保有しているため、SNSの効率的な運用により、企業はユーザとの継続的かつ効果的な顧客接点を持つことが可能になります。特に魅力的なSNS動画や広告動画を制作すれば、いわゆる「バズる」ことで、スピーディかつ爆発的に情報を拡散できます。
動画や画像ファイルの容量はどのくらい?
以上のように、マーケティングにおけるデータの重要性が大きくなるにつれ、マーケチームが保存する動画や画像ファイルの量も増大していきます。
マーケチームが日常的に制作する動画や画像ファイルの大きさはどのくらいなのでしょうか?例えば、1分のHD動画であれば約100MB、SNS用画像1枚であれば5MBを目安と考えていただければよいでしょう。動画1本、画像1枚であれば大した容量ではないように思いますが、動画であれば100本、画像であれば2,000枚で10GBに達します。
こうした動画保存や画像制作が続けば、あっという間に容量不足やデータ管理が課題になってしまいます。
.jpg)
データ量の増加に伴い、どのくらいのストレージ容量を必要とするかは各企業ごとに違いがあるでしょう。ただ、前述したように1分のHD動画100本で10GBに達することを考えると、年間で数十GB~数TB(1,000GB=1TB)に及ぶケースも十分考えられます。
1TB(テラバイト)とはどのくらい?パソコン(HDD)やデータストレージの容量も解説
データを保管する方法として考えられるのはサーバなどのオンプレミスか、インターネットを経由してデータセンターに保管するクラウドストレージです。それぞれメリットとデメリットがありますが、増加の一途をたどるデータ量に対応するためにはクラウドストレージがおすすめです。
オンプレミスVSクラウドストレージ
データ保管場所としてクラウドストレージをおすすめする理由は以下の通りです。
1. 拡張性
前述した通り、最大の理由はクラウドストレージの拡張性の高さです。オンプレミスの場合、初期設定の容量から増設するには、新たなファイルサーバを購入し、システム全体を再設定しなければなりません。
それに対してクラウドストレージは、サービス提供事業者にプランの変更やストレージの追加を依頼するだけで、容量を増やすことができます。
ファイルサーバのクラウド化と比較について知りたい方はこちら
2. コスト
オンプレミスの場合、導入する際に機器の購入やシステムの構築が必要なため、高額なイニシャルコストがかかります。また、専門スタッフによる保守・点検が常に必要なので、そのための人件費もかかります。
それに対して、クラウドストレージであれば、サービス提供事業者に依頼すればすぐに導入可能であり、ほとんどのサービスで初期費用は必要ありません。一般的に月ごと、年ごとの利用料を支払い続けます。当然、利用期間が長くなればなるほどコストは増えますが、社内に専門スタッフを常駐する必要がないため、別途の人件費は必要ありません。
一般的なクラウドサービスの比較
現在、個人や企業が利用できるクラウドサービスは山ほどあります。それらのサービスをストレージ容量に注目すると、容量無制限か否かで分けられます。
増え続ける社内データのことを考えると、容量無制限のサービスを選んだ方がよいのでは、と考える方は少なくありません。確かにマーケチームや制作チームの場合、扱うデータがテキストベースではなく、画像やデザイン、動画が多いため、必要なデータ容量も必然的に増えます。しかし、容量無制限であればその分コストがかかる可能性があります。必要性とコスト面でバランスのとれた選択をするように心がけましょう。
以下では法人向けのスタンダードなプランを比較してみましょう。
|
プラン
|
容量
|
利用可能なユーザ数
|
料金
|
|
Microsoft 365
Business Basic
|
ユーザ1人あたり
1TB
|
~300人
|
899円(月額、
ユーザ1人、税抜)
※年間サブスクリプ
ションの場合
|
|
Dropbox Business
(Busienss)
|
9TB~
(チーム全体)
|
3人~
|
1,500円(月額、
ユーザ1人)
※年間払いの場合
|
|
Box
(Business)
|
無制限
|
3人~
|
1,881円(月額、
ユーザ1人、税込)
※年間一括払いの場合
|
|
Google Workspace
(Business Standard)
|
2TB
|
~300人
|
1,360円(月額、
ユーザ1人)
※年間契約の場合
|
|
使えるファイル箱
(スタンダード)
|
1TB
|
無制限
|
21,230円(税込)
※1年契約の場合
|
.png)
セキュリティの確保
最初に注意したいポイントはセキュリティです。そもそもクラウドストレージをデータの保存先として選ぶということは、セキュリティ管理を自社ではなく、サービス提供事業者にお任せするということです。そのため、クラウドストレージサービスを選ぶにあたっては、セキュリティ面がどの程度充実しているかをチェックしておきましょう。
クラウドサービスへの不正アクセスによって情報漏えいが発生すれば、企業に対する信頼は失墜しますし、場合によっては金銭的な賠償も必要になりかねません。
また、企業によっては情報資産を守るためのセキュリティポリシーを定めている場合もあります。サービスの使いやすさだけでなく、自社のセキュリティポリシーに準拠しているかどうかにも注意しなければなりません。
さらに、マーケチームや制作チームの場合、社内だけでなく、クライアントなど社外ユーザとクラウド経由でデータのやり取りを行うことも考えられます。そのため、リンク共有や権限設定の管理を慎重にする必要があります。
アップロード上限
ストレージ全体の容量が無制限であっても、クラウドサービスの中には単一ファイルのアップロードに上限を設けている場合もあります。例えば、単一ファイルのアップロード上限が1GBであれば、ストレージ容量自体に余裕があっても、そのデータが1GBを超えれば保存することはできません。
マーケチーム、制作チームの場合、取り扱うデータが高画質な画像や動画ファイルの場合も少なくないため、事前に単一アップロードの上限を確認しておくことは欠かせません。
.png)
数あるクラウドストレージサービスの中で、特におすすめは使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」です。ここでは、使えるファイル箱の特徴とメリットを4つ紹介します。
無制限の容量で安心感:動画や画像を制限なく保存可能
使えるファイル箱は「スタンダード」と「アドバンス」の2種類のプランをご用意しています。
概要は以下の通りです。
|
プラン
|
容量
|
ユーザ数
|
料金
(月単位、税込、
1年契約の場合)
|
|
スタンダード
|
1TB
|
無制限
|
21,230円
|
|
アドバンス
|
3TB
|
無制限
|
60,500円
|
上図に示す通り、初期設定ではスタンダードプランの容量は1TB、アドバンスプランの容量は3TBですが、ご希望に応じて無制限に容量の追加が可能です。料金は1TBごとに月額8,580円(税込)です。
クラウドサービスによっては無制限がデフォルトのものもありますが、使えるファイル箱であれば必要に応じて追加できるため、より効率的にクラウドストレージを活用できます。
高速アップロードとダウンロード:業務の効率化をサポート
マーケチームや制作チームでは、日常的に頻繁にデータのやり取りを行います。それだけにスピードは欠かせない要素といえるでしょう。
使えるファイル箱なら、高速アップロード&ダウンロードで業務の効率化をサポートします。また、アップロードのファイルサイズ上限はないため、大容量のデータも気兼ねなく扱えます。
簡単な共有機能:社内外のコラボレーションをスムーズに
使えるファイル箱ならデータの共有も簡単。共有したいファイルを右クリックし、メニューから共有リンクを作成して送るだけです。
また、外部ユーザなどと連携する場合は、ユーザごとに権限を設定できるため、共有情報の管理が容易ですし、セキュリティ対策もばっちりです。
アドバンスプランの場合、グローバルIPアドレスを指定することで他のIPアドレスからクラウドストレージへのアクセスを制限できたり、新しいデバイスでの初回アクセスを管理者に通知することで、認証されたユーザのみにクラウドストレージにアクセスさせたりする機能も付帯しています。
コストパフォーマンスの良さ:競合サービスとのコスパ比較
使えるファイル箱のコストパフォーマンスを競合サービスと比較してみましょう。前述したように、多くのクラウドストレージサービスはユーザ1人あたりの料金を設定していますが、使えるファイル箱はユーザ数無制限で、スタンダードプランは月単価21,230円です。つまり、ユーザ50人で使えば1ユーザあたり約425円、100人だと1ユーザあたり約212円です。
容量が1TBでは心配なら、10TB追加してみましょう。1TBあたり8,580円ですから、10TB追加すれば85,800円が追加され、月単位の料金は107,030円です。これをユーザ100人で使っても1ユーザあたり約1,070円であり、コスパの高さがお分かりになるのではないでしょうか?
.jpg)
高機能かつコスパの高いクラウドストレージである使えるファイル箱を活用することで、大容量ファイルの共有や加工・編集も容易になり、忙しい現場のストレスを軽減できます。特に企業のマーケティング部署やSNSマーケチーム、広告代理店での運用において実力を発揮すること間違いなしです。
ここでは、使えるファイル箱の活用事例を2つ紹介します。
福助株式会社
福助株式会社は1882年(明治15年)に創業した老舗中の老舗で、足袋の製造、卸売、小売に加え、靴下・肌着・ストッキングの製造、卸売、小売を展開しています。2022年で創業140年を迎えた現在は、老舗の看板に甘んじることなく、オンラインストアの事業展開や有名ブランドとのライセンス契約など、デジタルも活用した戦略を推し進めている点が特徴です。
同社の課題は、中間卸に加えて直営店の運営も行っているため、約2,000社との取引があり、データのやり取りが急増していた点です。また、近年のハイブリッドな働き方の導入も増えており、社内外で安心してコストを抑えたクラウドストレージサービスを探していたといいます。
福助では使えるファイル箱の導入に向け、WEB事業部でトライアル期間を設け、1ヶ月ほどの試験運用を実施しました。トライアル期間中に社内への使えるファイル箱導入のアナウンスとマニュアルを準備していたこともあり、導入はスムーズだったそうです。
使えるファイル箱のスタンダードプランは容量が1TBと制限があるため、現在は一時的な共有用として使用しています。デザイン等で高画質な画像をよく使用するため、ファイルサイズが大きい場合の外部とのファイルのやり取りに活用しているとのことです。
株式会社NBG
株式会社NBGは全国規模のお酒の買取およびバー事業を展開している企業です。NBGの本社は京都ですが、他にも大阪、東京、福岡などにもオフィスを設置しているため、複数拠点でデータの共有を行う際にタイムラグが生じたり、データ送信の確認に手間取ったりなど、コミュニケーション面で課題が生じていました。
最終的に使えるファイル箱を選ぶ決め手となったのは、導入の手軽さ・使いやすさだったといいます。主に社内用のドキュメントを共有するために使えるファイル箱を活用しているそうですが、事業部や役職ごとにフォルダを分けるなど、細かい設定ができる点も便利だと感じています。
無料トライアルからお試しを
大容量動画や画像の保存も思いのままに行えるクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」。ユーザ数無制限で、ニーズに応じてストレージも無制限に拡張可能です。
まずは30日間の無料トライアルからお試しください。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
.jpg)
1. 動画ファイルの容量はどれくらいが一般的ですか?
動画の容量はフォーマット、解像度、フレームレート、動画の時間によって変わります。1分の動画であれば、容量は以下の通りです。
|
フォーマット
|
解像度
|
フレームレート
|
容量
|
|
MP4
|
1080p
|
30fps
|
約45MB
|
|
AVI
|
1080p
|
30fps
|
約80MB
|
|
MOV
|
1080p
|
30fps
|
約60MB
|
2. クラウドサービスで効率よく動画をアップロードするには?
クラウドサービスはインターネットを経由するので、通信状況の影響を大きく受けます。効率よく動画をアップロードするためには、高速回線の環境を選びましょう。また、バックアップ作業を同時に行っているとアップロードに時間がかかってしまいます。
3. チームでクラウドストレージを使う際の注意点は?
チームでクラウドストレージを使う場合、アカウントの管理が重要です。特にユーザ数無制限の場合、ユーザがいつの間にか増えてしまい、セキュリティ管理が手薄になってしまう可能性があります。社外ユーザもアクセスできる場合は、権限設定にルールを設けるなどの配慮が必要です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
令和5年の情報通信白書によると、世界のパブリッククラウドサービス市場は2021年に45兆621億円となり、前年比28.6%増加しました。日本のパブリッククラウドサービス市場も2022年に前年比29.8%増の2兆1,594億円に達しており、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるために今後どの企業もクラウドストレージをますます活用し、ICT基盤を強化していくことが予測されます。
今やビジネスに欠かせない存在となったクラウドストレージですが、自社にとって最適なサービスを選ぶのは至難の業です。ここでは、クラウドストレージの基本をおさらいし、クラウドストレージを比較するポイントをご紹介します。また、中小企業、個人事業主にぴったりのクラウドストレージサービスをおすすめします。
目次
クラウドストレージの特徴
法人・個人のクラウドストレージの上手な活用例
最適なクラウドストレージが見つかる6つの比較ポイント
無料ストレージと有料ストレージ、どちらを選ぶべき?
【法人・個人】「無料版の容量サイズが大きい」クラウドストレージ2選
【法人】「機能性重視」のおすすめクラウドストレージ9選
どのクラウドストレージを選ぼうか迷ったら
クラウドストレージの5つのメリット
クラウドストレージを活用・導入する際に注意すべきポイント
クラウドストレージを比較する際によくある質問
中小企業のリモートワーク導入におすすめの「使えるファイル箱」
FAQ

クラウドストレージとは?
クラウドストレージ(cloud storage)とは、インターネットを通じてアクセスする保管場所(データセンター)にデータを保存したり、転送・共有したりできるストレージサービスです。「オンラインストレージ」や「ファイルストレージ」と呼ばれることもあります。
クラウドストレージには以下のような特徴があります。
特徴1. いつでも、どこからでもアクセスできる
クラウドストレージはインターネットを通じてデータにアクセスするため、ネット環境さえあればどこからでもアクセスできます。スマートフォンやタブレットからでも利用できるため、出張先や営業先からでもストレージ上のデータをチェック可能です。そのため、コロナ禍での在宅ワークやテレワークの導入に伴い、その利用は増加しました。
日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とITRが国内企業1,022社を対象に2023年1月に実施した「企業IT利活用動向調査2023」によると、「大半はクラウドサービスを使っている」と回答した企業の合計は2022年1月の18.2%から23.8%に上昇しました。「一部クラウドサービスを使っている」と回答した企業を含めると、全体の約9割がなんらかの形でクラウドサービスを利用していることになります。
これらの調査結果からも、いつでもどこからでもアクセスできるクラウドストレージがテレワーク促進に貢献したことが分かります。

出典:日本情報経済社会推進協会「JIPDEC IT-Report2023 Spring」
特徴2. 必要に合わせて容量を調整可能
クラウドストレージは容量を増やしたり、減らしたりすることが可能です。一般的に容量の大きさと料金は比例するため、自社がクラウドにかけられるコストを必要に応じて調整できるのです。
例えば、従業員数の少ない中小企業がクラウドストレージを導入する場合、まず少な目の容量でコストを抑えておいて、業務規模の拡大や従業員数の増加に合わせて、徐々に増やしていくことができます。こうした柔軟な運用がクラウドストレージの特徴の1つです。
特徴3. 保守・点検が不要
クラウドストレージは自社で保守・点検を行う必要がありません。クラウドストレージの提供事業会社に在籍する専門家が保守・点検を行ってくれるため、自社のリソースを節約できます。もちろん、保守・点検が不十分であれば、重大なセキュリティインシデントにつながるため、サービスを選ぶ際には慎重に選択することが重要です。
クラウドストレージの主な機能
一般的にクラウドストレージは以下のような3つの機能を備えています。
機能1. 自動バックアップ
クラウドストレージは定期的に自動バックアップを行う機能を備えています。そのため、システム障害が発生したり、災害などで機器が破損したりしても、中にあるデータは保護されます。
バックアップを行わないとさまざまなリスクにつながります。例えば、トラブルが発生したときにシステムの復旧が行えず、業務取引や顧客との連絡が途絶えてしまう可能性があります。その結果、経済的損失が生じるばかりか、社会的信用を失うことにもなりかねません。さらに、コンプライアンス違反を指摘されたり、損害賠償を請求されたりすることも考えられます。
企業が保有するデータの量と重要性は日に日に高まっているため、クラウドストレージの自動バックアップは非常に心強い機能だといえるでしょう。
機能2. ファイル転送
クラウドストレージを使えば、サイズが大きいファイルを転送することも簡単です。
メールではサイズが大きすぎて送れないし、以前のようにフラッシュメモリを使って社内でやりとりするのはセキュリティ面で不安です。しかし、クラウドストレージなら、ファイルをオンラインストレージにアップロードし、相手にダウンロードURLをメールなどで連絡するだけで大きなデータのやりとりもスムーズに行えます。
ユーザとして登録しておけば、取引先など社外の人もデータのアップロード、ダウンロードを行うことができます。
機能3. ファイル共有
クラウドストレージにはファイル共有機能もあります。
ファイル共有機能を使うことで、オンラインストレージにアップロードされたファイルを複数人で閲覧したり、編集したりできます。チームメンバーすべてがオフィスに集まらなくても、クラウドストレージを使えば、在宅で業務をしている人も外出先でスマホでアクセスしている人も含めて、ストレスなく共同作業が可能です。
もちろん、管理者はファイルの閲覧や編集に関して制限を設けることができるため、部外者が社内や部署内の機密情報にアクセスすることはできません。
以上のような特徴や機能を前提にすると、クラウドストレージとオンプレミスには以下のような違いがあります。
クラウドストレージとオンプレミスの違い
違い1. データの保管場所
クラウドストレージは、インターネットを通じてアクセスする「クラウドサービス事業者のデータセンター」にデータを保管します。それに対して、オンプレミスは自社のサーバ内でデータを管理します。
違い2. 導入期間
クラウドストレージは、クラウドサービス事業者が提供するサービスであるため、データ保管のための環境はすでに構築されています。そのためすぐに導入できます。
それに対して、オンプレミスは自社の環境に最適化したシステムを一から構築しなければならないため、ハードウェアを購入・設定しなければなりません。導入を決定してから、実際にシステムを使えるようになるまで何か月もかかる場合も少なくありません。
違い3. コスト
クラウドストレージには、クラウドサービスを提供する事業者に対して利用する対価を支払います。初期費用はさほどかかりませんが、一般的に毎月、毎年ペースで利用料を払い続けるため、利用期間が長ければ長いほどコストが増大する可能性があります。
それに対して、オンプレミスの場合、前述したように導入する際に機器の購入やシステム設定が必要なため高額なイニシャルコストが発生します。ただ、いったん導入しさえすれば、あとは社内の担当部署の保守・点検のみで十分です。
違い4. 拡張性
クラウドストレージは、サービス提供事業者に対してプランの変更さえすれば、ストレージの容量を増やせます。
それに対して、オンプレミスの場合、新たなファイルサーバを購入し、再度設定しなければならず、拡張する上では手間がかかります。
参考:NTT東日本 「オンプレミスとは?意味やクラウドとの比較までわかりやすく解説」
オンプレミスについて知りたい方はこちら

法人・個人かかわりなく、クラウドストレージはサイズが大きいファイルの転送や共有をするために効果的なツールです。
法人に絞るとすれば、オンプレミスの負荷軽減のためにクラウドストレージを活用することもできます。全社が保有するデータやシステムをすべてオンプレミスだけに依存させると、アクセスが集中してシステムダウンが起きる可能性が高くなります。そうなると、システム復旧まで業務が停止してしまいます。
こうした事態を避けるために日常的にはクラウドストレージを使用し、もしもの場合に備えて重要なデータをオンプレミスに保管するのも1つの方法です。
クラウドストレージのメリットや上手な活用方法については後述します。
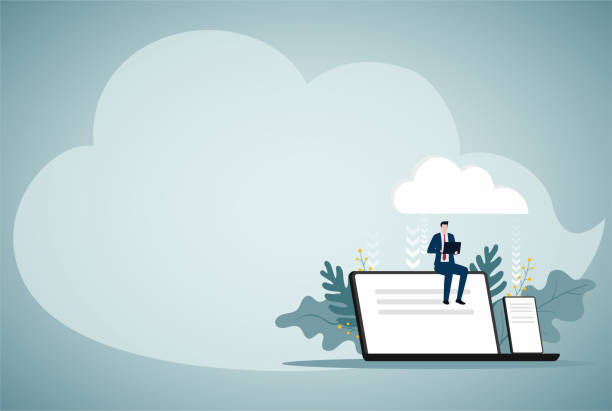
クラウドストレージのニーズが高まるにつれ、どんどん新しいサービスが登場しています。たくさんある中から最適なクラウドストレージを選ぶのは至難の業です。
ここでは、ぴったりのクラウドストレージを見つけるための6つの比較ポイントを紹介します。
1. 必要なデータ量を保存できるか
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
6. ストレスを感じない操作感か
1. 必要なデータ量を保存できるか
最適なクラウドストレージを選ぶ1つ目のポイントは、必要なデータ量を保存できるかという点です。
どのくらいの容量が必要かは個人と法人とでは大きく異なるでしょう。また、企業の中でも保存するデータがテキストベースの資料なのか、画像や動画が中心なのかによって変わってきます。例えば、デザインや図面を扱う企業であれば、必要なデータ容量も必然的に増えると考えられます。
法人向けのサービスには「容量無制限」のクラウドストレージがあります。確かに容量無制限であれば、将来データ量がどれだけ増えても安心と思うかもしれませんが、その分コストがかかります。必要性とコスト面でバランスのとれた選択をするよう心がけましょう。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
2. 料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスはどうか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ2つ目のポイントは、上述したデータ容量と料金プランのコストパフォーマンスです。
クラウドストレージサービスには、無料プランもあります。ただ、容量は5~20GB程度にとどまるため、法人で使用するにはやや足りない印象です。
有料プランを前提にすると、料金プランとデータ容量のコストパフォーマンスは「1GBあたりいくらか」で測ることができます。
3. ファイル共有やオンライン共同作業が可能か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ3つ目のポイントは、ファイル共有やオンライン共同作業に関してです。
上述したように、ファイル共有やオンライン共同作業はクラウドストレージの基本的な機能です。ただ、クラウドストレージサービスの中にはファイル共有機能のみに特化したものもあります。また、ファイル共有の際、リンクを共有することで閲覧するだけでなく、編集権限も付与できるか、パスワードや保存期間が設定できるかも異なります。自社の用途に合わせて、チェックしておきましょう。
4. 必要な機能やサービスが備わっているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ4つ目のポイントは、必要な機能やサービスが備わっているかという点です。
各事業者とも差別化をはかるために、さまざまな付加的なサービスを提供しています。例えば、以下のようなものがあります。
・スマホでも利用可能か
・導入後のサポートはあるか
・利用するすべての端末で利用可能か
・期限付き共有リンクの生成ができるか
自社の使用形態に応じて、必要十分なサービスが備わっているかも選ぶポイントの1つだといえるでしょう。
5. 万全なセキュリティ対策がされているか
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ5つ目のポイントは、万全なセキュリティ対策がされているかという点です。
セキュリティ対策を考えると、法人で無料プランは選ばない理由が分かります。当然ですが、利用料金が高くなればなるほど、事業者のセキュリティに対する責任は重くなるからです。
クラウドストレージでは、セキュリティ対策は自社担当者ではなく、事業者に大部分を委ねることになります。そのため、前もって事業者のセキュリティ対策について精通しておきましょう。
この点、総務省も2021年9月に「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」を改訂しました(第3版)。利用者の設定ミスや不十分な変更管理に加え、クラウドサービス自体の障害も多数報告されている点が指摘されています。そのため、セキュリティ対策をクラウドサービス事業者に丸投げするのではなく、クラウドサービス利用者も自らの責任範囲において、やるべきことをおこなうことが不可欠、というのが改訂理由だとしています。
参考:「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン (第3版)」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000771515.pdf) を加工して作成
セキュリティ対策について知りたい方はこちら
6. ストレスを感じない操作感か
最適なクラウドストレージサービスを選ぶ6つ目のポイントは、ストレスを感じない操作感かどうかです。
例えば、反応が遅かったり、操作性が普段使っているOSと大きく乖離するようなら、従業員はそのサービスを次第に活用しなくなってしまいます。また、操作を学ぶために特別な研修が必要になれば、普及するまで時間がかかることでしょう。

以上を前提とすると、法人がクラウドストレージを導入する際には有料ストレージを選ぶべきです。なぜなら、無料ストレージの場合、利用している側はセキュリティの脆弱性や容量に関して事業者に責任を問うことはできないからです。
事業規模の小さい企業の場合、ランニングコストを考えると、有料ストレージを導入することに二の足を踏んでしまうかもしれません。その場合、1つの方法は無料のトライアル期間を活用することです。無料期間中にコストパフォーマンスや必要性を検証することをおすすめします。

|
サービス名
|
容量
|
特徴
|
セキュリティ
|
|
MEGA
|
10GBまで無料
|
・転送マネージャーで大容量のファイルをアップロード
|
・エンドツーエンド暗号
・2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護
・ランサムウェア対策
|
|
Googleドライブ
|
15GBまで無料
|
・オンラインでの共同編集
・ファイルの一括管理
|
・ゼロトラスト機能
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
法人向けのクラウドストレージは有料版を選ぶことになると思いますが、部署やチーム内で共同作業を行う際に、あるいは個人で無料版を検討することもあるでしょう。
ここでは、10GB以上であることを前提に、無料版で容量サイズの大きいクラウドストレージを2つ紹介します。
1.『MEGA』10GBまで無料
MEGAはニュージーランドのMega Limitedが提供しているクラウドストレージです。10GBまでは無料で利用できます。
セキュリティ面では「エンドツーエンド暗号」を採用しており、第三者が通信内容を傍受できない対策がなされています。また、2要素認証によりアカウントを不正アクセスから保護し、データを安全に守ります。そのセキュリティの高さはサービスを提供しているMEGAさえもアクセスできないほどです。MEGAではファイルはゼロ知識で暗号化され、鍵を保有しているのはユーザだけだからです。
さらに、ランサムウェア対策も万全です。仮にランサムウェア攻撃を受けた場合、ローカルストレージとMEGA間で自動同期が行われている場合でも、感染する前の時点にファイルを戻せます。
MEGAのユーザが扱うファイルは大容量になりがちですが、デスクトップアプリでは強力な転送マネージャーが利用できます。そのため、短時間に大容量ファイルをアップロードすることが可能です。
有料プランである「ビジネス」は、最小3人のユーザで3TBの基本ストレージを利用でき、毎月の利用プランは2,399円(2024年12月11日時点の日本円での見積価格、実際はユーロで請求)です。ユーザ数や容量は必要に応じて変更可能です。
公式HP:MEGA
2.『Googleドライブ』15GBまで無料
Googleドライブは、Googleが提供しているクラウドストレージです。Googleアカウントを作成することで15GBまで無料で利用できます。1日あたり750GBまでなら大容量のファイルもアップロードが可能です。
Googleドライブの特徴は、ドキュメントの編集機能など、オンラインでの共同作業がしやすい点です。また、さまざまなタイプのファイルを一括して管理し、必要なファイルをすぐに見つけることができます。GoogleのAI機能を利用して、ユーザにとって必要なファイルをリアルタイムに予測し、表示できるのです。
また、Googleドライブはセキュリティにおいて「ゼロトラスト機能」を採用。ゼロトラストとは、テレワークの増加やモバイル端末によるアクセスなどにより、企業の内部と外部を隔てる「境界」があいまいになる中、その概念をすべて捨て去り、情報資産にアクセスしようとするものはすべて信用せずに安全性を検証しようとする考え方のことです。
法人が利用を検討する場合には、有料プランの「Google Workspace」がおすすめです。有料プランは「Business Starter」「Business Standard」「Business Plus」「Enterprise」の4つのプランが準備されており、料金や容量は以下の通りです。Googleドライブの無料版を個人で使っている方も多いと思いますが、Enterpriseを含めて、幅広い企業ニーズにも対応しています。
|
プラン
|
Business Starter
|
Business Standard
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜300人
|
無制限
|
|
容量
(ユーザ1人あたり)
|
30GB
|
2TB
|
5TB
|
5TB
(追加リクエスト
可能)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)※1年契約の場合
|
680円
|
1,360円
|
2,040円
|
要問い合わせ
|
公式HP:Googleドライブ

|
サービス名
|
月額(プラン)
|
機能
|
セキュリティ
|
|
使えるファイル箱
|
スタンダードプランの場合 21,230円~(税込、1年契約の場合)
|
・スマホアプリ
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元
|
・IDパスワード認証
・2要素認証
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
|
|
OneDrive for Business
|
Plan 1の場合 749円〜(税抜、1ユーザあたり)
|
・Microsoft 365と連携
・アクセス権のコントロール
・アクセス有効期限の設定
|
・データを暗号化
・各フォルダを保護し、バックアップ
|
|
Dropbox Business
|
Businessの場合 1,500円〜(1ユーザあたり、年間払いの場合)
|
・Dropbox上でファイルを作成、編集
・デスクトップアプリ
・コンテンツアップデートの通知機能
|
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
|
|
Box
|
Businessの場合 1,881円〜(税込、1ユーザあたり、年一括払い)
|
・Box Signで電子サイン
・仮想ホワイトボードツールBox Canvasにより、コラボレーションを支援
|
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・強力なユーザ認証
・7段階のユーザ権限設定
|
|
Fileforce
|
Small Businessの場合 990円〜(1ユーザあたり)
|
・Officeアプリ上で快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
|
・IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限
・キャッシュデータを自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
|
|
Box over VPN
|
Businessの場合 2,860円(1ユーザあたり)
|
・マルチデバイス対応
・優れたプレビュー機能
・管理者作業を一元管理・自動化
|
・様々な第三者認証を取得
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲などを柔軟に設定可能
|
|
GigaCC ASP
|
STANDARDプランで10IDの場合 12,000円〜
|
・リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・一斉振り分け送信機能
|
・2段階認証機能
・2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
|
|
NotePM
|
プラン8の場合 4,800円〜
|
・高機能エディタと画像編集機能
・全文検索
・チャット連携、API対応
|
・柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
|
|
IMAGE WORKS
|
ミニマムプランの場合 15,000円(税別)+初期費用 15,000円(税別)
|
・サムネイル画像を自動生成、高速表示
・直感的な操作性
・最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モード
|
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全アクセス、操作等を記録
|
※記載の月額はサービスにより契約期間(月払い、年払い)などの区分が異なります
ここからはいよいよ法人向けの有料プランをご紹介します。
以下に示すように、上述した6つのポイントに加え、利用可能なユーザ数についてまとめてみました。
・容量
・料金
・ファイル共有やオンライン共同作業
・特徴的な機能
・具体的なセキュリティ対策
・操作感
・利用可能なユーザ数
3.『使えるファイル箱』
使えるファイル箱は、使えるねっとが提供する「空気みたい」に自然に使える便利で安心なクラウドストレージサービスです。
使えるファイル箱の特徴は、PCにインストールしてエクスプローラーやFinderから使用できるため、操作性が高く、特別な研修も必要なくスムーズに導入できる点です。また、他のアプリケーションからも直接保存できますし、ブラウザ上でOfficeファイルをオンラインで直接編集したり、複数人で同時編集したりもできます。アップロードできるファイルサイズは無制限なので、大容量ファイルの共有も安心です。
特徴的な機能:
・スマホアプリ(Android&iOS)
・右クリックメニューから共有リンクを作成
・ダウンロード履歴の確認が可能
・ファイル復元(最大999日/最大999バージョン)
・汎用的なWebDAVプロトコルに対応しているため、さまざまなアプリが利用可能(アドバンス)
セキュリティ:
・IDパスワード認証
・2要素認証設定
・256ビットのAES暗号化
・SSL暗号化
・国内データセンター(長野)
・GDPRコンプライアンス(EU一般データ保護規則)対応
・サーバ内シークレットキー対応
・履歴ログ管理
・リンクのパスワード保護
・共有リンクの有効期限
・ランサムウェア対策
・ログイン許可IP制限(アドバンス)
・ダウンロード回数制限(アドバンス)
・デバイスデータの遠隔削除(アドバンス)
・特定デバイスからのアクセスブロック可能(アドバンス)
使えるファイル箱は、スタンダードプランでも利用可能なユーザ数が無制限で、容量も1TBから追加可能。拡張性の高さにも注目です。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
利用可能なユーザ数
|
無制限
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
月額料金
(税込)
※1年契約の場合
|
21,230円
|
60,500円
|
公式HP:使えるファイル箱
4.『OneDrive for Business』
OneDriveはMicrosoftが提供しているクラウドストレージサービスです。家庭向け、一般法人向け、大企業向けのサービスがありますが、ここでは一般法人向けを紹介します。
OneDriveの最大の特徴は、Microsoft 365のビジネスソフトとシームレスに連携できる点です。そのため、複数ユーザによる共有や編集作業がスムーズです。
特徴的な機能:
・ファイル共有のアクセス権のコントロール
・共有されるファイルやフォルダのアクセス有効期限を設定可能
・共有ファイルのダウンロードを防止
・Android、iOS、Windows用のOneDriveモバイルアプリでどこからでもアクセス
・ファイルのダウンロードをせずにアクセスできるため、デバイスのストレージスペースを節約
・差分同期を選択できる
・Webでのプレビューで320種類以上のファイルを忠実に再現
・最も関連性の高いファイルを検出するためのインテリジェントな検索と検出のツール
・複数ページのスキャン可能
セキュリティ:
・転送中および保管中のデータを暗号化
・「既知のフォルダの移動」を使用することで「デスクトップ」「ピクチャ」「ドキュメント」の各フォルダを保護、バックアップ
|
プラン
|
OneDrive
for Business
(Plan 1)
|
Microsoft 365 Business Basic
|
Microsoft 365 Business Standard
|
|
利用可能なユーザ数
|
ー
|
〜300人
|
|
容量
|
ユーザ1人あたり1TB
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税抜)
※年間サブスクリプション
の場合
|
749円
|
899円
|
1,874円
|
公式HP:OneDrive
5.『Dropbox Business』
Dropbox Businessは、個人向けの無料サービスも展開しているDropboxの法人向けクラウドストレージサービスです。従来のファイルに加えて、クラウドコンテンツやウェブコンテンツのショートカットもすべて同じ場所に保存できるため、情報を整理して効率的にチームで作業を進めることができます。
特徴的な機能:
・Dropboxで直接クラウドコンテンツやMicrosoft Officeファイルなどを作成、編集可能
・スマートなコンテンツ提案機能を備えたデスクトップアプリ
・フォルダ概要の説明やタスクが更新されたときの通知機能
・作業ファイルの横にある最近のアクティビティ情報で最新情報を把握
・Slack、Zoomなどの使い慣れているツールとリンクすれば、検索したりアプリを切り替えたりする必要なし
・Dropbox Paperでチームメンバー全員で締切とファイルを共有し、リアルタイムで更新しながら作業可能
セキュリティ:
・シングルサインオン(SSO)
・2段階認証設定
・256ビットのAES暗号化とSSL/TLS暗号化
・管理者がチームの共有権限をきめ細かく管理
・デバイスのリンクを解除
・社員が退職した場合やデバイスを紛失した場合、パソコンとモバイルデバイスの両方からデータとローカルコピーを削除
|
プラン
|
Essentials
|
Business
|
Business Plus
|
|
利用可能なユーザ数
|
1人
|
3人〜
|
|
容量
|
3TB
|
9TB〜
(チーム全体)
|
15TB〜
(チーム全体)
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり)
※年間払いの場合
|
2,000円
|
1,500円
|
2,400円
|
公式HP:Dropbox
6.『Box』
Boxはカリフォルニアに本社を置く、2005年にアメリカで設立されたクラウドストレージで、日本でも代理店を経由してサービス展開しています。Boxの特徴は、どのプランも容量無制限であり、ユーザも3人以上であれば、事業規模の拡大に合わせて人数に関係なく利用できる自由度の高さでしょう(「Box Starter」を除く)。
特徴的な機能:
・仮想ホワイトボードツールであるBox Canvasにより、コラボレーションを支援
・Box Signが標準機能として提供され、電子サインにより迅速でコスト効率の高いDXを支援
・Box Relayにより、デジタルアセットの承認や予算管理などの反復業務をシンプルでフレキシブルなワークフローとして自動化
セキュリティ:
・ゼロトラストのセキュリティ制御
・SSO(シングルサインオン)とMFA(多要素認証)をサポートする強力なユーザ認証
・柔軟で詳細な7段階のユーザ権限設定
・すべてのファイルが保管時また転送時にAES256ビット暗号化
|
プラン
|
Business
|
Business
Plus
|
Enterprise
|
Enterprise
Plus
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
3人〜上限なし
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
※年一括払いの場合
|
1,881円
|
3,135円
|
4,620円
|
6,600円
|
公式HP:Box
7.『Fileforce』
Fileforceは国内のさまざまな業界・業種の企業に導入されているクラウドストレージサービスです。端末に関係なく、Webブラウザからログインするだけで手軽に利用でき、スマートフォンやタブレット端末、自宅のPCなどさまざまな環境からアクセス可能です。Active Directoryなどに基づく権限管理に対応しているため、既存のファイルサーバの運用をそのまま引き継ぐことができます。
特徴的な機能:
・Officeアプリ上でもクラウドに保管されたデータを意識することなく快適に編集
・低負荷なプレビュー機能
・複合的な検索機能
・Fileforceに保管されるすべてのファイルは自動で保護される
・社内外問わずファイルやフォルダを共有
・変更履歴はすべて保存
・ファイル更新時には自動的に履歴を保存するバージョン管理を適用、ファイル単位で任意の時点に戻せる
セキュリティ:
・社外ユーザはメールアドレスとパスワードによる認証を基本とし、IPアドレスや位置認証に基づくアクセス制限も可能
・キャッシュしたデータはユーザが意識することなく自動で暗号化
・自動ウィルスチェック
Fileforceの料金プランはユーザ数やストレージ容量に合わせて細かく分かれており、事業規模や会社の成長に合わせて最適なサービスを選択できます。
|
プラン
|
Small Business
|
Unlimited-1
|
Unlimited-3
|
Unlimited-10
|
Unlimited-30
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
10ID
|
無制限
|
|
容量
|
ユーザ
あたり
10GB
|
1TB
|
3TB
|
10TB
|
30TB
|
|
月額料金
(税抜)
※年契約の場合
|
990円
/1ID
|
60,000円
|
108,000円
|
216,000円
|
360,000円
|
公式HP:Fileforce
8.『Box over VPN』
Box over VPNは、BoxをNTTコミュニケーションズが提供する閉域網サービス「Arcstar Universal One」経由で、セキュアなVPN環境下で利用できるサービスです。VPN回線を経由して利用できるため、Boxサービスよりもセキュリティレベルが強化されています。また、ネットワークからBoxまで、NTTコミュニケーションズが24時間365日の一元保守を担当してくれるため、手厚いサポートを受けられます。
特徴的な機能:
・マルチデバイス対応で、PCはもちろんのこと、スマートフォンやタブレットからもBoxを利用可能
・Boxの優れたプレビュー機能により、端末にインストールされていないアプリで作成されたデータも閲覧可能
・NTTコミュニケーションズが提供するBoxではユーザ登録など管理者作業を一元管理・自動化できるオプションを用意
・60日間無料トライアル実施中
セキュリティ:
・さまざまな第三者認証を取得、Boxは米司法省をはじめ、世界各国の政府機関や法人で採用されているため、機密性の高いファイルも安心して保管可能
・7種類のアクセス権限を設定
・ファイルの共有範囲、ダウンロードの可否、パスワードの有無、アクセス有効期限なども柔軟に設定可能
|
プラン
|
Business
|
Business Plus
|
Enterprise
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
20ID〜
|
|
容量
|
無制限
|
|
月額料金
(ユーザ1人あたり、税込)
|
2,860円
|
4,180円
|
5,500円
|
公式HP:Box over VPN
9.『GigaCC ASP』
GigaCCは、日本ワムネットが提供する純国産の企業間ファイル共有・転送サービスです。テレワークをより便利に行える各種機能を備えており、ユーザにITリテラシーを求めない使いやすさも魅力といえるでしょう。
特徴的な機能:
・Microsoft Entra IDと連携し、リアルタイムなID管理
・承認ワークフロー
・受信時にエラーが発生した場合は、スマートダウンロードのレジューム機能により、未受信部分からの再受信が可能
・一斉仕分け送信機能により、複数の宛先へ異なるファイルの自動送信・転送が可能
・「共有ノート」を活用し、アイディアや会議のメモなどを社内外で自由に共有できる
セキュリティ:
・メールによるワンタイムパスワードを利用した2段階認証機能
・スマートフォンの認証アプリを使用した2要素認証機能
・ウィルスチェック機能
・ID/パスワード認証
・アクセス元を制限し、なりすましを防ぐIPアドレス制限
・SSL/TLS暗号化通信
・万が一、権限のないユーザがファイルにアクセスしても中身を見ることができないようにするサーバ内暗号化
・誰がいつ、どこからアクセスし、どんなコンテンツを送信したかを記録する履歴ログ管理
導入には初期費用50,000円がかかります。STANDARD、ADVANCED、PREMIUMの3つのプランがあり、提供機能が異なります。基本月額費用は10IDが12,000円~、1000IDは280,000円~で、ADVANCEDプランはさらに25,000円、PREMIUMプランは42,000円が上乗せされます。
公式HP:GigaCC ASP
10.『NotePM』
NotePMは社内で情報共有をするための社内wikiツールです。いままでバラバラに管理されていたマニュアルやノウハウなどの社内ナレッジを一元管理します。例えば、ファイルサーバの検索が弱く、欲しい情報がすぐに見つからなかったり、マニュアルの作成が人によってバラバラで統一されていなかったり、ナレッジが属人化しているなどの悩みを解決します。
特徴的な機能:
・高機能エディタとテンプレートでバラバラなフォーマットを標準化、マニュアル作成に便利な画像編集機能も用意
・Word、Excel、PowerPoint、PDFなどのファイルの中身も全文検索するので、欲しい情報がすぐにみつかる
・チャット連携、API対応
・マルチデバイス対応
・お知らせ通知
・動画共有
・「人気ページのランキング」など、レポート機能
・変更箇所を自動でハイライト表示し、履歴を記録
・3,000以上のアプリとデータ連携が可能
・1,000以上の絵文字に対応
セキュリティ:
・プロジェクト単位、組織単位など、柔軟なアクセス制限
・アクセスログ・監査ログ
・SSO/SAML認証
・2段階認証
・IPアドレス制限
・閲覧履歴管理
・ログイン連続失敗した場合に自動でアカウントロック
・ログインした端末情報を記録
|
プラン
|
プラン8
|
プラン15
|
プラン25
|
プラン50
|
プラン100
|
|
利用可能な
ユーザ数
|
〜8人
|
〜15人
|
〜25人
|
〜50人
|
〜100人
|
|
容量
(チーム全体)
|
80GB
|
150GB
|
250GB
|
500GB
|
1TB
|
|
月額料金
(税込)
|
4,800円
|
9,000円
|
15,000円
|
30,000円
|
60,000円
|
公式HP:NotePM
11.『IMAGE WORKS』
IMAGE WORKSは富士フイルムイメージングシステムズが提供するクラウドストレージで、画像や動画コンテンツの一元管理・共有に特化したサービスです。検索機能が充実しており、AIを活用したラクラク検索機能も搭載しています。そのため、単にデータを詰め込むだけのオンラインストレージのみでなく、100項目を超えるファイル属性情報(メタ情報)から、業務や用途に合わせ、必要なファイルをすぐに探し出すことが可能です。
特徴的な機能:
・ファイル登録と同時に閲覧用のサムネイル画像を自動生成・高速表示
・直感的な操作性
・1ファイル最大60GBの大容量のファイルに対応
・英語モードも提供
・レジューム機能・整合性確認機能で送受信を支援
・IDを持たないゲストユーザとの送受信も可能
・ダウンロード申請・承認機能により、ファイルダウンロード前に利用者・利用目的等の申請を行う
セキュリティ:
・IPアドレスによるネットワーク認証
・クライアント証明書による端末認証
・全てのユーザのアクセス・操作等の利用状況をログとして記録
・SSO(シングルサインオン)
・プロジェクトの利用期限が定められていれば、あらかじめ決めた期間で自動的にユーザやデータを削除
費用は、初期費用15,000円(税別)+月額費用15,000円(税別)のミニマムプランから、今すぐ始められます。
公式HP:IMAGE WORKS

主に法人向けのクラウドストレージサービスを紹介しました。「あまりに多すぎて選べない」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、そんな方のために「中小企業向け」「個人事業主向け」に分けておすすめなクラウドストレージをご紹介します。
中小企業に特におすすめのクラウドストレージ2選
中小企業に特におすすめなクラウドストレージは次の2つです。
■使えるファイル箱
■Fireforce
これらのクラウドストレージに共通していることは、拡張性の高さです。中小企業の場合、スタート時のユーザ数は少なく、保存すべきデータもあまり多くないですが、短期間のうちに業務拡大の可能性が高いといえます。それとともに、クラウドストレージを使用するユーザや必要な容量も増えていくはずです。
また、中小企業の一番の悩みはコストです。クラウドを導入したいと考える一方、少しでもコストを削減したいという中小企業の経営者は少なくありません。その点、上述したサービスはどれもイニシャルコストはかからず、企業の成長に合わせてプランを選べます。ユーザ数が無制限なため、従業員が増えることを心配する必要もありません。
セキュリティ対策も見落とせないポイントです。最近のサイバー攻撃は大企業だけでなく、サプライチェーンを含めて中小企業をターゲットに絞ったものも増えています。そのため、企業規模が小さくてもセキュリティ対策は万全にしておくべきです。セキュリティ面でも、上述のサービスは総合的に高い基準を満たしているといえるでしょう。
個人事業主に特におすすめのクラウドストレージ3選
個人事業主に特におすすめなクラウドストレージは次の3つです。
■Googleドライブ
■OneDrive
■Dropbox Business
この3つのクラウドストレージに共通しているのは、無料もしくは低コストで使えることです。企業であれば保有するデータが機密情報や顧客情報を含むため、無料のサービスを選ばないはずです。しかし、個人事業主の中には機密性の高い情報を保有する方は多くないため、無料であり、かつ汎用性のあるGoogleドライブは十分考えうる選択といえるでしょう。
また、個人事業主の場合、企業のように多くのメンバーと情報のやりとりをすることはないと思われます。主に取引先やクライアントとファイルを共有することになるでしょう。そのため、ファイル共有や転送の際のセキュリティよりも、機能が充実しており、操作性が高いものを選びたいところです。

ここでは、オンプレミスではなく、クラウドストレージを選ぶメリットについて改めてまとめておきます。クラウドストレージには以下のようなメリットがあります。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
以下、1つずつ説明します。
1. ファイルが一元管理できるため業務効率が上がる
クラウドストレージを使えば、ファイルやデータを一元管理できます。そのため、ファイルを探す手間を省き、データを転送・共有する工数を減らせて、業務効率が上がります。
オンプレミスでもデータの一元管理は可能ですが、クラウドストレージはインターネット経由でアクセスできるため、出張先やテレワーカーとも情報の共有が容易です。また、オフィスと工場など拠点が複数に分かれている場合でもクラウドストレージなら簡単にデータの一元管理ができます。
2. ファイル共有や共同編集が簡単にできる
クラウドストレージを使えば、ファイル共有や共同編集も簡単です。どのサービスを選ぶかにもよりますが、容量の大きなデータも相手を選ばずに送ることができます。アップロードして、リンクを生成、送付するだけで完了です。
また、OneDriveやGoogleドライブだけでなく、多くのクラウドストレージサービスはさまざまなアプリケーションと連携しているため、オンラインで共同作業や編集が可能です。
3. いつでもどこからでもファイルにアクセスできる
クラウドストレージサービスを使うことで、オフィスだけでなくどこの場所からでもファイルにアクセスできます。また、アクセスする時間帯も選びません。
多くの企業でテレワークやワーケーションをはじめとした「時間や場所を選ばない働き方」が導入されていますが、そうした新しい働き方とも親和性があるのがクラウドストレージなのです。
4. ファイルサーバの運営や管理が不要になる
クラウドストレージを使えば、社内にファイルサーバを設置する必要がないため、運用管理業務は不要です。
オンプレミスの場合、サーバにかかる負担を監視したり、災害・停電などで起きるトラブルに対処するために運用管理者が必要になります。外注の場合は、サーバ構築費の10~15%が保守運用費用として月額でかかるといわれています。
5. 災害がおきた際もデータを消失するリスクが低い
クラウドストレージの場合、データは社内のサーバではなく、災害のリスクが低いデータセンターに保存することになります。
災害大国である日本はどこであっても地震や台風、水害のリスクがあります。システムが破壊され、データが失われれば、企業は業務を停止せざるを得ず、膨大な損害を被ることになります。企業のBCP(事業継続計画)対策の一環としても、クラウドストレージ導入は有効です。
BCP対策について知りたい方はこちら

さまざまな要素を考慮し、最終的にどのクラウドストレージを選ぶにしても、活用・導入にあたって注意したい以下のポイントがあります。
1. インターネット環境の整備
2. セキュリティ対策
3. 運用体制の整備
4. 課金要素
1つずつ説明します。
インターネット環境の整備
サービス自体がどれほど優れていても、インターネット環境が整備されていないと、持っているポテンシャルを十分引き出すことはできません。
クラウドストレージはインターネットを経由して利用するサービスのため、回線速度によってパフォーマンスが大きく左右されます。ネットワークの混雑によって、クラウドストレージの機能が低下しないように大容量の回線を準備しましょう。
セキュリティ対策
クラウドストレージを活用する際にはセキュリティ対策に注意を払うべきことは何度も強調しました。クラウドストレージを導入すれば、確かに自社での保守点検は基本的に不要になりますが、セキュリティ対策をクラウドストレージサービス提供事業者に丸投げしてしまって良いわけではありません。
いくらクラウドストレージ側にしっかりとしたセキュリティ対策が施されていても、利用者側でそれを使いこなせていなければ意味がありません。例えば、多くのクラウドストレージはユーザのアクセス権限を細かく設定できるようになっていますが、この設定のミスがセキュリティインシデントにつながるケースも増えています。
また、利用者側の端末のOSやアプリの脆弱性を放置すれば、サイバー攻撃者の格好のターゲットになります。情報漏えいなどを防ぐためには、常に最新のOSやアプリケーションにアップデートしておくことが必要です。さらに、クラウドストレージも万能でないことを認め、災害やサイバー攻撃によるデータ喪失に備えて、バックアップ先を複数用意するなどの対策も求められます。
脆弱性について知りたい方はこちら
サイバー攻撃について知りたい方はこちら
運用体制の整備
クラウドストレージを導入する際にも運用体制を整備することを忘れないようにしましょう。言い換えると、クラウドの運用を「仕組み化」「システム化」するということです。
「誰が」「何を」「いつ」するのかを決めずに責任の所在をあいまいにし、何となく人的な対応でやりくりしていると、効率化、コスト削減の面でも無駄が生まれます。それだけでなく、やるべき工程に「抜け」が生じて、それがセキュリティインシデントにつながることがあります。経営者主導でクラウドストレージの運用体制を盤石にしましょう。
参考:株式会社アールワークス 「システム運用方針のまとめ方と、運用体制構築に必要なこと」
課金要素
クラウドストレージ導入にあたっては、課金体系をしっかりと把握しておく必要があります。
クラウドストレージサービスの中には、どの程度料金が発生するか分かりづらいものもあります。また、不要になったサービスを利用していないのに停止せずに放置したり、実装したアプリケーションに不備があり、無駄な処理が発生したりすることもあります。
毎月の請求内容にはきちんと目を通し、不明な点はサービス提供事業者に確認するなどして、「なんとなく」料金を支払い続けることがないようにしましょう。そうでないと、イニシャルコストを抑えられるクラウドストレージの強みが失われてしまいます。

ここでは、クラウドストレージを比較する際によくある質問を3つ取り上げます。
Q1:クラウドストレージは社外の人でも使えますか?
クラウドストレージが利用できるか否かは、そのサービスのIDを保有しているかどうかです。そのため、例え社外の人であっても、IDがあれば利用可能です。もっとも管理者によりどの程度までアクセスできるか、権限が制限されることはあります。
Q2:容量無制限のサービスを選べば安心ですか?
「容量無制限」という響きにはたしかに魅力があります。しかし、前述したように容量無制限のサービスを選ぶべきかは企業の業務規模や従業員数によります。現状で使う必要がないのに、やみくもに容量無制限を選ぶと逆にコスト面で損をする可能性もあります。
Q3:クラウドストレージにはデメリットはないのですか?
もちろんあります。
クラウドストレージがあらゆる面でオンプレミスに優れているわけではありません。例えば、クラウドストレージはサービスが定型化、パッケージ化されているため、オンプレミスのように自由なカスタイマイズはできません。
大切なのは、自社がクラウドストレージを導入する目的を見極めることです。
.png)
ここでは、中小企業におすすめする「使えるファイル箱」についてさらに詳しく説明します。
使えるファイル箱の3つの特長
使えるファイル箱にはさまざまな魅力がありますが、ここでは3つの特長を取り上げます。
1. ユーザ数無制限
100人でも、1,000人でも料金は一律です。フォルダのアクセス制限が設定できるため、ユーザIDの一部を外部に渡して、大容量データのやりとりもできます。ちなみに、100人で使えば月額1人210円程度、300人では月額1人70円程度で済みます。
2. 普段のパソコンと同じように操作できる
使えるファイル箱は特別なインターフェースを必要とせずに、Windowsならエクスプローラー、MacならFinderで共有ファイルを操作できます。そのため、特別な研修は必要なく、普段のパソコンと同じような感覚でファイル共有が可能です。
3. 高機能なのに低価格、無料トライアルもある
使えるファイル箱はクラウドストレージサービスを利用したくてもコスト面で限界がある中小企業に使っていただきたいと思っています。そのため、容量課金制の低価格でサービスを提供しています。
また、スタンダードプラン、アドバンスプランいずれも30日間の無料トライアルがあるため、じっくり使い勝手を試してから決めることができます。
中小企業に最適な機能と料金形態
中小企業にとってコスパは重要な要素ですが、見逃すべきではないポイントはセキュリティです。使えるファイル箱なら、2要素認証やAES256ビット暗号化、ISO認証取得の長野県のデータセンターなど、貴重な情報資産を守るための対策もばっちりです。
さらに、使えるファイル箱は電子帳簿保存法上の区分のうち、電子取引にも対応しているため、書類の保管場所も節約でき、業務の効率化を図れます。
中小企業に最適な機能を備えた使えるファイル箱の料金体系は以下の通りです。
|
プラン
|
容量
|
1ヵ月契約
|
1年契約
|
|
スタンダード
|
1TB
|
25,080円(税込)/月
|
21,230(税込)/月
|
|
アドバンス
|
3TB
|
75,680円(税込)/月
|
60,500(税込)/月
|
おすすめは1年契約のプランで、容量1TBの場合は月単価21,230円(税込)。より高度な機能が搭載されたアドバンスプランではセキュリティを強化し、汎用性が増すWebDAV連携が可能です。容量3TBのアドバンスプランは60,500円(税込)!
最短で即日ご利用可能!
使えるファイル箱を試してみたいと思われたら、是非お気軽にご連絡ください。
即日または翌営業日に対応させていただき、お見積りいたします。ご希望に合わせてオンラインでのご案内や無料トライアル、勉強会を実施させていただき、本契約となります。最短で即日のご利用開始も可能です。
.jpg)
(1)無料クラウドストレージの容量は?
A:無料クラウドストレージの代表はGoogleドライブですが、ストレージ容量は15GBです。ほかのサービスは2~10GBのものが多いようです。
(2)ストレージ容量に余裕がなくなるとどうなるの?
A:ストレージはデータの保管庫のことで、クラウドに限らず、パソコンやスマホなどの端末でも容量不足の問題は付きものです。
クラウドストレージで容量が足りなくなると、バックアップがとれなくなったり、デバイス間のデータの同期ができなくなったりするなどの障害が生まれる可能性があります。個人で使用する場合であっても、無料のクラウドストレージでは容量不足の問題にぶつかると、有料版を購入することになります。
(3)自社サーバのデメリットは?
A:自社サーバを利用するデメリットには以下の点があります。
1. 運用管理の手間
2. 災害対策が容易でない
3. リモートワークに対応するためにはVPN環境を整えなければならない
4. 容量の拡張にコストがかかる
これらのデメリットもクラウドストレージなら解決可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
総務省が2024年6月に発表した「令和5年通信利用動向調査」によると、クラウドサービスを「全社的に利用している」「一部の事業所又は部門で利用している」と回答した企業の割合は合わせて77.7%であり、2022年の72.2%、2021年の70.4%から上昇し続けています。
さらに、同調査によると、「非常に効果があった」と回答した企業は33.5%、「ある程度効果があった」と回答した企業は54.9%で、合計88.4%がクラウドサービス利用の効果を実感している点は注目に値するでしょう。
ここでは、ますます導入が拡大しているクラウドサービスの基本や、使えるねっとの安心・お得なクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」について解説します。これからクラウドストレージの導入を検討している方、現在使用しているクラウドストレージの使い勝手に不満を感じている方は是非お役立てください。
目次
クラウドストレージとは?
クラウドストレージの容量無制限とユーザ数無制限のメリット
「使えるファイル箱」には本当に使える機能がたくさん
「使えるファイル箱」ならではの特徴
FAQ

クラウドストレージとは、「インターネットを経由してアクセスできるデータセンターにデータを保存するサービス」のことです。
従来、多くの企業でファイルはローカル環境(パソコンや会社のサーバなど)に保存していました。それに対してクラウドストレージの場合、ファイルを「クラウド」、つまりインターネットを経由してデータセンターに保存するため、以下のようなメリットがあります。
・いつでもどこでも、好きな場所・端末からファイルにアクセスでき、テレワークにもぴったり
・社内・部署内や、社外のコラボレーターと簡単にファイルを共有できる
・パソコンが壊れたり、会社のローカル環境が被災したりしても、データはクラウド内にあるから無事
.jpg)
クラウドストレージサービスにはたくさんの種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまうはずです。それぞれのサービスに特徴があり、強みがあれば、弱みもあります。
大切なのは、自社の業務スタイルや従業員規模に合ったサービスを選ぶことですが、迷ってなかなか決めきれない方におすすめなのは「容量無制限」、あるいは「ユーザ数無制限」のクラウドストレージサービスです。それぞれのメリットは以下のとおりです。
容量無制限のメリット
容量無制限のメリットは、サイズの大きなファイルや大量のデータも制限を気にせずに保存できることです。
近年中小企業も含め、多くの企業がDXに注力しています。デジタル技術を活用して新たな価値を創出しようとすると、企業が扱うデータの量は必然的に膨大になります。
また、毎日の業務で頻繁に利用することはないものの、法令により一定期間保管が義務付けられているデータもあります。こうしたアクセス頻度は高くないものの、削除するわけにはいかないデータを「コールドデータ」と呼びますが、容量無制限のクラウドストレージであれば心配することなく法的要請にも応えることができます。
容量に制限があると、企業が扱うデータが増加して足りなくなった場合、さらにコストを支払ってストレージを追加しなければならなくなります。そうなると、データ管理のためのコストが膨らみ、企業の経営を圧迫することにもなりかねません。その点、容量無制限のクラウドストレージサービスであれば、導入の段階でかけるコストを予測でき、管理がしやすいといえるでしょう。
ユーザ数無制限のメリット
ユーザ数無制限のメリットは、従業員の増減に柔軟に対応できることです。
例えば、わずかな従業員で企業を立ち上げた場合、クラウドストレージを利用するユーザ数はそれほど多くないでしょう。しかし、企業の成長とともに従業員は増えていきます。また、取引先などの社外と情報共有したいケースも増えてくるかもしれません。ユーザ数無制限であれば、ユーザの増加に伴う追加コストは必要なく、安心です。
限られているユーザ数で「ユーザ数無制限」のクラウドストレージを使うのは「もったいない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、企業の状況は刻一刻と変化し、その中でデータをどのように共有し、活用するかは重要な課題です。コストを気にすることなく、毎月同額で無制限のユーザにデータを共有できることは大きな安心感につながりますし、予算を組みやすい点でも大きなメリットがあるはずです。
クラウドストレージのタイプ比較とおすすめツールはこちら
.png)
使えるねっとの「使えるファイル箱」には、本当に「使える」機能が満載。以下では、そのうちのいくつかについて解説しましょう。
ユーザ数無制限
使えるファイル箱はユーザ数無制限のため、社員が増えてもユーザ課金や権限発行に悩むことはありません。これから成長が見込まれる中小企業としては、将来の発展を見据えながらも、予算を立てやすいといえるでしょう。逆に不要になったアカウントは、該当ユーザを削除するだけです。
他方、ストレージの容量はスタンダードプランで1TB、アドバンスプランで3TBです。もちろん、データ容量も追加は可能です。
シンプルで使いやすい抜群の操作性
使えるファイル箱は普段のパソコンと同じくシンプルな操作のため、クラウドストレージの導入に合わせて研修を実施して操作法を学ぶ必要はありません。Windowsならエクスプローラー、MacならFinderでデータのダウンロード、アップロードが可能です。
セキュアにファイルやバージョンを自由自在に復元
重要なファイルを保存し、共有する上で不可欠なのは、セキュリティです。使えるファイル箱なら、外部のユーザにファイルを送りたいときはWebリンクを使用して手軽にシェアできますが、パスワードと有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心です。ユーザごとにフォルダのアクセス権限を設定することも可能です。
ファイル箱についてよくある質問はこちら
.png)
使えるファイル箱には、上記で挙げた「使える」機能以外にも、以下のような特徴があります。
抜群のセキュリティで安心
SSL通信に加え、シークレットキーによる2重暗号化を実施。また、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムであるAES256ビット暗号化を採用しています。これは、2の256乗のパターンの鍵を持つことを意味しており、総当たり攻撃でパスワードを解析して不正アクセスを試みる場合、コンピュータによる解析を行ったとしても解読には数百兆年かかるといわれています。
充実のカスタマーサポート
どれだけシンプルな操作性だったとしても、はじめての方であれば使い方に悩むことはありますし、サイバー攻撃など思いがけないトラブルが発生することも考えられます。そのため、使えるねっとでは、専属スタッフによる充実のカスタマーサポートを設けています。電話はもちろん、メールやチャットでのお問い合わせも受け付けていますので、困ったときも安心です。
また、「使えるシャトル便」で弊社が郵送したHDDにお客様のデータをコピーして宅配便でご返送いただければ、弊社側でお客様の「使えるファイル箱」にアップロードを行います。(1回/1TB 55,000円、追加1TB 11,000円)
圧倒的なコストパフォーマンス
使えるファイル箱にはいずれもユーザ無制限のスタンダードプランとアドバンスプランをご準備。上述したように2つのプランでは容量が異なりますが、それ以外にもアドバンスプランでは、IP制限やダウンロード回数制限など、セキュリティ対策がさらに充実しています。
年間契約の場合、スタンダードプランは21,230円(月単価、税込)、アドバンスプランは60,500円(月単価、税込)です。スタンダードプランを従業員100人で使用された場合、月額1人あたり約210円、300人では月額1人約70円で済みます。
30日間の無料トライアルも実施しているため、気になる方は、「使えるファイル箱」でクラウドストレージの便利さを体感してみませんか?
使えるファイル箱の詳細はこちら
.jpg)
法人向けのクラウドストレージの市場規模は?
2021年度のクラウドストレージの市場規模は約3.5兆円でした。今後、クラウドストレージの市場規模は2025年~2026年には現在の2倍以上にまで拡大すると予測されています。
クラウドストレージのユーザ数は?
ICT総研によると、2021年3月末に5,176万人だった国内の個人向けクラウドストレージサービスの利用者は2022年3月末には5,345万人になりました。また、2021年3月末時点の有料サービスの利用者数は1,535万人でした。
クラウドストレージの国内シェアは?
ICT総研によると、2022年4月時点で個人利用のクラウドストレージサービスの中で最も利用者が多かったのはGoogleドライブで、ついでAppleのiCloud Drive、3位はMicrosoftのOneDriveでした。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
その便利さや手軽さから、企業の間でもクラウドサービスを導入する事例が増えています。データを安全かつ手軽にやり取りするために欠かせないファイル共有サービスに関しても、近年ではクラウドソリューションを選択するケースが多くなってきました。
ビジネスに様々な恩恵をもたらしてくれるクラウドコンピューティングサービスですが、やはり気になってしまうのがセキュリティ。クラウドを利用するメリットは理解しつつも、「セキュリティや使い勝手が心配で導入に踏み切れない」という方もいるのではないでしょうか。
クラウド導入にあたっては、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。今回は、クラウドサービスのメリットとデメリットについて解説した上で、クラウドベースのストレージサービスを選ぶときに必ずチェックしておきたい、セキュリティ上の3つのポイントをまとめてみました。
法人向けクラウドストレージのおすすめを知りたい方はこちら
目次
クラウドサービスのメリットとは?
クラウドサービスのデメリットとは?
データセンターの安全性
サーバの管理体制
データ転送の暗号化
使えるファイル箱で簡単・安全にクラウドを導入
FAQ

クラウドソリューションには多くのメリットがありますが、ここでは代表的な3つのメリットについて取り上げます。
いつでも、どこからでもアクセスできる
従来のオンプレミス型のファイルサーバは社内LANによって構築されており、社外からのアクセスは想定されていません。それに対してクラウドサービスであれば、インターネット経由でデータを共有します。そのため、リモートワークで自宅で勤務していても情報共有や共同作業が簡単に行えます。
また、社外からのアクセスが可能なため、社員以外の取引先とも大容量のファイルの共有が可能です。多くのクラウドサービスではファイルごと、フォルダごとに権限設定ができるため、情報セキュリティの観点からも安心です。
コストを抑えられる
一般的にファイルサーバ構築のためにはハードウェアとしてのサーバ購入に加えて、サーバを稼働させるためのルーターやUPS(災害時などのためのバックアップ用電源)、サーバ設定用のPCなどハードウェア環境、さらにはソフトウェアのインストールや設定が必要です。サーバの購入費用だけでも最低でも20~30万円かかりますし、企業規模が大きくなれば100万円を超えます。それに加えて、他のハードウェアを購入し、ソフトウェアの設定をしなければなりませんから、初期コストだけでも中小企業にはかなりの負担になります。
それに対して、クラウドサービスであればハードウェアを購入する必要はなく、従業員数に合わせてプランを選択し、月額の利用料金を支払えば低コストで使い始めることができます。
BCP対策になる
BCP対策とは、「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもので、「事業継続計画」と訳されます。つまり、企業が災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面したときに被害を最小限に押さえ、事業を継続できるようにするために行う対策や計画のことです。
企業にとって情報の価値はますます高まり、中には顧客情報などの機密情報も含まれています。そのため、情報漏えいや消失を防ぐために企業がいかなる対策をとるかは、投資家などのステークホルダーにとっても大きな関心事の1つといえるでしょう。
ファイルサーバはオフィスと同じ場所に設置するため、オフィスが被害を受ければデータも失われてしまいます。それに対して、クラウドストレージのデータセンターは災害や火災、停電にも耐えうる堅牢な設計であり、安全にデータを保管できます。その点でクラウドストレージはBCP対策の一環としても優れているといえるでしょう。
BCP対策について詳しく知りたい方はこちら
クラウド導入でDX化推進を検討している方はこちら

導入に多くのメリットがあるクラウドサービスですが、以下のようなデメリット、注意点もあります。ここでは2つ取り上げます。
カスタマイズに限界がある
クラウドサービスのデメリットの1つは、オンプレミス型のファイルサーバに比べてカスタマイズに限界がある点です。
上述したようにローカルファイルサーバの場合、ハードウェアの購入からソフトウェアのインストール、システムの構築まで自社のニーズに合わせて自由に行えます。それに対して、クラウドサービスはストレージ容量やユーザ数、セキュリティレベルに基づいてプランを選択できるものの、細かな設定には限界があり、ファイルサーバには及びません。
セキュリティ対策が必要
クラウドサービスの提供事業者はサイバー攻撃に対処するための自動アップデートなど、24時間体制でセキュリティ対策を行っています。といっても、セキュリティ対策はすべて任せて、自社では何もしなくて良いというわけではありません。
特に人為的なミスによってセキュリティリスクが発生しないように、IDやパスワードの管理、アクセス権限の付与などに関しては社内で明確なルールをつくり、周知徹底することが必要です。
また、クラウドサービスを選ぶ際には以下の3つのポイントに注意して導入することをおすすめします。
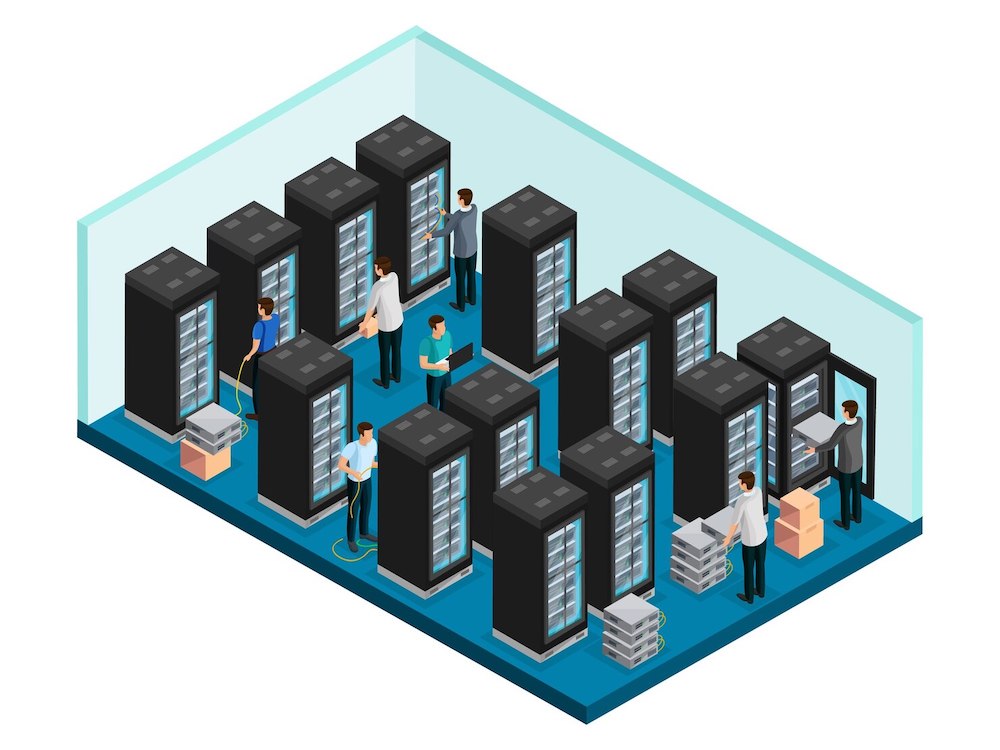
クラウドサービスを利用すると、データはサービス提供事業者のデータセンターに保存されることになります。セキュリティのことを考えると、データセンターの安全性、セキュリティ対策を確認することがとても大事なポイントになってきます。
具体的には、日本データセンター協会が制定した「データセンター ファシリティスタンダード」を参照するのも1つの手です。これは、グローバルな実情に合わせて作成された基準を、地震が多いなど日本の実情に合わせて改良したものです。
ティア1~4ごとに基準が設けられているので、データセンターのサービスレベルを測る1つの基準になります。
データセンターの立地については国内と国外のどちらが良いのか迷われると思いますが、二者択一というより、それぞれに一長一短あります。使えるねっとの国内データセンターは長野県にあり、その位置や地勢などから自然災害の影響を受けにくいエリアだといわれています。また前述のデータセンター ファシリティスタンダードでもティア3レベルの基準があります。
ティア3
・ 地震や火災など災害に対して、一般建物より高いレベルでの安全性が確保されている。
・ 機器のメンテナンスなど一部設備の一時停止時においても、コンピューティングサービスを継続して提供できる冗長構成の設備がある。
・ 建物およびサーバ室へのアクセス管理が実施されている。
・ 想定するエンドユーザの稼働信頼性:99.98%以上
ロケーションによりデータ転送速度も相違
また、データセンターのロケーションはデータの転送速度にも影響を与えます。クラウドであれば、自社のデータを世界中どこにいても同じように取り出し、処理できると思われるかもしれません。各サービスの特性により仕様は多少異なりますが、データは実際の物理的なロケーションに保存されているため、「データのロケーション」が国内か国外か、あるいはどのくらい離れているのかが重要なポイントとなる場合もあります。

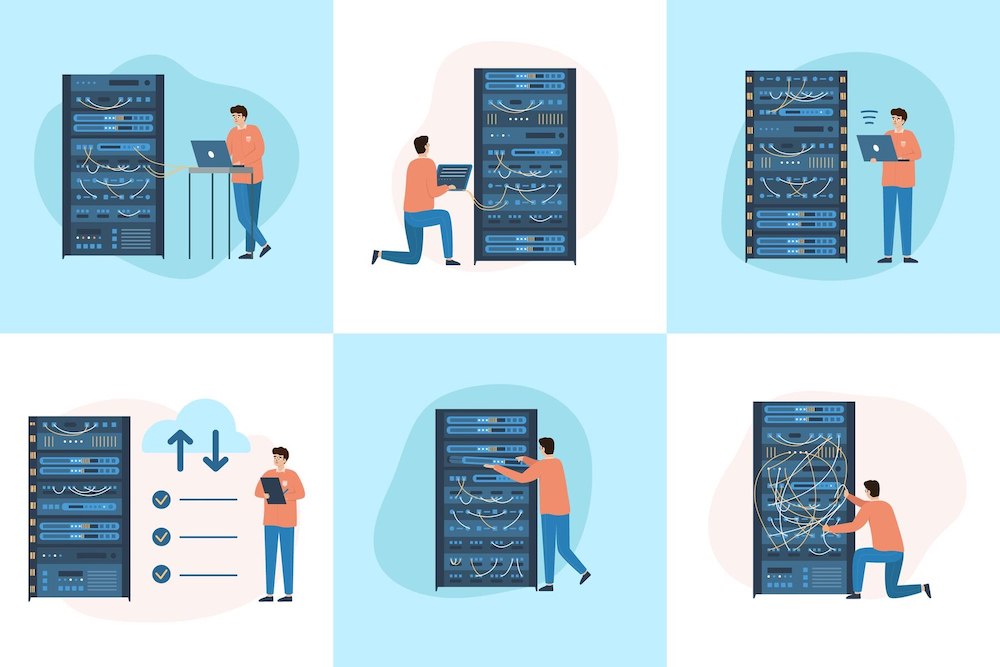
ファイルを保管するためのサーバをどのように管理しているのかは、事業者によってそれぞれ異なります。
外部への情報漏えいリスクを避けるためには、情報セキュリティ対策が万全で、ネットワークの冗長化ができているサービスを選ぶことが最善だと言えます。
使えるねっとは24時間体制のサポート&セキュリティ対策が万全
使えるねっとでは10時から17時まで、オペレーターへの電話やチャットサポートにてサービスに関する疑問や質問を受け付けています。もちろん、メールでのお問い合わせもいつでも可能。加えて、サーバトラブルやハード障害などによるサーバダウン時の緊急連絡は24時間受け付けています。
また、使えるねっとはISO27001(ISMS)認定の万全なセキュリティ対策に加え、ネットワーク冗長、自家発電設備など20年以上のホスティングサービス提供の経験を生かし、最高基準のセキュリティポリシーで安定運用を実現しています。

クラウドサービスのセキュリティにおいて必須ともいえるのが「暗号化」です。データをそのままの生の状態で転送するのではなく、暗号化と呼ばれる技術によって保護することにより、情報の機密性を保つことができるのです。
データを保管・転送するときにはそれぞれ暗号化技術が必要になりますので、利用するサービスがきちんと対応しているかどうか忘れずに確認しておきましょう!
AES-256ビット暗号化(高度な暗号化)とは?
一口に「暗号化」といってもさまざまな方法があります。その1つがAESです。AESとは「Advanced Encryption Standard(先進的暗号化標準)」の略で、米国国立標準技術研究所が公募の結果、2001年に承認した技術で、現在に至るまで通信データの暗号化アルゴリズムとして標準的に使用されています。
これは「共通鍵暗号方式」と呼ばれ、同じ暗号鍵を使用して暗号化と復号(暗号化されたものを元に戻す)を行う方式を採用しています。この場合、暗号化と復号に使う暗号鍵のデータが長ければ長いほど安全性が高くなります。この暗号鍵の長さを「鍵長」といい、一般的に「bit(ビット)」で表されます。
AES登場前はDESと呼ばれる暗号化方式が標準でしたが、その鍵長は56bitと短く総当たり攻撃に弱いのが弱点でした。それに対してAESは128、192、256bitの中から鍵長を選べます。つまりAES自体、2024年時点でもっとも安全性の高い暗号化技術ですが、その中でも鍵長が一番長いAES-256ビット暗号化は現時点で最強の暗号方式ということなのです。AES-256ビットの解読には、最高の計算速度を誇るコンピュータでも数百兆年かかるといわれるほどです。
使えるファイル箱ならセキュリティも万全で安心
使えるねっとが提供している法人向けファイル共有サービス「使えるファイル箱」はAES-256ビット暗号化を暗号化アルゴリズムとして採用しています。それだけでなく、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も行っており、万全のセキュリティ対策で安心です。

.png)
クラウドの導入では、安心・信頼できるサービスを選択することが一番大切なことかもしれません。データ管理体制がしっかりしているサービスを利用すれば、セキュリティを心配することなくクラウドの利便性を最大限活用できます。
「使えるファイル箱」は、セキュリティを第一に考えた厳重な体制でデータを管理しています。サーバは自社国内データセンターで熟練の専属スタッフが運用し、お客様のデータを保管から転送まで最新の暗号化技術できっちり保護。セキュリティ面にとことんこだわったサービスですが、ユーザ数無制限、大容量1TBで月単価21,230円(税込、1年契約)から導入していただけます。コストパフォーマンスの高さも大きな魅力といえるでしょう。
30日間の無料トライアルも実施しておりますので、クラウドストレージサービスの導入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
クラウドストレージについて知りたい方はこちら
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
使えるファイル箱についてさらに知りたい方はこちら
(1)クラウドが普及しない理由は何ですか?
クラウド導入が進む一方、さまざまな理由でクラウドサービスの利用を躊躇する企業も少なくありません。その理由として考えられるのは、業務で電子的にデータを管理したり、共有したりする必要性を感じないという点に加え、セキュリティリスクの懸念を挙げる企業もあります。
(2)クラウド導入とは何ですか?
クラウド導入とは、企業の基盤システムやデータ管理をクラウド上で行うように整備することです。従来のオンプレミス型のファイルサーバからクラウド導入をするのは敷居が高いと感じる場合、クラウドへの完全移行ではなく、オンプレミスとの併用を選択する企業もあります。
(3)クラウド導入にかかる期間はどのくらいですか?
ローカルでサーバシステムを構築する場合、自社環境に合わせてカスタマイズすることは可能であるものの、導入には長い時間がかかります。それに対して、クラウド導入にかかる時間は圧倒的に短くて済みます。例えば、使えるファイル箱であれば、最短で即日からのご利用も可能です。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
中小企業にとって業務効率化のためのIT投資は不可避です。それに加えて、さらに近年はDX化が叫ばれ、IT活用により新たな価値の創出や競合優位性の獲得が求められています。
そのためには、これまでアナログで行っていた業務をやみくもにデジタル化すれば良いというわけではなく、明確な企業戦略に基づいてシステム投資を行う必要があります。
ここでは、中小企業にとってのシステム投資のポイントや、その一環としてのクラウド導入のメリットやハードル、おすすめのクラウドサービスについて解説します。
法人向けクラウドストレージの比較を見たい方はこちら
法人向けクラウドバックアップの比較を見たい方はこちら
目次
中小企業にとってのシステム投資
クラウドサービスの導入ハードル
すぐに導入できる問題解決型クラウドサービス
使えるねっと製品ならサポートも充実で安心
FAQ
.jpg)
一般的に投資を行う際は、費用対効果をベースにして詳しい金額を算出することからスタートします。中小企業にとってのシステム投資の考え方も基本的には同じです。しかし、注意点が2点あります。
1点目は、システム投資の費用対効果を算出する場合、金額ベースでは算出が難しい「効果」もあるということです。例えば、システム導入によって社内コミュニケーションが促進されることで生み出される金額的価値はすぐに可視化することは困難です。
2点目に、中小企業にとってシステム投資にかけられる金額は限られているということです。大企業であれば、一からSIer(システムインテグレーター)に委託して自社の業務を分析してもらい、システム設計・開発から運用・保守点検まで行ってもらうことが可能かもしれません。しかし、中小企業にとってそこまでの投資は難しく、限られた予算の中でどのように効率的にシステムを導入するかが重要になります。
以上の2点を考えると、中小企業の経営者や担当者は、経営方針に沿ってシステム投資により何を成し遂げたいのか、骨太のコンセプトを明確にし、世の中のトレンドに振り回されないようにすることが大切です。
.jpg)
事業内容や規模に関わりなく、システムの導入を検討する中小企業に共通しているのは「いかにしてデータを効率よく管理し、共有するのか」という課題です。
多くの中小企業は複数の拠点を持っていることに加えて、コロナ禍をきっかけとしてリモートワークを導入しています。また、すべての業界でビジネスが加速しており、スピーディな情報共有が求められます。加えて、共有するファイルもテキストに加えて画像や映像ファイルが増えており、データ容量が増え続けています。しかも、個人情報や機密情報も含まれるため、サイバー攻撃などのリスクも考慮しながら、安全に共有する手段を確保しなければなりません。そうしたさまざまなニーズを満たすためのシステム投資の一つがクラウドサービスです。
情報共有のためのプラットフォームは、オンプレミス型のシステム構築に比べて技術面、コスト面いずれからもハードルが低いといえます。なぜなら、導入にあたってSIerにシステム設計・開発を委託したり、導入後も運用・保守にリソースを割いたりする必要がないからです。
サービス提供事業者が導入から運用まですべて担ってくれることを考えると、クラウドサービスは費用対効果の高いシステム投資と言えるでしょう。
中小企業のセキュリティ対策について知りたい方はこちら
.jpg)
現在、各社が提供しているクラウドサービスは数えきれないくらいあり、自社のニーズにフィットしたサービスを選択するのは至難の業です。選ぶ際のポイントもたくさんありますが、「予算が限られている中小企業が導入して費用対効果を最大化できる」システム投資という観点で考えると、「導入のしやすさ」「使いやすさ」「費用」の3点に注目して選ぶと良いでしょう。
この点から、使えるねっと社が提供するサービスをおすすめします。以下では主力サービスであるクラウドストレージ「使えるファイル箱」の概要と、おすすめの理由を説明します。
導入のしやすさ
使えるねっとのクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」は、最短で即日導入が可能です。もちろん、導入前にじっくり使ってみたいというニーズにも対応しており、30日間の無料トライアルをお試しいただけます。また、導入前に実際の仕様や状況にあったプランなどをオンラインでご説明したり、勉強会を実施したりすることもできます。
導入企業数が累計12,000社以上という数字からも、使えるファイル箱の導入のしやすさは証明済みです。
使いやすさ
使えるファイル箱はユーザ数無制限のファイルストレージサービスのため、社員が増えてもユーザ課金や権限発行に悩むことなく、追加費用も必要ありません。また、企業の成長に応じてストレージを追加することも可能です。
往々にして、使いやすさを追求していけばセキュリティが疎かになることもありますが、使えるファイル箱は使いやすさと高いセキュリティを両立しています。クラウドストレージ内のフォルダにはアクセス制限の設定もできるため、安心して外部とのデータのやりとりが可能です。また、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムを採用していますし、ウェブ管理画面をSSL化し、ウェブサーバとブラウザ間のデータ通信も暗号化しています。
費用
以上のような導入のしやすさ、使いやすさを兼ね備えている使えるファイル箱ですが、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。1年契約の場合、スタンダードプランでは容量1TBで月単価21,230円(税込)、さらにセキュリティを強化したアドバンスプランでは容量3TBまで使えて月単価60,500円(税込)です。
.png)
システム投資を考える上で重要な要素の一つは、導入後のシステムの安定性です。高い費用を払って導入しても、たびたびトラブルが発生し、解決に終始するようであれば、費用対効果は下がります。
クラウドサービスにおいても安定性は重要ですし、仮にトラブルが発生したとしてもすぐにサポートを受けられる体制が整っていれば安心です。
この点、使えるねっとのクラウド製品はサポートも充実しています。使えるねっとの専門スタッフは電話、サポートメール、チャットいずれの対応も可能です。また、詳細なFAQも用意され、ハード障害含むサーバトラブルなどでサービスを利用できない場合の緊急連絡を24時間受け付けております。
また、データセンターが国内の長野県にあるのも安心感につながります。オンプレミスサーバだと、万が一自然災害が起きた場合にオフィスが被害を受けるだけでなく、データも一緒に消失してしまい、復旧作業に多大な時間を要することになります。
導入事例
使えるファイル箱を導入した企業の事例を一つご紹介しましょう。
電子部品および精密板金の二部門を軸に、高い技術力と独自の一貫生産体制で高品質な部品・製品を送り出している松代工業株式会社は、従来ファイルサーバを自社運用し、業務ファイルを自前で管理してきました。しかし、定期的なメンテナンスや日常的に発生する煩雑な管理が負担になり、ファイルサーバのクラウド化を模索し始めます。
最終的に同社が使えるねっとを選んだ決め手はどこにあったのでしょうか?
「使えるファイル箱が一番違うのは、やっぱり中小企業にとっての使いやすさという部分。他にすごい大手の企業が使っているようなサービスもありましたが、そういうサービスが我々のような会社の規模感にフィットするか、無理なく使いこなせるか、ということを考えると、どうしてもズレがあるように感じました」
「使えるねっとは、純粋に実直にクラウド事業に取り組んでいる企業だと感じます。それに、実際に顔を合わせてお話できるという安心感もいいですね。会社まで来ていただいて一度お会いしているから、普段の意思の疎通もしやすいし、安心できます。やっぱり我々のような中小企業にとっては、相手の顔が見えるというのは嬉しい」
こうした導入企業の声から見えてくるのは、使えるねっとが製品を売り切って終わりではなく、継続的に中小企業に伴走して、サポートしてくれる安心感です。効果的なシステム投資を検討しているなら、是非一度お問い合わせください。
.jpg)
1. 中小企業におけるクラウド導入率は?
総務省の「令和5年通信利用動向調査」によれば、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は2023年には77.7%でした。ただ、クラウドサービス導入率は企業規模によって大きく異なり、資本金1,000万円未満だと54.8%、1,000~3,000万円未満だと69.4%、3,000万円~5,000万円未満だと72.2%でした。
2. クラウドデータ管理とは何ですか?
クラウドデータ管理とは、企業がクラウドやオンプレミスに保存したあらゆるデータをクラウドベースで管理するプロセスです。クラウドデータ管理を実現することで、スケーラビリティ(拡張性)が高まり、コスト削減にもつながります。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
企業が情報を管理したり、共有したりする方法はさまざまです。その中の一つにNASがあります。近年、従来のファイルサーバに替えて、NASを導入する企業が増加しているともいわれています。
ここでは、NASとファイルサーバの違いや、それぞれのメリット・デメリット、選び方について、さらには「第三の選択肢」としてのクラウド型ファイルサーバの特徴について解説します。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
目次
NASとファイルサーバの違いについて
NASとファイルサーバができること
ファイルサーバの見直しが求められている背景
ファイルサーバのメリット5つ
ファイルサーバのデメリット2つ
NASのメリット3つ
NASのデメリット2つ
NASとファイルサーバ5つの比較ポイント
NASとファイルサーバはどちらを使うべき?
NAS及びファイルサーバを運用する際の注意点
クラウド型のファイルサーバとは?
クラウド型ファイルサーバのメリット
クラウド型ファイルサーバのデメリット
「使えるファイル箱」ならコストを抑えてデータ共有が可能
FAQ

最初にNASとファイルサーバとは何か、それぞれの使い方と違いについて説明します。両者の違いについてよく理解しないまま導入すると、かえって業務効率が低下したり、必要以上にコストがかかったりする可能性があります。
NASとは
NASとは「Network Attached Storage」の頭文字を組み合わせたもので、日本語に訳すと「ネットワーク接続型ストレージ」です。
名前が示す通り、NASとはストレージ(補助記憶装置)です。すぐに思い浮かぶストレージとしてはPCとUSBケーブルなどで接続する外付けハードディスクがありますが、NASはネットワークを経由して接続する点が異なります。
NASの使い方
NASの主な使い方はファイルのバックアップと共有です。
ネットワークで接続しているため、ネットワーク内の異なるユーザがアクセスし、パソコンやスマートフォンなどのデータをバックアップしたり、相互に共有したりすることが可能です。
ファイルサーバとは
ファイルサーバとは、ネットワークを経由してファイルを管理したり、共有したりするためのシステムのことです。
サーバとはそもそも、ネットワークでつながるコンピュータからのリクエストに応じてさまざまなデータや機能を提供する仕組みのことです。サーバには、Webサーバやメールサーバがありますが、ファイルサーバとは、その中でもファイルの管理や共有に特化した機能を提供する仕組みを指します。
ファイルサーバの使い方
ファイルサーバは基本的に自社で導入構築するため、業務や用途に合わせて柔軟に設定したり、機能を追加したりできます。
例えば、管理者はファイルやフォルダごとにアクセス権限を自由に変更できます。また、ファイルサーバ上でのアクセスや編集などの履歴を記録すること(アクセスログ)も可能です。
NASとファイルサーバの基本的な違い
NASはハードディスクと同じような「機器」であり、ファイルサーバは「システム」です。
そのため、NASは購入して、すでに構築されているネットワークに接続すれば使えるのに対して、ファイルサーバは端末、ソフトウェアなどを組み合わせて構築するため、より手間がかかります。また、導入後に管理や運用をする上でも、ファイルサーバはNASよりもコストがかかります。

ここでは、NASとファイルサーバを比較します。どちら「にも」できること、どちらかに「しか」できないことを明確にすることで、自社にとって最適なソリューションを見つけられるでしょう。
NASとファイルサーバが両方できること
NASとファイルサーバが両方できるのは、ファイルの保存と共有です。
ファイルの保存ができるので、ネットワーク内のユーザは自分のパソコンを使って作成したファイルの保存先としてNASやファイルサーバを選べます。その結果、自分のパソコンのハードディスクがいっぱいになってしまうことを防げますし、データをNASやファイルサーバにバックアップし、万が一のデータ消失リスクにも備えられます。
また、NASやファイルサーバにデータを共有することで、他のユーザとの共同作業も楽になります。もし、NASやファイルサーバを使わなれば、メールに添付したり、USBメモリを使ったやりとりになったりするため、情報漏洩のリスクが高まります。つまり、NASやファイルサーバは情報セキュリティのソリューションとしても有効なのです。
NASだけができること
ファイルサーバと比べてNASが優れているのは、導入や運用が簡単なことです。NASはファイルサーバと違って自分でネットワーク構築する必要がないため、導入時に細かな設定は必要ありません。
ファイルサーバだけができること
NASよりもファイルサーバが優れているのは、導入時に自社のニーズに合わせて柔軟に機能を設定したり、追加したりできる点です。NASはあくまでも「ストレージ」のため、データの保存がメインですが、ファイルサーバは「システム」としてのカスタマイズが可能なのです。

ファイルサーバの見直しが求められている背景には、企業を取り巻く環境が大きく変化している点が挙げられます。ここでは具体的な2つの点を説明します。
・ランサムウェア攻撃などへの対応の必要性
・新しい働き方の普及
以下で一つずつ解説していきます。
ランサムウェア攻撃などへの対応の必要性
ランサムウェアとは、パソコンやサーバなどの端末を感染させて中のデータを暗号化し、そのデータを復元するために対価(金銭や暗号資産)を要求する不正プログラムです。いうまでもなく、ファイルサーバの中に保管されているデータも被害ターゲットになります。警察庁が2024年3月に発表した資料によると、2023年中に警察庁に報告されたランサムウェアの被害件数は197件で、前年比14.3%減でしたが、引き続き高い水準で推移しています。
リモートワークなどの柔軟な働き方に対応し生産性を維持しながらも、新たな脅威に対処していくことがすべての企業に求められています。
新しい働き方の普及
従来、端末がすべてオフィスに存在し、社内で情報を共有するにはファイルサーバで何ら問題はありませんでした。しかし、テレワークの導入で従業員が社外からもアクセスする必要が増大しています。
ファイルサーバに社外からアクセスする場合、VPNを使用することが一般的です。しかし、VPNを使用すれば安全という訳ではありません。例えば、IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ10大脅威2024」によると、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が組織の情報セキュリティ上の脅威で第9位にランクインしており、その主な理由の一つはVPNの脆弱性を狙った不正アクセスだと考えられます。
テレワーク導入の要となるクラウドストレージについて知りたい方はこちら

ファイルサーバの最大の特徴は、上述したように柔軟な設定と自社のニーズに合わせた機能の追加です。さらに具体化すると、以下の5つに集約できます。
1. アクセス権を詳細に設定できる
2. スムーズに容量を拡張できる
3. 機能をカスタマイズできる
4. 業務効率の向上
5. 情報セキュリティの向上
1つずつ解説します。
1. アクセス権を詳細に設定できる
一般的にWindows Serverなどのサーバ用OSでは、Active Directory(Microsoftのユーザ管理機能)などにより、権限管理が容易です。
アクセス権を詳細に設定することで、不正アクセスのリスクを軽減でき、社内の情報セキュリティが向上します。
2. スムーズに容量を拡張できる
通常、個人で使うパソコンでHDDやSSDを増設するのは2台が限界です。しかし、ファイルサーバであれば、数百から数千のHDD、SDDを搭載できます。近年、扱うデータや1つ1つのファイルの大きさが増大しているため、ファイルサーバの拡張性は大きな魅力といえるでしょう。
3. 機能をカスタマイズできる
ファイルサーバでは、自社の特性や業務に合わせて自由度高く機能を追加できます。また、データの重要性に基づいて、自社のセキュリティポリシーに合わせてシステムをカスタマイズできるのもファイルサーバのメリットといえます。
4. 業務効率の向上
企業にとって業務効率の向上は常に重要な課題です。そのための施策はいろいろと考えられますが、データの管理、共有方法は中でも鍵といえるでしょう。ファイルサーバなら、自社の規模や業務内容、直近の課題などに合わせて、比較的自由に設定を変更したり、機能を追加したりできます。
5. 情報セキュリティの向上
今や情報は企業にとっては「資産」のひとつです。データ消失が一旦発生してしまえば、顧客からの信頼を失いますし、経済的な損害もはかり知れません。ファイルサーバは、セキュリティ設定も自由度が高いため、日々変化する企業の情報資産を脅かすサイバー攻撃に合わせて対策を講じることができます。
サイバー攻撃とは何か知りたい方はこちら
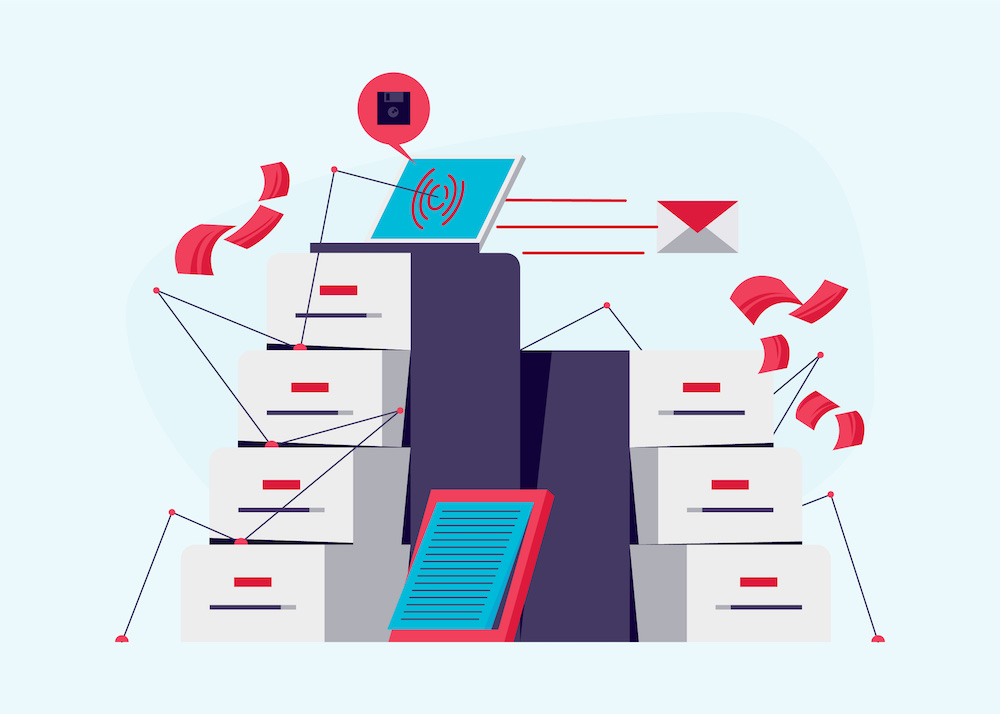
上述したようにファイルサーバには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。ファイルサーバは社内に設置するため、その保守管理を自社で行うことになります。具体的には、以下の2つのデメリットに集約されます。
1. 専門スタッフの常駐が必要
2. コストがかかる
1. 専門スタッフの常駐が必要
ファイルサーバは社内に設置し、社内に専門スタッフを常駐させることになります。その分、社内リソースをファイルサーバの保守管理に割くことになります。少子高齢化で労働力人口が減少している昨今、特に中小企業では人手不足が深刻です。そのため、専門スタッフを常駐することは現実的に困難な場合が少なくありません。
2. コストがかかる
ファイルサーバの設置には、高い導入コストがかかります。具体的には、サーバ機器の購入にかかる費用や社内環境の構築や初期設定にかかるコストも含まれます。
また、導入後のランニングコストにも注意が必要です。ライセンス費用やハードウェア、ソフトウェアのメンテナンス費用、サーバの稼働や空調のための光熱費などもかかります。さらにいずれ古くなったら、ファイルシステム全体を再構築することも不可避であり、それには膨大な費用がかかります。

上述したように、NASの最大の特徴は簡易な導入と運用です。そのことを前提にすると、具体的には以下の3点にまとめられます。
1. ファイルサーバに比べ手軽に導入できる
2. 自社の人的リソースの節約
3. 費用を抑えられる
1つずつ、各メリットの内容について説明します。
1. ファイルサーバに比べ手軽に導入できる
NASの最大のメリットは手軽に導入できる点でしょう。上述したようにファイルサーバの設定には膨大なイニシャルコストがかかります。それに対して、NASはほとんどの場合、ベンダーから製品を購入して、ケーブルをつないで簡単な設定をすればすぐに利用可能です。
2. 自社の人的リソースの節約
導入や運用が簡単なため、自社で専門スタッフを常駐させる必要がありません。そのため、社内の限られた人的リソースを他の業務に回すことができます。もし、使用上のトラブルが発生したら、社内スタッフがメーカーのサポートセンターに問い合わせることでほとんどの場合は解決が可能です。
3. 費用を抑えられる
「NASを導入する」と聞くと多額のコストがかかるイメージがありますが、簡単にいえばこれはストレージを購入することと同じです。そのため、従業員50人程度の中小企業向けなら10~30万円程度で購入でき、運用にも多くのコストはかかりません。

NASは導入、運用いずれの面でもコストを抑えられるため、中小企業には嬉しいのですが、デメリットもあります。具体的には主に2点にまとめられます。
1. 拡張性に限界がある
2. セキュリティレベルに限界がある
以下、それぞれのデメリットについて、その内容を説明します。
1. 拡張性に限界がある
NASは導入時に複雑な設定は必要ない半面、拡張性に欠けます。また、運用期間中に自由に設定を変更したり、機能を追加したりする点でも限界があります。
2. セキュリティレベルに限界がある
NASにもウイルス対策やアクセス権限の設定は可能ですが、状況に合わせた設定の自由度には限界があります。その点で、企業をとりまくサイバー攻撃の多様化を考えると、やや不安を感じる人もいるかもしれません。

NASとファイルサーバの比較ポイントは次の通りです。
1. カスタマイズ性
2. 利用範囲
3. セキュリティ対策
4. 導入、運用方法
5. 導入、運用のコスト
それぞれのポイントについてどちらが自社に最適なのか分析してみましょう。
1. カスタマイズ性
カスタマイズ性が高ければ高いほど、自社の業務や事業規模に最適化しやすくなります。この点、ファイルサーバはまさに自社にフィットするように機器を購入し、システムを構築します。そのため、非常にカスタマイズ性は高いといえるでしょう。一方、NASはファイルサーバほどのカスタマイズ性の高さはありません。カスタマイズ性についていえば、ファイルサーバに軍配が上がります。
2. 利用範囲
どんなシステムでも、漫然と導入すると失敗してしまいます。大切なのは、利用範囲や目的を確定しておくことです。例えば、自社は情報共有することでどのような課題を解決したいのか、そのためにはファイルサーバとNASとどちらが適切なのか、ということです。利用目的を明確にすれば、利用範囲も自ずから絞り込まれてきます。自社の従業員だけで利用するのか、それとも取引先など外部メンバーも含めて利用するのか、保管し共有したいデータはどのくらいのか、などです。
3. セキュリティ対策
結論からいうと、ファイルサーバの方がより安全性の高い情報セキュリティ対策を講じることができます。例えば、サイバー攻撃に対する対策についていえば、ファイルサーバはかなり細かいカスタマイズができるため、情報の重要度に合わせたセキュリティ対策が可能です。それに対して、NASはカスタマイズ性に限界があり、セキュリティ対策が手薄になりがちです。
また、物理的にもNASはコンパクトで持ち運べるメリットがある一方、その分、盗難などによるセキュリティリスクが高まります。ファイルサーバの場合、物理的な持ち出しはほぼあり得ません。
4. 導入、運用方法
上述したように導入の際にファイルサーバは大規模なシステム構築が必要です。それに対してNASは複雑な設定は不要であり、導入したらすぐに利用できます。
5. 導入、運用のコスト
NASはファイルサーバに比べて、導入や運用に手間がかからないため、その分コストも抑えることが必然的に可能です。
参考:NTTコミュニケーションズ 「ファイルサーバーとは? NASとの違いや選び方のポイントなどを解説」

NASかファイルサーバかどちらを選べば良いか迷いますが、重要なのは「何のために導入するのか」を明確にすることです。
「利用目的」に応じて選ぼう
NASとファイルサーバに限ったことではありませんが、機器やシステムを選ぶ際には利用目的をはっきりさせておくことが大切です。
例えば端末に関していえば、スマートフォンやタブレットはいつでもどこでもデータの閲覧をするのに最適なツールですが、動画編集など複雑な作業を行うには限界があります。対して、デスクトップはオフィスや自宅での使用に限られますが、作業範囲は広がります。
端末を使って何をしたいか明確にしておかなければ、費用をかけたものの十分に使いきれないという結果になりかねません。NASとファイルサーバにも同じことがいえます。
NASが適しているケース
NASが適しているのは、小規模の組織でできるだけコストを抑え、ファイルの保管や共有を行いたい場合です。小規模の組織であれば、ネットワーク内のユーザの業務も共通しているため、細かな設定変更がそれほど必要ないことも多いでしょう。
ファイルサーバが適しているケース
ファイルサーバが適しているのは、大規模な組織でファイルの保管や共有に加え、複数部署の多様な業務に対応するために柔軟な設定をしたり、機能を追加したりする場合です。
また、現在は小規模であっても、近い将来に従業員数や業務の増大が見込まれる場合もファイルサーバの導入を検討できます。そうすることで、イニシャルコストはかかるとしても、のちのち効率的にファイル共有を行うことで、生産性の向上が実現でき、長期的にはコスト削減につながるからです。
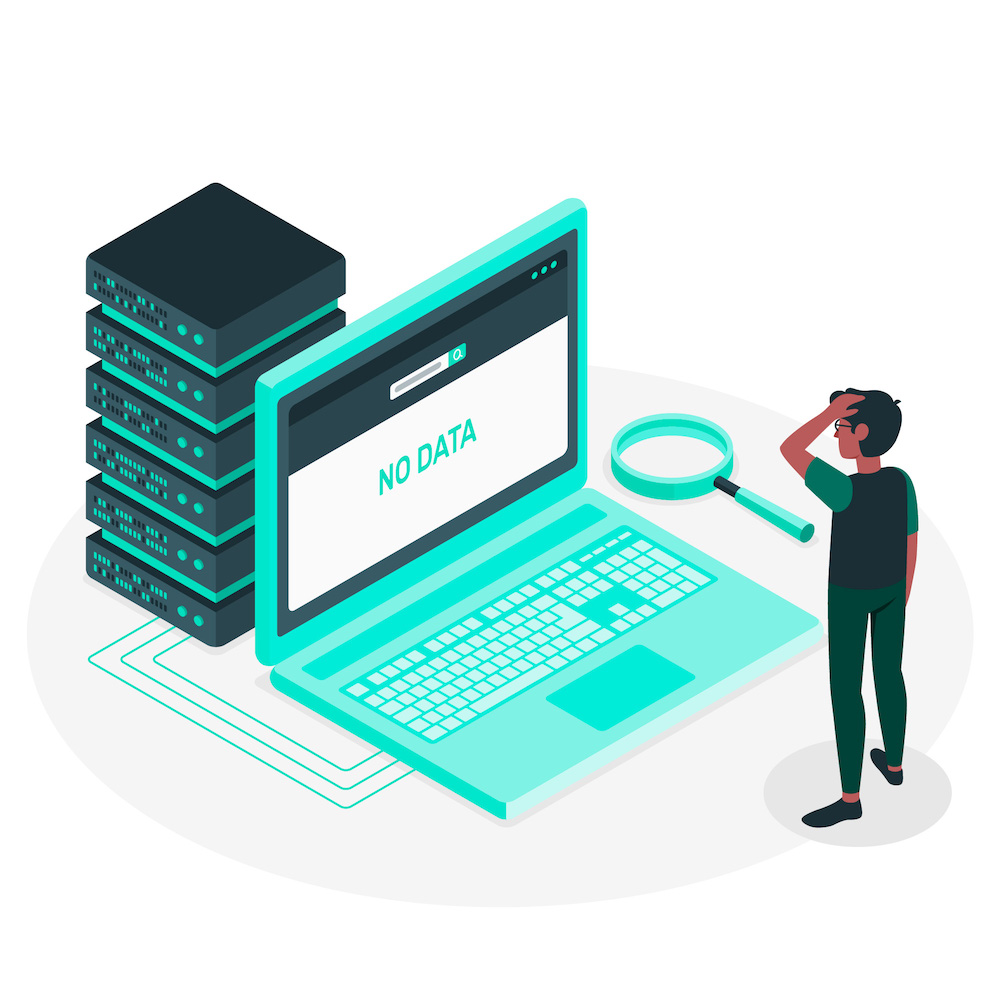
NASを運用する際には物理的影響によるデータ消失のリスクが高い点、ファイルサーバを運用する際には初期コストや人的コストがかかることに注意しましょう。
以下、それぞれについて説明します。
物理的影響によるデータ消失リスクが高い
NASはあくまでもハードディスクと同じように「機器」であるため、物理的な衝撃や経年劣化によるデータ消失リスクがファイルサーバよりも高いといえます。
NASを選択する場合はデータ消失のリスクに備えて、バックアップは必要不可欠でしょう。
導入・運用に対して初期コスト・人的コストがかかる
ファイルサーバは単に機器を購入すれば済むわけではなく、導入にはシステム設計や構築に専門家の手を借りなければなりません。また、導入後も運用や保守点検には専門知識が求められるため、初期コストや人的コストがどうしてもかかってしまいます。

ここまで、NASとファイルサーバを比較してきました。どちらにも一長一短があり、迷ってしまうかもしれません。もしそうであれば、「第三の選択肢」としてクラウド型のファイルサーバも検討してみることをおすすめします。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
法人向けクラウドストレージの比較を見たい方はこちら
クラウド型ファイルサーバは、インターネットを経由したファイルの管理、共有システムです。
インターネットという外部接続ネットワークを使用する点で、社内ネットワークを前提にしたNASやファイルサーバと異なります。
また、自社でファイル保管場所となる機器を設置する必要がない点も特筆すべき点といえるでしょう。
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら

クラウド型ファイルサーバのメリットは以下の4点です。
1. 専門スタッフを常駐させる必要がない
2. どこからでも接続できる
3. 柔軟な運用が可能
4. ランサムウェア対策が可能
以下で1つずつ解説します。
1. 専門スタッフを常駐させる必要がない
クラウド型ファイルサーバのストレージは、クラウドサービス提供業者のデータセンターです。そのため、ストレージの保守管理に自社でリソースを割く必要はありません。クラウドサービス提供業者の専門スタッフが24時間体制でモニターしているため安心です。
2. どこからでも接続できる
クラウド型ファイルストレージはファイルサーバと異なり、インターネットを経由してアクセスするため、どこからでも接続できます。中小企業を含め、多くの企業がテレワークを導入しており、働く場所も多様化しているため、オフィスの外からでも情報共有できるのは大きなメリットといえるでしょう。
3. 柔軟な運用が可能
ファイルサーバのカスタマイズ性の高さは大きな魅力ですが、クラウド型ファイルストレージもアクセス権限を制限したり、柔軟な運用が可能です。クラウド型ファイルストレージを提供している事業者はたくさんあるため、自社に合った機能やサービスをきっと見つけられるはずです。
4. ランサムウェア対策が可能
クラウド型ファイルストレージはランサムウェア対策でも大きな力を発揮します。
ランサムウェアとは、ターゲットが保有する情報を不正に暗号化し、データの復元と引き換えに多額の身代金を要求する悪質なマルウェアです。ランサムウェア攻撃に遭うと企業は多大なる損失を被ります。例えば、2024年6月に株式会社KADOKAWAグループはランサムウェア攻撃を受け、2025年3月期に36億円の特別損失を計上する見通しです。
大企業だけでなく、中小企業もランサムウェア攻撃の対象になります。警察庁が公表した「令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、業種を問わず中小企業が全体の約6割を占めています。
ランサムウェア攻撃を受けた場合、被害を最小限にとどめるためには早期に復旧作業を始めることがなによりも重要です。そのためには万が一に備えたバックアップが欠かせませんが、同じネットワークにつながっているファイルサーバやNASにバックアップデータを保存していると、端末がランサムウェアに感染することで、バックアップデータも暗号化されるリスクがあります。その点、クラウド型ファイルストレージにバックアップを取っておけば、安心なのです。
ウィルス・ランサムウェア対策からパッチ管理まで、クラウドバックアップの多彩な用途について知りたい方はこちら
.png)
もちろん、クラウド型ファイルサーバにもデメリットはあります。クラウド型ファイルサーバのデメリットは以下の3点です。
1. 既存システムと統合するのが困難
2. セキュリティリスクが高まる
3. 利用料金が高額になる可能性がある
以下で一つずつ解説します。
1. 既存システムと統合するのが困難
多くの企業がクラウド化を進めたいと思いながらも躊躇している理由の一つとして、既存システムとの統合が難しい点が挙げられます。新しく導入するクラウド型のシステムと既存システムとの連携がうまくいかず、データ共有の際に手作業工程が発生するなど、業務効率がかえって下がってしまうことはよくあります。もっともこの点は社内一丸となって一気にDXを進めることで解決することが可能です。クラウド化をチャンスととらえて、業務フローやシステム全体を見直してみるのも一つの手です。
DXについて知りたい方はこちら
2. セキュリティリスクが高まる
何度も述べているようにクラウド型ファイルサーバはインターネットを経由するため、「閉じられた」社内ネットワークよりもセキュリティリスクはどうしても高まってしまいます。ただ、多くのクラウドストレージサービスがセキュリティ向上に注力しているため、比較して選ぶことでセキュリティ面での不安はかなり軽減できるはずです。
3. 利用料金が高額になる可能性がある
クラウド型ファイルサービスの特徴の1つは導入コストがファイルサーバに比べて低いことです。しかし、課金体系に注意しないと、運用コスト(利用料金)が高額になる可能性もあることを覚えておきましょう。
基本的なクラウドストレージサービス以外にも、オプションでさまざまなサービスを選択できるため、自社にとって本当に必要な機能を見極め、きちんと契約内容を確認しておけば料金について心配する必要はありません。
.png)
クラウド型ファイルサーバをお考えなら、「使えるファイル箱」がおすすめです。
「使えるファイル箱」なら、クラウドに保存したファイルを編集・整理し、Webリンクを使用してファイルやフォルダを無制限に他のユーザに共有できます。
心配なセキュリティに関しても2要素認証設定、暗号化、ログ記録、ISO認証データセンターなどで、自社の情報資産を情報漏洩からしっかり守ります。また、暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムAES256ビット暗号化を採用し、ウェブサーバとブラウザ間のデータ通信を暗号化するウェブ管理画面のSSL化も行うため、ファイル型クラウドサービスの懸念点であるセキュリティの不安も払拭してくれます。
ファイルサーバとNASの、それぞれのメリットを併せ持った「使えるファイル箱」を是非ご検討ください。
容量1TB、ユーザ数無制限で月単価21,230円(税込、スタンダードプランで1年契約の場合)からご利用いただけます。セキュリティ対策を強化し、容量を3TBにしたアドバンスプランなら月単価60,500円(税込、1年契約)で、WebDAV連携も可能です。料金体系がシンプルで分かりやすいのも使えるファイル箱の魅力です。
30日間の無料トライアルも実施していますので、まずは使い勝手の良さを体感してみてください。
.jpg)
(1)ファイルサーバの種類は何がある?
主なファイルサーバには以下のようなものがあります。
・データベースサーバ
データベースサーバは数値などのデータの管理に特化したサーバで、通常ビジネスで使用するファイルは扱わない。
・クラウドサーバ
社内の機器ではなく、インターネットを経由してつながっているデータセンターにデータを保管するシステム。
・Windowsファイルサーバ
Windowsの機能を利用したユーザ間でファイルを共有するサーバ。導入が簡単だが、セキュリティリスクが高い点に注意。
(2)NASを導入するリスクは?
物理的損傷に弱いNASの最大のリスクは、設置場所で災害が起きた場合にデータ消失してしまう可能性が高い点です。
(3)NASやファイルサーバの置き場所は?
クラウド型ファイルサーバが社外のデータセンターにデータを格納するのに対して、NASやファイルサーバは社内に機器を設置して、そこにデータを保管します。
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
クラウドサービスを選ぶ際に気になる点はいろいろとあります。導入コストやセキュリティも重要ですが、決め手になるポイントの一つは容量ではないでしょうか?DX(デジタル技術によって経営やビジネスプロセスを再構築すること)が進む中、企業間で転送・保管するデータは増加する一方です。
大容量と聞くと何となく「TB(テラバイト)」は大きそうだな…と連想されますが、実際どのくらいの量のファイルを保存できるのかイメージがわきづらいのではないでしょうか。そこで、今回の記事ではTB、GBなどストレージの容量にスポットライトを当てて、保存できるデータの量と人気のストレージサービスの容量設定について解説します。
クラウドバックアップのおすすめサービスについて知りたい方はこちら
クラウドバックアップについて知りたい方はこちら
目次
1TB(テラバイト)とは?GB、TB、実際の容量別に解説
クラウドストレージサービスで一般的な容量設定
大容量データが必要な場合とは
業務で大容量データを使用する場合の例
クラウドバックアップサービスで一般的な容量設定
使えるファイル箱を導入した事例を紹介
使えるクラウドバックアップを導入した事例を紹介
使えるファイル箱で容量ニーズと高度なセキュリティ要件を両立
FAQ
1TB(テラバイト)とは1,000GB(厳密には1,024GB)のことです。具体的には1TB(テラバイト)の録画時間はフルHD動画で約166時間に相当します。しかし、容量が大きければ大きいほど良いわけでもありません。なぜなら、大きくても使い切れないこともあるからです。大切なのは、自社のユーザ数や業務形態に合わせて選ぶことです。
企業規模や業種に関わりなく、業務データの大容量化が進んでいるため、クラウドストレージサービスの導入が必須といえるでしょう。この点、使えるファイル箱なら1TB(追加も可能)、ユーザ数無制限で安心です。
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
ノートパソコンのハードディスク(HDD)1TB搭載容量とは
デスクトップパソコンに比べ、ノートパソコンには大型のHDDを搭載することは難しく、128GB(ギガバイト)、256GB、516GB、1TBなどが主流といえるでしょう。ただ、近年個人が扱うデータも大容量化しているため、hddで1tbか2tbのどちらか迷ったり、ノートパソコンでも1tbは必要と考えたりする人も増えています。そうしたニーズゆえに1テラのハードディスクの価格も以前では考えられないくらいリーズナブルになりました。
データの基本単位は1バイトで、厳密にはその1,024倍で次の単位に移行しますが、1テラは何ギガかといえば、1,000ギガと覚えておいて問題ありません。
・1,000B(バイト)=1KB(キロバイト)
・1,000KB=1MB(メガバイト)
・1,000MB=1GB(ギガバイト)
・1,000GB=1TB(テラバイト)
最近ではHDDより読み書きの速度が速く、衝撃に強いSSD(ソリッドステートドライブ)も普及しています。ただ、HDDよりも価格が高く、容量も少な目のものが多く、ノートパソコンに内蔵しているSSDは240〜500GBが大半のようです。
各メディアに換算した場合の容量比較
1TBが大容量ということは分かっても、数字だけではイメージがわきにくいと思います。以下では身近なメディアに換算してその大きさを具体化してみましょう。
.jpg)
デジカメ写真の1TBとは?
→1枚4MBのJPEG画像ファイル約25万枚
スマホの1TBとは?
→1台100GBのスマホ約10台
動画録画時間の1TBとは?
→フルHD動画ファイル約166時間、4k映像の録画時間は1tb=約65時間
音楽の1TBとは?
→1曲5MBのMP3音楽ファイル約20万曲
文庫本の1TBとは?
→1冊100MBの文庫本約10,000冊
いかがでしょうか?1TBの大きさがどのくらいか何となく分かっていただけたかと思います。
それでは、使えるねっとが提供しているようなクラウドストレージサービスでは一般的にどのような容量設定なのかを見てみましょう。各企業ともさまざまなプランを用意していますが、以下では法人向けのスタンダードなプランを例に比較してみます。
| |
容量
|
料金
|
備考
|
|
A社
|
2TB/ユーザ
|
1ユーザ/月1,360円
|
4ユーザ以下の
場合は1TB/ユーザ
|
|
B社
|
5TB
|
1ユーザ/月1,250円
|
3ユーザ以上
|
|
C社
|
無制限
|
1ユーザ/月3,000円
|
アップロード上限
5GB
|
|
D社
|
100GB
|
66,000円
|
10ユーザ分
|
|
E社
|
500GB
|
50,200円/月
|
2ユーザの場合
|
|
使えるファイル箱
|
1TB
|
21,230円(税込)/月
(1年契約の場合)
|
ユーザ数無制限で料金は固定
|
上表から「使えるファイル箱」が他社に比べて必要十分な容量を備えており、料金体系がシンプルであることが分かります。また、圧倒的な魅力はユーザ数無制限です。
容量は大きければ大きいほどよいのか?
上記表では容量と料金だけを比較していますが、お気づきのように業界大手の容量設定は無制限のサービスも含めて増加傾向にあります。ただ、料金は1ユーザごとの設定がほとんどであることに注意が必要です。
ポイント1:ユーザごとの容量が多くても「使われない」ケースが大半
大手クラウドサービスのプランには1ユーザあたり2TBなど大容量のものもありますが、ある企業内の1ユーザが2TBもの容量を効率的に利用することは非常にまれでしょう(エクセルやワードを200万ファイルも保存するでしょうか…)。
一見「大きい方がお得!」に見えがちですが、実際に運用を始めるとそこまで使わない…ということが多く、費用削減のためにアカウントを共有し、ユーザ数を減らすことで対応しようとするケースが多く見られます。しかし、複数ユーザでアカウントを使いまわそうとするとやはりセキュリティ面が懸念されます(例えば、誰がデータを削除したのか分からなくなるなど)。
また、オンラインストレージの最大の魅力である「フォルダ毎、ユーザ毎に誰が何を閲覧、編集できるかを一元管理できる」メリットが失われてしまいます。「重要なデータは結局部長の個人PCの中」、なんていうことが起こってしまいかねません。せっかく大容量のプランを契約しても宝の持ち腐れになってしまうだけでなく、結果として自らセキュリティの脆弱性を招いてしまうため、費用削減のためのアカウント共有はおすすめできません。
ポイント2:「ユーザ数無制限」だと容量もセキュリティ効果も両立
逆に使えるファイル箱のようにユーザ数無制限であれば、追加料金なしで全社員や取引先でフォルダを分けて、無駄なく容量を共有できます。基本プランでは1TBご利用いただけるため、中小企業のユーザ様には十分な容量です。ユーザごとにアカウントを作成し、退職や契約終了などで不要になったら削除するだけで済むため管理・セキュリティ面でも安心です。
このようにクラウドストレージサービスは容量が大きければよいというわけではなく、自社の業務内容や使用する人数、扱うデータ量や種類に合わせて選ぶことが大切です。
使えるファイル箱の初期容量が1TBに設定されているのをはじめとして、クラウドストレージサービスが大容量化しているのには理由があります。それはコロナ禍やDX推進に伴い、企業が生み出し、やり取りするデータ量が増加しているからです。
総務省の調査によると、2022年11月の国内固定系ブロードバンドインターネットサービス契約者の総ダウンロードトラフィックは約29.2Tbps*(推定)で、前年同月比23.7%増でした。
*Tbps(テラビット毎秒):1秒間に何兆ビット(1テラビット = 1,000GB)のデータを転送できるかを表す単位。
業務データの大規模化が進み、データ保管・共有ニーズが拡大
これまでは企業間のデータのやり取りはメールやFTP(ファイル転送プロトコル)が主流でしたが、転送できるデータ容量に制限があり、送信する際に圧縮や加工、分割などが必要でした。メールに添付できるデータ容量は10~100MBであるため、高画質の画像ファイルや映像を送りたい場合はほぼ不可能です。
こうしたやり取りがスムーズに行えなければ時間のロスが発生し、工期に大幅な遅れが出てしまうことになります。テレワーク導入で業務拠点がさらに増加しているため、データをどのように保存、共有していくか、この課題を首尾よく解決できなければ、企業は結果的に競争優位性を失ってしまうでしょう。
以下に具体例を挙げてみましょう。
・製造業などで設計・書類データをやり取りする場合
・海外にエンジニアやクリエイター、マーケターを抱えており、言語やOSの違いを超えて情報共有する場合
・建築・建設業において、施工者とCADデータ・図面・現場写真のやり取りをする場合
・研究所が解析した巨大な研究データを送付する場合
・デザインデータを印刷・広告会社に送信する場合
・国内メーカーが海外工場に作業手順に関する説明動画を送付する場合
いずれもクラウドストレージサービスなら共有がスピーディー、安全かつ簡単です。
.jpg)
バックアップをクラウドサービスを使って行う場合、どのくらいの容量が必要になるのでしょうか?基本的にはバックアップは端末に保存しているデータが使用できなくなった場合のためのものですから、それと同容量と見積もっておくとよいでしょう。もし、複数台の端末にデータを格納している場合、その合計の容量が必要になります。
数あるクラウドストレージサービスの中で、容量1TB、ユーザ数無制限の「使えるファイル箱」の使い勝手はどうなのでしょうか?それを知るには実際に導入した中小企業様の事例を見てみるのが一番です。以下、2つご紹介いたします。
ビジネスアプリケーション開発やネットワーク構築を行っているIT企業
トラステックは主軸である金融に加えて、交通・医療の分野にも事業展開しているIT企業です。
クラウドストレージサービスの導入にあたって、使えるファイル箱を選んだ決め手は1TBの十分な容量と固定料金制の2点だったようです。
導入後、エンジニアが客先からでもファイルを閲覧できたり、オフィスに戻らずとも資料のやり取りを行ったりできるため、交通費や移動時間の節約に繋がっていると実感しておられます。
また、ユーザ数無制限で社員だけでなく、取引先にもIDを割り当てて使えるため、システム開発など共同作業をする際にとても使いやすいとのことです。さらにファイルをすべてクラウド上で管理してもらえていることで、災害時も安心して構えていられるともおっしゃっています。
使えるファイル箱で業務効率化を達成した導入事例の全文はこちらからご覧ください。
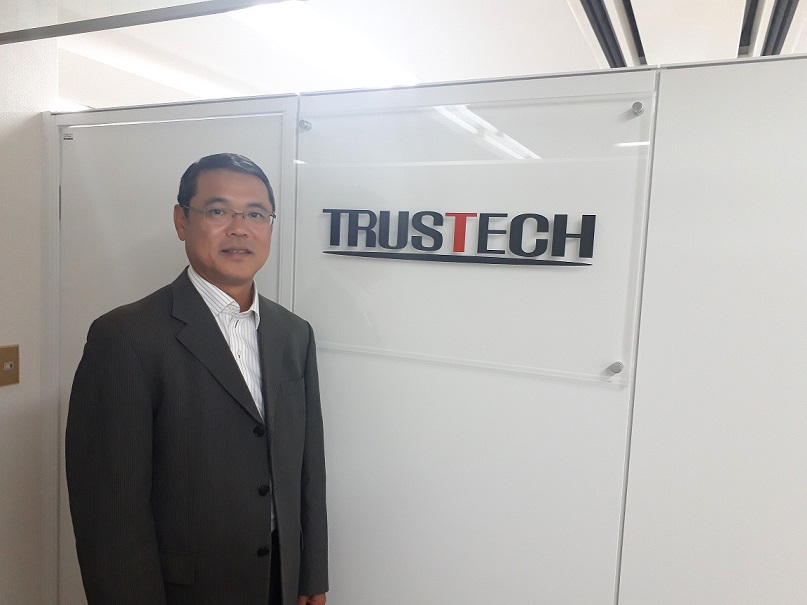
電子部品の製造や精密板金・塗装などを手掛ける老舗企業
松代工業株式会社は1958年の創業以来、電子部品および精密板金を軸にものづくりを通じて人々の豊かな暮らしや社会発展に貢献してきました。昭和・平成・令和という3つの時代を駆け抜けてきた同社は、変化に迅速に対応する先進的でチャレンジ精神旺盛な企業でもあります。
松代工業ではこれまで自社でファイルサーバを運用していましたが、日常的な運用コストだけでなく、定期的な物理サーバの入れ替えやアップデートが担当部門のリソースを圧迫していました。そうした中、ファイルサーバのクラウド化を模索し始め、最終的に「使えるファイル箱」を選択しました。
決め手になったのは、その「空気みたいに使える」使いやすさとシンプルさだったと言います。現在、同社では総務や経理に加えて、工場で発生したさまざまな品質保証データのやり取りに使えるファイル箱を活用しているとのこと。いずれは図面などの共有にも使いたいとおっしゃっていますが、余裕ある1TBの容量のため、将来性も抜群です。
1TBの導入実績に関する事例記事の全文はこちらからご覧ください。

データ容量が気になるのはクラウドストレージだけではありません。万が一に備えて利用するバックアップサービスの容量も、必要十分な大きさを選択する必要があります。
バックアップ先としてはオンプレミス(自社で保有、管理しているシステム)か、クラウドストレージが一般的です。総務省の情報通信白書(令和6年版)によると、クラウドサービスを利用している企業は77.7%(「全社的に利用している」50.6%、「一部の事務所又は部門で利用している」27.1%)で、そのうち42%が「データバックアップ」に利用していると回答しました。2019年には31.4%だったのが、5年で10%以上増加しており、データバックアップにクラウドサービスを利用する企業は今後ますます増えると思われます。
この点、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は初期費用不要で簡単に導入でき、効率的かつ安全な完全クラウド型バックアップソリューションとしておすすめです。容量は企業の事業規模や従業員数に合わせて、200GB~10,000GB(=10TB)まで選べます。
ここでは、使えるクラウドバックアップを導入した中小企業様の事例をご紹介しましょう。
全国約400社の中でトップシェアを誇るクラフトビールメーカー
株式会社ヤッホーブルーイングの基幹系システムは、サーバ1台、クライアントPC25台ほどからなるクライアント/サーバシステムで、従来NASへバックアップを取っていたそうです。しかし、バックアップの失敗が頻発するようになり、BCP対策の観点に加え、専門的な知識がなくても簡易にシステムを復元できるようにするため、2018年からクラウドバックアップを検討するようになったと言います。その際、重視したのがコストとバックアップ機能のバランスでした。
比較検討した結果、コスト面で最も優れていた「使えるクラウドバックアップ」をトライアルで使ったみたところ、操作のしやすさ、ランサムウェア対策機能が決め手になり、2019年1月から使えるクラウドバックアップの正式利用をスタートしました。
最初のフルバックアップは2時間ほどでスムーズに完了し、その後の毎日の増分バックアップも数分以内で終了すると言います。毎日のバックアップ完了をメーリングリストに通知するように設定したところ、メンバーのバックアップに関する意識も大きく向上したそうです。
使えるクラウドバックアップの導入実績に関する事例記事の全文はこちらからご覧ください。
使えるクラウドバックアップは月単価2,200円(税込)〜、用途や容量に合わせて多彩なプランから選べます。
テラバイトのクラウドストレージサービスである使えるファイル箱はユーザ数無制限で、スタンダードプランなら1年契約をしていただくと月単価21,230円(税込)でお得にご利用いただけます。
容量に関しては、WordやExcelのやり取りや保存であれば特に気にする必要はありませんが、前述したように建築会社やデザイン・動画の制作会社は専用のツールを用いて作業するため、そもそも処理するデータが大きくなりがちです。1TBの大容量であれば、個々の社員が処理するデータ量が比較的大きい場合でも安心です。
さらに大容量のデータを扱う場合にはアドバンスプランもご検討ください。容量は何と3TB、さらに以下4つの機能が追加されます。
|
IPアドレス
ホワイトリスト
|
指定のグローバルIPアドレスを登録することにより、登録外のIPアドレスからのアクセスを制限
|
|
デバイス管理
|
新しいデバイスからの初回アクセス時、管理者に通知が届き、管理者から認証された場合にのみアクセスが可能
|
|
WebDAV連携
|
WebDAVに対応したサードパーティ製のソフトウェアや、LinuxOS上で直接、ファイル箱の共有ドライブをマウント可能に
|
|
高度な共有リンク設定
|
ダウンロード回数の制限、リンク先にアクセスできる宛先を指定、閲覧のみ・ダウンロードのみ・閲覧とダウンロード両方と、設定を使い分けられる
|
アドバンスプランは1年契約の場合、月単価60,500円(税込)でご利用いただけます。
ユーザ数無制限+容量課金制でどんなユースケースでも安心
スタンダード、アドバンスいずれのプランでもユーザ数は無制限のため100人でも1,000人でも費用は固定です。データ容量は企業の成長や扱うデータ量に合わせて無制限に追加可能で(追加容量1TB/税込8,580円)、どんなユースケースでも安心。ウェブ管理画面での操作も可能ですし、普段の使い慣れたWindows、Macを使うように操作もできるため、メンバーの教育コストも不要です。まずは30日間無料のトライアルを試してみてはいかがでしょうか?
.jpg)
(1)BCP対策に「使えるクラウドバックアップ」が有利なのはなぜ?
BCP(Business Continuity Plan)とは「事業継続計画」のことで、自然災害やテロ、サイバー攻撃などの緊急事態に直面しても損害を最小限にとどめ、事業継続、早期復旧を可能にする事前計画のことを指します。使えるクラウドバックアップなら、データはデータセンターで安全に守られますし、BCP対策に有効なディザスタリカバリオプションを利用すると、万が一のときにバックアップイメージからクラウドの仮想マシンに瞬時に切り替え、ビジネスを止めません。
(2)データ保管に「使えるファイル箱」が有利なのはなぜ?
オンプレミスだとハードウェアの導入やシステムの構築のために莫大な初期費用がかかりますが、クラウドストレージサービスである使えるファイル箱なら、最小限の初期費用で簡単に導入できます。また、クラウドストレージでの大容量データ管理ができるだけでなく、必要に応じてリソースの調整がしやすいこと、保守や運用の負担が軽減できる点も使えるファイル箱の利点です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
「使えるクラウドバックアップ」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
2010年以降、企業のITインフラをクラウド化する流れが一気に加速しました。しかし、ここにきて「オンプレミス」に回帰する動きが出始めています。
2023年12月にエイチシーエル・ジャパンが国内企業のマネジメント層150人を対象に実施した調査によると、全体の52.7%が「今後3年以内に勤務先のIT環境の一部を従来のオンプレミスへと移行を予定または検討中」と回答しました。
今回はクラウドと比較される「オンプレミス」とはそもそも何か、そのメリット・デメリット、および導入する際に注意すべき点についてご説明します。
目次
オンプレミスとは?
オンプレミスとクラウドの違い
オンプレミスを利用するメリット
オンプレミスを利用するデメリット
事例紹介:松代工業株式会社、オンプレミスのデメリット対策でクラウド化
オンプレミスとクラウドを導入する際のポイント
オンプレミスをクラウドに移行する際の注意点
使えるファイル箱なら、コストを抑えてデータの共有が可能
FAQ

オンプレミス(on-premises)とは、サーバやデータベース、ソフトウェアなどの情報システムを自社の施設内に導入・設置し、運用することです。現在、多くの企業が導入しているクラウドベースのシステム構築の対極にあるといえます。
現在のようにSaaS(Software as a Service)が多くの企業で利用される前は、オンプレミスが社内システムを構築するための方法でした。多くの場合、ハードウェアベンダーにサーバなどの機器を設置してもらい、SIer(エスアイヤー)と呼ばれるシステム開発会社に自社のニーズに合わせて業務システムや基幹システムの設計開発、サーバやデータベースの構築などをしてもらいます。また、導入後のシステム保守管理もそのまま外部事業者に委託したり、自社の専門部署で行ったりしていたのです。
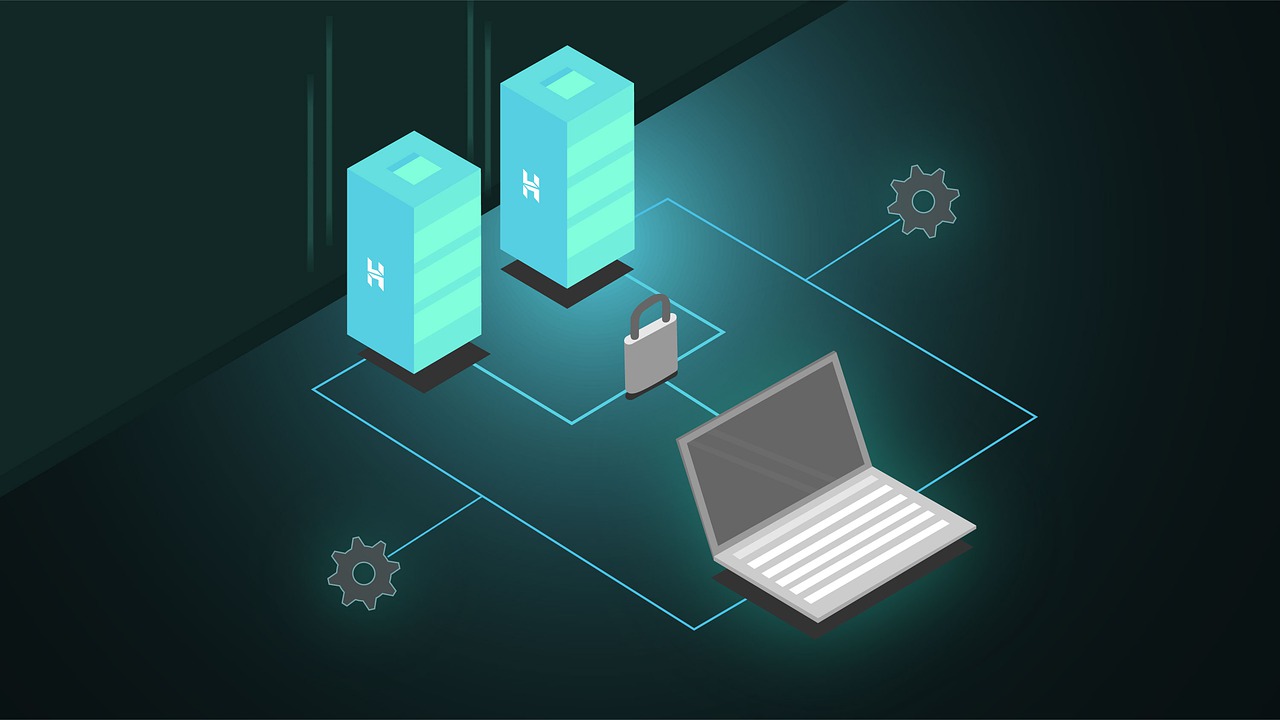
オンプレミスに対してクラウドでは、業務で利用するサービスやソフトウェア、データベースなどは自社内に格納せずに、インターネットを経由して利用します。
オンプレミスとクラウドの違いは具体的に以下のような点に表れます。
導入費用
システムの構築をオンプレミス、クラウドで行う場合、それぞれ以下のような初期コストがかかります。
|
オンプレミス
|
開発コスト、導入費、ライセンス価格
|
|
クラウド
|
ライセンス価格(サービス利用料)
|
オンプレミスでシステムを構築する場合、まずはハードウェアを準備し、基本的なソフトウェアなどを導入します。企業の業務形態によってはさらにカスタマイズをしたり、拡張機能を追加したりする必要があり、別途開発費がかかります。また、操作方法に精通するための教育費用も追加することになるでしょう。さらにライセンス価格も事業所ごと、ユーザごとに必要になります。具体的にどのくらいの費用になるかは企業規模や従業員数にもよりますが、オンプレミスの場合、初期費用が1,000万円を超えるのは珍しいことではありません。
それに対して、クラウドの場合は自社にサーバなどのハードウェアを設置する必要はありませんし、すでに製品化されたソフトウェアを使用するため基本的には開発コストもかかりません(最近ではカスタマイズできるクラウドサービスも増えています)。ライセンス価格(サービス使用料)が主なコストであり、導入後もランニングコストとして継続的に支払う必要があります。
導入までの時間
オンプレミスの場合、導入の際にサーバなどのハードウェアを選定することから始めなければなりません。そのため、ハードウェアの調達に少なくても1カ月かかりますし、ソフトウェアの開発やカスタマイズにはさらに数カ月という長い時間が必要です。導入の際の設定やテストにも手間とコストがかかります。
それに対して、クラウドの場合、申込からサーバの立ち上げまで基本的にはすべてインターネット経由で行うため、大きなトラブルがなければ数分から数時間で完了します。
操作性
「オンプレミスだから操作が複雑」、「クラウドだから簡単」と一律にはいえません。操作性は主に製品によって大きく異なります。そのため、オンプレミス、クラウド関わりなく、導入の際にはある程度の研修が必要になるでしょう。
ただ、オンプレミスは自社に合わせてカスタマイズできることから操作しやすいと考えがちですが、その逆になることもあります。つまり、細かなカスタマイズを行うことでかえって操作が複雑になる可能性があることも覚えておきましょう。
他システムとの連動性
オンプレミスは自社のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのが強みです。そのため、すでに自社に導入している既存のシステムと連動させやすいでしょう。
クラウドの場合、さまざまな企業のニーズに基づいて設計されているため、すでに導入している自社システムとの連動が難しい場合も考えられます。そのため、システムを統合するには「IaaS(Ingrastructure as a Service)」や「PaaS(Platform as a Service)」の導入も検討しなければなりません。
IaaSとはサーバやストレージ、ネットワークなどハードウェア環境やインフラまでを提供するためのサービスであり、PaaSとはプラットフォームや開発環境まで提供するサービスです。
セキュリティ
オンプレミスは自社独自のセキュリティ対策を講じやすく、サーバの設置場所やセキュリティ対策ソフトの導入、不正アクセスの監視など、かなり自由にカスタマイズできます。
それに対して、クラウドはオンライン上のサービスのため、オンプレミスに比べてセキュリティリスクが高いといわれることがあります。ただ、クラウドを利用する場合でも事業者によってセキュリティレベルは大きく異なるため、一律に「クラウド=セキュリティが弱い」、「オンプレミス=セキュリティに強い」とはいえません。クラウドでシステムを構築する場合は、自社のセキュリティポリシーにかなうサービスを選ぶことが大切です。
また、導入後のセキュリティ管理を誰が行うかもオンプレミスとクラウドでは異なります。オンプレミスは基本的に自社のセキュリティ部門が担当するか、外部事業者に委託するかのどちらかです。
クラウドの場合はクラウドサービスの提供事業者に委ねるため、自社で専門人材を準備する必要はなく、コスト削減につながります。それだけに、繰り返しになりますが、どの事業者を選ぶかは非常に重要な選択です。
オンプレミスとクラウドの比較まとめ
以上のオンプレミスとクラウドの比較を表にまとめてみましょう。
| |
導入費用
|
導入までの時間
|
操作性
|
他のシステムとの
連動性
|
セキュリティ
|
|
オンプレミス
|
高額
|
数カ月
|
複雑になることも
|
連動しやすい
|
ローカル環境で
安心
|
|
クラウド
|
低額
|
数時間
|
製品による
|
連動しにくいことも
|
インターネット
経由で不安も
|
クラウドストレージのおすすめ比較を知りたい方はこちら
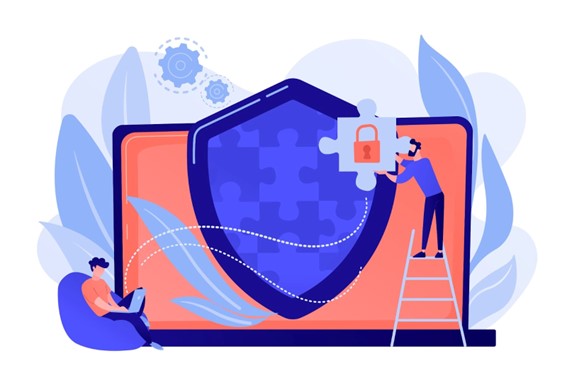
以上の比較からオンプレミスにもクラウドにも一長一短があることが分かります。ただ、冒頭で取り上げたように近年多くの企業で「オンプレミス回帰」の動きがあるのは、オンプレミスを利用するメリットが大きいからにほかなりません。
以下では、そのうちの3つを取り上げます。
カスタマイズ性に優れている
オンプレミスの最大の特徴は、自社でハードウェアもシステムもカスタマイズできる自由度の高さです。
クラウドの中にも柔軟な開発やカスタマイズが可能になるサービスが増えてきているとはいえ、拡張性の高さを考えるとオンプレミスに軍配が上がります。給与計算や労務管理、顧客管理、ストレージサービスといったどの企業にも共通するサービスでは細かなカスタマイズは必要ありませんが、中には業務の独自性が高く、パッケージ化されたサービスでは対応できない企業もあります。その場合は必然的にコストがかかるとしてもオンプレミスを選択することになります。
安全なセキュリティ構築ができる
オンプレミスは社内に設置しているローカル環境でシステム構築をしていることから、外部からのサイバー攻撃に対して比較的安全なセキュリティが構築できます。
ただ、上述したように「オンプレミス=セキュリティに強い」、「クラウド=セキュリティが弱い」という単純な図式では説明できない部分もあります。
例えば、2021年1月29日に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は「Salesforceの製品の設定不備による意図しない情報が外部から参照される可能性について」という異例の注意喚起を出しました。「Salesforce」はクラウド型のCRM(顧客管理)ツールですが、このサービスを利用する楽天やPayPay社をはじめ、多くの企業で「設定不備」によって個人情報流出が起きたのです。この事故はSaleforceがクラウドサービスゆえの脆弱性を攻撃されたというより、担当者の「設定不備」というヒューマンエラーに起因するものでした。
また、調査会社のガートナーは2019年、「2025年にかけて、クラウド上のセキュリティ事故の99%は利用者自身の設定ミスによるものとなる」と警告していましたが、まさにその通りのことが起きています。
このことはオンプレミスであっても、クラウドであっても注意深い運用があってはじめて安全なセキュリティが構築できることを示しています。
他のシステムと連動しやすい
オンプレミスはカスタマイズ性に優れていることから、自由度が高く、他のシステムとも連動させやすいといえます。ただ、その分のコストはかかることに注意が必要です。
.jpg)
初期費用が高い
上述したように、クラウドに比べ、オンプレミスに初期費用がかかることは間違いありません。ただコストは初期費用だけをみるのではなく、長期的な視野に立って考えることが大切です。
クラウドサービスの場合、初期費用はあまりかからないものの、月々のライセンス料(サービス利用料)がかかります。どのようなサービスを利用するかにもよりますが、毎月の支払いによって数年後にはオンプレミスの初期費用に追いついてしまうことも考えられます。
さらに、クラウドには多種多様な追加サービスがあります。例えば、ローカルで保管していたデータをクラウドストレージサービスに移行する場合、データが増えれば増えるほどストレージ容量を追加しなくてはならず、それに伴って費用がかかることになります。業務遂行に必要なサービスを追加していたら、いつの間にか費用がかさみ請求書を見てびっくりする、ということもあるようです。
導入までに時間がかかる
ハードウェアもソフトウェアの開発も必要としないクラウドに比べ、導入までに時間がかかるのはオンプレミスの大きなデメリットです。ビジネスにおいては、スピードが欠かせません。オンプレミスにしろ、クラウドにしろ、システムそのものが大事なのではなく、システムを使って生産性を高め、業績向上につなげることが企業の最優先課題です。
運用に専門の知識やリテラシーが必要になる
オンプレミスの運用は自社で行わなければなりませんが、専門知識を有する担当者を確保しなければなりません。
その点、クラウドであれば、運用は専門知識を持つ提供事業者に任せ、より多くの人材を本業に振り向けられます。もっとも、上述したように最低限の設定の仕方やセキュリティに関するリテラシーは自社のすべての従業員が押さえておくべきでしょう。
松代工業株式会社(本社・長野市)は、電子部品の製造や精密板金・塗装などを手がける老舗企業です。同社は、これまでオンプレミスでデータ管理を行ってきました。しかし定期的なメンテナンスや、日常的に発生する煩雑な管理が負担になり、担当部門のリソースを圧迫していました。
そんな中、本業により集中できる安心・安全なファイルマネジメント環境を構築すべく、松代工業はファイルサーバのクラウド化を模索し始めます。最終的にオンプレミスから使えるファイル箱にした決め手について、中小企業にとって「空気みたいに意識しないで使える」点だったといいます。
【松代工業株式会社様】事例の全文はこちら>>

セキュリティ重視ならオンプレミス
クラウドの場合、慎重に事業者ごとのセキュリティレベルを検証し、最終的には自分たちの側が相手のセキュリティポリシーに合わせるしかありません。この点、オンプレミスなら、自社の独自のセキュリティポリシーに基づき、コストをかけさえすれば、いくらでも厳格なセキュリティシステムを構築可能です。
オンプレミスは外部ネットワークから遮断されているため、機密度の高い個人情報を保管すれば、情報流出のリスクは最小限に抑えられます。それに対して、クラウドはインターネットをつないだ状態でしか利用できないため、常時不正アクセスやサイバー攻撃のリスクにさらされています。
とりわけ高いセキュリティを保つことが求められる金融機関や医療機関などはオンプレミスが適しているといえるでしょう。
コスト重視ならクラウド
上述したようにオンプレミスは初期費用がかかるのに対し、クラウド利用の場合も長期的にみればそれ相応のランニングコストがかかるため、どちらが「安い」とは言い切れません。
ただ、「コスト」には「人材」や「時間」も含まれます。オンプレミスの導入はもちろんのこと、運用やセキュリティ対策にも専門的な知識をもつ人材を継続的に確保しなければならず、それが難しい中小企業の場合は外部に委託することになります。
その点、クラウドは運用を完全に事業者に任せられるため、自社で選任のスタッフを持つ必要はありません。特に中小企業の場合は人材も限られているため、多方面でコストを削減できるクラウドの活用はメリットが大きいのです。
容量無制限のクラウドストレージについて知りたい方はこちら
クラウドファイル共有サービスについて知りたい方はこちら
.jpg)
オンプレミスとクラウドのどちらが最適なのかは各企業の状況によります。完全にクラウドに移行せずに、機能によってオンプレミスとクラウドを使い分ける「ハイブリッド型」を選ぶ企業も増えています。
客観的に自社の現状を分析し、オンプレミスからクラウドに移行することを検討しているなら、以下の3つの注意点を覚えておきましょう。
データのバックアップをとっておく
オンプレミスのシステムが比較的シンプルなものであっても、移行する際には事前の準備やテストが欠かせません。しかし、予想外のトラブルが発生し、データの移行がスムーズにいかない場合もあります。データ消失のリスクを回避するために、データのバックアップは必ずとっておきましょう。
自社システムと連携できない可能性がある
既存システムとクラウドの連携がうまくいかないケースも考えられます。そうした事態を避けるためには現在の自社システムの要件洗い出しを行い、段階的に移行を行う必要があります。
カスタマイズ性に優れていないサービスがある
クラウドサービスもカスタマイズできるものが増えていますが、上述したようにオンプレミスの自由度にはかないません。そのため、クラウドに移行する際はオンプレミスと同じレベルの機能や操作性を求めるのではなく、自社にとって必要なものは何か取捨選択が必要でしょう。

オンプレミスからクラウド、あるいはハイブリッドへの移行をご検討中なら、使えるねっとのクラウドストレージサービス「使えるファイル箱」もおすすめです。
使えるファイル箱はクラウドストレージサービスのメリットを最大化し、デメリットを最小化しています。3つのポイントをご紹介します。
万全のセキュリティ対策
オンプレミスに比べてやや心配になるのがクラウドのセキュリティかもしれません。この点、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズムAES256ビットを採用しています。NIST(米国国立標準技術研究所)が採用している暗号技術で、AESの中でも最も安全といわれています。
また、2要素認証設定やウェブ管理画面のSSL化も採用し、ログインやウェブサーバとブラウザ間のデータ通信の安全対策も万全です。
さらにフォルダにはアクセス制限の設定も可能なため、取引先など外部ユーザとのやり取りも安心して利用していただけます。
企業の成長に合わせてユーザ数やデータ容量の調整が可能
オンプレミスはカスタマイズのしやすさがメリットですが、使えるファイル箱も負けていません。ユーザ数無制限のため、企業の成長に合わせて社員が増えても課金や権限発行に悩むことなく、自由自在に対応可能。また、データ容量も追加可能です(1TB追加で税込8,580円/月)。
高いコストパフォーマンス
クラウドストレージサービスのメリットの一つに低コストで導入できる点があります。この点、使えるファイル箱は、長く使っていただきたいので、毎月の料金も低めに設定、容量1TBのスタンダードプランなら月額21,230円(1年契約・税込)です。、容量3TBのアドバンスプランなら月額60,500円(1年契約・税込)で、IPアドレス制限などさらなるセキュリティ強化とWebDAV連携が可能になり、容量だけでなく機能面も拡張されます。
30日間の無料トライアルも実施しています。お気軽にお問い合わせください。
使えるファイル箱についてさらに知りたい方は、よくある質問をまとめたこちらの記事もご覧ください。
.jpg)
オンプレミスとクラウドの違いは何ですか?
オンプレミスは導入コストが高額になりがちですが、個々のニーズに合わせてローカル環境で構築できるため、他のシステムとの連携がしやすく、セキュリティ面で安心です。それに対して、クラウドは低額でスピーディに導入でき、拡張性が高い点がメリットです。
クラウドサービスはオンプレミスよりもセキュリティ面で不安?
一般的にクラウドサービスはインターネット経由で利用するため、オンプレミスよりセキュリティ面で不安があると指摘されることがあります。しかし、各クラウドサービス提供事業者によってセキュリティレベルが異なるため、一概にクラウドサービスがセキュリティ面で劣るとはいえません。例えば、使えるファイル箱は暗号化技術の中でも高い強度を誇るAES256ビットを使用し、ウェブ管理画面のSSL化など、万全のセキュリティ対策を行っています。
「ハイブリッドクラウド」とは何ですか?
ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなど、複数の環境を連携させて運用することを指します。マルチクラウドが複数のクラウドサービスを組み合わせるのに対し、ハイブリッドクラウドは異なる種類のクラウドやオンプレミスを組み合わせることで、それぞれのデメリットを最小化し、メリットを最大化することができます。
使えるファイル箱の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
ここ数年、企業のあり方・方向性がテーマになると必ずといってよいほど登場するのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というキーワード。「企業のデジタル化が大事なんでしょ?」くらいのイメージはあっても「IT化」との違いはいまいち分からない、という方も多いのではないでしょうか?
今回の記事ではこのDX化について理解を深め、自社の成長戦略にどのように活用できるか、また企業のデジタル変革とクラウドストレージの関係について、具体例を取り上げながらご説明します。
ファイルサーバのククラウド比較を見たい方はこちら
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
DXに対する認識の相違
スポーツ界にもデータ活用の波
使えるファイル箱
FAQ
Chatworkが2023年11月に中小企業の経営者・バックオフィス担当者2,125人を対象に行った調査によると、49.7%がDXを「聞いたことがない」と回答しました。「聞いたことはあるが、意味は知らない」と答えたのは19.5%で、「意味は知っているが、説明はできない」と答えたのは16.6%、「意味を理解しており、説明できる」人は14.3%にとどまりました。
政府や自治体が声を大にしてDXの重要性を叫び、補助金などの施策を講じても中小企業にはなかなか浸透しておらず、デジタルによる経営のアップデートを実現できていない状況がうかがえます。
DXの定義
では、そもそもDXとは何なのでしょうか?
2018年12月に経済産業省が公表した「DX推進ガイドラインVer.1.0」によると、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。
この定義から、企業がITを活用して組織を根底から変革することが「DX」だとお分かりいただけると思います。単にこれまで紙で送っていた請求書をPDFにするなど「ペーパレス化」を進めればDXが実現できるわけではないのです。
DXに取り組むべき理由〜「2025年の崖」とは?
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が2023年10月に行った調査によると、「DXに取り組むにあたっての課題」について「ITに関わる人材が足りない」が28.1%で最も多く、次に「DX推進に関わる人材が足りない」が27.2%、「予算の確保が難しい(24.9%)」、「具体的な効果や成果が見えない(21.0%)」、「何から始めてよいか分からない(19.9%)」と続いています。
とはいえ、経済産業省の報告によると、このままDX化を進めなければ2025年にはIT人材の不足が約43万人に拡大すると予想されています。さらに、古い基幹システムが全体の6割を占め、2025~2030年の間に年間最大12兆円の経済損失が出るという試算もあり、この問題は「2025年の崖」と呼ばれています。逆にDX化をいま推進すれば、2030年には約130兆円の実質GDPの押し上げが期待できるようになります。

前出の中小企業基盤整備機構が行った調査によると、「DXに期待する成果・効果」については「業務の効率化」が64%、「コストの削減」が50.5%と上位を占めました。また、「DXに向けての取組みの進捗状況について」で最も多かったのは「アナログで行っていた作業やデータのデジタル化を進めている」で29.1%、「個別の業務や製造等のプロセスのデジタル化を進めている」が13.4%でした。
前述したようにDX化の目的は、デジタルイノベーションによりビジネス変革を実現し、「競争上の優位性を獲得する」ことであるにもかかわらず、多くの中小企業がDXを業務効率化を目的とする「IT化」「企業の業務デジタル化」とほぼ同じようなイメージで捉えていることがうかがえます。
「ITを導入すればDX」になるの?
DXの狙いはデータとテクノロジーによる「デジタル変革」ですから、ITインフラを導入してもそれが業務効率化だけのためであれば、DXとはいえません。いわばDXは目的であり、IT活用はそのための手段に過ぎないのです。
上述した経済産業省の「DX推進ガイドライン」でも「DXを実現していく上では、デジタル技術を活用してビジネスをどのように変革するかについての経営戦略や経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた企業内の仕組みや体制の構築等が不可欠である」と述べており、データとデジタル技術を活用して「何をどのように変革したいのか」というビジョンこそが最重要であるといえます。
DX導入事例1)松代工業株式会社様、老舗企業の業務プロセスを改善
1958年創業の松代工業株式会社様(本社・長野市)は電子部品の製造や精密板金・塗装を手掛ける老舗企業で、長野県におけるものづくりを長年リードしてきました。本社・工場とのファイルマネジメントのためにローカルサーバを自社運用してきましたが、やりとりや管理が大変だったといいます。
同社はこうした業務プロセスを根本的に改善するために使えるねっとの「使えるファイル箱」を導入しました。それによりファイルのやり取りが楽に行えるようになり、クラウドストレージを「空気みたい」に使っているとのことです。技術やノウハウの積み重ねや承継を大切にしつつも、必要なときには大胆に新しい価値観を取り入れ、テクノロジー活用によりDX化を進めた事例といえるでしょう。
.jpg)
【松代工業株式会社様】事例の全文はこちら>>
DX導入事例2)株式会社レイメイ藤井様、災害の経験からクラウド化の必要性を痛感
明治23年(1890年)に熊本で創業し、現在は九州全域をカバーする拠点網を構築している株式会社レイメイ藤井様は、「知的生産をサポートする複合企業」を掲げ、商社や文具メーカーとして幅広い事業を展開しています。
同社は、2016年に発生した熊本地震がターニングポイントとなり、クラウド化の必要性を痛感したといいます。その際、数日出社できない社員が多数発生し、社外でも仕事ができる仕組みづくりが急務になったのです。ところが、当初導入したクラウドサーバはOSアップデートの度にシステムがダウンするなど、安定面から不安とストレスを感じていたとのこと。その後、「使えるファイル箱」に移行し、安定性の高さだけでなく、低コストや使いやすさに「目から鱗が落ちた」そうです。創業130年を経て今も進化し続ける原動力の1つがクラウドストレージだといえるでしょう。
(1).jpg)
【レイメイ藤井様】事例の全文はこちら>>
DX化が著しい業界にスポーツ界があります。とりわけ米大リーグ(MLB)ではその傾向が著しく、投手の投球速度や回転数、バッターの打ち出し角度や推定飛距離、球場での選手の動きを追跡してデータ化するシステムが導入されており、実際にデータ分析・活用の結果、ホームラン数が増えているとのことです。
.jpg)
スポーツ×テクノロジーで実現できるもの
かつてチームの強さは選手一人ひとりの力量や監督の経験によって大きく左右されましたが、ITによって膨大な情報をリアルタイムに得られるようになり、それをいかに分析し、活用するかで試合の結果を変えられるようになってきました。それとともにデータを高い精度で分析し、チーム内に分析結果を共有するシステムを構築できる専門家が求められています。
例えば、2019年のラグビーワールドカップで日本代表チームが大躍進できた背景にも、試合が優勢になるためにどのようにスクラムを組むべきなのか、試合の映像、選手一人ひとりのスピードやパワーを数値化して分析したアナリストたちの存在がありました。
使えるねっとのサービスでDXをサポート〜信州ブレイブウォリアーズ様
使えるねっとのサービスは、長野県長野市および千曲市を本拠地とするプロバスケットボールチーム、信州ブレイブウォリアーズ様にご利用いただいています。2021年10月からスタートしたシーズンにおいて、高品質で安定したクラウドサービスをチームに提供するのみならず、クラウド技術を活用したデータ管理を行ってチームのDX化をサポートしていきます。
(1).jpg)
使えるねっとが提供する「使えるファイル箱」は使いやすくて低価格のため、多くの中小企業様に選ばれ、DX化のお手伝いをさせていただいています。
手軽なのにユーザ数無制限+高度なセキュリティ機能も搭載でDX化に最適
使えるファイル箱が使いやすい理由は専用のインターフェースを必要とせず、Windowsならエクスプローラーのように普段の使いなれた方法でデータのアップロード、ダウンロードが可能な点にあります。また、ユーザ数は無制限で100人でも、1,000人でも料金は一律のため、社員が増えてもユーザ課金や発行権限に悩むこともありません。
DX推進のために欠かせないのがデータ保存・データ管理のセキュリティ対策です。扱うデジタルデータの量は爆発的に増加し、機密性は高まる一方です。また、ランサムウェアなどサイバー攻撃の脅威も懸念されます。
ランサムウェアの意味や感染対策を知りたい方はこちら
この点、使えるファイル箱が採用しているのは暗号化技術の中でも高い強度を誇る暗号化アルゴリズム「AES256ビット暗号化」。また、ウェブ管理画面のSSL化でウェブサーバとブラウザ間のデータ通信の暗号化も徹底しています。さらに、各フォルダごとにアクセス権限の設定が可能なので、セキュリティ面を心配せずに取引先など外部とのやりとりも自由自在です。
嬉しいことに、従来14日間だった無料トライアルの期間が2024年5月28日より30日間に延長。クラウドストレージサービス導入をお考えの方はじっくり、ゆっくりお試しいただけます。
使えるファイル箱は、デフォルトで大容量1TB、月単価21,230円(税込、1年契約)から導入可能。デジタル化によるビジネス変革を実現したい経営者の方、クラウドストレージサービスの導入方法についてお悩みの担当者の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
.jpg)
(1)DXとIT化はどう違う?
IT化は特定の業務に焦点を当て、デジタルを活用して効率化を目指すことです。それに対して、DXとは企業がデータやデジタル技術を活用し、自社のビジネスモデルや業務プロセス、企業文化などを変革し、競争上の優位性を確立することをいいます。つまり、DXは単なる効率化にとどまらず、組織全体の変革を指します。
(2)中小企業がDXを推進すべき理由とは?
中小企業はコストや人手不足ゆえにDXを後回しにしがちです。しかし、リソースが限られている中小企業こそ、DXを推進し「2025年の崖」を乗り切る必要があります。中小企業が遅らせずにDXに着手することで業務効率化のみならず、生産性や競争力の向上を実現できます。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)
各業界でオンプレミスに替わるオンラインストレージの導入が進んでいます。導入の際の手軽さやコスト、使いやすさなどが理由に挙げられますが、実際に導入してみて分かることもたくさんあります。「こんなはずじゃなかった…」、「オンプレミスの方が使いやすかった…」ということにならないよう、導入予定のオンラインストレージサービスについて熟知しておくことが大切です。
今回は使えるねっとの「使えるファイル箱」のよくある質問のうち、いくつかを取り上げてお答えしたいと思います。
目次
オンラインストレージとは?
よくある質問
「使えるファイル箱」

まず改めてオンラインストレージとは何かについて簡単に触れておきましょう。
オンラインストレージ(クラウドストレージ)とは、インターネット上にデータを保存しておく記憶装置のことです。オンラインストレージと比較されるデータの保存手段としてオンプレミスが挙げられますが、こちらは自社内に情報システムを保有し、サーバを運用することを指します。
一般的にオンプレミスは自社のニーズに合わせてカスタマイズがしやすい一方、導入コストが高く、運用までに数週間から数カ月かかるといわれています。そのため、自社内に専門知識を持つ人材を確保する必要もあります。
これに対して、オンラインストレージは自社運用ではないため、オンプレミスほどのカスタマイズのしやすさはないものの、人的・時間的・経済的コストいずれにおいても優れているとされます。また、最近どの企業にとっても脅威となっているサイバー攻撃や頻発する災害によるデータ消失に備える点でもオンラインストレージは有利です。
ただ、こうしたメリット、デメリットはあくまでも一般的な比較であるため、自社がオンラインストレージを導入する場合、メリットを最大化し、デメリットを最小化できるサービスを選ぶことが非常に重要です。
オンラインストレージについて詳しく知りたい方はこちら
オンプレミスについて詳しく知りたい方はこちら
1. 一契約につき何人までユーザを作成できますか?
「使えるファイル箱」はユーザ数無制限です。つまり、人数に関わりなく全社員のアカウントを作成しても料金は一律で、必要に応じて取引先にもアカウントを自由に発行できます。
ユーザ数課金型のサービスの場合、アカウントを追加するたびに費用が発生しますし、増えた分の容量を十分使いきれない企業も多いようです。それに対して、ユーザ数無制限であれば、必要に応じて容量を追加することで費用を抑えることが可能です。
さらに、「使えるファイル箱」ではそれぞれのユーザタイプを「管理者」「内部」「外部」から自由に設定することができ、「書き込み」や「読み取り」についても状況に応じたユーザ権限を付与できます。このように社員一人ひとりにアカウントを持ってもらい、その上で細やかな設定を行うことで共有フォルダの活用の幅が格段に広がるのです。
.jpg)
2. アカウントを持っていないユーザにファイルを共有したり、編集してもらったりすることはできますか?
大容量ファイルをメールに添付する際はZIPファイルを作成するなどの手間がかかりますが、「使えるファイル箱」なら容量を気にすることなく簡単に共有リンクを作成し、それをメールやチャットに貼り付けることでファイルを共有することが可能です。もちろん、パスワードも簡単に設定できます。メールやチャットを受け取った相手はそのリンクをクリックすることでデータをダウンロードできるというわけです。
また、「使えるファイル箱」はユーザ数無制限のため、頻繁にやり取りをする外部ユーザであればアカウントを付与することも1つの選択肢です。アカウントを付与すれば共有はもちろん、編集も自由自在です。また、PPAP(パスワード付きZipメール)対策としても有効です。
3. 作成できるフォルダ数や、保存できるファイル数に制限がありますか?
ご契約容量の範囲内であれば、フォルダやファイルの数に制限はありません。「使えるファイル箱」のストレージ容量の基本設定は1TB、つまり1,000GBです。これはオフィスファイル(1ファイルあたり1MB)であれば約100万ファイル、1分程度の動画キャプチャ(1ファイルあたり10MB)であれば約10万ファイル収納できる大きさです。
容量比較についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
4. アップロードするファイルの容量制限はありますか?
前項の質問同様、ご契約容量の範囲内であれば、個々のファイルごとの容量制限はありません。大容量のファイルもアップロードし、リンクをメールやチャットに添付することで共有が可能です。
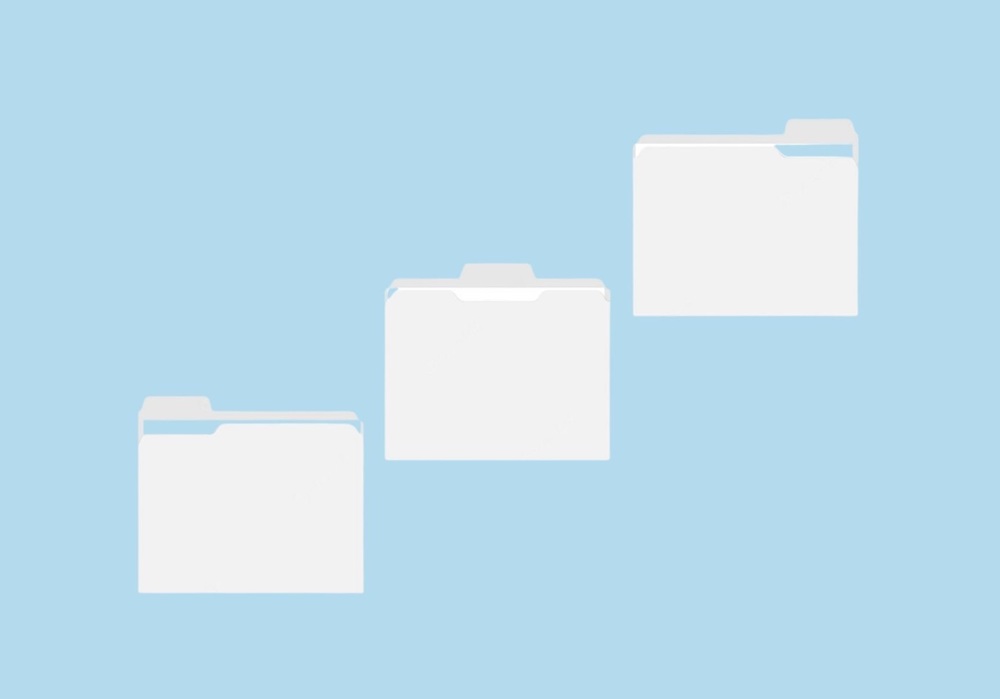
5. スマートフォンでも利用できますか?
はい、できます。テレワーク導入が進み、スピードが重視されるビジネスシーンでは「オフィス以外のさまざまな場所から社内データにアクセスできるかどうか」は重要なポイントです。
「使えるファイル箱」はスマートフォンでも簡単にファイルを確認でき、アップロードやダウンロードも可能。製造や建設の現場からも本社と瞬時にデータを共有できます。
お使いの端末がiOSであればApp Storeから、AndroidであればGoogle play ストアから専用アプリ「RushFiles」をダウンロード、ログインすればすぐにスマホでも「使えるファイル箱」を利用できるようになります。
6. 各ユーザの使用履歴を確認できますか?
はい、できます。「使えるファイル箱」には管理者によるログ監視機能があり、各ユーザの削除履歴、アップロード履歴、ログイン履歴などの管理が可能です。
7. ブランドカラーに変更したり、ロゴを追加して使用したいのですが、カスタマイズはできますか?
はい、できます。近年、「ホワイトラベル」や「OEM(Original Equipment Manufacturing)」といった言葉を耳にすることも増えましたが、「使えるファイル箱」も自社ブランド化してお使いいただけます。
現在、使えるねっとは北海道から沖縄まで約150社のパートナー様と提携していますが、約9割は「使えるファイル箱」の自社ブランド化です。実際にお申込みいただきますと、約1カ月から1カ月半くらいでロゴやコーポレートカラーのカスタマイズを行った上で引渡しいたします。自社ブランド化された「使えるファイル箱」の価格設定や契約期間は、販売戦略にあわせて自由に決めていただけます。
8. 料金プランを教えてください。
スタンダードプランは容量の基本設定は1TB、ユーザ数無制限です。容量の追加はいつでも可能で、追加容量1TBで月単価8,580円(税込)です。料金プランは単月払いなら月単価25,080円(税込)ですが、一般的には年間での契約を選ばれるお客様がほとんどで、よりお得に利用していただけます。また1年契約には、初回契約期間中ならいつでも解約・返金申請できる全額返金保証が付帯します。
|
プラン
|
スタンダード
|
アドバンス
|
|
容量
|
1TB
|
3TB
|
|
1カ月契約
(月額、税込)
|
25,080円
|
75,680円
|
|
1年契約
(月単価、税込)
|
21,230円
|
60,500円
|
9. 日本語以外の言語でも使用できますか?
はい、使用できます。Web版ではログイン画面で使用言語の変更ができ、24ヶ国語の中から選択していただけます。
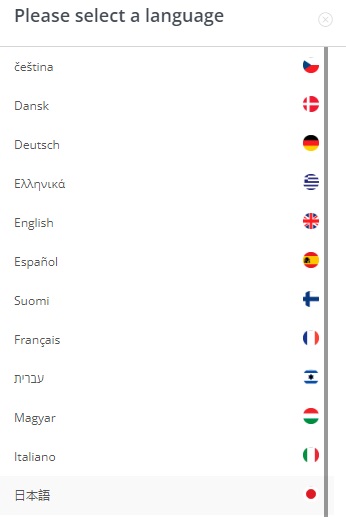
10.「使えるファイル箱」の排他制御について教えてください。
排他制御とは、複数のプロセスが同時に1つのデータに集中してアクセスすることを防止し、データの整合性を保つ仕組みのことです。
「使えるファイル箱」をエクスプローラー上で使用する場合、複数人が同一ファイルを開くことは可能で、入力も行えます。もし誰かが上書き保存した場合は、画面にポップアップの通知が出るため、他のユーザが同一ファイルにアクセスしていることが分かるようになっています。上書き保存そのものを防ぎたい場合は、ファイルをロックすることも可能です。
ちなみにWebブラウザから利用する場合は、同時編集を行えます。
11. オンプレミスから「使えるファイル箱」にデータを移行する作業の代行は可能ですか?
もちろん可能です。「シャトル便」をご利用いただき、お客様のデータを弊社が郵送したHDDにコピーしてからご返送いただければ、弊社側で直接お客様の「使えるファイル箱」にアップロードを行います。
シャトル便の利用料金は1回/1TBで55,000円(税込)、容量を追加する場合は1TBあたり11,000円(税込)です。
シャトル便の詳細はこちら>>
12.【番外編】「使えるファイル箱」のアドバンスプランに含まれる機能を具体的にいくつか教えてください。
|
機能
|
内容
|
|
IPホワイトリストの設定
|
IPアドレスをホワイトリストに追加することでアクセスを制限。
|
|
デバイス管理
|
ユーザ/IPアドレス/ブラウザ/デバイスを組み合わせて、「使えるファイル箱」のクライアント、Web管理画面、APIへのアクセスを制限。
|
以上、「使えるファイル箱」に関するよくある質問を取り上げました。ただ自社の業務にフィットするのか、使い心地は実際に試してみないと分かりません。「使えるファイル箱」は30日間の無料トライアルも行っていますので、是非お気軽にお問い合わせください。
簡単・安全に使えるクラウドストレージ、サポート体制も充実で安心
使えるねっとでは、万全のサポート体制を設けてクラウドストレージサービスが社内に定着するお手伝いをさせていただきます。電話やメール、チャットのいずれでもお問い合わせ可能、サーバのトラブルなど緊急連絡は24時間受け付けていますので安心です。
「使えるファイル箱」の詳細はこちら>>
.jpg)
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)



.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




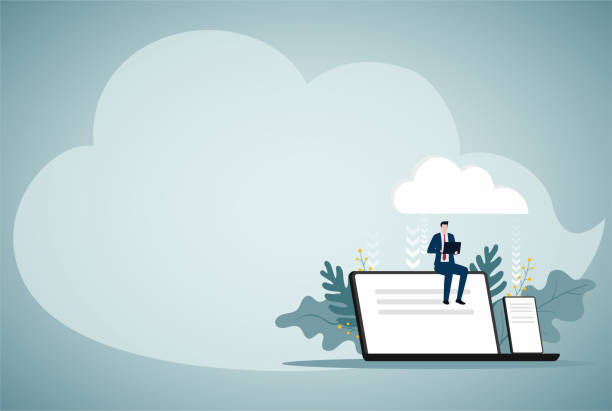





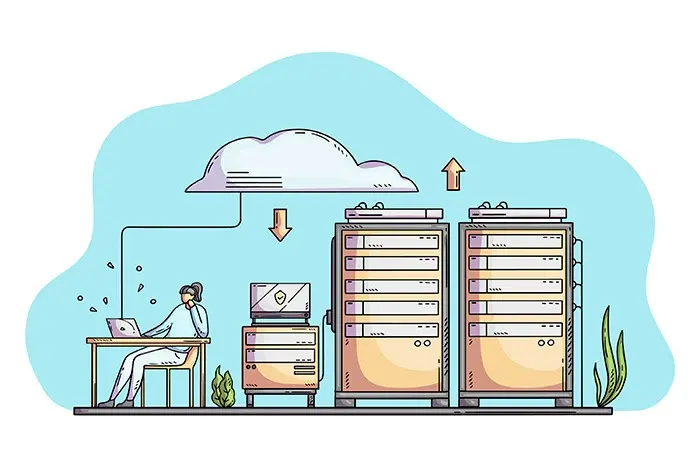


.png)
.jpg)

.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)


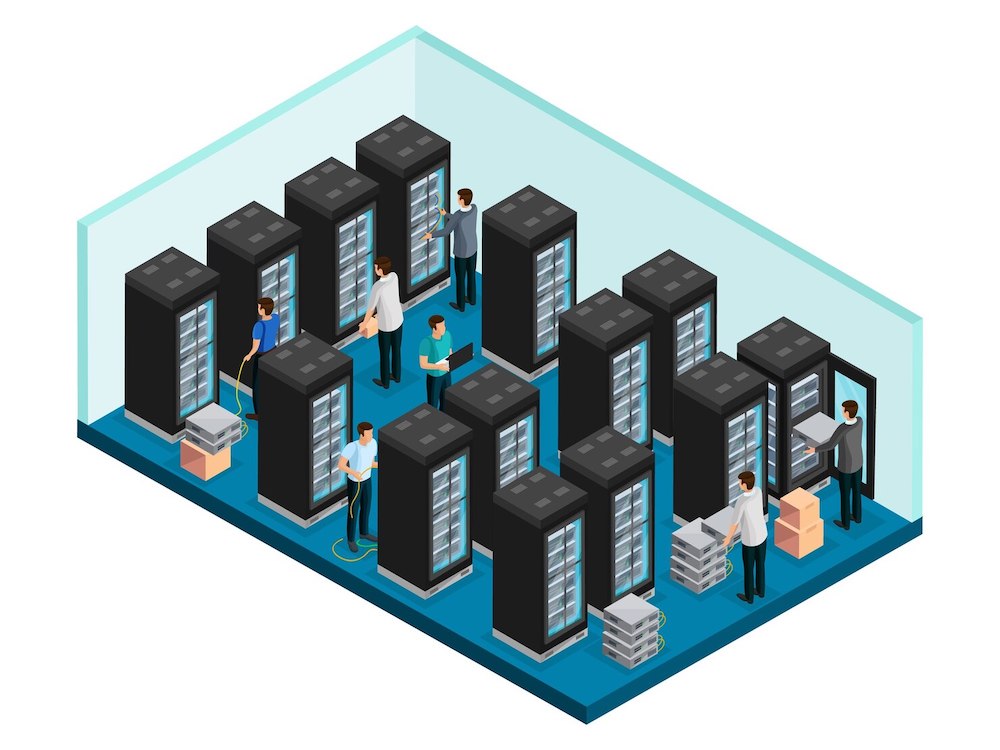

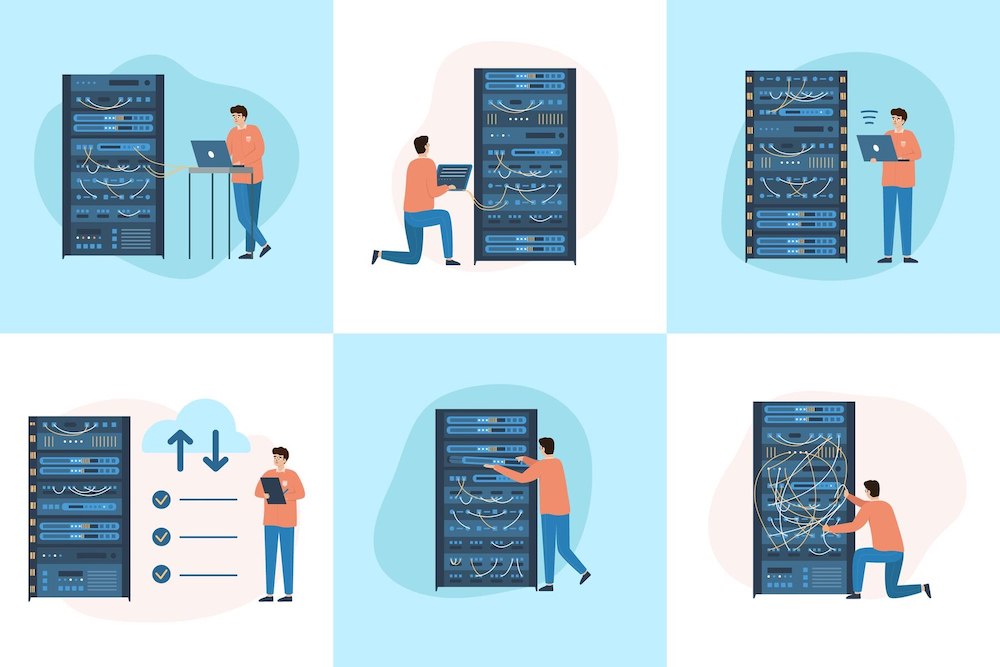

.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)



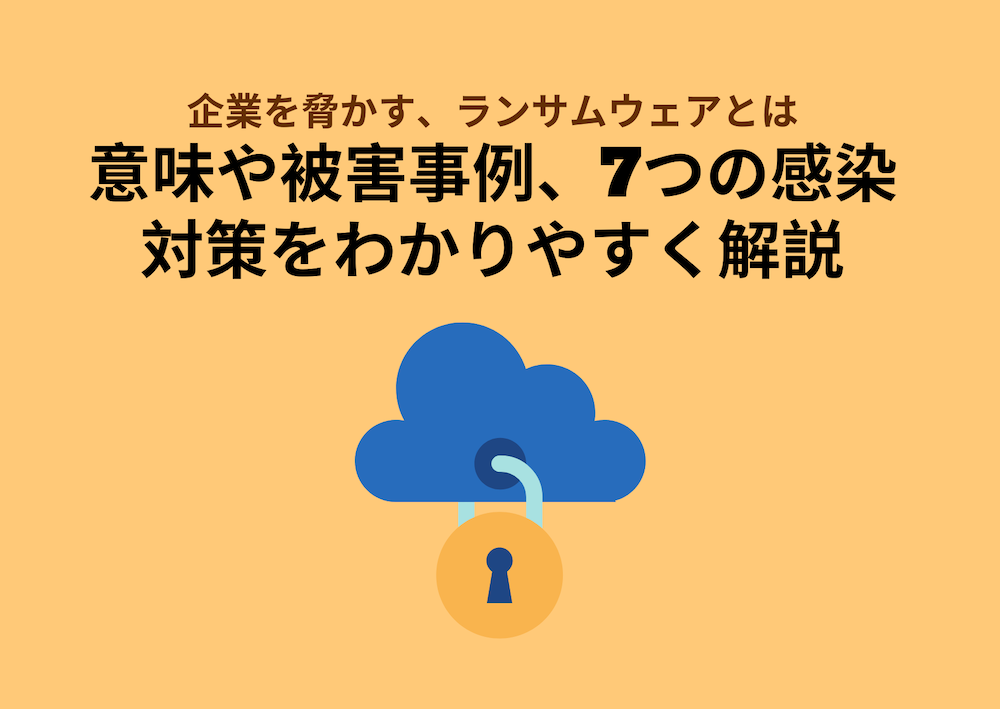

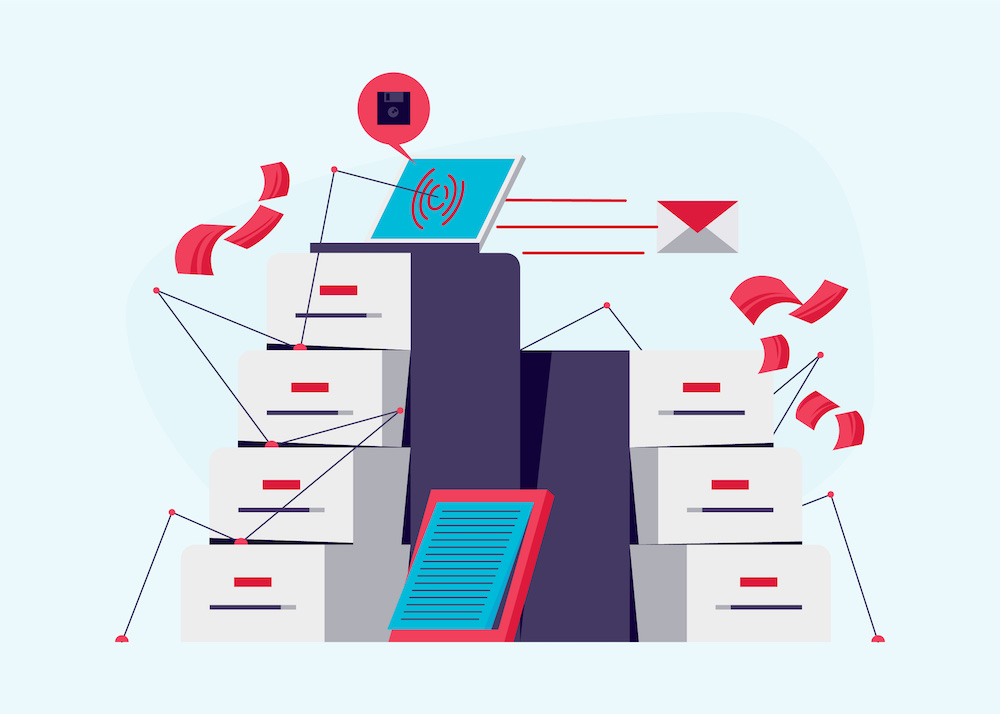




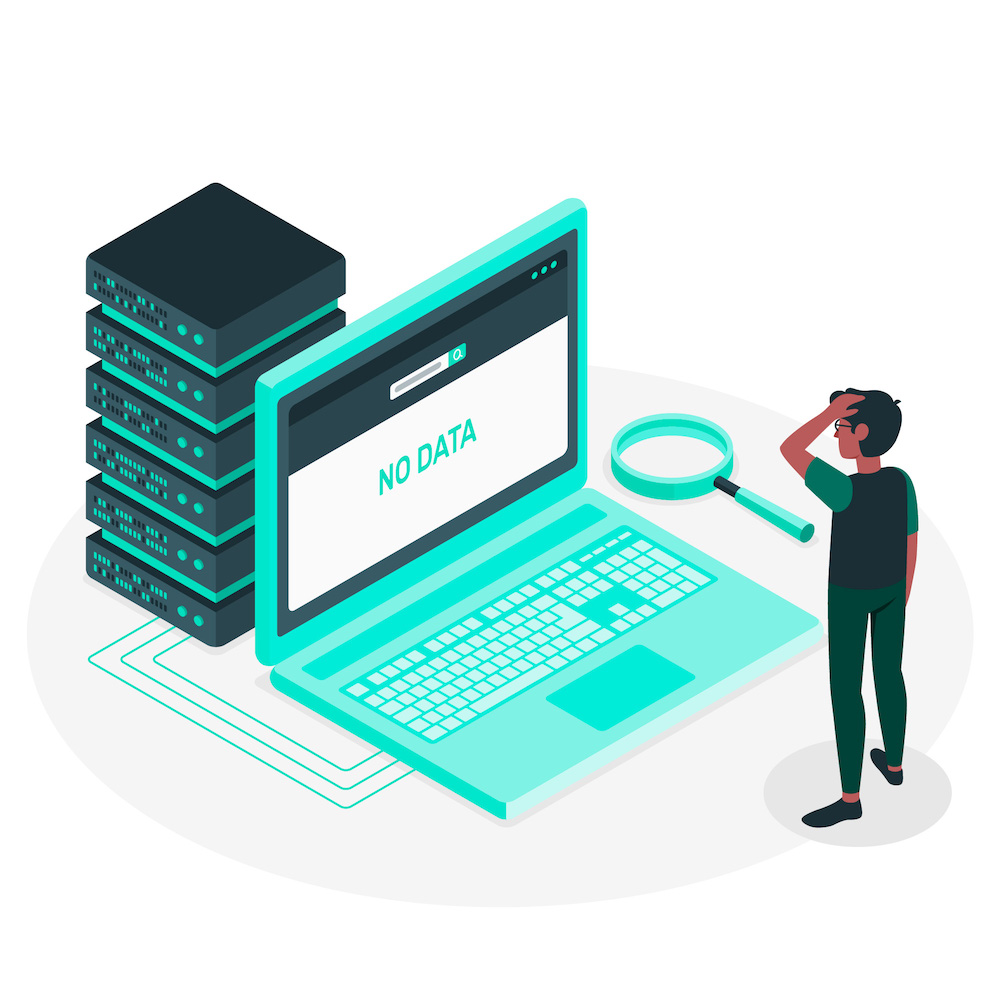


.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
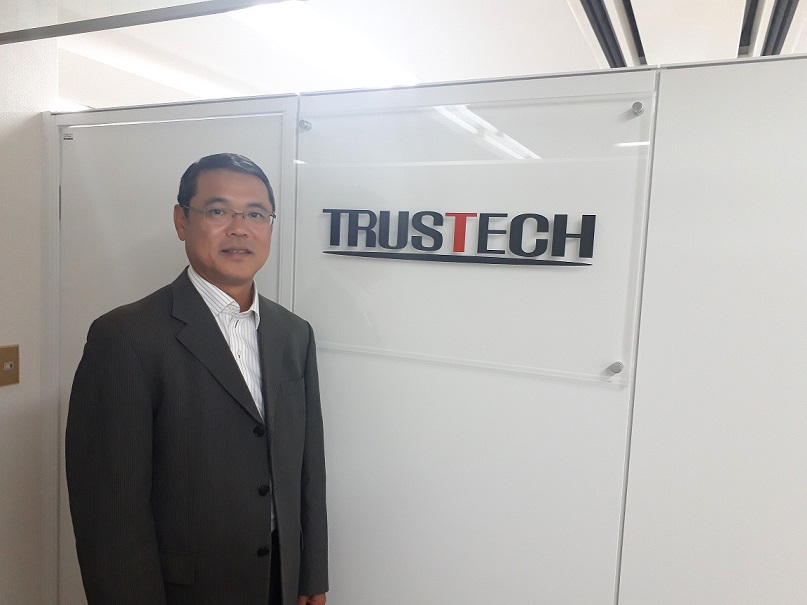

.jpg)
.jpg)

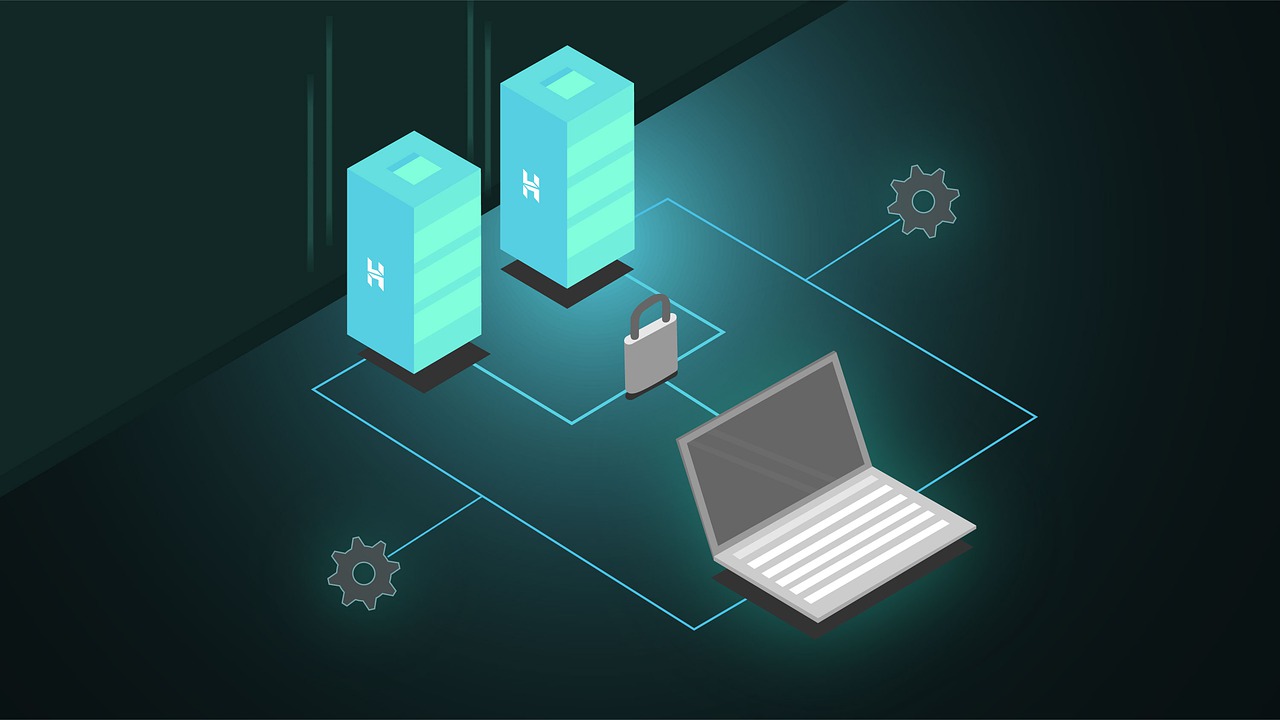
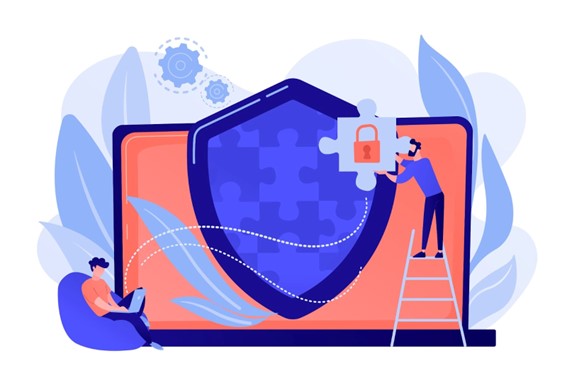
.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)

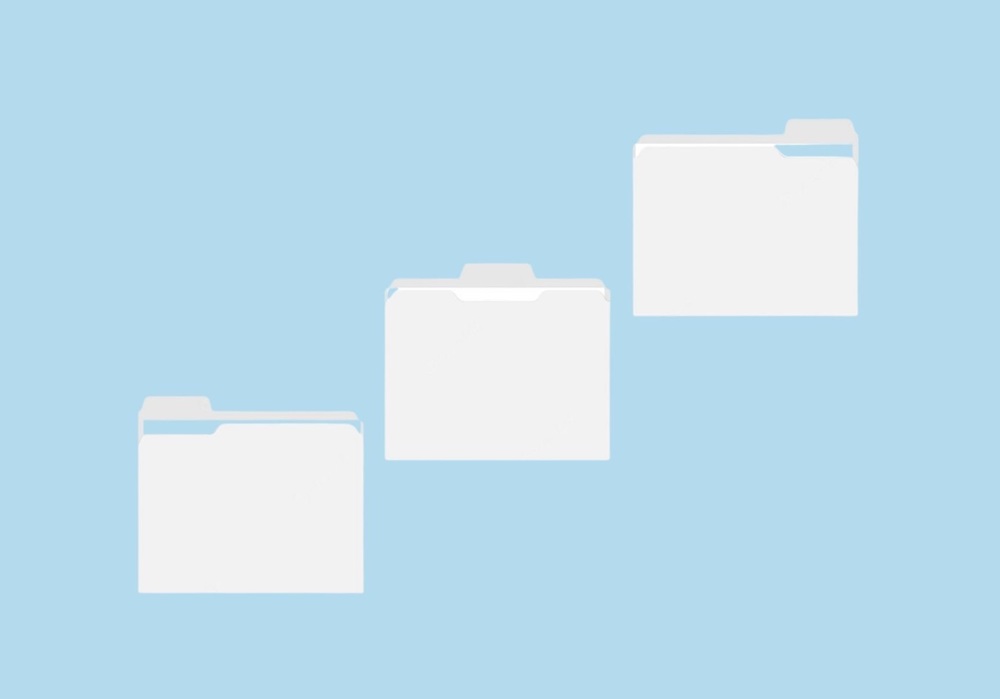

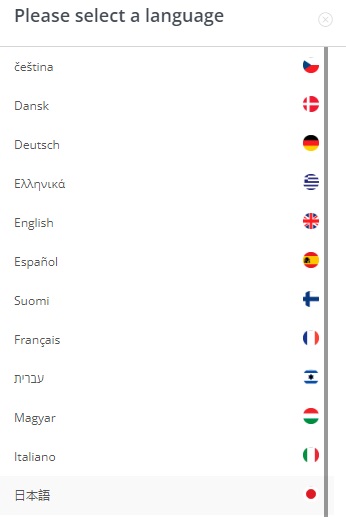
.jpg)
